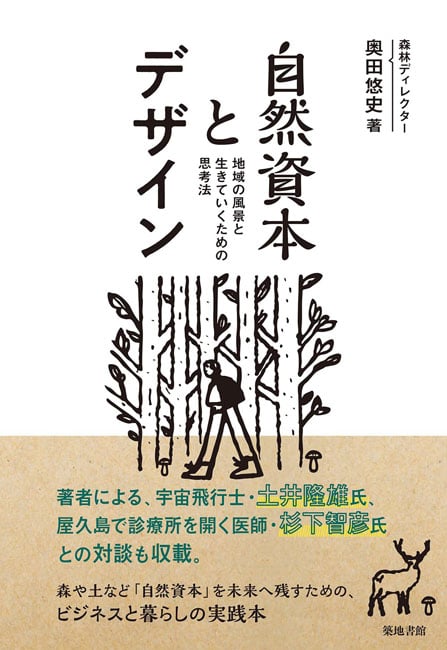2021/9/19 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、公益財団法人「日本財団(にっぽんざいだん)」の常務理事「海野光行(うんの・みつゆき)」さんです。
海野さんは藤枝市出身、1990年に日本財団に入り、海洋関係の事業を担当。そして2016年に美しく豊かな海を次の世代につないでいくために「海と日本プロジェクト」を創設。そこには子供たちや若い人たちに、もっと海に親しんでほしいという熱い思いがあるんです。現在は1万をこえる団体が協力する一大プロジェクトになっているそうです。そして、その功績により、先日、令和3年「海の日」海事関係功労者大臣表彰を受賞されています。
きょうはそんな海野さんに海洋ごみの現状や、減らすために取り組んでいる大きなプロジェクトのお話などうかがいます。
☆写真&ロゴ協力:日本財団

ペットボトル450年! 漁網600年!
※それでは海野さんにお話をうかがっていきましょう。この番組でも海洋ごみの問題は以前にも取り上げ、その厳しい現状をお伝えしてきましたが、世界の海には大量のごみが漂っているんですよね?
「はい、色んな調査、各国でなされているものはあるんですけれども、やっぱりプラスチック類が最も高い割合を占めているということが分かっています。世界では毎年少なくとも800万トンのプラスチックごみが海に流れ出ていると推計されています。東京スカイツリーの重さが約4万トンなので大体200本分、こういったものが出ているということなんです。日本からも毎年2万トン〜6万トンが流出していると言われています」
●膨大な量ですよね。北太平洋には太平洋ごみベルトと呼ばれる一帯もあるっていう風に聞いているんですけれども、これはどんなエリアなんですか?
「アメリカのカリフォルニア州からハワイ沖にかけての北太平洋上の海域なんですけれども、ここの大きな潮の流れに乗ってプラスチックごみが集まってくる。プラスチックごみだけではないんですけど、いわゆる海洋ごみが集まってくる海域があります。これが帯のように見えるようなことから太平洋ごみベルトという風に言われているところなんですね。
面積は大体160万平方キロメートルを超えると言われていまして、日本の面積の約4倍以上の大きさになってきます。ここに漂っているプラスチックのごみの総重量で言いますと、大体7万9000トンという数値も言われているところでありますね」
●色んな場所から漂って来ちゃうっていうことなんですか?
「そうですね。アジア諸国ですとか、北アメリカから流れ出てきたものがあると言われていますけれども、当然のことながら、この日本からのものも含まれていると言われています」
●以前、海洋研究開発機構 JAMSTECのかたに、深い海の底にプラスチックごみが沈んで分解されることなく、そのまま残っているんだっていうお話もうかがったんですね。さらに行方不明のプラスチックごみがまだまだ大量にあるんだっていうお話もうかがったんですけれども、このままですと世界の海がごみで埋まっちゃうんじゃないかっていう危惧もありますよね?
「まずプラスチックのごみが海に出ると、どういう風になるかっていうことがあるんですけれども、いずれにしても人工的に作られたプラスチックっていうのは、基本的には自然界で完全に分解されるということはありません。ですので長い年月、海を漂うことになります。例えば最近、有料化になったものとしてはレジ袋、これ海に流れ出ると何年ぐらい漂うと思います?」
●どうなんでしょう・・・かなりずっといそうな気もしますよね。
「ものにもよるんですが大体20年。その他にも私たちがよく使うペットボトル、これ450年ぐらいなんです。さらには、プラスチックごみの中の4割くらいを占めている、いわゆる漁具、漁網ですね、これに至っては600年って言われているんですね。そういったものが、形はある程度保ったまま浮遊していると・・・。
ですから、今私たちがごみを捨てて海に流れ出てしまうと、私たちの子供の世代、孫の世代、ひ孫、玄孫(やしゃご)、その先なんだろう、来孫(らいそん)とか、その世代まで影響を及ぼしてしまうという問題があるということなんですね。
現在、世界の海に流出している海洋ごみの量は、大体1億5000万トンという風に言われているんですけれども、このまま何もしなければ、2050年に重量ベースでいくと、魚よりもプラスチックごみの量のほうが多くなると発表している機関、あるいは学者さんもいるんです」
●そんな未来、いやです!
「一体どうなっちゃうんだろう!? って思いますね」
プラスチックに囲まれた生活
●海洋ごみの問題を解決するためには、家庭から出るごみを減らすために生活を見直すことも大事かなと思うんですけれども、なるべく家庭にプラスチックを持ち込まないようにしたいなと思っても、スーパーとかコンビニに並ぶ商品って、ほとんどプラスチックの容器とか袋に入っていると感じるんですが、どうしたらいいんでしょうか?
「どうしたらいいんでしょうね(笑)。自分も同じような疑問を持って一度試したことがあって。それは何かというと、朝起きてから寝るまでプラスチックに触れないで、自分は生活できるのかどうか、これやってみたんですね」
●どうでした?
「大失敗しましたね。朝起きる時、目覚ましを鳴らします。目覚ましが鳴って押した瞬間にその目覚まし時計がプラスチックで・・・」
●ああ〜!(笑)
「もう何もならない、そこでもうゲームは終わってしまうというところがあります。そういったところからすると、プラスチックに触れないで、今、現代人が生活できるかっていうと、これはほぼ無理なんだろうなと思いますね」
●(プラスチックは)至る所にありますよね。
「フランスのルモンド紙に載っていた写真を見たんですけど、愕然としたんですね。その家の中からプラスチック製品を全部出してみようと、庭に全部出していたんですよ。そしてその写真を見たら、家の中はもうほとんど何も残っていなかった。プールサイドに家財道具が全部並んでいたというぐらいなんですね。
そういったところからも、今の私たちの社会にとってプラスチックは欠かせないものになっているのかなと。今収録している部屋の中にも、どれだけプラスチックがあるかっていうようなことにもなってきますよね(笑)。
ただ、よく誤解されるところがあるんですけれども、たとえプラスチックをたくさん使っても、きちんと分別をするとか処理さえすれば、海洋ごみになることはないんですね。逆に、たとえプラスチックの使用を減らす、もしくは生産を減らしていったとしても、ポイ捨てしたり、あるいは我々がずさんな管理をしてしまえば、それは海洋ごみになってしまう可能性があるということなんです。
プラスチックが生活にこれだけ浸透しているのは、やっぱり便利で安くできるからというところだと思います。今のコロナ禍においては感染対策においても、改めて使い捨てのプラスチックの価値が見直されているというところも聞いていますので、プラスチック並に便利で、たとえ海に流れても分解されるような代替の素材が開発されるまで、まだまだ時間がかかりますので、それまではプラスチックの使用を中止するのは現実的ではないと思います。
プラスチック=悪と決め付けるのではなくて、例えばリサイクルをして再利用していく。そういったものをしっかりとシステムとして作り上げるとか、あるいは再利用できないものは、例えば日本でいうと燃やしてエネルギーにしていく。これはCO2の問題なんかもあるので、各国では問題になるんですけれども、こういった活用方法を賢く考えて使うということを、私たちは生活の中でも考える、もしくは政府の中、研究者の中でも考えていく必要はあるのかなと思っています」
※補足:ポイ捨てや、うっかりで出てしまったペットボトルやレジ袋など、ごみとなってしまったプラスチックは、河川や水路を通って海に流れ出しています。そんなプラスチックごみは海洋生物や海鳥などに影響を与えていることは以前番組でもお伝えしました。
また、5ミリ以下のマイクロプラスチックや、肉眼では見えないナノサイズのプラスチックが魚などから見つかっていますが、人体への影響については、まだはっきりしたことはわかっていないそうです。
たくさんの企業の技術を結集

※日本財団では海洋ごみの削減に向けた取り組みを行なっています。去年立ち上げた連携組織「アライアンス・フォー・ザ・ブルー」ではどんな活動をされているのか海野さんにお聞きしたら、まず、素敵なバッグを見せてくださいました。
「これが何からできているかってご存知ですか? 見た目で分かりますか?」
●見た目では全く、素敵な水色の、あと皮と、おしゃれなバッグです。
「何からできているかというと、実はこれ、魚を捕る網で出来ています。リサイクルなんですね。リサイクル商品としてはものすごくいい形で仕上がっていると思うんですね。海洋プラスチックの中でも重量ベースで最も多いのがいわゆる漁具、その中でもやっぱり悪さをするのは漁網って言われているんです。
これをたくさんの企業のお力をお借りして実現したのが、ひとつのものとして、これなんですね。実はこの取り組みの前に、日本最大の消費者団体であります生活協同組合のCO・OP(コープ)ってご存知ですよね? 彼らと一緒に消費者のプラスチックごみに対する声っていうものちょっと調べてみました。そうしたところですね、興味深い実態が浮き彫りになってきました。
挙げるとですね、3つほどあるんですけれども、ひとつは、消費者は企業が提供する選択肢が乏しいことに不満を持っている、これがまずひとつ。それともうひとつは、企業による新しい選択肢の提供を待っている。もっとたくさん(選択肢が)出てきたら私たち消費者は買いますよと思っているんですね。
さらに、環境に配慮した商品がたくさん出てくれば、それは一定のコスト負担、付加価値が付いたものがあれば、コストを負担してもそれを許容できますと、要は買いますよということを生活者の皆さんは思っているんですね。
この調査結果からも、何が言えるかというと、企業の協力、企業の貢献というのは、これはやっぱり欠かせないということを改めて感じたところです。もちろん一筋縄じゃいかないところもあるんですけれど、例えばプラスチック製品の商品企画から流通、製造、消費、処分、あるいはまたこれを再利用していくと、こういった一連の過程の中で色んな企業さんが関わってきます。ですので、ひとつの企業や業種で取り組むだけでは、限界が出てくるんですね。
なので、日本財団では石油化学ですとか、あるいは日用品、食料品、包装材のメーカーさん、小売さん、リサイクル企業さん、色んな企業のかたがたを集めて、本気度のある、ちゃんとした製品を作ろうじゃないかということで集まったのが、”アライアンス・フォー・ザ・ブルー ”というもので、2020年7月に立ち上げて、今、大体34社になっています。
自分たちが足りないもの、もしくは自分たちはこんないい技術を持っているっていうものを出し合って、ひとつのいい製品を作ろうと出来たのが、この漁網のバッグということです」
●リュックもトートバッグもショルダーバッグも、本当に生地もしっかりしていますし、見た目もお洒落ですね。
「そうなんです」
※補足:日本財団が立ち上げた連携組織「アライアンス・フォー・ザ・ブルー」にはセブン&アイ・フォールディングスや大日本印刷、三菱ケミカルなど、いろいろな業種の企業が34社参加しているとのことでした。
そして、漁網をリサイクルしたバッグは10月1日から「豊岡カバン」のオフィシャルショップやオンラインで販売される予定だそうです。ぜひネットでチェックしてください。
ごみは人の心から出てくる
※日本財団の取り組みとして、きのうから「秋の海ごみゼロウィーク」がスタートしました。海野さん、これはどんな活動なんですか?
「日本財団と環境省で共同開催しているものでございまして、全国一斉の清掃キャンペーンになります、要はゴミ拾いキャンペーンですね。で、この春の海ごみゼロウィークというものがあって、こちらは5月30日、ごみゼロの日から6月8日まで。6月8日っていうのは国連で定められた世界海洋デーなんです。
この期間を“春の海ごみゼロウィーク”ということで、一斉ゴミ拾いをやってもらったら、コロナ禍でもありますのでなかなか難しいということで、今回は秋にもこれを設置しようということで、9月の第3土曜日、これはワールドクリーンアップデーにもかかるんですけれども、この前後を踏まえて、1週間は“秋の海ごみゼロウィーク”と名付けて今、実施をしているところであります」
●これ、今からでも参加はできるんですか?
「もちろん参加できます。“海ごみゼロウィーク2021”のホームページがありますので、こちらの応募フォームから申し込んでいただければ、ごみ袋を無償で提供をさせていただきますので、ぜひ参加していただければと思っています」
●日本財団のご協力をいただいて、bayfmでは”LOVE OUR BAY! 海ごみゼロ!プロジェクト”を進めております。私も近所のごみ拾いをして、写真を撮ったりしているんですけれども、色々な企業や自治体などが連携していけば、どんどん大きな力になっていきますよね」
「おっしゃる通りだと思います。海ごみと聞くとあたかも誰かが海に行って、そこでごみを捨てているような感じに捉えられるかもしれませんが、先ほど申し上げた通り、もともとは陸から出たものなんですね。
海洋ごみは川から来ます。川のごみはどこから来るかというと町から来ます。町のごみはどこから出てくるかというと、やっぱりこれは人の心から出てくるというところはあると思います。海洋ごみ問題というのは全ての人に関わる問題ではあると思っています。
そういった意味ではプラスチックを製造販売している企業、そして処理関係の権限を持っている自治体さん、各地のNPO団体、スポーツ団体、あるいはマスメディアのかたがた、あらゆるステークホルダーと連携しながら、国民ひとりひとりがこれ以上ごみを海に出さないんだという強い意志を持って連帯していく、こういう気運作りというかムーブメント、こういったものを作っていければと思っています。解決のカギを握るのはやっぱり人の心だと思いますので」
※補足:2019年の「海ごみゼロウィーク」では全国1500カ所でおよそ40万人のかたが参加する一大イベントになったそうです。新型コロナの影響で、今年は開催規模は小さくなってしまっているそうですが、感染が落ち着いている地域で対策を万全にして実施しているところもあるとのことです。開催は9月26日まで。詳しくは「日本財団」のホームページでご確認ください。
◎日本財団「海ごみゼロウィーク2021」:https://uminohi.jp/umigomi/zeroweek/
「瀬戸内オーシャンズX」!

※それでは最後に、今後取り組んでいきたいこと、そして目標について海野さんにお話いただきました。
「”海と日本プロジェクト”、これは前からやっていたんですけど、この一部に”チェンジ・フォー・ザ・ブルー”という海洋ごみ対策のプロジェクトを2018年の11月から開始をいたしました。
チェンジ・フォー・ザ・ブルーのザ・ブルーというのは、青は海を象徴する色なので、海の豊かさを守るという意味。それとチェンジというのは、海にごみを出さない社会に変えていこうという理念のもと、チェンジ・フォー・ザ・ブルーって名付けたんですけれども、こういった中で産学官民が連携したオールジャパンの取り組みとして、海洋ごみの問題を解決するモデル事例を、とにかくたくさん作っていきたいという思いで今進めているというところではあります。
もちろん何をするにしても調査結果、いわゆる科学的なエビデンス・データっていうのは必要です。ですので、これを踏まえた上で何をすることが効果的なのかということを考えながら今、対策というか事業を進めているところであります。
チェンジ・フォー・ザ・ブルーを開始しまして、自治体とも連携してモデル作りを進めていくような中で色んな課題も見えてきました。そもそも海に流れ出たごみというのは県や市町村を越えて移動してしまうんですね。ごみに県境はないし、海も県境や市境はありませんので、そうなってくると誰がどのように回収するのか、あるいは役割分担や回収の責任の所在というのは結構曖昧になってくるんですね。
そうなると各地域で海洋ごみ対策というのが、地域の人たち、あるいは個人、個々の人の取り組みに任せられてというのがあるんですね。なので、ある意味放置されている状態であったというところはありました。
そこで、単一の自治体の枠を超えて、広域のエリアで海洋ごみ対策、これのモデルを構築しなければいけないのではないかということで、2020年の12月だったんですけれども、ターゲットは瀬戸内海、美しい海ですよね、美しい海にもごみってあるんですよね。このごみをなんとかゼロにしてきたいということで、新しいプロジェクトを開始しました。
それが”瀬戸内オーシャンズX”。何でXかというと、今回参加してくださっている自治体というのは香川県、愛媛県、岡山県、広島県、これは瀬戸内を巻き込んでいる自治体になっていますけれども、(地図で見ると)X型に連携をするというところで、このプロジェクトを進めました。
なんで瀬戸内海かというと、瀬戸内海ってやっぱり外海からごみが流れ込む確率は少ないんですね。そういった意味では我々、閉鎖性海域と言っているんです。瀬戸内にあるごみは逆に言い換えると、ほぼ自分たちの出したごみなんです。なので、ここで対策をすると何が起こるか可視化しやすいんですね。
要は対策をして、県民の皆さんがしっかりと取り組んでさえくれれば、瀬戸内のごみは限りなくゼロに近づくということが分かってきました。ですので、今、環境省さんが法律を変えるような形で進めているんですけれども、それと相まって私たちもこういうプロジェクトを進めていく中で、瀬戸内のごみをゼロにするということで、ごみを通じてちゃんと海のことを考えてもらう意図も踏まえて、この瀬戸内オーシャンズXを始めました。
大体5年間でゴミの流入を70%減らす。これは川のゴミを遮断すれば、ある程度できます。それと同時に回収ですね、海洋ごみの回収を10%増やす。これをすることによって理論上、ごみはゼロに近づいていくと。5年間でなんとかこの取り組みを成功に導きたいなと思っています。
当然のことながら調査研究をしながら、企業の皆さん、地域連携をやりながら、あとは教育と、市民の皆さんに対しての行動ですね。こういったことをしながら政策形成、自治体の皆さんに対して、私たちもごみに対するシンクタンクを持っているものですから、こういった政策形成の部分もサポートしながら、この4つの柱を掲げ、先駆的な様々な取り組みを進めていきたいなと思っておます。上手くいけば、この成功事例が海外にも持っていけるのかなと、日本発、瀬戸内発のモデルとして出ていけばいいなという風に思っています」
INFORMATION
日本財団が進めている海洋ごみ対策のプロジェクト「チェンジ・フォー・ザ・ブルー」そして連携組織「アライアンス・フォー・ザ・ブルー」に今後も番組として注目していきます。
海野さんが創設した「海と日本プロジェクト」は海洋ごみの削減だけでなく、子供たちや大人たちにも海に関心を持ってもらうための様々な取り組みを行なっています。詳しくはぜひ日本財団のオフィシャルサイトをご覧ください。
◎日本財団 HP:https://uminohi.jp/
ベイエフエムでは日本財団の協力のもと、「LOVE OUR BAY! 海ごみゼロ!プロジェクト」を進めています。参加方法は簡単! ゴミを拾って、それを写真に撮って送るだけ。ぜひ一緒にチーバくんごみゼロMAPを完成させましょう。詳しくはベイエフエムのサイトを見てくださいね。
◎bayfm HP:https://www.bayfm.co.jp/info/umigomi0/