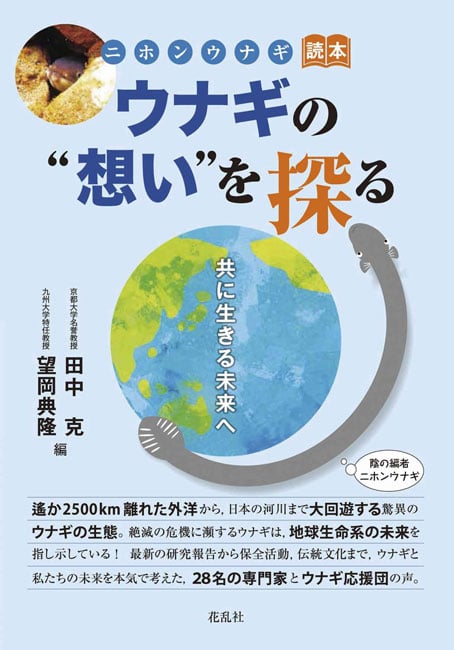2021/5/30 UP!
◎入江紫織(茨城県那珂市地域おこし協力隊)
『農家さんの思いとともに〜茨城県那珂市「地域おこし協力隊員」の活躍〜」』(2021.5.30)
◎小池伸介(東京農工大学大学院・教授)
『ツキノワグマの知られざる生態〜クマはタネの運び屋!?〜」』(2021.5.23)
◎リピート山中(シンガー・ソングライター)
『ギターを背負って山小屋コンサート〜山と歌がつないでくれた縁〜』(2021.5.16)
◎佐藤 輝(ダイビングガイド/葉山のダイビングショップNANAの代表)
『カラフルな湘南の海〜光と影のメッセージ』(2021.5.9)
◎廣瀬泰士(「こどもみらい」の代表)
『園庭のテーマは「自然と冒険」〜子供たちに豊かな感性を〜』(2021.5.2)
2021/5/30 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、茨城県那珂市(なかし)地域おこし協力隊の「入江紫織(いりえ・しおり)」さんです。
入江さんは地元の農家さんや飲食店、農業関係者のみなさんと一緒に、コロナ禍で販路を失った農産物を、マルシェを開催して販売するなど、農業の活性化に力を入れていらっしゃいます。
きょうはそんな入江さんに地元の農家さんの支援活動や、農業への想いなどうかがいます。
☆写真協力:入江紫織

自然に溶け込んで農業がある那珂市
※それではさっそくお話をうかがっていきましょう。
●入江さんは茨城県那珂市の、地域おこし協力隊のメンバーとしてご活躍されていますけれども、まず、この地域おこし協力隊とはどういったものなんでしょうか?
「地域おこし協力隊は総務省が主体となって実施している事業です。全国47都道府県に地域を盛り上げるっていうことをしたい方が、たくさん隊員として派遣されているんですけれども、皆さんそれぞれ、自分たちの得意分野を活かしながら、町おこしの活動を3年間限定でするっていう事業ですね」
●何人ぐらいメンバーっていらっしゃるんですか?
「メンバーは、今は全国で5500人ぐらいが活躍されていますね」
●そうなんですね。全国色々な地域おこし協力隊があって、入江さんは那珂市の地域おこし協力隊ということなんですね。茨城県の那珂市のご出身でいらっしゃるんですか?
「あ、全然出身じゃないですね」
●あれ? じゃあどうして那珂市の地域おこし協力隊に応募されたんですか?
「私の前職が日本農業新聞という新聞社に勤めておりまして、その時は農家さんに農業の最新情報を発信する立場だったんですけれども、それとはまた別に、一般の消費者の方に農業の魅力をお伝えすることにすごく興味を持ち始めて、それをちょうど募集されていたのが那珂市だったので、エントリーして、ご縁をいただいて採用いただきました」
●今は那珂市に移住されているということですか?
「そうですね」
●那珂市ってどんなところですか? 行ったことないんですけれども。
「那珂市はすごく景色が豊かで、例えば白鳥が冬になったらシベリアから飛来してきて、色んな湖に白鳥がいたりとかして、あとは、干し芋の大産地なので、季節になると色んな所で農家さんが干し芋を干している風景が見られたりですとか。お蕎麦も花がすごく真っ白で綺麗なので、そういう景色が見られたりですとか、すごく自然に溶け込んで農業があるっていう地域ですね」
●たくさんの農産物が作られている場所なんですね。入江さんのご実家も農家さんでいらっしゃるんですか?
「そうですね。農業関係者で実家が京都市なんですけれども、九条ネギの卸売の仕事を実家がしておりまして」
●じゃあもう昔から農業に対する思いというのは強かったわけなんですね。
「そうですね。生まれた頃からそんな感じですね」
ドライブスルー形式でセット販売!?
※具体的にどんな活動をされているのか、教えてください。
「地元にフェルミエ那珂というチームがあるんです。だいたい40人ぐらいがいらっしゃるんですけれども、地元の農家さんですとか、あと飲食店ですとか、JAさんが集まって農業を盛り上げようというので色んな活動しています。私はその団体のPRですとか、マルシェのお手伝いですとか、それを通した農産物の販売促進等をさせていただいています」

●具体的にどんなことをされているんですか?
「具体的には月に1回マルシェを開催したりですとか、あとは法人化をしたので、これから色々積極的にPRしていきたいっていう方のブランディングをお手伝いさせてもらったりしています」
●マルシェってどういう形で開催されているんですか?
「1箱のダンボールに野菜を10品目程度入れて、2000円で販売させてもらっております」
●どれぐらい用意されているんですか?
「だいたいいつも50箱用意させてもらっています」
●次のマルシェの開催は、どのように皆さん把握されるんですか?
「公式のインスタグラムを作っておりまして、そこで最新情報を更新しております」
●なるほど!
「マルシェは地元の農産物直売所の、ふれあいファーム芳野っていうところがあるんですけれども、そこの駐車場をお借りして開催しています」


●先ほどの、PRっていうのは農家さんのPRっていうことなんですか?
「そうですね! 主にインスタグラムを通して情報を発信させてもらっていますね」
●今はインスタグラムを使って色々PRされているわけですね〜。例えばどんな風にPRされるんですか?
「例えば今月入るお野菜の、このトマトを作っている農家さんはこういう方ですよとか、こういうところにこだわりを持って普段栽培されていますっていうのを、野菜と農家さんの顔写真とセットで紹介したりですとか、そういう取り組みをさせてもらっています」
●ドライブスルー形式で農作物の販売も以前されていたんですよね?
「そうですね。私が着任したのが去年の4月1日だったので、ちょうどコロナってなんだろうみたいな、みんなが分からない時期だったんですね。農家さんたちもマルシェを中止されていたので、何かいい方法ないかなと思って、ドライブスルー形式でダンボールに野菜を詰め合わせて、セット販売するっていう方法を提案して、それが少しずつ形を変えて、今ではテイクアウト形式(マルシェ)で野菜を販売するっていうのをさせてもらっています」
●珍しいですよね! ドライブスルーで販売っていうのは。お客さんたちの反応はいかがですか?
「やっぱり当時はなかなかイベントもないし、ずっと家にいがちで、スーパーにもやっぱり買い物に行くの怖いわっていう方が多かったと思うんですけれども、こうやってちょっと外に出て行くきっかけが出来てよかったですとか、那珂市ってこんなに新鮮な野菜をたくさん作っている農家さんがいるんだねとか、色々お声がけをいただいて、農家さんのことを紹介できていたのかなっていう風にその話を聞いて嬉しかったですね」


フードロスと、脱プラへの取り組み
※入江さんは活動の一環としてフードロスを減らす取り組みもされていますよね?
「そうですね。これは茨城県のイチゴ農家さんで梅原農園さんっていらっしゃるんですけれども、その農家さんの捨ててしまっていたイチゴを、地元の生パスタ専門店で生パスタに加工してもらって販売したいっていうのを、地元の水戸農業高校の生徒さんが企画されていたんですね。ただ販売先がないっていう相談を受けて、それだったら是非マルシェで販売してくださいってお話をして、先月初めて販売させてもらいました」
●高校生たちとコラボっていうのもいいですね! 地域全体で盛り上がっていく感じがしますよね。あと「粉活プロジェクト」というのもちょっと気になったんですけれども、これは何でしょう?
「これもやっぱり廃棄される野菜ですとか、質はいいけれど、まだ食べられるのに捨ててしまわないといけないっていう野菜が結構日本にはたくさんあると思うんですけれども、そういう野菜を買い取って粉末化します。粉末化するとやっぱり栄養分がすごく高まったりとかするので、それを日々、スープに入れたり、お味噌汁に入れたりして、手軽に栄養補給しましょうっていうプロジェクトを始めました」
●新しい発想ですね! パウダー状にするっていうのは。そういうことをしながらフードロスを減らしていこうという取り組みなんですね。地元の農家さんたちと脱プラスチックの取り組みも始められたということですけれども。
「本当につい最近始めて、まだ色々打ち合わせ中なんですけれども、農業の現状っていうのが、例えばトマトを作る時に、大きなハウスを建てるのにたくさんのプラスチックを使わなきゃいけなくて、ビニールハウスなのでそれを止めることって、やっぱりどうしてもできないんですね。
ほかで何かプラスチックを捨てずに取り組むことができないかなっていうので、皆さんも多分スーパーとかで袋に入った野菜を見たことあると思うんですけれども、あの袋を少し再利用したものにできないかなとか。あとはあれを半分だけでも紙にできないかなとか、少しずつなんですけれども、打ち合わせを進めているところです」
●農家さんご自身も皆さん変わろうという努力をされているわけなんですね!
「そうですね!」
高齢化で毎年、栽培面積が増える!?
※入江さんは、以前、日本農業新聞の記者として、全国の農家さんを取材されていたということですが、現在、多くの農家さんが抱えている問題はなんでしょうか。
「やっぱりいちばん大きいのは、もう皆さん多分もうご存知かと思うんですけれども、高齢化がどんどん進んできていて、これから農業を始めようとか、まだ農業できるっていう農家さんに、耕してほしいっていう農地がどんどん集まってきているのが結構問題で、やっぱり毎年毎年、栽培面積を増やさなきゃいけないっていう農家さんが出てきていますね」
●どうして栽培面積って増えていっちゃうんですか?
「毎年高齢化してきて、今年からもう畑を耕すのをやめるっていう農家さんがいるので、そういう方の農地を引き受ける農家さんや、これから営農するっていう農家さんの使命みたいな形になっていますね」
●そのまま放置するっていうのは出来ないっていうことですか?
「放置すると隣の畑に影響を及ぼして、草がぼうぼうだと隣の畑も同じような影響を受けたりするので、耕し続けないといけないっていうのがありますね」
●新しい農業の形っていうのは生まれてきているものなんでしょうか?
「少しずつ農業もデジタル化ですとか、農業DXと言って、どんどん国も推進している事業があるんです。例えば栽培管理を、昔ながらの天候を見て、野菜の葉っぱの様子を見て、勘で分かるっていう風な栽培は結構もう難しくなってきています。
それをデータ化して見える化するとか、あとは最近ドローンを使って農業を始めたいっていう農家さんも増えてきていて、ドローンが実際に動いてるところを見ましょうかってことで、ドローン飛ばしてくれるメーカーさんに見学会を開いていただいたりしました。これから那珂市の農業もどんどんDX化していくのかなっていう風に思っています」
●入江さんご自身も農園を借りて野菜を育てていらっしゃるとうかがったんですけれども、どんなものを育てているんですか?
「去年はサツマイモを植えて、地元の子供たちの収穫体験として使わせてもらったり、あとはトマトとかナスとかオクラを栽培したりしましたね」
●実際育ててみていかがですか? 畑にいる時ってどんなことを感じますか?
「やっぱり安定して野菜をいつも収穫して出荷している農家さんってすごいなって思いますね。大雨が降ったあとに天候がよくなると、すごく草がぼうぼうになったりするんですけれども、毎日栽培管理を丁寧にしているから、私たちって食べ物を安定して食べられるんだなって。栽培して失敗することすごく多いので、それを体験しているからこそ余計に食べ物を大切にしなきゃいけないなと思う気持ちが強くなっていきましたね」


農家さんの思いも一緒に
※最後に、入江さんが「地域おこし協力隊」の活動で、特に心がけていることを教えていただけますか。
「特に心掛けているのは、農家さんの思いと共に農産物を届けたいなっていつも思っているので、農業を始めたきっかけや、どういうところにこだわって日々農作業をしているのかを、きちんと情報として自分も入れておくことと、最近どういうこと困っていますかとか、そういうことはいつも頭の中に入れて活動していますね」
●じゃあ結構頻繁にコミュニケーションを取られているんですね。
「そうですね」
●これまでの活動でいちばん喜びを感じた時ってどんな時ですか?
「初めてドライブスルー・マルシェって開いた時に、消費者のお客様から、”那珂市に新しい風を吹かせてくれてありがとう”って言っていただいたのがすごく嬉しくって。やっぱり県民性なのか市民性なのか分からないんですけれども、どうしてもPR下手だったりとか、すごく魅力があるのにそれを露出するのが苦手な方がすごく多くて、それをうまく出せた瞬間なのかなと思って、それがすごく嬉しかったですね」
●日本全国の方に那珂市の魅力をもっともっと知ってもらいたいですよね!
「そうですね!」
●改めて、この番組を聴いてくださっているリスナーさんに伝えたいことがあれば、是非お願いします!
「多分この番組を聴いている方も、地域おこし協力隊と付き合う機会っていうのも多分あると思うんです。皆さん色々思いを持って、首都圏からはるばるその地域に根付こうと思って活動している方なので、是非優しく接していただきたいと思います。
あとは日本の農業って結構マイナスに言われることもすごく多いんですけれども、個々の農家さんはすごく努力して日々農産物を作っていらっしゃるので、是非スーパーとか直売所に行かれた時には、なかなか難しいかもしれないけど、その思いと共に一緒に購入して、家で料理していただきたいなって思います!」
INFORMATION
入江さんの活動については那珂市「地域おこし協力隊」のサイトをご覧ください。
◎那珂市「地域おこし協力隊」HP:https://www.city.naka.lg.jp/iinakakurashi/page/dir000068.html
個人的な活動として入江さんは、仲間と一緒に一般社団法人「ベジタブル漢方協会」を設立。不足している栄養素を野菜などの粉末で、毎日の食事に効果的に取り入れましょうということで、「ベジタブル漢方アドバイザー」を養成する講座を立ち上げました。
詳しくは「ベジタブル漢方協会」のオフィシャルサイトを見てください。
◎「ベジタブル漢方協会」HP:https://vegekanpo.com/
「粉活プロジェクト」については以下のサイトをご覧ください。
◎「粉活プロジェクト推進委員会」HP:https://kona-project.jp/
2021/5/30 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. CIRCLE / SWAN DIVE
M2. THOSE GOOD OLD DREAMS / THE CARPENTERS
M3. A BRAND NEW ME / DUSTY SPRINGFIELD
M4. STRAWBERRY FIELDS FOREVER / BEN HARPER
M5. Precious memories / JURI
M6. THE FEELING’S GOOD / MARLENA SHAW
M7. BRAND NEW START / PAUL WELLER
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2021/5/23 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、東京農工大学大学院・教授「小池伸介(こいけ・しんすけ)」さんです。
小池さんは1979年、名古屋市生まれ。東京農工大学卒業後、日本生態系協会などを経て、現職の東京農工大学大学院・教授に。専門は生態学など。現在は東京の奥多摩、栃木、群馬などの山林で、ツキノワグマの生態や、森との関係などを調査・研究されています。
きょうはそんな小池さんにツキノワグマの知られざる生態や、クマの視点で見る日本の森のお話などうかがいます。
☆写真協力:小池伸介、横田 博

ツキノワグマ=アジアクロクマ
※それではさっそく小池さんにお話をうかがっていきましょう。
●そもそも小池さんは、ツキノワグマの研究者と言ってよろしいんでしょうか?
「そうですね。実はツキノワグマだけじゃなくて、私は森林の研究をしているので、森林に生活している色んな生き物を対象にはしているんですけれども、ツキノワグマに関してはもう20年以上研究対象としていますね」
●去年『ツキノワグマのすべて〜森と生きる。』という本を出されましたけれども、この本はこれまでの研究の集大成といってもいい本ですよね。
「そうですね。22年ぐらいツキノワグマと関わっていて、その間、学んだこととか、現場で撮った写真を、写真家の方の写真と併せて掲載したものになりますね」
●第4章に、ツキノワグマがわかるQ&Aというのがあって、ツキノワグマ初心者の私でもすごく楽しく読めました。まず「ツキノワグマは世界のどこにいるの?」という問いがあったんですけれども。
「日本だとツキノワグマっていう名前なんですけれども、世界的に見るとアジアクロクマっていう名前なんですね。その名前の通りアジアに広く分布していて、西はイランあたりで、東南アジア、東の端が日本っていうように、アジアの広い地域の森林に生息するクマの種類になります」
●日本の固有種ではないっていうことなんですよね?
「固有種ではないですけれども、ただやっぱり大陸にいるツキノワグマに比べると、日本のツキノワグマはちょっと体が小さいって特徴はあったりします」

●続いて「ツキノワグマに天敵はいるの?」という問いもありました。
「今、日本ではツキノワグマを襲って食べたりするような野生動物はいないですね。ところが、海の向こうのロシアなんかですと、ちょうど沿海州と言って、北海道の対岸あたりを我々も調査しているんですけれども、そこだとツキノワグマの天敵は実はトラだったりするんですね。ツキノワグマはやっぱり冬眠しますので、そうするとその冬眠中のツキノワグマがトラに襲われたりするっていうのが結構知られています」
●この問いにも書いてありましたけど、「冬眠中に筋力は落ちないの?」というのがありまして、確かに人間は動かないと筋力って落ちちゃうイメージありますよね。
「そうですね。よく宇宙に行った宇宙飛行士が帰ってくると、筋力が弱くなっていたりとか、骨が弱くなっていたりとかしますね。
冬眠は3ヶ月から長いと半年ぐらいにわたって穴の中でじっとしているんですけれども、その間に骨も弱くならないですし、筋力も大きく落ちることはないんですね。
まだ分かっていないところは非常に多いんです。例えば筋力に関しては、冬眠中のエネルギーっていうのが秋の間に溜めた脂肪なんです。それをうまく使っているわけですね。それで命を維持しているんですけれども、その過程で出てくるタンパク質を上手く筋肉の方に回しているんじゃないかってことが知られています」
●へ〜! じゃあ冬眠を終えた後も、何事もなかったかのように動き回る生活が始まるっていうことですか?
「そうですね。春になったら動きますし、実は冬眠中でもずっと寝ているわけではなくて、うとうとしているんですね。我々が朝、布団から出たくても出られないようなあんな感じで、うとうとしていて。
近くを人が通るとか、何か人が作業をしたりすると、パッと起きて、穴から(匂いを)嗅いだりするんですね。いきなり走って逃げていったりとか、そんなこともできたりするので、やっぱり何かあった時のために、行動できる筋力を失わないんじゃないかって言われたりしています」

ツキノワグマの生態
※改めてツキノワグマの特徴といえば、なんでしょうか?
「色々あるんですけれども、やっぱりひとつは名前の由来になっている月の輪というところです。本にも色々写真がありますけれども、首もとにある三日月のような白い模様がツキノワグマの特徴のひとつですね。
ただ、ほかのクマでも、例えば東南アジアにいるマレーグマとか、あとヒグマの中でもそういう模様を持つ個体はいるんですね。その中でもツキノワグマは白が非常に美しい三日月のような模様があるというのはひとつ特徴になりますね」
●その月の模様っていうのは個体によって、大きさとか形も異なってくるんですか?
「そうなんですよ。我々の指紋と同じように個体によって模様が違うんですね。非常に綺麗な三日月のような模様のクマの写真がよく見られるんですけれども、中には真っ黒のもいたりとか、あとはエプロンのようにすごく大きい白い模様があったりとか、右半分しかない、左半分しかないとかっていうように、個体によって違うので、その模様の違いを使って個体を識別して、山の中に何頭いるかを数える取り組みも行なわれたりしています」
●なるほど〜。日本にだいたい今、ツキノワグマって何頭ほどいるんですか?
「実はそれは誰にも分からないんですよ。日本のツキノワグマで分かっているのは、どこにいるかっていう生息範囲って言いますけれども、範囲、場所と、あとは人為的に獲った数ですね。狩猟だったりとか、有害駆除なんかで、人間が捕獲した数は分かるんですけれども、実は山の中に何頭いるかは全く分かってないんですね。
北海道にはヒグマと言われる別の種類のクマがいて、ツキノワグマはいないんですね。ツキノワグマがいるのは本州と四国です。九州は以前は生息していたんですけれども絶滅してしまいましたね。四国も実はもう残り数十頭で、すぐ絶滅してもおかしくないような状況になっているんですね」
(注釈:九州ではツキノワグマは絶滅、四国では絶滅の危機にあるというお話がありましたが、その原因は、九州では戦後まもなく絶滅してしまい、記録がほとんどなく、わからないとのこと。また、四国はスギやヒノキの皮をはいでしまうので、林業の害獣としてたくさん駆除されてしまい、そのため、減ったままで数がもどらず、絶滅するのではないかと危惧されているそうです。
小池さんいわく「先進国で大きな動物が絶滅するのは、恥ずかしいことだ」とおっしゃっていました)
●ツキノワグマって1年をどう過ごしているんですか?

「ツキノワグマは、場所によって多少違うんですけれども、3月か4月ぐらいに冬眠が終わって出てきます。冬眠する場所は木の大きな穴だったりとか、地面の窪みだったりとか、そういった隠れられるようなところで冬眠をするんですね。
3月、4月ぐらいに冬眠を終えて出てきたクマは、最初やっぱりそんなに活発じゃないんですね。寝たり起きたりを繰り返しながら徐々に活発になっていって、5月ぐらいになると繁殖期になります。
5月、6月、7月ぐらいが繁殖期で、この時期はもうオスはひたすらメスを探す生活で、食べるよりもメスを探すっていうような生活をしています。メスの方は実は冬眠中に子供を産むんです。冬眠中に子供を産んで、子供を連れて出てきている母親は、この間は育児をしているんですね。メスの場合は育児をしているか、子供がいない場合はオスと繁殖行動したりするわけですけれども、それが7月まで続いて、8月ぐらいになると一旦ちょっとクマの活動も落ち着きます。
暑いっていうのもあるんですけれども、山の食べ物も少ないので、それほど活発じゃない時期が8月ぐらいにあって、9月ぐらいになるとまた活動がさらに活発になるんです。それはなぜかというと、秋の9月、10月っていうのは、そのあとに控えている冬眠に向けて食い溜めをするんですね。
冬眠中っていうのは飲まず食わずなんですね。飲まず食わずで過ごすために、そこで必要なエネルギーを秋の2ヶ月か3ヶ月の間に全部食べ蓄えるんですね。それを脂肪という形にして、食べ蓄えて、だいたいこの秋の間に体重を30%とか、場合によっては50%くらい増やして、それで冬眠に入る。なので結構1年間忙しい生活を彼らはしていますね」
成功体験が行動を変える!?
※小池さんは、どんな方法でツキノワグマの調査を行なっているんですか?
「色々クマを調査する方法があるんですけれども、私たちのグループがずっと行なっているのは生体捕獲と言って、野生のクマを山で捕獲をして麻酔で眠らせている間に、GPS受信機というクマの行動を追跡する装置を装着して、クマがどうやってどこでどう行動してるか、というような行動調査を行なうのがまずひとつです。

あとはやはり彼らの食生活に迫ったりするためには、山に行って彼らの糞を拾ったりとか、食べた痕跡を探して何を食べているのか、そういった調査をするのがクマの調査の基本ですかね。
シカとかサルとかと違って、クマって観察が非常に難しいんですね。シカやサルだと、テレビ番組にもあるように直接観察して、何をしているとか何を食べているっていうことを記録できるんですけれども、クマは群れは作らず、単独で行動していますし、森の中でひっそりと暮らしているので、なかなかクマに近づくのは難しいんですね。ですので、色んな道具とか方法を使って、クマに近づいてみるということを行なっていますね」
●調査や研究を積み重ねていく中で、どんなことが分かってきましたか?
「色々分かってきていることはあるんですけれども、やっぱりここ20年ぐらいで色んな調査技術が発達してきたんですね。例えば、ここ何年かもそうですけれど、秋にクマが出没しましたってニュースがあると思うんですけれども、実は昔から秋に出没するっていう現象はあったんですね。
ところが、何で秋にクマがよく出没するのかっていうのは、はっきりしたことはよく分からなかったんですね。おそらくドングリが不作だからなんじゃないかっていうことを言われていたんですけれども、はっきりとした関係は分かんなかったんですね。
ところがここ20年ぐらいで、先ほど言ったGPSを使ってクマの行動を追跡する装置が飛躍的に技術が向上して、クマの追跡がかなり、楽ではないんですけれども、はっきり分かるようになってきたんですね。
そういった調査をしていくと、やはりドングリがない時にクマは行動のパターンを変えて、普段生活しているところから遠くまで遠征して、ドングリを探したりとか代わりの食べ物を探すということは分かってきて、ドングリがないことがクマの行動を変える、それが出没に関係しているんじゃないかってことが、分かってきたことのひとつですね」
●じゃあドングリさえ手に入れば、人里には降りて来ないっていうことなんですか?
「基本的にはそうなんですけれども、実はドングリがないからといって、簡単にクマは人里に出るわけじゃないんですね。先ほど言ったようにドングリがないときは、普段行かないところまでドングリとか、ほかの食べ物を探しに行くんですけれども、そこに行った時に何もなければ、また次のところに彼らは行くんですね。
ところが普段行かない人里近くまで行った時に、ちょっと人里を見た時に例えば、収穫していない柿があるとか生ゴミがあるとか。彼らにとってはやっぱり人里に出るっていうのはすごいプレッシャーだし、リスクがあるわけですよね。でもそのプレッシャーとかリスクを上回る魅力的な誘引物があると、それに引き寄せられるように人里に出てしまう。
なので、いつもドングリがないから出没しますって言われてしまうんですけれど、実はその間にもうワンクッションあって、さらに人里に誘引するようなものがあると出てしまうということなんですよね。簡単に手に入るような食べ物があると、やっぱりそれに恐る恐るチャレンジして、簡単に食べられたっていう成功体験が彼らの行動を変えていくんですよ」
クマはタネの運び屋さん!?
※今までツキノワグマの視点で森を見ることって、あまりなかったのでしょうか。
「やっぱり先ほど言ったように、クマに迫る方法っていうのはなかなかなくて、先輩方が色んな調査をしたりして、やっとクマの姿っていうのが分かってきたっていうのがちょっと前までだと思うんですね。
で、色んな技術が発達して、クマの調査が色々出来るようになってきたっていうのと、たまたま私はどっちかというと、森林にかなり興味があって、どうしても最初は森に色んな生き物が棲んでいますので、その棲んでいる生き物のひとつとしてクマを見ようっていう感じで見ていたんですね。
実は私、昔は、今もそうなんですけれども、クマと植物、森林との関係をずっと研究してきていて、クマは実はベジタリアンなんですね。ほぼ9割ぐらいが植物を食べていて、特に果実が大好きなんですね。
ドングリを始め、森にある色んな果実が非常に大好きで食べているんですね。その中でも例えば、野生のさくらんぼとか、野生のぶどうとか、ちょっとタネの周りにジューシーな果肉が付いている果実って山にもあるんですけれども、ああいった果実を食べた時にクマってほぼ丸呑みなんですね。丸呑みした果実を糞として出すとどうなるかっていうと、実はタネがそのまま出てくるんです。
つまりクマは森にある色んな果実を食べながら、山の色んなところを動くことで、その木の実のタネを山中にばらまいている、種子を散布しているってことを私は研究していたんですね。
そんなところからも、やっぱりクマと森の関係というのは非常に大事で、もちろんクマは森を住処として暮らしているんだけれども、森の植物がクマをタネの運び屋として使っている、そういう言い方はよくないんですけれども、お互いにウィンウィンの関係にあるんじゃないかっていうことが、ひとつの分かってきたことになりますね」
●ちゃんとツキノワグマは森に貢献しているっていうことなんですね!
「そうですね。クマだけじゃないんですけれども、色んな動物が植物のタネを運んでいるんです。中でもクマはほかの動物が運べないような遠くまで、ものすごく行動力があるので、すごく遠くまで、何十キロも遠くまでタネを運ぶことができる役割を果たしているっていうのが分かってきましたね」
●今、ツキノワグマが置かれている状況はどうなんでしょうか?
「世間一般ですとやっぱりここ数年、特に秋になると(人里に)出没しましたとか、人間が怪我しましたとか、そういったニュースが非常に目立ってですね、世間一般のクマに対する印象とかイメージはあんまりよくないのかなと私は思っています。
一方で、本当に山の中に棲んでいるクマをちゃんと見たことがある人ってほとんどいないんですよね。ほとんどの人が人間に囲まれて街中走っているクマか、柿の木に登っているクマか、檻に入っているクマか、動物園のクマで、でもそれはクマの極々一面で、ほとんど山にいる多くのクマは一生に1回も人間に会わずに森の中でひっそり暮らしているんですよね。
そういう本当のクマの姿が知られていない中で、悪い印象ばかりが増えちゃったなっていうのが、最近の私のクマに対する、世間一般に対するイメージかなと思っています」

クマの個性はどう決まる!?
※小池さんは今後もツキノワグマの研究を続けられると思うんですが、今いちばん関心のあることって、なんですか?
「私は20年近くクマの調査をしてきて、先ほど言ったように捕獲をして、捕獲した時に血液を取ったりとかするんですね。そうするとその遺伝情報から例えば、人間の家系図みたいな、このクマとこのクマの子供があのクマで、このクマとこのクマの子供がまたこのクマで、っていうような家系図が出来てくるんですね。
クマって非常に個性の強い動物で、例えばクマと言っても非常にアクティブなクマもいるし、非常にオドオドしているクマもいたりとか、実はひとつの山の中でもクマの一頭一頭が食べ物って実は違うんですね。
我々人間を考えれば当たり前なんですけれども、やっぱりこれが好きなクマもいるし、あれが好きなクマもいるっていう感じで個性が非常にあるんですね。そういった個性が、どうやって決まっていくのかなっていうところに興味があって、ひとつはやっぱり親子関係というのも関係しているのかなと思っています。
子供は生まれてから母親と1年半ずっと一緒にいるんですね。その間に子供は母グマから、これは食べられるよ、これは食べられないよとかですね、ここに行けば食べ物があるよとか、ないよとか、色んな生きていく上で大事なことを教わって、1年半経つと子供と母親が別れるんですね。
そのあとはもうクマは単独なので、ほかのクマと接することが基本的になくて、例えば、あそこに行けば美味しいものがあったよとか、そういうやりとりは基本的にはないと考えられているんですね。
ですので、やっぱり最初の1年半の母親との行動が、おそらくそのクマの一生の行動とか個性を決めるんじゃないかなっていう気がしていて、そのあたりが生物学的には興味があるし、今各地で起きている人間との間の不幸な事故がいっぱいあるんですけれども、そういったクマが何で生まれてしまうのか、何でそういう状況になったのか、その個性が何で決まるかというところが分かれば、人間とクマとの間の不幸な事故を減らす、ひとつのきっかけになるんじゃないかなっていう気はしています」
●では最後に、小池さんの本『ツキノワグマのすべて〜森と生きる。』を手にする読者の皆さんにどんなことを読み取って欲しいですか?
「先ほどQ&Aのクマはこんな生き物だっていうところもあったんですけれども、やはりこの本のいちばんは、前半部分の写真家の澤井さんの素敵な写真がいちばんだと思うんですね。
先ほど言ったように皆さんが知っているクマっていうのは、ちょっと変わったというか、街に出てしまったクマとか、動物園のクマなんですけれども、でも実はこの狭い日本にこんな大きなクマが森の中にいるんだっていうあたりを、澤井さんの写真から感じ取っていただけるだけでも私は嬉しいなと思います」
●すごく大型のクマであっても、山を背景にするとこんなに小っちゃいんだっていう感じで、すごく雄大な壮大な写真ですよね!
「しかもやっぱりクマがいる風景っていうのが結構落ち着くんですよね。何か普通に自然な感じがするんですよね。でもそれが日本の自然だっていうところを知っていただけるといいなと思います」
INFORMATION
『ツキノワグマのすべて〜森と生きる。』
ツキノワグマの基礎知識から知られざる生態まで、わかりやすくて面白く、写真家「澤井俊彦(さわい・としひこ)」さんの写真も見どころいっぱいです。この本でツキノワグマのイメージが変わると思います。小池さんの20年以上の研究成果がまとめられた本、ぜひ読んでください。文一総合出版から発売中です。
詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎文一総合出版HP:https://www.bun-ichi.co.jp/tabid/57/pdid/978-4-8299-7232-8/Default.aspx
◎小池伸介さんの研究室HP:http://web.tuat.ac.jp/~for-bio/top-2jp.html
2021/5/23 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. THE ANIMAL SONG / SAVAGE GARDEN
M2. LOOK THROUGH MY EYES / PHIL COLLINS
M3. LOVE FOR ALL SEASONS / CHRISTINA AGUILERA
M4. KEEP ON MOVIN’ / SOUL II SOUL
M5. ぼくはくま / 宇多田ヒカル
M6. HELLO / LIONEL RICHIE
M7. RETURN TO POOH CORNER / KENNY LOGGINS FEAT. AMY GRANT & GARY CHAPMAN
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2021/5/16 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、シンガー・ソングライター「リピート山中」さんです。
山中さんは1960年、神戸市生まれ。12歳から弾き語りを始め、1996年にグループでデビュー。その後ソロ活動も行ない、2000年に「ヨーデル食べ放題」が大ヒット! そして、子供の頃から地元・六甲山に親しんでいたこともあり、山小屋や山頂などでライヴ活動。ほかにも地球や心の環境、家族をテーマにした楽曲作りなど“出かけて 出会って 感じて歌う”体験派シンガー・ソングライターとして活躍中です。
きょうは、そんな山中さんに山小屋コンサートのことや、山に魅せられた登山家への想いなどうかがいます。
☆写真協力:リピート山中

僕が山の歌を作る!?
●今週のゲストはシンガーソングライターのリピート山中さんです! よろしくお願い致します〜!
「はい! よろしくお願い致します! 」
●山中さん、今手に持っていらっしゃる楽器はウクレレですか?
「これね、ギターなんですけど、優れものでね。ギタレレっていう、某会社の割と低価格で買えるウクレレ・サイズのギターなんです。これ、山に行く時は必ずザックに縛り付けて、どこでも歌えるようにしているんですよ」
●へぇ〜! せっかくなので、ぜひ1曲何か弾いてください!
「じゃあ、ちょっと名刺代わりにね、唯一僕が作った歌でちょっとヒットした歌があるんで。こんな歌です」
(ここでギタレレの弾き語りで「ヨーデル食べ放題」の一節を歌っていただきました)
●うわ〜! ありがとうございます!
「この歌、今から20年以上前にちょっと東京方面でヒットしたんですけど、”ヨーデル食べ放題”」
●いやもう誰もが知っている曲ですよね〜!
「そうですか! 聴いたことありますか!? ありがとうございます」

●テンション上がります!(笑)。きょうは色んなお話をうかがいたいと思うんですけれども、リピート山中さんのオフィシャルサイトを見てみたら、山小屋でコンサートを行なっている記事がすごくたくさん載っていたんです。これはいつ頃、どんなきっかけで始まったんですか?
「最初は2004年のゴールデンウィークに、北アルプスのわさび平という小屋がありましてね、そこから始まったんですけれども、きっかけというのはね、私、中学生くらいからずっとギターを持って歌っては何かしていたんですよね。
その頃から山の歌も好きでね。昔ダークダックスさんとかが山の歌のLPレコードを出したりとかしてね。それこそ“雪山讃歌”とか色々有名な歌があるんです。ところがよく考えてみると、最近山の歌を作ったり歌ったりしている人がいないなと思いまして、若者たちはみんな海辺の歌が好きで。だから山の歌を作る人がいなければ、僕がやるしかないな、なんて思ってね。
で、歌から山につながるんですけど、じゃあ山に登って山小屋でコンサートをやろうと思い始めたのが大体2003年ぐらいなんです」
●ギターを背負って登るわけですよね?
「そうですね。まぁこれ(ギタレレ)は小っちゃいんで、ずっとザックの横に縛り付けているんですけど、いわゆる通常の大きなサイズの、ドレットノートサイズのギターも背負って登ったりもします」
●登山に必要なウェアや道具とかも持っていくんですよね?
「そうですね。最小限にして、それは小さなザックで前に赤ちゃんを抱っこするみたいな感じで。だから後ろにギターで、前に小さなザック、そういう感じで登って、最高の高さは富士山の剣ヶ峰までは行きました。で、ちょっと歌ったりとかして」

●ええ!? 何時間もかけて歩いてやっと山小屋に到着して、そこから歌うってなると、かなり体力的にも厳しいんじゃないですか?
「これはね、体力もさることながら、気力が・・・。通常、山に登られる方っていうのはやっぱり山小屋に着いたらほっとして、ここで一応ね、きょうのスケジュール終わりと。あとはもうビールを飲んだり、くつろいだ時間を楽しまれるわけですが、私はそこからが仕事なんで(笑)。
とにかくまだ、はめは外せないという、私がはめを外せるのは、皆さんの食事が終わったあとに1時間ほどコンサートして、そのあとですから、本当に消灯までのわずかな時間なんです。でもね、やっぱりそのために登っていますから、全然苦に思ったことはないです」
加藤文太郎に惹かれて
※山小屋コンサートで披露する定番曲にはどんな曲があるんですか?
「先ほど、ご挨拶で歌いました”ヨーデル食べ放題”、これ必ず歌うんですけど、やっぱり山の歌を作ろうと思って、私が作詞作曲して第1弾で作ったのは、実在した登山家”加藤文太郎”という、小尾さんお聞きになったことあります?」
●お名前だけは・・・。
「明治生まれの方で、兵庫県の浜坂っていう日本海側に生まれて、14歳から私の住んでいる兵庫県の神戸で、造船所で図面を引きながらね、山を覚えていくんですけど、当時画期的な、たった一人で真冬の北アルプスを縦走して歩くという、とんでもない登山をやった人で、今の社会人登山の先駆者なんですよね」
●どうしてまた加藤さんの歌を作ろうと思ったんですか?
「山に登るに際して、色んな山に行っている先輩に話を聞いたんです。何か注意しないといけないことないですか? とか、何か知っておいた方がいいことないですか? とか言うと、この本を読んどけって言われてね。それが新田次郎という小説家の『孤高の人』っていう小説だったんです。それの主人公が加藤文太郎という実名、小説はフィクションなんですけど、その人の魅力に惹かれて、故郷の浜坂を訪ねたり色々しながら歌を作ったんです」
(ここでオンエアでは「加藤文太郎の歌」を聴いていただきました)

嘘のない山の歌
※山での体験は、シンガー・ソングライターとしては、曲作りにつながっていますよね?
「そうなんですよ。山に登って山の歌を作って山の歌を歌うというのを出発点にしているんですけど、やっぱり行った者でないと分からないものがあるんですよ。だから街中で山を想像して作るのと、実際に登ってその苦しさとか、爽やかさとかを体感して作るのではやっぱり違うんですね」
●そうですよね〜。
「だから嘘のない山の歌を作れているなと」
●山関係の方とも色々つながりとかはありそうですけれども、いかがですか?
「やっぱり加藤文太郎っていう人がすごく山の世界ではまだ有名人で、昭和11年に亡くなっているんだけども、いまだに人気があるんですよ。で、この文太郎さんの歌を私が歌っているということで、色んな人が私に話しかけてくださったりとか、文太郎さんのご縁で、例えば(登山家の)田部井淳子さんであるとかね、モンベルの辰野会長であるとか、この前(この番組に)ゲストで来られたシェルパ斉藤さんもそうですね」

●歌がつないでくれたご縁ですね。田部井淳子さんは2016年10月にお亡くなりになっていますけれども、田部井さんに作詞をお願いして出来上がった曲もあるんですよね?
「そうなんですよ。出会ったのは某公共放送のラジオの公開収録だったんですけど、そこでご一緒しまして、私の色々な歌を聴いてくださって、やっぱり“加藤文太郎、私も好きなのよ”ってね。
で、私の持っているこのギタレレ、これを“私も弾きたい”って言ってね。当時70歳だったんですけど、田部井さんがこのギターを売ってくれと言って、だから私、別あつらえで購入して田部井さんにお送りしまして。
そのあと色々交流があって。で、山の日というのが制定されるというので、その時に山の日の歌を私、作ろうと思ったんです。
でも、リピート山中ごときが山の日の歌を作りましたって言っても、誰も相手にしてくれないだろうと思って、誰かに詞を書いてもらおうと思った時に、この人しかいないと思ったのが田部井淳子さん。
田部井さんに山の日をイメージして歌を作ってもらったら、僕が曲付けてこれを皆さんに知ってもらいたいなと思ってお願いしたら、お亡くなりになる直前にメールで詞が届いたんですよ。だから出来上がりを田部井さんに聴いていただくことはできなかったんですけど、身内の方とか、そのお友達の方にはお披露目もして、今一応CDも作ってはあるんですけどもね」
●天国で聴いてくださっていると思います。
「この詞がね、田部井さんの遺言みたいな詞なんです。というのは、女性で世界で初めてエベレストの頂上に立った人なんですけど、そういう命がけの厳しい登山もする一方で、とにかく男の世界だった山の世界に、女の人どうぞ! 行きましょう! 楽しいよ! って言ってね。
低い山でいいんで一緒に行って、ピクニックがてらお弁当を食べてって、ものすごくたくさんの人を山に誘ったんですよ。そんな気持ちをずっと持っておられて、山って楽しいよっていうことを、どうぞ山の楽しみを知っているあなたが伝えてあげて、みんな山に連れてあげてよっていう思いを書いてくださったんです」
(番組ではここで「山ってやっぱりたのしいよ」をオンエアしました)
「行きあたりばっ旅」 はサプライズ曲!
※先月この番組にご出演いただいたバックパッカー「シェルパ斉藤」さんから、リピート山中さんが、自分の誕生日に歌を作ってプレゼントしてくださったと連絡があったんですが・・・タイトルが「行きあたりばっ旅」?
「シェルパ斉藤さんの人生観そのものやね、”行きあたりばっ旅”っていうのはね。とにかく行ってみるというね。そのシェルパさんの言葉をいただいてタイトルにしたんですけども、元々はこれ、ご本人には内緒の話だったんです、サプライズで誕生日プレゼントをしたいと。
息子さんの一歩くんがちょっと知り合いなんで相談に来られましてね。もちろん奥様もなんですけど、家族のみんなで、お父さんのシェルパ斉藤さんに誕生日サプライズプレゼントしたいと、だから歌を作ってほしいと言われて。で、何度も一歩くんと打ち合わせして、当日まで気付かれないように、家族の人も大変だったみたいなんですけど、出来上がりました」
●そうだったんですね! 作詞は奥様や一歩くんのアドバイスがあったってことですか?
「そうです。やっぱり一人の人物のことを歌にするとなると、知ってないと出来ませんから。一歩くんや奥様から色々資料を、新聞の記事とか本とか、そういうのをいただいて、とにかく本人が聴いて、“おい、それは嘘だぞ”って言われたらおしまいなので、とにかく本人のチェックがないままに発表するわけだから、よく練り合わせて作りました」
●斉藤さんには生演奏で披露されたということですけれども。
「そうです、そうです。生で聴いていただいて、その横で奥さんと、ご近所歌劇団がいらっしゃってね。ご近所の仲良しのお姉さん方が振り付けして踊ってくださって、それをシェルパ斉藤さんはもう照れながらというか何ていうか、面白かったですわ(笑)」
●シェルパ斉藤さんは何かお言葉はおっしゃっていました?
「嬉しいという気持ちは持っている、ただどう表現していいか分からないと。とにかく照れ臭いし、いちばんいいのは泣いたらいいだろうけど、泣くわけにもいかんなと(笑)。この気持ちはわかるんです。仮に私が斉藤さんの立場であっても恥ずかしいですよ! 家族の者が私に何か歌を作ってプレゼントされて、いきなりそれ聴かされたら、まぁ正直戸惑いますね。ただね、こうやって小尾さんのこの番組“ザ・フリントストーン”に斉藤さんの方から情報がいったということは、気に入ってくれている証拠ですよ、これは!」
●本当そうですよ! すごく喜んでいると思います〜。すごく嬉しいと思います。
「聴かせたくなかったら内緒にしているはずですから、だから斉藤さんも、これは例えば仮にオンエアしてもいいよというぐらいのね、気持ちになってくださっているってことやから、よかったんじゃないですか(笑)」
●サプライズ大成功ですね!
(ここで「行きあたりばっ旅」をオンエア!)
「見えてるラジオ」生配信中!
※いまは新型コロナの影響で、なかなかライヴができない状況にありますが、そんな中「見えてるラジオ」という生配信ライヴをやっているそうですね。これはどんな配信ライヴなんですか?
「これFacebookで基本的に毎週やっていまして、今50回目まで終わったんですけど、週末の夜の10時からね、私とFacebookで繋がっている人はみんな無料で見られるんですよ。そのあとYouTubeにも“リピート山中チャンネル”っていうのがありますので、検索していただいたら、そこにも全部アップしています。
ギター1本で、自分の家の汚い部屋で何の飾りもなく、ただただ歌って喋ってという歌語りのラジオ。一応映像は見えていますけど、ラジオ好きなんで」
●山小屋コンサートはいずれ復活させる予定はあるんですか?
「これはもう小屋の状況次第ですね。一応今年も槍ヶ岳山荘とか、南岳小屋、槍沢ロッヂ、このグループがやろうという方向では話を進めてくださっているんです。ただこれは本当に状況判断しないと、今決められないので、一応やる方向だけど、今後の状況次第。もしやるとしたら7月の後半になると思いますけどね。まだこれは未定の話ですけど」
●今後も山を歌う活動は続けられるということですよね。
「そうですね。毎年7件から8件、レギュラーで小屋に行っていますから、そこに本当に安全にみなさんが集って、僕も歌を歌って、みんなと一緒に歌える日が1日も早く来ることを本当に心から願っております」

INFORMATION
山中さんが毎週土曜日の夜10時からFacebookで生配信している「見えてるラジオ」、ぜひ見てくださいね。歌ってトークをして歌って、という感じで、ほんとにラジオのような親しみやすさがあります。YouTubeの「リピート山中チャンネル」でもご覧いただけますよ。
今後の山小屋コンサートを含めたライヴ情報などは、ぜひリピート山中さんのオフィシャルサイトを見てください。また、山中さんのCDや音源はオンライショップで購入できます。
◎リピート山中さんオフィシャルサイト:http://repe.jp/
2021/5/16 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. PEACEFUL EASY FEELING / EAGLES
M2. FOR ONCE IN MY LIFE / STEVIE WONDER
M3. 加藤文太郎の歌 / リピート山中
M4. 山ってやっぱりたのしいよ / リピート山中
M5. WE ARE NEVER EVER GETTING BACK TOGETHER / TAYLOR SWIFT
M6. 行きあたりばっ旅 / リピート山中
M7. RADIO / THE CORRS
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2021/5/9 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、葉山のダイビングショップNANAの代表で、ダイビングガイドの「佐藤 輝(さとう・てる)」さんです。
1976年、葉山に生まれた佐藤さんは、学生時代はヨット部に所属し、毎日のように葉山の海で練習。卒業後は有名ホテルの営業マンとして働いていたそうですが、体験ダイビングでその魅力に取りつかれ、ダイビングガイドの道へ。そしてサイパンなどで修行したのち、15年ほど前にダイビングショップNANAをオープン、湘南の海を知り尽くしたガイドとして活躍されています。
そんな佐藤さんが先頃、写真集『湘南 波の下水族館』を出されました。この写真集は鎌倉在住の水中写真家「鍵井靖章(かぎい・やすあき)」さんとの共著という形で出版されています。
きょうは子供の頃から葉山の海に親しんできた佐藤さんに湘南の海の特徴や、気になる海の変化などうかがいます。
☆写真協力:佐藤 輝

魚と同じ目線に感動!?
※それでは佐藤さんにお話をうかがいましょう。初めて地元の、葉山の海に潜ったときは、どうでしたか?
「それは今でも鮮明に覚えているんですね。ヨットで海の上にはもう毎日のように行ったし、小さい時から磯場とかでもいっぱい生き物を見たりもしたんですけど、初めて葉山の海に潜った時は何かもうびっくりするぐらい感動しました。水中で苦しくなくて、普通に呼吸が出来て、魚と同じ目線にいる自分に感動っていう感じでした」
●ダイビングガイドになろうと思ったのは何故なんですか?
「それは、ライセンスは社会人1年目で取ったものの、本当に軽い趣味だったんですね。年に2回ぐらい海外に行ったら潜ってみたりとか、そんな程度だったんですけども、だんだん社会人の時の趣味が、どんどんのめり込んでいくというか、土日にどこに潜りに行こうかなっていうのを考えるのが、いちばんの楽しみぐらいダイビングが好きになっていて、ある日とっても浅はかなんですけど、これを仕事にしたら毎日潜れるのになぁ〜みたいな気持ちになってきて、もうその気持ちが抑えられなくてサラリーマンを辞めました」
●そうだったんですね! 今はお客さんの案内を含めて年間どれぐらい海に潜っているんですか?
「その年によってちょっと違うんですけど、だいたい数えたら250日でした」
●ええ!? すごい! 転職してよかったですね!
「そうですね。本当に好きなことを仕事にしているっていうことに、とっても毎日のように感謝はしています」
●毎回、未だに感動しますか?
「これはとっても正直に言うなら、さすがに毎日のように潜っているんで、毎回、感動の頂点みたいなのを迎えているわけではなくて(笑)、とっても今は基本的には日常というか、普通の方が会社に行ってくるねっていう感覚で潜っているんですね。
ただサラリーマンの時と大きく違うのは、毎日じゃないですけど、見たことないウミウシっていう生き物が出てきたりですとか、あとは普段いっぱいいるお魚が、生態行動って言うんですけど、産卵してみたりとか、そういうことがちょいちょい起きるんで、そういうのを見た時はやっぱり、どの仕事も感動って毎日やっていてもあると思うんですけど、僕たちはそういうところにすごく感動を覚えますね」

穏やかな海
※改めて、葉山を含めた湘南の海の特徴を教えてください。
「相模湾っていう湾にある海なんですけども、相模湾の中では結構奥まったほうにあって、水深とかも深くなくて、イメージ的にはお気軽にダイビングできるというか、来るのも近いし、ボートに乗っている時間も短いし、潮の流れが強いとかもなくて、とっても穏やかな海にちょっと気軽に潜りに行けるっていう感じが特徴の海ですね」
●年間を通してどれくらいのお魚を見ることができるんですか?
「ちょっと考えてみたんですけど、何種類って分からないなと思いまして、例えばきょうの朝も潜ってきたんですけど、バッと見渡しただけでも何十種類っていう風に、一箇所見てもブワッといるんで、今度機会があったら数えてみたいと思います(笑)」
●そんなに葉山の海にたくさんの生き物がいるっていうのは、やはりそれを支える豊かな生態系があるからっていうことですか?
「それは本当そう思います。やっぱり岩場があって、砂地があって、色んな環境があって、そういうことがたくさんの魚たちがいる環境を作ってくれているんだと思います」

海中の春夏秋冬
※陸上は初夏を迎えつつありますが、海の中も春・夏・秋・冬と季節の変化はありますか?
「とってもありまして、陸よりも海の方が春夏秋冬を少しだけ先取るんですよ。ざっくり言うと、春は気温が冬から春になって、だんだん上がってきて、魚が増えてくる季節みたいな感じで、プランクトンが増えて、海の透明度が落ちて、海が汚くなるんですね。でもそれはとっても海にとっては栄養が豊富で大事なことで、生まれてきた小さなお魚たちはそのプランクトンを食べて大きくなっていきます。
夏になると水温がどんどん上がってくるんで、いちばん魚が多い季節みたいな、海の中に群れがいっぱいいます、みたいなのが夏です。夏の終わり頃になると今度は、季節来遊魚って言うんですけど、黒潮っていう南からこっちのエリアの方に流れている潮に乗っかって、熱帯魚たちが流れてくるんですね。夏秋は群れとその季節来遊魚っていう熱帯魚、普段は見られない子たちを楽しむ季節ですね。
秋が終わってだんだん水温が下がってくると、さっきとは逆でプランクトンがどんどん減ってくるんで、透明度がドンドン上がってくるんですね。綺麗な海になってきて、その代わり群れは減って、水温が落ちた冬は、冷たい水温でしか生きられないお魚たちを観察できるようになるサイクルでまわっています。本当に春夏秋冬で全然違うものになるっていう感じがあります」
●葉山の海でそれぞれの季節を代表する生き物は、例えばどんな種がいるんですか?

「いちばん人気みたいな感じで言うと、春はダンゴウオです。ダンゴウオは大きさ1センチもないようなお魚なんですけど、お団子みたいな、これがもうとにかくダントツ人気で、この子は3月ぐらいから5月しか見られないんですよ。水温が上がってくるといなくなっちゃうんですね。
夏になると、夏秋はやっぱり季節来遊魚が人気なので、ミナミハコフグの赤ちゃんとか分かりますかね? さかなクンが被っている帽子の」
●あ〜! はいはい!
「あれも1センチとかそれぐらいの大きさなんですけど、あんなお魚たちが人気の魚です。夏秋はそういうのが人気で、冬になると葉山の場合は、ウミウシって分かりますか? ナメクジみたいな、本当は貝の仲間なんですけど、そのウミウシが冬になると一気に増えるんですね。1日30種類とか40種類とか見られるんですけど、冬はそのウミウシが人気ですね。人によって好きなものが違うんで何とも言えないんですけど、僕のお勧めはそんな感じです」


海藻が激減している!?
※葉山の海に潜り始めた頃と比べて、何か変化を感じることはありますか?
「これは多分どこの海も、この辺でいうと伊豆や千葉がダイビングポイントとしては、割と多くの方が潜っている場所なんですけど。どこもだと思うんですけど、やっぱり海藻が激減しているエリアが多いですね。
昔はアカモクっていう海藻に引っかかっちゃって、浅いところは冬になると前に進めないぐらい海藻が生えていたんですけど、それが全く何もなくなっちゃっているところもいっぱいあって、10年前と比べたら全然違う景色です」
●そうなんですか。地球温暖化の影響っていうのも感じることは多いですか?
「僕はその専門家ではないので、ダイビングガイドの僕が地球温暖化ですって言い切るのはちょっとよくないのかもしれないんですけど、確実に冬の水温が昔に比べると1度か2度は高いんですね。昔は12度から13度までいちばん冬の冷たい時に落ちたのが、今は14度ぐらいにまでしか落ちていなくて、陸上に比べると水中の2度っていうのは、陸上の何倍も大きい差があって。
やっぱりよくよく考えてみると、昔当たり前のようにいた魚がすごく減っていたりとか、いなくなっちゃっていたりとか、そういうのはやっぱりすごく大きく言ったら、地球温暖化は絶対関係しているんだろうなとは思います」

●佐藤さんがいちばん危惧していることって何ですか?
「それは写真集にもそういうページを作らせていただいたんですけど、色んな魚が減ったりとか、色んなことが起きているんですね。もととなっているいちばん悪いことは、さっきも言ったんですけど、海藻が減っちゃっていることだと思います。海藻が減って小さいお魚たちが隠れる場所がなくなるから大きいお魚に食べられちゃうとか、だから何とかその海藻を取り戻すことが出来れば、もとにもう一回戻るチャンスはあるんじゃないかなっていう気がします」
●どうやったら戻るんでしょうか?
「例えば僕たちがいつもやっているのは、海藻が減ったことによって”磯焼け”って言うんですけど、ウニとかが食べるものがなくなっちゃうんですね。海藻を食べていたのに海藻がなくなっちゃうんで。
今までは岩の下とかに隠れていて、夜ちょっと出てきて、いっぱいある海藻を少し食べていたウニが、食べるものがなくなっちゃうんで、どんどん表に出てきて、もう何でもかんでも食べだしちゃうんですね。そうすると岩肌が全部見えてきちゃうような状況に今はなっていて。それもまた賛否両論あると思うんですけど、その海藻を食べてしまうウニを漁師さんと一緒にみんなで駆除したりするんですね。
でも僕がいつも思っているのは、そのウニを僕らレベルが10人20人で潰したところで、海藻が全部のエリアに戻ってくるとはもちろん思っていないんですけれども、何かそういう地道な活動をして、今そういう大変なことが海に起きているんだよっていうことを、少しでも多くの方に知っていただくことが大事なのかなと思います」
気をよくしてくれる場所!?
※最後に「佐藤」さんが感じる海の魅力って、どんなところですか?
「やっぱり何かちょっと神がかっているかもしれないんですけど、気がよくなる感じがすごく僕はしていて。やっぱり嫌なこととかあっても、毎日海に潜っているといつもフラットな気持ちでいられますし、あとはたまに潜りに来てくれたお客さんが、潜るとなんとなく自然な感じで、“海はいいなぁ〜”みたいなことを本当に自然に言っているのを見たりしていると、やっぱり人間をリフレッシュさせて気をよくしてくれる場所なんだなっていうのが魅力なんじゃないかなと思います」
●私はシュノーケリングしかしたことなくて、ダイビングはしたことないんですけれども、やはり深いところから見るとまた全然違いますか?
「シュノーケリングとはやっぱり違いますね。最初に言った、魚と同じ目線にいるっていうのがやっぱり僕の中では大きく違いますね」

●気持ちよさそうですね! 一緒に泳げるわけですよね。
「そうですね。本当に一緒に泳いでいる感じですよ」
●今後も佐藤さんは、葉山の海の写真っていうのは撮り続けるわけですよね?
「もう僕は、写真集を出させていただくのは今回が人生で最後だとは思っているんです。でもやっぱり10年前の写真と今の写真は、要は今は10年前の写真を本当に撮れなくて、海藻もなければ絶滅した魚もいれば。
なので10年前の写真を撮っておいてよかったなと思うこととかいっぱいあるので、これからも写真を撮って、楽しみつつ、ちゃんと葉山の自分のホームとしてる海の記録を残すという意味でも撮っていこうと思っています」

●改めて今回の写真集『湘南 波の下水族館』でいちばん伝えたいことは何でしょうか?
「湘南に住んでいる子供にもとっても伝えたいんですけれども、都心から近い湘南って何かすごくお洒落な海だけど、潜るっていうイメージがまだ多分ないと思うんですね。でも東京から近い海にはたくさんの生き物が暮らしていて、とってもカラフルな海が広がっていて。
でも今その海には温暖化を含め色んな危機が迫っていて、このままだったらそのカラフルな海は失われちゃうんじゃないかなっていう危機感も感じています。素晴らしい海だっていうことと、今その海に危機が来ているんだよっていう両方を見ていただけたら嬉しいなと思います」
INFORMATION
『湘南 波の下水族館』
佐藤さんが水中写真家の鍵井靖章(かぎい・やすあき)さんと共に出版した写真集です。東京から近い海にこんなにもカラフルな生き物がたくさんいることに驚きます。数メートル潜っただけで別世界が広がっていることが分かり、可愛らしくてユーモラスな生き物たちに癒されますよ。青菁社(せいせいしゃ)から絶賛発売中です。
詳しくはダイビングショップNANAのオフィシャルサイトをご覧ください。
◎ダイビングショップNANA HP:https://nana-dive.net/
◎青菁社 HP:https://www.seiseisha.net
2021/5/9 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. 希望の轍 / サザンオールスターズ
M2. UNDER THE SEA / 平井大
M3. TO THE SEA / JACK JOHNSON
M4. FISH / JEFFREY FOSKETT
M5. ピンク・シャドウ / ブレッド&バター
M6. BEYOND THE SEA FEATURING JOHN SHIPE / HALIE LOREN
M7. DEEP SEA DIVER / BRISTON MARONEY
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2021/5/2 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、「こどもみらい」の代表「廣瀬泰士(ひろせ・たいじ)」さんです
廣瀬さんは1973年、高知県生まれ。学生時代に建築を学び、都市計画のコンサルタント会社から造園会社に転職、園庭造りに携わり、2011年に独立し、「こどもみらい」を設立。園庭造りのかたわら、講演活動も行なっていらっしゃいます。
園庭というと、滑り台やアスレチック用の遊具があるイメージだと思いますが、廣瀬さんが手がける園庭は、草木や生きものたちと触れ合えるような造りになっています。そして先頃、『園庭づくりのヒントがいっぱい〜こどもがあそべる木と草花』という本を出版されました。
☆写真協力:株式会社 こどもみらい

先生たちと一緒に造るオリジナル園庭
※それでは廣瀬さんにお話をうかがいましょう。廣瀬さんが手がける園庭にはどんな特徴があるんでしょうか。
「基本的に園庭っていうのは遊具先行型っていうのが主流です。ですが僕たちは、当然遊具もお客さんのご要望があればご提案させていただきますが、決して遊具ありきの園庭造りではないというところです」
●具体的にはどんな庭を作ってらっしゃるんですか?
「基本的なテーマと言いますか、自然と冒険というテーマで取り組んでいます。その中で園庭造りにおいては、弊社の者が保育園に対して一方的にご提案するわけではなくて、先生方と一緒に話をしながら積み重ねていって、その都度、ご提案をして修正をしてというような組み立てと言いますか、積み重ねで園庭造りをしています。結果的に園オリジナルの園庭が出来上がるというところです」

※廣瀬さんの園庭造り、その工程を少し説明しておきましょうね。
保育園や幼稚園からの問い合わせを受けて、現地におもむき、丁寧にヒアリングを行ないます。そこには今ある園庭を良くしたいという園長さんや先生たちの思いがあるのでそれをしっかり汲み取りつつ、今まで廣瀬さんが手掛けた事例を説明。そして本格的な図面を作る前に、改造する園庭のイメージを絵で表現し、共有します。
その後、着工しても一度には工事を終わらせないそうです。そこそこの面積がある園庭の場合、先に取り掛かるエリアを決めて、第1期の工事を行ないます。そして、そのエリアで四季を通して、園児たちと遊んでもらい、第2期の工事に入る前に、着工前に決めた計画で進めていいのか先生たちに問いかけるそうです。
そうすると先生たちから意見や要望が出てきて、それを受けてマイナーチェンジを行ない、その後、夢の園庭が完成するということです。

廣瀬さんいわく、短期間で完成させるのではなく、工事をする期間を1期から3期くらいまで分け、中長期で取り組むのがポイントだそうです。また、植物を植えたりする作業を、先生や園児たちと一緒に行なったり、工事をしている様子を園児たちに見てもらったりするそうですよ。これ、いいアイデアですよね。園児たちに愛着がわきますよね。
廣瀬さんの会社「こどもみらい」では完成後も定期的に樹木の剪定や木の遊具のメンテナンスも行なっているとのことです。
もともと自然が好きだった!
※廣瀬さんは自然豊かな四国の高知で育っていらっしゃいます。そのことも今の仕事のバックグラウンドになっているようですよ。
「地域独特の特徴のある自然ってあると思うんですけど、僕の祖父母だとか、あと友達とかと遊んだその豊かな自然っていうのが、僕の今の人間性をすごく形成したと思えるんです。自然と本当に共に生活したという、まぁ市内なんでね、そんな山の中っていうわけではないんですけども、お爺ちゃんお婆ちゃんから生活の中でいろいろ教わった、季節が巡るその自然と共に生活したっていう、それが僕の中で染み付いているもんですから、そういったことですかね」
●冒険とか自然体験ができる園庭を造ると言っても、色んな知識がないとだめですよね? 土木的な知識から、植物だったり生き物だったり、幅広く知っていないといけないと思うんですけれども、廣瀬さんはどちらで勉強されたんですか?
「もともとは自然が好きだったものですから、虫とかそういうことにはすごく興味、関心はありました。当然学問として勉強しているわけじゃないんですけども、すごく興味があったので、本だとかはすごく常々読んでいたりもしていました。
で、造園の技術っていうのは当然(造園会社に)入社した時から社内の人間、先輩とか、職人さんとか、いろいろ教わっていました。ただ園庭造りに関してはそれだけではなかなか出来なくて、そこで僕も前職の頃から、やはりこれは保育に関する専門的な知識は必要だなと思って、通信で保育士の資格を取ったっていうのがありますね」
●やはり保育士さんの視点っていうのも大事な要素ですね。
「そうですね。僕は必要かなと思っています。社内のスタッフにも頑張ってねとは言っていますが、なかなか両立が難しいところがあって、やっぱり子供の成長とか発達っていうのは僕たち設計する上ですごく基本になるところなんです。だから今の園庭をいろいろ考えていく中での基礎になっていると思います」

豊かな人生を味わうきっかけに
※廣瀬さん、自分が手掛けた園庭で、園児たちにどんなことを感じとって欲しいですか?
「自然の大切さと言いますかね、触れ合うことでの喜びとか感動を味わってほしいんですね。当然、人間って誰しもが生き物が大好きとか、土に触るのも全然問題ないよってなかなかそうはならないですね。苦手な人もいます。
それは決して良い悪いじゃなくて、やっぱり人として成長していく中で、何か出来事があって、それに対する反応で、苦手だなとか見るのも嫌いってなると思うんですけれども、それはもう止められないし、決して悪いわけでもないんです。
おぎゃあと産まれた子供が生き物を見て、例えば蝶の幼虫を見て、これ気持ち悪いとはならないんですよね。そもそも生き物とは認識しないんです。ムニュムニュ動くもんだと思って、やっぱり子供っていうのはいろんなものに興味を持ちます。でもそれがいつぞや成長していく過程で先ほど言ったように苦手になるんですね。
その中で特に好きっていう人たちが、例えば昆虫博士になったり生物学者になったり科学者になったりすると思うんですね。ですので、弊社が関わらさせていただいた、先生たちと共に作った自然豊かな園庭で子供たちに、せめて乳幼児期、0〜5歳までのこの間、思う存分自然と触れ合ってほしい、そこでいろんな体験をしてほしい、いろんな感動を味わってほしいですね。
でも、その中でも苦手な子は早々に出てくるし、もっと興味のあるサッカーとかで遊びたいってそういう子たちも興味はそっちに行きます。でもそれはそれでいいです。いいですというか、僕はそんな良い悪いを判断するわけじゃないですけど、それはそれで尊重していいと思うんですね。

ましてや一緒に造った自然豊かな園庭で、ここで育った子供たち全員、生物学者になってほしいなんてこともないわけです。ただそういった環境を整えることで、経験する機会が要するに増えるわけなので、少しでも(自然や生き物に)興味を持って、その子の豊かな人生を味わうひとつのきっかけと言いますかね。園庭でやれることなんて本当に人生の中では一瞬なんですが、その一瞬だけでも思う存分、安全と言われる園庭の中で、先生たちと一緒にその感動を味わってほしいなと。
どういう結果に繋がってほしいとかそういうことはないです。単純にその瞬間を思い切って、“センス・オブ・ワンダー”って言うんですけどね、自然の不思議さとかそういったことに目を見開いて、感動とか感性を思いっきり育める環境を、先生と共に育みたいと思っています」
名前はあえて教えない!?
※廣瀬さんは先頃『園庭づくりのヒントがいっぱい〜こどもがあそべる木と草花』という本を出されています。この本は保育園や幼稚園の先生向けに書いた本なんですか?

「そうですね、僕たちが日頃やっぱり接していますのは先生方とのお話、対応っていうのが多いですから、やっぱり先生たちに対するメッセージがありますが、本として世に出ていますから、当然お母さんに限らず、お父さんも含めて、子供と関わる方々は読んでくださいとは言いませんが(苦笑)、ご参考に何かしていただければいいかなという風に思っています」
●公園に咲いている花について、ちょっとうんちくが言えたりとかできますね! この本を参考にすると。
「よく園庭で木を植えたりして、先生方が名前を知りたがるんです。この木は何? って、それは子供たちに伝えたいから、それは分かります。でも、何かね、名前を書いて覚えてくださいって言って覚えたら、先生の中で完結しそうで。
この名前を知った、でも実はその後のストーリーが大事で、子供たちとどう遊ぶか、共有するか、その本にもあるようにどのように遊べるか、食べられるか、どんな味がするかっていうのはその先にあるもの。だから僕、名前を聞かれてもあんまりパッと答えずに考えてみてくださいって言います。
植物って昔の人は生活と馴染んで名前をつけたものが多いじゃないですか。だからそれの名前をすぐ言わずに、“先生これ何に似ていると思う?”というところから始まって順番に考えて、“そうそう、それ!”とかね。そういうのを先生にぜひ子供たちと一緒にって。名前はあんまり僕はあえて言わないようにしています」
●ストーリーごとお伝えするっていうことなんですね。
「そうそう、そこが実は楽しいところなんですよ」
●この本はお庭がある一軒家に住んでいる方にも参考になりそうですよね!
「そうですね。ぜひ子供たちと一緒に(植物を)植えてほしいですし、季節を感じてほしいですね」
子供たちの豊かな感性のために

※では最後に、廣瀬さんが園庭造りを通して伝えたいことを教えてください。
「僕たちは園さんからご要望あったことを誠実に応えている、スタッフとみんなで頭を悩ませて頑張っているだけなんですけども、おそらくひと昔前は、僕たちのようなこの仕事の取り組みってビジネスにならなかったと思います。っていうのは身近な自然っていうのはそこら中にありましたから。
そこに対するアプローチとか、まさにその本に書いてあるようなことっていうのは、僕が友達や爺ちゃん婆ちゃんとかと一緒に生活する中で、実は身につけたものなんです。だからこの時代だからこそ、こういったことを伝えないと、子供たちの豊かな感性とかそういうことは育まれないんじゃないかなと一方で危惧をしながらも、僕たちは仕事に一生懸命向き合うだけなんですけども、そういったことを先生たちと一緒に子供たちに伝えられたらなというだけです 」
INFORMATION
『園庭づくりのヒントがいっぱい〜こどもがあそべる木と草花』
この本には園庭造りのヒントが第5章にまとめられていますが、第1章の「春」編から第4章の「冬」編まで樹木や草花を紹介。植物の特徴はもちろんなんですが、その植物にどんな昆虫が寄って来るのか、葉っぱでどんな遊びができるのか、熟した実を食べたり、ジャムを作ったり、植物を通して、どんな遊びができるのか、それをイラストや写真でわかりやすく解説。これは小さなお子さんを持つパパやママ、孫がいるおじいちゃんやおばちゃんにも読んで欲しい一冊です。小学館スクウェアから絶賛発売中! 詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎小学館スクウェアHP:https://shogakukan-square.jp/publish/books_new/747/
廣瀬さんが代表を務める「こどもみらい」のオフィシャルサイトは以下。
◎「こどもみらい」HP:https://www.codomomirai.com/