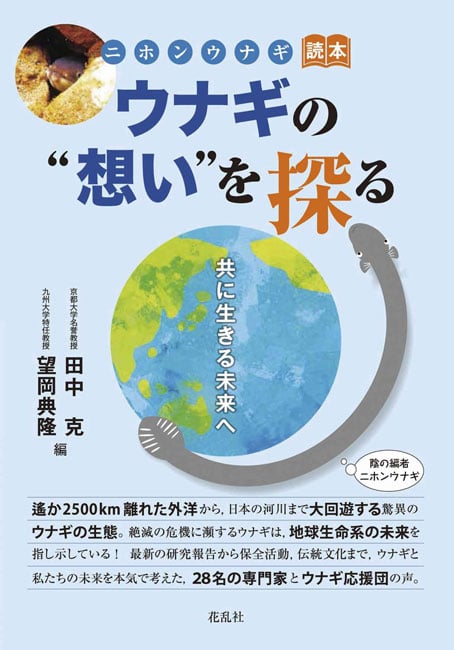2024/12/29 UP!
◎服部文祥(サバイバル登山家)
『サバイバル登山家 「服部文祥」の持続可能な登り方・生き方』(2024.12.29)
◎四倉武士(現役の高校の先生)
『「地理おた部」地理を楽しく、わかりやすく!』(2024.12.22)
◎松本明子(タレント)
『松本明子「心に栄養、私の元気は山登りから」』(2024.12.15)
◎嶋田哲郎(公益財団法人「宮城県 伊豆沼・内沼環境保全財団」の研究室長)
『冬の妖精ハクチョウたちを追跡調査する「スワン・プロジェクト」〜カメラ付きGPSロガーから送られてくる画像に注目!』(2024.12.8)
◎鈴木香里武(岸壁幼魚採集家)
『漁港は幼魚のパラダイス!〜岸壁幼魚採集家「鈴木香里武」』(2024.12.1)
2024/12/29 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、サバイバル登山家の「服部文祥(はっとり・ぶんしょう)」さんです。
服部さんは1969年、横浜生まれ。東京都立大学在学中にワンダーフォーゲル部に所属し、日本国内の山々を縦走。96年に世界第2位の、カラコルム山脈K2・標高8611メートルに登頂。97年から冬の北アルプス 黒部横断などに挑戦。99年からは食料を現地調達するサバイバル登山を始め、その後、狩猟にも取り組んでいらっしゃいます。
山好きのかたは、山岳雑誌『岳人』の連載で、服部さんのことを知っている、というかたもいらっしゃると思いますが、実はもともと『岳人』の編集者で、現在もフリーランスという立場で編集にも携わっていらっしゃいます。
そして作家としても数々の本を出されていて、いちばん新しい本が『今夜も焚き火をみつめながら 〜サバイバル登山家随想録』。これは山岳雑誌『岳人』に連載していた記事を中心に、えりすぐりのエッセイを加えて編纂した本となっています。
今回は14年ぶりのご出演ということで、改めてサバイバル登山とは、どんな山登りスタイルなのか、そんな初歩的なことから、数年前から始めたという自給自足的な古民家暮らしのお話などもうかがっていきます。
☆写真協力:服部文祥

「サバイバル登山」〜フリークライミング思想
※私、小尾は今回初めて「サバイバル登山」という山登りがあることを知りました。改めて、これはどんな登山スタイルなのか、教えていただけますか。
「自分の力で登ることにこだわった登山だと思っているんですけども、メインの思想というか中心の思想はフリークライミングにあります。フリークライミングは、自然のまんまの岩を自然のまんまの自分で登ろうっていう考え方だと、僕は理解しているんですけども、それをやってみると面白いんですね。
その前の段階のことをちょっと説明しておくと、人工登攀(じんこうとはん)っていうのがあって、岩登りがどんどん発展していく中で、岩に穴を開けて、そこにボルトを打って、それから縄梯子をぶら下げて登るっていうふうにどんどん発展していく、それが人工登攀なんですね。その中で、登るってことは一体どういうことなんだろう? って考えた人たちがいて、それがフリークライミングを生んだんです。
登るっていうことは、もともとある自然の岩の、登りたい人にとって、利用できる(ものが少ない)弱点を、自分たちの肉体を利用しながら、使うことでそれ(岩)を登っていく。
簡単に言えば、子供たちが岩とかを見た時に、これ登れる? ずるしないで登れる? みたいな・・・梯子をかけたりとか、上から垂れているロープとかをつかまないで、自分の体だけで登れるっていうようなのと同じだと思うんですね。そういうフェアな思想っていうか、スポーツマンシップみたいな思想を前面に押し出したというか、それに忠実にやろうと思って考えたのがフリークライミングだと思うんですよね。
実際、僕も自分でやってみて面白いし、これが登ることだなっていうのがすごくよくわかる。あと登れなかったら、今まで人間がやってきたように、その対象を加工しちゃうんじゃなくて、梯子をかけちゃうとか、穴を開けちゃうとかっていうんじゃなくて、一回おうちに戻ってというか、一回その岩から降りて自分を鍛えるんです。またそれにチャレンジするっていう、フェアネスの精神みたいなものもある。
岩を加工しないんで、岩は原始のまま、そこにずっとあるわけですよ。だから100回目にチャレンジした人も、最初にチャレンジした人と同じように、その岩と向き合うことができる。簡単に言うと持続可能なんですよね。

人間っていうか、我々は結構、自然環境を都合のいいようにいじってしまって、持続可能ではない世界をたくさん生んでしまったというか、(自然を)壊してしまったんですね。フリークライミングはそうではなくて、できるだけ自分たちの都合のいいようにいじらずにそのまんまの状態にして、だからこそ、ずっとこれから何年も何年も、最初に触った人と同じような喜びを、2回目でも100回目でも1000回目でも感じることができるっていう意味で持続可能なんですよ。
そういう意味でフリークライミングってすごく面白いというか、これから地球を対象に遊ぶ場合の、我々のすごく理想的なやり方だと思うんです。僕は日本の山を登って育ってきたんで、日本の山でフリークライミング的なことができてるのかって考えた時に、できてないな~と思って・・・。
今から日本にできちゃった道とかロープウェイとか、壊してもしょうがないんで、そういうものをできるだけ避けて、フリークライミングと同じように、過剰に便利な道具は使わないってことを課して、そういう条件で山に登ってみたらフリークライミング的にやっぱり面白いんですよ。
で、やったのがサバイバル登山で、名前は営業もあって、目を引くような、耳にちょっとなんなの? って、みんなが思うようなものを敢えてつけたっていう感じですね」
(編集部注 :初めてのサバイバル登山は、南アルプスの北に位置する「仙丈ヶ岳<せんじょうがたけ>」だったそうです。この時、持って行った道具はタープと薄い生地の寝袋など、食料はコメなどの穀類を少しと塩だけ。あとは現地調達にチャレンジしたそうですが、ご本人いわく、食べられる山菜やキノコがわからない、釣りが下手でイワナも釣れない。寒くて腹は減っていたけれど、面白くて清々しい気持ちだった。山を降りたあとに登山として美しいと思ったそうです。
その後、食料の現地調達に向けて、釣りの練習のほか、山菜などの知識を身に付けるために図鑑を見たり、友人に教えてもらったりと、スキルを磨いたとのことです)

肉も現地調達〜山の見方に変化
※食料は基本的には現地調達ということで、釣りに加え、その後、狩猟が加わりました。そのあたりの思いをお話しいただきました。
「食料って我々普通に生活していると、食料品店で買うのが当たり前ですけど、よくよくサバイバル登山をしてみると、本来の食料は自然環境から自分の手で獲ってくるものなんですよね。みんな、そうやってずっと何万年も生きてきて、最近は買うものになりましたけど・・・でもやってみると、そういうもんだなと思っているのに肉に関しては買ってんですよね・・・自分も買っていた。
サバイバル登山を通して、魚を釣って山菜を採ってキノコを採ってみたいなことをやっているけど、肉に関してはまだ買っているな~って・・・。肉もちゃんと自分で調達してみたいなと思って、一回登山はちょっと横に置いといて、狩猟だけをする2シーズンぐらいがあって、獲れるようになった時に、シカやイノシシを食料に、もしかしたら冬もサバイバル登山できるかもしれないって思って、思っちゃうとね、気がついちゃうとやらないといられないってわけじゃないですけど(笑)、気が付いちゃったんでやってみたのが、冬のシカを食料にしたサバイバル登山です」
●猟銃を持ってってことですよね?
「そうです。狩猟を始めた時は冬のサバイバル登山の意識っていうか、そういう発想は全くなくて、とにかく肉をちゃんと自分で調達して、その時、何を自分が感じるのかを知りたいなと思ってやっていたんですけど、獲れるようになっていく過程で、獲れるようになっていったんで、これが食料になるって気がついてしまった。めんどくさいぞ! と思ったんですけど(笑)。やってみると、やっぱりひとりでやると効率があんまりよくない。鉄砲は重いし、シカを獲ると荷物が一気に増えるし、そういう意味ではひとりでは効率がよくないですね」
●仕留めた獲物はその場で解体するんですか?
「そうですね。それしかないんで・・・」
●そうですよね〜。
「その場で解体して持ち運ぶとか、できるだけその場で食うわけです。でも20〜30キロの肉が手に入るわけで、それを全部食うことなんてできないですし、運ぶこともできないんで、悪いけど森に返す、みんなで食べてください。実際みんなで食べてくださいっていう状態になるんですけど、あっという間に鳥とか獣とかに食べられちゃう・・・」
●狩猟を始めて、山の見方は変わりましたか?
「変わりますね。狩猟もサバイバル登山もそうですけど、やっぱり普通の登山って結局、道を歩く。岩登りとかでも、ある程度ルートが決まっていて、そのラインをたどるみたいなところがあるんですけど、食料とか燃料とかを現地で、山の中で調達しようと思ったら、もちろん山をよく見なきゃいけないですね。
登山道を歩いて線上で山と接していたのが、獲物を探すとか獲るとかっていうことで、それが広がっていく。面とまではいかないんですけど、かなり幅を持って広がっていく。実際にそこに生えていたり、そこに棲んでいたりするものを見つけて獲らなきゃいけないんで、よく見るようになりますよね。幅広くよく見るようになる」
(編集部注:服部さんは大学時代の縦走に始まり、エベレストよりも難しい山と言われるK2の登頂のほか、岩登り、沢登り、山スキーなど、いろんなことに挑戦してきました。その理由は、なんでもできたほうがかっこいいし、登山家として、オールラウンダーでありたいという気持ちがあったからだそうです)
自分で考えて超えていく
※先鋭的な登山家のかたは、人がたどったことがないルートを踏破するとか、まだ誰もやってない登り方で頂上に立つとか、「登山史上、初めて」に挑むことがありますよね。なぜ「登山史上、初」にこだわるのでしょうか?
「面白いからですね! っていうのは、やっぱり誰もやってないから、そこは自分で工夫しなきゃいけないわけですよ。何が起こるかわからないですし、どういうふうになっているかも実際に行ってみないとわからないわけなんで・・・。
実際に行って、ぱっと見て、あっここが難しいとか、ここはどうやって登るんだろうみたいな、わかんないところを自分で考えて工夫して、超えていくっていうのは、ものすごくクリエイティヴなことなんですよ。だから未知っていうものはやっぱり、そういうことにチャレンジしたい人にとっては魅力のあることですけどね」
●ワクワクするんですね~。
「でも今はもうそういう未知の部分もなくなってきてしまったんで、そういう志はもう絶滅危惧種というか・・・。さっき言ったフリークライミングはそういう意味では、最初の人と2番目の人も3番目も100番目の人も、最初の人と同じような気持ちを楽しめるようなシステムにはなっているんですけどね。
情報をフリークライマーたちは(自分の中に)入れないんですよ。っていうのは、やっぱり登り方がわかっていたら、あんまり面白くないんで・・・。自分で岩に取りついて、登り方を考えながら登るのが面白いんで、敢えて人が登った登り方を調べたりしないし、登った人たちもそういうことを敢えて言わないんです。
それはその人たちの喜びを奪うことになっちゃうんで、これから登山もそういう方向にいってもいいんじゃないかなと思いますけどね。僕なんかは敢えてもう調べない。今『ヤマレコ』(*)とかでいくらでも調べられるじゃないですか。調べることもあるんですけど、敢えて調べないことによって、すごく面白いっていうか、初めてそこに行った人と同じような気持ちで登ることができる。自分もいろいろ悩んで工夫する余地があるっていう意味で、これから情報を入れないで、敢えて自分も初期衝動を楽しむのは、登山にもあってもいい考えなのかなと思いますけど・・・」 (*山のコミュニティサイト)
●でも登っている最中に怪我しちゃったとかもあると思うんです。山はやっぱり危険と隣り合わせっていう印象もあるんですが、リスク・マネジメントは常に意識されていますか?
「そうですね・・・いや、どうなんですかね? っていうか、マイナスのことを考え始めると、きりがないですよね。それは行かない理由にはならないんで・・・もともと登山者とか我々みたいなタイプの人間はおそらくですけど、僕はそうなんですけど、できないとか、やめる理由を探し出したら、いくらでもあるんで、それはもう考えないですよね。
それよりもどうすれば、自分がやりたいことをできるか、どうすれば、自分の登りたい山に登れるか、どうすれば、自分が憧れているルートを越えられるかっていう方向から、ってわけじゃないですけど、そこで何があるのかっていうことはもちろん予想するわけです。その予想をどうすれば、自分の能力で超えられるかっていう方向でしか考えないんで・・・。
ベクトルが常に上に向いているっていうか、それで突っ込んで怪我とかしたりしたらしょうがないんで、もちろんリスク・マネジメントは考えるんですけどでも、それがやめる理由にはならないっていう意味で、“危ないじゃん”って言われると、“うん、危ないよ”って、危ないから考えて、安全を考えて登ります! っていう感じですかね」
100年前の生活!?
※服部さんは横浜の郊外にあるご自宅のほかに、狩猟でよく行くエリアに古民家を手に入れ、2020年から二拠点生活をされています。横浜のご自宅でも自給自足に近い暮らしをされているとのことなんですが、それでは物足りなくて、古民家暮らしを始めたそうです。そのあたりの思いを語っていただきました。
「サバイバル登山って当たり前だけど、お金を使わないんですよね。食料は現地調達、水は流れているし、空気はもちろんタダだし、寝る場所だって別にキャンプ場じゃないんで勝手に寝るわけです。燃料はもちろんタダで、それをやっていると本来生きるのにお金はかかんないじゃんっていう・・・。で、そっちのほうが面白いし、まっとうというか、もともとはこういうことが生きるってことだよな・・・みたいな感じで思っていたので、それを自分の実生活でもやったら楽しいかなというふうに思って・・・。
横浜の家でもストーブは薪ストーブだけ、ニワトリを飼ってっていうことをやってみたんですけど、実際面白い面もある、っていうか面白いので、のちのち狩猟の基地が別に欲しいなと思っていて・・・。

それまでは電車とバスで猟場に行って、獲ったら電車とバスで帰ってきていたんですよ。荷物がすごく重くて、猟場に解体場みたいな拠点があったら、いろいろ楽だなと思っていたところ、山の廃村の中に古民家みたいなというか、完全な廃屋ですけど、まだギリギリ住めるだろうなって家がふたつ残っていて、たまたま知り合いができて、そのうちのひとつを譲ってもらえることになったんですね」
●ずっと誰も住んでなかった家を住めるような状態にするのは、なかなか大変だったんじゃないですか?
「まあ、掃除だけですね。あと水を引くこと。もともと田舎暮らしにちょっと憧れがあって、登山なんてやっているから、そういうのはあったんですけども、実際に廃屋みたいのを手に入れて、現場に寝泊まりしながら掃除をしていて、単なる田舎暮らしを求めていたんではないってことに気がついて・・・まさにその古民家を100年前のまんま使う生活が、自分の力で生きることに近いってことに古民家を見て気がつかされたっていう、こっちを求めていたんだ! って。
だから土間は土間として使う。囲炉裏は囲炉裏として使う。まあ竈(かまど)ですけど、竈は竈として使う。水は水船(*)から引いてくる。これは塩ビパイプ使ってやっているんで現代的なんですけども、あとは本当に昔のまんまにするほうが・・・。 (*飲み水をためておく大きな桶というか箱のようなもの)
100年前に建った家なんで、100年前の生活に適したようにできているんですよね。それが僕の求める自分の力の割合が多い生活なんで・・・。だから古民家と言っても現代風の別荘みたいな感じにするんではなくて、単に掃除して昔の状況、状態を再生すればいいので、掃除は大変でしたけど、特にリフォームとかそういうのはほとんどしてないんで、そんなに大変ではないと・・・」
●古民家暮らしもサバイバル登山の一環っていう感じですね?
「そうですね。登山の一環というか、僕のあり方というか、世界の向き合い方の延長線上に生まれてきたっていう感じですかね」
(編集部注:1年の半分くらいを古民家で過ごしている服部さん、年に数回、ご家族が泊まりに来るとのことですが、普段、生活に必要なこと、例えば薪割りや火を起こしての食事作りなどは全部ひとりでやるので、清々しいけれど、面倒臭いとおっしゃっていましたよ。畑もやっていて、それは面白いとのことでした)
サバイバル登山家の25年後!?
●サバイバル登山を始めて、今年で25年ぐらいになりますかね?
「そうですね。29歳の時に始めたんで、25年ぐらいですね」
●どうですか、サバイバル登山というスタイルの山登りは円熟してきましたか?
「う~ん、サバイバル登山って言っても、やっぱり行ったことないところに行きたいんですよ。もちろん何度も何度も同じところに行っているんですけど、行ったことないエリアがなくなっちゃったのが寂しいっていうのかな・・・」
●ここ数年は愛犬との山旅もあったりしましたが・・・?
「そうです! 犬は面白いっすね」
●山登りのやり方もちょっと変化してきているんですね。
「うん、変化しています。やっぱり、自分の肉体が歳をとってきて、動かなくはなってないですけど、若い時みたいにできることが増えていかないですよね。できることが増えていかないとリスクをかけられないっていうか、できることが増えていかないから新しいことができないんで、その新鮮さみたいなものはないんですよね。
だから自分の肉体にはもう新鮮さがない。そうなると、あんまりいいことかどうかわかんないですけど、獲物とかその世界に新鮮さを求めてしまって・・・獲物は同じことはほとんどないんで、すごくいつでも新鮮です。犬もやっぱり、ちょっと想像つかないんで面白い、いろんなことを教えてもらいました。新鮮なものを見せてもらいましたね」
●誰でも1年にひとつ歳を重ねますけれども、サバイバル登山家 「服部文祥」の、例えば25年後、80歳の時にはこうなっていたいとかありますか?
「いやぁ~死んでいるかもしれないけど、自然環境の近くで活動したり、特に獲物の相手をしていると遠い未来、遠い未来って言っても、2ヶ月ぐらい、まあ1週間でもそうですね。あんまり考えても意味ないから・・・。
徒歩旅行でもそうですね。20キロ以上先のことを考えても、あんまり意味がないんですよね。雨が降るかもしれないじゃないですか。何か別のことが起こるかもしれないんで、だからその場その場で生きていく。いわゆる、狩猟採集民族みたいに半径10キロとか、時間的には1日2日ぐらいのことしか考えなくなるっていうか、考えてもしょうがない、何が起こるかわからないんで・・・。
遠い未来のことを考えると怖くなるっていうか、気分が悪くなるっていうか・・・それまでに超えなきゃいけないものをイメージしちゃうっていうか・・・でも、元気な爺さんで、畑とか狩猟はもう続けてないかもしれないですけど、自分の力でできるだけ、自分の力で生きていたらいいなとは思いますけどね」
☆この他の服部文祥さんのトークもご覧ください。
INFORMATION
山岳雑誌『岳人』に連載していた人気コラムを中心にまとめた本。第一章の「ケモノを狩る」から第二章の「山に登る」、そして第五章の「現代に生きる」まで5つの章に選りすぐりのエッセイが載っています。導入部の「ちょっと長いはじめに」には、服部さんの生い立ちや登山の半生が綴られていて、これも興味深いですよ。物事の本質や生き方、社会のあり方などを問いかけるようなエッセイ集をぜひ読んでください。
モンベル・ブックスから絶賛発売中。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎モンベル・ブックス:https://webshop.montbell.jp/goods/disp.php?product_id=1991015
2024/12/29 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. STRONGER / KERRY CLARKSON
M2. UNSTOPPABLE / SIA
M3. HUNTER / DIDO
M4. START ME UP / THE ROLLING STONES
M5. STYLE OF LIFE / THE JACKSONS
M6. SURVIVOR / DESTINY’S CHILD
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2024/12/22 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、「高校地理お助け部」
略して「地理おた部」のメンバーとして活動されている現役の高校の先生「四倉武士(よつくら・たけし)」さんです。
「地理おた部」は「ケッペンちゃん」という、地理を題材にした漫画をオフィシャルブログで展開しているので、ご存知のかたもいらっしゃるかも知れません。
そんな「地理おた部」名義で先頃、新しい本『自然のふしぎを解明! 超入門「地理」ペディア』を出されたということで、 この番組でご紹介することになりました。
きょうは「地理おた部」を代表して四倉さんにどんなメンバーが集まっているのか、そして現役の先生として地理を教える醍醐味のほか、『超入門「地理」ペディア』から、日本の気候的な特徴や地球規模の変動についてうかがいます。
☆イラストレーション:ちまちり、協力:地理おた部/ページ画像・協力:ベレ出版

代表作は「ケッペンちゃん」!
※まずは、気になる「地理おた部」について。どんなことがきっかけで、「地理おた部」が始まったのか、そして具体的にどんな活動をしているのか、お話しいただきました。
「私は本当は専門が歴史関係なんですよ。ただ、高校の地理の先生、社会の先生って日本史、世界史、地理で採用されるので、採用されるまでに地理に触れ合うことが多くて、そのまま地理のほうに自分の進路を変えて、地理を専門にしました。
その際に自分の中で難しいなとか、わかりにくいなっていうところを教材化して、これが本当に合っているのか、ちょっと自信がなかったので、それをインターネットで公開して、いろんな先生に見てもらおうというのがきっかけで始まりました」
●「地理おた部」は、いわゆるサークルみたいな感じなんですか?
「そうですね。私ができないことをできる人たちに・・・私は絵が描けないので、絵を描ける人だとか、私よりも知識がある人にいろいろ協力してもらって作っています」
●メンバーは何名ぐらいいらっしゃるんですか?
「今は私を含めて4人ですね」
●どんなかたがいらっしゃるんでしょうか?
「イラストを担当しているのが、“ちまちり”さんっていうかたで、うちの代表作である『ケッペンちゃん』の漫画を描いています。今回の本の挿絵もすべて彼女が描いています。
あとは、私よりも圧倒的に知識の宝庫である“瀧浪(一誠)先生”っていうかたがいらっしゃいます。1冊目の『ゼロから学びなおす 知らないことだらけの日本地理』っていう本があるんですけど、それは瀧波先生に大変協力していただいて、書いていただきました。
あと、地理をネタにしたお笑い芸人トフィー、たぶん日本にひとりしかいないと思います。元々高校の先生だったんですけど、そこから松竹のお笑い芸人になりまして、今も頑張っているかた・・・多種多様な人が地理おた部のメンバーです」
●ほんと多種多様ですね! 職業もみなさん違いますけど、どうやって知り合ったんですか?
「X、旧Twitterですね。私が教材を発信し、そこから親交があって、いろいろやり取りしていくうちに、この人と一緒だとなんかもっと面白いことができるなっていうことで、私が声をかけて今の形になっています」

●「地理おた部」の活動テーマとか、モットーみたいなものはあるんですか?
「とにかく授業は楽しく、地理を楽しく、わかりにくいことをわかりやすくをモットーにしています。
代表作である『ケッペンちゃん』は、『はたらく細胞』がきっかけになっていて、あれを見て”あ〜なんかこういう漫画を作りたいな”と思って、読んでいるだけで勉強になる、楽しいし面白いし・・・そういう授業で使えるような楽しくてわかりやすい教材を作りたいをモットーに活動しています」
●「地理おた部」のブログでも展開されているケッペンちゃんは、漫画でわかりやすく高校地理を解説していますけれども、ネタとかってどなたが考えるんですか?
「これは全部、私が考えています」
(編集部注:四倉さんによると、地理が「地理総合」という科目になり、選択科目から必須になったため、生徒全員が学ぶことになったそうです。そのため、地理の先生が足りなくなり、専門外の先生も教えることになったとのこと。
このお話をお聞きして、現場の先生は大変だな〜と思ったんですけど、だからこそ、教材になるような地理ネタを発信している「地理おた部」の存在は大きいな〜と思いました)
地理は今を理解できる教科
●今回「地理おた部」として出された新しい本『自然のふしぎを解明! 超入門「地理」ペディア』を拝見しました! 今の地理って世界の国々とか地域の特徴だけじゃなくて、自然環境とか気候の変化、さらには世界の動きまでをも扱う、まさに今の地球を知るための科目なんだなって感じたんですけれども、幅が広すぎますよね?

「そうですね。逆に言えば、きのうやきょうあった事件をそのまま授業の頭で使えたりもするので、台風が来たよねとか・・・だからそれこそ今の世界情勢いろいろ起きているので、起きていることをそのまま授業で使えるところは、やっぱり地理の良さではありますね」
●なるほど、すべて地理につながっているっていうことですね。
「そうですね。なるべく授業の冒頭にニュースや、いろんな出来事を使って、今学んでいることは、まさに今を理解できる教科なんだよっていうことを生徒たちには言っていますね」
●この本では地形、気候、そして環境の3つのカテゴリーに分けて、全部で80のトピックが掲載されています。その中から番組でいくつかトピックをピックアップさせていただきました。
見出しを言いますので、ご説明をお願いしたいんですが・・・まずは「ハワイはいつか日本にやってくる?」という見出しがありました。年末年始をハワイで過ごされるかたもいらっしゃると思いますが、これはどういうことですか?

「要は日本にあるプレートとハワイのプレートが近くて、狭まる関係にあって、プレート同士が近づいているわけですよ。だからだんだんハワイのほうがやってきているっていう形にはなっているんですけど・・・何千万年後とかでもなく、何億年も先なので果てしないんですけども、いずれはなるよっていう話です」
●へ〜〜! いずれは南国のハワイがすぐ近くにあって、気軽に泳いだりとかできちゃうっていうことですか?
「そうですね。でも残念ながら、(日本)海溝があって、そこにハワイは沈むだろうという予測もあったりとか・・・タイムマシンがあったら見られるんですけども、なかなか見ることはできないですね(笑)」
●どれぐらいのペースで近づいてきているんですか?
「1年間に数センチなんですけど、地球の年齢を考えた時に、1年間に数センチだったとしても、何万年とあれば、何キロにもなるわけですよね。だからもう気の長い話ですね。歴史の授業とは桁違いな時間のスパンで動いているので・・・」
日本は世界一の温泉保有国
※続いて、新しい本『自然のふしぎを解明! 超入門「地理」ペディア』に載っているトピックから「温泉大国ニッポン」について。日本は世界一の温泉保有国なんですね。
「そうですね。まず温泉がある国が珍しいのかなっていうところで、火山がないとやっぱり(温泉は)発生しませんし、雨が降らないとどうしても湯の元になりませんし、さらには雨を蓄えるための地盤ですよね。固い岩盤とかがないと水が溜まりにくいので・・・だからやっぱり諸外国を見た時に温泉がある国は少ないですよね」
●ちなみに温泉の数がいちばん多いのは、どの都道府県なんですか?
「数で言うと北海道なんですよね。やっぱり面積が広いからなんですけども・・・。ただ湯の量で考えると、大分が奇跡的な地形になっているらしくて、水が溜まりやすいっていうのもあって・・・実際に大分に行くと学校とかにも、地熱発電の機械があったりするんですよ」

●え~~っ!
「学校に(行った時に)“片隅にある機械はなんですか?”って聞いてみたら“地熱発電です!”っていう・・・不思議ですよね。それぐらいやっぱり大分って恵まれているみたいですね」
●すごいですね~。数が多いのは北海道で、湯の量で言うと大分県なんですね。
「そうですね」
●では続いて、「日本は世界でいちばん雪が積もる国」っていう項目があって驚いたんですけど、ほんとなんですか?
「これは結構、意外に思われると思います」
●はい、思いました!
「雪が降るっていうことは、水蒸気が必要なんですよね。基本的に寒い地域って、そもそも水資源が凍っていたりとか意外と雪が降らなかったりするんですよね。あとは海からものすごく遠かったりとかして、だから(水資源が)凍っているっていう感じなんですよ」
●なるほど~。
「日本って雪が降るすごく奇跡的な地形をしているんですよね。周囲を暖流で囲まれていて、だから海が凍らない。その水蒸気が雲となって、陸地に着いた時に寒さで雪になるっていう形で、だから(本に載せた)データぐらい降っているんですよね。意外ですよね」
●日本より寒そうな国ってたくさんあるイメージがあったんですけど・・・。
「そうですね」
●でも雪が積もる国って考えると、日本が世界でいちばんになるんですね。
「そうですね。だから雪っていうのと、寒さっていうのがどこまでリンクしているかっていうのと、雪ってなんだろうって(考える)きっかけにはなるのかなとは思っています」
●カナダとか雪のイメージがありますけど・・・。
「カナダも海のほうは緯度が高いので、結構、海が凍っていたり、あとは内陸地が水資源から遠くて、そもそも雨が降らない、乾燥しちゃっているっていう地域も多かったりするので・・・」
(編集部注:本に載っている2016年のデータによると、世界の年間降雪量の第1位は青森市で792センチ、2位は札幌市、3位は富山市なんですが、4位のカナダのセントジョンズという街では、年間333センチの降雪なので、青森は倍以上の降雪量なんです。日本は雪がたくさん降る国なんですね)
赤道の「赤」の意味
※続いてのトピック、「赤道の『赤』の意味とは?」、これ、考えたことなかったです。この「赤」の意味って何なんでしょう?

「よく生徒たちも、“赤”って聞くと、なんかあったかいイメージがあったりすると言ってますけど、そもそも古代中国の天文学で使われていたんですよね。太陽が真上を通る地球上の線のことを“赤道”って言っていただけで、だから実は英語にすると“equator line”とか”当分するライン“、だから”red line”って言わないんですよね」
●へぇ~~!
「だから英語にすると意味がわかるっていうか、だからちょうど真ん中だよ! 当分する線だよっていう・・・」
●赤道っていう意味の国家もあるんですよね?
「そうですね。エクアドルがまさにそれで、赤道が通っている・・・だから決して赤っていう意味ではないんですね」
●おしまいは「エルニーニョの意味は”神の子”」というトピックがありました。エルニーニ現象という言葉をよくニュースでも聞きますけれども、改めて用語の由来も含めてどんな現象なのか教えていただけますか?
「エルニーニョっていうのは“神の子イエス・キリスト”っていう意味で、エルニーニョっていうのは、スペイン語で“男の子”を意味するんですよね。
ちょうどクリスマスの時期になると、ペルー沖の海面の温度が上昇して、いつもとは違う魚が大量に獲れて、これは神様の恵みだっていうことで、“エルニーニョ”っていう名前が付いているわけです」

●海面の温度って、なぜ上がるんですか?
「これはちょっと難しいんですけど、南アメリカの近くにはペルー海流っていう南極から来ている寒流、冷た~い水が流れているんですよ。これが貿易風が吹くと、どんどん太平洋のほうに流れていって、(海水を)冷たくしてくれるんですよ。
ところが、この貿易風が弱くなるとどうなるかっていう話なんですよ。弱くなると太平洋に注ぐ量が減っちゃうわけですよね。そのままペルー海流が北上してしまうので、結果として冷たい、ペルー海流の水が太平洋に入らない、温度が上がっちゃう、結果として今までとは違う魚が獲れるっていうことになるわけですね」
●で、海面温度が上がるってことなんですね。
「そうですね。冷たい水が入ってこないので上がっちゃうんですね」
(編集部注:ちなみに、ペルー沖の海面温度が下がることを「ラニーニャ現象」と呼びますが、この「ラニーニャ」は女の子という意味だそうですよ)
今見ている光景に名前が付く!?
※改めて思ったんですけど、地理を学ぶと、普段見ている景色が違って見えそうですね?
「そうですね。授業で習ったことが(学校の)帰りの道で見えるようになってほしいなって思っています。自然堤防とか微高地になっているとかを聞いた時に、家路で、”あれ? 自然堤防じゃない?”とか・・・。
浜堤(ひんてい)っていうのがあるんですけど、海の近くにちょっと高くなっているところがあるんです。海岸沿いにたまに高くなっているところ・・・それを浜堤って言うんですけど・・・。“あっ! これが浜堤か!”みたいな感じで、地理を学ぶことによって、今見ている光景に名前が付いて見えるようになるのは、地理の楽しみでもあるかなとは思っています」
●現役の高校の地理を教える先生として、どんなことを大切にされていますか?
「いちばんは、学ぶってものすごく楽しいことなんだっていうところですね。地理って意外と知らなかったことをものすごく学べる教科ですので、学んだことをそのまま現実世界に活かしたりとか、ニュースが少しでもわかるようになったりだとか・・・。
遠足とか修学旅行に行った時に、“あっ! 先生、これ、あれでしょ?”って生徒が言えた瞬間は、教えていてよかったと思いますね。
ほかにも卒業していった子たちがgoogleアースを使って家を探してみたりだとか、仕事で役立てたりだとか、何か自分たちのスキルアップになる教科だなって思っているので、楽しくそして自分を高める教科だと思って、いつも教えています」

●では最後に「地理おた部」としての今後の目標ですとか、新たに取り組みたいことがあれば教えてください。
「はい、やりたいことはいっぱいあって、今の目先はやっぱりケッペンちゃんをどうにかこうにかしてアニメにできないかな~だとか、V-tuber化してもっとわかりやすく、もしくはAIを使って、ケッペンちゃんが地理を教えるコンテンツを作るだとか・・・。
今、地理が必須化されて、先生たちのほうが困っているんですよ。専門じゃない先生たちが教えなきゃいけない。専門じゃない先生が無理やり教えたことを聞いた生徒たちはもっと可哀そうなんですよね。
なので、そういう人たちみんな、先生も生徒も助けられるようなコンテンツ、この動画を見たら、とにかくわかる!とか、わかんなかったらこの漫画を読む!とか、“地理って楽しいよね!”“面白いよね! わかりやすい!”っていうような教材をこれからもどんどん作っていこうと思っています」
INFORMATION
「地理おた部」の新しい本をぜひチェックしてください。「地形」「気候」「環境」の3つのカテゴリーにわけて、全部で80のトピックをそれぞれ見開き2ページで解説。気になる見出しから読めますし、イラストや写真がたくさん載っているので、とてもわかりやすいですよ。地理や自然の基本が学べる入門書、おすすめです。ベレ出版から絶賛発売中。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎ベレ出版:https://www.beret.co.jp/book/47704
「地理おた部」のオフィシャルブログもぜひ見てください。4コマ漫画「ケッペンちゃん」もチェックしてくださいね。
2024/12/22 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. I WISH EVERYDAY COULD BE LIKE CHRISTMAS / BON JOVI
M2. YOU’RE MY BEST FRIEND / QUEEN
M3. MAPS / MAROON 5
M4. LET IT SNOW / BOYZ Ⅱ MEN
M5. Fun Fun Christmas / BENI
M6. RED / TAYLOR SWIFT
M7. CHRISTMAS TIME / BRYAN ADAMS
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2024/12/15 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、タレントの「松本明子」さんです。
松本さんは、香川県高松市出身。1982年にテレビ番組「スター誕生!」チャンピオン大会に合格し、それを機に歌手デビュー。その後はバラエティ番組などで人気者となり、バラドルの元祖としても知られていますよね。
そんな松本さんの趣味が山登り。現在アウトドア雑誌に連載を持つ、そんな一面も注目されています。
松本さんが山登りを始めたのは、ある舞台に出演されたときに膝を痛めてしまい、それから運動をしなくなり、どうしたものかと悩んでいたそうです。そんなとき、ママ友や同級生から、運動しないのは健康にもよくないので節約家の松本さんにぴったりの、お金をかけない遊びとして、ハイキングや山登りを勧められたことがきっかけだったそうです。松本さんのYouTubeチャンネルを拝見すると、冬山に行くほど、のめり込んでいらっしゃいます。
きょうはそんな松本さんに趣味の山登り、それがきっかけで始めた軽自動車のキャンピングカー・レンタカー事業のほか、芸能界でも節約家として知られる松本さんに台所の大掃除に大活躍する「あるもの」の活用法についてもうかがいます。
☆写真協力:ワタナベエンターテインメント、オフィスアムズ

心に決めた瞬間!?
※初めての山登りは、どこに行かれたんですか?
「初めて登ったのは2019年の11月ぐらいだったと思います。いちばん最初は神奈川県にある大山(おおやま)っていう山を選びました。電車に乗って登山口までバスに乗り継いで行って登ったんですね。ケーブルカーはあるんですが、早朝から登ったので、まだケーブルカーも動いていない時間、5時半とか6時ぐらいから登ったと思います」
●標高1200メートルを超える山ですよね?
「結構高かったです。お仕事で新幹線に乗るときに、いつも車窓から大山が見えていて、大きくてすごく素晴らしい山だな〜と思って、いつか登れたらいいな〜なんて思っていたんです。いつも新幹線で見ていたので、大山を選んで登ったんですけど、結構石段もハードで・・・で、中腹に神社があるんですね。その神社の脇の道からまた鬼の石段がずーっと続いていて、そこから山道に入っていくんですね」
●膝は大丈夫だったんですか?
「膝をかばいながら、恐る恐る登ったんですけど、結構ハードでしたね。その時に偶然、知っていらっしゃるかたも多いと思うんですけど、百名山を走って登っているランナーのかたがいて・・・田中陽希さんって言ったかな・・・? そのかたがカメラマンのかたとふたりだけなんですけど、颯爽と走って登って動画を撮っていたんです。それをYouTubeとかにあげていらっしゃるかたで、何回も日本中の百名山を制覇しているかたなんですよ。
そのかたがカモシカのように、私の横を颯爽と駆け上がっていくっていう、そのすれ違いのシーンもあったんです。私はもう必死で登ったんですが、やっとの思いで山頂に出た時は、達成感とその絶景を見た感動とで、山登りっていいな、これを本当に趣味にして自分のペースでいいから、少しずつ登れたらいいなっていうのを心に決めた瞬間でしたね」
(編集部注:松本さんは仕事柄、先の予定が立てられないので、山に行くのはいつも急だそうです。翌日が休みだとわかると、天気予報とにらめっこしつつ、山のガイドブックを見ながら、どこの山に行こうか、体力や体調と相談しながら、初心者や女性でも登りやすい、おもに東京近郊、そして、ちょっと足を伸ばして甲府や山梨方面の低山を選ぶことが多いそうです。頂上から富士山が見えたら最高ですよね、とおっしゃっていました)

五感が磨かれた運命の山
※その後、登った山の中で、強く印象に残っている運命的な山があったそうですよ。
「これね、唐松岳(からまつだけ)という山なんですけれども、標高約2700メートル、もう自分の中では本格的な登山。早朝5時台から登ったんですけど、最初、小雨が降っていて、うわ〜これ、先が思いやられるな、せっかく来たのに雨なのかと思って、がっかりきていたんです。
まずはリフトに乗るんですね。ふたり掛けのスキー場にあるようなリフト、それにふたつ乗るんです。一回乗って、もう一回ふたり乗りのリフトに乗り換えていくんです。でもずーっとリフトに乗っている間、小雨なんですよ。寒くて、うわ〜これ、ちょっと天気選び、失敗しちゃったなと思って後悔していたんですけれども、標高2700メートルですから、どんどん登っていくうちに雲を突き抜けちゃうんですよ。
そうすると、右のほうの眼下には八方池っていう、とても素晴らしい池があって、白馬岳が鏡のように映るんですよ。そういうのを見下ろしながら、ずーっと登っていって、もう雲の上まで行きます! そうすると、標高が高くなると樹木が生えてこないんですよね、高すぎて・・・。草木があったのがだんだん見えなくなってきて、笹になっていくんですよ、植物が・・・。その笹を通り越すともう岩なんです。植物は生えない、高すぎて・・・。
で、カンカン照りで、暑くて暑くて、9月くらいに登ったんですけれども、真夏で、サンサンと太陽を浴びているのに雪渓が見えるんです。上のほうの山にはまだまだ雪が残っているんですよね。なんか不思議な光景でしたけれども・・・。
どんどん登って、山頂にやっとの思いで着いた時は、迫り来る周りのアルプスの景色、壮大な景色で濃い緑色の山がこちらに迫ってくるような感じがして、それはそれは感動的、達成感もあるし絶景の感動もあるし・・・。山に登って壮大な景色を見ていると、なんかきのうまで気にしていたこと、”私の悩みごとなんかちっぽけなんだな、ホコリみたいなもんだ、私の悩みなんて”っていうふうな、大らかな気持ちになれるというか・・・。
あと、時間に追われて暮らしている都会の生活の中で、忘れかけていた五感っていうんですかね、土に触れた触感とか、山の匂いとか、山の音とか、小鳥たちのさえずりとか、雲の流れを見ていて、視界がすごく透き通って晴れやかに見えたりとか、五感が磨かれるというか、そういうのも感じましたね。すごくよかったです〜」
「もったいない」から始まったレンタカー事業!?

※お話にあった、北アルプスの唐松岳は東京から直ではなく、前乗りして泊まってから向かったそうです。実は、この時の経験がレンタカー事業につながったそうですよ。
「やはり前の日に松本市に入ってビジネスホテルをとって、宿泊代もかかるし、松本市までの列車代もかかるんですよね。で、結局、登山口まで行くのに、バスもないので、前の日から駅前でレンタカーを借りて、結構お金がかさばっちゃって・・・」
●確かにそうですよね〜。
「お金のかからないレジャーということで選んだのに、長野県の標高が高い山に登ろうとすると、結構お小遣いがかかっちゃうなと思って・・・これはやっぱり私の信条ではもったいない! なんとか交通費と宿泊費を一緒くたにできるような、なんか面白いことはないかな〜と思ってずーっと考えていたんですね。
で、よし、これは車中泊ができる、女性でも運転しやすい、初心者でも私でも運転できる、小回りのきく、大きいキャンピングカーじゃなくって、小ぶりのかわいい軽自動車で車中泊ができるような車があったら、一石二鳥でいいな〜と思ってずーっと探していたんです。
そしたら出会いがありまして、よし、これは自分で乗ろう、いやいや自分で乗るだけではもったいないな、これは山ガールの女の子たちにも乗ってもらえたら、喜ばれるんじゃないかと思って、レンタカーを始めよう! っていう考えがどんどん転換されちゃって、それでひらめいてしまって、すぐ事務所の社長に直談判に行って、こういうことで私の夢なんです、事業を始めさせていただけないでしょうか、ということでお願いをしました。
で、ひとりキャンパーで有名な芸人のヒロシさんにも電話をして、”こういうふうに考えているんだけど、どう思う?”って聞いて、”いいじゃないですか〜!”って言われたんですね。で、やっぱり日本の山となると、山梨の甲府の駅前か、長野の松本の駅前でレンタカー店を出したほうがいいのかな〜って思って、考えを言ったんですね。そしたら、”ぜひとも、経費はかかるかもしれないけれども、絶対に都内でやってください”というふうにヒロシさんから背中を押されて・・・。
(自動車の)免許は持っているんだけれども、山登りに行きたいんだけれども、車を持てない、駐車場代を払うのがもったいないっていう大学生とか、若いカップル、若い夫婦のためにも、そういうレジャーを気軽に楽しんでいただけるように都内でやってください! って背中を押されて、よし、じゃあ近所でやろうっていう考えになっちゃったんですよね〜」
(編集部注:そんな経緯で始めた軽キャンピングカーのレンタカー事業、レンタカー店「オフィスアムズ」のオープンは2021年3月。開業するまでは、運輸局などの許認可を取得したり、レンタカー事業を行なっている会社に、フランチャイズ化のお願いに行ったりと、準備におよそ半年かかったそうです。

「オフィスアムズ」が保有している軽キャンピングカーは、いずれも専門の会社がカスタマイズした、オシャレで可愛い軽キャンばかり。アメリカンスクールバスをイメージした、イエローやミントグリーンにペイントされた軽キャンのほか、荷台に幌(ほろ)タイプのテントがある軽トラなど、どれも魅力的です。ぜひオフィシャルサイトでチェックしてみてください。
☆オフィスアムズ:https://officeams.com
車種によっては女性のために、女優ミラーライト付きのドレッサーやミニテーブルを装備しているそうですよ。また、レンタル・グッズも充実していて、車中泊用のセットのほか、テントや寝袋、ランタン、焚き火セット、さらには照明や充電用のバッテリーなども完備しています。
運営は松本さんと、もうひとり、長年専属ドライヴァーを務めている方と一緒にやっていて、松本さんも芸能界のお仕事がないときはお店にいて、車の掃除・点検、電話の応対などを行なっているそうです)

※開業して3年半が経ち、お客様の傾向も変わってきているそうですよ。
「今年はお陰様で、インバウンド効果で外国人のお客様が結構多く利用されています。英語のホームページもありますので、それを見て海外からネット予約をしてくださるんですよ。松本明子なんて全く知らないかたが、外国人のかたがいらしてくれています。
日本人のかたと外国人のお客さんと全然違うのは、日本人のかたって働き者なんですよ。やっぱり仕事が第一優先で、仕事の合間にレジャーを楽しむっていうことで、1泊とか2泊とかされるかたが主流なんですけれども、外国人のお客様はドカーンと2週間バカンスとか、長く日本でレジャーを楽しむんだっていうことで、1ヶ月間、車を借りま~す! みたいなお客様がいます。“布団を貸してください!”って、車中泊しながら日本全国、京都に行ったり富士山を見たり、九州に行ったりとか北海道に行ったりとかっていうお客様が増えて、ありがたいな~と思っていますね」
もったいない精神〜油汚れにティーパック!?
●ではここからは、松本さんが去年出された本『この道40年 あるもので工夫する 松本流ケチ道生活』から、年末の大掃除に向けてヒントになるお話をうかがっていきたいと思います。
「ありがとうございます」

●松本さんは芸能界で倹約家としても知られていますけれども・・・。
「そうなんです(笑)。私が香川県の出身で、雨が降らない県なんですよ。県民性というか教育というか、とにかく小さい頃から家族とか学校の先生に“節水して! お水を使うのはもったいないから!”っていうことで、水とかペーパーとかは絶対捨てちゃいけない、大切に使うんだっていうのをずーっと親から言われ続けて、学校の先生からも言われ続けて・・・香川県のみなさん、みんな節約家というか倹約家というか、そういうもったいない精神の塊ですね」
●小さい頃から根本にもったいない精神があったんですね~。
「はい! そうなんです」
●この本を読ませていただいて、節約のために仕方なくっていうよりは楽しみながら、いろいろ工夫されているんだなっていうのがすごく伝わってきました。
「ありがとうございます、楽しんでやっています!」
●アイデアを出すのも、すごく楽しまれているんだなと感じたんですけれども、実際にお掃除のヒントになるお話をうかがっていきたいと思います。
まずは出がらしのティーパックが油汚れの救世主、なんですね?
「そうなんですよ!」
●使い終わったティーパックを取っておくんですね?
「そうなんです。使い終わったティーパックを捨てずに取っておくんです。いつも流し台のところにもたくさんストックがあるんですね。私は割とコーヒー派なんですけど、主人とか息子は紅茶党なんですね。なので、毎朝ミルクティーを飲むんですけれども、その出がらしのティーパックを捨てずに取っておく。そうすると炒め物をしたフライパンの油汚れとか食器とか、いきなり洗剤をつけたスポンジで洗うと、スポンジがヌルヌル、ヌメヌメになっちゃって長く使えないんですよね。
もうそれが嫌で嫌で、許せなくて、なんかいいアイデアはないかと思って、新品のティッシュペーパーで油汚れを取るためにぬぐうのも、もったいないと言えばもったいなくて、なんとか捨てるものでできないかなと思って考えていたら、そうだ! 出がらしのティーパック、これでひと拭きしたらどうだろう! と思ってやったのがもう20年前ぐらいなんですけど、消えるんですよ、油が!」
●へ~~っ!
「もうね、9割がた取れます、フライパンの油汚れや食器の油汚れが・・・。なので、スポンジに洗剤をつけて洗う前に(ティーパックで)一拭いしていただけると・・・。これ、紅茶の葉の成分も油汚れを分解するっていう科学的な、理にかなった展開がちゃんと証明されていますので・・・」
●いや~捨てていました(苦笑)
「ぜひとも参考に! もう騙されたと思ってやってみてください」
●すぐに試したいと思います!
セーターをたわしに!? 日焼け止めクリームが大活躍!?
※松本さんの本には、ほかにも「着古したセーターをほどいてアクリルたわしに」というアイデアが載っていました。これは何か、コツのようなものはありますか?
「これはね、高級な毛100パーセントの(お値段が)高いセーターじゃないほうがいいです。できればアクリルが何パーセントか入っている毛糸、もう着なくなった手編みのセーターなんかを全部ほどいて、カギ編みでいいです。もう適当な編み方でいいです。
それで油汚れを拭い取ると、アクリルっていう性質が油を吸収するんですって、この繊維の中に・・・。これでもうほとんど洗剤はいらないです。洗剤もいらないし、地球の環境にも優しいし、これもぜひとも、おすすめですね。アクリルたわしも適当なカギ編みをして(台所に置いて)ありますね」
●なんかカラフルですごく可愛いたわしですよね~。
「そうです、そうです! 見た目にも華やかで」
●あと、余った日焼け止めクリームは掃除アイテムにということで・・・。
「そうなんですよ!」
●日焼け止めクリームって余りますよね。
「ひと夏で使い切らないんですよね。お子さんがテーブルとか床とかにちょっと書いてしまったマジックの汚れ、それを使いきれなかった日焼け止めクリームを塗ってティッシュで拭くと、綺麗に」
●取れるんだ・・・。
「油性のマジックが取れちゃうんですよね~! あとね、ハサミの・・・ネバネバ、粘着がちょっと引っ付いちゃって、ノリのところをハサミでカットしたところに、ネバネバが付いちゃった刃の部分、あれを使い切らなかった日焼け止めクリームを塗ってティッシュで拭くと、あら不思議! 綺麗に取れます!」
●へえ~! すごいです、ほんとに!
「これ、いいですよね~。だから捨てずに、何かに利用してみていただきたいと思います」
(編集部注:ほかにも、歯ブラシだけじゃなく、歯間ブラシを隙間の掃除に再利用しているそうです。ぜひご参考に)
元気の源はレジャーから
●お金を節約する山登りから生まれた軽自動車のキャンピングカー・レンタル事業、実際、松本さんも軽キャンピングカーを使って、山登りに出かけていらっしゃるんですよね?
「はい! そうです」
●やはりキャンピングカー・ライフは楽しいですか?
「そうですね。自由ですし、キャンプの達人ではない私でも、自然に触れるというだけで、自分の心の栄養になりますし、明日また元気になれる、心に栄養をもらえるのがやっぱりアウトドアであり、山登りかなというふうに思いますね」
●どんなところに喜び感じますか?
「ほんとに適当にお弁当を持っていくんですよね、お昼ご飯とかも・・・やっぱり景色を見ながらお弁当を食べると、本当に笑顔になれるというか、体も栄養! 心も栄養! 食べて美味しい! お金もかからない! っていうことで楽しくなりますね(笑)。毎日が元気になります。私の元気の源はそういうレジャーから来ているのかもしれないですね」
●松本さんのレンタカー店「オフィスアムズ」で軽キャンを借りたいなと思ったら、どのようにしたらよろしいでしょう?
「ぜひとも、ホームページでネット予約ができます。すぐ予約もできますので、なんでも相談事があれば、言っていただきたいと思います。それに全面協力しますので・・・あと、記念写真をいつもお客様のスマホで撮っています」
●松本さんと!?
「大学生とか10代、20代は、“店員さんとこんなサービスがあるんですか(笑)”ってよく言われるんですけど、40代、50代のお客様には喜んでいただけます!」
●そうですよ~、松本さんにお会いできるなんて~。
「いえいえ~、元気にお店でスタンバっていますので、ぜひともおしゃべりをしに来てください!」
●ありがとうございます!
INFORMATION
松本さんが運営する軽キャンピングカーのレンタカー店「オフィスアムズ」の軽キャンをぜひご利用ください。オシャレで可愛い軽キャンがそろっていますよ。また、装備やレンタル・グッズも充実しています。お話にもありましたが、松本さんがお店にいるときは、記念写真を撮るサービスも行なっているとのこと。
レンタカーの利用料金など、詳しくは「オフィスアムズ」のオフィシャルサイトをご覧ください。
◎オフィスアムズ:https://officeams.com
松本さんが去年出された本には大掃除のヒントになるアイデアや、日頃の節約につながる特に主婦には役立つヒントが満載です。ぜひ読んでください。アスコムから発売中。詳しくは出版社のサイトを見てくださいね。
◎アスコム:https://www.ascom-inc.jp/books/detail/978-4-7762-1290-4.html
2024/12/15 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. JOY TO THE WORLD / MARIAH CAREY
M2. ROAR / KATY PERRY
M3. AIN’T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH / JOCELYN BROWN
M4. DREAMS / VAN HALEN
M5. CLEAN UP WOMAN / BETTY WRIGHT
M6. I LOVE YOUR SMILE / SHANICE
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2024/12/8 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、公益財団法人
「宮城県 伊豆沼(いずぬま)・内沼(うちぬま)環境保全財団」の研究室長
「嶋田哲郎(しまだ・てつお)」さんです。
宮城県北部にある「伊豆沼・内沼」は、毎年たくさんのガンやカモ、ハクチョウ類が飛来する国内有数の越冬地で、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」通称「ラムサール条約」に登録されています。
千葉県市川市出身の嶋田さんは働きながら、「マガンの越冬生態と保全」というテーマで論文を書き、博士号を取得。縁あって、研究者を探していた財団に勤務することになったそうです。

「宮城県 伊豆沼・内沼 環境保全財団」は1988年に設立された公益財団法人で、沼の自然環境の保全や研究、そして環境教育などの啓発活動を実施。普段はガンやカモなど、水鳥の個体数のモニタリングや外来魚の駆除なども行なっていらっしゃいます。
現在、嶋田さんは伊豆沼・内沼にやってくるハクチョウを調査する「スワン・プロジェクト」に力を入れています。いったいどんなプロジェクトなのか、じっくりお話をうかがいます。
☆写真協力:宮城県 伊豆沼・内沼 環境保全財団

渡り鳥たちが安心して暮らせる越冬地
※まずは、宮城県北部にある伊豆沼・内沼について。沼自体はどれくらいの大きさなんですか?
「面積は559ヘクタール、東京ドームでいうと110個分ございます」
●おっきいですね~。
「はい、周辺は農地に囲まれています。(沼は)いちばん深いところで1.6メートルというとても浅いって特徴があって、広くて浅い、そういう地形をしています。浅いので、夏になりますと沼一面にハスが咲くんですね。ハス祭りなども開催されています」

●そちらの財団のホームページを見ると、この伊豆沼・内沼は、秋から冬に極東ロシアからやってくるガンやカモ、そしてハクチョウなどの貴重な越冬地と書かれていました。ほかにも越冬する場所はたくさんありそうな気がするんですが、どうしてこの伊豆沼・内沼にやってくるんでしょうか?
「人も食住というのが大事なように、実は鳥も同じなんですね。伊豆沼には10万羽ほどのマガンですとか非常に多くの鳥が来ます。マガンは沼周辺の農地で、稲刈り後の田んぼに残っている落ちもみを食べています。また、ねぐらとなるこの伊豆沼は凍りにくい特徴があって、天敵となる哺乳類が入って来にくいんですね。そのため安全です。ですので、食もあり安心なねぐらがある、食住が安定しているということが理由で、たくさんの鳥が集まってきます」
●渡り鳥たちは毎年いつ頃やってきて、いつ頃までいるんですか?
「9月の下旬頃に初雁(はつかり)と言って、最初のマガンの初飛来があって、それからどんどん数が増えていきます。だいたい2月上旬には北帰行(ほっきこう)と言って北へ帰る、そういった動きが始まります」
●毎年どれぐらいの数の渡り鳥たちがやってくるんですか?
「年によっても少し異なるんですけども、伊豆沼・内沼ではマガンなどのガン類が10万羽ほど、ハクチョウ類で3000羽、カモ類で4000羽ほどが越冬しています」

●すごい数ですね。そんなにたくさんだと、渡り鳥たちの食べるものとかなくなっちゃうんじゃないかなって心配になっちゃうんですが・・・。
「沼周辺には非常に広大な農地があって、そこにはたくさんの落ちもみがありますし、実はオオハクチョウはレンコンを食べています。先ほどのハス祭りの後に、ハスが枯れて地中にレンコンができます。それを食べていて、そういったいろんな食物が豊富なので、これだけ多くの鳥を支えていると思います。
鳥というのは、生態系の食物網の頂点にいる生き物です。つまりこれだけ多くの水鳥がいるということは、それを支えている植物や魚類を含めた生態系が豊かなことを示しています。最近では特にオオクチバスの駆除による保全の成果が見られてきまして、沼の魚が回復してきています。
また、沈水植物といった水の中に生える植物も増えてきていますので、生態系が回復してきています。こういったことも鳥たちの生活に大きく貢献していると思います」
カメラ付きGPSロガー「スワンアイズ」
※ここからは現在、嶋田さんが進めていらっしゃる「スワン・プロジェクト」についてうかがっていきます。まずはどんなプロジェクトなのか、教えてください。
「このプロジェクトは2023年12月に始まりました。我々の財団ですとか、中国のドルイドテクノロジーといった会社を中心に始まったプロジェクトで、カメラ付きのGPSロガー、通称『スワンアイズ』と呼んでいますけども、それをオオハクチョウ10羽、コハクチョウ10羽に装着して追跡しています。
これまでなかった最大のオリジナリティが、カメラによってハクチョウ目線の画像を見られるってことです。そして位置情報とか画像を一般公開しています。市民のかたがそれを見てハクチョウを見守ろうという、そういった国際共同プロジェクトです」
●野鳥に認識番号付きの足環を付けたりとか、発信器を付けたりするのは聞いたことがあったんですけど、カメラ付きっていうのは画期的ですよね。
「カメラ付きGPSロガーっていうのは、たぶん世界初だと思います」

●重くないんですか?
「これはちゃんと計算しておりまして、GPSを中心にふたつの小型カメラがついていて、カメラの全体の重さは130グラムです。この重さはオオハクチョウの体重の2%以下ということになっていて、とても軽量なんですね。鳥の行動に影響しない重さで作られています」
●負担はそんなにない感じなんですね。
「はい、ほぼないです」
●(スワンアイズは)自然に外れるものなんですか?
「そうですね。やはり野外でずっと使っているものですので、劣化してだいたい2〜3年で脱落することになっています」
●ハクチョウにカメラ付きのGPSロガー「スワンアイズ」を付けるためには、捕まえる必要がありますよね? どうやって捕まえたんですか?
「なかなかこれが簡単ではないことなんです。オオハクチョウは水と一緒に食物を食べる、漉(こ)しとって食べるので、水があるところが食べやすいんですね。ですので、農家さんのご協力をいただきまして、田んぼをお借りして、そこに水を張ります。そして1ヶ月前から餌付けをするんです。餌付けをしてハクチョウを集めておいて、集まってきたところを網で被せて捕まえるってことをします」
●へぇ~、でも大きい鳥ですから、なかなか大変ですよね?
「大変です。本当に大変です。翼を広げると2.4メートルありますし、体重も10キロ、結構重いんですよ。本当に捕獲作業は泥だけになって、オオハクチョウと格闘しなければなりません」
●格闘の末にカメラを付ける作業になりますけれども、ハクチョウのどこに付けたんですか?
「首です。首についていますので、本当にハクチョウの、若干目線が下がりますけど、ハクチョウ目線に近い形で(撮られた)画像を見ることができます」

●なんか蝶ネクタイみたいな感じですよね。
「はい、そうです」
●捕獲してスワンアイズを付けるということですけれども、許可は得ているんですよね?
「もちろんです。これは環境省にちゃんと申請をして許可証をもらった上でやっています。また農地は私有地なので、当然その農地のかたに許可をもらってやっていて、全て手続きを済ませた上で実施しています」
ハクチョウ目線の画像に感動!
※「スワン・プロジェクト」のサイトを見ると、ハクチョウそれぞれに名前を付けていますよね。それはなにか意図があるんですか?
「このプロジェクトは、樋口広芳(ひぐち・ひろよし)*先生に顧問になっていただいているんですね。樋口先生はこのスワン・プロジェクトの10年前に、実は“ハチクマ”という鷹の位置情報を一般公開する『ハチクマ・プロジェクト』をやっておられるんです。先生からのご助言で、“愛称をつけたほうが市民に親しみが湧くんです”というアイデアをいただきまして、それでそうさせていただいたんですが、まさにその通りでした!」
(*鳥類学者。東京大学名誉教授。当番組にも出演)
●確かに愛着が湧きますよね! スワンアイズからは、定期的にデータが送られてくるっていう仕組みなんですか?
「そうです。携帯電話通信を用いているんですけども、それで位置情報が1日6回、画像が1日4回取得されて、定期的に送られてきます。少しタイムラグがあるんですけども、ほぼリアルタイムで位置情報とか画像を見ることができます」

●送られてきたデータで、これまでにどんなことがわかってきたんでしょうか?
「やはり位置情報と画像がセットになっているので、ハクチョウがいつどこで何をしているかっていうのが非常によく理解できます。レンコンを食べているとか、田んぼにいるとかっていうこともわかります。それから、飛んでいる画像がありますので、飛行場所の特定できるんですね。どう飛んでいるかっていう、そういったこともわかります。
さらには、当然ハクチョウは群れで暮らしていますので、同じハクチョウの仲間ですとか、同じガン科の仲間を(カメラが)写します。そうすると、ほかの種や、ほかの個体も映るので、時期とか地域に応じて、異なる鳥同士の関係性が見えてきます。非常に面白いです!」
●ハクチョウが見た景色を画像で見られるってすごいですよね?
「はい、私もやってみて、こんなにすごいとは思ってなくてですね・・・私自身が感動しているところがあります。きっとそれを見ている多くの市民のかたも感じておられると思います」
●私も見せていただいたんですけど、雄大な自然の中を飛んでいる時の画像がありましたよね?
「あれはびっくり! びっくりです!」

●すごいですよね~! ハクチョウの羽も映っていますし、一緒に飛んでいる6羽の仲間たちも映っていて、本当に感動しました!
「なかなか見られないですよね! 私も感動しました!」
●すごい写真ですよね~。実際、最初に送られてきた写真を見た時は、どんなお気持ちでした?
「思わず声が出ましたね! おぉ~って!(笑)」
●人間じゃ撮れない写真ですからね~。
「そうです! その通りです!」
一般のかたも追跡調査!
※嶋田さんが進めている「スワン・プロジェクト」のサイトにアクセスすると、どなたでも、ハクチョウの位置情報や画像が見られるようになっています。このプロジェクトには、一般のかたも参加できるんでしょうか?
「はい、もちろんです。そのためにX、旧twitterでスワン・プロジェクトを立ち上げています。Xでは、“スワン・プロジェクト”と検索すると、そこのページに行くんですけれども、多くのかたが位置情報を頼りにハクチョウを探しに行っています。探しに行って写真を撮って、その写真を投稿いただいたりとかしているんですね。
そういったことは観察記録にもつながってくるんです。ですので、多くの市民のかたに関心を持っていただいて、近くにいれば行っていただいて、写真を撮って投稿いただくっていうのは、非常にありがたい話です」
●「スワンアイズ」をつけたハクチョウを見つけました! っていうふうに、Xに写真を投稿するのは積極的にやってほしいっていう感じですか?
「できればやってほしいです。というのはハクチョウ目線の写真はわかるんですけど、全体像がわかんないんですよね、逆に言うと・・・。それを撮っていただくことによって全体像、こういう田んぼにいるんだとか、こういうところにいるんだっていうのがわかるので、とても助かるんです」
●カメラ付きGPSロガー「スワンアイズ」をつけたオオハクチョウたちは、いずれは(越冬を)終えて極東ロシア方面に戻っちゃうんですよね。戻っちゃったらこのデータっていうのはどうなるんですか?
「携帯電話通信を使っていますので、当然圏外だと通信できなくなります。北へ戻ってロシアの繫殖地にいると当然、通信網がないので一定期間通信できなくなります。今年の場合で見るとだいたい6月から9月までは一切通信が入ってきませんでした。だけども日本に帰ってきて携帯電話通信網に入ればまた回復します。そうするとそれまでの間のデータが全部取得できるんですね」
●なるほど・・・。
「それによって、ロシアでの素晴らしい繁殖地の景色なども見ることができました」

鳥の世界を楽しんで!
※去年から始まった「スワン・プロジェクト」、今後はどんな展開になりそうですか?
「今年も(オオハクチョウなどの)捕獲と装着をやります。このスワン・プロジェクトに関心を持っていただくために、捕獲地なども少し広げたいと思っていますし、これからも続けていきたいなと思っています」
●今後、何年ぐらい続ける予定ですか?
「そうですね・・・まず今年はやります! 今年の様子とか去年の装着した状況とか、今年これからやることは状況を見ながら、いろいろ検討していきたいと思います」
●この「スワン・プロジェクト」でどんなことを伝えたいですか?
「お陰様でXの投稿数ですとかフォロワー数が増えているんですね。これは多くの市民の方に関心を寄せていただいているからだと思っております。位置情報や画像をもとに多くの市民の方がハクチョウを追跡して、Xに投稿していただいている、こういったことは鳥に関心を持つことにつながりますし、または生態の面白さの気づきになると思うんですね。ゆくゆくはそういった研究につながっていって、鳥の世界をお楽しみいただければなっていうふうに思っています」
INFORMATION
「スワン・プロジェクト」にぜひご注目ください。オフィシャルサイトにアクセスすると、ハクチョウに装着されたカメラ付きGPSロガー「スワンアイズ」から送られてくる位置情報や画像を見ることができます。
また、嶋田さんもおっしゃっていましたが、一般のかたも調査に参加することができます。特に東北や北海道にお住まいのかたは、位置情報を頼りにハクチョウを探して、その個体がいるフィールドの写真を撮って投稿いただくと、観察記録になるということですので、ぜひご協力をお願いします。
◎スワン・プロジェクト :https://www.intelinkgo.com/swaneyes/jp/
◎スワン・プロジェクト「 X」アカウント:
https://x.com/swaproj?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
「宮城県 伊豆沼・内沼 環境保全財団」のサイトもぜひ見てくださいね。
◎http://izunuma.org
嶋田さんは3年前に緑書房から『知って楽しいカモ学講座』という本を出されています。ぜひチェックしてください。
2024/12/8 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. CIRCLE / SWANDIVE
M2. ORINOCO FLOW / ENYA
M3. SUPERSTAR / SWEETBOX
M4. SWAN SONG / DUA LIPA
M5. ワタリドリ / [ALEXANDROS]
M6. SWANHEART / NIGHTWISH
M7. SONG BIRD / FLEETWOOD MAC
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2024/12/1 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、漁港で魚の赤ちゃん 幼魚を、網で採って研究されている岸壁幼魚採集家の「鈴木香里武(すずき・かりぶ)」さんです。
金髪に白いセーラー服というトレードマークの香里武さんは、魚の研究者、経営者、プロデューサー、タレント、番組パーソナリティ等々、幅広い分野で活躍中。
そんな香里武さんに、漁港で採取する幼魚や、館長を務めている「幼魚水族館」、そして先頃出された本『水の世界のひみつがわかる! すごすぎる 海の生物の図鑑』から、変態するお魚、農業をするお魚など、魚に関連する面白いお話をたっぷりうかがいたいと思います。
☆写真協力:鈴木香里武、幼魚水族館、KADOKAWA

名付け親は「明石家さんま」!?
●今週のゲストは、岸壁幼魚採集家の鈴木香里武さんです。鈴木香里武さんは先頃『水の世界のひみつがわかる! すごすぎる 海の生物の図鑑』という本を出されています。後ほどそのお話もうかがいます。よろしくお願いいたします。
「よろしくお願いします。ごきげんようぎょ! これを言わないと始まらない(笑)」
●ごきげんようぎょ!(笑) よろしくお願いいたします! まずはプロフィール的なお話から。どうしても気になるのでお聞きしたいんですが、鈴木香里武さんというそのお名前は本名でいらっしゃるんですか?
「はい! 芸名だとよく思われるんですけど、これ本名なんですね。“スズキ”も魚の名前ですよね」
●確かにそうですね~!
「“香里武”がカリブ海からとられた名前で、3月3日生まれの魚座なので、全部揃っているという(笑)、作ったような話なんですよね」

●海のために生まれてきたみたいな感じですよね!
「ちなみに“香里武”って名前をつけてくださったかたも、魚にまつわる人なんですよ」
●どなたなんですか?
「明石家さんまさん! “さんま”、やっぱり魚ですね!」
●え~~〜っ! どういう経緯で?
「これは、うちの両親が当時さんまさんに仕事ですごくお世話になっていまして、(両親が)新婚旅行でカリブ海に行ったんですね。そのお土産を持って、さんまさんのところにお届けに行った時に、子供の話が出たらしくて、“名前はどうするんだ?”みたいな話が出たと・・・。
両親は海が好きなので“、海にまつわる名前をつけたいです!”って言ったら、さんまさんなりにいろいろ考えてくださるわけですね。“オホーツク”とか“エーゲ“ “カスピ”とかいろいろと出るわけです。でもふと(さんまさんが)思い出して “カリブ海に行ったんやろ? だったらカリブでええやん“って、その”ええやん“の一言で決まったのが僕の名前でございます」
●そうだったんですね~。名付け親は、さんまさんだったんですね!
「そうなんですね。ここまで魚と海に囲まれたら、もう魚のことをやるしかないですよ」
●運命ですね! では子供の頃から海とか魚には興味があったんですか?
「そうですね。生まれた時から家には魚を飼う水槽がありましたし、両親も海が好きなので、休みの日になると僕を連れて海辺によく遊びに行ってくれていたんですね。なので、魚のいない生活は逆にしたことがないです」
●なるほど。魚のことをどなたかに教わったりはしたんですか?
「当時はね・・・今32歳なので、32年前は今ほど魚の情報ってなかったんですよね。もちろん魚図鑑で勉強したりはしましたけれども・・・。いちばん衝撃的だった先生との出会いは、“さかなクン”かなぁ~と思います」
●お~〜、そうなんですか?
「小学校3〜4年生の頃かな、初めてお会いしたのが・・・その時に衝撃を受けました。それまで魚の先生と言えば、白衣を着て顕微鏡を覗いているような大学の教授、もしくは水族館の職員さん、そんなイメージだったんですよね。でもご本人がそのまま、魚の使者みたいな人が登場して、すごくびっくりして、もう嬉しくなっちゃって、こんな人いるんだと思って憧れて、(さかなクンの)あとをくっついて歩いていた時期がありました」
(編集部注:実は香里武さん、学習院大学大学院で心理学を専攻し、「観賞魚の癒しの効果」というテーマで、魚を見たときの人の心理を研究。そして現在は、北里大学大学院の海洋生命科学研究科に籍を置き、魚の一生、特に幼魚が漁港で人工物をどのように利用して生き抜いているかを研究されています)
「岸壁幼魚採集家」とは?
※ところで、肩書きの「岸壁幼魚採集家」も気になりますよね。この肩書きにしたのは、どうしてなんですか?
「聞き慣れない言葉ですよね~」
●漢字がたくさん並んでいる感じ(笑)
「これを本業だと言い張っている人は、たぶん世界でも僕しかいないと思うんです。やっていることはものすごくシンプルで、”タモ網”っていう柄のついた網を持って、それで漁港に行って・・・岸壁っていうのは漁港の壁面のことですね。そういう港で這いつくばって、上から海面にいる魚たちを覗いて、そこにいる幼魚をすくうと・・・壮大な金魚すくいみたいなもんですね。

それをやる人のことを『岸壁採集家』っていうふうに一部のジャンルとしてあったんですよ。趣味としてやっている人がいたんですね。その中でも幼魚に特化して本業にしよう! っていうことで、こんなまどろっこしい肩書をつけております」
●インパクトがありますよね~! 漁港に魚の赤ちゃんっているんですか?
「そう! これもね~結構灯台もと暗しっていう感じで、漁港だけに灯台もと暗しですけど・・・そんなことはどうでもよくて(苦笑)。みなさん、釣り糸を垂らしたりしていますよね。その足元に実はいるんですよ、幼魚って・・・」
●たくさんいるものなんですか?
「たくさんいるんです。ただあまりにも小さかったり、透明になって身を隠していたり・・・。あとは擬態と言って、枯れ葉そっくりだったり岩そっくりだったり、生き物らしからぬ、いろんな姿で身を潜めているんですね。それは大きな魚に食べられないためだったり、上から狙っている海鳥のカモメとかに食べられないためだったり、身を守るために見えなくて当然な姿しているんですね」
●へ~〜っ!
「だから言われないと気づかないですね」

●そうなんですね~。今まで何種類ぐらいの幼魚に出会えたんですか?
「どうかな・・・700(種類)は超えていると思うんですけど、もはや数えられないですね」
●季節的にはいつ頃がいいとかあるんですか?
「春夏秋冬、朝昼晩いつでも面白いんですよ。魚がいちばんたくさん見られるのは夏から秋にかけて、南のほうからもカラフルな幼魚がやってきたりするので、とても楽しいんですね。
でも今の季節、冬12月ですね。冬になると深海魚の赤ちゃんが上がってきたりもするんですね。水温が低くなるので、冷たい海に暮らしている深海魚も浅いところまで上がってきて泳げるようになってしまう・・・そうすると普段はなかなか生きた姿を見られないような、幻の深海魚たちに足元で出会えるっていう、これまた興奮の連続の季節がやってきます」
●これまで採集した幼魚で、特に印象的だった幼魚っていますか?
「う〜〜ん・・・『リュウグウノツカイ』かな~。深海魚で体長5メートルぐらいある、ものすごく長い体を持った深海魚がいるんですね。時々成魚が砂浜に打ち上がったりして・・・。そうするとあまりにも珍しいので全国ニュースになったりする、それぐらいの魚なんです。
そのリュウグウノツカイの幼魚、最初に出会ったのは7センチぐらいのちっちゃい子だった・・・その子に漁港で初めて出会ったのが、僕はたぶん人生の中でちゃんとした深海魚の赤ちゃんに、足元で出会った最初の経験だったんですね」
●へ~~〜っ!
「その時に衝撃を受けて・・・僕は幼少から深海魚が大好きだったので憧れていたんだけど、いつも僕が見ている水深0メートルの世界では到底出会えない、本当に遠い世界の存在っていうイメージだったんです。それが実は0メートルにも現れる、それを体感した時に、海って横にも繋がっているし、縦にも繋がっているんだっていうことをすごく感じて、感激した瞬間だったんですね」
変態する魚!? 農業をする魚!?
※香里武さんは先頃『水の世界のひみつがわかる! すごすぎる 海の生物の図鑑』という本を出されています。この本には、可愛いキャラクターが登場したり、イラストや写真もたくさん載っていて、お子さんを意識した作りにはなっているんですが、専門用語もまじえ、魚の生き様を紹介。香里武さん的には、すべての世代のかたに「海の世界へのパスポート」として読んでほしい、そんな思いを込めたそうです。
それでは、本に載っている75のトピックから、いくつかピックアップしてお話をうかがっていきます。まずは「美しき変身ヒーローと、愛すべき変態たち」という見出しのトピックがありますが、これはどういうことなんでしょうか?
「これは、海の生き物って卵から生まれて、そして一生を終えるまでの間、ずっと同じ姿をしていることって少ないんですね。それは生活のスタイルを変えるので、それに合わせて姿もガラリと変わるんです。それが変身ぐらいだったらまだしも、昆虫と一緒で体の構造を全く変えてしまう、変態をするような生き物もいるので、ドラマチックな変わりっぷり! これをぜひ知っていただきたいなと思って書きました」
●幼魚から成魚になる時に大変身するってことなんですね?
「そういうのもいますね」
●たとえば、どんな魚が・・・?
「たとえば、渦巻き模様のお魚で『タテジマキンチャクダイ』いうお魚がいるんですね。とっても見た目が可愛らしくて水族館でも人気の幼魚なんですけれども、このウズマキちゃんが成長すると名前の通り、縦じま、縞々模様に大変身しちゃうんです」

●模様が変わっちゃうんですね?
「色もディープブルーな色だったものが、黄色と青のストライプになっていくんですね」
●全然違いますよね?
「全然違います! たぶん言われないと同じ魚だとは思えない。これもちゃんと意味があって、彼らは親同士の縄張り争いが激しいんですね。なので、同じ柄の別の個体を見ると攻撃を仕掛けるわけです。
でもその攻撃を幼魚にまで仕掛けてしまうと、幼魚はまだデリケートな存在なので、種の保存っていう意味ではよろしくないわけですね。やっぱり自分たちの種類を繁栄させなきゃいけないから、子供は守んなきゃいけない。そこで一目瞭然で喧嘩の対象外だってわかるように、親子で全然柄が違うんじゃないかっていうのが、今の主流で言われている説です」
●面白いですね!
「本当かどうかは、本人に聞かなきゃわかんないです(笑)」
●それから「地道に農業をする魚」!
「これも面白いですよね~」
●「クロソラスズメダイ」という魚ですけど、農業するってどういうことなんでしょうか?
「いるんですよね~、草食で草なんかを食べるお魚なんですけれども、お気に入りの海藻があるわけですね。イトグサっていう海藻が大好き! そればっかり食べる。
でもイトグサは放っておくと、ほかの海藻のほうが強いので負けちゃって、ほかが生えると、雑草がいっぱい生えちゃうと、本物のイトグサさんが枯れてしまうっていう問題がある。そこで、このクロソラスズメダイは岩の表面をせっせと手入れして、イトグサ以外の雑草むしりを常にやっている。イトグサがたくさん生える環境を整えて、自分の畑を耕して、それで大切に育てたイトグサを最終的には食べちゃうわけなんです」
●食べちゃうんですね!
「それもすごく面白い関係だなと思いますね。イトグサはイトグサで、クロソラスズメダイが面倒を見てくれないと育たない海藻なので、ある意味ではwin-winの関係・・・結局食べられちゃいますけどね(笑)」

サメのために、あのKISSが洋上ライヴ!?
※では、本に載っているトピックのお話を続けましょう。
●おしまいは、ホホジロザメのためにライヴをしたロックバンドということで、これはどういうことですか?
「意味がわかんないですよね(笑)。世界的に有名なロックバンドのKISSっていう、あのメイクしているKISSが2019年に船の上でライヴをやったことがあるんですね。オーストラリアの海かな・・・。そのライヴは人に向けてのライヴではなくて、実はサメを呼び寄せるためのライヴだったんですよ」
●面白いことをしますね!
「船の下から水中に音が出るようにスピーカーつけて、それでハードロックをオーストラリアの海に響かせたわけですね。なんでそんなことやったかっていうと、ホホジロザメをはじめとするサメの仲間は、低周波の音に反応する習性があるんですね。重低音と言えばロックだろう! それで本当にサメが来るんだろうかっていうこの面白い企画をやった人がいて・・・結局(サメは)来なかったんです(笑)」
●来なかったんですね~。
「来なかったんですけど、でもこの企画に乗ったKISSのメンバーのロック魂には拍手です」
●確かにサメに向けてライヴするって、すごいことですよね!
「面白い発想ですよ〜。でも、お笑いでやっているわけじゃなくて、ちゃんとそこにはサメという生き物ならではの習性があって、彼らが海のハンターと呼ばれるゆえんは、そういう周波数とか、ちょっとした電波みたいな、電気みたいなものとかを感じ取る器官がすごく発達しているから、だからああやって、かっこいい姿で海の王者になっているわけなんですよね。そんなことを感じられるエピソードかなと思います」
幼魚に特化した水族館

●2022年7月に静岡県駿東郡清水町に「幼魚水族館」がオープンして、香里武さんはそこの館長さんでもいらっしゃるんですよね?
「はい、そうです!」
●この水族館では、香里武さんが採集された幼魚が見られるそうですね?
「僕をはじめとするスタッフたちが、夜な夜な近くの漁港まで行って、その季節に出会える幼魚をすくってきて展示しているので、どの季節に行っても今の駿河湾を見ることができるんですね」
●現在どれぐらいの数の魚を飼育・展示されているんですか?
「大体100種類、150匹ぐらいは泳いでいますね」
●オフィシャルサイトを見ると、魚の展示だけじゃなくてユニークな展示もされているんですね?
「そうですね。いろいろ海で僕がいつも上から海面を覗いているので、横からだけじゃなくて上から覗くことができる水槽を作ってみたりとか・・・。
あとはどうしても、一生懸命育てていても死んでしまう幼魚もいるので、そういう死んじゃった子たちも、もう1回見てもらいたいっていうことで透明標本という形で・・・、中部大学の武井(史郎)先生というかたが作られているその特殊な技術で、生きたままの姿で透明化することができるんです。そうすると生きている時は見えなかった体の中の構造も間近で見ることができるので、新しい形でまた“第2の魚生”を歩んでいただいています」
●ほかの水族館と比べて、いちばんの違いってどんなところですか?
「そもそも魚の赤ちゃん、幼魚に特化した水族館は世界で初めてなので、これはほかではなかなか幼魚って見られないと思います」

●確かにそうですよね~。
「あとは、幼魚ならではのこととして、どんどん成長していくんですね。成長すると姿形がさっきの変態のように変わっていくので、その様子を飼育員だけじゃなくてお客さんも一緒に見届けることができる。そして成長して幼魚ではなくなったら『卒魚式(そつぎょしき)』っていうのをやります。今度は、別の水族館に成魚として無償提供するんです。ちゃんと式典をやるんですよ、1時間の!」
●そうなんですね~。
「来た時はこんなだった子がこんなに大きくなりましたっていう成長記録を発表したりとか、ちゃんと町長さんまで来て祝辞をいただいたりとかですね。そうやってお客さんと一緒に育てた幼魚たちを、お客さんと一緒に見送って、別の場所で今度は成魚として別のお客さんに感動を届けてもらいたいと、そういうふうにストーリーを繋げています」

海の変化、海洋ゴミ〜自発的なSDGsに
※日頃、岸壁幼魚採集家として活動されていて、海の変化を感じたりすることはありますか?
「あ~〜ものすごく感じますね。ここ10年ぐらいだけでも、かなり変化したかなと思っています。たとえば、ちっちゃい頃だったら、春先になると漁港の足元には海藻が青々と茂っていたんですね。それが最近暖冬が続いて、温暖化で海水温が下がらなくなって海藻が育たなくなってしまったんですね。
そうすると、春先にもう海藻はないし、その海藻に身を隠していた幼魚たちも忽然と姿を消してしまう。逆に夏になると昔は見られなかったような、沖縄あたりに暮らしているカラフルな魚たちが黒潮っていう海流に乗って、こっちまでやってきて、それが秋、冬とずっと生き延びている姿を見るようになりました。
昔だったら冬を越せなかった子たちが、今は暖冬で冬を越すようになっている。新しい魚が来たってことは、もともといた魚がいなくなっているってことなので、そういう足元で出会える魚の種類の変化からも温暖化は感じますね。
あと、漁港の隅って海洋ごみがたくさん打ち寄せられるんですよ。風に乗ってゴミが流されてきて結構汚いんですね。いかにゴミが海に多いかを知る場所としても漁港はいいのかなと思っていて・・・年々ゴミの量も増えています。でもそのゴミさえも、敵から身を守るために利用して、ゴミの下に隠れている幼魚がいたりなんかするんですね。
そういう姿を知ると、ゴミを拾いに行きましょう! っていうのと、ちょっとまた違った入り口が広がると思っています。そのゴミの周りにいるたくましく健気な幼魚たちの生き様を見て、彼らの暮らしている海を汚してはいけないなと、綺麗にしたいなっていう気持ちがわいてくれば、義務としてのSDGsではなくて、自発的なSDGsに繋がっていくのかなと思っています」

●幼魚たちの調査や研究をされていて、ワクワクするのってどんな時ですか?
「まだ出会ったことがない幼魚に出会った時ですね。32年やっていてもあるんですよ、初めての出会いが・・・。今年も8月に『イシガキフグ』っていう、世界で誰も幼魚を見たことがない(その幼魚を)すくったことがあって、成魚はいっぱいなのに幼魚を誰も見つけたことがない・・・。でもそうやって、毎年のように新しい出会いがあるから、これはやめられないですね」
●「岸壁幼魚採集家」として、いちばん伝えたいことはどんなことですか?
「思っているより魚たちは身近にいるっていうことですね。海に潜っていかなくても沖に出なくても、足元をちょっと覗くだけで魚に出会える。これは日本の豊かさでもあるし、海全体の豊かさなのかなと思います」
INFORMATION
香里武さんの新しい本をぜひ読んでください。香里武さんの視点で取り上げた、魚や海に関する75のトピックを掲載。イラストや写真がたくさん載っていて、見開き2ページでひとつの話が完結しています。見出しを見て、面白そうなページから読めますよ。おすすめです!KADOKAWAから絶賛発売中! 詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎KADOKAWA :https://www.kadokawa.co.jp/product/322404001466/
鈴木香里武さんのオフィシャルサイトもぜひ見てくださいね。
◎鈴木香里武:http://karibu-collabo.main.jp/top/?page_id=7
静岡県にある「幼魚水族館」にぜひお出かけください。展示内容やアクセス方法など、詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
◎幼魚水族館:https://yo-sui.com/