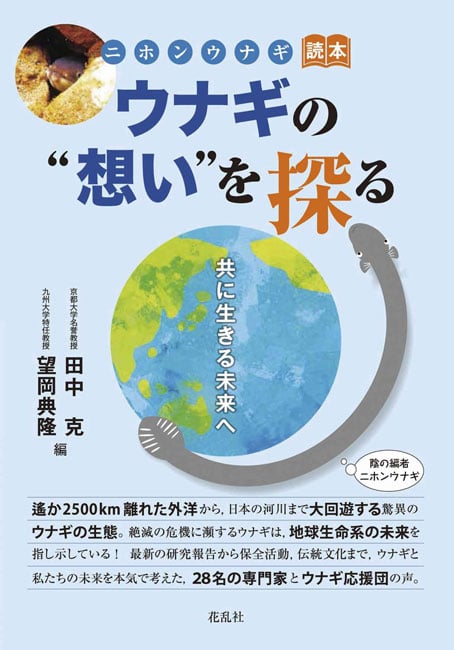2021/2/28 UP!
◎布施大樹(種継人の会・代表) 『種を介して繋がる〜在来作物を守る「種継人の会」』(2021.2.28)
◎浅川陽子(世界自然保護基金「WWFジャパン」野生生物グループ) 『「ワンヘルス」〜新興感染症の発生とパンデミックを防ぐために〜』(2021.2.21)
◎露木志奈(環境活動家) 『情熱と行動力があれば、世界は変えられる〜20歳の環境活動家「露木志奈」〜』(2021.2.14)
◎北田雄夫(アドベンチャー・ランナー) 『地球を走るアドベンチャー・ランナー〜挑戦すること自体が面白い!〜』(2021.2.7)
2021/2/28 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、茨城県常陸太田市の在来作物を守る「種継人(たねつぎびと)の会」の代表「布施大樹(ふせ・たいき)」さんです。
布施さんは東京都出身。東京農工大学卒業後、栃木の帰農志塾で農業を学び、その後、常陸太田市に移住。家族で有機農業を営む「木の里(このさと)農園」の代表でもいらっしゃいます。
「種継人の会」は、2013年頃に地元の仲間と一緒に行なった、山形の在来作物の種を守り継ぐ人々を撮ったドキュメンタリー映画『よみがえりのレシピ』の自主上映会をきっかけに発足。そして、仲間たちと一緒に、常陸太田市にどれくらいの在来作物があるのかを調べたところ、30種ほどあることがわかったそうです。
きょうは布施さんに、「種継人の会」の活動や、暮らしの根っこにある在来作物への思いなどうかがいます。
☆写真協力:布施大樹

可愛い、美味しい、在来作物
※常陸太田市の在来作物は約30種ということですが、具体的にはどんな作物があったんですか?
「常陸太田市は茨城県の北部になるんですけども、標高が数メートルから800メートルぐらいの、結構多様な地形になっていまして、元々いろんな作物が栽培できる場所なんですね。
例えば、お米ですとか、あとはこの辺はあまり知られてはいないんですけれども、日本一って言われている“常陸秋そば”の産地で、そのそばの在来種があったりですとか。
あとは小豆ですね。“娘来た”って言われている斑の模様の小豆。他にもたくさんのインゲンや大豆、芋類、菜の花のようなものですとか、あとは胡麻や、こんにゃくとか、本当にいろんなものが見つかりました」

●いろんな在来作物があるんですね! 「種継人の会」はどんな活動をされているんですか?
「種継人の会という名前の通り、地元にある在来作物の種子を受け継いでいくということが大きな目標ではあるんですけれども、最初は地元のいろんなイベントに誘われて、こんな作物があるよって提案したりですとか、そういうことをしていたんです。
在来作物を守ってきた人たちがいるんですよね。もう80代ですとか年配の方なんですけれども、そういう人たちと話しているうちに、やっぱりその人たちが守ってきたものを、もう少しこの地域の外に出していきたいなと思うようになりまして、ワークショップをやったりですとか、試食会をやったりですとか、そういった活動を少しずつするようになりました」
●在来作物の魅力って何ですか?
「多分、小尾さんも聞いたことがあると思うんですけれども、(在来作物は)栽培が難しかったりとか、あとは収穫の量が少なかったりとか、そういったことが理由で、もっと生産性の高い新しい品種に切り替わってきたという歴史が在来作物にあるんですよね。
ただ、僕自身は物事はやっぱり良い面と悪い面が両方あると常々思っています。採れる量が少なかったりする反面、見た目が可愛かったりとか、味がとても美味しかったりですとか。あとは地元の伝統的な仕事と紐づいて残ってきた作物だったりとか、そういった他にはない魅力があるのが在来作物の特徴だと思います」
種を残し、仕事を残す
※「ホウキモロコシ」という作物を「種継人の会」のサイトで見つけたんですが、これも常陸太田市の在来作物なんでしょうか?

「座敷ほうきって使われますか? 」
●祖父母の家で、っていう感じですかね(笑)。そのほうきを作るためのトウモロコシっていうことですか?
「そうなんです。厳密にはトウモロコシではないんですけれども、トウモロコシですとか、きびだんごの“高きび”ですとか、大きく分けると、もろこしっていう雑穀の仲間があります。その中のトウモロコシだったり、あと餌になる他のもろこしだったり、いろんな種類があるんですけども、その中のひとつで工芸用に作られている、ホウキモロコシっていうイネ科の牧草の一種です。
高さが3メートルぐらいになりまして、それを真夏に穂先だけを1本ずつ折り採って収穫をして、茹でて天日で乾燥させて、冬場に、農閑期にほうきを作って販売するっていう仕事が江戸の後期の頃から常陸太田市で行なわれてきました」
●布施さんはホウキモロコシの栽培方法だけじゃなくて、ほうきそのものの作り方も学ばれたっていうことですか?
「そうですね。僕たちが在来作物の調査をしていて、そのメンバーの方がこういった仕事をしてきた人もいるはずだよということで教えていただきました。その職人さんをお宅に尋ねたところ、仕事を今年で辞めようっていうことをおっしゃっていまして、その方がその当時は最後の一軒だと僕らも聞いていました。
ホウキモロコシの材料っていうのは買えるものではないんですよ。材料を購入して作ったりすることができないもので、種から育てないといけないものなんですね。
多くの工芸品っていうのは、例えば木の道具だったら木を仕入れて作ったりとか、鉄を仕入れて作ったりとかするものなんですけれども、座敷ほうきっていうのは、種を畑に6月の末ぐらいに撒いて、間引きをして土寄せをして草を取って育てて、8月の末ぐらいに収穫します。
畑で種から育てて初めて材料が作れるものなので、その種がなくなってしまうと、ほうき作りが地域から消えてしまうんですよね。
日本に何箇所も座敷ほうきの産地は今でも残っているんですけれども、各地に特徴のあるホウキモロコシの種が継承されてるんです。常陸太田には常陸太田の種子がずっと残されてきたということで、種をただ残すということではなくて、仕事を残していくことが初めてその種子の継承に繋がっていくということに気がつきました」
地域の人と一緒に
※布施さんは「木の里農園」を運営する農家さんでもいらっしゃいますが、東京のご出身です。どういう経緯で農業に従事するようになったんですか?
「元々は大学の農学部で林業の勉強をしていたんですけれども、その当時から第一次産業の現場で働きたいという希望は持っていました。大学2年の春休みに、沖縄の波照間島っていう、人が住んでいるいちばん南の島で、西表島の南に浮かんでいる島なんですけど、そこで1ヶ月ほどサトウキビ狩りのアルバイトをしました。
そこで何というか、皆さん、すごく仕事もハードですし、生活も大変な中でも地元の海と島と畑の中で、この人たちは非常に輝いて生きてるなという風に、都会人の僕は感じてしまいまして、それからやっぱり自分も一度きりの人生なので、農業を目指して生きていきたいという風に思いました」
●そうなんですね。でも農業をする場所って日本全国いろんな場所があると思うんですけど、どうしてこの常陸太田市で農業を始めようと思われたんですか?
「私自身が都会人で、農業の現実をあまりよく分かってなかったということもあるんです。
大学では林業のことですとか、環境のことを勉強していたので、その当時ですと過疎の問題ですとか、今でもありますけれども、リゾート開発の問題ですとか、そういった問題があった中で、自分は農家にはなりたいんだけれども、なるべく山の中の厳しい環境に身を置いて、そこで地域の人と一緒に自分は農業をやって生きていきたいという無謀な夢を持ちまして、現在地に就農しました」

●実際いかがでしたか?
「最初の5〜10年ぐらいは毎日が必死だったので、この土地の厳しさとか、あまり考えることもなくて、もうひたすら毎日一生懸命働いていたんですけれども・・・ふと立ち止まった時に、やっぱり山間部ですので日照時間が短かったりとか、野生動物の被害が多かったりとか、土が痩せているですとか、いろいろなデメリットがあるなっていうことにようやく気がつきました。
その反面、やっぱり自然が豊かで、水が綺麗で、空気も澄んでいて、空が高くて、もうこれ以上ないという環境で作物を育てることができるという、良い面もすごくあるなという風に今は感じています」
大切にしている3つこと
※布施さんの「木の里農園」では1年を通して、どんな作物を育てているんですか?
「うちは消費者に直接野菜をお届けするというスタイルで農業をやってますので、年間ですと、品目でいうと70品目ぐらいの野菜を育てて、その中でもいろんな品種を作るので、全部合わせると250品種ぐらいの野菜、米、麦、大豆、蕎麦、とにかくありとあらゆる作物を、私と妻と、あとは一緒に働くメンバーが3人ほどいるんですけれども、力を合わせて栽培しています」
●在来作物が多いんですか?
「地元の在来作物も作っていますけれども、私自身は、農業者としてはそれにすごくこだわっているということはないです。在来作物の重要性っていうのは先ほどお話しした通りですけれども、一方で、やっぱり現代の新しい野菜ですとか、品種改良された品種の良さっていうのも、農業者としては非常に分かっているので、そういったものも積極的に取り入れたり、外国の品種とかも作ってはいます。
ただ、やっぱりその中で、現在の優れた品種と比較しても、やっぱり輝きを失わない在来作物っていうのもあるので、うちでも積極的に栽培して、自分で毎年種を採って品種改良を試みたりとかしています。
それで消費者の野菜ボックスに入れたり、お付き合いのあるレストランのシェフに提案したりとか、この土地ではこういったものがありますよっていう、こちらからどんどんそういったものを発掘して、提案していくっていうようなこともやっております」

●消費者に直接届ける野菜ボックスには、何かコンセプトとかあるんですか?
「日々の食卓、本当に毎日の朝昼晩の食卓に普通に食べていただきたいと思っていまして、そこをすごく大事にしています。
大きく申し上げると3つ大切にしていることがあって、1つ目は“食卓の変革”って僕ら勝手に呼んでいるんですけれども、地元の田畑と繋がった食卓が増えていったらいいなっていうことを大事にして考えています。
もう1つが“持続性”ですね。サスティナビリティというのをすごく大切に考えていまして、栽培方法ですとか。農薬とか化学肥料は一切使わずに、地域の資源、例えば常陸太田市でしたら山林がたくさんあるので、そういったところの落ち葉を、本当に無尽蔵に手に入るので、大量に集めて発酵させて土作りに使ったりですとか、地域にあるものを大切に利用するということを考えています。
最後の1つが“信頼関係”ですね。消費者との信頼関係はもちろんあるんですけれども、例えば地元の自然環境との信頼関係とか、あとは、いろんなものが信頼関係で結ばれるような農園でありたいし、そういった地域を作っていきたいし、そういった繋がりが増えていくこと。僕たちはそういう世界で生きていきたいと思っているので、そういった未来を目指して農業をやっています」
繋がりを大切にしていく
※今後、農家として、また「種継人の会」として、どんなことに取り組みたいと思っていますか?

「種継人の会としましては、さっきちょっとお話が漏れてしまったんですけれども、“娘来た”っていう可愛い小豆があります。その小豆の栽培会を作って、地元の丁寧なお仕事をされている小さなケーキ屋さんですとか、レストランとか、旅館とか、パン屋さんとかいろんなところと繋がって、契約栽培をもう3年ほどやっています。
ただ種を残すということではなくて、ほうきもそうなんですけれども、ものづくりのいろんな営みと種子を介して繋がっていく、生産者と作り手が繋がっていく、そのお店に来た人がまた地元で小豆を使って、いろんな料理にチャレンジしていったりとか、そういった繋がりを増やす活動をしていきたいなと思っています」
●繋がり、大事ですね! 消費者として農家さんに出来ることはどんなことなんでしょうか?
「今の時代って農業者っていう、ものがすごくプロフェッショナルの世界になってきてると思うんですね。会社組織も増えたりですとか、それはすごく僕はいいことだと思うんですけれども、反面やっぱり食卓と農業の距離がすごく離れてしまっているのかなと思っています。
なので、例えば安全安心ですとか、農法にこだわって農産物を選ぶ方もいらっしゃいますけれども、その前に、僕が大事だと思うのは、誰がどんな思いで作ったのかっていうことを、僕らも伝えなきゃいけないし、皆さんもそういうことを知って、作物を選んでいただけたら嬉しいなと思いますね。
で、私たちも同時にどんな消費者に届けたいのか、どんな思いを伝えたいのか、作る側も意識して、お互いが繋がる努力をしていく。努力っていうんですかね・・・そういうことが楽しめるような関係性を作っていけたらいいんじゃないかなと思います」
●この番組を聞いてくださっているリスナーの方にいちばん伝えたいことは、改めてどんなことですか?
「種継人の会の活動にも関連してくるんですけれども、今すごく国際化が進んできて、労働者も外国から入ってくるし、会社の仕事も国境とかどんどん関係なくなっていく中で、やっぱり地元にある小さな仕事だったり営みだったり、そういったものの価値は、これから逆にすごく輝きが増してくるんじゃないかなと思っています。それが地域のアイデンティティだったり、日本の特徴だったり、伝統的な仕事もそうですけれども、繋がっていくと僕は思っています。
ですので、そういったものにちょっと意識を向けていただいて、少し興味を持って関わってみたり、その人たちがどんな人たちなのか会いに行ってみたりとか、そういったことをすることが、これからの時代を生きていくヒントになるのではないかなと私は考えています」
INFORMATION
「種継人の会」
布施さんたちの活動や常陸太田市の在来作物については「種継人の会」のサイトをご覧ください。
◎種継人の会のHP:https://tanetsugibito.com
「木の里農園」
「木の里農園」の人気アイテム、消費者に直接野菜などの作物を届ける「野菜ボックス」(大変人気があって、いま新規の受付はしていないそうです)ほか、布施さんが育てた野菜を扱っている小売店や食材に使っているレストランについては「木の里農園」のサイトを見てください。
◎木の里農園のHP:https://konosato.com
2021/2/28 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. STRAWBERRY FIELDS FOREVER / BEN HARPER
M2. LET IT GROW / ERIC CLAPTON
M3. LOVE FIELD / ELVIS COSTELLO & THE ATTRACTIONS
M4. WAITING FOR A STAR TO FALL / BOY MEETS GIRL
M5. ベジタブル / 大貫妙子
M6. HEAVEN ONLY KNOWS / SWING OUT SISTER
M7. WE BELONG TOGETHER / MARIAH CAREY
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2021/2/21 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、世界自然保護基金「WWFジャパン」野生生物グループの「浅川陽子(あさかわ・ようこ)」さんです。
私たちはいま、新型コロナウイルス感染症の世界的な大流行パンデミックによって、大きな危機に直面しています。そんな中、先月、世界自然保護基金「WWFジャパン」が新たな感染症の発生とパンデミックを防止するために「ワンヘルス共同宣言」を発表しました。この「ワンヘルス」という言葉には、私たちの未来を左右する、といっても過言ではない、とても重要な意味が込められています。
そこで今週は、「WWFジャパン」の浅川陽子さんをお迎えし、「ワンヘルス」=健康はひとつ、という考え方、そして感染症発生の原因と予防策についてうかがっていきます。
☆写真協力:WWFジャパン

「ワンヘルス」の理念
※先月、WWFジャパンが発表した「ワンヘルス共同宣言」、その宣言の内容については、のちほどうかがいますが、まずは「ワンヘルス」の解説をお願いします。
「ワンヘルスは、ひとつの健康という意味なんですけれども、まさに人と動物、あと生態系の健康をひとつと考える概念になっています。これは人が健康であるためには、その感染症の発生原因となる自然破壊を止めて、生態系を健全に保って、動物の健康も一緒に守っていきましょうという考え方になっています」
●感染症の発生原因は自然破壊ということですが、自然が壊されると、どうして新しい感染症が発生してしまうんですか?
「新型コロナウイルスのように新しく発見される感染症の多くが、野生動物から由来したものだと言われています。これは人と動物の距離が近づくことによってウイルスが動物から人にうつるんですけれども、この人と動物の距離が近づく要因に、森林伐採とか生物多様性の損失ということが関係していると考えられているんですね。 実際ウイルスの増加と反比例するような形で、世界の森林面積というのは減少していることが分かっていて、感染症のリスクというのは熱帯雨林地域で高いということも明らかになっています」

●野生動物と人が接触してしまうと、未知のウイルスに感染してしまうということなんですか?
「はい、やはり森林破壊のために、人が森に立ち入ったり、生息地を奪われた野生動物が都市部に移動したりするということもありますし、森にアクセスしやすくなって、人が森に入って行って動物を獲って、都市部で販売するという行為の過程で、やはり動物から人にウイルスがうつってしまうという可能性があるんですね」
●森林破壊以外にも何か原因はあるんですか?
「他にも地球温暖化とか、あとは野生生物取引というのも新興感染症を発生させる原因と言われています。いま特にWWFジャパンが問題にしているものに、違法、あるいは不適切な野生生物取引というのがあります。
中国とか東南アジアにはやはり様々な野生動物が狭い檻に閉じ込められて、不衛生な状態で保管、販売されるような市場が確認されているんですね。こうした状況は、ウイルスが動物から人にうつる状況を生んで、新興感染症が発生しやすい要因のひとつとなっています」

毎年発生する新しい感染症
※新興感染症は、新型コロナウイルス感染症のほかに、過去にも同じようなことは起こっていたのでしょうか。
「みなさん、記憶に新しいと思うんですけれども、SARSとかMARS、あとはエボラ出血熱といった病気も新興感染症のひとつだと言われています」
●毎年のように新しい感染症が発見されているような気もするんですけれど、これって本当なんですか? どういう状況なんですか?
「毎年3〜4つの新しい感染症が確認されているような状況で、大体それらの70%が動物から由来していると言われています」
●毎年3〜4つは結構な頻度ですよね? やはり動物がウイルスを媒介しているんですね。
「はい、動物から動物、そして感染した動物から人へウイルスが伝播した事例っていうのも確認されています。実際に先ほどお伝えしたエボラ出血熱はコウモリからゴリラ、ゴリラから人間へ感染したと言われていますし、SARSもコウモリからハクビシンという動物にうつって、人間に感染したんじゃないかと考えられています」
●ウイルスによっては、人に感染するウイルスと感染しないウイルスがあると思うんですけれども、こうやって人にも動物にも感染してしまうウイルスっていうのはどれくらいあるんですか?
「世界保健機関WHOによると現在、人に感染が確認されたウイルスは200種以上あると言われています。さらに野生動物は、まだ確認されていないウイルスを持っていると言われているんですけれども、そのうち人間に感染する可能性があるよ、と言われているウイルスは80万種を超えるとも言われていて、まだまだ新しい感染症が出てくる可能性は十分にあるなと心配しているところです」
●その数を聞いてしまうとちょっと恐ろしいですね。でもすべてのウイルスが悪ものではないんですよね?
「そうですね。実際に、ある動物には無害であっても、他の動物に有害なウイルスというのもあります。やっぱり様々な生き物がバランスよく関わって生息している、いわゆる健康な生態系っていうのは、ウイルスが特定の動物の中だけに留まって大人しくしているので、私たちにそんなに被害が及ぶことはないと考えられています」
海外青年協力隊でインドネシアへ
※浅川さんは2018年にWWFジャパンに入ったそうですが、何か入るきっかけがあったのでしょうか。
「実はですね、その前にもうWWFジャパンでアシスタントとして働いていたことがあって、その後、運よくインドネシアにJICAの青年海外協力隊で派遣していただき、2年間インドネシアの国立公園で働かせてもらいました。
そこで結構、緑に毎日触れる機会がありましたし、自然が本当に豊かな国なので、いろんな生き物を見ることもできて、改めて環境の大切さ、あとは美しい地球の素晴らしさっていうのも感じて、もう一度自然環境に携わる仕事がしたいなと思いまして戻ってまいりました」
●2年間は具体的にどんなことをされていたんですか?
「私は国立公園で主にコミュニティ開発と環境教育という2つの仕事をしていたんですね。
実際に国立公園の問題として、現地の方々が農業とか、あとは採取のために森に入ってしまうという問題があって、どうしたらその人たちが森に目を向けずに、むしろ森を守るような取り組みをしてくれるかなっていうところを、現地のスタッフと一緒に考えながら、代替産業を作るような取り組みをしていました。
環境教育は現地の小学校、中学校に行って、環境の大切さを授業するというような活動をしていました」
ワンヘルス共同宣言
※ここまでのお話で、感染症の発生原因が森林破壊や野生動物の取引などにあるということを、みなさんと共有できたと思いますが、それでは、どうすればいいのか・・・。
先月、WWFジャパンが発表した「人と動物、生態系の健康はひとつ〜ワンヘルス共同宣言」の中にそれは示されています。ここで「ワンヘルス共同宣言」について詳しく教えてください。
「ワンヘルスは人と動物と生態系の健康をひとつと考えますよ、というお話をしました。実際に人の健康を守るのはお医者さん、動物の健康を守るのは獣医師さんだったりするわけですけれども、そういう人たちと、生態系を守るような環境保全団体が一緒にこのワンヘルスに取り組んでいこうという思いで、このワンヘルス共同宣言というのを作らせていただきました。
その宣言の中では、ワンヘルスの3つの要素をそれぞれ専門分野の問題だけに取り組むんじゃなくて、他の分野との重なりとか、課題といったものを一緒に、視野を広げて考えていきましょうというものになっています」
●具体的にはどんなことに取り組んでいくんですか?
「これからどういうところに課題があって、どういう連携が必要なのかということを、みんなで話していこうというところなんです。
例を挙げると、WWFジャパンはいま、野生動物を捕獲してきて販売するようなことが、実は新興感染症の発生に影響しているということで、心配しているわけなんですけれども、日本には海外の生きた動物を輸入して販売するような、エキゾチックペット市場というのが存在しているんですね。
例えばカワウソとか、フクロウとか、トカゲとか、そういったものがエキゾチックペットと言われているんですけれども、こういったペットは、やっぱりブームによって、輸入される動物の種類とか取引は日々変わっていきます。
もちろん輸入する上で、本当にその動物が安全なものなのか、公衆衛生上問題ないのかということを法律で厳しく定めているわけですけれども、この輸入規制については、長年見直しがされていないような感じです。
なのでこういった規制についても、私たち環境団体はペットブームや取引状況に関する、持っている知見を情報提供する。で、感染症の専門家とか、獣医の方々には逆に感染症のリスクの点から情報をいただいて、それぞれが取るべき対策とか、課題を共有すれば、適切な規制とか施策が作れるんじゃないかなと思っています」
●いま、新型コロナウイルスに効果のあるワクチンや薬の開発も急務とされていますけれども、開発とか製造には莫大な費用がかかりますよね。一方で新興感染症の予防には、それほど費用はかからないということなんですけど、それは本当なんでしょうか?
「昨年秋に発表された科学レポートによると、パンデミックによって被る被害額の100分の1で予防できると推計されています。生態系の健康が新しい感染症の発生にものすごく関係しているので、やはり私たちは予防のところ、生態系保全っていうものに力を入れていく。で、そのコストは実はワクチンよりも削減可能じゃないかと考えられています」
修復できるのは人間しかいない

※新型コロナウイルスの猛威によって、いま世界は大変な状況になっていますが、その原因は私たちにあるんですね。
「そうですね。新興感染症、新しい感染症の発生っていうのは過去50年ですごく急増しています。残念ながら私たちの、人間の活動の影響を受けて、生態系の損失も同時に進んでいる。つまり私たちの環境への負荷が、地球にものすごく大きな影響を与えていると考えられます」
●人間の活動がそんなに大きく関係しているんですね。壊してしまった自然とか環境を修復できるのは、また人間しかいないですよね?
「そうですね。感染症のパンデミックは、自然破壊とか、あとは(野生生物の)取引とか、人の手で行なわれた行為によって引き起こされているのであれば、やっぱりその危機も必ず人の手で防ぐことができると私は考えています。
ですから人と動物の健康に配慮して、持続可能な共生社会っていうんですかね、そういうものの実現に向けて、いま一度、自然とか野生動物との付き合い方を見直していくことが重要じゃないかなっていう風に考えています」
●本当にそういう意味ではワンヘルスっていう考え方をみんなで共有して、その理念のもとに行動していくっていうのが大切になってくるんですね。
「はい、新型コロナウイルスも発生源が海外であったことから、ウイルスの発生がその国の問題であると、そういう風に感じている人もいるかもしれません。
でも私たち日本人が森林破壊によって得られた木材製品を使っていたり、アジアの不適切な市場で販売されている動物が、ペットとして日本に輸入されている可能性というのは十分にあります。自分たちの消費、生活というものが、野生生物の生息地の感染症リスクを高めているかもしれないんですね。
環境に配慮した製品を選んだり、むやみに野生生物を欲しがらないといったライフスタイルの見直しは海外の生き物を守る、そして自分たちの健康を守ることに繋がっているということを認識していただきたいと思っています」
INFORMATION

「人と動物、生態系の健康はひとつ〜ワンヘルス」
新興感染症の発生とパンデミックを防ぐために、まずは「ワンヘルス」という考え方を共有しましょう。そして次のステップはライフスタイルを見直すこと。買い物をする時、環境に配慮した製品を選ぶだけでも人や動物、そして生態系の健康につながるということを意識しておきたいと思います。
「ワンヘルス」について、詳しくはぜひWWFジャパンのオフィシャルサイトをご覧ください。この番組のホームページにリンクをはっておきます。
◎WWFジャパンのHP:https://www.wwf.or.jp/tags_k_829/
2021/2/21 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. EMERGENCY ON PLANET EARTH / JAMIROQUAI
M2. ONE / U2
M3. WHERE IS THE LOVE? / THE BLACK EYED PEAS
M4. WHAT A WONDERFUL WORLD / LOUIS ARMSTRONG
M5. SAVE OUR SHIP / 松任谷由実
M6. FRAGILE / STING
M7. (JUST LIKE) STARTING OVER / JOHN LENNON
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2021/2/14 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、環境活動家の「露木志奈(つゆき・しいな)」さんです。
露木さんは2001年生まれ、横浜市出身。通っていた幼稚園の影響もあって、幼い頃から自然が大好き。中学生の頃は英語が苦手だったそうですが、英語を話せるようになりたいという本人の希望から、インドネシアのバリ島にあるインターナショナル・スクール「グリーンスクール」に単身留学。
2018年にはポーランドで開催された気候変動に関する国際会議COP(コップ)に「グリーンスクール」の仲間たちと参加。帰国後は慶應大学・環境情報部に進学。現在は休学し、環境活動家として活躍されています。
きょうはそんな露木さんに活動への熱い想いや、彼女が通っていた世界最先端のエコスクールといわれているバリ島の「グリーンスクール」のお話などうかがいます。
☆写真提供:露木志奈

大事なのは、ひとりでも行動すること
※去年の11月から始めた講演活動は、全国の小中高、時には大学に招かれて、主に気候変動について講演しているそうですが・・・ほかにはどんなお話をするんですか?
「もちろんマイクロプラスチックって言われる、海に流れてしまっているプラスチックが波とか、太陽の熱とかによって分解されて、目に見えないくらいまでの小さなプラスチックになっているってお話も、もちろんさせてもらっているんです。
あとは自分がインドネシアのボルネオ島にある熱帯雨林に行ったことがあって、そこって(アブラヤシから採れる)パームオイルって言われる、世の中で結構何にでも使われているような植物油があるんですけど、(そのアブラヤシを植えるために)伐採されている森を実際に見て、自分で植林をしに行ったりとかっていうのがあったので、自分にしか話せない内容っていうのを届けています」
●熱帯雨林などのそういった現場をご覧になって、具体的にどんなことを学生さんたちに伝えていらっしゃるんですか?
「熱帯雨林については、自分が直接行ったことがあるので、まず普通の植物と熱帯雨林の違いについてお話しさせてもらっています。
その上で日々、自分たちが消費しているものの中に、その原材料に(パームオイルが)使われているっていうこと、どういうものに使われているのかっていう説明をします。で、買う時に後ろの(ラベルに書かれている)材料を見て、無意識な選択じゃなくて、意識した選択っていうのがとても重要になっていくっていうことを、具体的にお話しさせてもらっています」
●気候変動については、どこにいちばんポイント置いてお話しされているんですか?
「いちばんポイント置いているのは、自分たちが行動するっていうことがすごく大事っていうこと、最も重要なこと、ってお話ししています。
ひとりが行動するって、意味がないって思っちゃうことがすごくあるし、私も実際にそういう風に思っていた時もあるんですけど。でも、みんながそう思っているからこういう問題が解決していかない。誰かが解決してくれるってみんなが思っているから解決していかないなって思うので、ひとりひとりの日々のアクションがすごく大事っていうことを、最終的なメッセージとして伝えさせてもらっています」


同世代にメッセージを届けたい!
※講演を聴いた生徒さんや学生さんたちの反応はどんな感じですか?
「学校にもよるし、学年にもよるし、本当に人それぞれなんですけど。もちろん本当に人生が変わりましたっていう風に言ってくれる人もいるし、自分の将来と環境っていうのは同じこと、考えるっていうのは全く同じことだから。
今までは環境は環境、自分は自分っていう風に捉えていたけれども、そのふたつっていうのは全く同じことなんだって思ってくれる生徒さんもいらっしゃったりとか。
あと先生は、毎日その生徒さんと関わっている中で、私が講演させてもらったあとに、反応をやっぱり見てくださっているんですけれども、この前、静岡の方で講演させてもらった学校で、校長先生が“僕はこの学校で2年ぐらい勤務させてもらっているんですけど、あんなに生徒の目が輝いているのは初めて見ました!”って言ってくれて。
確かにその学校、講演が終わったあとに私の周りに(生徒さんが)30人ぐらい集まってきてくれて、ずっと質問してくれて、そのあともお母さんのアカウントを使ってインスタグラムから質問をさらにくれたりとか」
●へ〜! SNSなども活用しながらいろいろされているわけですね!
「そうですね。私は基本的にいちばん多いのはインスタグラムを通して発信はさせてもらっているんですけど、でもこっそりYouTubeとかもやっています」
●やはり学生さんたちにとっても、歳の近い方が話してくださるっていうのも大きいのでしょうね。
「そうですね。私と同世代の子たちにお話を届けたいって思ったのも、やっぱり同世代である自分が話すことによって、メッセージがより深く、強く伝わるかなって期待しているのが、いちばんの理由で、学生の方にお話をさせてもらっています」
グリーンスクールよりサバイバルだった幼稚園!?
※露木さんが環境活動家として活動するようになったのは、世界でいちばんエコなスクールといわれているインドネシア・バリ島にある「グリーンスクール」で学んだことがきっかけ。その学校では、環境のことなどを学べる授業がたくさんあったそうです。具体的に、どんなことを学んだんですか?


「授業は結構様々で、数学とか理科とか社会とかっていう、日本にもあるような教科も、もちろんあるんですけど、それとは別に面白い授業もたくさんあって。
例えば音楽を作るっていうDJのクラスがあったりとか、あとはチョコレート・メイキングっていって、毎日チョコレートを自分たちで作って、ただ作って食べるっていうだけだったら授業にならないので、どういう風にビジネスをするかを学ぶっていうことをやっていました。
あともうひとつ。グリーンスクールは幼稚園から高校まであるので、高校生の場合だと全部選択授業なんですね。大学みたいな感じで好きな授業を選べるんですけど、その中でもし好きじゃない授業があったりとかしたら、自分で授業を作ることもできるんです。
私の場合は高校1年生の時から自分で化粧品作りをやっていましたね。インデペンデント・スタディっていうんですけど、独立的に勉強するっていう授業を作る枠があって、そこで化粧品をずっと作っていました」
●本当にグリーンスクールって英語だけじゃなくていろんなこと学べるんですね。
「そうなんですよ」
●もともと子どもの頃から自然っていうものは近くにあったとか、お好きだったんですか?
「そうですね。今まで自然に触れることがなかった人がグリーンスクールに行って、急に環境に関心を持つってなかなかないと思うんですけど、私の場合は小さい時から、幼稚園の時もトトロ幼稚舎っていう磯子区杉田にある幼稚園に通っていました。その幼稚園もなかなかユニークで、お昼ご飯って普通、幼稚園って出してくれるじゃないですか。トトロ幼稚舎は飯盒でご飯を焚くんですよね、木を燃やして」
●えぇ!?
「それを幼稚園生がやって、あとは普通に包丁を持って料理とかしていました」
●そうなんですね〜。もうその頃からいろいろなものが芽生えていたわけですね。
「そうですね。卒業遠足とかも、箱根八里、30キロ歩くような幼稚園なんですよ」
●へぇ〜! そうだったんですね! じゃあグリーンスクールに特に抵抗というか、そういったものはなかったわけですね。
「そうですね。幼稚園の方がサバイバルだったなと思っています(笑)」
グリーンスクールで学んだ3つのこと

※世界最先端といわれているエコスクール「グリーンスクール」に通って、ご自身の中でいちばん変化したことってなんですか?
「これは結構よく聞かれることだったので、どういうこと学んだのかなって、やっぱり振り返らないと具体的に言語化って上手くできないじゃないですか。だからまとめたことがあって。
3つあるんですけど、ひとつ目が、まずは“人数分の答えがある”っていうこと。数学みたいに1+1=2みたいな、みんなが共通で同じ答えを持つっていうことは、世の中に出た時になかなかなくて、みんな人それぞれ意見とかも違うし。
それって育った環境だったりとか、話している言語とかによって、全く同じものを見ていても見方とかがそれぞれ違う。だから人数分の答えがあって、みんなそれぞれで合っているんだよっていうことを、グリーンスクールに行って学んだっていうのがひとつ。
ふたつ目が“ないものは自分で作る”っていうこと。私の妹が、2歳下の妹なんですけど、私が高校1年生で、妹が中学2年生の時に、お年頃だったっていうのもあって、市販の化粧品を買いに行ったんです。そこでナチュラルって書いてあるものを買ったんですね。
で、すごくワクワクしてお家に帰ってきて、その化粧品を試した時に、私の肌は何ともならなかったんですけど、妹の肌がものすごく荒れちゃって。その時に私は、あれ? でも化粧品にナチュラルって書いてあるじゃんって。商品の裏って原材料が書いてあるじゃないですか。その時にできることって原材料を見て、何が入っているのかって調べるぐらいだったので、最初はそれをやっていたんですけど。
でも調べていった時に、日本っていう国にナチュラルとかオーガニックとか、無添加って言われる言葉の定義がしっかりと定められてないから、マーケティング・ワードとして使われちゃう場合もあるんだなって。だからそういう言葉=100%安全じゃないんだなって思ったんですよ。
あとは動物実験のことだったり、日本のプラスチックのリサイクル率の話だったりを知っていく中で、妹のために信用して使える化粧品がないなと思って、そこから自分で作りました。だからないものは自分で作るっていうのはそこで学んだことです。
3つ目が“大人になるまで待たなくていい”ってこと。これは学校から学んだとか、先生から学んだっていうわけじゃなくて。
同い年の女の子でマラティっていう子がいるんですけど、そのマラティっていう女の子は今“バイバイ・プラスチックバッグ”っていう NPOを運営している子です。その子は普通にバリで育った女の子で、妹にイザベルっていう女の子がいる姉妹なんですね。
そのふたりは自分たちが育ったバリ島にゴミが溜まっていくのがすごく嫌だったから、最初はふたりでゴミ拾いをしていたみたいで。でもゴミ拾いってずっとやっていてもゴミはなくならないじゃないですか。ゴミが出る量を減らしていかないとゴミってやっぱりなくならないから、それに気づいたふたりは、とにかくゴミの中でもプラスチックバッグを減らしていきたくて。
結局署名を集めて、国の法律を変えていかなきゃこの問題は根本的に解決しないと思ったみたいで、最終的にそのふたりが法律を変えたんですね。
そのふたりが直接(“大人になるまで待たなくていい”と)言っていたっていうことではないけれども、行動で示してくれているっていうか。法律を変えるってすごく大きなことにも聞こえるし、普通だったら政治家がやるとか、大人になってからそういう関連の仕事をして、みたいなイメージあると思うんですけど、そんなの関係なくて、もし目の前に変えたいものあるんだったら、別にいつでもやっていいんだよっていうことを、それが可能なんだよっていうことを、行動で示してくれていて、私は“そういうことか!”って思いました」
人の心を動かすのは情熱!
※露木さんは2018年に「グリーンスクール」の仲間たちと気候変動に関する国際会議COPに参加した時に、スウェーデンの環境活動家「グレタ・トゥンベリ」さんの講演を聴いたそうです。彼女の存在にインスパイアされるし、刺激を受けるともおっしゃっていました

今後も環境活動家としての活動を続けていくと思うんですけど、学校で行なう講演で心掛けていることはありますか?
「情熱を伝える、情熱を持って話をするっていうことですかね。
やっぱりデータとか数字とかを伝えても、もちろんそれで危機感を持ってくれる人もいるけれども、話している人がどれぐらい本気でこの話をしていて、どれぐらい危機感を持っているのかって、やっぱり話し方だったりとか、情熱がどれぐらいその言葉に含まれているのかっていうことなんじゃないかなっていう風に思っていて。どの歳の人でもいちばん最後にやっぱり人の心を動かすのって、情熱なんじゃないかなって思っています」
●この番組を聴いてくださっている、特に10代から20代のリスナーさんにいちばん伝えたいことってどんなことですか?
「私は今まで、いろんな挑戦とか体験をさせてもらえるような環境にいたんですけど。でも、やっぱり学んだことって、今やりたいことを今その時にやるのがいいなってすごく思っています。
大学も普通だったら高校を卒業して行くっていうのがパターンで、みんなそのまま大学を卒業するっていうのが当たり前で、普通で、って思っているとは思うんですけど、私は大学よりも優先したいものがあったから、今は休学をして講演活動をしています。
必ずしもみんなと同じように行動とか考えとかを持たなくてもいいし、自分の考えとか何か今やりたいこととかがあるんだったら、それを大切にしていってほしいなって。必ず出来るので !」
INFORMATION
露木さんはインスタグラムやYouTubeでも定期的に発信しています。YouTubeではエシカル商品やハチドリ電力、あとビーガン料理なども紹介。ぜひチェックしてください。
◎露木志奈さんYouTube:https://www.youtube.com/channel/UCnpCdNkwmJSdFpxMkQWReqw
◎露木志奈さんインスタグラム:https://www.instagram.com/shiina.co/
露木さんにうちの学校にも来て欲しい、講演をやってほしいと思ったかたは、露木さんのオフィシャルサイトにアクセスして、「コンタクト」からお問い合わせください。
◎露木志奈さんHP:https://www.shiina.co/
2021/2/14 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. YOUNG HEARTS RUN FREE / CANDI STATON
M2. CHAIN REACTION / DIANA ROSS
M3. I’D LIKE TO TEACH THE WORLD TO SING / THE NEW SEEKERS
M4. CASE STUDY / THE FIVE CORNERS QUINTET
M5. あの街この街 / D.Wニコルズ
M6. CHANGE IN MIND, CHANGE OF HEART / CAROLE KING
M7. I NEED TO WAKE UP / MELISSA ETHERIDGE
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2021/2/7 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、アドベンチャー・ランナーの「北田雄夫(きただ・たかお)」さんです。
北田さんは1984年生まれ、大阪府堺市出身。幼少期から貧血持ちだったそうですが、中学から陸上部に入り、高校・大学と短距離で活躍。その後、就職し、一時は競技から離れますが、自分の可能性に挑戦したいという思いから、2014年、30歳のときにアドベンチャー・マラソンに参戦。会社をやめて競技に専念し、2017年に日本人として初めて、世界7大陸のアドベンチャー・マラソンを走破!
そして先頃、これまでの挑戦の記録を綴った本『地球のはしからはしまで走って考えたこと』を出されました。
きょうはそんな北田さんにどうしてそんなに厳しいマラソンに挑戦するのか、過酷なトレーニング、そして現在チャレンジ中の世界4大極地レースのお話などうかがいます。
☆写真提供:北田雄夫

ビビッとゾクゾク!?
※北田さん、この世界7大陸のアドベンチャー・マラソンとはどんなマラソンなんですか?
「地球の大自然の中を、食料や寝袋やサバイバル道具を背負って、1人で何百キロも走ると、そういうスポーツが世の中にあります。そういうマラソン競技になりますね」
●大自然の、どんな場所を走るんですか?
「暑い砂漠だったり、寒い南極だったり、衛生環境の悪いジャングルだったり、本当に厳しい自然環境が舞台になっています。そんな中で、コースにやっぱり道がないので、砂漠とか。大会によっては、目印を付けている大会もあれば、はたまた全く目印がない中で、自分のGPSだけを頼りに行くとか、そういったコースになっています」

●睡眠とか食事はどうされるんですか?
「レースによってなんですけど、ノンストップでずっと走り続けるレースであれば、睡眠時間も競争となるので、ほぼ寝ずに進むことになります。食事も基本的には自分で背負っていくんですけど、あまりにも距離が長いレースだと、途中にあらかじめ荷物をおけるポイントがルール上、設定されています。そこに置いていた食料を途中で補給しながら走り進んでいくという感じですね」
●へ〜! どんな方が参加されるんですか?
「なかなかの強者ばかりなんですけど(笑)、まぁ普通じゃない人は多いかもしれないですね」
●世界からだいたい何人ぐらいの方が参加されるんですか?
「それも大会によってなんですけど、多いと1000人、少ないと10人とか、本当に規模が様々ですね」
●参加条件みたいなものっていうのは何かあるんですか?
「これも大会によってなんですけど、次に挑戦を考えているヒマラヤの850キロっていうレースでは、 標高が高いところを走りますので、これまで4800メートル以上の標高の活動経験が必要とか、超長距離レースの実績があるとかですね。レースによって決められていたり決められてなかったりということになります」
●日本人は大体いつも北田さんだけですか?
「いや、(日本人も)参加されていることも多いんですけども、僕がいつも参加、挑戦したりしているのが、日本人がまだ挑戦すらできていない大会が多いので、そういう時は僕ひとりってことが多いです」
●そもそもどうしてこんな過酷なアドベンチャー・マラソンに挑戦しようって思ったんですか?
「誰もやっていないことをやりたかったっていうのがいちばんですね」
●でも、いろんな選択肢がある中で、どうしてこのアドベンチャー・マラソンを選んだんですか?(笑)
「もうビビっとゾクゾクきてしまいまして。この厳しさも、ちょっと理解できないところも含めてなんですけど、自分の体力と心と知識と人生と、全てを捧げてチャレンジできるんじゃないか、というところに興味を抱きましたね」

これが自分の人生だ!
※とても厳しい自然環境に身を置くことで、何か見えてくるものがあるんでしょうか?
「やっぱりありますね。毎回日本にはないような、想像を超えた大自然で、限界までチャレンジしますので、自分の可能性に出会うこともありますし、やっぱりゴールしたあとの達成感とか喜びっていうのは、味わったことがない、言葉にできないほどの大きいものもありますね。すごく自分にとって、やりがいであったり、喜びは大きいですね」
●走っている時はどんなことを考えているんですか?
「いろいろ考えるんですけど、今どう乗り越えるかって考えていることは多いですね。例えば、暑い砂漠を走ると熱中症気味になって、脱水症状になって、でもチェックポイントまであと20キロあると。じゃあ持っている水はどんだけあるから、これをどういう風に使ったらいいんだろうとか。
足の疲労は痛みとか出てきて、このペースでいけるのか、この先を越えるにはどう越えようかとかですね。いろいろ自分の体とメンタルとレース条件と、いろいろ踏まえた上で、今何を考えてどうすべきかって、常々考えていることは多いですね」
●もうやめたいって思ったことはないですか?
「止まりたいとかはめちゃくちゃありますね。もう止まりたい休みたいとか、何でやっているんだろうとか思うことは多いんですけど、やめようと思ったことはないですね」
●何でですか? 毎回きついなって思って、でもまたやりたいって思うのって。そのモチベーションというか、それはどういった気持ちから出てくるものなんですか?
「終わったあと、もっとできるなっていうのがいつもあるんですね。もう1回やったらもっと上手くできるなとか、速く走れるなっていうのが本当毎回あってですね。まだ先に行けるんじゃないか、もっとできるんじゃないかっていうのは常にあるので、それを目指していきたいなっていう思いはありますね」
●忘れられない光景とかってありますか?
「大体レースってひとりで孤独で走っているので、夜が長かったりするんですね、12時間とかあったりして。
アラスカを走っていた時に、孤独で寒くて辛くて、でもそれから一晩越えて、朝日が登った時に、その朝日が本当に眩しくて、輝いていて、生きる力が湧いてきてですね。夜、孤独で寂しかったところから生き延びたっていうのと、何かいろんな感情が合わさって、その光景っていうのはすごく忘れられないものになっていますね」
●過酷なレースをこなしていく中で、ご自身の中で変化っていうのはありますか?
「そうですね、たくさんありますね。いちばんはこれが自分の人生なんだ、っていうことが思えるようにはなりましたね。
30歳までの会社員の頃は、まぁ充実した日々だったんですけれども、これが自分の生き方だ! 人生だ! っていうことを言えなくてですね。今はそれだけの想いだったり、時間だったりを注いでいて、挑戦もしているので、何か自身の中で、自分の道を歩んでいる、生きているって思えることは大きいですね」

砂漠の次は極寒のアラスカ!?
※北田さんは2018年から「世界4大極地の最高峰レース」に挑戦されていますが、これはどんなレースなんですか?
「自分なりに決めたものなんですけれども、地球上で人間が走れる4つの極地があると。それが暑い砂漠、 寒冷地、衛生環境の悪いジャングル、そして標高の高い山と。その4つの環境で、いちばん難易度が高いであろうレースに全部行くというのが、僕の掲げている4大極地の最高峰レースになります」

●最近でいうと、どんなレースに出場したんですか?
「2019年の秋に行ったモーリタニアのサハラ砂漠で1000キロ走るというレースでした」
●砂漠を1000キロ!!!
「はい(笑)」
●どんな世界なんですか(笑)
「走っても走っても、もう地平線で砂漠が終わらないんですよ。地球は広かったです」
●でもこれも無事に走破されたんですよね?
「そうですね。幸い無事完走、6位でゴールとなりました」
●次回がアラスカ? ですか?
「そうですね。2月末からスタートとなって、10日間で560キロ、完走を目指す、ノンストップで進むというレースになります」
●これはどんなレースになるんですか?
「冬の寒いレースでして、冷えるとマイナス30〜40度まで落ちると。なのでかなり厳しくて、汗をかくと全部凍ってしまって、凍ると全て解凍ができないので、難易度がすごく高くてですね。
装備が本当にエベレストを登るような防寒具を全て持っていかないといけないので、ソリを引きながらになりますね。とてもリュックじゃ背負えないので。そこに食料とかお湯も入れて、万が一の時には雪をお湯に溶かすようなバーナーとか、いろんなサバイバル道具を積んだ、おそらく15キロとか20キロの(重さの)ソリを引きながら、毎日雪の上を進み続けると」
●へ〜! 頑張ってください!
「はい!」

55時間、眠らずに!? マイナス20度の冷凍庫!?
※2月末から開催される予定の、アラスカのレースに向けて、トレーニングの最中だと聞いたんですけど、どんなトレーニングをしているんですか?
「例えばアラスカに向けてで言いますと、ノンストップで10日間進むっていうことで、睡眠時間がいちばんもったいないなと。なので、睡眠ゼロでいけばいいんじゃないかと思ってネットを叩くんですけど、出てこないんですよね〜。これだけ情報が溢れているのに、人間どれまで寝ずにいけるかっていうのが。じゃあ自分でやるしかないと思って、この前55時間寝ずに山を走っていましたね」
●えっ? それはどんな山を?
「兵庫県に六甲山脈っていうのがあるんですけど、そこをずっと55時間、往復しましたね」
●55時間!? 全く寝ずにですか?
「そうです」
●できるものなんですか? そういうのって。
「結構、幻覚もそこまで見えず、できました。なので、とりあえず55時間は動けるなっていうのがそのチャレンジで分かりましたね。あとやっぱりやる中で、どこまでいったら自分の意識が飛んで、手足の感覚を失うのかっていう限界値が分かっていないと、本番ではそれ以上の条件になるので、それを試すためにっていうので、それをやりました。
寒さでいうと、本番がマイナス30〜40度になるっていうことで、前回同じアラスカに行った時に、マイナス30度だったんですけど、凍っていない川があったんですよ。そこにちょっと足をはめてみたら、瞬く間に足が凍っちゃって、危うく凍傷になりかけたんですけど。
次回もあるだろうっていうことで、もし自分が下半身ずぶ濡れになったら、どうやったら復活、回復できるのか、体温を取り戻せるのか、その時に考えるべき、注意することをいろいろ見つけようと思って、それでマイナス20度の冷凍庫に入って下半身ずぶ濡れにして、そこから10分後に着替えを、っていうのをやってみてですね。やっぱりむちゃくちゃ寒かったんですけど、10分間はとりあえずマイナス20度に耐えられてですね。着替える順番がすごく重要だなとか、手間取ったら凍傷の確率が高くなるなとかですね。
なのでソリの、何センチ単位で自分がどこの荷物に何を入れているかっていうのを明確に把握しておいて、着替える順番もどんだけ疲労していても、どんだけ意識がなくても、無意識ぐらいに順序よくいけるように認識、把握しておくとか、そういうことが大事だなっていうのが改めて分かりました」
●北田さんのアドベンチャー・ランナーとしての挑戦は今後も続いていくんですね。
「そうですね。今、僕の中では第2章です。第1章の、7大陸の走破が2017年に終わりまして、今第2章の、4大極地を行くということでやっています。2022年ぐらいまでに達成できたらなと。それが終われば第3章、第4章と挑戦したいなと思っています」
●このような過酷なレースに出場して得るもの、そして出場することで伝えたいことを、改めて教えてください。
「チャレンジするのは面白いっていうのが、世の中に広まればいいなとは思いますね。挑戦って、いろいろ考えることもあったり、難しいんですけど、成功とか失敗ではなくて、チャレンジすること自体が面白いんだ! っていう風に、まぁ僕自身が経験させてもらってですね。
やっぱり失敗したら辛かったり人の目も気になったり、落ち込むこともあるんですけど、でもそこには絶対成長があってですね、新しく出会える人もいたり。なので、本当に挑戦することで僕の喜びは膨れていたので、そういう何か、面白いなっていうのは伝えられたらなと思います 」
INFORMATION
『地球のはしからはしまで走って考えたこと』
アドベンチャー・マラソンに挑戦するようになったいきさつから、日本人として初めて走破した世界7大陸アドベンチャー・マラソンのエピソードなど、挑戦と挫折と成長の日々が綴られています。胸が熱くなる冒険物語。チャレンジする姿勢に勇気をもらえる一冊です。ぜひ読んでください。集英社から絶賛発売中です。
◎集英社HP:
https://books.shueisha.co.jp/items/contents.html?isbn=978-4-08-788046-5
「旅ラン」「アドベンチャー・クラブ」情報
北田さんは国内を旅するように走る「旅ラン」シリーズをYouTubeで公開。奥様とのハネムーンも400キロの「旅ラン」だったそうですよ。

また、「アドベンチャー・クラブ」というコミュニティを運営。このクラブでは北田さんのレースを、より身近に楽しみ、そして一緒に挑戦してくださる会員を募集中です。詳しくは北田さんのオフィシャルサイトをご覧ください。
◎北田雄夫さんHP:https://takaokitada.net/
2021/2/7 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. BORN TO RUN / BRUCE SPRINGSTEEN
M2. I’LL TRY SOMETHING NEW / A TASTE OF HONEY
M3. SUNRISE / NORAH JONES
M4. Quiet Light / ハナレグミ
M5. アドベンチャー / D.Wニコルズ
M6. AFRICA / TOTO
M7. BORN TO TRY / DELTA GOODREM
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」