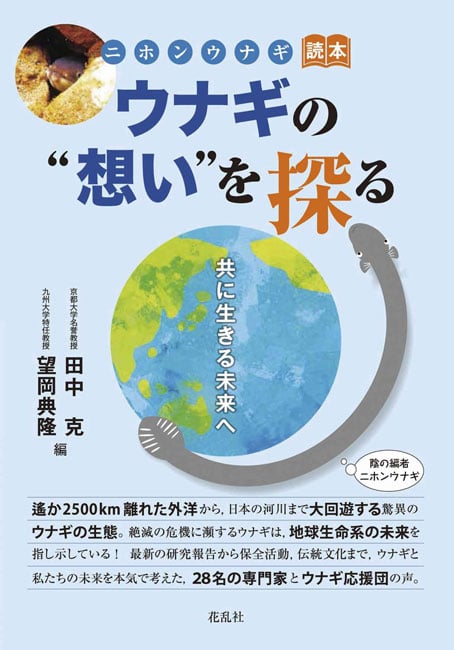2023/10/29 UP!
◎深澤 遊(東北大学大学院の准教授)
『「枯木こそ山のにぎわい」〜枯木が育む生き物と森林生態系』(2023.10.29)
◎新宅広二(動物行動学者)
『あなたのお悩みに「動物」を処方!?心がちょっと軽くなる“動物行動学的”読むお薬』(2023.10.22)
◎笠原里恵(信州大学の助教)
『この秋、可愛くてワイルドな「カワセミ」を観察しよう~水辺のある公園や小さな河川にきっといる!?』(2023.10.15)
◎奥野克巳(立教大学・異文化コミュニケーション学部の教授/人類学者)
『「人類学」入門~ボルネオ島の狩猟民プナンから「人間」が見えてくる!?』(2023.10.08)
◎森 昭彦(サイエンス・ジャーナリスト/ガーデナー)
『「雑草」を知れば知るほど、「人生」は豊かになる!?』(2023.10.01)
2023/10/29 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、東北大学大学院の准教授「深澤 遊(ふかさわ・ゆう)」さんです。
深澤さんは1979年、山梨県生まれ。信州大学 農学部卒業、京都大学大学院 農学研究科修了。そして、研究職から、森林組合やトトロのふるさと財団の職員を経て、現在は東北大学大学院の準教授として活躍されています。
子供の頃の深澤さんはコケが大好きな少年で、小学校3年生の夏休みの自由研究が「リアルコケ図鑑」。その後、やはり小学生の頃に、国立科学博物館の子供向け講座でアメーバの仲間「変形菌」に出会い、その時もらった飼育セットで変形菌を育てたり、自分で見つけた変形菌をスケッチしたりと、夢中になっていたそうです。
現在、深澤さんは、森林の生態に関する研究をされていて、特に枯木が生き物や環境に対してどんな役割を果たしているのかを調査・研究されています。そして先頃『枯木ワンダーランド』という本を出されました。
きょうはそんな深澤さんに枯木を舞台に繰り広げられる、生き物たちの驚くべき営みや、枯木が人間にもたらす恩恵のお話などうかがいます。
☆写真協力:深澤 遊

枯木のスペシャリスト
※まずは、深澤さんのご専門を教えてください。
「森林の生態学を研究しています。生態学っていうのは生物がどのように暮らしているかとか、環境やほかの生物と、どのような関係性を持って暮らしているのかを調べる学問分野です。
その中で森林生態学は森にどのような生物がいて、それらによって森がどのように成り立っているのかを調べています。僕はその中でも特に木が枯れたあとの枯木ですとか、そこに棲んでいる菌類など、微生物の生態に注目して研究しています」
●具体的には、どんな研究をされているんですか?
「具体的には、森の枯木の中にどんな種類の菌類がいて、それによって枯木がどのように分解されていくかを調べています。最初は同じ枯木でも分解に関わる菌類の種類によって、全く違うように腐朽していくんですよ。それが森林の炭素貯留量に影響する可能性ですとか、森林の生物多様性に影響する可能性のようなものを探っています」
●どんな菌類なんですか?
「枯木に生えているシイタケとか、そういったキノコを想像していただければいいと思うんです。キノコは、要は花みたいなもので、枯木の表面に菌が花を咲かせたような状態なんですよね。
その菌の本体は枯木の中の菌糸。カビと同じような形で枯木の中にいて、それが本体なわけですね。その本体の菌糸が、枯木を分解して栄養にして生活しているんですけども、枯木の中でどういう菌がいて、どういうふうに菌が枯木を分解しているのかっていうようなことを研究しています。
枯木の中を削ってみると、枯木の断面に黒い線が見えるんですよね。その黒い線は枯木の中にいる菌類のコロニーの境界線なんです。それを見ると本当にモザイク模様みたいになっていて、枯木の中でいろんな菌類のコロニーがあって、それが空間の獲得競争をして、陣地争いみたいな状態になっているんですね。そういうのを見ると面白いですね」

(編集部注:深澤さんは大学の2年生まで山岳部で活動、大学院生の時にはアメリカのカリフォルニア州にあるヨセミテ国立公園に行き、クライミングを楽しんだこともあるとか。研究者になって調査のためにひとりで山に出かけることもあるので、やはり、安全を確保する山の経験は活きているそうです)
生き物で賑わう枯木!?

※ここからは深澤さんが先頃出された本『枯木ワンダーランド』から、番組で気になったワードや項目についてお話をうかがっていきます。
前書きに「枯木も山のにぎわい」ではなくて「枯木こそ山のにぎわい」と表現されています。枯れてしまった木が「にぎわう」とは、どういうことなのか、教えてください。
「これは枯木に棲んでいる生き物が、非常に多様だっていうことですね。森に虫を探しに行って何も見つけられなかったら、多分枯木をひっくり返せば、大抵何かいますし、例えば、クワガタが好きな人だったら、枯木の中にクワガタの幼虫が棲んでいることをよく知っていると思います。
それだけではなくて、腐った倒木の上にはよく苔や木の芽生えも生えていますし、目を近づけてみるといろいろなキノコが生えていたり、小さい虫が歩き回っていたり、何かを食べていたりします。

さらに、先ほど言いましたようにノコギリで切って中を覗いてみると、菌類のコロニーの境界線が見えたりしますので、それらを見ているだけでも面白いんですよ。さらに培地の上に培養してどんな菌類なのか調べたりですとか、枯木の成分の分析をして、どんな物質が残っているかを調べると、枯木の中の生き物の営みがわかってきて、さらに面白いです。
そういうことが見えてくると、枯木は多種多様な生き物の営みでにぎわっているということがよくわかると思います」
●枯木ってものすごく情報量があるんですね?
「そうですね」
●2015年からは森の中にあるご自宅の庭で、枯れたコナラをそのままにしておいたり、伐採した同じくコナラなどの丸太を庭に放置してあるということですけれども、お庭が研究のためのフィールドになっているっていうことですか?
「はい、そうです。庭はやっぱりいちばん近いフィールドなので、大事にしています。生態学で新しい発見をするのに、やっぱりどれだけ生き物を観察できるかっていうのが肝になることが多いんですね。遠くのフィールドと違って、庭はいつでも観察できるので、誰も知らない発見ができるかもしれません」

●今、特に注目していることはあります?
「実際、本にも書いたんですけれども、ある冬の朝、リスが庭にやってきて枯木の樹皮を剥いて、その下の菌を食べることを初めて発見したんですよ。さらにその樹皮の下に菌が生えていて、その菌に独特な昆虫がやってくることも庭の調査からわかりました」
●ものすごく近いフィールドでいいですね、研究しがいがあって!
「そうです。自分の(部屋の)椅子の上から全部見えるので・・・」
お菓子の家に棲む!?
※枯木は、分解するまでには長い時間がかかると思いますが、年ごとに、季節ごとに、枯木を利用する生き物も変化していくってことですか?
「そうですね。やっぱり分解していくので時間に伴って、分解していく時の成分だとか、いろいろなものが変化していくので、そこに棲んでいる生き物もだんだん移り変わっていきます」
●どういう生き物が、どうやって変化していくのかを教えていただけますか?
「はい、いちばん重要になるのはやっぱり水分で、木が生きている時は、ある程度水分を含んでいて、これによって菌類の侵入を防いでいるっていう側面があるんですけれども、木が枯れると一旦乾燥していきます。この乾燥によって菌類が成長して、木を分解できるようになるんですね。
最初は、木が生きていた時から内部に潜んでいた菌類がいて、”内生菌”っていうんですけれども、これが成長を開始します。 ただこの菌はあまり木材の分解力はなくて、糖分なんかを食べて生きているんですよ。この糖分がなくなるとすぐにいなくなっちゃうんです。
そのあとに木材を分解できるような種類の菌類が胞子とかで定着してきて、枯木を分解していくと、だんだん木材がボロボロになっていきますよね。そうすると水が染み込みやすくなって、含水率がだんだん上がってきます。
そうなると表面にだんだん苔が生えてきたりだとか、乾燥した木材が好きなカミキリムシやゾウムシの幼虫から、湿った材木が好きなクワガタムシの幼虫に、内部の昆虫種も移り変わってきたりします。この頃になると、倒木の表面に木の芽生えが生えてきたりして、次の世代の森が倒木の上で育っていくわけです」

●生き物たちは枯木から、どんな恩恵を受けているんですか?
「枯木に棲んでいる生き物にとって多くの場合、枯木は住処であると同時に食べ物でもあります。イメージとしてはお菓子の家に棲んでいるようなものなのかもしれません」
●枯木って本当にただの燃料みたいなイメージもありましたけれども、そうではないわけですね。枯木には、いろんな生き物に必要な養分があるっていうことですか?
「そうですね。枯木は重さの半分程度が炭素でできています。炭素はすべての生き物が体を作る上でいちばん重要な物質で、あらゆる生き物はどこかから炭素をもらってくる必要があるわけですね。
植物は光合成によって空気中の二酸化炭素から炭素をもらってきていて、ほかの生き物は植物を食べることで、あるいはほかの動物を食べることで炭素を得ています。枯木を食べる生き物は、枯木から炭素を得ているっていうわけです」
枯木は燃料!? バイオマス発電の是非
※本の第2部に「枯木が世界を救う」という見出しがついていて、その中に「枯木が消える」というチャプターがあります。これは森から、枯木が消えてしまうってことですか?
「はい、そういうことです」
●これは日本の話ですか?
「日本では現在まだ、それほど消えていないと思います。ただ心配なのは、枯木などのバイオマスを燃やして発電するバイオマス発電が、とても推奨され始めていることです。
木材は確かに木が成長すれば(発電は)できるので、再生可能エネルギーなんですけれども、燃焼で失われるスピードに対して、木が成長するスピードはあまりにも遅いので、とてもではないですが、現在の人口が必要としているエネルギー量をバイオマス発電で賄って回していくことができるとは思えません。
なので、バイオマス発電が広く行なわれるようになったら、山から枯木はあっという間になくなってしまうんじゃないかと思います」
●あっという間になくなってしまったら、生物多様性がそれこそ損なわれてしまうと思うんですけれども、ほかにはどんな影響が考えられますか?
「やっぱり枯木が燃料として使われると、枯木の中に保存されていた炭素が二酸化炭素として大気中に放出されますので、温暖化が進行するんじゃないかと思います。バイオマスを発電に使うと、化石燃料を使った場合の2〜3倍の炭素を放出する可能性もあるそうです」

●改めてなんですけど、木は光合成を行なう過程で、地球温暖化の主な原因になっている二酸化炭素を吸収してくれているんですよね。で、木はその二酸化炭素を自分の中に溜めているということですよね?
「はい、そうですね。それで体を作っているので」
●その木が枯れてしまったら、その二酸化炭素は・・・?
「分解されたり燃やされたりすると、二酸化炭素として放出されるってことになります」
(編集部注:枯木をバイオマス発電などに広く利用するようになると、森から枯木がなくなってしまうというお話がありましたが、深澤さんは森の中にある枯木を、単なる燃料として見ることに警鐘を鳴らしています。詳しくはぜひ、深澤さんの本『枯木ワンダーランド』をチェックしてください)
枯木の下もワンダーランド
※枯木を観察していて、どんなときにいちばんワクワクしますか?
「やっぱりまだ見たことのない生き物を見つけた時ですかね。初めて見る変形菌とか、キノコ、苔、虫、ナメクジ、カタツムリ、ヘビ、サンショウウオとか、いろいろな生き物を枯木で観察できますので・・・。あとは、ものすごい巨木の枯木を見た時とかは、目の前に保存されている時間の長さにくらくらしたりします」
●都市公園には枯木がそのままにしてあったりとか、丸太が放置されているっていうことはなかなかないと思うんですけれど、もし見かける機会があったら、どんなところを見ると面白いですか?
「もし許されるのであれば、樹皮を少し剥がしてみたりですとか、樹皮の裏側にいろいろな生き物が隠れていたりしますし・・・・。あと丸太、枯木を転がして、その下に隠れている生き物を探してみると面白いと思います。
実際、僕も枯木を調査しながら、いろいろな国で枯木の下を見てみるってことをやっているんですけれども、国とか場所によって、本当に枯木の下に潜んでいる生き物が全然違っていて面白いですよね。
日本だとミミズがいたり、シロアリとかアリがいたり、時々ヘビがいたりとかすることが多いです。アメリカの東海岸では、枯木の下にサンショウウオがいっぱいいたりだとか、ヨーロッパではナメクジが大量にいたりしましたね」
●国によって全然違うんですね! では最後に、今後の研究で明らかにしたいことを教えてください。
「研究テーマは、マクロなものからミクロなものまで、いろいろあるんですけれども、マクロなテーマとしては、枯木を分解する菌類や、その分解機能が世界的に見て、どのような分布をしているのかを明らかにしたいと考えています。これは地球の環境が変わると、菌類の種や枯木の分解がどのように変わるかといった予測にもつながると思います。
ミクロなテーマとしては、個々の菌類が環境に応答しているとしたら、その生理的なメカニズムですとか、これはちょっと違う話になってしまうんですけれども、菌類の菌糸が持つ機能と知能とか、そういったものについて明らかにしていきたいと思っています」

INFORMATION
『枯木ワンダーランド~枯死木がつなぐ虫・菌・動物と森林生態系』
深澤さんの本をぜひ読んでください。枯木が分解の過程で、いかに生物多様性に貢献しているのか、まさに「枯木こそ、山の賑わい」というのがよくわかりますよ。そして、森から枯木をなくすことで、どんな影響が出てくるのか、さらに枯木が地球環境の保全に役立っている仕組みなど、興味深い内容になっています。深澤さんが描いた精密なスケッチも必見! 築地書館から絶賛発売中です。
詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎築地書館:http://www.tsukiji-shokan.co.jp/mokuroku/ISBN978-4-8067-1653-2.html
深澤さんのサイトもぜひ見てください。
2023/10/29 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. NORWEGIAN WOOD / THE BEATLES
M2. TREES / TWENTY ONE PILOTS
M3. FIELDS OF GOLD / STING
M4. AMAZING GRACE / SARAH BRIGHTMAN
M5. エイリアンズ / キリンジ
M6. A HARD RAIN’S A-GONNA FALL / BOB DYLAN
M7. I STILL HAVEN’T FOUND WHAT I’M LOOKING FOR / U2
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2023/10/22 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、動物行動学者の「新宅広二(しんたく・こうじ)」さんです。
新宅さんは1968年生まれ。上智大学大学院、京都大学霊長類研究所を経て、上野動物園、多摩動物公園に勤務。その後、国内外のフィールドワークを含め、400種以上の野生動物の生態や飼育方法を修得。専門は動物行動学と教育工学。
そんなキャリアを活かし、国内外のネイチャー・ドキュメンタリーや科学番組、そしてきょう解説していただく動物フィギュア「アニア」などの監修も担当。さらに国内外の動物園や水族館、博物館のプロデュース、また、大学や専門学校で教鞭をとるほか、これまでに『しくじり動物大集合』や『危険生物最恐図鑑』など、生き物に関するユニークな本を数多く出されています。
そんな新宅さんの新しい本が『あなたにゴリラを処方します。悩みがちょっと軽くなる動物の読み薬』。
この本は、私たち人間が抱えているお悩みに対して、「ところで、動物たちはどうしているんだろう」という観点から、読者から寄せられたお悩みに、動物を処方するという設定で動物の生態や行動を紹介。くすっと笑えて、少し心が軽くなる、読むお薬になっているんです。
そこできょうは、私たち人間が抱えているお悩みを、動物行動学の視点で分析していただくほか、新宅さんが監修されている動物フィギュア「アニア」についても解説していただきます。
応募方法はこちら!

寝相のお悩みにパンダ!?
●この本は7つのチャプターに分かれています。まずは、チャプター1「小さな悩み」から「寝相が悪いんですけど・・・」という33歳の女性のお悩みに、ジャイアントパンダが処方されています。 これはどういうことなんでしょうか?
「私の中でいちばん寝相の悪い動物は何かなって考えた時に、ジャイアントパンダだったんですね。 私は上野動物園にもいましたので、やっぱりあの寝相や寝姿がヴァリエーションが多くて、非常に面白いんですよね」
●どんな寝方をするんですか?
「普通の動物にとっては、お腹は骨がない部分で、いちばん急所なんですよね。寝るっていうことは、いちばん無用心になっちゃうので、お腹をさらすっていうことはないんですよね。いちばん大事な部分を下にして、丸くなって寝るのが大体の動物ですけど、パンダは文字通り、大の字になってグーグー寝ますから」
●お腹、全開!
「もうお腹を全開にしちゃって寝ますからね~。寝姿の悩みはパンダに聞いてもらったほうが・・・(笑)、パンダがなんと言っても、寝姿の最高の進化を遂げた動物なんですよね」
●すごいですね! 安全性は大丈夫なんですか?
「これは、実は生態とも関係しているんですね。パンダは(標高)4000メートル以上に棲む、すごく高山の動物なんですよね。だから天敵がいないので、用心する気持ちが、長い進化の過程でなくなっちゃったんです。なので、動物園で飼うようになっても不用心な姿で寝るようになっているんですよ。野生の緊張感の高い生態で暮らしているような動物たちは、なかなかお腹丸出しで寝るってことはないです」
●続きまして、チャプター2「容姿性格の悩み」から「ダイエットに失敗しました」という24歳の女性からのお悩みにクマが処方されていますけれども・・・。
「ダイエットとリバウンドの最強の動物と言えば、クマですね」
●痩せたり太ったりっていうことですか。
「動物の中でいちばんその差が大きいですよね。よくご存じかと思います。例年秋口に、冬眠に入る前なんかにクマのトラブルの問題が報じられますよね。あれは食い貯めをしとかなきゃいけないので、どんぐりとかいろんなものを食べ漁って、1日5000キロカロリーっていうとんでもないカロリーモンスターですから、それを取っていくんです。
一方、半年間1日5000キロカロリーも食べるような食生活をしたかと思うと、それ以降、半年間の冬眠では1滴も飲まず食わずの減量期間で、冬眠明けの春には激痩せして出てくるんですよね」
●え~〜、なんだか人間としては体に悪そうって思っちゃいますけど・・・。
「もうすごいですよね〜。ですから、その生理のメカニズムがまだ完全に解明しきれていなくて、医学的にも非常に注目されているんですよね。冬眠がどういうメカニズムになっているのかっていうのは、まだまだ謎が多くて面白いんですよね」
●そんなに体重が変化していても、健康状態は別に悪化したりっていうのはないんですよね?
「そうですね。飲まず食わずというだけじゃなくて、おしっこ、うんちもしないっていうところが面白いとこなんですよね。毒で体に貯めておくといけないものをエネルギーに変える能力が、実はクマにはあるんですよね」
●え~! すごいですね~!

仕事のお悩みにミツバチ!?
●では、チャプター3「仕事の悩み」から25歳の女性、「仕事が楽しくなくて」というお悩みに処方箋がミツバチ。で、次のページに37歳の男性からの「働かないとダメですか?」という悩みに対して、ミツバチのオスを処方されています。これはどうしてミツバチなんですか?
「ミツバチは面白いんですよね。無脊椎動物、どういう点を見るかにもよるんですけど、脊椎動物でかなり社会性が複雑になって頂点を極めているのは、ひとつは人間もあるかと思うんですけれども、その対極って言うんでしょうかね。無脊椎動物で非常に複雑な社会に進化させているものがミツバチなんですよね」
●ミツバチ!?
「特に分業で、仕事が割り当てられていて、それがいろいろ選べるって言いますかね」
●例えば、どんな分業がありますか?
「例えばですけど、ミツバチの働きバチ、“ワーカー”って言われているのは、みんな実はメスなんです。まだ羽化したばっかりの時は、いろんな経験を積んでいないので下手くそなんですよね。だからまず、お掃除係から訓練して・・・」
●へ~〜! 下積みみたいですね。
「下積み期間があって、そこでいろいろ学んでいくと、今度は育児、卵とか幼虫の世話をする仕事に昇格して、経験を積んでいくと、門番と言って、巣のところで見張りをしたりするんです。例えば、クマとかいろんな天敵が蜜を盗みに来たりして、そういうのから守るガードマン役をやったりするんですね。
だんだん配属を変えていきながら出勤して、OJT(*)みたいにやってですね。いちばん究極に難しいのは、餌を採ってくること。それまでは内勤の仕事なんですよね。これが外勤バチって言われるんですけど、外に出て花の蜜を探して採ってくる作業は、かなりの経験が必要で、仲間にそれを伝えなきゃいけないんですよね。
何キロも先の餌源(えさげん)がどっちにあって、それがどんな食べ物なのかっていうのを伝えて、みんなで採りに行くんですけど、いちばんベテランになると、そういうのができるようになってくるので、きっとそういう仕事の中で楽しみを選べるかもしれないですね(笑)」
(*On the Job Trainingの略 )
●なるほど! 確かにそうですね。ところでミツバチのオスっていうのは?
「一方で、面白いんですけど、オスがほとんどいないんです。ちょこっとはいるんですね。何千匹、何万匹いる中で、数匹いたりするんですけど、それの役割がよくわかっていないんですね。もちろん卵を産ませるっていう仕事はあるんですけど、それ以外は巣の中でうろちょろしているんです。別に餌を採りに行くわけでもなく、お掃除するわけでもなく、育児を助けるわけでもなく・・・」
●メスがこんなに忙しく働いているのに!
「(メスが)命がけでやっていても、(オスは)何にもしてなくて、ぼーっとしていて、うろうろしているだけで、時々蜜なんかをちょっとつまみ食いなんかしてっていうように、働かないバチなんですよね、オスっていうのはね。
だからすごく両極端で、でもそれが進化的に淘汰されてもいい、そういうものができるだけ存在しないような形にも進化的にできたでしょうが、なんとなくそういうものも生きていける余裕を残してくれている面白さっていうのが(ミツバチの)進化の中にありますよね」
●では、働かないとダメですか? っていうこの37歳男性のお悩みには・・・。
「まあ、ミツバチをお手本にしたらいいかもよ! っていうところですね(笑)」
ビーバーはマイホームパパ!?
●続いてチャプター4「家庭の悩み」から「マイホームを持つのが夢」という38歳男性からの悩みですね。悩みというか願望なんですけれども、処方箋がビーバーとなっています。これはどういうことでしょう?
「このマイホームパパを代表したような動物がビーバーなんですね。ビーバーはネズミの仲間で水辺、水性に適応して進化した動物なんです。木を切って川をせき止めてダムのようなものを作るのは、割とみなさんイメージとしてあるかと思うんですけど、(川の)真ん中のところに木を集めて巣を作るんですよね。
天敵の泳げない猫科の動物なんかは水を嫌ったりするので、水の中に行けないんです。生き残るために機能的な巣を作っているんですけども、実はそれだけじゃなくて、このビーバーのお父さんはメンテナンスもすごくこまめにやるんですね。自分で作ったお家が大好きで、枝の角度とかそういうのを、ちょっと気にいらないと直したりとか・・・」
●DIYみたい!
「DIY! ひとりでね! 子供とか呆れているかのように、またやっているよ! っていう感じで、お父さんがすごく一生懸命、家のメンテナンスを欠かせないんですよね。
私は動物園にいた時にビーバーに実験したことあるんですね。ダムが決壊したりした時に補修をするのもビーバーのお父さんの仕事なんです。すっ飛んで行って泳いで、枝とかをあてがって補修をするんですね。
水の流れる音を、おトイレのジャ〜って流す音を録音して、飼育しているビーバーに聴かせたら、ビーバーがものすごいダッシュで飛んできて、“どこですか? 壊れてるの! どこ?”って感じで、直す気満々で。それぐらい、なんて言うんでしょう、子供を守る以前に、マイホームのメンテナンスに命をかけているぐらいの面白い動物ですよね」
動く動物フィギュア「アニア」
※新宅さんは、タカラトミーの動物フィギュア「アニア」の監修もされています。この「アニア」、陸や海の動物をはじめ、鳥、昆虫、恐竜など、幅広いジャンルの生き物、およそ100種類ほどが販売されていて、子供はもちろん、大人にも大人気なんです。

●きょうはスタジオにたくさん持ってきていただきました。ありがとうございます。ゴリラとかキリンとか、サイとかパンダとか、いろいろな動物がいますけれども、よくできていますね~!
「このアニアは、動物フィギュアとしてもちょうど10周年になって、だいぶラインナップも揃ってきたんです」
●すごい! 質感もしっかりしているというか、合皮のような感じで・・・。
「そうですね。普通の動物フィギュア、いま世界中で割と大ブームになっているので、いろんな精工なものがありますけど、その多くが飾って楽しむようなものがほとんどなんですね。アニア はやっぱり玩具メーカーのものなので、遊んでもらうためのものっていうことで、いろいろ動く部分があります」
●首とか足が動いたり・・・これはハヤブサですね。羽も動くんですね!
「ぜひハヤブサを作って欲しいなと思って、開発チームの人にお願いして、特に400キロ出せる、飛ぶ時の姿を再現したくて・・・ハヤブサは最高速が出る時は、身体を畳んで弾丸のような形になって、“ストゥープ”っていう飛び方になるんですけど、それで400キロ出すんですよね」
●かっこいいですねー!
「かっこいいですよね!」
●リビングにオブジェとして飾っておきたくなるぐらい大人も楽しめますね!
「そうですね!(アニア)は子供向けとして作っているんですけど、割とそういうちょっと映える感じで遊びでやっているかた、多いみたいです」
●かっこいいです! ゴリラの親子も凛々しくて、かっこいい~。
「そうなんですよね。ゴリラは猿の中では(子育てに)唯一お父さんがいるんですよね。ハーレム型の社会構造なので、そういうメッセージを遊びながら(学べるように)・・・ほかの動物はお父さんがあまり存在しないんですよね。だからこのゴリラに関してはお父さんがけっこう赤ちゃんや子供を、ちょっとあやしたりなんかすることもあるので、そういうので遊んだらいいんじゃないかなと思って選んでいますね」
●特に人気のあるフィギュアって、どれになるんですか?
「そうですね・・・いろんなギミックが盛り込まれて、最近出ているのだと、カメレオンで舌が伸びるような・・・」
●ビヨ〜ンって伸びるんですね~、すごーい! 面白い!
「あと、アルマジロが丸くなるとかね」
●まん丸に! コロンコロンになるんですね!
「ただそれで遊ぶだけじゃなくて、ごっこ遊びみたいに、いろんな物語を作ったりとかしてやると、すごく楽しいものになるので、そういう遊びかたをしてくれたらいいなっていうのを想定して、動く部分だとか動物の種類を選んだりとか、そういうのを考えていますね」
●制作する時に心がけていることってありますか?
「私の専門が動物行動学なので、(アニアは)飾り用のフィギュアではなくて、ここの部分を使って遊んでほしいな! っていうのを盛り込みたいので、その動物の特徴的なところに稼働部分をつけたりとかしていますね」
●やはりリアリティーは大事にされているってことですね?
「そうですね。それで遊んでもらうっていうかな、動かしてみて、いろんな気付きとか発見とかもありますので・・・」
(編集部注:「アニア」の監修を担当されている新宅さんによれば、ひとつの動物の制作期間はだいたい1年ほど。中には構想から完成まで2〜3年かかるものもあるそうです。また、古生物に関しては、研究資料などで調べても、体の色まではわからないので、こんな色にしてみませんかという大胆な提案もされるとか。
ちなみにカバは、お風呂でも遊べるように浮くようになっているそうですよ。動物の生態をもとに、子供たちが遊べるように工夫されているんですね)

人間だけの特性「笑い」
※新宅さんは、これまで数多くの動物を調査・研究されてきました。そんななか、今回の新しい本もそうだと思うんですが、「人間」という動物を探究しているようにも感じます。そのあたりは、いかがですか?
「なんて言うんでしょう・・・一瞬忘れがちですけれども、ついつい自分とか、人間っていうものが動物であることをうっかり忘れちゃうというか・・・我々は違うって考えがちなんですけど、共通点とか違いっていうのを、動物を調べることで、見えてくるものもたくさんあるので、そういうところはいちばん興味ある部分ですね」
●先日、人類学者のかたに「人類学とは人間とは何かを問う学問だ」っていうふうに教えていただいたんですけれども、動物行動学的に見て人間っていうのはどういうものなんでしょうか?
「難しい質問ですけれども、どこが逆に人間が動物っぽい部分なのか、そして動物っぽくない部分ってなんなのかっていうのは、すごく整理していきたいなと思っています。そんな中で例えば、突出して面白いのは、いくつかあるんですけど、ひとつは、“笑い”・・・動物って笑えないんですよね。
笑うっていう表現はやっぱり人間の、動物の行動としてはかなり特殊なもので、面白いユニークなものですよね。笑いっていうのは面白いから笑うっていうだけではないですよね。
その場を取り繕ったりだとか、相手をリラックスさせるとか、一緒に笑うとか、敵意がないこと示すとか、いろんな要素をそこに組み込んで、言葉を使わずに、つまり人間の中でも言語を使わないで、敵意がないことを伝えたりとか、そういうことができるユニークなツールになっていますよね」
●確かにそうですね~。ということは、まさに人が人にしてあげられる処方箋といえば、笑いになるんですかね。
「そうですね。やっぱりそこも面白いんですけれども、人は、赤ちゃんで生まれてまだ歩けない、寝返りも打てないようなレベルで、最初に笑うんですよね」
●笑っていますね、確かに!
「“新生児微笑”って言って笑うんですよね。あれは別に赤ちゃん、おかしくて笑っているわけじゃないんですね。 おそらくそういうものが人間にとっていかに大事か、順番としても最初にそれをやらなきゃいけない、練習しなきゃいけないっていう順番が、歩くよりも先にそれをやる、何かそこに鍵があるような気がしているんですよね」
●ほかの動物にはない、人間ならではの特性ですね。面白い!
「いろんなこじれたこととか、ストレスとかそういうのも、笑いっていうのは自分に対しても向けられるので、悩みを笑い飛ばすとかね。そういうふうにできると少し(気持ちが)軽くなったりすることもありますよね」
●そうですね!
「笑いを上手に使いこなせるようになると、悩みとか、あと人との関係、ギクシャクしたり喧嘩してしまったものも、笑いとか冗談で、一転して仲良くなったりってことはありますからね。すごく大事にしたい行動ですよね」
☆この他の新宅広二さんのトークもご覧下さい。
INFORMATION
『あなたにゴリラを処方します。悩みがちょっと軽くなる動物の読み薬』
新宅さんの新しい本、おすすめですよ! 人間のお悩みに対して、動物を処方する形式をとりながら、生き物の生態や行動をわかりやすく解説しています。ひとつの項目が見開き2ページで完結しているので、とても読みやすいです。イラストは以前番組に出てくださった「きのしたちひろ」さんです。ぜひイラストもチェックしてください。
エムディエヌコーポレーションから絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎エムディエヌコーポレーションHP:https://books.mdn.co.jp/books/3222103055/
新宅さんの近況についてはぜひfacebookを見てください。
◎新宅広二さんfacebook:https://www.facebook.com/koji.shintaku.7/
新宅さんの本『あなたにゴリラを処方します。悩みがちょっと軽くなる動物の読み薬』と、タカラトミーの動物フィギュア「アニア」の「サバンナの人気動物セット」を合わせて、3名のかたにプレゼントいたします。

件名に「プレゼント希望」と書いて、番組までお送りください。
メールアドレスはflint@bayfm.co.jp
flintのスペルは「エフ・エル・アイ・エヌ・ティー」
flint@bayfm.co.jp です。
あなたの住所、氏名、職業、電話番号を忘れずに。番組を聴いての感想なども書いてくださると嬉しいです。
応募の締め切りは10月27日(金)。
当選発表は発送をもって代えさせていただきます。たくさんのご応募、お待ちしています。
応募は締め切られました。たくさんのご応募、誠にありがとうございました。
2023/10/22 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. ANIMALS / MAROON5
M2. ぼくはくま / 宇多田ヒカル
M3. UN HOMME ET UNE FEMME / CLÉMENTINE
M4. MY HOMETOWN / BRUCE SPRINGSTEEN
M5. 楓 / スピッツ
M6. I LOVE YOU / DEBELAH MORGAN
M7. SMILE / ELVIS COSTELLO
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2023/10/15 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、信州大学の助教「笠原里恵(かさはら・さとえ)」さんです。
笠原さんは1976年、長野県生まれ。子供の頃は、里で当たり前に見られる鳥よりもリスやネズミなどの小動物が好きだったそうです。
そして、大学進学後に、自然を観察するサークルに入部、1年生の時に、先輩から鳥を見に行かないかと誘われたことが転機となり、野鳥研究の道に進むことになったそうです。
現在は、信州大学理学部附属・湖沼高地(こしょうこうち)教育研究センター・諏訪臨湖(すわりんこ)実験所の助教。専門は鳥類生態学や保全生態学など。
具体的には、水辺の自然環境が多様性に富んでいる千曲川の中流域をメイン・フィールドに、野鳥たちが川のどんな場所に暮らし、どこに巣を作り、何を食べて生活しているのかなどを研究されています。

そんな笠原さんが先頃『知って楽しい カワセミの暮らし』という本を出されました。きょうは野鳥好きの心を捉えて離さないカワセミの、意外に知られていない生態や、変化する河川環境を利用する鳥のお話などうかがいます。
☆写真協力:笠原里恵
カワセミの色は構造色!?
※カワセミは、特にバードウォッチャーにはとても人気がありますよね。カワセミの特徴といったら、まずは、コバルトブルーに見える羽の色だと思うんですが、どうしてあんなに綺麗に見えるんでしょうか?
「日本で見られる鳥は600種と少しって言われているんですけれども、みなさんが身近な鳥を思い浮かべると、やっぱりカラスの仲間だったり・・・。もちろんスズメもよく見ると複雑な色をして綺麗なんですが、全体としては茶色であったり、派手な色をした鳥って少ないと思うんですよね。そういう中にあって確かにカワセミは非常に目立つ色、綺麗な翡翠色をしていると思いますよね」
●光の加減によって、また色の見え方が違いますよね。
「どうして見る角度によって変わるのかは、色の見え方、私たちの色の認識の仕方に関係しているんですけれども、私たちは通常、色素で色を見ています。
光の三原色が赤・青・緑だっていう話は聞いたことがあると思うんですけども、その光の波長が太陽とか室内光の明かりに含まれていて、それらの波長が何かに当たるとします・・・リンゴに当たる、葉っぱに当たる、そうするとリンゴとか葉っぱとかが持つ色素がその波長の一部を吸収して、吸収されなかった波長の光が我々の目に届いて、色として認識されることになります。
けれども、実はカワセミの羽の色は、そういういわゆる色素とは違っていて、その光の構造を説明する上でよく挙げられるのがシャボン玉になります。石鹸水で作ったシャボン玉って、透明なのに光に輝いてキラキラ虹色に光りますよね。
それは実は色素によるものではなくて、シャボン玉の薄い膜内の、光の屈折によって生じた光の波長同士の干渉なんですね。それによって特定の光成分が強まって発色しています。
こういうのを『構造色』って言うんですけれども、カワセミの羽の色も構造色の一種です。カワセミの場合は、シャボン玉のように薄い膜というわけではなくて、その羽毛の内部に、網目状のスポンジのような微細な構造があって、その並び方から青色の光が強められるようになっているんだそうです」

●カワセミの色以外の、ほかの特徴も教えていただけますか?
「色もとても美しいんですが、やはりその形ですよね、全身の形・・・。頭がちょっと大きくて、くちばしが非常に長い。くちばしの長さがだいたい3.6センチあって、頭よりもくちばしのほうが長いんですね。それに対してずんぐりした体と非常に短い足をしています。
足の形も、ほかの鳥と違っていて、足の指・・・みなさん、なかなか鳥の指先って見る機会がないと思うんですけれども、普通の鳥と少し違っています。これは彼らが巣を作る場所に関係しているんですけれども、指の一部がちょっとくっついて、シャベルのような形になっているのも大きな特徴だと思います」
(編集部注:カワセミの羽の色や形については、笠原さんの本に、山科鳥類研究所の研究員、森本 元(もりもと・げん)さんの解説が「豆知識」として載っていますよ。
ちなみにオスとメスの見分け方で、いちばん分かりやすいのが「くちばし」。オスが上も下も黒なのに対し、メスは下のくちばしがオレンジ色になっています」

水辺に特化した能力
※カワセミが水辺を好んで暮らしているのは、どうしてなんですか?
「現状、彼らが水辺で暮らしているのは、やっぱり魚を獲って・・・彼らの主食は魚なんですけれども、魚を獲りやすく、また彼らは子育ての時に土の崖に巣穴を掘って、中に卵を産むんですね。そういった食べ物についてもそうだし、巣を作って子育てをする場所についても、やっぱり水辺に特化している種類と言えますね」
●魚を獲るとおっしゃっていましたけれども、水中にダイブして獲物をゲットして、水面に戻って羽ばたくんですよね。それってすごい能力ですよね。
「そうですね。特にカワセミは、水辺に張り出した枝先から水の中の魚を狙って一瞬で飛び込みます。で、飛び込んで水の中に入っている時は、目が『瞬膜』っていう膜で覆われていて、目を保護しているんですね。
彼らは水の中で泳ぐとかではなくて、水の中に飛び込んだ勢いで魚のところまで到達して、あっという間に咥えて、すぐに戻ります。水面に上がった時にはもう羽ばたいていて、枝に戻って獲った魚を食べるわけですけれども、そういうことができる種類は、やはりあまり多くないと思いますね」
(編集部注:カワセミの求愛行動はよく知られていますが、そこに至るまで、オスとメスはどう過ごしているか・・・笠原さんによると、冬の間はそれぞれのなわばりで過ごし、春先になるとオスがメスのなわばりに進入、当然メスはオスを追い出しにかかり、追いかけ合うそうです。
そんなことを繰り返していくうちに、オスがメスに小魚をプレゼントし、メスが受け取って飲み込んでくれたらカップル成立! オスはメスが飲み込みやすいように、小魚の頭を向けて渡すそうですよ)

※カップルになったら、次は巣作りだと思うんですけど、カワセミはどんな巣を作るんですか?
「彼らは露出した崖、川の近くのあまり草木が生えていない、ちょっとだけオーバーハングって言って、下よりも上の方が水面に向かってせり出すような、そういったオーバーハングした崖を好みます。
その崖に・・・彼らの足はちょっと特殊で、短い足ですけれども、その足とくちばしで横穴を掘って、おおよそ50センチから80センチと言われていますけれども、彼らの体がだいたい17センチですから、自分の体の3倍とか4倍とか、そういった長さの穴を掘って、いちばん最後に『産座』と呼ばれる場所、卵を産んで温める場所ですけれども、少し大きめの空間を作ってそこに卵を産みます」
●その穴を掘る作業って大変な作業ですよね。オスとメス、共同で作業するんですか?
「こちらについても、つがいによってけっこう違うと言われていますが、やっぱり基本的にはオスが巣を作る場所をメスに示して、メスが気に入ったらオスが掘り始めます。オスが掘っていって、その間 手伝うメスもいれば、オスが掘っているのをただ見ているだけのメスもいます。オスはなかなか偉くて、巣穴を掘っている間にもたびたび魚を持ってきて、ちゃんとメスにプレゼントするんですね。
確実なのは、ある程度巣穴ができて、最後に卵を産む産室(産座)ができますが、その産室ができる頃になると、メスも積極的に参加して・・・卵を産んで温める作業はオスもメスもするんですけれども、メスにとっては特別なことだと思いますので、やっぱりとっておきというか、お気に入りの産室にするように、自分で掘って整えているんじゃないかなと思います」
●1回にどれぐらいの卵を産むんですか?
「これは私の調査をしている千曲川の例ですけれども、おおよそ7つくらい卵を産みます。多ければ8つっていうこともあるし、少なければ5つっていうこともあります」
●育つまでどれぐらいの日数がかかるんですか?
「だいたい卵を産み始めて、産んでから雛(ひな)が孵化するまでがおおよそ20日間前後と言われています。カワセミの雛は孵った時に全然羽毛が生えていません。もちろんくちばしも非常に短いんですけれども、翼がある程度生えて、外の世界に飛び出して飛べるようになるまでが、だいたい24日間というふうに言われています。ですので、卵を産んでから育つまでを考えると1ヶ月以上、ずっと巣穴の中にいることになりますね」
カワセミの仲間、ヤマセミとアカショウビン
※日本で見られるカワセミの仲間には、おもにどんな種がいますか?
「私たちがよく見かける、日本で子育てをしているカワセミの仲間は『ヤマセミ』っていう非常に体が大きい、みなさんが公園で見かけるドバトくらいの大きさのカワセミの仲間がいるのと、それからその姿から火の鳥なんていうふうに呼ばれる『アカショウビン』という、くちばしから姿が全体的に真っ赤なものがいます。その3種がメインだと思います。日本でこれまで確認されているカワセミの仲間は8種ですね」

●カワセミとヤマセミは、暮らしているエリアは違うんですよね?
「そうですね。みなさん、カワセミっていう鳥は名前を聞くと、あの青いちっちゃいやつだなっていうふうに思い浮かぶと思うんですけど、ヤマセミと聞いて思い浮かぶかたって少ないと思うんです。
ヤマセミは鹿の模様、鹿の子で“かのこ”っていうふうに呼ばれたりもするんですけれども、全体的に体が白いんですね。そこに黒が鹿の子模様のように入った美しい姿をしています。
そんなヤマセミをどうして見る機会が少ないのかと言いますと、ヤマセミのほうが一般的に上流域に、カワセミのほうが下流域に棲むというふうに言われています。上流域でも、けっこうヤマセミは渓流なんかが好きですので、あまりみなさんが普段生活しているような範囲では(ヤマセミの)姿を見ることはないからですかね」
●日本には8種類とおっしゃっていましたけれども、海外には何種類いるんですか?
「これがまた海外はけっこうたくさんいます。国際鳥類学会が出している『世界の鳥のリスト』っていうのがあるんですね。そこから(引用)すると、2022年の時点ですけれども、世界のカワセミの仲間は116種記載されています」
●そんなにいるんですね!
「はい。最も多いのがアカショウビンの仲間で、72種記載されていて、カワセミの仲間はおよそ35種、先ほどお話したカワセミと似ているけど、棲んでいる場所が違うヤマセミについてはけっこう少なくて、9種が記載されているような状況です」

川は人間だけのものではない
※笠原さんはカワセミを含めた、水辺の鳥たちや河川の環境を長年、調査・研究されてきて、こんなことを感じているそうです。
「川と鳥の関係ですごいなと思ったのは、これまでは多くの増水は8月とか9月の台風で起きているものが多かったんですね。8月9月っていうと、多くの鳥は繁殖を終えています。子供も育って、ある程度飛べるようになっていてという時期ですので、そういう時期に増水が起きても、そんなに次世代に命をつなぐという点では影響が小さいですね。
その一方で、そういう水の流れで木や草が流されて、できあがる環境に生息しているような種類にとっては、台風による増水が翌年の生息地の維持につながるわけですね。
なんですけれども、近年、今年もそうでしたけど、6月とか、明らかに鳥の繁殖の真っ只中に豪雨が降って、水が溢れたり、家が流されてしまうような大きなことがありました。そういった気候の変化がこれまでは、鳥たちの繁殖の間には増水がなく(繁殖が)終わってから増水があって、翌年の生息地が作られるみたいに、うまく回っていたメカニズムが壊れてきているというように非常に危惧しています。
もうひとつは、やっぱり最近は人の生活に影響を与える水害が毎年のように起こって、胸が痛いんですけれども、そういったことが頻繁に起こることによって、川、もしくは川の管理、そういったものがより治水に、自然との調和っていうよりは、人の命を守りましょうっていうほうに急速に傾いていると思います。
それは当然、当たり前のことだと思います。やっぱり人の命を第一に治水は行なわれるものですので、それはそれでいいんですけれども、その一方で鳥だけではなくて、川で生活しているいろんな生き物への配慮が、やっぱり置いてきぼりになってしまう・・・ここは非常に難しいです。
人の命より鳥の命のが大切ですか? って言われると、やっぱり答えにくいところは非常にあるんですけれども、やはり自然ですね・・・我々が生きていく中で、川からいろんな、水をもらって水田を作ったりとかして、我々は生活しています。川はもちろん人間のものだけではなくて、そこで生きている生き物がいるわけですから、治水がどんどん進められていく一方で、それでもやっぱり、川がもともと持っている変動性に依存した生き物がいるんだよっていう部分は、忘れてはいけないのではないかなと思っています」

(編集部注:笠原さんの調査・研究のメインフィールド千曲川は、笠原さんいわく、生き物にも人々の生活にも配慮した治水の方法がとられているそうです。上流に大きなダムがほとんどないこともあって、自然の力に任せた河川環境の維持につながっているとのこと。詳しくは、笠原さんの本の第7章「生き物に配慮した川づくり」をご参照いただければと思います)
可愛らしい、ワイルド、したたか
※この時期でも、カワセミを見ることはできますか?
「はい、今も見ることはできますね。多分これから冬に向かっていきますと、今まで子育てをするために川の近くだったりとか、巣がある場所の周辺にいたカワセミも、子育てがだんだん終わってきます。
それから今年生まれた若いカワセミが、親元にいつまでもいられるわけではありませんから、独り立ちをした子供が別の住処を探して移動したりとかしていて、みなさんの近くの公園とか、それから小さな河川でも見られる時期になっていると思います」

●笠原さんが思うカワセミのいちばんの魅力はなんでしょうか?
「私自身がカワセミに感じているところとしては、カワセミのその愛らしい姿がけっこう人気はあると思うんですけども、その愛らしい姿に対して、割とワイルドな採食方法、飛び込んで魚を捕えて、その魚を捕らえたあと、枝に戻って叩きつけるんですね。叩きつけて食べるという、そういった野性味溢れる部分もあって、そういう可愛らしい姿と、行動のギャップみたいなところですね。
それからもうひとつ、これは2005年に起きた増水のあとなんですけれども、水が引いたあとに、私が調査していて、カワセミが通らないような河畔林を歩いていたんです。河畔林って言ったら木が茂っているわけですね。そこに増水のあとの大きな水たまりができていて、そこでカワセミを見る機会があったんですね。
なんでこんな森の中にカワセミがいるんだろうと思ったら、増水のあとでしたので、その河畔林の中の水たまりに取り残された魚がいっぱいいました。カワセミはそれを目ざとく見つけて、普段は使わないような場所だと思うんですけれども、そこに素早く現れて魚を獲っているっていう姿だったんですね。環境の変動が激しい中で、増水のあとですら、その増水で残った魚を捕るというしたたかな部分、そういったところに非常に魅力を感じています」
INFORMATION
国内外のカワセミを中心に、ヤマセミやアカショウビンなどの基礎知識ほか、調査・研究から分かってきた意外な生態、そして水辺に暮らす鳥たちと川との関係や、これからの川づくりなど、興味深い解説が満載です。カワセミの生態をとらえたカラー写真は必見ですよ。
緑書房から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎緑書房:https://www.midorishobo.co.jp/SHOP/1620.html
笠原里恵さんのオフィシャルサイトもぜひ見てください。
2023/10/15 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. I’M LIKE A BIRD / NELLY FURTADO
M2. BIRD OF BEAUTY / ESTHER SATTERFIELD
M3. BIRD SET FREE / SIA
M4. BIRDS / PAUL WELLER
M5. ワタリドリ/ Alexandros
M6. THE WATER IS WIDE /JAMES TAYLOR
M7. FREE AS A BIRD / THE BEATLES
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2023/10/8 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、立教大学・異文化コミュニケーション学部の教授で、人類学者の「奥野克巳(おくの・かつみ)」さんです。
奥野さんは1962年生まれ。高校生の頃の、将来の夢は日本脱出、ということで大学に進学後、メキシコ、インド、東南アジアなど、自由な旅に没頭。卒業後、商社に就職するも、20代後半で退職し、今度はインドネシアを放浪。その後、大学院で文化人類学を専攻、博士号を取得されています。
現在は人類学者として多方面で活躍、数多くの本も出版。そんな奥野さんの新しい本が『はじめての人類学』です。
入門書的な本を出された奥野さんに、人類学とはどんな学問なのか、初歩的なことをお聞きしつつ、奥野さんが研究のために長期間滞在し、寝食を共にしたボルネオ島の森に暮らす狩猟民の興味深いお話をうかがいます。
☆写真:奥野克巳

人類学の礎を築いたマリノフスキ
※この本は、人類学のおよそ100年を、4人の最重要な人類学者を紹介しつつ、振り返り、今後の人類学を示唆するような内容になっています。まずは、人類学とはどんな学問なのか、教えてください。
「人間探究ですね。ティム・インゴルドっていう人が『Anthropology is philosophy with the people in.』っていうふうに言っているんですね。つまり人類学とは哲学だと。で、哲学って何かっていうと、人々と共にする哲学。その人々というのが、最後にinがついていて、人々がいるところに行って、人々と共にする哲学だというふうに言っているんです。
まさに人類学というのは現地のフィールドワークを通じて、人々と共に行なう哲学ということになっています」
●フィールドワークに基づいた新しい人類学を切り開いたのが、重要人物のひとり、ポーランド出身のイギリス人、マリノフスキというふうに本に書かれていましたけれども、このマリノフスキというかたはどんなかたで、どこに行って、何をされたのか、かいつまんで教えていただけますでしょうか?
「出身はポーランドなんですけれども、イギリスで勉強していて、オーストラリアのトーテミズムの研究をしていたんですね。そのトーテミズムを文献の中で研究していたんですけれども、わからないので行ってみて、実際のところを知りたいと思ったんですね。
最終的にオーストラリアの隣のニューギニアの島、トロブリアンド諸島というところに行って、それまでは現地語をマスターするということはなかったんですけれども、彼は現地語をマスターして、そこに長期滞在してフィールドワークを行なったんです。その成果を、エスノグラフィーって呼んでいるんですけれども、ある民族、文化が体系的にまとめて、それを出版したと、そういったことをした人です」
●当時ニューギニアってまだまだ未開の地と言ってもいいですよね。そんなニューギニアで長期滞在するって相当大変だったんじゃないですか。
「そうだと思いますね。それまでは椅子に座って本を読んで、文化の姿を空想していただけだったんですね。実際にマリノフスキが現地のフィールドワークを始めて、様々な困難もあったんですけれども、それ以降の現代の人類学の礎を築いたんです。
現地に行ってフィールドワークを行なって、そこで見えてきた人々の生き方、こういったものを記述、それから分析することを始めたのが、マリノフスキということです」
(編集部注:奥野さんによると、人類学という学問は15世紀の大航海時代まで遡るそうです。当時ヨーロッパの人たちが異文化に出会い、興味関心を高めていくなか、キリスト教の宣教師が持ち帰った記録や旅行記、船乗りの航海日誌などが情報のリソースとなり、知見を広めていったということですが・・・
ということは、大航海時代は文献だけで「人間」を探究していたわけですから、
フィールドワークという手法を取り入れ、礎を築いたマリノフスキの功績は大きいと言えますね)

人類の原初のあり方を探る
※奥野さんの調査・研究のメイン・フィールドはどこになるんですか?
「インドネシアを1年間放浪していました。その中でカリマンタン島、これはボルネオ島なんですけれども、そこの放浪を終えて、大学院に入ったんですね。フィールドワーク中はボルネオ島ですね。そこで最初、90年代の半ばに焼畑農耕民の『カリス』という民族の調査を行なって、そこから今度はマレーシア側のボルネオ島にシフトして、そこで狩猟民の研究を行なってきています。2006年からその狩猟民の研究をしています」
●その狩猟民が「プナン」ということですよね。ボルネオ島の狩猟民プナンを研究対象として選ばれたのは、どうしてなんですか?
「人類学ですから、その大きなテーマというのが人間とは何かなんですね。かつて私は農耕民の研究を2年間やっていたんですが、そこではシャーマニズムとか呪術というものをテーマにしていたんです。
どちらかというと農耕民ですから、我々日本人の古い姿というか、懐かしいあり方というのが見えてくるんですけれども、もうちょっと遡って、人類の原初のあり方、人間とは元々はどういう存在であったのかを探るために狩猟民の研究を始めたんですね。
で、狩猟民がボルネオ島には、プナンという非常に魅惑的なというか魅力的なグループがいたんですね。そこに入って行って、調査研究を始めたという、そういった経緯です」
●どう魅力的なんですか?
「魅力的っていうのは、あまり狩猟民が残っていないんですね。地球上に残っていなくて、農耕が行なわれ始めたのが、今から1万年とか8000年ぐらい前のことなんです。それまでの人類は約25万年ぐらい前からずっと、1万年とか8000年くらい前までは、すべての人類が狩猟採集を行なっていたんです。
そのあと農耕、牧畜に移行してきたわけですけれども、古い人間のあり方が残っていると言いますか、そこから想像することができるという意味で、人類の古い姿、もともとこういったことを考えていたんじゃないか、あるいはこういったことをやっていたんじゃないか、ということを探る手がかりとして、非常に魅力的だということですね」
(編集部注:奥野さんは、狩猟民プナンの人たちと、当初は、マレーシア語を介してコミュニケーションをとり、徐々にプナン語をマスターしていったそうです。プナン語はマレーシア語とよく似ているそうですよ)
狩猟民プナンの暮らし
※プナンの人たちは、どんな暮らしぶりなんですか?
「1980年代までは、だいたい森の中で流動生活をしていたんです。流動っていうのはノマディックな生活ですね。獲物、食べ物があるところに住んで、それがなくなると、別のところに移動するというライフスタイルだったんですね。
政府が定住地を見つけて、そこに住みなさいということで、80年代以降は(定住地に)住むようになったんですが、でも狩猟という生業そのものをやめてしまうのではなくて、定住地から森の中に入って行って、狩猟キャンプを建てて生活するということ、これは半定住って言っていますけれども、半定住の暮らしが今日に至るまでの主流です。だから森の中に狩猟キャンプを作って、そこでいろんな動物を獲って食べて生きていく、そういった人たちですね」

●どんな動物たちを食べているんですか?
「森の中にいる動物たちです、すべて。例えば・・・いちばんの好物がヒゲイノシシなんですね。シカ、ホエジカ、あるいはサルをいっぱい食べるんです。リーフモンキーであるとか、カニクイザル、ブタオザル、テナガザルとかですね。あとはオオトカゲであるとか、あと魚も食べますので、森の中にいるもの、川の中にいるもの、こういったものをすべて食べます」
(編集部注:プナンの人たちの家族グループには、母親や父親が違う子供たちがたくさんいるそうですが、分け隔てなく、みんなで育てる、そんな文化があるそうですよ)
※奥野さん自身は、どんな暮らしをしていたのでしょうか?
「基本的には人類学者は誰でもそうですけれども、彼らと同じキャンプの中に住んで、一緒に労働もしながら、労働っていうのはこの場合狩猟ですね。狩猟をしながら一緒に食べ物を獲りに行って、彼らと同じような暮らしをすると、そういったことを原則として彼らと一緒に暮らしていました」
●今でこそアウトドアブームですけれども、奥野さんご自身はそういう経験はあったんですか?
「そうですね。(キャンプは)子供の頃からとても好きでしたし、ある時は中学校に1回キャンプから通ったこともありました」
●そうだったんですね〜。では現地での暮らしには最初から馴染めましたか?
「これはですね、なかなか馴染めない面があるんですよ。というのは、私が自分のために持ち込んだ食料を、例えば、米であるとかラーメンであるとかそういったものを、彼らが何も食べ物がない時に料理して食べるわけですね。段ボール箱で持っていったんですけれども、私がいない時に段ボール箱がなくなっていた、そういうことがちょくちょくあるんです。
彼らは別に悪いというふうに思っていないんです。それはあとからわかったんですけども・・・。馴染めたかっていうことで言うならば、とんでもないところに来たなって思っていたというのがありますね。
それは彼らの贈与交換の仕組みと言いますか、シェアリングなんですね。あるものをみんなで分けると。つまり個人所有がないんです。そういうことがあとからわかってきて、その生活に溶け込んでいくことができたわけですけれども、最初からは馴染めなかったですね」

寝転がって調査!?
※プナンの人たちの調査も17年ほどが過ぎ、最近は、人々が暮らしているど真ん中に、寝っ転がって調査していると、本のあとがきに書いてありました。これはどういうことなんでしょう?
「寝っ転がって調査を最近はしていると・・・つまり文化人類学者って基本的にはアンケート調査なんか行なわないんですよね。参与観察、言葉ができるようになってインタビューをしたりはしますけれども、その場で参与観察という、参加しながら観察をするというような調査をしているんです。
最近、私はインタビューもせずに、狩猟キャンプで寝っ転がって調査をするというか、そこにいるということでわかってくることが、けっこうあるなって思っています。
言葉もできるようになると、神話であるとか民話であるとか人々の話、これがなかなか面白いんですね。これ、寝転がって聞いていると非常によくわかるんです。言語以前に理解できると言いますか、これをノートにつけようとしたりすると、何を言っていたのかが、なかなか整理できないことに気付くんですね。
なんて言うのかな〜、彼らが言っていることは、人々が言っていることは、ロジカルにまとめて理解しようとすると、なかなか理解できない、その部分が彼らの日常生活における、実際の生活の数値化できない部分なんですよね。データになかなかできない部分なんですけども、それが寝っ転がっていると、つかむことができると最近わかってきたということです」
●そういうプナンでの生活があって、日本に帰られた時に、逆に日本の生活にすんなり戻れなかったこともあったりしますか?
「1年間プナン(のキャンプ)に滞在していた時に、先ほど言ったように最初はなかなか馴染めなかったんです。これは例えばトイレがないとか、そういうことも含めて馴染めなかったんですが、帰る近くになると、もう彼らの暮らしが非常に心地よくて、逆に日本に帰ったら、またあの地獄が待っているのか! そういうふうに思うようになりました。逆転したっていうことですね、反転してしまったっていうことです」
●そうなんですね〜。
三者の視点で森を見る!?
※今はそうでもないかも知れませんが、欧米人のかたにとって「自然」は征服するもの。一方、日本人は自分も自然の一部、そんな考えかたがあるように思います。「先住民」のかたたちと、似たような価値観があるのではないかと思ったんですが・・・そのあたり、どうでしょう?
「日本もかつてはそうだったんでしょうけれども、たぶん日本は、”脱亜入欧(だつあにゅうおう)”という明治の時代、そのあとに自然と人間と言いますか、自然と文化というものを大きく分断させたっていう、けっこう複雑な歴史があるんだと思うんですね。
人間も自然の一部だというのが、具体的にどういうことなのかを探るのが、実は私の調査と言いますか、フィールドワークの大きな目的なんですね。
先ほどプナンの話をしましたけれども、ここでのその経験を少しお話したいと思います。それは何かと言いますと、彼らは狩猟ために森の中に入っていくんです。様々な動物がいるんですけれども、先ほど言ったようにサル、リーフモンキーっていうサルがいるんですね。これは葉っぱばっかりを食べているサルです。
リーフモンキーとそれから鳥に、リーフモンキーの名前が付いている鳥がいるんです。リーフモンキー鳥っていうふうに一応言っておきます。リーフモンキー鳥と、ちょっとややこしいんですけど、リーフモンキーってサルがいるんですね。
狩猟に行くと、リーフモンキー鳥が木の上で鳴いているんです。すると、そこにリーフモンキーがいると彼らは察知するんですね。そのリーフモンキーを獲りにプナンは行くわけですけれども、リーフモンキー鳥が鳴いて、リーフモンキーを獲りに駆けつけると、もうすでにリーフモンキーはそこから逃げていると、そういうふうに彼らはよく言っています。
これはどういうことかというと、リーフモンキー鳥は木の上から見ていて、リーフモンキーに、つまりサルに人が近づいて来ているということを警告するんだって言うんですよ、プナンの人たちは・・・。
つまりプナンは、その三者の視点から森を想像しているんです。つまりリーフモンキーというサルがいて、狩猟で(森に)入っていく人間がいて、そしてリーフモンキー鳥がその二者を、上から鳥瞰図的に見ている、これを想像しているんですね。
何が言えるのかというと、リーフモンキー鳥に見られる人間を組み入れているわけですよ。これは何を示しているのか・・・必ずしも人間は自然に向かう主体ではない、場合によっては自然から見られる客体になる、こういうことをよく知った上で狩猟をしている、リーフモンキー鳥という名前が付けられているっていうふうに見ることができる。
つまり、自然は征服するものではなくて、人間が主体的に征服するものではなくて、自然の側が人間を客体視しているということでもあるんだ、ということを分かった上で狩猟をしている、ということが言えるんじゃないかということです」
(編集部注:昨今では、未開の地に暮らす人たちもスマホを持つ時代ということで、プナンの人たちもスマホを持っているそうです。奥野さんは、スマホを介して連絡を取り合っているそうですが、彼らは文字が読めないので、おもにボイスメッセージでやりとりしているとおっしゃっていましたよ。人類学に新しい手法が加わるかも知れません)
※奥野さんのお話を聞いて、人類学に興味を持ったかたたちにひとことお願いします。
「人類学は、これはマリノフスキがそうだったんですけれども、いくら文献や本を読んでもわからないので、実際に現地や現場に行って、そこで本当のことを探ろうとする学問です。
人間が生きるとはどういうことか、ということを知るために、この本ではこの学問が発展してきた歴史を、4人の人類学者を通じて明らかにしていますので、人類学に興味を持ったかたはこの本を読んでいただきたいと思います」
INFORMATION
奥野さんの新しい本をぜひ読んでください。きょうご紹介したマリノフスキはじめ、人類学を学ぶうえでは欠かせない、最重要な4人の人類学者を中心に構成されています。個性的な4人の足跡や功績がとても興味深く、一気に読み進めてしまうと思いますよ。人類学の入門書の決定版、おすすめです。
講談社現代新書シリーズの一冊として絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎講談社HP:https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000380075
奥野さんのオフィシャルサイトもぜひ見てください。
2023/10/8 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. WHAT’S GOING ON / MARVIN GAYE
M2. HUMAN / GABRIELLE APLIN
M3. SHOWER THE PEOPLE / BABYFACE
M4. THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN’ / BOB DYLAN
M5. more than words / 羊文学
M6. BEAUTIFUL PEOPLE (FEAT. KHALID) / ED SHEERAN
M7. HUMAN NATURE / TRAINCHA
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2023/10/1 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、サイエンス・ジャーナリストでガーデナーの「森 昭彦(もり・あきひこ)」さんです。
森さんは1969年生まれ。雑草との出会いは20代後半、生き方に悩んでいたときに、足もとに咲くオオイヌノフグリの小さな花の色に心を奪われ、それから図書館で植物の本を片っ端から読むようになったそうです。
そして1999年、30歳の頃に自宅でガーデニングを始め、当初は西洋ハーブや野菜を栽培。その後、雑草や野草も育て、その数は1,000種以上になるとか。試験栽培などを通して、さらに植物に詳しくなった森さんに出版社から声がかかり、36 ,7歳の頃に初めて本を出すことになったそうです。
ちなみに奥様は公園に勤めていたときのヘッドガーデナーで、森さん曰く、結婚というよりも、奥様に弟子入りしたようなものですと、笑いながらおっしゃっていました。
そんな森さんの新しい本が『庭時間が愉しくなる雑草の事典』。ということで、きょうはガーデニングをやっている人には特に厄介者とされている「雑草」にフォーカス! 身近な植物「雑草」を知ることで人生が豊かになる、そのヒント満載でお送りします。
☆写真:森 昭彦

「雑な草」とは?
※森さんは『庭時間が愉しくなる雑草の事典』のほかにも、これまでに雑草に関する本をたくさん出されています。雑草に着目されるようになったのは、なにかきっかけがあったんですか?
「自分が大事に育てている植物のまわりに、植えた覚えも見たこともないものが、ばーって生えてきて、すごく邪魔するってことがよくわかって、俺の大事な植物に何してくれているんだ! と思いましたね。こいつは名前が何で、一体ここで何をしているんだろう?というのを不思議に思ったのがきっかけです。ひとつひとつ見ていくと結構な種類があるんですよね。
それまでは、ただの草むらとか雑草でおしまいだったんですけれども、細かく見ていくと、いろんな顔のいろんな子たちがいて、それぞれがやっていることが違うな、これ!と思ったんですね。
結局、育てたい植物を育てたいがために、雑草を調べ始めたら、どっちかっていうと雑草のことが気になり始めて、栽培植物は奥さん任せで(笑)、私はガーデニングの最中に生えてきた植物をピックアップして、どんな植物がいつ生えてくるんだろうっていうのを調べ始めてしまったということなんです」
●どんどん雑草に興味がわいてきたっていう感じなんですね?
「本末転倒も大概にしろという感じですけど、そんな感じです」
●種類が多いっておっしゃっていましたけど、日本にはどれぐらいの種類の雑草があるんですか?
「そうですね・・・雑草というと、どんな植物をイメージされたりしますか?」
●種類というか、それこそいろんなところに生えているっていうか・・・。
「こんな葉っぱのとか、こんな葉っぱのとか!(笑)」
●たくましいイメージはありますけど・・・。
「そうなんです。実は雑草って人によって、それを雑草とするかどうかって、全然違っているんですね。植物の世界では、雑草は何種類というふうには考えておらず、自然界に勝手に生えている植物の数としましては、学者によって違うんですけども、日本中でだいたい2600種から7000種と、幅があるんですよ」
●でも多いですね。そんなにあるんですか?
「世界でもこんな国はなかなかないと思います」
●「雑な草」って書くじゃないですか。雑草ってどうしてこういう呼び方になったんですか?
「もともと雑草っていうと私たちは、こんにゃろめ! こんにゃろめ!という踏み付けたくなる、いや〜なイメージがありますよね。『雑』ってそんな感じのイメージがあるんですけれども、実は正月に食べるお雑煮も『雑煮(ざつに)』と書きます」
●お〜〜、そうですね!
「おめでたい時に、雑煮とは?と思って調べてみますと、雑という字は『いろんなもの』とか『たくさんの様々なもの』という意味が本来あるようです。
雑草のほうも、名前とか種類とかよくわからないけれども、いろんなものが生えているように見えるということで、名前はわからない草ということで、雑草と呼ばれるようになったんではないかとも言われています」
(編集部注:雑草に定義があるのか、森さんにお聞きしたら、学者さんの間でも認識が違い、確定していないとのことでした。
また、関東圏で特に目立つ雑草として、クズをあげてくださいました。クズ粉になるつる性の植物ですが、3年経った株が1年に伸ばす茎の総距離は、なんと! 1.5キロにもなるとか。確かに鉄塔などに絡みついているのを見たことがありますよね。
ほかにもアレチウリという外来種が日本全国で猛威をふるっていて、庭や畑に見つけたら、すぐに駆除してくださいとおっしゃっていました)
タチツボスミレは、変幻自在!?

※ここからは、森さんの新しい本『庭時間が愉しくなる雑草の事典』をもとにお話をうかがっていきます。庭で植物を育てているかたにとって、雑草は厄介者だと思うんですけど、この本の視点は違いますよね?
「そうですね。どうしても付き合わざるを得ない子たちなんですけれども、付き合い方の考え方を変えると、あんまり汗水たらして駆除する必要もないのかなと、長年の経験でちょっと思った次第でして・・・」
●雑草の寄せ植えですとか、ブーケとしての活用も提案されていて、素敵だなと思ったんですけれども、この本には130種類ほどの可憐な花を咲かせる雑草が掲載されていて、ひとつの種が見開き2ページで紹介されています。写真も豊富でとっても読みやすくて、そしてどれも見出しが素晴らしいですよね!
「ありがとうございます(笑)。そんな言っていただいて」
●その中からいくつか気になった見出しをご紹介しながら、その雑草の特徴などを教えていただきたいと思います。
まずは「春の青空は変幻自在」という見出しありましたよね。これは「タチツボスミレ」ですけれども、ご説明いただけますか?
「スミレの中でも結構、住宅地とかに勝手にやってくるタイプ、なかなか大胆不敵な子なんですね。ちょっと日陰に咲きまして、花心も普通のスミレ、いわゆるニホンスミレと呼ばれているスミレよりも大振りなんですけれども、空色のような、春の青空のような色をたたえた、非常に可愛らしいスミレの種類になっています」
●変幻自在というのは、どういうことなんでしょうか?
「この子も追っかけていくと、本当にカオスでして、住んでいる地域とか標高ですとかによりまして、花とか葉っぱの形を変えたり、色も変えたりするんです。旅先で見るタチツボスミレと、ご自宅の近くで見るタチツボスミレはかなり違っていたりするんですよ」
●地域ごとによって違うんですね。
「そうなんです」
●え~〜不思議!
「これがわかってくると、ほんと旅も面白くなりますし、こんな些細な違いでこんなに雰囲気が変わるんだね、お前の面持ち!ってぐらい変わってくるんで楽しいです」
●ヴァリエーションに富んでいますよね〜。
「はい!」
愛おしい!? ナズナ

※それでは続いて、気になった見出しから「なでたくなるほど愛おしい」。これはナズナですが、そうなんですか?
「これは本当に素晴らしい植物です」
●どう素晴らしいんでしょう?
「とにかく最初は見た感じ、なんかぱっとしない、骨組みだけの、やさぐれって感じの草だな〜みたいに見えるんですけれども、民間薬として長く親しまれてきたものなんですね。例えば、庭仕事なんかやっていますと、(手を)怪我したり転んじゃったり、傷がつきやすいんですけれども、その時に身近にナズナがあったら、葉っぱを揉んで傷口につけるといいんだよ〜なんて、昔は言われてきたんですね。食べても美味しいです」
●春の七草のひとつっていう印象はありましたけれども、そんなに重宝されている重要なものなんですね。「野草世界の野菜です」というふうに本にも書かれていました。やはりそれだけ重宝されているんですね。
「そうなんですよ。ビタミンとミネラルも豊富で、しかも味わい深いのが好きな人はこの根っこが美味しくて、鍋物に入れると出汁が出るぐらい美味しいです」
(編集部注:春の七草のひとつ「ナズナ」はアブラナ科の植物で、別名ぺんぺん草。1月7日に七草粥として食される風習があることは知られるところです。尚、特定できない植物は口にしないでください)
カタバミは可愛いけど、頭にくる!?

●では続いて「小さな時間泥棒」という見出しで「カタバミ」。これはレモンイエローで可愛らしい小ちゃな花ですね。
「はいはい。あっ、ご存知ですか? カタバミ」
●いえ、本で知りました! 可愛い花ですね〜。
「可愛いんですよ〜、ほんとうに(笑)。ハート型の葉っぱを3枚ワンセットにして、小さくこんもり茂るので、本当に頭にくるんですけれども、本当に可愛いんです」
●頭にくるんですか?
「ものすごく頭にきます(苦笑)」
●どうしてですか?
「そこに生えてもらうとすごく薄汚く見える、でも違うところに生えてくれるとすごく綺麗に見えるところで、いちばん嫌なところに(カタバミが)生えてくるんですよ!
だから抜き始めると、あそこにも! あそこにも! 気づいたら、あっちこっちにあるので、いつまでたってもカタバミって終わんないと、多分ガーデニングをやられているかたは、みなさん思われていると思います」
●だから時間が奪われてしまうんですね!
「そうです! 普通、冬になったら、みなさん冬ごもりで、おとなしくされるかたもいらっしゃるんですけれども、雑草の中でもこの子たちは、冬も元気よく芽を出してきて、なんかここにいるとムズムズするって言って取り始めると、1日が暮れてしまう・・・」
●え~〜っ、可愛い花なのに〜。
「可愛いんです(笑)。ほんと可愛いです!」
●あと「果てしない地下の攻防」ということで、「ヨモギ」ですね。
「ヨモギは、最近女性の間ですごく人気なんです。美容ですとか薬用とかで・・・。実際ガーデナー的に見ると、もう地獄ですね!」
●地獄ですか(笑)。どのあたりが・・・?
「カタバミは表に出てくる部分がイライラしてむしって地獄なんですけれども、ヨモギは本領が地下にありまして、根っこを追いかけ回していると1日が暮れてしまうというぐらい四方八方に広がっているので、抜ききれないんですよ」
●果てしないんですね。
「果てしないです。しかも途中でぷつって切れるところを用意しているので、やられた〜って(苦笑)」
●厄介なんですね〜。
「厄介です!」
雑草はタネから育てる
※実際に雑草を自宅の庭や鉢植えで育ててみようと思ったら、どうすればいいですか?
「そうですね。大概みなさん根っこから掘り上げて、鉢植えにされるんですけれども、ほとんどのケースは長持ちせず消えていくことが多いです。私もかなりの雑草を鉢植えにしましたけれども、例のごとく、やっぱり不思議なことに枯れていくんですよ、バタバタ・・・。ですが、タネを撒くとかなりの率で発芽して定着します。
ですので、直植えでパラパラっと(タネを)撒くと、あとで大変なことになりますので、プランターとか鉢植えにちょっとパラパラっと撒いていただいて、ほかの草花と寄せていただくのがいちばんいいかもしれないですね」
●そのタネは、どうやって採取したらいいんですか?
「はい、この時分になってきますと、だいたい植物の茎が枯れて、上のほうに小ちゃいタネがついてきます。それが茶色く変色したものを、小ちゃいポリ袋とかにちょっと入れて、家に帰ってからそのままパラパラ撒いていただければなと思います」
●この時期、どんな種類のタネが採れますか?

「例えば、美味しいものに興味があるかたには、本に載っているやつなんですけれども、『スベリヒユ』というものが今ちょうどタネが採れる時期になります。これもプランターかなんかに撒いていただくと、たいして水やりをせずとも、むくむくと育っていきます。
あともうひとつ、愛らしいのでは、私は個人的に好きなんですけれども『ザクロソウ』。これは小さな植物なのでプランターとかで寄せ植えに使っていただいたりですとか、しばらくここは管理しないから、ほかの雑草が生えてもらうと困るなってとこにタネを撒いていただくと、そこを美しく飾ってくれるんで、この2種はちょっとおすすめしたいです」

足もとに広がる雑草の世界
※長年、雑草を見続けてきて、どんな思いがありますか?
「一歩外出るともうワクワクしかないんですよ。そこら辺の道端の用水路で、あっ!お前、きょうも元気で花咲いたなっていう感じで、いつまで咲くのかな、お前は!とか、びっくりすることは本当に日常茶飯事です。
普通に暮らしていると、うわー! 面白い!ってことってあんまり多分ないと思うんですけど、結構私の場合は日がな一日、うわー! すごい!で、暮らしていけるので実にありがたいです」
●ワクワクしますね! いいですね~。厄介者と言われている雑草でもその植物をちゃんと知ると見方が変わって、世界が広がる感じがしますよね?
「そうなんです。だいたい植物に対する印象は、本でもそうですし、一般的にもそうなんですけれども、よくできた生き物、光合成とかすごいことできる。その光合成ひとつとっても、あいつら、調べるとほんと苦労しているんだなとかがわかって・・・見るからに見すぼらしいなっているやつも、いろいろ苦労しているんだな〜っていうのがわかってくると、面白くてしょうがないです(笑)」
●特に森さんが今気に入っている雑草はありますか?
「時々聞かれるんですけれども、結構満遍なく好きで・・・でもあえて言うなら今は、本当にみなさんの足もとに必ずいるやつなんですけれども、「スズメノカタビラ」という小さなイネ科の植物なんです。これが可愛いなって最近思うようにはなりました」
●どう可愛いんですか?
「畑とかお庭に必ずといっていいほど生えてきて、プランターにも生えてくる、小ちゃいイネ科の雑草なんですね。こんもりしてくるとなんともいじらしい、あの美しい姿で広がってくれるので、それがちょっと微笑ましいというか、華やかな花に飽きると、そういうのにいくのかなとちょっと思ったりもします」
●では最後に、森さんにとって雑草とは?
「雑草とは私にとっての、やはり人生を変えた導き、今もどこに向かっているのかさっぱりわかりませんけれども(笑)、このまま草に導いてもらって、人生を歩んでいけたらなと思っています」
INFORMATION
『庭時間が愉しくなる雑草の事典
~身近にあるとうれしい花、残しておくとヤバイ野草』
この本には、可憐な花を咲かせる130種ほどの雑草が掲載されています。ひとつの種が見開き2ページで紹介されていて、写真も豊富。何より見出しが素敵なんです。ぜひ読んでください。きっと雑草が好きになりますよ。ご自宅にお庭がなくても、一歩外に出て、あなただけの雑草の庭を探してみてください。
SBクリエイティブから絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎SBクリエイティブ :https://www.sbcr.jp/product/4815611644/
森さんの近況については、facebookをご覧ください。
◎森 昭彦さんfacebook:https://www.facebook.com/akihiko.mori.750/?locale=ja_JP