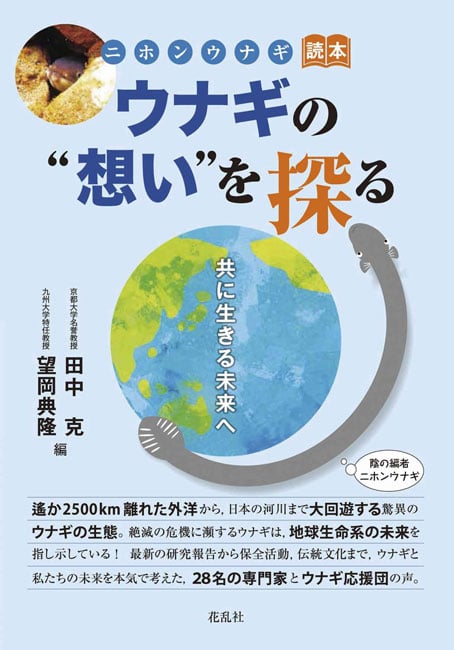2022/8/21 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、自然と人をつなぐ写真家「渡邉智之(わたなべ・ともゆき)」さんです。
渡邉さんは1987年生まれ。現在は岐阜市を拠点に、人の営みの近くで暮らす生き物を撮影。また、ニコンカレッジ名古屋校で講師としても活躍されています。そして先頃『きみの町にもきっといる。となりのホンドギツネ』という写真絵本を出されました。
きょうは、私たちのすぐそばで暮らしているホンドギツネの繁殖、子育て、そして人との関係など、あまり知られていない生態などうかがいます。
☆写真:渡邉智之

自然と人のつながり
※渡邉さんは「自然と人をつなぐ写真家」と名乗っていらっしゃいますが、そこにはどんな思いがあるのでしょうか?
「今の時代って人と自然がどうつながっているのかが、すごく見えにくい時代だなって感じているんですね。そういう見えにくい、自然と人のつながっている部分を、なんとか見える化できないかなっていうことを考えています。
自分からは動物写真家って名乗らないようにしているんですね。動物写真家と名乗ってしまうのは、ありではあるんですけど、僕は動物だけを撮りたいわけじゃないんです。動物と人のつながっていく様子だったり、動物同士のつながっている部分だったりとか、そういう見えにくい部分を表現していけたらなと思っているので、そういう意味で”自然と人をつなぐ写真家”と名乗っています」

●テーマが「自然と人のつながり」ってことなんですね。
「そうですね。なんとなく僕の中のイメージとして、自然と人をつなぐと自分では言ってはいるんですけど、僕の中で人という位置も、ほかの生き物と変わらなくて、結局自然の中で同じように生きている生き物なんですね。特に日本の自然なんかだと、野生動物の生態を撮るにしても野生動物だけで完結するわけじゃなくて、必ずそこには人の気配がどこかしらにあるんですね。
だから自然と人の関係性だったりとか、自然と人をつなぐというふうにわけていますけれども、自然の中に人は含まれているよっていうのは常に感じていますね」
●都会に暮らしていると、自然とつながっているんだなっていう意識は薄くなってしまう印象はあるんですけど、その辺りはいかがですか?
「そうですよね。田舎に暮らしていても、いま僕、岐阜市に住んでいますけど、県庁所在地で名古屋から20分くらいの場所なので、それなりに都会ではあるんです。
でも、そういうところに暮らしている人たちと話をしても、自然とそんなに関わっていなかったりとか、自分たちの身の周りでどういう自然現象が起こっていて、自分たちの暮らしにどういうふうに影響があってとか・・・逆に自分達の暮らしが野生動物、自然に対してどういうふうに影響しているのかを、気づかなかったり知らないっていうかたは、ものすごくいっぱいいますね」
昔から身近にいるキツネ
●先頃発売されました写真絵本『きみの町にもきっといる。 となりのホンドギツネ』、まさに自然と人のつながりがテーマになっているなと感じました。

私もこの写真絵本を読ませていただいて、遊歩道だったり公園だったり、すぐそばでキツネが暮らしていることにすごく驚いたんですね。ほとんどの人間は気づいていないとも書かれていましたが、こんなに人の近くにキツネっているんですね!
「そうなんですよね。みなさん、キツネって聞くと北海道をイメージするかたがすごく多いんですよ」
●はい! まさに私もそう思っていました。
「まさにそうですよね。たぶんそういうかたはすごくいらっしゃって、北海道にしかキツネはいないと思っているかたもいるんですね。
でもよくよく考えると、お稲荷さんのキツネだったりとか、キツネの能とかお祭りで売っているお面だったりとか、新美南吉(にいみ・なんきち)の童話『ごん狐』だったりとか、身近な場所にキツネに関する文化とか民話とか、そういうのが実はいっぱいあるんですよね。
そういう文化が生まれてきたっていうことは、つまり昔から人とキツネは常に近くにいて、なにかしらの関わりがあったことの証拠でもあるんですよね。だから昔の人たちは、おじいさん、おばあさんの世代の人たちはよく、キツネに化かされたっていう話を本当に真剣にするかたもいらっしゃいますよね。でも、今の僕たちってキツネに化かされたってほとんど言わないと思うんです。
それはやっぱり科学がどんどん進んでっていうのもあると思いますけど、僕たちのキツネを感じる、気配を感じることの力がどんどん弱くなっているっていうか、そういうのもあって、キツネはずっと身近にいるんだけど、キツネの存在にどんどん気づけなくなっているような感じはするんですよね」
(編集部注:写真絵本に掲載されているホンドギツネの写真は、主に岐阜市の渡邉さんの住まいからすぐ近くの河川敷で撮ったものだそうです)

ホンドキツネの繁殖、子育て
ここで、主人公ホンドギツネがどんな動物なのか、ご説明しておきましょう。
ホンドギツネは世界中に広く分布しているアカギツネの仲間で、日本では沖縄を除いて、本州より南に生息。見た目は柴犬(しばいぬ)をほっそりさせたくらいの大きさで、体重は4キロから7キロほど。人のそばで暮らしていても警戒心が強く、人前に姿を見せることはほとんどないそうです。
北海道に生息するキタキツネも同じアカギツネの仲間ですが、ホンドギツネよりも体が少し大きく、足元がくつ下をはいたように黒い個体が多いとか。
キツネの特徴としては、走るのが得意で、草刈りされた場所や、見通しの良い畑などを好んで狩りをする、ということなんですが、耳がいいので、獲物となる虫や小動物の出す小さな音を聴いて狩りをするそうです。
※ホンドギツネの繁殖シーズンはいつ頃なんですか?

「早いと11月ぐらいから繁殖期なってきますね。繁殖期になると面白いのが、オスが”コンコン”って鳴きます。”コンコン、コンコンコン”って鳴くんですね。これが実はオスがメスを探して、自分はここにいるよ、メスはどこだい? ってアピールしている時の声なんですよ。
そういう声を11月くらいの夜に、河川敷や堤防で待っていると結構、聴こえてくるんですよね。その声を聴いて、メスが、あ! オスがいたって分かって、オスとメスが出会えるわけですね。だいたいそれが11月ぐらいから始まって、12月の末とか1月とかに交尾をして、早いと2月の末から3月の中旬くらいに巣穴の中で子供を出産します」
●何匹くらい産むんですか?
「2匹から多いと5匹ぐらいですね」

●この写真絵本には子育ての様子なども掲載されていましたけれども、メスとオスで一緒に子育てするっていう感じなんですか?
「そうですね。キツネはオスも子育てに参加する動物なんです。オスが子育てに積極的に関わる動物って結構珍しくて、日本ではタヌキとキツネしかいないですよ。ほかの野生動物はメスが主体で子育てをするんですね。キツネの場合だとオスが子供に食べ物を持ってきたりとか、おもちゃを持ってきたり遊んであげたりとか、そういうことをしますね」
●基本的には出産も子育ても巣穴で行なわれているってことなんですね。
「はい、そうですね。巣穴も常に同じ巣穴を使うわけではなくて、お母さんのメスの縄張りの中に巣穴がいくつかあるんですよ。だいたい数十メートル置きぐらいにポンポンポーンとあって、なにかあると巣穴の引越しをして子育てをするっていう感じですね」
(編集部注:渡邉さんによると、いくつかある巣穴の、どれを使っているのかを入念な観察で突き止めても、警戒心がとても強いので撮影が難しく、川をはさんで対岸にブラインドテントをはって、やっと姿を見せてくれるそうです)
※ホンドギツネは夜行性なんですよね?
「はい、夜行性と言われています。基本的に夜に活動するんですね。なんだけど、夜じゃなくても昼間とか、例えば冬だと、雪が降ったあとにちょっと早い時間にキツネが出ていることもあります。
オスがメスを早い時間から探し出したりとか、子育ての最中だと朝とか昼間とか、お母さんが朝昼晩みたいな感じで(子ギツネに)お乳をあげに来たりするので、夜行性と言われているけど、完全な夜行性ではなくて、昼間でも結構動いています」
●撮影自体は、多いのは夜っていう感じなんですか?
「そうですね。撮影自体は、昼間にそういうふうに見られるのは、そこまで多いことではないので、ほぼほぼ夜の撮影になります」
(編集部注:ホンドギツネの撮影は、観察が8割、そして夜の撮影が多いため、光をどう作るのかが、とても難しいと渡邉さんはおっしゃっていました)

キツネが腰を抜かした!?
※ホンドギツネの撮影をされていて、思わず見入ってしまった瞬間はありましたか?
「いっぱいあるんですけど・・・面白かったなぁと思ったのは、キツネが腰を抜かした瞬間があって(笑)、人でも腰を抜かすってあんまり見たことないじゃないですか。たぶん一生見ない人もいると思うんですけど、キツネが腰を抜かした瞬間を見たことがあります。
2匹の子ギツネが夕方、河川敷の草やぶから出てきていて、一段落してちょっと休憩しているような感じでいたんですけれども、そこに突然別の子ギツネが草やぶからぱーっと出てきたんです。
それに2匹の子ギツネがびっくりして飛び跳ねて、1匹のキツネはほんとに立てなくなっちゃったっていう、本当に腰を抜かして、腰が砕けちゃってヨタヨタしていて、しばらく立てなくて・・・こんなことあるんだなという感じですよね(笑)。人ですら(腰を抜かした瞬間を)見たことないのに、野生動物の腰を抜かす瞬間を見てしまったと、それはちょっとびっくりしましたね〜。

ほかにも面白いこととしては、2013年に観察をしていた時に、僕のことを全然気にしないオスがいたんですね。その子は僕に対してすごく興味があるらしくて、毎日のように彼らのところに会いに行くので、彼らが僕のことを覚えてくれるんですよ。
その中でもその1匹の子は僕にすごく興味を持っていたので、僕が堤防の上で待っていると、草やぶから出てくるんですよ。出てきて、堤防の上に僕を見つけると、わざわざ堤防の上にあがってきて、なぜか僕の横に座って・・・本当に面白いですよね。なんか絵本の世界みたいな感じです。
僕のすぐ横に座って、一緒に夕陽を眺めたりとか、時間的にどんどん車が渋滞していく時間なので、渋滞する車を一緒に見ていたりとか・・・同じ風の匂いをすぅーっと、あ! 同じ匂いを今嗅いでいるな、みたいなことがあったりとか。それが住宅街のすぐ横であったので、そういうところに絵本みたいな世界があって、それは本当に忘れられない経験だなと思います。

子ギツネも遊び好きなんですけど、大人のキツネも遊び好きなんですよ。キツネって、オスが長い棒をくわえて走っているあとを、後ろからメスが追っかけて、追いかけっこをしたりとか、そういうことをするんですよね。結構遊び好きな姿、大人でも子供でも遊んでいたりするのを見ると、なんか人間との共通点じゃないけど、そういう部分も感じて、なかなか面白いですね」
人間をよく見ているキツネたち
※ホンドギツネたちは、人間のそばで健気に、そしてしたたかに生きているような気がするんですけど、渡邉さんはどう思いますか?
「彼らが人のそばで生きることのひとつ大きな理由として、やっぱり食べ物があると思うんですけど、食べ物が比較的手に入りやすいと思いますね。人間がゴミとして出している残飯とかも食べるし、作物とかも食べるし、今の時期は、トウモロコシ好きなんで、トウモロコシもめちゃくちゃ食べるんですよ。
そういう食べ物を食べたりとか、あとは畑だったらネズミがいっぱいいるので、ネズミを狩っていたりとか。人の近くにいるとキツネが生きていく上で、食べ物が比較的得やすいっていうのはあると思うんですね。
だから人の近くをずっと彼らは離れないんだろうと思うんですけど、逆にそういういいこともあれば、(キツネが)車にひかれてしまうとか、そういうことも結構あるんですよね」
●可哀想な状況を目にすることも多いですよね。
「そうですね、結構ありますよね。」
●開発も含めた自然環境の変化は、やはり野生動物には厳しいと感じますか?
「そうですね。開発もちょっと難しいところですけど、突然ぐっと大きな変化で、彼らの暮らしが変わることをすごく感じていますね。そんな中でも彼らは上手いこと、人の暮らしをよく見ていて、どういうふうに自分たちがその状況に対応していけるのかっていうのを、常に考えて生きているような感じはするんですね。

テトラポットが河川敷にばーっと置かれて、キツネの寝床とか潰れる時があったんですけど、そういう工事のあとでも子ギツネたちは、そのテトラポットの上で翌日には跳ね回って追いかけっこしていたりとか、そういうしたたかさもすごくあると思いますね。確かに開発で彼らの暮らしがどんどん変わっていくっていうのもあるんですけど、同時にそれをうまく許容していって彼らの暮らしもどんどん変化しているなってことは実感していますね」
●改めてホンドギツネを通して見えてきたもの、感じたことってなんでしょうか?
「ずーっと見ていて面白いなって思うのが、彼らって人のことをよく観察しているんですよ。人が気づかないだけで、人が散歩している様子をじーっと見ていたりとか、犬を散歩させている姿を見ていたりとか・・・そういうのを草陰からじーっと観察していて、人がいない時間に合わせて出てきたりとか、草刈りしたりすると、そこで狩りをしたりとか、人の暮らしをよく見ているんですね。
すごくよく見ているからこそ、僕たちのことをすごく理解しているんですよ、彼らって。それがまず面白いなって思うんですけど、逆に僕たちって彼らのことをどれくらい知っているのかなっていうのは常に思いますね」

INFORMATION
渡邉さんの写真絵本をぜひご覧ください。これまでほとんど知られることのなかった、ホンドギツネの生態に迫る初めての写真絵本です。
こんなに身近にキツネがいることに驚きます。河川敷や畑、公園などで、健気に生きている姿が素晴らしく、子ギツネたちの愛くるしい写真に思わずにっこりしてしまいますよ。ホンドギツネたちは、人の暮らしにひっそりと寄り添いながら、きょうも生きていて、あなたをすぐそばで見ているかも知れません。ぜひお子さんと一緒にホンドギツネの世界を覗いてみてください。「文一総合出版」から絶賛発売中です。
◎「文一総合出版」HP:
https://www.bun-ichi.co.jp/tabid/57/pdid/978-4-8299-9017-9/Default.aspx
渡邉さんのオフィシャルサイトもぜひ見てくださいね。ホンドギツネ以外にタヌキやムクドリなどの写真も載っていますよ。
◎オフィシャルサイト:https://wtnbtmyk47.wixsite.com/watanabetomoyuki