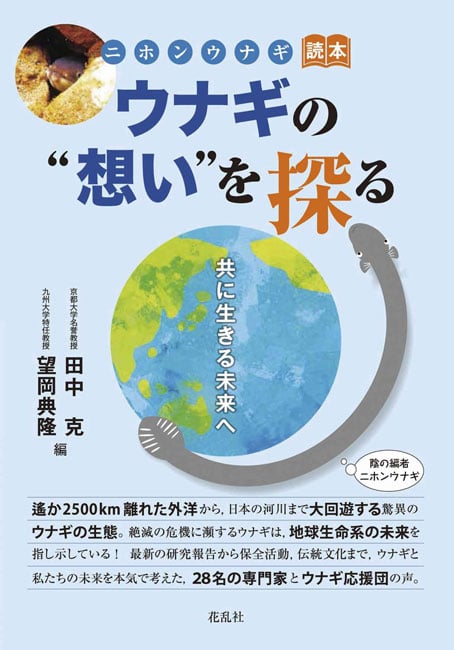2022/9/11 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、京都女子大学・教授、
そして動物行動学者の「中田兼介(なかた・けんすけ)」さんです。
中田さんは1967年、大阪生まれ。子供の頃から生き物好きだったそうですが、ご本人曰く、昆虫少年ではなく、普通の子供だったとか。専門は動物の行動学や生態学で、おもにクモの研究をされていて、「クモ博士」として知られています。
そして先頃、中田さんも所属する「日本動物行動学会」から動物行動学を広める活動や以前出版された『クモのイト』という本が評価され、賞を授与されています。
きょうはそんな中田さんに、生き物たちの摩訶不思議な生態や、クモの驚くべき営みのお話などうかがいます。
☆写真協力:中田兼介、ミシマ社

「りくつ」に込めた思い
※中田さんは先頃『もえる! いきもののりくつ』という本を出されました。本のタイトルに「りくつ」と入れたのは、どうしてなんですか?
「生き物って、やっぱり僕らと全然違いますやん。僕ら人間は、なんとなく自分と違うものを、ちょっと遠ざけたりとか下に見たりとか、そういうことをしがちでしょ?
やっぱりそれって生き物好きとしては悲しいじゃないですか。違うものでも受け入れてもらおうと思ったら、相手もちゃんと理由があって、合理的なもんなんだっていうことがわかれば、ちょっと違うから嫌だ、みたいなところが和らげられるかなと思って、そこの部分を”りくつ”っていう言葉に込めたんですけどね。
全然違う生き物でも、相手がなんでそうしているのかがわかれば、ちょっと近づけるじゃないですか。そういうことです。
人間でもそうでしょ? 全然知らん人がやってきて、なんかわけのわからんことをやっていても、話を聞いてみると、この人こういうことしてんねんやって思ったら、ちょっと近づけるかなっていう感じですね。そういう言葉を“りくつ”っていう言葉に込めたんですね。理屈って、ちょっと堅苦しいなみたいに思われるところがありますけど、まぁそう言わんとっていうところですね」

●この本では81編の生き物たちの面白い生態が紹介されています。その中から気になった生き物についてうかがっていきたいと思います。まずはタツノオトシゴが”イクメン”とありましたが、そうなんですか?
「はい、オスのお腹に育児嚢(いくじのう)っていう小さな袋があるんです。で、メスがその袋の中に卵を産み付けるんです。そうすると、卵からかえって小さなタツノオトシゴが育つまで、時間が掛かるんですけど、その間はお父さんがお腹の中で子供を守っている、育てるっていうんですかね」
●オスが妊娠しているみたいな感じっていうことですか?
「そうです、そうです。で、お腹の中でかえると、ある程度大きくなったタツノオトシゴがたまってくるんだけど、それをギュッとお腹から噴き出させるんです。だからオスが出産するっていうんですかね(笑)」
●すごい! そういう世界がタツノオトシゴにはあるんですね。
「魚の中にはオスが子育てをする、卵を守るっていう種類は結構いるんです」
●メスはその間は何をしているんですか?
「メスは、ほかのオスを探しに行きます」
●え!? そうなんですか。
「だから、逆ですよね(笑)」
卵が育つ場所で性別が変わる!?
※新しい本には、中田さんがご自宅で飼っているイシガメの話が載っています。卵から孵化する子ガメがオスになるのか、メスになるのか、何が作用して、オス・メスが決まるのか教えていただけますか。

「カメの仲間って、特にイシガメとかそうなんですけど、卵が育つ場所の温度でオスになるかメスになるかが決まるんです」
●温度が高ければ・・・?
「高いとメスで、低いとオスになります。これ”温度性決定”って言うんです。温度によってオスかメスかの性が決まるっていう意味なんですけど、結構こういうことをする動物はほかにもいて、爬虫類では割といますし、そのほかにも結構いますね」
●例えばオスが欲しいな、なんて思ったら、卵が置かれた場所の温度を低くすれば、オスが産まれる可能性が高いってことですか?
「そうですね。うちで産まれてくる子ガメって、結構オスばっかりなんですよ」
●ということは、温度が低いってことですか?
「多分温度が低いところに産んでいるんでしょうね。ここ3年くらい毎年、子ガメが産まれているんですけど、最初の頃はオスばっかりやったんです。最近ちょっとメスが混じってきているなっていう感じで、暑い夏やからかな〜とか・・・本当かどうかわかりませんけどね(笑)」
●面白い〜! 温度によってどうして性別が変わるんですか?
「それは卵が成長していく時に、そうなるようなメカニズムがあるんですけどね。オスになるのかメスになるのかっていうのは、僕ら人間は遺伝的に決まっていますけど、そんなにカチッとしたものじゃないんです。
遺伝的にはっきり決まっているっていうわけでもないですし、魚の中には性転換するものもいて、若い時はメスだけど、歳をとってくるとオスになるとか、体の中が作り変わるとか、そういうことをするのもいるので、僕らが思っているほど(性別は)ガチっと固まっているものじゃないんです」
つられ「あくび」には意味がある!?
※新刊の『もえる! いきもののりくつ』には「つられあくびのライオンたち」という話が載っていましたが、動物もつられてあくびをするんですね。

「そうですね。結構そういうことが知られている生き物もいますね。猿の仲間とか、豚とか犬とか、うつるみたいですね」
●あくびしているのを見ると、別に眠いわけではないのに勝手に出ちゃいますよね。
「そうですね。そういう動物ってみんな社会で暮らしているから、なんていうか気持ちを同調させるっていうかな、そういう効果があるんじゃないかっていうことを言ってる人もいます」
●ライオンもそうなんですね。
「ライオンもそうだっていう話で、ライオンの場合は誰かがあくびをしたら、ほかにうつるだけじゃなくて、立ち上がったら一緒に立ち上がることもあるみたいで、やっぱりそれが同調の、みんなで気持ちを一緒にするような効果があるんじゃないかっていう、そういう話です。
ただね、あくびをなんでするかって、ほかにもいろんな説があって、脳を冷やすっていう話もあるらしいんですよ。大きく息を吸うでしょ。そうしたら冷たい空気を取り入れて喉を通すと、喉に血管が走っているから、その血管が冷やされて脳が冷やされるという話があってね。脳の大きな動物ほど、あくびがたくさん出るっていう話もあって・・・いろいろあるみたいなんですけどね」

●へ〜! あと、シマウマのシマの謎、これもすごく意外だったんですけれども、ぜひこちらも説明をお願いします。
「シマウマになんでシマがあるかって不思議じゃないですか。昔は、彼らサバンナにいるから、草がいっぱい生えていて、草の陰に自分の身を隠すために役立つんちゃうかっていうようなことを言われていたらしいんです。
ところが調べてみたら、病気を媒介するハエがいるところにシマウマがおるでっていう話があって、ひょっとして病気にならないために、ハエを寄せ付けないためにシマができたんちゃうかって考え始めたんですって。なんでそんなことを思い付いたんか、僕も分からないんですけど(笑)、そういうことを思い付いた人がいて、調べてみたらシマ模様にはハエがとまりにくいらしいんですよ。だから病気になりにくいって効果があるみたいですね」
●シマシマ模様は虫対策ってことですか?
「そういう話らしいんです。ちょっと不思議ですよね。なんか聞いたところによると、黒い部分と白い部分があると、太陽の光を受けて温まるところと、あんまり温まらないところってできるでしょ。それで微妙な気流が生じてハエがとまりにくくなってんちゃうか、みたいなことを言ってる人もいるんです。
ホンマかどうか、こういうのっていろんな論文に書かれているんですけれども、論文に書かれているだけで、即本当かっていうとそれは必ずしもそうではないので、なるほど、こんな説もあるんだなくらいの形で聞いとく感じですね」
クモのギョッとする生態
※中田さんはおもにクモを専門にされているということですが、具体的にはどんな研究をされているんですか?
「最初の頃は網(蜘蛛の巣)の作り方をずっとやっていたんですけど、最近は交尾行動で、なかなかエグいことをするのがいるんですよ、クモの中には。ギョッとするような交尾行動を研究しています」
●クモは、私は正直苦手なんですけど(笑)、クモの研究はどうですか、面白いですか?
「そうですよね(笑)。(クモの研究は)面白いですよ、結構複雑なことをいっぱいしてくれるので、見ていて飽きないですね。網を張るクモはどこかへ行かないんですよ。だから同じ場所で割と長いこと1匹を見続けることができて、いろんなことがわかるんですね」
●そもそもクモは、どうして巣を作れるんですか?
「なんて言うんですか・・・もともと体の中にそういうプログラムを持っているみたいで、体から糸を出すんですけど、その糸を組み合わせて、自分の種類に応じた形の巣を作るんですね。だからどうしてっていうのは・・・これで答えになっていますかね(笑)」

●縦糸と横糸で強度が違う、なんてことも聞いたことがあるんですけど・・・?
「そうですね。いろんな種類の糸をクモは出すことができて、種類によっていろいろなんですけど、最大で7種類の糸を持っているんです。その中には強い糸もあるし、ネバつくのもあるし、すごく伸びるっていうような糸もあって、用途に応じて使い分けているっていう感じなんですね」
(編集部注:クモの糸の特性を研究し、微生物を使ってタンパク質素材を量産、そして作られた糸を使った繊維製品が開発されているそうですよ。今後も注目です)
●先ほど中田さんが、ギョッとする行動をするなんておっしゃっていましたが、どんな行動をするクモなんですか?
「オスとメスが交尾をするんですけど、その時にオスがメスの交尾器を壊して、今後使えなくして去っていくんです。
オスの側からすると、今交尾したメスが自分の子供を確実に産んでくれるかって分からないんですよ。自分が離れたあとに別のオスがやって来て交尾すると、このメスが産む卵がほかのオスの卵になっちゃうかもしれない。それを防ぐために交尾器を壊しちゃうんです。使えなくしちゃうんです。
そうすると、そのあと交尾はできなくなるんですけど、卵は産めるので、自分が後尾したあとの子供は、全部自分のものみたいな・・・(笑)」
●へぇ〜すごい〜!
「ちょっと、人間の目からするとギョッとするんですけど・・・」
※先ほどクモの糸のお話がありましたが、その強度はどれくらいなんですか?

「クモの糸は自然界にあるやつは、めちゃくちゃ細いので・・・あの細いのがそれなりの太さになっていれば、結構強いんです。鋼鉄ぐらいの強さはあります。ここで強さって結構面倒臭くって、切るのにどれぐらいの力が必要かっていう話で言うと、鉄と同じぐらいなんですよ」
●すごい強度ですね!
「それだけじゃなくて、クモの糸は伸びるんですよ! 切るのに力がいるのに加えて伸びるんです。
伸びるとなにがいいかと言うと、虫が飛んできた時にぶつかりますよね、糸に。ぶつかった動きを止めるためには、鉄やったら鉄自体が壊れる割れるとか、そういうことになるんですけど、糸は伸びるから、ぷにょーんって変形して、また伸びたもんが元へ戻る時に動きを止められるので、糸は切れずに止められるんですよ。
これ結構クモにとっては便利で、昆虫がぶつかるたびに糸が切れて、網が壊れていたら餌が獲れなくなるんで、そこがいいところですね」

よく光る糸で作られているそうです。昆虫をおびき寄せる働きがあるらしいと
クモ博士・中田さんに教えていただきました。クモの世界は摩訶不思議!
(編集部注:クモの糸が強くて伸びるというお話で、映画のスパイダーマンを思い浮かべたかたもいらっしゃると思いますが、クモ博士の中田さんは2012年公開の『アメイジング・スパイダーマン』のワールドプレミア、そのYouTubeの生中継にコメンテーターとして登場されたそうですよ。映画好きでクモ好きな中田さんだからこそのエピソードですね)
人間の外側にものさしを持つ
※生き物の生態を知ることは、人間そのものや、人間社会を知る手がかりにもなりますよね?
「なんて言うんかな・・・自分のことを知りたいって思った時に、何かものさしってっていうか基準が必要だと思うんですよ。自分のことを知りたいと思った時に、ほかの誰かと比べてみて、あっ、僕はあの人と比べて、ここが違うから僕はこういう人間なんやと思うと思うんですね。
人間ってなんやろなと思った時に、人間じゃないものを見て比べる、そういうことをすることが、自分自身を、人間を、理解するひとつのやりかたになるんちゃうんかなと思っているんです。
生き物のことを知るっていうのは、人間の外側に何かものさしを持つっていうのかな、そういうことになるんかなと思っています」
●中田さんご自身も生き物たちの行動から学ぶことも多いですか?
「あ〜いやぁ〜、生き物は僕らと違いますから、学ぶとかっていうんじゃないです。生き物がこういうことするから、僕らもっていうのは、それはちょっと違うと思うんです。彼らは彼らだし、僕らは僕らだと。違いがあって、違いがあるけど同じ環境、地球をシェアしている仲間ですからね。そういうものとして、自分たちを位置付けられるようになればいいなって思いますけどね。学ぶっていうのはちょっとなんか違いますね」
●では最後に長年、生き物たちを見てきて、どんなことを感じられていますか?
「なんだろうな・・・いろいろあるんで・・・生き物に対してというか、自分の人生が短すぎるなとよく思います。
僕30年以上も研究しているんですけど、それでわかったことなんて、本当にちょっとしかないんですよ。いろんな生き物がやっていることのちょっとだけしかわかっていなくて・・・まだまだたくさんあるのにね。
自分の寿命が1万年ぐらいあったら、もっと面白いことがわかるのにな〜と思っています」
INFORMATION
中田さんの新しい本をぜひ読んでください。世界の動物行動学者たちの最新研究をもとに、中田さんがわかりやすく解説した、生き物の不思議で面白い生態が81編、載っています。中田さんのキャラクターも垣間見られて、楽しく読めますよ。各解説の最後にQRコードが載っていて、その話のもとになっている論文にリンクしています。
「ミシマ社」から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎「ミシマ社」HP:https://mishimasha.com/books/9784909394729/
動物行動学に興味を持ったかたは中田さんも所属する「日本動物行動学会」のサイトもご覧ください。
◎「日本動物行動学会」HP:https://www.ethology.jp/