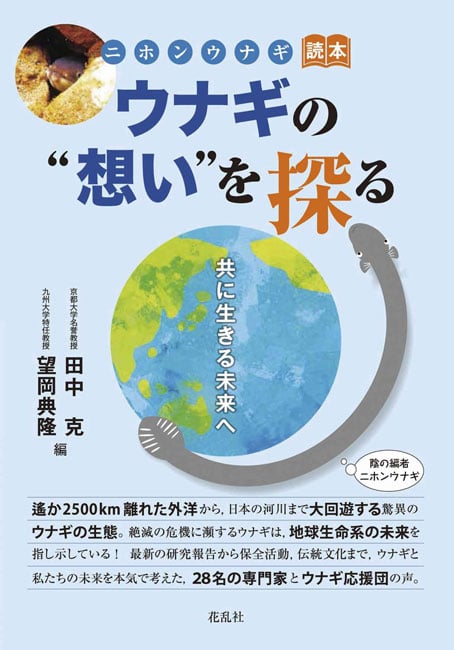2022/9/25 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、中部大学・准教授で、
サボテン博士の「堀部貴紀(ほりべ・たかのり)」さんです。
堀部さんは岐阜県出身。名古屋大学大学院を修了後、1年ほど岐阜放送・報道部に勤務。その後、研究の道に戻り、現在は中部大学でサボテンを研究中。日本では数少ないサボテン博士でいらっしゃいます。
堀部さんがサボテンを研究するようになったきっかけは、日本でいちばんサボテンの生産量が多いとされている愛知県春日井市のお祭りで、食用のサボテンに遭遇したこと。名古屋大学で園芸学や植物生態学を専攻していた堀部さんは俄然、サボテンに興味がわき、また、国内でほとんど研究されていないことを知って、春日井市にある中部大学にいれば、サボテンのサンプルがたくさん手に入る、そう思い、2015年からサボテンを専門に研究されています。
そして先頃『サボテンはすごい! 過酷な環境を生き抜く驚きのしくみ』という本を出されました。
きょうは、ほとんど知られていないサボテンのトゲの秘密のほか、いま世界が注目している、地球を救うかも知れない、サボテンの計り知れない可能性についてうかがいます。
☆写真協力:堀部貴紀

トゲの、驚きの役割
※園芸用として人気の多肉植物がありますが、サボテンも多肉植物、ですよね?
「はい。サボテンも基本的には多肉植物です。ただし、多肉植物って結構いい加減な言葉でして、学術上の定義がないんですね。こうだったら多肉植物という定義がなくて、だいたい水っぽくて膨らんでいたら、多肉植物っていう言葉の使われ方をしているんです。
でもサボテンの中には見た目が樹木みたいな、木みたいなサボテンもいるので、多肉植物じゃないサボテンもいます」
●へぇ~、そうなんですね。アロエはサボテンじゃないんですか?
「よく言われるんですけど、アロエはサボテンじゃないんですね。で、サボテンは何か? ってことなんですけど、サボテンは、バラ科とかイネ科とかあると思うんですけど、サボテン科っていうのがあって、サボテン科に含まれるやつをサボテンと言います」

●サボテンは世界に何種類ぐらいいるんですか?
「だいたい最近の研究だと、2000種類ぐらいですかね。ただし、品種がいろいろあって、イチゴでも『とちおとめ』とか『あまおう』とかあると思うんですけど、そういう品種を入れると、大体8000品種と言われています」
●そんなにあるんですね~。サボテンの原産国はどちらになるんですか?
「サボテンの原産国は、だいたい南北アメリカですね。結構広くて、北はカナダ南部から南はアルゼンチン・パタゴニア地方の先端までですね。南北アメリカ全体にサボテンはいます」

●そうなんですね~。サボテンの大きな特徴といえば、トゲですけれども、あれは何ですか?(笑)
「あれは葉っぱが変化したものだと言われています」
●葉っぱ!?
「昔、サボテンのトゲは葉っぱだったんですけど、葉っぱがだんだんと変化していって、葉っぱになったと考えられています」
●トゲの役割って何ですか?
「実はいろんな役割があって、まずは動物から食べられないように体を守っているよ、っていうのもあるんですけど、ほかにも例えば、強い光から身を守るカーテンみたいな役割をしたりですとか、あと高温とか低温から身を守る毛布みたいな役割をしてたりとか・・・まだまだあって、トゲから蜜をだしてアリを呼んだりとか、あと空気中の水を吸着するような機能も報告されています」
●ほぉ~、そうなんですね。サボテンは独特な形をしていますけど、どうしてあんな形になったんですか?
「まずサボテンは、丸っこいイメージがあるかと思うんですけど、あれはまず体の中に水を貯めているんですね。より具体的にいうと、茎の中に貯水組織といって、水をいっぱい貯める細胞があるんです。それがいっぱいあるから、ああいう丸くて水のタンクみたいになっているんですね。なので、長い期間、雨が降らなくても平気なんです。これまで長いものだと6年間、雨が降らなくても枯れなかったという報告がありますね」

体の一部からも繁殖!?
※植物のほとんどは花を咲かせ、タネを作って自分たちの生存範囲を広げていますが、サボテンはどうやって増えていくんですか?
「ほかの植物と同じようにまずタネで増えます。花が咲いて果実がなって、その中にタネが入っていて、そこから増えるんですけど、もうひとつ特徴的な増え方があって、植物体の一部からも繁殖するんですね。
具体的にはサボテンの枝とか茎の一部がぽろっと落ちて、そこからまた大きくなるんです。そういうのを『栄養繁殖』って言うんですけど、イモとか球根みたいなイメージですね。ぽろっと落ちた茎とかには水分がたくさん含まれているので、タネよりも生存する確率が高くなるんですね。タネはやっぱり小さいし、水もぜんぜん含んでいないけど、植物体の一部ですといっぱい水があるから、生存する確率が高いってことになります」
●サボテンの花は毎年咲くわけじゃないですよね!? 毎年咲くんですか?
「一応、毎年咲くんです。あまりサボテンの花が咲くイメージはないと思うんですけど、花が咲くまでに時間がかかるんです。種類にもよるんですけど、例えば”桃栗三年柿八年”という言葉がありますけれども、サボテンだと長いものだと最初の花が咲くまでに30年ぐらいかかります」
●だから花のイメージがあまりないんですね。
「そうなんですよね。でも1回咲くようになったら、毎年だいたい咲くんですよ」
●受粉は昆虫ですか?
「自生地ですとハチとか、夜咲く花だとコウモリとか蛾とか、まあやっぱり昆虫が多いですね」
●過酷な環境の自然界で、どうやって増えているのか、ちょっと想像がつかない世界なんですけど・・・。
「そうですよね。まあ普通にタネで増えるのもありますし、それこそトゲを使って、ほかの動物にくっついて移動していくサボテンもいるんですよ。
アリゾナ砂漠にいるやつなんですけど、“ジャンピング・カクタス”って呼ばれていて、ちょっとでも触るとトゲで体にくっ付いてくるんですよ。体の一部がぽろっと取れて、それを取ろうとすると、またその手にくっ付くので、ジャンプしているみたいだから、ジャンピング・カクタスっていうんですね。
そういうやつなんかは、本当にすれ違った動物にペタッとくっ付いて運ばれていって、別の場所で落ちて、根を張って成長するみたいな育ち方をするやつもいます。たくましいですね」
巨大なサボテンの林!?

※新しい本に、6〜7年前にアリゾナ州の国立公園に調査に行った話が載っていました。なぜアリゾナに行くことにしたんですか?
「それは、サワロサボテンっていうほんとに西部劇に出てくるような、ザ・サボテンがアリゾナ砂漠にいるんですね。それを見たかったからです」
●本の表紙になっている、大きなサボテンが林のようになっているのがその場所ですよね?
「そうです、そうです! アリゾナのサワロ国立公園っていう所ですね」
●実際にこの大きなサボテンをご覧になっていかがでしたか?
「いや〜もうびっくりというか感動ですよね! 普段そんなに生き物を見て感動するほうではないんですけれども、本当に初めて圧倒されて感動しましたね。おっ! すごいみたいな」

●大木ですよね、このサボテン!
「そうなんです。乾燥地なので木があまり生えていないんですね。さっきの大きなサワロサボテンは10メートル以上になるものも多いんですけど、それが何千本と見渡す限り生えていてなかなか感動ですよ。日本の人にも行ってほしい、本当に!」
●世界最大のサボテンが、このサワロサボテンになるんですか?
「昔はそのサワロサボテンが世界で最大だって言われていたんですけど、実は今は世界最大じゃないんです。
当時1996年には、17.5メートルあったので、ギネス記録を持っていたんですけど、2007年にほかのサボテンが19.2メートルの記録を出して、それは和名でいうと武倫柱(ぶりんちゅう)っていうサボテンがいて、(サワロサボテンと)同じような見た目のサボテンなんですけど、そっちが今は世界最大だと言われています」
●それはどこにいるんですか?
「それもアリゾナに生えているんですね。サワロと同じような場所に生えていて、見た目はそっくりですね」
●そんな大きなサボテンがいるんですね~。
「いやもう~びっくりしますよ! 近くで見たら」
●サワロサボテンに巣を作る鳥がいるんですよね?
「はい、キツツキですね。あとフクロウなんかも棲んでいますね。というのも乾燥地に行きますと木がないもんですから、サボテンがいちばん大きな植物になるんですね。なので、キツツキなんかがサボテンの幹に穴を開けて巣を作って、そこに棲んでいるんです」
●サボテンにキツツキ!?
「実際にソノラ砂漠に行きますと、サワロサボテンは穴だらけなんですよ。いたるところに穴が開いていて、その中に鳥が棲んでいるんですね。(現地に)行った時に幹をパーンと叩いたら、中から鳥がバサバサって出てきたんです。ガイドに怒られましたけれども、叩くなって(苦笑)」
●動物たちとの関係性があるんですね。
「生態系において大事な役割をしている植物を『キーストーン種』というんです」
●キーストーン種!?
「そうです。サワロサボテンはアリゾナ砂漠において、キーストーン種であるっていうふうに言われています。大事な役割をしているよ、っていうことですね」
*編集部注:堀部さんの本には、国内でサボテンを見られるスポットも掲載されています。伊豆シャボテン動物公園や筑波実験植物園などのほかに、なんと千葉県銚子市にあるウチワサボテンの群生地が紹介されています。
銚子市長崎町の海岸沿いにあって、海を背景にサボテンが見られる場所は珍しいそうで、堀部さんいわく、青い海にサボテンが映えて、おすすめだそうですよ。

メキシコは国旗にもスーパーにもサボテン!?
※サボテンといえば、メキシコをイメージするかたも多いと思います。堀部さんは、サボテンの聖地ともいえるメキシコにも調査に行かれていますが、メキシコの国旗には、サボテンが描かれているんですよね?
「そうなんです! あまり知られていないんですけど、メキシコの国旗を見ると、ど真ん中にサボテンが描かれているんですよ」
●知らなかったです! その由来は?
「ちょっと難しい話になっちゃうんですけど、昔アステカ人があちこちさまよっていた時に、神様のお告げとして、サボテンの上でヘビを食らっているワシがいる土地を探しなさい! そういうお告げがあったんですね。
そして見つかったのが、今メキシコシティがある場所なんですよ。そういう建国神話に由来していて、それで未だに国旗にはサボテンとワシが描かれているんです。国旗をよく見ると真ん中にサボテンがあって、その上にワシが乗っていて、さらに(ワシの)口にはヘビをくわえているんですよ」
●なるほど! 神話の通りなんですね。
「そうなんです!」
●メキシコでは食用サボテンをたくさん作っているんですよね。
「メキシコだとサボテンは、どちらかというと野菜なんですね」

●へぇ〜、どんなサボテンが食用に向いているんですか?
「だいたい食べるのはウチワサボテンですね。ウチワ型の平たいサボテンがあるんですけど、それを食べますね」
●どんな味がするんですか? サボテンって。
「日本にいると(サボテンは)食べられるの? みたいな、絶対まずいだろって言われるんですけど、結構美味しいんですよ。ちゃんと調理するとサボテンは美味しいんです! 言い切れますね」
●メキシコのスーパーマーケットに行くと、野菜と同じように食用のサボテンが並んでいるっていうことですか?
「普通に並んでいますし、特設コーナーを設けられることが多いですね、食用サボテン専門のコーナーが・・・。
サボテンはメキシコに行くと普通にその辺に生えているんですね。なので、昔は貧しい人が食べるものだと思われていたらしいんですけど、最近は機能性の報告なんかも多くて、富裕層が敢えてサボテンを食べるようになっているみたいです」

●ちょっとサボテンの味、想像がつかないんですけど〜。
「味はひとことでいうとネバネバして酸っぱいのが、サボテンの味なんですね。ちゃんと理由があって、サボテンはCAM(キャム)型光合成っていうちょっと変わった光合成をしていて、その光合成をするとリンゴ酸っていう酸が溜まるんです。だから酸っぱいっていうのと、ネバネバの物質は多糖なんですけど、水を逃さないためにそういうネバネバ物質を溜めているんですよ。だから酸っぱくてネバネバした味になるんです」
●酸っぱくてネバネバ・・・!?
「日本でいうとオクラとかメカブが近いですね。結構美味しいですよ」
●どうやってサボテンを調理するんですか? どんな料理に使われるんですか?
「日本だとちょっと誤った認識が広がってるんですけど(笑)、まず食べるサボテンは若くて柔らかい時のサボテンを使うんですよ。日本だと大きくなったサボテンをサボテンステーキだって言って食べちゃったりする、あれは違うんですよ。ああいうふうには食べないんですよ。大きいと固くなっちゃって、あまり食べられないんですね、タケノコみたいな感じで・・・。
メキシコや海外だと、柔らかいウチワサボテンを肉料理の添え物にすることが多いですね。というのもヌルネバ系なので、チキンとか赤みの肉とかと一緒に食べると飲み込みやすくなるんですよ。嚥下促進作用(えんげそくしんさよう)があって食べ合わせがいいと・・・。あとはそのままちょっと焼いたりとか、生でサラダに入れたりとかして食べることも多いですよね」

●へぇ〜、食べて見たいです〜。
「美味しいですよ、結構!」
*編集部注:サボテンの生産量と消費量は、やはりメキシコが世界一とされています。
サボテンが地球を救う!?
※サボテンが地球を救うと本に書かれていますが、いま世界でサボテンが注目されているそうですね。
「はい。まずサボテンに注目が集まっている理由はひとことで言いますと、どこでも育てられて用途が広いからなんですね。
具体的に言いますと、例えば野菜が育てられないような乾燥地でもサボテンなら育てられる。なので、地球温暖化や砂漠化に対して強いんですね。用途も例えば野菜にもできるし、家畜の飼料にもできるし、加工食品にもできるし、最近だとサプリメントや化粧品にも使える。つまりなんでも使えると。
さらに少ない水や肥料でも育てられるし、無駄がないと! つまり持続性がある植物として注目が集まっています。すごいんですよね。
2017年には国連食糧農業機関FAOが、これからはサボテンを積極的に使っていこうという声明も出しています。世界が注目!」

●サボテンには知られていないポテンシャルが、もっともっとありそうですね!
「そうなんです! これまでは、今もそうなんですけど、サボテンを食べるっていうことに注目が集まっていたんですね。でも、私が個人的に注目しているのは二酸化炭素の固定です。地球温暖化対策にサボテンが使えるかも知れない、というのに注目しています」
●え〜っ、サボテンが、ですか?
「そうなんです。具体的に言いますと、例えば地球温暖化を防ごうと思ったら、空気中の二酸化炭素を吸収しないといけないんですね。それで植林というのがひとつの選択肢としてあります。木を植えると。ただし、乾燥地だと木が植えられないんですね。でもサボテンだと乾燥地でも植林できる。なので、乾燥地で二酸化炭素を固定できるっていうのがひとつあるんですね。
しかも最近、実際に昨年の11月にイギリスで、COP26気候変動枠組み条約締約国会議というのがあったんですけど、そこでメキシコの企業がサボテンを使った植林事業、カーボンオフセット事業を実際に紹介しているんです。なので、すでに世界の企業は、サボテンを使ったカーボンオフセットを始めているんですね」
●サボテンって本当にすごいですね!
「すごいです! ついでに私の研究も紹介していいですか?」
●もちろんです!
「ちょうどそこをやっていまして、実はサボテンを二酸化炭素の固定に使うメリットがもうひとつあって、サボテンは空気中の二酸化炭素を結晶化することができるんです」
●結晶化!?
「具体的に言いますと、透明な金平糖(こんぺいとう)みたいな結晶に二酸化炭素を変換しちゃうんですよ。バイオミネラルって言うんですけど、石みたいにしちゃうんですね。そうするとなにがいいかって言いますと、普通の木だと枯れた時に木の中にあった二酸化炭素は全部また逃げていっちゃうんです。
なので、保持できるのは一時的なんですけど、サボテンだと体に閉じ込めた二酸化炭素の一部が結晶化しているので、サボテンが枯れても出ていかないんです」
●残るわけですね!
「残るんですね、地面に。なので、二酸化炭素の長期固定にサボテンは使えるかもしれないということです。そうすると1000年以上、安定して二酸化炭素を固定できる、そのメカニズム、どうやってサボテンが二酸化炭素を結晶化しているのかとか、その結晶がサボテンの中で何をやっているのかを私は今調べています」
*編集部注:実は堀部さんはつい最近、カンボジアに行っていたそうです。これは日本の企業や政府機関とともに行なう人道支援事業のためで、カンボジアにたくさん残されている地雷原の跡地に、食用になるウチワサボテンを植え、雇用を産み出し、産業を作るというものだそうです。サボテンの可能性がさらに広がりそうですね。
●では最後に、サボテン博士として研究対象であるサボテンから、改めてどんなことを感じていらっしゃいますか?
「そうですね。正直、サボテンに限ったことではないんですけれども、生き物ってすごいなぁっていうことですね。と言いますのは、サボテンについて調べていると、乾燥とか高温に耐えるための仕組みが何重にも存在するんです。
さっきご紹介した茎の形だったりとかトゲだったりとか、あと根っこの構造なんかも乾燥に強くなるための仕組みが何重にも備わっているんですね。それはサボテンだけではなくて、すべての生き物はそれぞれに特徴的な生きる力っていうのを持っているんです。
そういうのを見るとすごく感心しますし、なんか元気づけられるんです。生き物は、生きるための仕組みをすごく備えて、よくできているから、多分自分も大丈夫なんじゃないかなみたいに思っているんですよね。勝手に励まされるみたいな感じです」
INFORMATION
サボテンに興味を持ったかたは、堀部さんの本をぜひ読んでください。サボテンに関する学術的なことも載っていますが、サボテンの初心者のかたが読んでも「へ〜〜っ! そうなんだ〜!」の連続で、面白いですよ。アリゾナやメキシコに調査に行った時の珍道中も楽しく読めます。サボテン・多肉植物のミニ図鑑も掲載されています。ぜひご覧ください。
ベレ出版から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎ベレ出版HP:https://www.beret.co.jp/books/detail/841
堀部さんの研究室のサイトもぜひ見てくださいね。
◎堀部さんの研究室HP:https://www3.chubu.ac.jp/faculty/horibe_takanori/