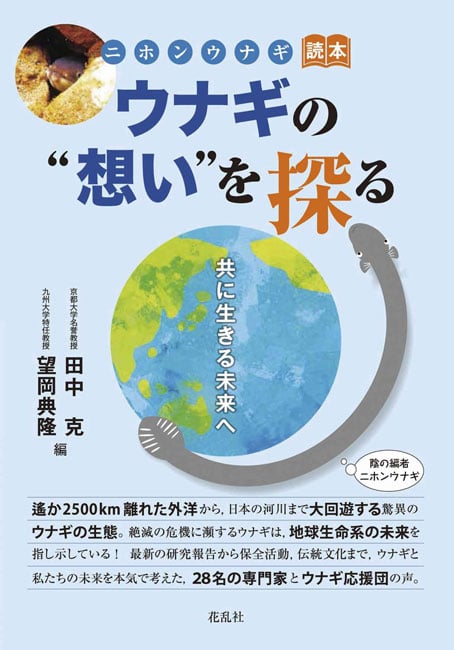2023/9/10 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、動物園・水族館コンサルタントの「田井基文(たい・もとふみ)」さんです。
田井さんは1979年生まれ、早稲田大学卒業。2009年に世界で初めての動物園・水族館の専門誌「どうぶつのくに」を創刊。その後、日本動物園水族館協会の広報誌を手掛けるなど幅広く活動。2012年から動物園・水族館コンサルタントとして活躍。さらに動物園写真家としての顔も持っていらっしゃいます。
そして先頃、『世界をめぐる 動物園・水族館コンサルタントの 想定外な日々』という本を出されました。
きょうは、この本をもとに動物園・水族館コンサルタントとは、どんな仕事なのか、国内外の動物園や水族館の現状やあり方はどうなのか、そして、田井さんが作りたい夢の動物園のお話などうかがいます。
☆写真提供:田井基文

動物園・水族館コンサルタントの仕事
※まずは、動物園・水族館コンサルタントとはどんなお仕事なのか、教えていただきました。
「私は10数年ほど前から、動物園・水族館コンサルタントの名刺を持つようになったんですね。といっても、これに明確な、例えば資格試験があるというわけではない仕事で、どれだけこの業界のことであるとか、人のこと、ネットワークや知見があるかっていうことが、問われる仕事なのかなと思っています。
つまり単純に、特定の動物の種類やその個体に対して、深い知識を持っていますっていうことよりは、自分の持っている知識や経験、そういったことを、いかに柔軟にクリエイティヴに結びつけて、新たな価値を提示できるかっていうことが私の仕事になるのかなと。
例えば、ある動物園で新しくホッキョクグマの展示を作りますと、なにかいいアイデアはないでしょうか? なんていうご相談を受けた場合に、あの動物園ではホッキョクグマのこんな展示が人気ですよとか、あるいはあの水族館ではこんなふうにチャレンジしていますよとか・・・。
あるいは全く別の種類で、こんな動物はこんなふうに見せていますけど、これをホッキョクグマの展示にうまく応用できないかなっていうようなことだとか・・・。それを生物学的なことはもちろんなんですけど、動物園学的、あるいはデザインだったり建築学的なこと、そしてそれを受け入れる背景としての社会学的な部分も含めて、非常に多面的に検討して検証しながら、動物園や水族館に対して提案をしていくということになるかなと思います」

●動物園・水族館コンサルタントという肩書きで仕事をされているのは、日本では田井さんだけでいらっしゃいますけれども、海外ではスタンダードな存在なんですか?
「そう言っていいんじゃないでしょうか。非常に専門性の強い分野でもありますし、経験が物を言う業界、そんな背景がありますので、どこかの動物園や水族館で長くご活躍された館長、あるいはキュレーターみたいなかたを、そういったポジションで、また別の施設でお迎えするというのは珍しいことではないと思いますね」
●それだけ需要があるってことですよね。
「まあそうですね。そう言っていいと思います」
(編集部注:田井さんが動物園・水族館コンサルタントになった大きなきっかけは、ビジネスパートナーであるユルゲン・ランゲ博士との出会い。
ランゲ博士は、ベルリン動物園の統括園長を長年続け、ヨーロッパの業界では大変有名なかたで、田井さんいわく、魚類や哺乳類、家畜ほか博物学にも精通し、その幅広い知識とネットワークは、ランゲ博士の右に出る人はいないそうです。そんなランゲ博士から、一緒にやらないかと誘われ、ふたりで動物園・水族館コンサルタントの仕事を始めたということです)

動物と動物園のサステナビリティ
※田井さんによれば、日本には大小合わせて、動物園が160から170箇所、水族館が120から130箇所、合わせると300箇所ほど、アメリカにはおよそ200箇所、ドイツには150箇所ほどあるそうです。海外との違いは、日本は県や町が運営する公立の施設が多いのに対し、海外はほとんどが企業が運営しているとのこと。
田井さんは取材を含めて、国内外の施設を1000箇所以上訪れているそうですが、特に感銘を受けた施設を挙げるとしたら、どこになりますか?

「動物園は、ひいき目なしにやっぱりベルリン動物園が大好きですね。飼育している数、飼育の展示施設のデザイン、それから歴史的な背景も含めて、やっぱり動物園ではベルリン動物園に右に出るものはいないでしょうね。
水族館で言うと、スペインのバレンシアの水族館(*)が、僕は大好きですね。建築にご興味のあるかたは特におすすめしたいんですけど、水族館の肝になるのはひとつ建築の要素が、本当に大部分を占めると僕は思っているので・・・」
(*編集部注:施設名「オセアノグラフィック」)
●建築ですか?
「はい、建物としての美しさはバレンシアの水族館はダントツですね。ぜひ行ってください(笑)」

●水族館と建築には、そんなに深い関わりがあるんですか?
「やっぱり日本でも水族館を作るにあたっては、単なる四角い箱の中に(生き物を)入れるということではなく、それをある種の美術館や博物館のような感じで捉えて、建築している例がいくつかありますよね。海外の場合はもっと顕著にそういうのが出てくるわけですけれども・・・」
●日本では新たにオープンするっていうよりも、リニューアルが多いように思います。やっぱりコンサルタントとしては腕の見せ所だと思うんですが、田井さん自身、コンセプトというか、どんなことを大事にされていらっしゃいますか?
「いかにその展示施設全体が、その動物にとって自然な環境であるかっていうことは、大前提になると思います。動物たちにとってナチュラルな環境がなかったとすると、本来彼らが自然界でとる自然なアクションは、もちろん見られなくなるし、そうなってくると、本質的な動物の魅力も引き出してお見せすることはできなくなる・・・。
さらにそういった環境下になければ、もちろんペアリングだとか子育てみたいな、次なるミッションにもなかなか取り組んでいけない、無駄なハードルを勝手に作っちゃうみたいなことになるわけです。その動物たちにとってのサステナビリティは、動物園としてのサステナビリティにも直結するっていうのが、ひとつのモットーですかね」
●その施設のある町がどんな町なのかを調べると、本に書かれていましたけれども、それはどうしてなんですか?
「先ほどの自然環境の話と、ある意味では遠からず、つながった話かなとは思うんですね。本にも書きましたが、例えば 日本の高知県で高知のかたにアンケートを取った時に、きっと坂本龍馬のことを知らない人いないと思うんですよね。もちろん直接的に龍馬ゆかりの何かをっていうことでは、決してないんですけど、そのことを知った上でやるか、あるいは知らずにやるかは大違いだと思います。
だから世界的に有名かどうか、そんなことは割とどうでもよくて、むしろその地元ゆかりの人物、あるいは建物、文化でもいいし、風習でもいいし、郷土料理なんかもいいと思うんですが、そういうところには必ず何かヒントがあると私は思っています」
(編集部注:田井さんは、個人的に期待している動物園として、千葉県では市川市動植物園の名前を挙げてくださいました。園長さんも優秀なかたで、施設自体にも高いポテンシャルがあるとおっしゃっていましたよ)

動物園と水族館のあり方
※時代とともに動物園と水族館のあり方が変わってきているように感じます。以前は狭い檻での展示でしたが、今はその生き物がもともといた環境に近い状態で展示している施設も多くなったと思います。そうなった背景にはなにがあるのでしょう?
「いちばん大きな要素としては動物福祉、『アニマルウェルフェア』なんていう言い方をしますけれども、あるいはその動物たちがより自然な、よりナチュラルな形でいられるような『ウェルビーング』なんていう言い方をする、そういう考え方、観点が非常に強く意識されるようになってきたというのが、大前提としてあると思います。
アメリカやヨーロッパでは30年40年前ぐらいから、そういう意識がどんどん高まっていて、そういったことをスローガンに掲げた団体が非常に活発に活動されていました。そういった考え方や概念が日本の動物園や水族館にも、ちょっとずつ持ち込まれるようになってきたというのが、経緯かなとは思いますね」
●動物園も水族館も飼育展示する生き物を、どこから持ってくるのかが課題だと思いますけれども、絶滅の恐れのある動植物の取引を禁止したワシントン条約の存在も大きいですよね?
「そうですね。日本はワシントン条約を1980年に批准し、現在183カ国が加盟しています。これらの国と地域では、この条約に定められたルールにのっとってのみ規定された動植物に関して、輸出・利用させるということが大前提になりましたから、それまでとは違って、簡単に動物を持ち込むことができなくなっていると思いますね」
●となると、やはり繁殖させるっていうのが大事になってくるわけですよね?
「もちろんです。やっぱり飼育下での繁殖は喫緊の課題ですよね。動物園業界では『ブリーディングローン』なんていう言い方をしていますけれども、繁殖を目的とした動物の個体の貸し借りは、本当に国内外問わず積極的に行なっていますね。
ただその動物を貸し借りするにあたっても、やっぱり常にリスクは伴います。例えばゾウとか、大きな動物キリンでもいいですけれども、Aという動物園からBという動物園に貸し出すことが決まっても、運ぶリスクがあったりするし、運んだはいいけれど、行った先で体調を崩してしまうとか、環境が肌に合わないとか、水が合わないとかっていうようなことも常にあります。
それに対して例えば、冷凍で精子だったり細胞を保管しておく方法も、最近は少しずつ考えられていくようになりましたね。
アメリカのサンディエゴの動物園だったり、イングランドの自然史博物館なんかが有名なんですけれども、本当に100単位の種類の動物たちの細胞だったり、精子だったりっていうのを冷凍状態で保管して、いざという時にはそれを利用して繁殖させられるように、ということも考えてやっていますよ。
もちろんそれぞれ全部がうまくいっているわけではないですけれども、そういう考え方も一般的にはなってきましたね」

(編集部注:田井さんの本によれば、国内で飼育されているラッコは1990年代には120頭ほどいたそうですが、年々減って、現在なんと!たったの3頭。なぜ減ってしまったのか、それはぜひ本を読んでいただければと思います。田井さんがおっしゃるには、飼育下で絶滅が危惧されている動物は意外とたくさんいるそうですよ。対策が急がれますね)
夢は家畜の動物園
※田井さんは「家畜専門の動物園」を作りたい! そんな夢があると本に書かれています。それはどうしてなんですか?
「家畜ってまずなんなのか、説明できない人が圧倒的に多いと思うんですよね。家畜ってなんですかって言われて、説明できます?」
●豚とかそういうのは言えますけど、確かに家畜とは?って言われても・・・人のために、っていう感じですか。
「そうそう、おっしゃる通りです。いちばん重要なのはそこで、もともと家畜動物は人間が作り出して、人間と共に暮らして、人間と共に進化してきた、人間のために生きてきた動物です。我々人間にとっていちばん身近な存在の動物だって言えると思うんですよね。
毎日みなさん、きっと牛乳を飲んだり、チーズを食べたり、あるいは卵を食べたりすると思うし、寒くなってくると、まだ暑いですけど、ウールのニットのセーターを着たりとか、あるいはダウンジャケットを着たりするかたが多いと思います。 あるいは革製品のバッグだったり、靴だったり履くでしょうし・・・。
もちろんペットもそうですよね。飼っているかたはたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。これ全部、家畜がいなかったら成立しないことばっかりです。

牛も馬も羊も鶏も豚も、それから犬も猫もみんな家畜です。この家畜はやっぱりその国やその地域によって、それぞれ暮らしてきた人たちに合わせて進化してきているので、非常に多様な進化をそれぞれの地域で遂げてきているわけですよね。
つまり住んでいる人が違えば、その環境も違えば、やっぱりそれに適した家畜も違ってくるということなんです。アメリカにはアメリカの家畜がいるし、インドにはインドの家畜がいると・・・。もちろん日本には日本の家畜がいるんですけど、じゃあここで質問です。みなさんに牛を絵で描いてくださいって言ったら、どんな牛を描きます?」
●白に黒の・・・?
「そうですよね。きっとそうだよね」
●はい。
「鶏を描いてくださいって言ったら、どんな色で鶏を塗りますか?」
●えっと・・・トサカがあって、赤で・・・。
「トサカが赤で、足が黄色ってイメージすると思うんですけど・・・。みなさんが描かれる、白くて大きな体に黒いドットのある牛は、ホルスタインという品種ですね。あれはもともとオランダとかドイツの家畜ですし、みなさんが鶏だと思ってイメージされる、白い羽根で赤いトサカの黄色い足をした鶏は、『白色(はくしょく)レグホン』という品種で、あれはもともとはイタリアの品種だったりするわけなんです。
じゃあ日本を代表する家畜とか動物ってどんなの? って言っても、9割以上のかたはきっとご存じないので、そこのギャップをちょっとでも埋められたらいいなっていうのを考えていますね。
きっとみなさん動物園に行かれても、パンダのために2時間3時間並ばれることは、今はざらだと思うんですけど、じゃあ牛や鶏のためにきっとそんなことなさらないと思うんですよね。
もちろん好みもあって、それでいいんですけど、希少性っていう意味で考えた時に、よほどパンダよりも希少な家畜は本当にたくさんいます。それが古来から日本で暮らしてきて、我々日本人の生活を支えてきてくれた存在だっていうことだったりとか・・・。
あとはさっきも言った通り、所変われば品変わるじゃないけれども、家畜としての多様性、世界中にいろんな種類の家畜がいるよっていうことを、少しでも興味を持って知っていただけたら、いいんじゃないかなっていうことは考えていますね」
(編集部注:家畜専門の動物園、その手始めとして、田井さんは世界中の家畜などを知ってもらうために「LIVESTOCK ZOO」というサイトも運営されています。現在はリニューアル中とのことですが、ぜひサイトを見ていただければと思います)
◎LIVESTOCK ZOO http://livestockzoo.com
写真や映像にはないものがある
※以前から、動物園や水族館はほんとうに必要なのか、そんな問いもあったと聞いています。今後、動物園や水族館はどう進化していけばいいのか、田井さんは何が大事になってくると思いますか。
「やはり教育ということが、その大部分を占める要素になることは間違いないでしょうね。あらゆる動物たち、それは植物もそうですし、昆虫もそうですけれども、あらゆる生き物って我々人間が暮らす地球をシェアする、ある意味では仲間だと思うんですね。
その仲間たちがそれぞれ今どういう環境で、どんな状況で暮らしているかを知っていただく、あるいは思いを馳せていただく、最低限そんなきっかけを得られる施設って動物園・水族館を差し置いて、ほかにないと僕は思っているんですよね。
もちろん写真も素晴らしいし、映像だってクオリティが上がっているし、AIだってすごいなと思いますけど、チャットGPTでは教えきれないものが、やっぱり生の動物のインパクトにはある、そこにはかなわない要素が必ずあるんじゃないかなっていうのが僕の考え方です。
例えば、その動物を実際に見に行くために、野生に行けばいいじゃないかっていう考え方もちろんあるし、それは重要なことですけれども、ライオンを見ようと思った時にまずアフリカまで飛行機で飛んでいかなきゃいけないですよね。何十時間もかけて、何十万円もお金をかけて旅をして、現地でレンジャーに案内をしていただいてライオンが出てくるのを待つ、探す、でも確実にライオンを見られるかどうかなんて本当はわからないですよね。
それがありとあらゆる種類に対して言えるわけで・・・ただそういう希少で稀有な動物たちに出会うチャンスを、数百円、数千円で、動物園に行けば、自分の町で 生きた動物たちに出会うことができる、こんな施設が今すぐなくなっていいとは、僕は思わないですけどね」
●そうですね。飼育されている生き物たちからどんなことを感じますか?
「飼育されている生き物から感じることか〜どんなことだろうなぁ〜」
●動物の身で考えると、野生で生きていたほうが幸せなのかな?とか・・・。
「なるほど、なるほど、そういうことか。それってよく言われることですけど、動物に聞いてみないとわかんない(笑)」
●確かに(笑)
「聞いてみてって思いません? いや、もちろんわかりますよ。とってもわかるし、動物園反対論者のかたに面と向かって、それがすべて間違っているなんて、僕は到底思わないんだけど、本当にその動物が幸せかどうかなんて、本人にしかきっとわからないし・・・」
●おっしゃる通りですね。
「ホッキョクグマ、ライオン、なんでもそうですけど、それだけ広い環境、それだけ自然に近い環境を与えられていれば、本当に幸せかっていうことはわからないんですよね。と同時に野生で暮らしていて、明日食べるものがどうなるかもわからない状況で暮らしているホッキョクグマが本当に幸せなのか、どっちがハッピーですか?って言ったらわからないし・・・。
ただ忘れてはいけないことは、やっぱりその動物たちのことを、自然を第一に考えて飼育をすることは、もう大前提にはあるわけです。かつての見物小屋だった時代に戻ることは、決してあってはいけないことだとは思いますが、とはいえ、そうやって動物園や水族館で今暮らしている動物たちにも、それ相当の役割があって、今そこにいることに我々は感謝しながら付き合っていくべきなんじゃないかなと思いますね」
INFORMATION
『世界をめぐる 動物園・水族館コンサルタントの 想定外な日々』
田井さんの多岐に渡るお仕事やその流儀、動物園・水族館の舞台裏、海外出張でのハプニングや、ビジネス・パートナー「ユルゲン・ランゲ博士」への思い、そして国内外のおすすめの動物園や水族館なども載っています。動物園・水族館好きにはたまらない一冊! 産業編集センターから絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎産業編集センター:https://www.shc.co.jp/book/18861
田井さんは、動物園の様子を有料でライヴ配信するプロジェクト「KIFUZOO(きふずー)」も運営されています。これはコロナ禍で入場料収入が激ってしまった動物園や水族館を支援するために「寄付しよう」をコンセプトに3年ほど前にスタート。北海道の旭山動物園や、沖縄こどもの国ほかから定期的に配信中です。過去には千葉市動物公園からの配信もありました。
「KIFUZOO」については、オフィシャルサイトを見てください。
田井さんのオフィシャルサイトもありますよ。