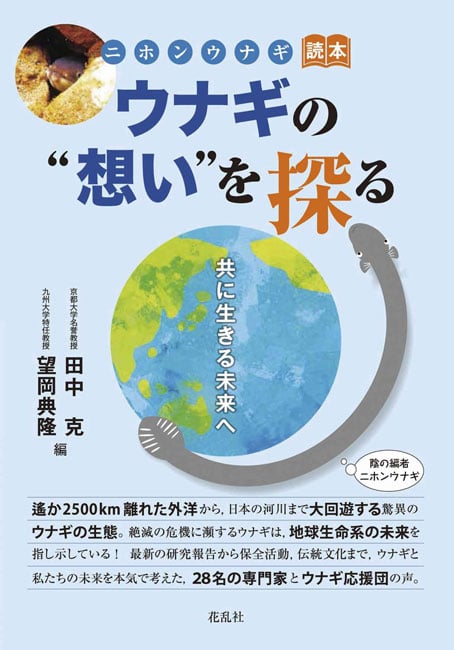2023/11/26 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、秩父在住の写真家「阪口克(さかぐち・かつみ)」さんです。
阪口さんは1972年、奈良県生まれ。写真スタジオ勤務を経て、オーストラリアに渡り、自転車による 大陸一周1万2千キロの旅を達成。これまでに訪れた国は40カ国以上。現在はフリーカメラマンとして、旅やアウトドア雑誌の撮影を担当。ほかにも海外の辺境に暮らす人々の一般家庭に居候する取材も続行中。また、暮らしの中の焚き火を数多く経験し、それをもとに焚き火の本も出されています。
阪口さんの活動テーマは「旅と自然の中の暮らし」ということで、現在は埼玉県秩父の山里に、ご自分で建てた家に、ご家族と一緒に暮らしていらっしゃいます。
セルフ・ビルドした家の顛末も、実は本になっています。奥さまを説得し、貯金をはたいて、秩父に280坪ほどの土地を購入。経験ゼロなのに国産材による伝統工法にこだわり、悪戦苦闘しながら、木造の平家をなんと6年かけて建築。総工費はおよそ560万円だったそうです。
きょうはそんな阪口さんに、ご自分で建てたマイホームのことや、世界辺境の旅、そして先頃出された、子供向けアウトドア料理レシピ集『冒険食堂』から、おすすめ焚き火料理のお話などうかがいます。
☆写真:阪口 克

6年間の家づくり
※そもそも、なんですが、なぜ自分で家を建てようと思ったんですか?
「雑誌の取材を僕は多数やっていまして、田舎へ移住されたかたへの取材を一時期よくしていたんですね。自分で古民家を改造したり、あるいは自分で一から家を建てたりする人に取材する機会が非常に多かったんですよ。それで自分でもそういうことをやってみたいなというのが、始まりですね」
●家は自分で建てられるんですね!
「家は(自分で)建てられますね(笑)」
●ひとりで建てたわけじゃないですよね?
「そうですね。加工とかはひとりでもできるんですけども、大きな構造材を組み立てるとなると人手が必要なんで、もちろん家族であるとか友人にその時は助っ人を頼んで(家を)作っていきました」
●家作りのアドバイザーのようなかたはいらっしゃったんですか?
「いや、それはいなかったです。本で調べたりインターネットで調べたりしながら、やっていました」

●その6年間という年数ですけど、具体的にどういう流れで6年間になったわけですか?
「まずは、土地を探して購入して、次に近所の材木屋さんに行きまして、正直に自分で家を建てるんだ!って言って、構造材に使う材料を売ってもらうっていう感じですね。
並行して、建築確認申請っていうのはどうしても必要なので、その確認申請は建築士さんの資格を持っていないとできないんですよね。なので、自分で書いた設計図を建築士さんにお願いして清書してもらって、法律上問題ない手続きをしてもらって建築をスタートしたという形ですね」
●どんなことがいちばん大変でした?
「そうですね・・・いちばん体力的に大変なのは、大きな材木を持ち上げるとか屋根の上で炎天下、延々屋根の板を張るとかが大変だったんですけども、どちらかというと最初の2年ぐらいは、始めてみたけど、本当に(家が)できるんだろうかという心配ですよね。メンタルのほうがだんだん、こんなこと始めちゃって大丈夫かなってなってきましたね。家族も巻き込んでいますし、そこはやっぱりちょっと辛かったですね。で、2年過ぎてある程度、形になってきてからは気分が楽になって楽しくなってきたっていう感じでしょうかね」
●6年経って、実際できあがった家をご覧になっていかがでしたか?
「まあ、ずーっと毎日6年間見ているんで(笑)、意外と感動とかもないですよね。住み始めた日はもちろんあるんですけども、ずっとそこにいましたからね。家族で引っ越して、最初の晩御飯を食べたとか最初にお風呂に入ったっていうのは、もちろん嬉しかったですけども、まあやっと終わったかっていう感じですかね」

辺境の一般家庭に居候!?
※阪口さんは、これまでに世界40か国以上を旅されているそうですが、どちらかというと「辺境好き」・・・なんですよね?
「そうですね、わりかし・・・。いわゆる辺境というか、そういうところへ行くのは好きですね」
●どんな旅のスタイルなんですか?
「もちろんカメラマンですので、お客様の雑誌から依頼を受けて、取材に行くっていうのがメインなんですけども、そういう時はたいてい大きなホテルだったり、観光地だったりの取材になるんですね。
それとは別に、相棒の旅行作家がいるんですけども、彼とふたりでいろんな国に行って、1週間一般家庭に居候をするっていうのをやっています。それがたまるとと週刊誌でその国の暮らしを紹介するというような形でずっとやっていました」
●印象に残っている旅先ってどこかありますか?
「もちろんどこも思い出深いんですけども、カメラマンとしてやっぱり視覚的な刺激が強かったのは、サハラ砂漠の遊牧民のお宅に居候した時はすごかったですよね」
●どうすごかったんですか?
「あたり一面、絵に描いたような砂漠ですよね。寝る時もずっと砂まみれですし、カメラのダイヤルもジャリジャリになるしね(笑)。すごいところに暮らしていらっしゃるなっていうのは正直なところでしたね」
●見たことのない景色に出会えるのも旅の醍醐味だと思うんですけど、人との出会も魅力がありますよね?
「もちろんそうですね。まあ居候なんで、それもお金持ちの邸宅じゃなくて一般家庭にお願いしているので、毎度そこのお父さん、お母さん、子供たち、おじいちゃん、おばあちゃんとも一週間寝食を共にする形になるので、なかなか深い付き合いができますね」

●すぐにパッと思い出される人たちっていますか?
「もちろんそれは顔もすぐ浮かびますね。例えば、いちばん最初にこの居候の企画をやった時に、モンゴルで泊めてもらったベギさん一家はやっぱり思い出深いですね」
●どんなご一家だったんですか?
「それ以上にまず僕たちは、そういう居候取材まだ手探り状態だったんで、どうしていいかわかんなくて、思っていた以上に、まず英語が通じないっていうのがカルチャーショックでしたね。僕もそれほど英語が得意ではないんですけども、ワン、ツー、スリー、イエス、ノーも通じないんですよね。
そうすると身振り手振りと、簡単なモンゴル語の単語帳みたいなのを手がかりに会話をするしかなくて、お願いしたドライバーさんはもう帰っちゃって大草原の中で逃げ場もないわけですよ。そこで一週間後発つまで、誰も迎えに来てくれないという状況だったんです。
最初は僕も戸惑いましたけど、受け入れた先のベギさんも当然動揺していたようで、ここまでモンゴル語ができないやつが来たのか! っていう感じで、“こんにちは”の言い方すら簡単にしか知らなかったですからね」
●そんな中で共に生活をするっていうのはすごい経験ですよね?
「いや〜面白かったですね。今思い返せば面白かったですね(笑)」

自分でやってみる「冒険食堂」
※阪口さんの新しい本が、子供向けアウトドア料理のレシピ集『冒険食堂』。この本は、毎日小学生新聞に連載した記事をまとめたものです。
本には、阪口さんのお嬢さん「春音(はるね)」さんがモデルとして登場しているだけでなく、大人の味付けになりがちだったレシピを、春音さんの意見を取り入れ、より子供向けにするなど、参考にしながら作ったそうですよ。

『冒険食堂』の基本として「焚き火・炭火料理を楽しむための4つの約束」が書かれています。この4つの約束をご紹介いただけますか。
「焚き火料理を楽しんでもらうためには、まずいちばんに、どんなことも自分の力で挑戦しよう、としました。2番目が安全のための決まりを守る。3番目においしい料理はしっかりした準備で決まる。あと4番目は楽しんだあとは、来た時よりも美しく片付ける。この4つになります」
●やっぱり失敗してもいいから、自分でやることが大事なんですね?
「そうですね。この企画が始まった時にいちばんに浮かんだのは、この『冒険食堂』っていうタイトルだったんですね。単にアウトドア料理だと、美味しい料理っていうだけになると思うんですけども、そこに冒険っていうか、今まで自分がやったことがないもの、ちょっと怖いなと感じるものに対して、チャレンジするというのをテーマに掲げているので、ちょっと心配だから、お父さんやお母さんに頼んでみようとかなるところを、自分でやってほしいっていうのがやっぱりいちばんですね」
●まさに冒険ですね!
「そうですね」
●料理をするための熱源として、焚火と炭火を勧めてらっしゃいます。そこには子供たちに自分で火を起こせるようになってほしいっていう、そういう思いがあるからなんですか?
「そうですね。やっぱりキャンプと言えば、いちばんの楽しみで浮かぶのは、焚き火なんじゃないかと思うんですよ。さっきも言ったように冒険のひとつのきっかけとして、焚き火をいちばんに持ってきているんですよね。
焚き火じゃなくて、例えば、魚を釣ったら自分でさばくとか、お肉をナイフで切ってみるとか、そういうことでも、もちろんいいんですけども、まずはキャンプ場に着いたら、自分の力で一回火をつけてみようっていうのは、僕は提案したいですね」
●阪口さんは焚火の本も出されていますけれども、やっぱり焚き火の技術とか作法を身につけるっていうのは、現代でも大事なことなんでしょうか?
「そうですね。焚き火の本を作った時に調べてみたら、人類と焚き火の付き合いってのは、何十万年にも及ぶんですよね。日本でも数万年前の焚き火の跡が残っていたりするので、そういう長い付き合いの中で、ほんのここ50年ぐらいで自分の周りから“直の火”っていうのが、ちょっと見えなくなっていると思うんですよ。
我々は今、電気を使っていますけども、この電気も例えば、火力発電だったり原子力発電の火で発電されているわけじゃないですか。なので、火っていうのは人間の今の文化とか暮らしの、いちばんベースになっているエネルギーのひとつだと思うんで、それを一度自分の手元に戻してみるってのは、いいことなんじゃないかなと僕は思っているんですよね」

(編集部注:『冒険食堂』には焚き火のベテラン、阪口さんが考案した「焚き火で守る9か条」も掲載されています。風の強い日には絶対にやらないなど、基本的なことはもちろんなんですが、もし、ウエアに火が燃え移るようなことがあったら行なう緊急時の対策法「ストップ!」「ドロップ!」「ロール!」がイラストとともに解説されています。
これはアメリカの消防士さんが考えた対策法だそうで、「ストップ」止まって、「ドロップ」倒れて、「ロール」転がって、火を消す方法なんです。ぜひ阪口さんの本で、ご確認ください)
おすすめ焚き火料理!
※本に掲載されているアウトドア料理のレシピから、誰でも簡単に作れるおすすめ料理をご紹介いただけますか。

「まず僕が基本にあげたのは、『野菜ごろごろポトフ』という1番目に出てくるメニューなんですけれども、特にこれからの季節、あったかいスープは非常に美味しいと思うので、ぜひ作ってほしいですね。今の時期ですと冬のキャベツが美味しいですから、キャベツをいっぱい入れて、ソーセージとかニンジンとか入れて、あったかいスープにすると、寒いキャンプ場で美味しいと思います」
●いいですね〜。この本を拝見していて思ったんですけど、ダッチオーブンがひとつあると、ぐぐっと焚き火料理の幅が広がるな~っていうふうに感じました。ダッチオーブン料理でおすすめってありますか?
「ダッチオーブンはいろんな料理を作れるんですけども、やっぱりダッチオーブンとキャンプ好きな人が聞いて、いちばんに思い浮かべるのは『チキンの丸焼き』だと思うんですよね。これはぜひ作ってほしいですね! すごく美味しいですから」
●具体的にどんなふうに作るんですか? 初心者でも作れますか?
「はい、比較的簡単だと思いますよ。スパイスと塩を揉み込んだ丸鶏を、ダッチオーブンに突っ込んで炭火にかけるだけなんです。コツとしては、ダッチオーブンの底に玉ねぎとかセロリなどの香味野菜を敷くのと、あとは、鉄の鍋のダッチオーブンは、上に炭火を乗せられる構造になっているんですね。なので、下の火は弱めにして蓋の上の火を強くすると、焦げないでジューシーな丸鶏が作れますね」
●すごいですね。見た目も豪華でいいですよね!
「これは間違いないですよ! 蓋を開けた時にみんなだいたい、わ~って言いますよね」

●本を拝見して驚いたのが、牛乳パックでホットドッグを焼くというレシピもありました。どんなレシピなのか教えていただけますか?
「『カートンドッグ』って言いまして、アメリカでは比較的よくバーベキューで作っているみたいなんです。ホットドッグのパンにソーセージ、あるいは好きな具材、僕だとポテトサラダなんかを挟んで、それをアルミホイルで巻くんですね。
で、牛乳パックに突っ込む、その牛乳パックに火をつけると、牛乳パックが燃えていく過程で、ホットドッグが過熱されるという形ですね。これは子供でも失敗せずに上手に焼けるので、ぜひチャレンジしてほしいですね」

●ダンボール箱でオーブンを作って、お料理を作るというアイデアにもびっくりしたんですが、ローストビーフとか作れちゃうんですね?
「作れますね! ピザも焼けますし、ケーキを焼いたこともありますね。ダンボールオープンで・・・」
●なんかすぐに燃えちゃいそうだなと思ったんですけど・・・。
「いや、意外と紙って燃えないんですよ。紙の種類にもよるんですけども、だいたい紙の発火温度っていうのが250度から450度ぐらいなんですね。逆に言うと200度を超えなければ、紙は燃えないんで、ダンボールオーブン、もちろん直火にかけたら燃えちゃうんですけども、まずはダンボールの中に全面アルミホイルを貼ります。
その中に熱した炭を入れたお皿を入れて、加熱するんですけども、この時に段ボールの中が大体180度ぐらいの、電気オーブンぐらいの温度になるんで、そこで調理する分には何の心配もないですね」
●へ~〜、じゃあ簡単にできちゃうんですね!
「そうですね。比較的簡単にできますね」
冬こそ、焚き火のキャンプ
※焚き火は、お料理を作ったり、暖を取ったりと、キャンプには欠かせないものだと思うんですけど、焚き火を楽しんだあとの、後始末が大事ですよね。どんなことに注意すればいいですか?
「まずは絶対、消火ですね。必ずつけた火は自分で消すってことですよね。よくある間違いが(地面に)埋めちゃえばいいっていう人がいるんですね。もちろん埋めることで酸素が遮断されて消えるっていうか火勢は弱まるんですけども、そんなに簡単には消えないんですね。
もしなんかの拍子に次に来た人が掘り出したりとか動物が掘ったりしたら、そこで酸素が供給されて、ほんの少しでも火が残っていたら、そこからまたわっと火が燃え広がることがあるんですよ。
なので、埋めて消火とかはなし! ましてや、地面の上で燃えているまま、帰ってしまうってのは絶対あり得ないことですから、必ず火消壺であるとかバケツの水に燃えてる火を沈めて、酸素を断って消すっていうのを習慣づけてほしいですね」
●改めて阪口さんは、焚き火にどんな思いがありますか?
「僕も昔、都市部に住んでいて、キャンプばっかり行っていた頃は、焚き火が大好きで、ずっと焚き火をしていたんですけど、今秩父の山里に暮らしていますと、日常で焚き火がいっぱい出てくるんですよ。なので、最近はちょっと暮らしの一部分になっているって感じでしょうかね」
●キャンプはオールシーズン楽しめるアクティビティだと思いますけれども、ウィンターシーズンの注意点ですとか、こんな楽しみ方があるよなど、何かアドバイスがあればぜひ教えてください。
「どっちかというと、焚火とかバーベキューは、秋冬のほうが向いているんですよ。夏は暑いじゃないですか、焚き火・・・そうすると冬場のほうが焚き火はより楽しめますよね。焚き火の火がつくまでは寒いんですけども、冬のキャンプはぜひ楽しんでほしいなと思います。虫も少ないですし、雪景色の山が遠くに見えたりして、すごく気分がいいと思うんで、みんなで焚火を囲みながら焚火料理を楽しんでもらえたら、すごくいいんじゃないかなと思うんですね」
●ぜひこの『冒険食堂』のレシピを見ながら・・・
「ぜひ楽しんでほしいですね!」

INFORMATION
阪口さんがお嬢さんの春音さんの意見も取り入れながら作った本、お勧めです。子ども向けではありますが、大人でもとても役立ちますよ。火の起こし方から食材や調味料、作り方まで、写真をもとに解説してあるので、その手順に従ってやれば、初心者でも美味しくできると思います。どこにでも持ち歩ける便利なハンドブック・タイプ。ヤマケイ新書シリーズの一冊として絶賛発売中です。
◎山と渓谷社 :https://www.yamakei.co.jp/products/2823510830.html
家をご自分で建てた顛末も本になっていますよ。先月、草思社から文庫で発売されました。
◎草思社 :https://www.soshisha.com/book_search/detail/1_2686.html
阪口さんのオフィシャルサイトもぜひ見てください。