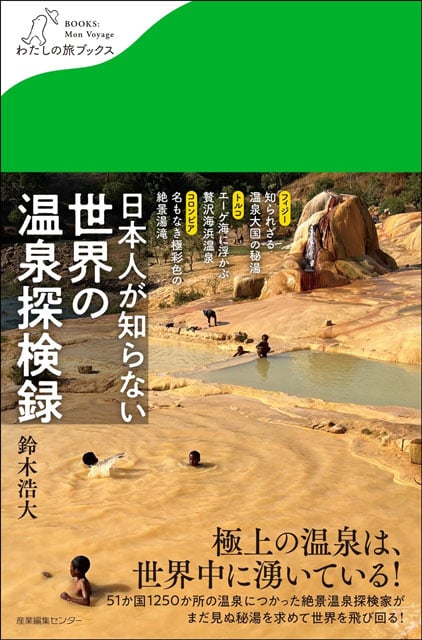2024/5/26 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、京都大学名誉教授の「田中 克(たなか・まさる)」さんです。
田中先生は1943年、滋賀県大津市生まれ。京都大学大学院と水産庁の水産研究所で、おもに日本海のヒラメやマダイ、有明海のスズキなど、稚魚の研究に40年以上、取り組んでこられたそうです。
そして、2003年4月に設立された「京都大学フィールド科学教育研究センター」の初代センター長に就任。ご自身の研究などから、森と海の関係性に着目し、「森里海連環学(もりさとうみ・れんかんがく)」を提唱。
現在も「森里海を結ぶフォーラム」や「“宝の海”の再生を考える市民連絡会」などで、精力的に活動されています。また「森は海の恋人」運動で知られる気仙沼の漁師さん「畠山重篤(はたけやま・しげあつ)」さんとは、活動をともにする同志的な関係でもいらっしゃいます。
きょうは、そんな田中先生に「森里海連環学」がどんな学問なのか、改めて解説していただくほか、有明海の再生を願う市民運動のシンボルにニホンウナギを掲げ、
「サステナブル・ウナギ ・ゴールズ」SUGsを提唱されているということで、そんなお話もうかがっていきます。
☆写真協力:田中 克

「森里海連環学」は『里』が肝心
※2003年から提唱されている「森里海連環学」とはどんな学問なのか、改めて教えていただけますか。
「ちょっと堅苦しい名前なんですが、基本的には森と海とは不可分につながっている。ところがその間の里は人の生活集団みたいなもんですから、その里の、都会も含めた人々の営みと、広くとっていただくと、その営みが海にも森にも少なからぬ影響を与えて、海と森の間の、命の最も大事な源である水の循環を壊してきていると。それが地球環境問題の根源のひとつで、それをもとのまっとうな形に直したいという思いの学問なんですね。
今までの学問というのは、客観的な事実を明らかにして論文にすれば、事が足りたと。でもここまで地球環境問題が深刻になってくると、研究者の役割もそこでストップするんじゃなくて、得られた科学的データを基にして、森とのつながり、自然の再生、それを壊してきた社会の仕組みの再生も含め、まっとうな方向まで戻す提案までできる学問になればということがひとつの思いですね。
それからもうひとつは、森は森、海は海、その間の里や、あるいは森と海をつなぐ川、それぞれ個別にこれまで研究も教育もされてきた。でもそれらは一体につながっていることがだんだん明らかになって、そういう個別細分化された学問じゃなくて、バラバラになった専門分野をもう一度つなげ直して、もうちょっと大きな視野で物を見て、物事が多様につながりながら地球が動いている、そういうメッセージを発したいという思いの学問になります」
●森と里と海は、川でつながっている。そのつながりを強く意識するようになったのは、何かきっかけがあったんですか?
「私は、もとは京都大学の農学部に在籍をしていたんですが、農学部はある面では総合学問領域で、森を研究する部門もあれば、海を研究する部門もあるし、里に関わる部門もあるし、川に関わる部門もある。でもそれぞれ10個ぐらいの学科で、森は森の林学科、海は海の水産学科・・・一切の交流がなかったんですね。
たとえば(農学部は)京都府にありましたから、京都府のいちばん代表的な森というのは、由良川という京都でいちばん大きな川の上流域に、森の研究や教育をする演習林、芦生研究林っていうのがあるんですね。そこから由良川が140キロぐらい流れて、若狭湾の河口近くに海の研究をする水産実験所がある。
同じ農学部であるのに何十年も一切、教育研究でつながりがなかったというのを、これはちょっとおかしいよっていうので、まずは森の教育研究施設と海の教育研究施設がもう一度、川を介してつながっているんだから、一緒にいろいろ進めましょうというのが思いのひとつにあります。
確かに森と海は川がつなぐんですが、最近の研究では見えない川があるんです。見えない川というのは地下水で、目に見えないつながりがある。ともすれば、見える川だけに注目しますけれども、地下水も含めて、本来は森と海を水がつなぐという意味では、森川海連環学でいいんですが、 そうではなくて、川の流域に住む私たちの暮らしのあり様、産業のあり様をもういっぺんちゃんと問い直すという意味で、間を『里』にしたんですね。そこが味噌になります」
「森は海の恋人」運動、畠山さんとは同志
※以前、この番組に「森は海の恋人」運動で知られる気仙沼の漁師さん「畠山重篤(はたけやま・しげあつ)」さんにも何度かご出演いただいています。畠山さんは牡蠣などの魚介類が育つには、川が運ぶ森の養分が欠かせないことに、いち早く気づき、気仙沼の海に注ぐ川の上流に、木を植える運動を長年続けていらっしゃいます。
田中先生は、畠山さんの活動に影響を受けた、そんなこともありますか?
「はい、結果的にはものすごく影響は受けているんです。畠山さんたちの、気仙沼の牡蠣やワカメの養殖漁師さんたちは、海が汚れてきて、それは自分たちが海を汚したわけではなくて、川の流域だとか森の荒廃だとか、そこに感覚的に気づかれたんです。それで漁師が山に登って木を植えようと。それが始まったのが1989年なんですね。それから2003年に京都大学に森里海連環学が生まれて、それまでは基本的には一切つながりがなかったんです。
私たち研究者が頭をひねって、これからこういう学問が大事だっていう思いを深めたら、既に現場の漁師さんたちは、そんなことは当たり前だと言って、行動に移されて10数年続けていた・・・。それでこれからは社会運動としての『森は海の恋人』運動と、それを支えながら協同する森から海までのつながりの学問、森里海連環学が、その後は一緒にお互いに助け合いながら動いてきた。ですから『森は海の恋人』のほうが先輩ですし、いろんな影響を受けております」

●では畠山さんとは、志を共にする同志のような関係なんですね。
「そうですね。(畠山さんとは)生まれも1943年で同い年ですし、それから私も、もともとは海の出身で、畠山さんたちは代表的な生き物として牡蠣を指標にして、牡蠣がまっとうに育つためには、森からの栄養分や微量元素が必要だということで、私は魚の研究でしたけれども、魚の子供たちが海辺の水際で育つのも全く一緒の原理だということで、思いはひとつですし、同い年だし、志が一緒ですから、むしろ私のほうが教えられながら一緒に歩んできているというのが現実ですね」
(編集部注:田中先生は、2011年3月11日の東日本大震災で壊滅的な被害を受けた気仙沼の、牡蠣やホタテなどの養殖業を1日でも早く復活させるために、全国の研究者に呼びかけたそうです。そして2011年4月に予備調査を行ない、5月には全国から手弁当で研究者が集まったということです。
畠山さんからは、牡蠣やホタテなどの養殖に欠かせない、植物プランクトンが回復しているかを調べてほしい、そんな要望があり調べたところ、予想以上の回復が確認され、養殖業再開への希望の明かりが灯ったとのこと。この調査は現在も続けられているそうですよ。
実は田中先生は、気仙沼の舞根湾(もうねわん)に2014年に設立された「舞根 森里海研究所」の所長でもいらっしゃいます。この研究所は、漁師さんが漁網などの道具を保管する小屋「番屋」を復活させる、日本財団の「番屋」の復興プロジェクトの一環として作られ、現在も研究者や学生さんの活動の拠点として大きな役目を果たしているそうです)

ニホンウナギのブックレット
※田中先生の活動はさらに加速し、2021年10月には「森里海を結ぶフォーラム」を発足。これは森の養分が海の養殖業を支えている仕組みは気仙沼に限らず、全国の主要な河川とその流域でも同じなので、森の人、海の人が一堂に介して相談や情報交換ができる場を作ろうということで、年に一回、フォーラムを開催。また、広場という名目で、隔月でオンラインでも開催しているそうです。
そんな田中先生は現在、「森里海連環学」を象徴する生き物といえるニホンウナギをテーマにしたブックレットを制作されています。企画と編集は田中先生なんですか?
「そうですね。一応、呼び掛け人的な役割をさせていただきながら(進めています)。ウナギというのはご存知のように、南の遠い海で生まれて、半年かけて日本にやってきて、川の入り口や汽水域や、場合によっては川の上流で、要するに森の中で育って、今度は子孫を残すためにふるさとに帰っていく・・・。どんなふうにして日本にやってきて、どんなふうにして向こうに帰るかっていうのはいまだに謎で、とっても面白い生き物だと。地球のことを我々人間よりもずっと長い年月をかけて、よく知っていると。
そういう大先輩を絶滅危惧種にしてしまった人間が彼らに謝って、彼らの賢さをもう一度学びながら、まっとうな自然や社会に再生したいと。そんなことで、ウナギはきっと迷惑でしょうね。そんな位置付けにされるのは、ほっといてくれって言われそうですけども・・・(笑)。
私たちに続く未来の世代がもうちょっと自然を楽しみながら、自然と共存できる、共生できる暮らしをするためには、最も身近な絶滅危惧種のウナギの、彼らが発信しているメッセージを聞き取って、そしてウナギと私たちが共に確かな未来を開こうよと、そういうことをまとめた本なんです。
(執筆者が)28名にもなると、いろんなかたがおられて、なかなか思うようには原稿が集まらないという・・・(笑)、でもほぼ集まりましたので、今年の土用の丑の日までにはウナギの声としての、いちばん端的には、野生の生き物ウナギにも、こんなに厳しい環境に追い込まれた彼らにも、裁判所に訴えて裁判ができるという、『自然の権利』と言って、今世界中でもそういうことが認知されているんです。
日本ではまだまだ認知度が低くて・・・ですからウナギ読本、ウナギ・ブックレットは、ウナギにもちゃんと自然をまっとうにしたいということを願う、訴訟する権利があるんですよって、そんな本なんです」
●その本は一般のかたでも入手可能なんですか?
「むしろ一般のみなさんにぜひ! 特に小学校高学年から中高生ぐらいの、これからの時代を担う人に、自然と共生するということの意味だとか、そういうことを世界に発信できる、そういう日本にしていきたいというので、むしろ若い世代の人に読んでもらいたいという本ですね」
「サステナブル ・ウナギ・ゴールズ」=SUGs
※去年の夏に長崎県諫早市で、「“宝の海”の再生を考える市民連絡会」という市民団体が発足したという記事がありました。この運動のシンボルが、ニホンウナギになっていますが、この市民連絡会の代表も田中先生なんですか?
「そうですね。これまで有明海、”宝の海”というのは本当に豊かな海だったんですね。貝も魚もエビもいろんなものがたくさん獲れて、獲っても獲っても獲り尽くせないぐらい豊かな海だったのが、いろんな問題が重なって、そういうものはだんだん獲れなくなってきた。

獲れなくなっただけじゃなくて、日本では有明海だけにしかいない魚介類が、これは中国大陸の沿岸に起源を持つ、氷河期の遺産的なすごく面白い生き物がたくさんいる。要するに生物多様性の宝庫なんですね。その生物多様性の宝庫で、漁業者にとっても暮らしが成り立つし、地域の経済も回る。そういう海が残念なことにこの半世紀の間にどんどんおかしくなって、今では”瀕死の海”と言われるぐらいになってしまった。
これまでは、そういうことに関心を持った地元のみなさんが、本当に頑張って再生を願っておられたんですが、裁判に訴えてもなかなか認められない。ですから、もう地元のみなさんだけの話ではなくて、この国が多かれ少なかれ関わった、そういう水際を大事にしてこなかったツケとして、今まで関わった人たちだけじゃなくて、もっと広くみなさんにというので、今進めつつあるということですね」
●目指しているのがSDGsならぬSUGs「サステナブル・ウナギ・ゴールズ」と記事に書いてありました。これにはどんな思いが込められているんですか?
「ひとつは有明海全体の、いちばん上に筑後川が流れて、その河口が柳川市なんですね。柳川市は堀割が巡らされて、そこにはいっぱい昔はウナギがいたと。今もウナギのせいろ蒸しで、すごく有名な場所なんですね。
有明海の、筑後川から流れた砂や水が最後に半時計回りに流れてたどり着くのが諫早湾で、諫早湾の湾奥には本明川という川があって、牡蠣とウナギがたくさん獲れて、そこもウナギがすごく大事な場所なんです。
でも堤防を作ったりすると、なかなかウナギが来なくなったというので、有明海の森とのつながりの、命の循環を考える上でウナギがいちばんわかりやすいし、しかも人間が絶滅危惧種にしてしまった彼らと共に生きることが、人間にとってもすごく大事ですよっていうので、SDGsのDはディベロップメントですよね。
これはやっぱり人間中心の人間のためのディベロップメント・・・そうじゃなくて、自然とともに共生するためには、野生の生き物の知恵を借りて物事を考えていくのが大事だというので、これまたウナギに無断でSUGsにしてしまったということです(笑)」

(編集部注:「“宝の海”の再生を考える市民連絡会」には共同代表として、元テレビキャスターの野中ともよさんや、ファッション・モデルのNOMA(ノーマ)さんも名を連ねているそうですよ)
シーカヤックで海遍路
※田中先生は70歳を前にシーカヤックを始め、高知大学の名誉教授「山岡耕作(やまおか・こうさく)」さんたちが2011年にスタートした、四国お遍路の海版「海遍路」に2年目から参加。東北、九州、三浦半島、山陰など、日本の漁村をめぐる旅を、いまもこんな感じで続けているそうですよ。
「年に1週間から10日間ぐらいですけれども、数人のグループ、カヤック2艘ぐらいで、すべての生活機材を積んで、たどり着いた漁村で泊まって自炊をしながら粗食に耐えていると、漁師さんがもの言わず“これ食べろ”って魚をくれる。そうすると自然な対話ができるんですね。もういっぺん、海からものを考えようという旅になっています」
●シーカヤックの魅力ってどんなところにあると思いますか?
「漁師の人から見れば、すぐにひっくり返ってしまうように見えるんですけど、意外に安定性もある。まずは自分の力で漕がないと目的地に行けない。でも頑張れば目的地にも行ける、そんなところですね。
要するに現代社会が失ってしまった、何かみんなレールの上に乗せられて、自分が行きたいとこじゃないところに連れていかれるようなこととは違う。その代わり危険なことも体感しながら、逆に新しい出会いがある、そんないろんな魅力がいっぱい! とても面白いですね。
もともと日本人がどこから来たかというのも、大陸説もあるし海洋説もあるし、かつての我々の大先輩もあんなボートの原型みたいなので、暮らしを切り開いてきたのかもしれない。
そんなことも思うというのと、もうひとつは、一般の船よりはお尻が水の中に入るぐらいの位置ですから、目線が言ってみればアメンボ目線みたいに・・・ですから本当に海の生き物たちと同じ目線でものが見られるというのも特徴かもしれませんね」

「つながり」をもう一度大事に
※「森里海連環学」を提唱されて20年以上が過ぎました。いまどんな思いがありますか?
「私自身は提唱して4年で現役を退職して、森里海のやっぱり”里”が鍵だと、我々自身の振る舞いですね。ですから、それを畠山さんたちと一緒に現場で取り組んできた。そういうのと、現役の京大フィールド研の研究者のみなさんは研究教育の分野、それが今、両方がかさ上げしながら少しレベルアップして、幸いなことに畠山さんのお力がすごく大きいと思いますが、テレビや新聞とかいろんなニュースにも森と海のつながりが、比較的当たり前のように出始めたというので、それは非常に喜ばしいんです。でも、それで私たちの行動がどう変わるかというのが次のステップで、それをもうちょっと頑張ってやれればという思いでいます」
●では最後に、リスナーのみなさんに特に伝えておきたいことなどがありましたら、お聞かせください。
「いろんなことが本当はつながっている。ところが目先の暮らしの利便性だとか直近の経済の成長とか、どうもそちら側に舵が切られすぎて、この世に自分たちが生まれてきてよかった! っていうような思いが、なかなか実感できない世の中です。
それは目に見えない、さっきの川じゃないですけれど、地下水が大事な役を果たしているように、縁の下の力持ち的な、目に見えないつながりをもう一度丹念に紡ぎなおす。そして同時に次の世代が幸せになるにはどうしたらいいかっていうのをいちばんに、物事を考えられるようになり行動できれば、地球ももうちょっとよくなるし、日本社会もよくなるんではないか・・・。ですから、いろんなことがつながっていることをもう一度大事にしましょうよ! というのが、いちばんの思いですね」

INFORMATION
ぜひ田中先生の活動にご注目ください。先生が代表を務める「森里海を結ぶフォーラム」や「“宝の海”の再生を考える市民連絡会」、そして畠山さんの「森は海の恋人」運動のサイトを定期的にチェックしていただければと思います。
◎森里海を結ぶフォーラム :
https://morisatoumi-forum.studio.site
◎“宝の海”の再生を考える市民連絡会 :http://www.einap.org/jec/subcategory/projects/49
◎森は海の恋人 :https://mori-umi.org
今年の「土用の丑の日」に出す予定で進めていらっしゃるニホンウナギのブックレット、発売日や入手方法については、分かり次第、この番組または番組ホームページでもお知らせします。