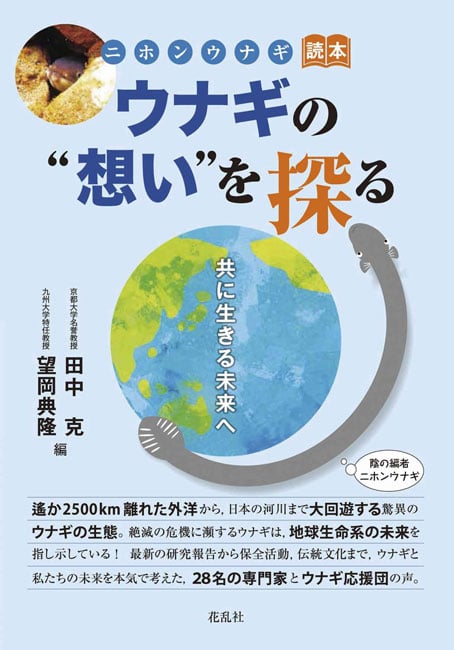2024/9/29 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、カリフォルニア大学バークレー校の教授で、理論物理学者の「野村泰紀(のむら・やすのり)」さんです。
野村さんは1974年生まれ、東京大学理学部から東京大学大学院で理学博士に。現在はカリフォルニア大学教授、バークレー理論物理学センター長のほか、ローレンス・バークレー国立研究所の上席研究員など、多方面で活躍されています。
ご専門は素粒子物理学や宇宙論で、近年は宇宙はひとつではない、たくさんあるという「マルチバース理論」の研究でも世界的に注目されています。また、2年前に出版されたブルーバックス・シリーズの一冊『なぜ宇宙は存在するのか〜はじめての現代宇宙論』がロングセラーを記録しています。
宇宙研究の最前線にいらっしゃる野村さんですから、きっと子供の頃から、星や宇宙にのめり込む天文少年だったのかな〜と思ったら、そうでもなかったそうです。ただ、NASAの探査機ボイジャーが土星に接近する時期に合わせて、1980年に日本でも放映された、アメリカの科学者カール・セーガン監修の科学ドキュメンタリーを見て感動! また、高校生の時に、特別講義で相対性理論をわかりやすく解説するような、とてもいい先生に出会ったことで、野村少年の意識の中に「物理学」はあったそうですよ。
そんな野村さんが一時帰国されていたときに、都内某所でお話をうかがうことができました。今回は宇宙の、数ある謎や不思議から、膨張しているとされている宇宙はこの先どうなるのか、そしてマルチバース理論や パラレルワールドのお話などお届けします。

素粒子物理学とは? 宇宙論とは?
※野村さんは東京大学大学院で、今のご専門「素粒子物理学」と「宇宙論」を研究されていたんですか?
「当時は、まあ今でもそうなんですけど、一応、素粒子物理学の研究室と宇宙論の研究室が分かれているので、僕は素粒子だったんですよ。で、素粒子の人って宇宙論を結構やるんですね。宇宙を調べるのに実は素粒子っていう、非常に高い温度とか高い密度の状態で、物がどうなるかを調べる学問が必要なんですよ。
なぜかというと、宇宙は実は昔すごく熱かったんです。なので(宇宙論も)やるんですけど、僕は素粒子論研究室にいたので、宇宙はセミプロというか素人として手を出すみたいな感じだったんです、最初は。で、だんだんやるようになっていったという感じですね」
●その素粒子物理学ってどんな学問なのか、かいつまんで教えていただいていいですか?
「はい、たぶんかいつままないと、とんでもなくひどいことになると思うので(笑)、できるだけかいつまんでいきますね。
僕らの世界って、例えばいろんな物質があるけど、原子でできている、そこぐらいまでは習うというか、聞いたことがあると思うんですけど、実は原子には構造があって、中心に原子核があるんですね。本当に核みたいなやつがあって、プラスの、正の電気を持っているんですけど、その周りをマイナスの電気を持った電子っていう、小さな粒がフラフラしているんですよ。
そういう絵とかを見たことがあるかたもいらっしゃるかもしれないんですけど、そのスケール感って実はすごくて、例えば原子核が1円玉ぐらいだとすると、原子のサイズってサッカーコートぐらいのサイズなんですよ。だから電子がフラフラ飛んでいるのってものすごく遠い、5桁くらい大きさが違うんですね。
原子のサイズが0.000000000、0が9個ぐらいついて1ぐらいなんですけど、さらに0を5個ぐらいつけたサイズが原子核なんですね。その原子核も実は陽子っていう粒と、中性子って粒からできていることが分かってきたんですね、20世紀初頭の頃ですけど・・・。そうすると、実はその陽子ももっと小さいクォークっていうものからできていることが分かってきているんですよ。
で、現在どのぐらい小さいところまで人間が分かっているかっていうと、原子核のサイズの1万分の1とか、10万分の1ぐらいまで見ることができている。で、だから自然界って何でできているのか、全部クォークと電子とか、あとちょっと変なのがいろいろあるんですけど、ニュートリノって聞いたことあるかもしれないんですけど・・・。
そういうふうに世の中が何で成り立っているのか、そういうものがどういう仕組みで動いているのか、具体的にはどういう力を感じて、どういうふうに、相互作用っていうんですけど、お互いに影響を与え合って動いていくのかを調べていく学問です。
今ある意味、それは解明されつくしていて、1本の式ですべてが、人間も物質も机もすべてが、その1本の式に従って動いているだけだ、っていうところぐらいまではいっているんですよね。それより小さい世界はまだ分からないし、今でも観測と理論、実験と理論で調べているっていう、それが素粒子っていう学問ですね。
宇宙論はよくイメージするのは、おそらく宇宙っていうと、僕もよくいろいろ(講演で)呼ばれたりするんですけど、宇宙開発とかそういうのは宇宙論とはちょっと違うんですね。もちろん興味はあるし、つながっているんですけど、それこそ天体すらあんまり関係ないみたいな、アンドロメダ銀河があっていろんな銀河があって、銀河がどういう形をしていてとか、それすらあんまり関係なくて・・・。
宇宙論と言った場合は、例えば地球って一方向に歩いていくと、後ろから戻ってくるじゃないですか、球面なので。そういう感じで宇宙は、例えば一方向にずっと進んでいったら、後頭部の後ろから戻ってくる構造になっているのか、例えばそれとも無限に続いているのかとか、宇宙っていうのは実は変わっているんですね。膨張しているんですけど、物と物との距離が広がり続けているんですよ。
ということは、昔はもっとギューギューだったはずなんです。高い密度なので温度も高くて、ビッグバンとか言うんですけども、もうピカピカに光り輝いている世界、そんな世界がどうして始まったのかとか、どうやって温度が下がってきて、その過程で何が起こったのかとか、そういう宇宙全体を見るみたいのが、宇宙論って呼ばれている分野です。
近くの星とかをイメージするのはどちらかというと、例えば天体物理学とか天文学って呼ばれる分野になりますね」
●なるほど〜、ちょっと違うんですね。
「もちろん、お互いにいろいろ刺激も与え合うし、ほかの研究もしますけど、一応そういう名前としては棲み分けみたいになっていますね」
ビッグバンとは!?
※野村さんの本『なぜ宇宙は存在するのか〜はじめての現代宇宙論』でも触れていらっしゃいますが、宇宙はビッグバンという大爆発で誕生したんですよね?
「そうと言われているんですけど、いわゆる一般に思っている爆発と違う可能性が結構あって・・・ビッグバンっていうと、宇宙は昔ギューギューだったのは確かなんですよ。
さっき膨張していると言ったのは・・・これ、20世紀の頭ぐらいに分かったんですけど、自分の銀河系以外にも銀河系があるってことが分かってきたんですね。アンドロメダ銀河とかも点に見えますから、僕らから見ると・・・。
それが本当に僕らがいわゆる銀河って言っている星の塊のひとつなのか、それとも同じような星の塊がもっと遠くにあるのかっていうのは分かんなかったんですよ。僕らの銀河系を宇宙って呼んでいたんですよね。宇宙以外に宇宙はあるのかって言った時は、アンドロメダとか別の銀河の話をしていたんですよ。
でも20世紀に実は、銀河っていうのはいっぱいあるんだってことが分かってきて・・・で、その銀河までの距離を測れるようになったら、あと、銀河がどれだけのスピードで近づいているか、遠ざかっているかを測れるようになると、どうもほとんど全部の銀河が遠ざかっているんですよ、僕らの銀河系から。
で、それを考える時に僕らが中心だと思っちゃう、みんなが遠ざかっているから。でもそうじゃなくて、イメージする時によく言うのは、風船の上に点々を書いて、ふーって膨らましていくと、点と点の距離って全部広がっていくので、自分がどの点だったとしても、すべての点が遠ざかっていくように見えるわけですよ。
同じことがやっぱり起こっているようで、理論的にもそうだってことは分かってきて、距離が遠ざかっているんですね。ってことは・・・すいません、ビッグバンの話ですね。これね、悪い癖なんですよ。ひたすら話しちゃうんで、止めてください(笑)。
で、距離が遠ざかっているってことは、時間を遡っていくと、物と物との距離が近かったんですよ。物と物との距離が近いと、やっぱり密度がギューギューになって、密度がギューギューになると、温度が高いっていう状態なんですよ。だから昔に遡れば遡るほど、すごく熱い状態だった、それをもってビックバンっていうので、宇宙全体のサイズが0になったりする必要ないんですよ。
全体は、例えば非常に大きいというか無限に大きいまま、密度が非常に高い状態から出発して、密度がどんどん下がっていったっていうことだけが分かっていて、その高温高密度の状態を一応ビッグバンと言うんですよね」
100億年後は、超巨大銀河!?
●先ほどもお話にありましたけれども、宇宙はこのまま膨張し続けるってことですか?
「それが知りたくて・・・宇宙の膨張って、広がっているんですけど、みんな(研究者は)その広がりのスピード自体は遅くなると思っていたんですよ。なぜなら重力は必ず引力なので、万有引力って言われるように、物と物は引き合っているから、遠ざかっていてもその遠ざかるスピードは遅くなる、どのくらいのスピードで遅くなるかを測っていたんですね、みんな。
なんでそれを測ったかっていうと、遅くなり方が非常に早いと、どっかでその膨張は止まって、今度は収縮フェーズに入って、逆に“逆戻しビッグバン”みたいな、『ビッグクランチ』とか言っているんですけど、それが起こって、すごく高温高密の世界になっちゃうか、それとも遅くなり方がそんなに遅くなってないと、そのまま膨張のスピードが遅くなりながら、でもずっと永遠に広がり続けるかを知りたくて、どれだけ減速しているかを測っていたんですね。
で、1998年に精密なその結果が出て、答えはその膨張が早くなっていたんですよ、加速しているんですよ。
それは理論的にはすごいことで、物は必ず減速させるんで、さっき言ったように万有引力なので、宇宙のエネルギーのほとんどって物ですらないってことで、重力、引力なはずなのに、物をはじき飛ばして、加速させて膨張させるようなことが実際に現在起こっている・・・。
そのまま続いていくと加速しているので、ひたすら膨張していって、しかももっと早く膨張するような、ある意味ずっと膨張を続ける感じになるじゃないかなと思ってますね」
●加速して膨張し続けると、どうなっちゃうんですか?
「あるところですごく早くなっちゃうので、遠くの物って原理的に見えなくなっちゃいます。なぜなら、例えばすごく遠くの銀河から、こっちに向けて光が来ているわけですけど、光がこっちに来ようと思っても、空間が膨張するほうが早いので、空間膨張って、より空間ができるって感じなんですよ、イメージ としては。物と物との間に空間が作られ続けちゃう、その作られているスピードのほうが光より早いので、原理的に見えなくなっちゃうんです。
だから、あるところから壁みたいのがあって、全くそこから先は見えないっていう世界になって、しかもアンドロメダとか僕らの銀河はそんなに遠くないので、実は引き合っているんですね、重力で。近い銀河たちはそれが勝つので、それこそ40億年ぐらいすると、僕らの天の川銀河は隣のアンドロメダ銀河に吸収されます。ひとつになっちゃう・・・。
その近くにある、ちっちゃい銀河は全部ひとつになって、ひとつの超巨大銀河になるので、100億年後ぐらいにはたぶん、”え、宇宙って巨大銀河がひとつあって、あと遠くは全く見えない世界だよね”っていう、その頃に宇宙論の人がいればですけど、宇宙ってそういうのに決まっているだろ、みたいな感じの世界にまずはなります」
宇宙はひとつじゃない!? 〜マルチバース、パラレルワールド
※宇宙は英語では「ユニバース」で、この「ユニ」は「ひとつの」という意味ですから宇宙はひとつと、これまで当たり前に思っていました。ところが、野村さんの本で初めて「マルチバース」という言葉に出会いました。このマルチバースとは何なんでしょう?
「人間ってこの世界がすべてだと思ったのが、すべてじゃなかったっていう繰り返しをやっているんですよ。
ルネサンスの時代に太陽系、実は地球が中心じゃなくて、太陽を中心として、ほかの惑星があるんだって言った時も、ほかの星の背景は壁紙みたいに思っていたわけです。でも、実は違ったんですよね。この太陽系みたいなものがたくさんあったんですよ、本当に一部にすぎなくて・・・。銀河系を理解した後も実は銀河系、たくさんある銀河系のひとつに過ぎなかったんですよね。
で、僕らが全宇宙だと思っていた領域も、実はもっと大きな構造のひとつっぽいということがわかってきて、だからあまり衝撃的な話では、ある意味ないんですけど、その都度やっぱり自分が思っていたより、全然大きい世界があるっていうのは、衝撃的ですけどね」
●宇宙ってたくさんあるっていうことなんですか?
「そう! 具体的に言うと、宇宙とは何かって言わないと、実は今の話もあまり意味がなくて・・・宇宙のほかに何かがあったとするじゃないですか。それも含めて宇宙って呼ぼうぜって言えば、宇宙しかないに決まっているので・・・。
まず僕らの宇宙は何かって言うと、さっき言った、それこそ素粒子の研究が進んできて、僕らの宇宙ではアンドロメダに行こうが、遠くの銀河に行こうが、原子でできていて、電子がフラフラしていて、原子核があってっていうのは同じなんですよ。同じ法則というか、同じ素粒子の種類、同じ力の性質とかで全部(式が)書ける。
で、それがすべてだと思っていたんですけど、どうもそうじゃないらしくて、例えば電子のない世界、それこそ光もない世界とか、素粒子の質量っていう重さとか種類とかが全然違う世界がやっぱり山ほどある・・・。
僕らの周りというか僕らの宇宙って呼んでいるところは、たまたまこの原子核なり電子なりっていう性質の構造になっていると考えないと、なかなか理解できないような現象がいっぱい見つかってきて、理論方程式を見直してみたら実際そういうふうになっていた・・・人間は気づいてなかったけど、80年代に作った方程式はそうなっていたみたいなことで、そうなんじゃないかなって思うようになってきたっていうまだレベルですね」
●どうして、そもそもそのマルチバースに着目しようって思われたんですか?
「僕の場合は、本当はもう少しテクニカルなこともあるんですけど、僕らの宇宙がよくできすぎているんですよ。例えば電子とか原子核みたいのを調べていくじゃないですか。僕のキャリアはその素粒子物理から出発したので・・・。
そうすると例えば電子の重さなりを変えますと・・・変えてもいいはずなんですよ、理論的には。単に重さって、パラメーターって言うんですけど、測ってこうだったんだから、こうだって言っているだけで、それをちょっと変えた世界を考えてみたりすると、ちょっと理論を少し変えるだけで、何にもない世界になっちゃうんですよ。
人間とかが変わるのは当たり前ですよね、変えているんだから・・・じゃなくて、例えば元素の種類が百何十種類ありますよね。日本でも『ニホニウム』が見つかったりして、それがあっという間に1種類とかになっちゃうんですよ、ちょっと変えると。ほかのパラメーターもちょっと変えると、銀河なんか一切できないですよ。本当にピッタリうまくいった時にしか、こういう構造ってほとんどできないっぽいんですよ。それは困りますよね。やっぱり神様が作った、でもない限りは、なんで世の中そんなふうになっているんだと・・・。
ところが、同じ現象をもうすでに僕ら何度も経験していて、例えば地球ってすごくよくできていますよね。水があって森があって自然があって生物が繁栄して・・・。でも太陽と地球の距離がちょっと違っていたら、あっという間に灼熱の世界とか液体窒素だけになっちゃうけれど、なんでこんなにうまく、神様が作ってくれた星なのかと・・・いや、違いますよね。
いろんな距離のところにいろんな大きさの惑星が山ほどあるから、ほとんどのところは実際本当になんもいないんですよ、なんも構造ないんですよ。灼熱の世界だったりするんだけど、たくさんの種類のものがものすごくあるから、そうするとたまたまラッキーなところもあって、そういうところにだけ、こういう知的生命体とか構造が生まれるから、その人たちが周りを見た時には、なんでこんな奇跡的なんだ、俺ら超ラッキー! ってなるわけですよ。
おそらく宇宙全体にも同じようなことが起こっているんですよ。だから構造がなんでこんなにラッキーかっていうと、違う種類の宇宙が山ほどあるので、そうすると山ほどあれば、たまたまレンジに入る、レンジに入ったところにしか銀河なり、生命体ってできない。
それは計算で示せるので、ちょっとずらすと何にもできなくなっちゃうから、そうするとたぶんそういう理由で、僕らが見ている宇宙の構造自体が決まっていたんじゃないかと考えると、神様を持ち出さなくて済む。
で、サイエンスっていうのはやっぱり神様を持ち出さずに、僕らが観測した周りをどれだけ理解できるかっていう学問なんですよね。神様はいるかもしれないですけど、それを持ち出さずにどれだけ理解できるかっていう学問なので、自然に考えると、理解して僕らが全宇宙だと思っていたのも、たくさんの構造のひとつなんじゃないかっていうルートですね、僕は」
●映画になりそうですね?
「そうですね。なんか映画で逆に結構使われますよね。でも実は映画で使っている『マルチバース』というと、いろんな世界があるってことなんですけど」
●パラレルワールドみたいな、またそれとは違うんですか?
「パラレルワールドとは、もともとは違うコンテクストで出てきたんですね。僕自身が言っているのは、あまり違うものでもないんじゃないかっていうことなんですけど、ちょっとずつ違った世界があるんですよ。それがパラレルにあるのか遠くにあるのかを考えると、遠くにあっても無限にデカければ、必ず繰り返して似たような世界ありますから、ちょっとずつ僕が違う・・・きょうはここに来るのにちょっと遅刻をしてしまったんですが(笑)、してなかった世界とか、ちょっとずつ違う世界があるはずだっていうふうになると、映画とかに使いやすいですよね。
あの時、ああしてなかった世界もあって・・・ただ、映画と現実ではちょっと違う、映画は自由に行ったり来たりできるんですよ。そうじゃないとストーリーにならないので・・・。でもそれはやっぱりなかなかできないですよね。例えば遠くにあれば、光のスピードを超えられないので物理的には行けないし、パラレルワールドもそんなに簡単に干渉できないのはわかるので・・・でも映画によく使われたりしますよね」
●もしかしたら私たちのような地球人が、ほかの宇宙のどこかにいるかもしれないってことですか?
「いるじゃないですかね。実はパラレルワールドみたいな考え、量子力学って言うんですけど、それを考えると、物っていろんな状態の重ね合わせっていうか、いろんな状態に分かれていくのは、電子とかの簡単なシステムでは、その分かれた世界をもう1回、一緒にさせるみたいなことができているので、電子とかの世界では、どうもパラレルな世界がいっぱい分かれているって事実なんですよ。
でも僕らって電子とかからできているから、それがちょっとずつ違う位置にあるような世界に分かれているんだったら、 ちょっとずつ違うってことは、僕らのシナプスとかもちょっとずつ違っているはずなので、ちょっとだけ考えが違う世界とか、ちょっとずつずれている世界ってやっぱりあるんですよ。
でも、どこまでが僕なのかっていうのは微妙ですよね。ちょっとずつ変わっていって、顔もちょっと変わって、僕は大谷選手ぐらい野球がうまくて、それはもう僕じゃないだろう!という感じなので、いろんな僕がいるっていうけど、どこまで僕なのかとか、そういう話になって面白いですよね」
夢は『量子重力理論』の完成
※今後、解き明かしたい宇宙の謎はありますか?
「実は僕らが宇宙とかマルチバースを調べる時って、実は理論的にはパッチワークでやっているんですよ。
それはどういう意味かっていうと、僕らの世界って量子力学って、実はさっき言った変な仕組みで動いているんですね。それを使って計算なんかやろうっていうのもあって・・・量子コンピューターって名前を聞いたことがないかもしれない、これから聞くと思うんですけど、そういう原理で動いているんですよ。でもその原理を使う方程式は普通、重力は入ってないんですね。
重力を扱う時には、僕らはアインシュタインが作った一般相対性理論を使っているんですけど、その理論の中に量子力学の効果は入ってないんですよ、全く。でも両方あるはずなんですよ。僕らは量子の世界に生きておきながら、重力もあるのは確かなので、両方が入った理論はあるはずなんですけど、人間、完全に持ってないんですよ。一緒にしようとすると、クラッシュしちゃうんです。すごく難しいんですよ!
だからマルチバースの話をする時とかも、重力が重要なところはアインシュタインの理論を使って、量子が効くところはこっちを使って調べているんですけど、本当はそれを一緒にした理論を使って、バン!と調べなきゃいけないような・・・。
なぜか重力が重要になるところって、量子が重要じゃないんですよ。量子が重要になるところって、重力が重要じゃないんだけど、宇宙に例えば空間の始まりとか時間の始まりとか、そういうところってやっぱり両方が効いてきちゃうので・・・。その『量子重力理論』を完成させるのは、僕だけというよりはこの業界というかコミュニティの夢なんですよね。それが解明できたら嬉しいですよね。その瞬間、やることなくなってクビですけど(笑)」
●宇宙を研究したいと思っているお子さんたちや、学生さんたちに伝えたいことがあれば、ぜひお願いします。
「研究したいと思ってくれているかたたちがいるとしたら、もうそれはその時点でありがたいというか、そのまま興味を持ってくれれば嬉しいですね。
実際、例えばプロの研究者としてやりたい人じゃなくても、やっぱり面白いですから、興味を持ち続けてほしいっていうのがひとつと、もしそういう興味を持ってその先に研究っていうのがあるんだとすると、やっぱり情熱を持ち続けることが、これはどんな分野でもそうですけど、いちばんなので、刺激あるものに触れて、新しいものを読んで聞いて、人に会って刺激を受け続けながら、新しいことを開拓していってくれれば嬉しいなと思います」
●野村さんが宇宙に行けるとしたら、どこに行って何をしたいですか?
「そうですね・・・基地とかができていたら・・・基地を作ろうとしているわけじゃないですか。その基地に行って、窓から火星の真っ赤なのが見えたりしたらすごいですよね。たぶん1週間で慣れちゃうと思うんですけど、人間って・・・。でもそういう全然違う世界を死ぬ前に1回見られたら、見てみたいなとは思っていますね」
INFORMATION
ロングセラー中の野村さんの本をぜひ読んでください。宇宙論とあるように、天体とか銀河の話ではなく、宇宙全体の話で、この100年ほどの宇宙論の歩みを、いち科学者の視点で解説されています。ダークマター、ビッグバン、マルチバースなど壮大なスケールで語られる宇宙論にぜひ触れてみてください。
講談社のブルーバックス・シリーズの一冊として好評発売中です。詳しくは、出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。
◎講談社:https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000362613
野村さんの研究サイトも見てくださいね。
◎カリフォルニア大学バークレー校:https://physics.berkeley.edu/people/faculty/yasunori-nomura
◎理化学研究所:https://ithems.riken.jp/ja/members/yasunori-nomura