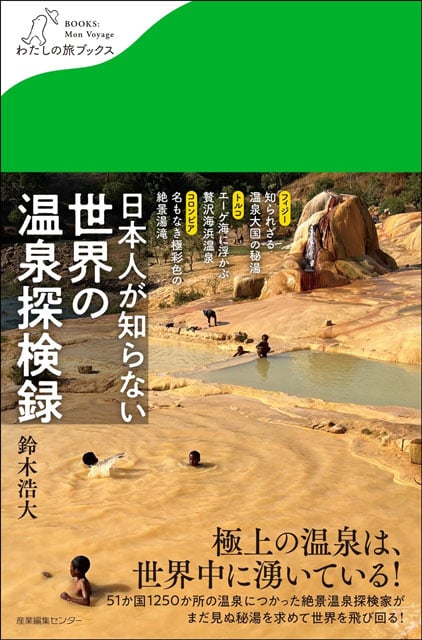2024/12/29 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、サバイバル登山家の「服部文祥(はっとり・ぶんしょう)」さんです。
服部さんは1969年、横浜生まれ。東京都立大学在学中にワンダーフォーゲル部に所属し、日本国内の山々を縦走。96年に世界第2位の、カラコルム山脈K2・標高8611メートルに登頂。97年から冬の北アルプス 黒部横断などに挑戦。99年からは食料を現地調達するサバイバル登山を始め、その後、狩猟にも取り組んでいらっしゃいます。
山好きのかたは、山岳雑誌『岳人』の連載で、服部さんのことを知っている、というかたもいらっしゃると思いますが、実はもともと『岳人』の編集者で、現在もフリーランスという立場で編集にも携わっていらっしゃいます。
そして作家としても数々の本を出されていて、いちばん新しい本が『今夜も焚き火をみつめながら 〜サバイバル登山家随想録』。これは山岳雑誌『岳人』に連載していた記事を中心に、えりすぐりのエッセイを加えて編纂した本となっています。
今回は14年ぶりのご出演ということで、改めてサバイバル登山とは、どんな山登りスタイルなのか、そんな初歩的なことから、数年前から始めたという自給自足的な古民家暮らしのお話などもうかがっていきます。
☆写真協力:服部文祥

「サバイバル登山」〜フリークライミング思想
※私、小尾は今回初めて「サバイバル登山」という山登りがあることを知りました。改めて、これはどんな登山スタイルなのか、教えていただけますか。
「自分の力で登ることにこだわった登山だと思っているんですけども、メインの思想というか中心の思想はフリークライミングにあります。フリークライミングは、自然のまんまの岩を自然のまんまの自分で登ろうっていう考え方だと、僕は理解しているんですけども、それをやってみると面白いんですね。
その前の段階のことをちょっと説明しておくと、人工登攀(じんこうとはん)っていうのがあって、岩登りがどんどん発展していく中で、岩に穴を開けて、そこにボルトを打って、それから縄梯子をぶら下げて登るっていうふうにどんどん発展していく、それが人工登攀なんですね。その中で、登るってことは一体どういうことなんだろう? って考えた人たちがいて、それがフリークライミングを生んだんです。
登るっていうことは、もともとある自然の岩の、登りたい人にとって、利用できる(ものが少ない)弱点を、自分たちの肉体を利用しながら、使うことでそれ(岩)を登っていく。
簡単に言えば、子供たちが岩とかを見た時に、これ登れる? ずるしないで登れる? みたいな・・・梯子をかけたりとか、上から垂れているロープとかをつかまないで、自分の体だけで登れるっていうようなのと同じだと思うんですね。そういうフェアな思想っていうか、スポーツマンシップみたいな思想を前面に押し出したというか、それに忠実にやろうと思って考えたのがフリークライミングだと思うんですよね。
実際、僕も自分でやってみて面白いし、これが登ることだなっていうのがすごくよくわかる。あと登れなかったら、今まで人間がやってきたように、その対象を加工しちゃうんじゃなくて、梯子をかけちゃうとか、穴を開けちゃうとかっていうんじゃなくて、一回おうちに戻ってというか、一回その岩から降りて自分を鍛えるんです。またそれにチャレンジするっていう、フェアネスの精神みたいなものもある。
岩を加工しないんで、岩は原始のまま、そこにずっとあるわけですよ。だから100回目にチャレンジした人も、最初にチャレンジした人と同じように、その岩と向き合うことができる。簡単に言うと持続可能なんですよね。

人間っていうか、我々は結構、自然環境を都合のいいようにいじってしまって、持続可能ではない世界をたくさん生んでしまったというか、(自然を)壊してしまったんですね。フリークライミングはそうではなくて、できるだけ自分たちの都合のいいようにいじらずにそのまんまの状態にして、だからこそ、ずっとこれから何年も何年も、最初に触った人と同じような喜びを、2回目でも100回目でも1000回目でも感じることができるっていう意味で持続可能なんですよ。
そういう意味でフリークライミングってすごく面白いというか、これから地球を対象に遊ぶ場合の、我々のすごく理想的なやり方だと思うんです。僕は日本の山を登って育ってきたんで、日本の山でフリークライミング的なことができてるのかって考えた時に、できてないな~と思って・・・。
今から日本にできちゃった道とかロープウェイとか、壊してもしょうがないんで、そういうものをできるだけ避けて、フリークライミングと同じように、過剰に便利な道具は使わないってことを課して、そういう条件で山に登ってみたらフリークライミング的にやっぱり面白いんですよ。
で、やったのがサバイバル登山で、名前は営業もあって、目を引くような、耳にちょっとなんなの? って、みんなが思うようなものを敢えてつけたっていう感じですね」
(編集部注 :初めてのサバイバル登山は、南アルプスの北に位置する「仙丈ヶ岳<せんじょうがたけ>」だったそうです。この時、持って行った道具はタープと薄い生地の寝袋など、食料はコメなどの穀類を少しと塩だけ。あとは現地調達にチャレンジしたそうですが、ご本人いわく、食べられる山菜やキノコがわからない、釣りが下手でイワナも釣れない。寒くて腹は減っていたけれど、面白くて清々しい気持ちだった。山を降りたあとに登山として美しいと思ったそうです。
その後、食料の現地調達に向けて、釣りの練習のほか、山菜などの知識を身に付けるために図鑑を見たり、友人に教えてもらったりと、スキルを磨いたとのことです)

肉も現地調達〜山の見方に変化
※食料は基本的には現地調達ということで、釣りに加え、その後、狩猟が加わりました。そのあたりの思いをお話しいただきました。
「食料って我々普通に生活していると、食料品店で買うのが当たり前ですけど、よくよくサバイバル登山をしてみると、本来の食料は自然環境から自分の手で獲ってくるものなんですよね。みんな、そうやってずっと何万年も生きてきて、最近は買うものになりましたけど・・・でもやってみると、そういうもんだなと思っているのに肉に関しては買ってんですよね・・・自分も買っていた。
サバイバル登山を通して、魚を釣って山菜を採ってキノコを採ってみたいなことをやっているけど、肉に関してはまだ買っているな~って・・・。肉もちゃんと自分で調達してみたいなと思って、一回登山はちょっと横に置いといて、狩猟だけをする2シーズンぐらいがあって、獲れるようになった時に、シカやイノシシを食料に、もしかしたら冬もサバイバル登山できるかもしれないって思って、思っちゃうとね、気がついちゃうとやらないといられないってわけじゃないですけど(笑)、気が付いちゃったんでやってみたのが、冬のシカを食料にしたサバイバル登山です」
●猟銃を持ってってことですよね?
「そうです。狩猟を始めた時は冬のサバイバル登山の意識っていうか、そういう発想は全くなくて、とにかく肉をちゃんと自分で調達して、その時、何を自分が感じるのかを知りたいなと思ってやっていたんですけど、獲れるようになっていく過程で、獲れるようになっていったんで、これが食料になるって気がついてしまった。めんどくさいぞ! と思ったんですけど(笑)。やってみると、やっぱりひとりでやると効率があんまりよくない。鉄砲は重いし、シカを獲ると荷物が一気に増えるし、そういう意味ではひとりでは効率がよくないですね」
●仕留めた獲物はその場で解体するんですか?
「そうですね。それしかないんで・・・」
●そうですよね〜。
「その場で解体して持ち運ぶとか、できるだけその場で食うわけです。でも20〜30キロの肉が手に入るわけで、それを全部食うことなんてできないですし、運ぶこともできないんで、悪いけど森に返す、みんなで食べてください。実際みんなで食べてくださいっていう状態になるんですけど、あっという間に鳥とか獣とかに食べられちゃう・・・」
●狩猟を始めて、山の見方は変わりましたか?
「変わりますね。狩猟もサバイバル登山もそうですけど、やっぱり普通の登山って結局、道を歩く。岩登りとかでも、ある程度ルートが決まっていて、そのラインをたどるみたいなところがあるんですけど、食料とか燃料とかを現地で、山の中で調達しようと思ったら、もちろん山をよく見なきゃいけないですね。
登山道を歩いて線上で山と接していたのが、獲物を探すとか獲るとかっていうことで、それが広がっていく。面とまではいかないんですけど、かなり幅を持って広がっていく。実際にそこに生えていたり、そこに棲んでいたりするものを見つけて獲らなきゃいけないんで、よく見るようになりますよね。幅広くよく見るようになる」
(編集部注:服部さんは大学時代の縦走に始まり、エベレストよりも難しい山と言われるK2の登頂のほか、岩登り、沢登り、山スキーなど、いろんなことに挑戦してきました。その理由は、なんでもできたほうがかっこいいし、登山家として、オールラウンダーでありたいという気持ちがあったからだそうです)
自分で考えて超えていく
※先鋭的な登山家のかたは、人がたどったことがないルートを踏破するとか、まだ誰もやってない登り方で頂上に立つとか、「登山史上、初めて」に挑むことがありますよね。なぜ「登山史上、初」にこだわるのでしょうか?
「面白いからですね! っていうのは、やっぱり誰もやってないから、そこは自分で工夫しなきゃいけないわけですよ。何が起こるかわからないですし、どういうふうになっているかも実際に行ってみないとわからないわけなんで・・・。
実際に行って、ぱっと見て、あっここが難しいとか、ここはどうやって登るんだろうみたいな、わかんないところを自分で考えて工夫して、超えていくっていうのは、ものすごくクリエイティヴなことなんですよ。だから未知っていうものはやっぱり、そういうことにチャレンジしたい人にとっては魅力のあることですけどね」
●ワクワクするんですね~。
「でも今はもうそういう未知の部分もなくなってきてしまったんで、そういう志はもう絶滅危惧種というか・・・。さっき言ったフリークライミングはそういう意味では、最初の人と2番目の人も3番目も100番目の人も、最初の人と同じような気持ちを楽しめるようなシステムにはなっているんですけどね。
情報をフリークライマーたちは(自分の中に)入れないんですよ。っていうのは、やっぱり登り方がわかっていたら、あんまり面白くないんで・・・。自分で岩に取りついて、登り方を考えながら登るのが面白いんで、敢えて人が登った登り方を調べたりしないし、登った人たちもそういうことを敢えて言わないんです。
それはその人たちの喜びを奪うことになっちゃうんで、これから登山もそういう方向にいってもいいんじゃないかなと思いますけどね。僕なんかは敢えてもう調べない。今『ヤマレコ』(*)とかでいくらでも調べられるじゃないですか。調べることもあるんですけど、敢えて調べないことによって、すごく面白いっていうか、初めてそこに行った人と同じような気持ちで登ることができる。自分もいろいろ悩んで工夫する余地があるっていう意味で、これから情報を入れないで、敢えて自分も初期衝動を楽しむのは、登山にもあってもいい考えなのかなと思いますけど・・・」 (*山のコミュニティサイト)
●でも登っている最中に怪我しちゃったとかもあると思うんです。山はやっぱり危険と隣り合わせっていう印象もあるんですが、リスク・マネジメントは常に意識されていますか?
「そうですね・・・いや、どうなんですかね? っていうか、マイナスのことを考え始めると、きりがないですよね。それは行かない理由にはならないんで・・・もともと登山者とか我々みたいなタイプの人間はおそらくですけど、僕はそうなんですけど、できないとか、やめる理由を探し出したら、いくらでもあるんで、それはもう考えないですよね。
それよりもどうすれば、自分がやりたいことをできるか、どうすれば、自分の登りたい山に登れるか、どうすれば、自分が憧れているルートを越えられるかっていう方向から、ってわけじゃないですけど、そこで何があるのかっていうことはもちろん予想するわけです。その予想をどうすれば、自分の能力で超えられるかっていう方向でしか考えないんで・・・。
ベクトルが常に上に向いているっていうか、それで突っ込んで怪我とかしたりしたらしょうがないんで、もちろんリスク・マネジメントは考えるんですけどでも、それがやめる理由にはならないっていう意味で、“危ないじゃん”って言われると、“うん、危ないよ”って、危ないから考えて、安全を考えて登ります! っていう感じですかね」
100年前の生活!?
※服部さんは横浜の郊外にあるご自宅のほかに、狩猟でよく行くエリアに古民家を手に入れ、2020年から二拠点生活をされています。横浜のご自宅でも自給自足に近い暮らしをされているとのことなんですが、それでは物足りなくて、古民家暮らしを始めたそうです。そのあたりの思いを語っていただきました。
「サバイバル登山って当たり前だけど、お金を使わないんですよね。食料は現地調達、水は流れているし、空気はもちろんタダだし、寝る場所だって別にキャンプ場じゃないんで勝手に寝るわけです。燃料はもちろんタダで、それをやっていると本来生きるのにお金はかかんないじゃんっていう・・・。で、そっちのほうが面白いし、まっとうというか、もともとはこういうことが生きるってことだよな・・・みたいな感じで思っていたので、それを自分の実生活でもやったら楽しいかなというふうに思って・・・。
横浜の家でもストーブは薪ストーブだけ、ニワトリを飼ってっていうことをやってみたんですけど、実際面白い面もある、っていうか面白いので、のちのち狩猟の基地が別に欲しいなと思っていて・・・。

それまでは電車とバスで猟場に行って、獲ったら電車とバスで帰ってきていたんですよ。荷物がすごく重くて、猟場に解体場みたいな拠点があったら、いろいろ楽だなと思っていたところ、山の廃村の中に古民家みたいなというか、完全な廃屋ですけど、まだギリギリ住めるだろうなって家がふたつ残っていて、たまたま知り合いができて、そのうちのひとつを譲ってもらえることになったんですね」
●ずっと誰も住んでなかった家を住めるような状態にするのは、なかなか大変だったんじゃないですか?
「まあ、掃除だけですね。あと水を引くこと。もともと田舎暮らしにちょっと憧れがあって、登山なんてやっているから、そういうのはあったんですけども、実際に廃屋みたいのを手に入れて、現場に寝泊まりしながら掃除をしていて、単なる田舎暮らしを求めていたんではないってことに気がついて・・・まさにその古民家を100年前のまんま使う生活が、自分の力で生きることに近いってことに古民家を見て気がつかされたっていう、こっちを求めていたんだ! って。
だから土間は土間として使う。囲炉裏は囲炉裏として使う。まあ竈(かまど)ですけど、竈は竈として使う。水は水船(*)から引いてくる。これは塩ビパイプ使ってやっているんで現代的なんですけども、あとは本当に昔のまんまにするほうが・・・。 (*飲み水をためておく大きな桶というか箱のようなもの)
100年前に建った家なんで、100年前の生活に適したようにできているんですよね。それが僕の求める自分の力の割合が多い生活なんで・・・。だから古民家と言っても現代風の別荘みたいな感じにするんではなくて、単に掃除して昔の状況、状態を再生すればいいので、掃除は大変でしたけど、特にリフォームとかそういうのはほとんどしてないんで、そんなに大変ではないと・・・」
●古民家暮らしもサバイバル登山の一環っていう感じですね?
「そうですね。登山の一環というか、僕のあり方というか、世界の向き合い方の延長線上に生まれてきたっていう感じですかね」
(編集部注:1年の半分くらいを古民家で過ごしている服部さん、年に数回、ご家族が泊まりに来るとのことですが、普段、生活に必要なこと、例えば薪割りや火を起こしての食事作りなどは全部ひとりでやるので、清々しいけれど、面倒臭いとおっしゃっていましたよ。畑もやっていて、それは面白いとのことでした)
サバイバル登山家の25年後!?
●サバイバル登山を始めて、今年で25年ぐらいになりますかね?
「そうですね。29歳の時に始めたんで、25年ぐらいですね」
●どうですか、サバイバル登山というスタイルの山登りは円熟してきましたか?
「う~ん、サバイバル登山って言っても、やっぱり行ったことないところに行きたいんですよ。もちろん何度も何度も同じところに行っているんですけど、行ったことないエリアがなくなっちゃったのが寂しいっていうのかな・・・」
●ここ数年は愛犬との山旅もあったりしましたが・・・?
「そうです! 犬は面白いっすね」
●山登りのやり方もちょっと変化してきているんですね。
「うん、変化しています。やっぱり、自分の肉体が歳をとってきて、動かなくはなってないですけど、若い時みたいにできることが増えていかないですよね。できることが増えていかないとリスクをかけられないっていうか、できることが増えていかないから新しいことができないんで、その新鮮さみたいなものはないんですよね。
だから自分の肉体にはもう新鮮さがない。そうなると、あんまりいいことかどうかわかんないですけど、獲物とかその世界に新鮮さを求めてしまって・・・獲物は同じことはほとんどないんで、すごくいつでも新鮮です。犬もやっぱり、ちょっと想像つかないんで面白い、いろんなことを教えてもらいました。新鮮なものを見せてもらいましたね」
●誰でも1年にひとつ歳を重ねますけれども、サバイバル登山家 「服部文祥」の、例えば25年後、80歳の時にはこうなっていたいとかありますか?
「いやぁ~死んでいるかもしれないけど、自然環境の近くで活動したり、特に獲物の相手をしていると遠い未来、遠い未来って言っても、2ヶ月ぐらい、まあ1週間でもそうですね。あんまり考えても意味ないから・・・。
徒歩旅行でもそうですね。20キロ以上先のことを考えても、あんまり意味がないんですよね。雨が降るかもしれないじゃないですか。何か別のことが起こるかもしれないんで、だからその場その場で生きていく。いわゆる、狩猟採集民族みたいに半径10キロとか、時間的には1日2日ぐらいのことしか考えなくなるっていうか、考えてもしょうがない、何が起こるかわからないんで・・・。
遠い未来のことを考えると怖くなるっていうか、気分が悪くなるっていうか・・・それまでに超えなきゃいけないものをイメージしちゃうっていうか・・・でも、元気な爺さんで、畑とか狩猟はもう続けてないかもしれないですけど、自分の力でできるだけ、自分の力で生きていたらいいなとは思いますけどね」
☆この他の服部文祥さんのトークもご覧ください。
INFORMATION
山岳雑誌『岳人』に連載していた人気コラムを中心にまとめた本。第一章の「ケモノを狩る」から第二章の「山に登る」、そして第五章の「現代に生きる」まで5つの章に選りすぐりのエッセイが載っています。導入部の「ちょっと長いはじめに」には、服部さんの生い立ちや登山の半生が綴られていて、これも興味深いですよ。物事の本質や生き方、社会のあり方などを問いかけるようなエッセイ集をぜひ読んでください。
モンベル・ブックスから絶賛発売中。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎モンベル・ブックス:https://webshop.montbell.jp/goods/disp.php?product_id=1991015