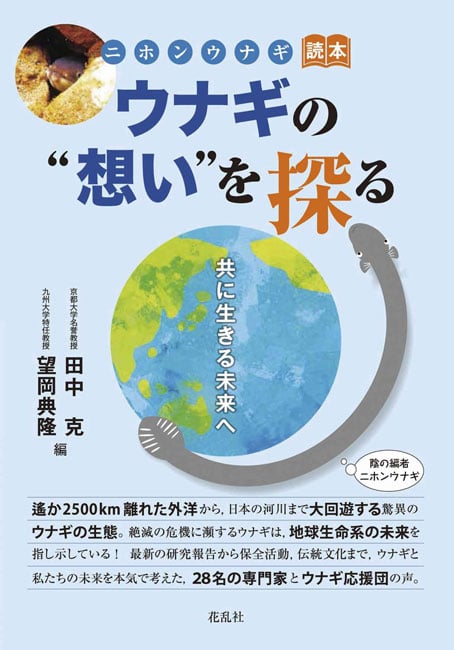2025/1/26 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、認定NPO法人「JUON NETWORK(樹恩ネットワーク)」の事務局長「鹿住貴之(かすみ・たかゆき)」さんです。
JUON NETWORKは都市と農山村をつなぎ、地域と自然を元気にする活動を行なっています。大学生協を母体に設立されたJUON NETWORKがなぜ、都市と農山村をつなぐ活動を始めるに至ったのか、その背景には、大学生協が過疎化の進む地域の廃校、小学校をセミナーハウスとして再生したこと。
そしてもうひとつの大きなきっかけが、1995年1月に発災した阪神・淡路大震災。
被災した大学生たちのために、仮設学生寮を作ることになり、その際、徳島の林業関係者から間伐材で作った組み立て式のミニハウスを提供してもらったこと。ここで農山村とのつながりが生まれます。
1995年の阪神・淡路大震災はボランティア元年とも呼ばれ、多くの大学生も支援に駆けつけましたが、その際、学生の間から、普段からボランティア活動をしたくても「場」や「きっかけ」がない。活動するためのネットワークがあれば、という声があがったそうです。
そこで学生たちの活動の場づくり、そして都市と過疎化が進む農山村をつなぐ活動をしたい、そんな思いから、大学生協の呼びかけで、1998年にJUON NETWORKが設立されたそうです。
設立当初からのメンバーである鹿住さんは、大学生のときに知的障害者の子供たちと遊ぶボランティア・サークルに所属。また、東京で学生ボランティアのネットワーク作りにも参加していたこともあって、JUON NETWORKのスタッフになったそうです。
きょうは、以前にもこの番組にご出演いただいた鹿住さんに、いろいろな活動の中から、おもに間伐材を有効活用する「樹恩割り箸」のほか、「森林(もり)の楽校」や「田畑(はたけ)の楽校」のお話などうかがいます。
☆写真協力:JUON NETWORK

樹恩割り箸〜森作りと仕事作り
※オフィシャルサイトを拝見して活動のひとつとして「樹恩割り箸」というのがありました。これはどんな活動なんですか?
「日本の森林を守るためには、ただ放っておけば守れるっていうことではなくて、手入れが必要だと。その手入れのひとつが間伐、“間(あいだ)を伐採する”で、間伐ですね。その “間伐材”とか、あるいは“国産材”が使われることで山側にお金が入るので、森の手入れが進むっていうことになる。日本で森林を守るっていうことは放っておくことじゃなくて、国産材とか間伐材を使うということが、すごく大切なんですね。
日本の森林を守るために、間伐材や国産材を原材料として使うっていうことと、もうひとつ大きな特徴としては、障害者の仕事作り。いま全国4つの障害者施設、障害者と言っても知的障害の人たちが多い施設なんですけれども、その障害者施設で割り箸を作って、大学の食堂で中心的に使ってもらっています。ほかにも一般のスーパーだったり飲食店でも使っていただいたりしています。
なぜ私たちが割り箸作りに取り組んでいるかというと、日本の森林を守るために国産材・間伐材を使うことの中で、JUON NETWORKがもともと大学生協とつながりがあったということ。学生に間伐材とか国産材を使ってもらうには、大学生協が経営している大学の食堂で割り箸として使ってもらえばいいということから、1998年の設立の時にスタートして、26年ぐらいやっています。そういった取り組みですね」

●大学の食堂などで使われているということでしたけれども、一般のかたでも購入はできるんですか?
「はい、そうですね。私どものウエブサイトから購入していただくことができます」
●樹恩割り箸は、年間ではどれぐらい売れていますか?
「大体1000万膳っていう(笑)ちょっとあまりピンとこないと思うんですけれども、1000万膳という量を製造しています。日本で割り箸が1年間にどれぐらい使われているかってわかりますか?」
●え~〜!? どれくらいだろう・・・(笑)
「考えたこともないと思いますけど・・・(笑)」
●でもかなりの量ですよね?
「はい、190億膳と言われています」
●うわっ!
「これでもあまりピンと来ないと思うんですけれども、日本の人口がたとえば1億2000万とか3000万人ですけど、1億人って考えると、ひとり(年間)190膳ぐらい使っているということなんですね。
木材の自給率はずっと20パーセントぐらいだったけれども、最近ちょっと上がってきていて、40パーセントを超えたんですね。それでも木材の自給率は少ないですけどね。こんなに森があるにも関わらず、外国の木を6割使っているっていうことですから。で、割り箸の自給率は、実は2パーセントしかないんですね。
ですから、ほとんど海外から入ってきているんです。その国産の割り箸のうちの大体2パーセントぐらいが、JUON NETWORKの割り箸っていう感じです」

(編集部注:樹恩割り箸は現在、福島の南会津、埼玉の熊谷、東京の日の出町、そして徳島の4つの知的障害者の施設で製造。材料はもちろんその地域から出た間伐材です。こうすることで、障害者のかたの仕事作りのほかに、森作りにも役立っているということなんですね)
森林の楽校〜森の手入れ
※ほかにも「森林(もり)の楽校」そして「田畑(はたけ)の楽校」という活動があります。まずは「森林の楽校」、これはどんな活動になりますか?
「森というのは手入れが必要です。森林ボランティア活動っていうと、木を植えることを多くの人がイメージすると思うんですね。木を植えることも大切なんですけども、むしろその後の手入れのほうが大切なんです。
例えば、木を植えます。日本では春に植えることが多いんですけれども、春に植えると、夏になると周りの雑草がたくさん生えてきます。木は大きくなるけど、成長はゆっくり、草は大きくならないですけれども、成長が早いということで、植樹した木を、夏になると周りの雑草が覆い隠しちゃうので、日の光が当たらなくなってしまい、木の成長が阻害されてしまうわけですね。そこで周りの雑草を刈ってあげる、下草刈りとか下刈り、光が木に当たるようにする作業、これが手入れのひとつですね。

植えてから7年ぐらいは、木が草よりも大きくなるまで下草刈り、下刈りやるんですけども、成長してきて10年ぐらい経ってくると、外から山のほうを見ると緑がたくさんで、日本はいいな~って思うかもしれないんですけども、枝が伸びてきますので森の中が真っ暗、木に光が当たらない状態になってしまうんですね。
そうすると森の役割が発揮できなくなってしまいます。例えば緑のダム機能、水を溜め込んでいつまでも川に水を流してくれるような、そういう機能とか、二酸化炭素を吸収する機能が発揮しにくくなるので、間伐して木を間引く、森の下まで光を当ててあげる作業ですね。そういう手入れをボランティア活動として取り組んでもらうのが“森林の楽校”です。
こういう活動に、JUON NETWORKの特徴でもあるんですけども、単発でもいいから参加してくださいっていう、イベント的なボランティア体験、森林ボランティア活動の入門的な活動が“森林の学校”になります」
●日本全国で開催されているんですか?
「そうですね。北は秋田の白神山地から、南は九州の長崎とか佐賀、全国18か所で開催しています」
田畑の楽校〜援農ボランティア
※続いて「田畑(はたけ)の楽校」について。これはどんな活動ですか?
「これは過疎高齢化で大変な農家さんをお手伝いしようということで行なっている活動、農家を応援する支援する援農ボランティア活動です。この援農ボランティア活動もやはり入門的な活動になります」

●現在、何か所の農家さんを支援されているんですか?
「いま全国4か所でやっています。いちばん古くからやっているのが山梨のブドウ農家のお手伝い、次に始まったのが和歌山県の那智勝浦の棚田、お米棚田のお手伝いで、次に三重県のミカン農家のお手伝い、それと長野県のリンゴ農家のお手伝いという、その4か所で開催しています」
●ブドウ作りのお手伝いとかって、普段できないですよね? 参加者の中から農家さんに転身されたみたいなかたもいらっしゃるんじゃないですか?
「そうなんですよね。農山村地域と都市を結ぶ活動は、私たちは交流人口って言って、 農山村地域に行く人を増やすような活動が基本です。その体験的な入り口を作っているのがJUON NETWORKの特徴なんですね。
山梨のブドウ農家のお手伝いで、交流人口から農山村地域に移り住む定住人口、実際にブドウ農家になったかたが4家族いるっていうことで、JUON NETWORKの活動の中では、いちばん移住した人が多い活動ですね」

●この「森林の楽校」や「田畑の楽校」に参加したいと思ったら、どのようにしたらいいんでしょうか?
「JUON NETWORKのウエブサイトを検索していただいて、そこから申し込みができます。もちろん電話でも申し込めます」
●会員じゃなくても体験だけの参加もできますよね?
「そうですね。基本、私たちは会員ではない人にも参加していただきたいということで、会員にならなくても参加できますし、むしろ会員でないかたの参加のほうが多いです。ただその中から会員になると、会員割引っていうのもあるので、会員になっていただくっていうことも多いですね」
環境教育のリーダーを育てる
※オフィシャルサイトに「森林ボランティア講座」の情報が載っていました。これは具体的にはどんな講座なんですか?
「ちょっと前までは“森林ボランティア青年リーダー養成講座”っていう名前だったんですけども、“里山・森林ボランティア入門講座”っていう名前に変えたんですね。
これは、大学生協が呼び掛けた組織っていうこともありますので、若い森林ボランティアのリーダーを育てようっていうことでスタートしています。大学生や高校生が参加する場合もあるんですけども、基本は大学生から40歳代、50歳未満のかたを対象としています。森林ボランティア活動の技術を身につけていただいて、将来的には活動のリーダーになっていただくことを期待しているっていう、そういう5回連続講座ですね。日にちは離れていますけれども、5回の講座がひとつになっています」
●JUON NETWORKでは「エコサーバー検定」という資格制度も実施されています。これはどんな資格なんですか?
「環境教育のリーダーを育てようということで、森林ボランティア活動も最近は取り入れているんですけども、小学生とか中学生とか、そういう子どもたちに向けたような環境教育を学んでもらう資格制度です。
アメリカに“プロジェクト・ラーニング・ツリー”、木に学べっていう、木から世界を学ぶっていうような感じで、ほかにも環境教育のプログラムがあるんですね。そういうものを(リーダーとして)実施できるように学ぶっていうことと、あと野外での作業の技術を学ぶという、リーダーの養成を目指して実施しているものです。今年度は2月からスタートし、2月に1回3日間の講座やるんですけども、(今回で)20回目ということになります。
JUON NETWORKのエコサーバーっていう資格が取れるだけではなくて、それが取れると、日本共通の指導者資格、『自然体験活動推進協議会CONE(コーン)』が進めている、『ネイチャー・エクスペリメンス・アクティビティ・リーダー NEAL(ニール))』っていう自然体験活動リーダーっていう資格があって、そういうものも取ることができます
(編集部注:鹿住さんいわく、日本ではボーイスカウトやカブスカウト、YMCAやキャンプの協会、ネイチャーゲームの協会など、それぞれの団体が自然体験の指導者を養成する活動を行なっていますが、その共通の資格になるのがNEALだそうです。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください)
◎自然体験活動推進協議会:
https://cone.jp
◎NEAL:
https://neal.gr.jp
ボランティア活動、意識の変化
※いまやSDGsという言葉がメディアで盛んに取り上げられて、その意味や目的などが一般的になってきたと思います。鹿住さんはJUON NETWORKで26〜7年、活動されてきて、いまどんな思いがありますか?
「(設立された1998年)当時は本当に間伐っていう言葉も一般的じゃなくて・・・実は日本でも木を植えてからやっぱり30年、40年、50年ぐらいは間伐が必要な時期なので・・・その頃に比べたら間伐を知っている人も非常に多くなったと思います。
私たちの“樹恩割り箸”が、間伐を知っていただくために果たした役割もあったかなと思うんですけれども、そういうことがあまり知られてないようなところからやってきていると、だいぶ社会的な理解も進んできたなぁというような思いを強く持っていますね」
●20年くらい前と比べて、「森林の楽校」などに参加されるかたの、意識の変化みたいなものって感じますか?
「そうですね。 特に東日本大震災前後で、参加する人の動機って言うんですか、ちょっと変わってきたような感じも受けているんです。昔から自然に触れたいみたいなことだったり、森のためになんかしたいとか、ボランティアしたいっていうのはあったと思うんですね。東日本大震災以降、能登半島地震もありましたけれども・・・。
やっぱり自然を生活の中に取り入れ入れたいって言うんですかね、自然とのつながりを持つ必要性みたいなものをお感じになって参加するっていうような・・・だから暮らしの中で森を切り離して守るっていうよりは、暮らしの中に森とどうつながるかみたいなことを意識しているかたが多くなっているような印象があります。

で、ボランティア活動を災害のボランティアってことで、自分は子供の時、小さかったからボランティアとして被災地に行けなかったけれども、大人になってボランティア活動をしたいと。で、調べていたら自然に対するボランティアもあるんだってことで参加しましたみたいな・・・ボランティアについても、社会的にも関心が広がってきているかなという気もします」
●鹿住さんご自身はいろんなNPO法人の理事などを兼任されています。その辺りはどんな思いがあるんでしょうか?
「私たちもそうですけれども・・・実はJUON NETWORKの設立と同じ1998年にNPO法っていう法律が施行されたんですね。日本はやっぱり基本的に行政が公共のことをやるっていうような意識がとても強いと思うんですけれども、阪神淡路大震災の時に行政だけではとてもその対応ができなかった。で、市民活動とかボランティア活動が被災地で活躍して、大切だっていうことを認識して、そのきっかけでNPO法っていう法律もできたんですね。
そういう意味では、私たちひとりひとりの市民が社会作りっていうんですかね・・・社会を作っていくことに参加していくことがとても大切だと思っているんですね。行政、企業、市民の(それぞれの)立場で、非営利の市民セクターの、この3つのセクターが協力して社会を作っていくことが大切だと思っていますので、その市民の立場で活動を広げたり、みなさんに社会の活動に参加してもらうことを広く呼び掛けて(ひとりでも多くのかたに)参加してもらいたいなと思って活動をしています」
INFORMATION
「樹恩割り箸」はJUON NETWORKのオフィシャルサイトから購入できますよ。価格は紙袋に封入したもので、100膳550円となっています。
「森林(もり)の楽校」や「田畑(はたけ)の楽校」には会員ではなくても体験として一般のかたも参加できるとのことですから、興味のあるかたは、ぜひサイトをチェックしていただければと思います。
JUON NETWORKでは随時会員を募集中。学生会員で年間2000円、個人会員で4000円。また、寄付も受け付けています。ぜひご支援いただければと思います。いずれも詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
◎JUON NETWORK:https://juon.or.jp/