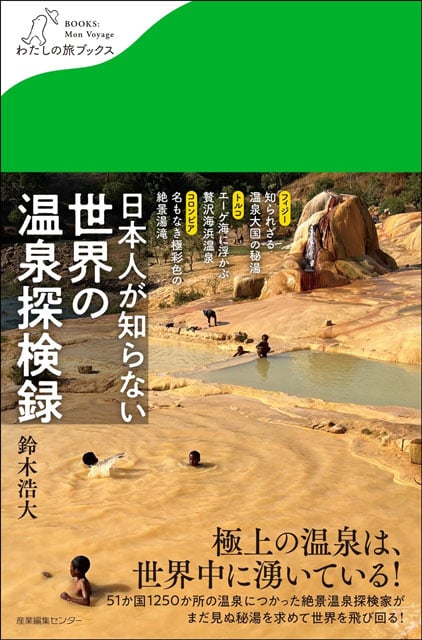2025/3/16 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、一般財団法人セブン-イレブン記念財団「高尾の森自然学校」の代表「後藤 章(ごとう・あきら)」さんです。
2015年4月に設立され、今年開校10周年を迎える高尾の森自然学校は東京の西、八王子市に広がる里山の森を保全するなど、いろいろな活動に取り組んでいます。
高尾の森自然学校のフィールドは、もともと薪や炭を取る里山の森として使われていましたが、時代の流れで利用されなくなり、暗い森になっていたそうです。
そこで、東京都とセブン-イレブン記念財団の協働事業として、森の手入れを行ない、明るい森に再生。植物や動物の多様性を守りながら、その一方で一般のかたに親しんでもらい、自然について学ぶフィールドにもなっています。

面積は26.5ヘクタール、東京ドームおよそ6個分! 四季折々、いろんな表情を見せてくれる森には散策路があって、子供たちが遊べる遊具やベンチも設置。土日と祝日には原っぱが解放され、昆虫観察などもできるそうです。
森には、管理棟で受付さえすれば、どなたでも自由に入れます。また、事前に予約すれば、スタッフが森の中を案内してくれるそうですよ。
きょうは高尾の森の、動植物の特徴のほか、森と人々をつなぐ体験型のプログラムやボランティア活動のお話などうかがいます。
☆写真協力:高尾の森自然学校


植物300種、野鳥50種
※高尾の森自然学校のフィールドには、どんな樹木が多いんですか?
「里山の森ですので、そこで使っていたコナラやクヌギなどのどんぐりがなるような、そういった木がいちばん多くて、それ以外にもヤマザクラだったりツツジ、そういった樹木たちが多いと思います」

●種類としては何種類くらいあるんですか?
「樹木だけ、というのは数えてはいないんですね。植物全体ですと、毎月調査をしているんですけども、300種類を超える植物が見られます」
●野鳥などの生き物も多いんじゃないですか?
「そうですね。野鳥は冬、樹木が葉っぱを落としている時期がいちばん見ごろなんです。コゲラだったりアオゲラといったキツツキの仲間だったり、メジロやエナガなどの小さな野鳥たち、そういったものがたくさん見られます。確認できているのは約50種類くらいですかね」

●へ〜! 貴重な動植物に出会うこともありますか?
「今お話した鳥の中だと、例えばオオタカだったり、ノスリといったタカの仲間だったり、フクロウは夜だけここにいたり・・・。希少なものでしたら、沢が流れているので、そこでホタルが見られたり・・・あと一昨年、ここでキツネが繁殖して、キツネの親子が見られたり、そういったこともありました」
●自然学校のスタッフとして森の手入れもされるんですか?
「ここはボランティアのかたと一緒に整備をすることが多いんですね。暗い森になった原因の笹を刈ったりとか、増え過ぎてしまった木の一部を間伐したりして、森を明るくするような手入れを基本的にしています」
●木を植えたりとか、そういうことはされるんですか?
「木は基本的には植えていなくて、森を明るくすることによって、ここにもともといる植物、動物たちが増えるように、そしてまた周りから入ってくるようにということを目指しております。
森の手入れをすると本当に見違えるほど明るくなるんですね。1〜2時間くらいのボランティア・サークルの活動だけでも、真っ暗だった森に太陽の光が入ってきたっていうことを感じることができます。
そうすると例えば、明るくなったところに、春になるといろんな草花が花を咲かせたり、明るくなったことを生き物たちが感じて、また戻ってきてくれたということを感じることがよくありますね」

(編集部注:先ほど、高尾の森自然学校のフィールドには、基本的に木は植えないというお話がありましたが、後藤さんによると、全国で「ナラ枯れ」という木の病気が流行っていて、高尾の森も例外ではなく、コナラなどが枯れているそうです。そこで今後、枯れた木は伐採し、森の中にある苗の移植を検討しているとのことでした)
自然を体感! 大人の植物観察会
※高尾の森自然学校では、体験学習ということで、いろんなプログラムを実施されています。具体的にはどんなプログラムがあるのか、教えてください。

「ここではこの森を再生しながら、帰ってくる生き物を観察したりとか、手入れの時に発生した間伐材を利用したクラフト、そういったものを中心としながら地域の自然と、そして地域の文化を学ぶようなプログラムをやっています。
ここでやっているものとしては、例えば昆虫観察会、連続プログラムとしてやっているんですね。春はチョウ、夏はホタルやカブトムシ、秋はバッタ、冬は冬越しする昆虫といった、1年を通じてここにいる昆虫たちを観察して学んでいくプログラムだったり・・・。
野鳥観察のプログラムとしては、夏鳥と冬鳥というのがすごく特徴なんですけれども、その観察にプラスして、野鳥の巣箱を設置して、1年間子育てに使った巣箱と新しい巣箱を取り替えて、使った巣箱の材料を観察しながら、どんな材料を使っているんだろうか・・・。
例えば街に近いところだったら人工物を多く使っていたり、森の奥のほうだったら自然素材を多く使っていたり、そういった違いだったりを鳥の目になって環境を見るようなことを行なっていたり・・・。

また少し変わったものとして、お子さんが学ぶプログラムが多いんですけれども、やはり大人のかたにもたくさん来ていただきたいと思っておりまして、『大人の植物観察会』といった名前で、森を歩きながら季節の植物を観察します。
で、大人のプログラムですので、その植物だけじゃなくて環境、森自体の自然を感じるような、木を触って感じたりとか、流れる沢の水を感じたりとか、森の中に寝っ転がって、森の木々の音、鳥の鳴き声を静かに感じるような、そういった自然を感じながら行なうのが自然観察会、そういったこともやっています。
また、自然が好きな人はたくさんいるんですけども、そうじゃなくて、小さなお子さんだったりとか普段、森に入らないような人たちにも森を、自然を学んでもらったり感じてほしいということで、『森の音楽祭』というプログラムをやっています。これは、例えば中学校さんの吹奏楽部だったり太鼓部だったり、そういった子供たちが森の中で音楽を演奏する、それをみんなで楽しみながら、自然の入口になるような、そういったプログラムもやっています」
森と畑のボランティア活動

※先ほどもお話に出てきましたが、ボランティアを募集されているんですよね?
「ボランティアとして、『森のお手入れボランティア』っていう森の手入れをするようなボランティアさん、そして『畑クラブ』という、ここにある畑の一部を手入れするボランティアさん、あと子供たちの活動で『森のジュニアボランティア』、この3つのボランティア活動をやっているんですね。いずれも一般のかたをホームページ等で募集して行なっています」
●随時募集されているんですか?
「『森のお手入れボランティア』と『畑クラブ』は随時募集です。『森のお手入れボランティア』は月に3回、『畑クラブ』は月に1回(の活動)なんですけど、これは随時募集しておりますので、ホームページからいつでも応募することができます。『森のジュニアボランティア』だけは、1年間通じて学んでもらいたいと思っていますので、3月から4月ぐらいに1年間の募集をして、年間そのメンバーで活動するという形でやっております」
小笠原諸島と高尾の森
※後藤さんが高尾の森自然学校のスタッフとして活動するようになったのは、なにかきっかけのようなものがあったんですか?
「私は大学にいた時に、生き物を守るための研究、『保全生態学』というんですけれども、生き物の生き様、生態を研究しながら、自然を守っていくにはどうしたらいいかということを研究する学問なんですね。
大学で研究しながら、それをたくさんのかたに伝えていかないと守っていけないというふうに感じまして、大学を卒業して大学院を出た後に、高校の教員だったりとか、NPOの職員として仕事したりとかいろいろやっていたんです。そんな時にこの高尾の森自然学校の募集にすごく運命的なものを感じて応募して、それからこちらで活動するようになりました」
●「保全生態学」は、具体的にどんな研究をされていたんですか?
「保全生態学は生き物の生態を研究しながら、絶滅が心配される生き物だったりとか、失われている自然をどう守っていけばいいのかっていうことを研究する学問なんですね。私はその中で、大学の頃は小笠原諸島、そこに生息する絶滅危惧の植物の生態を調べて、その減っている原因を解明しようということを大学院の最初の頃にやっていました。
そこから今度は関東の東京の近辺で、小学校に小さな池『ビオトープ』を造って、そこに来る生き物たちや、周りの環境を知ることができるんじゃないかということで研究しながら、子供たちに周りの環境を伝えていく、そういったことを研究の生業にしておりました」
●高尾の森もやっぱり魅力的なフィールドですよね?
「そうですね。小笠原諸島はすごく固有種が多くて、あそこにしかいない生き物がいるんですけども、高尾の森のような里山も、日本にしかないすごく貴重な環境で、そして人が(森を)使われなくなることによって、失われつつあるというところで共通点があります。そういった意味では高尾の森もすごく魅力的な場所だと思っています」
地域で活かす里山の森

※これからの時期、高尾の森自然学校のフィールドは、いい季節を迎えるんじゃないですか?
「そうですね~。落葉広葉樹は冬は葉っぱを落とすので、春はいちばん明るくて見通しもいい時期なんですね。そうすると太陽の光を浴びて林床(りんしょう)の植物たち、スミレだったり、イチリンソウ、ギンラン、色とりどりの花々が林床を彩っていきます。そして上のほうには、桜だったりとか山桜がすごく多いんですけれども、そういったものが咲いてすごくいい季節になりますね」
●後藤さんが個人的に好きな季節とか時間帯はありますか?
「季節はやっぱり春の時期がいちばん綺麗かなぁと思いますね。で、時間・・・やっぱり朝早い時間だと、本当に鳥たちがすごく喜んで鳴いていますよね。そういったものを聴きながら散策するのがいちばん気持ちいい時間かな~と思います」

●今後、自然学校のスタッフとして、どんなことを伝えていきたいですか?
「里山の森、自然学校は里山の森なんですけれども、ここは地域の人が使うことによって維持されてきた森ですので、やはり今後もこの地域で活かされていく、地域のかたのボランティア活動だったり、地域のかたが学ぶ場として、この自然学校のフィールドを使ってほしいと思います。そういったことをたくさんのかたに伝えていきながら一緒に(高尾の森を)守っていけたらと考えています」けて、備えていくきっかけにしていただけたら嬉しいなと思っています」
INFORMATION

今年10周年を迎える高尾の森自然学校にぜひご注目ください。お話にもあった「大人の植物観察会」や「野鳥観察」「昆虫観察」などなどいろいろな体験型のプログラムを行なっています。また「森のお手入れボランティア」や「畑クラブボランティア」などもありますので、ぜひご参加ください。まずは、これからとてもいい季節を迎える「高尾の森自然学校」のフィールドに遊びに行ってみていかがでしょうか。
開館時間は午前9時30分から午後5時まで。定休日は毎週火曜日です。アクセス方法など、詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
◎高尾の森自然学校:https://www.7midori.org/takao/