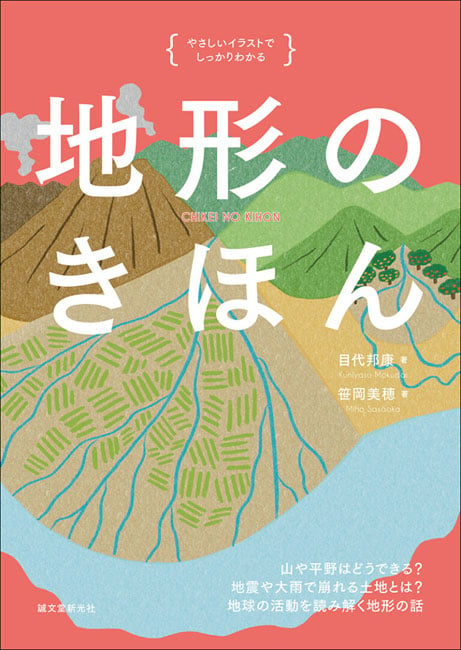2025/5/4 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、東北学院大学の准教授「目代邦康(もくだい・くにやす)」さんです。
目代さんは1971年、神奈川県生まれ。東京学芸大学・教育学部・在学中に、中学や高校の社会科の先生になろうと、科目として「自然地理」を選んだところ、その先生がとても面白い方だったということで、自然地理や地形学の道に進むことになったそうです。
そして、京都大学大学院・理学研究科の博士課程修了後、筑波大学の研究センターなどを経て、現職の東北学院大学・地域総合学部の准教授としてご活躍されています。ご専門は「地形学」や「自然地理学」で、その学問を一般の方向けにわかりやすく解説した本『地形のきほん』を先頃出されています。
きょうは目代さんに、地形が私たち人間や生き物に与える影響のほか、九十九里浜が出現した地形的な要因、そして、住んでいる地域の地形を知る必要性などうかがいます。
☆写真協力: 目代邦康

液状化は「砂粒」の性質が原因!?
※目代さんのご専門は、地形学や自然地理学ということですが、どんな学問なのか教えていただけますか?
「地理は小学校とか中学校で習うかと思いますけれども、その中で特に自然、地球の表面で起こっている、いろいろな自然現象について調べるというのが自然地理学です。
特にその中でも私、地形についていろいろ調べております。地球の表面がデコボコしていますけれども、そういった山とか海岸とか、そういう場所がどうやってできたのか、どういうような地層からできているのかとか、今後どうなるかとか、そういうようなことを考える研究分野です」
●研究のためには、実際にフィールドに行って調査するんですよね?
「実際に現場に行って、土地がどんな形をしているのかを計ったり、穴を掘って、そこにある土とかを持って帰ってきたり、あと石を叩いて、どんな地層があるか調べたりですね。それだけで終わらなくて、持って帰ってきたら、今度はそれを分析したりします。
最近は飛行機から撮った写真とか衛星から撮った写真とか、あるいは自分でドローンを飛ばして撮るとか、そういうのも含めて、分析するというようなことをやっています」
●いろんな方法があるんですね。メインのフィールドはどこになるんですか?
「いろいろなところをやっています。ここ1年間は、能登半島地震がありまして、そのあと被害を受けた場所の地形を調べているので、ここ1年間は金沢のほうに何回か行っていました」

●具体的には、どういった方法で何を調べるんでしょうか?
「今調べている、能登半島地震のあとの現象ですと、”液状化”です。地震の揺れで(地面が)液体のように変わってしまう、それで建物が曲がってしまうとか、そういう現象なんですね。
そこの形を調べていくのと同時に、何でそういった変化が起こるのかを、地層を掘って、砂からできているんですけども、砂粒の大きさとかを測るんですね。で、どういうような砂の性質なのかが、地面の形が変わってしまう原因になったりしますので、そういうのを分析したりしていますね」
日本列島の地形が多様な理由とは?
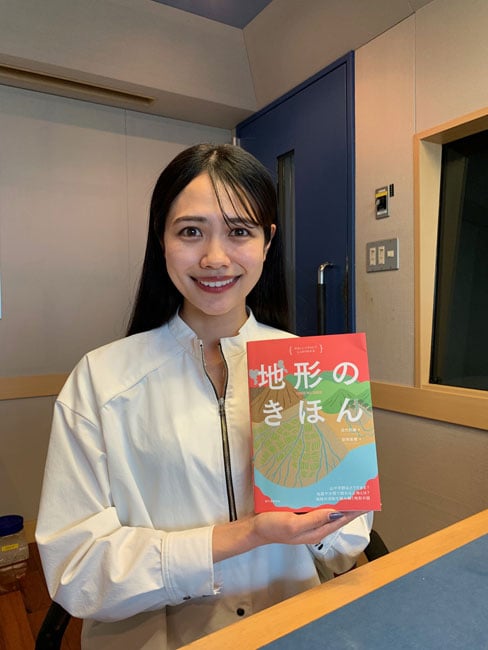
※ここからは目代さんが先頃出された本『地形のきほん』をもとにお話をうかがっていきます。本を読んでいて、改めて、地形は私たち人間の暮らしにいろんな影響を与えているんだな〜と思いました。地形の多様性が、自然や生き物の多様性を生み出していたんですね。
「いろいろな場所に地面があって、生き物は、鳥はちょっと飛んでいますけど・・・とはいえ、地面の上で生活するので、生き物の生活は切っても切り離せないですね。
切っても切り離せないんですけれども、いろいろな生き物がいる今の状況を考えると、場所がそれぞれ違うので、そこに合わせて生き物がそれぞれ進化してきています。やはり、地球の環境の基盤というか、ベースになるのが地形の違いというところになるんだと思います」
●日本列島の地図を思い浮かべると、山脈が連なっていて、川もたくさんあって、海岸線もすごく複雑で、ところどころに平野があってっていう感じで、地形的にかなり多様で複雑なイメージがあるんですけれども、その多様さを生んだ要因は何なんですか?
「いちばん大きいのは、地球の表面に10数枚のプレートというものが覆っているんですけども、それがお互いに動いておりまして、(日本列島があるのは)あまり動かないプレートと、よく動くプレートのちょうどそのぶつかり合うところなんですね。
あまり動かない大陸のプレートと、よく動く海のプレートがぶつかり合うことで、ギュッと押されて山はできますし、海のプレートが日本列島の下に沈み込むことで火山ができます。
で、さらに気候の条件として雨がよく降るので、削られた土砂が運ばれて、平らな土地が作られてと・・・条件からするとふたつですね。地球の上でよく動いている場所だということと、雨がたくさん降る場所だということかと思います」
●そういった要因があったんですね〜。日本列島の地形を大きく分けると、山と平野になるんですか?
「日本列島に限らず、高くて尖っているところが山で、低くて平らなところが平野で、地球上、分けると基本そのふたつなんですね。で、日本の場合だとその中間もあって、丘陵地って呼ばれる場所がその中間になるんですけども、基本的には高さと、丘か丘でないかというところで分ける、そういった分け方になります」
●この山と平野、だいたいどれくらいの割合になるんですか?
「だいたい日本列島は、ほぼほぼ山でして、7割以上が山地です。で、3分の1から4分の1ぐらいの狭いところが平野です。その平野に多くの人が住んでいるというのが日本の特徴です」
●日本で考えてみると、人口が集中しているのは首都圏だったり、関西圏だと大阪や名古屋あたりですけれども、平野ができるのはやっぱり川が影響しているんでしょうか?
「そうですね。平らな土地は何で平らかっていうと、川が運んできた土砂が、川が氾濫して土砂を溜めて、あるいは海からも土砂が入ってくることがあるんですが、そういう水の働きがあるから平らな土地ができるんですね。そういう意味では川の働きというのは重要です」
(編集部注:ちなみに「山脈」と「山地」の違いなんですが、その定義は、目代さんの本によると、日本列島の場合、規模がより大きなものが「山脈」、山脈より規模が小さいものが「山地」、山地よりもさらに規模が小さいものが「高地」になるとのこと。これはあくまで日本列島の区分だということです)
九十九里浜が長いのは、硬い岩盤があるから!?
※ベイエフエムがある千葉県には、九十九里浜という日本で2番目に長い砂浜があります。その長さはおよそ66キロもありますが、どうしてこんなに長い砂浜ができたのでしょうか?
「なかなか難しい質問ですね(苦笑)。砂浜のいちばん端っこに何があるかなんですね。ずーっと砂浜なんですけれども、いちばん端っこは硬い岩盤が出ているんですね。どこもそうなんですけれども、削られにくい硬い岩盤があるところがふたつあると、その間が砂浜になるんです。
で、九十九里浜ですと、北の銚子のところに少し古い硬い岩盤が出ていますね。一方で南のほう、房総半島の南のほうもちょっと山がちですけども、そこもまた岩盤が出ています。そのふたつの岩盤が離れているので、その間が砂で埋められて、非常に広い砂浜になっているということです」
●そうやってできるんですね〜。今、この日本で砂浜がどんどん減っているっていう話を聞いたことがあるんですけれども、原因は何なんでしょうか。
「根本的には、先ほど平野は川が運んできた土砂でできるということを言いましたけれども、川が土砂を運んでこなくなったんですね。
運んでこなくなった理由は何かというと、ひとつには山から崩れた土砂が川を経由して海まで来るんですけれども、その途中でダムがあったり、いろいろな人工構造物があって、せき止められて流れてこないというのがあります。
もうひとつの理由は、今はあまり掘ってないんですけども、昔はコンクリートに入れる砂を川から取っていたんですね。川底をどんどん掘って・・・。
やがて砂が流れてくるだろうと思っていたんですけど、全然流れてこなくて・・・で、川でたくさん取っちゃったので、最終的に海の近くの平野まで流れていかないので、砂浜の砂が供給されるほうが少なくなってしまったので、波でどんどん侵食されて減っている、そういうことになります」
●観光地としても知られる鳥取砂丘に、植物が生えて草原化しているっていうニュースが以前ありましたけれども、これはどうしてなんでしょうか?
「砂丘に限らずなんですけれども、日本の地形はどこもちょっとずつ動いているんですね。で、砂浜も山のほうから砂が運ばれて、海からちょっと削られて、そのバランスが取れているとあまり形が変わらず、山のほうから(砂が)運ばれてこないと、どんどん削られて減ってしまう・・・。
で、砂丘は砂浜にあるんですけれども、そこの砂丘にやはり同じように山のほうから土砂があまり流れてこなくて、海のほうから削られるのもあり・・・。さらに砂が減ると風が吹いた時に、動く砂の量が減っちゃうんですね。砂がたくさんあると動ける砂がたくさんあるんですけど、あまり動ける砂もなくなって・・・そうすると雨は降りますから、どんどん草が育って雑草が増えてしまうと、そういうような状況です」
地形が地名の由来に!?
※地形はお天気にも影響を与えていますよね。やはりその要因になっているのは山ですか?
「そうですね。冬の間、例えば関東地方ですと、乾燥して乾いた風が吹いてきますけど、同じタイミングで日本海側はたくさん雪が降っています。
大陸のほうから風が吹いて日本海側で湿った空気があって、その湿った空気を含んだ風が日本海側で雪をどんどん降らせちゃうんですけど、風はずっと吹いてくるので、その風が山に雪を降らせたあとに吹き上がって、山を越えてきた時にはもう乾燥しているので、湿った空気が乾いた風に変わるというのは、山を越えるということが大きいですね。冬場の関東地方の乾燥なんかは、基本的には日本列島の大きな山が影響しています」
●そういう関係性なんですね~。あと違った側面だと、地形は観光資源とも言われたりしますよね。景勝地には人が集まってきますが、そんな観光資源を守るための制度と言えば、日本ではどういった制度があげられますか?
「そうですね。観光地ですと美しい景色があるので、多くの人が訪れますけども、人がたくさん来るからいろいろな開発をしてしまおう、お金儲けに使おうっていう人もだんだん出てくるので、そういった利用を制限するような仕組みがいくつかあります。
いちばん大きいのが国立公園と呼ばれるものでして、レクリエーションなどで私たちが自然に親しむということと同時に、そこの場所を保護しましょうというようなことが、国立公園の中で法律として定められていて、適切な管理というのが行なわれています。
あとは、最近ですとジオパークですとか、湖ですとラムサール条約の登録湿地とか、そういう国際的な取り組みなんかも含めて、いろいろな場所で適正な管理、使い過ぎ、“オーバーユース”って言うんですけれども、そういったことはなるべくやめるようにして、そこの場所の自然環境が維持されるような取り組みが各地でされています」
●そうなんですね。話は変わりますが、地形の特徴がその場所の地名になっていたりもするんですか?
「そうですね、非常に多いですね。先ほど(話に)出た九十九里浜も、長いって話になりましたけれども、九十九里もないんですけれども、長いのが象徴で九十九里ですし、いろいろな場所の形の特徴で(地名を)付けていたりします。
ちょっと変わったものですと、岩場は山ですと“ゴーロ地形”、岩がゴロゴロしているから、“ゴーロ地形”と言うんですけれども、その“ゴーロ地形”がなまって、“ゴロウ”になりまして、北アルプスにある“野口五郎岳”や“黒部五郎岳”なんかは、その“ゴロウ”から来ています。岩がゴロゴロしているという地名です」
地形を知ると防災につながる!?
※改めてなんですが、地形を理解すると、どんなことが分かってきますか?
「自然の中で生きているということを、私たちはなかなか普段は、便利な生活、都会で暮らしていますので、認識することがないんですけれども、考えてみると住む場所に平らな場所があるとか、土地がちゃんとあるというのは、それも地形ですし、山のほうから水が流れてきて、その水を使って私たちは生活するための水を得ています。そういった自然がある、地形がちゃんとあることによって、生活基盤が支えられているんですね。
そういった自然がどういうふうにして、そこに存在しているのかが分かると、自分たちがどんな場所にそもそも暮らしているのかが分かります。さらにその自然、時々地形は変化するんです。
その変化した時に何が起こるのかというのは、どんな地形だったら、どんなことが起こるのかは大体予想がついているので、そこの場所が今後どんな自然災害が起こるのかというのが、おおよそ予想をつけることができます。それが分かるとそれに対して準備することができるんですね。
川の近くだったら、どういうふうに逃げなきゃいけないかをあらかじめ考えておくとか、地震の揺れがどうも強そうな場所だったら、家を建てる時に丈夫に作っておくとかですね。
そうすると私たちの生命や財産を守ることもできますので、自分たちがどんな場所に住んでいるのかを知ることは、よりよく快適に、さらに自分たちの生活や命を守る、そういったことにつながると言えます」
●地形を知ることは、防災にもつながるということですね!
「はい! そうですね」
●どうやって調べればいいんですか?
「(私の)本を読んでいただくのがいいんですが(苦笑)、自然現象なので地形に限らず、ほかのものもそうですけど、よく観察してもらうというのがいいかと思います。
同じように見えても実は小さい坂があったり、ちょっとした崖があったり、土地の高さが違ったり・・・あと川のところでは砂があったり石があったり、形の違いがあったり・・・そこにある物、土とか石とかそういったものに違いがありますので、その違いに気づいて、なんでそれが違うんだろうかって考えていくと、だんだんと地形が見えてくるかと思います」
●最後にこの本『地形のきほん』を読むかたが、どんなことを感じ取ってくれたら、目代さんとしてはうれしいですか?
「地形を自分が認識するようになって、考えていたこと、気になっていたことをなるべく盛り込むようにしました。
周りの景色の中に地形は溶け込んでいますので、意識しないとなかなか気づかないところがあるんですね。なので、そういった “あっ、周りに実は坂があるじゃん!”とか、“こんなふうにここの場所、土地の利用の仕方が違うけど、出来方が違うのかな?“とか、そういういろいろな、気づくきっかけになってくれると嬉しいですね。
景色は一様ではなくて多様性に富む自然の中に自分が住んでいるんだっていうのを、今回の本を読んで景色を見て、旅行をした時に周りを見ていただいて、いろいろ気づいてもらえると嬉しいと思います」
INFORMATION
目代さんの新しい本をぜひ読んでください! 地形を作り出す働きから、代表的な地形や暮らしとの関わり、さらには災害や歴史など、地形の基礎知識を豊富なイラストと共にわかりやすく紹介。ひとつの項目が見開き2ページで完結しているので、関心のあるところから読めますよ。地形を知るための入門書的な一冊、おすすめです!
誠文堂新光社から絶賛発売中! 詳しくは、出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。
◎誠文堂新光社:https://www.seibundo-shinkosha.net/book/science/91487/