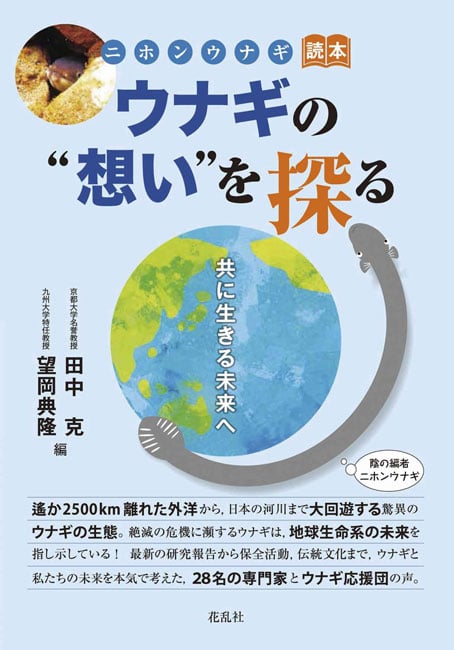2020/10/25 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. ANIMALS / MAROON 5
M2. RADIO / THE CORRS
M3. EVERY BREATH YOU TAKE / THE POLICE
M4. AIN’T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH / MARVIN GAYE & TAMMI TERRELL
M5. 炎 / LISA
M6. THE ANIMAL SONG / SAVAGE GARDEN
M7. ZOO / ECHOES
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2020/10/18 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、国立科学博物館・動物研究部の研究員「田島木綿子(たじま・ゆうこ)」さんです。
田島さんは日本獣医生命科学大学から東京大学大学院、そしてテキサス大学を経て、2006年から国立科学博物館の研究員。専門は海の哺乳類の進化や形、比較解剖など。そしてイルカやクジラなどが浅瀬や海岸に打ち上がってしまう「ストランディング 」調査の専門家として、その謎を病気という観点から解き明かそうとされています。
もともと大きな動物が好きだった田島さんは、写真家で科学ジャーナリスト「水口博也(みなくち・ひろや)」さんのオルカ(シャチ)について書かれた本に出会い、彼らの生態に興味を持ち、海の哺乳類の研究者になったそうです。
きょうは「クジラの先生」と呼ばれる田島さんに、イルカやクジラの進化、そしてストランディングについてうかがいます。
☆写真協力:国立科学博物館

ストランディングの原因
*それでは「クジラの先生」田島さんにお話をうかがいましょう。まずは、9月の末にオーストラリアで起こった大規模なストランディングの話題から。
●イルカやクジラが海岸に打ち上げられてしまうっていうニュースをよく耳にしますけれども、つい最近もオーストラリア南部のタスマニア州の湾に、270頭のゴンドウクジラが浅瀬に迷い込んでしまったと・・・。
「結局500頭以上死んじゃったんじゃないかな」
●そんなに、だったんですか?
「そう、あれはちょっと本当にひどい話で。みんなで原因を追求したいと思うんですけど、3メートル近くのクジラが500頭だと、もうどうにもできないですね」
●どうしてそういうことになっちゃうんですか?
「大体いつも言われてるのは、あの種類は社会性がすごく強くて、みんな集団で行動してるので、なんとなく1頭がそっちに行っちゃうとみんなで行っちゃって。気づいた時には手遅れみたいなことをよく言われるんですけど、大体、大量に座礁するのは社会性が強い種類が多いですね。
群れのリーダーとかサブリーダーみたいな子達が、ちょっと調子悪くなると全部が行っちゃうみたいな風によく言われてるんですけど、まぁいろいろですね。寄生虫説とか、それこそ彼らもウイルス感染症で死ぬので、例えば、あれ全体が病気で一斉に調子悪くなって死んだとか、それはやっぱり解剖とか調査をやってみないと分からないんですよね」
●そういった解剖や調査を田島さんは、されているということなんですか?
「そうですね。病気を見つけたいので解剖しないと分からないんです。一刻も早くとにかく解剖したいっていうのが、私の一番やりたいことなんですけど、なかなかそうはいかないんですけどね」
●迷い込んでしまうのは、方向を探知する能力がないということですか?
「いや、あるんです。ハクジラの場合は耳から超音波が流れてきて、そこを伝って私たちで言う鼓膜みたいなところに行くんですけど、たまにそれが狂ってしまうとかっていう説もあるんですけどね。大型のヒゲクジラはちょっと違うんですけど。それがおかしくなるっていう報告はあります」
●田島さんはどうしてストランディングが起こるとお考えですか?
「そうですね。大量座礁の時は、そのリーダーが調子が悪くなって群れで座礁、っていうのがあったんですけども、1頭だけが上がる場合はやはり私としては、病気で死んでしまったと思いますね。感染症、あとはちょっと難しいですけど、代謝疾患って言って、人間で言うと糖尿病みたいなのとかそういう病気が、同じ哺乳類なので私たちがかかる病気は基本的に彼らもかかるんですね。
なのでまずそういう病気で死んだ個体とか、あとは網に絡まって死んでしまうっていうのも結構あるし、船と衝突するとか、やはり人為的なものも多いので、どうして死んだのかっていうのは、やはりつぶさに観察しながらチェックしてるんですが、いろんな原因があるのは事実です」
骨から分かること

※博物館というと、化石や標本などがたくさん展示されているイメージがありますよね。田島さんは、骨格標本を集めるのもお仕事のひとつなんだそうです。
「今は博物館の職員なもので、博物館の標本として、標本というのはもうありとあらゆるものが標本になりますので、その中の1つとして骨格標本だったりします。
あとは特に野生動物の場合は分かってないことが多いので、例えば犬、猫とかは2歳って言われると例えば、人間の何歳ですねってすぐ分かったりするじゃないですか。それは膨大な資料があって人と犬を比べた時に分かるんですけど、人間は分かってても、クジラのこの種類とか、タヌキでもなんでもいいんですけど、野生動物の場合は当たり前の基礎情報がわかってないことが多いので、そういう意味ではいろんなサンプルとか標本を採集するっていうのが、今の使命でもあるし私もやりたいことなので」
●そもそもどうやって骨格標本って作られるんですか?
「骨格標本は大きさによりますけど、大きいクジラの場合は海岸とか適切な場所に、発見された場所の近くとかに2年ぐらい埋めますね。あとはうちの場合は5メートルぐらいまでのクジラだったら持って帰ってきて、大きな鍋があるんですけど、グツグツ煮るみたいな、豚骨ラーメンの豚骨じゃないですけど(笑)、ああいう感じでグツグツした骨をピックアップして、綺麗にするっていうこともあります」

●骨から何がわかるんですか?
「いろいろ分かりますよね。例えば、子どもたちとかによく言いますけど、私たちここに肋骨ってあるじゃないですか、なんで肋骨ってあるかご存知ですか?
●なんででしょう?
「哺乳類とかでも、肋骨がない動物もいるんですけど、あと肋骨がずーっとある動物とか。なぜ哺乳類は、まぁ哺乳類だけじゃないけど、胸のところに骨があるのか。息をする時に胸郭が膨らみますよね? 実はその肋骨がないと胸は膨らまないし、肺で呼吸できないんですよね。
そうするとエラ呼吸してる魚も実は肋骨はあるんですけど、ずーっと背中まで、お尻の方まで肋骨があるんですよ。子供たちに聞くと、見た目が魚みたいなイルカだけど、実は骨を見ると肋骨が胸にしかない。でも魚は全部あるとか、爬虫類とかいろいろ見ると、そういうところから(イルカは)我々と同じ哺乳類なんだねって言えたりとか。
あとはヒレ状の手だけど、実は体の中の構成要素は我々と同じ上腕骨があって、橈骨(とうこつ)と尺骨(しゃこつ)があってとか、そういう一緒のところと違うところが分かりますよね」
●骨から得る情報量ってのはかなり多いんですね!
「と思いますけどね、はい」
(日本でも年間に200〜300件、浅瀬や海岸にイルカやクジラなどが打ち上がるそうです。
以前、千葉県袖ヶ浦に12メートルのクジラが打ち上がったことがあると「田島」さんが教えてくださいました。そんな大型のクジラの解剖や調査は、10数人のチームを組んで、クレーン車などの重機を手配して行なうそうです。人間ひとりの非力さを感じるとも「田島」さんはおっしゃっていました)

哺乳類の変わり者!?
※続いては、イルカやクジラの進化について。彼らは進化の過程で、一度あがった陸から、海に戻った哺乳類ですよね?
「そうですね。1回全体的に海から陸に上がって、やっと陸の生活ができたぜ!って、みんなでわーいってしてたのに、何故か、俺たちもう1回海に戻るわ、っていう仲間がいたんですね。それが今私たちが知っている海の哺乳類なんですね。私は最近はよく変わり者だなという風な言い方をしますけど(笑)、せっかく上陸して、やっと陸の生活にも慣れてきたにも関わらず、もう1回戻るわけですから」
●なぜ戻ったんでしょう?
「そこはね〜、分からないんですよ。進化ってそこが分からないんですよ。なぜ?っていうのが絶対分からないんです。みんな知りたい、なぜ恐竜は絶滅したとかから始まり、推測はできますけど、絶対真実は分からない。私たちは進化が終わったあとのものを今見ているので、その後ろで何が起こっていたかってのは、タイムマシンとかなければ絶対に分からないですね」
●食べ物が豊富だったとかですか?
「昔はネガティブなプロセス、例えば陸上では負け組だから海に行ったとか水中に行ったっていう説と、積極的に海に行ったっていう説が2つあったんですけど、最近は積極的な方の選択肢の方が支持されているので、多分彼らは自分たちで海の方がいいと何か思ったんでしょう。それはおっしゃる通り、彼らは非常に本能で生きていますから、エサ生物が多かったとか、子育てしやすいとか、本当に単純な本能的な理由で行ってみたら、意外といけたっていう風に思いますね」
●子育ては陸の方が良さそうなイメージがありますけどね。赤ちゃんのイルカやクジラって肺呼吸ですから、海面に上がってから呼吸しなきゃいけないっていうのを見ると大変そうな感じ。でもあえて海に戻ったということなんですね? 不思議ですね!
哺乳類であり続けることを選んだっていうのも何かイルカたち、クジラたちの理由があったっていうことなんですかね?
「理由は分からないけど、多分水に適応しようと進化しなかったんですよね。エラ呼吸に戻るとか、そういうこともせず。私はだからセンチメンタルに言うと、俺たちは哺乳類でいたいんだ! って意地みたいなものを感じるってよく言っちゃうんですけど、いや分かりませんよ?(笑)そういう風に思うとなんかちょっとシンパシーを感じるなっていうか」
● そうですね〜!
胃の中からプラスチックゴミ
*ここ数年、海洋を漂う膨大なプラスチックゴミが大きな問題となっています。俳優のレオナルド・ディカプリオが製作総指揮の映画「プラスチックの海」が来月日本でも公開されますが、まさに海洋を漂うプラスチックゴミにフォーカスしたドキュメンタリーで世界各国で注目を集めています。
(映画「プラスチックの海」オフィシャルサイト:
https://unitedpeople.jp/plasticocean/)
田島さん、海洋プラスチックゴミは当然、イルカやクジラにも影響はありますよね?
「そうですね。私たちも調査を20年ぐらいやってるんですけど、残念ながら実際20年前ぐらいから、いわゆる海岸に打ち上がってきてしまうクジラたちの胃の中からは、大きなプラスチックはもう見つけてしまっていますので、解剖して胃を開けてみると、胃の中に我々が出したプラスチックゴミを見つけることがまず最初に発見する、初見ですね」
●具体的にはどんなものが見つかるんですか?
「園芸用の苗を植える黒い、育苗ポットって言うらしいんですけど分かります? あれが多いのと、あとはアイスコーヒーとか飲む時の、ミルクとかガムシロップを入れる小さな容器、子どもたちが食べるゼリーの容器とか、あとはPPバンドって言うんでしたっけ? 荷物を縛るバンドとか、本当に皆さんが見たことあるっていうものとかもあります。あとは普通のゴミ袋の破片とか、ビニール片がすごく多いですね」
●私たち人間が作って捨てたものですよね、こういったプラスチックゴミっていうのは。
「まさにおっしゃる通りです」
●私たちは何をすればよろしいんでしょうか?
「それはもう本当にシンプルなことだと思いますけど、とにかくゴミをまず出さない、極力出さない。でも出さないっていうのも難しいので適切に処理をする。ゴミ箱に捨てるとか、リサイクルするとか。
やっぱりこれだけ豊かになってしまうと、そのレベルを下げろっていうのも非常に大変なのは、私含めてもちろん分かるんですけども、やはり周りに迷惑をかけつつ、人間だけが一人勝ちしたところで、その先に明るい未来は待っていないと思うんです。なるべくみんなで一緒に生活する、共存するためには、人間ばっかりが快適な生活を送ってていいのかなと」
●このままの状態が続くと、クジラやイルカたちはどんな風になってしまうんですか?
「一番懸念するのはやっぱり、さっきもおっしゃった海面に息を吸いに上がってきますから、その海面にゴミだらけだったら、彼らは息ができなくなるとか、エサが減ってくるとか、あんまりいい状況は、とにかく彼らにとっていいことは何一つないと思っているんです。
私たちが快適だと思うことは決して、彼らにとって全く快適ではないので、それをもうちょっとね。ちょっと考えるだけで行動って変わるんじゃないかなって思うんですけど、やはり強制されても人ってやらないのは分かってるので、そういう事実を知って、じゃあどうするって、ちょっとだけでも変われば、それが塵も積もればどんどん大きい力になってくるので」
●本当に1人1人の意識が大事ですね。
「本当にそう思いますね 」
INFORMATION
<田島木綿子さん情報>
イルカやクジラなどの海の哺乳類が浅瀬や海岸に打ちあがってしまうストランディング、その国内のデータが国立科学博物館のオフィシャルサイトに載っているので、興味のあるかたはご覧になってください。いつ頃、どこにどんなイルカやクジラがあがったか、ひと目でわかるようになっています。田島さんの研究や活動についても国立科学博物館のサイトをご覧ください。
◎国立科学博物館HP:https://www.kahaku.go.jp
2020/10/18 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. THE WHALE THAT SWALLOWED JONAH / JOE BONAMASSA
M2. I SAVED THE WORLD TODAY / EURYTHMICS
M3. 伝えたいことがあるんだ / 小田和正
M4. BONES / GALANTIS
M5. エメラルド / back number
M6. UNTIL YOU COME BACK TO ME / BOBBY CALDWELL
M7. THE GOOD LIFE / TIM MYERS
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2020/10/18 UP!
<イルカ・クジラのコミュニケーション能力>
イルカやクジラは「ハクジラ」と「ヒゲクジラ」に分類されますが、ハクジラとヒゲクジラは仲間同士のコミュニケーションの方法も違うって、ご存じでしたか?
大きく分けると、イルカを含むハクジラは超音波を発信・受信するエコーロケーション、シロナガスクジラなどのヒゲクジラは“声”でコミュニケーションを取っていると考えられています。イルカなどのハクジラは呼吸器から頭にかけての構造で超音波を発生させ、前方の物体に当たって戻ってきた音を聴くことで、獲物の場所や仲間の位置などを知るほか、様々な情報を仲間同士で伝えているとされています。
一方、ヒゲクジラの代表格で地球上最大の生き物とされるシロナガスクジラは、声の大きさもビッグスケール! ジェット機の離陸音より大きな音を出すこともあるんだそうです。また、人間には聞こえない低周波の声も出し、コミュニケーションを図っているそうです。
同じくヒゲクジラのザトウクジラはなんと歌うといわれています。ホイッスルのような高音から低い唸り声まで数種類のフレーズを組み合わせ、数分から1時間以上も歌うことがあり、メスへの求愛の意味があるとされています。1970年にはザトウクジラの鳴き声を録音したレコード「Songs of the Humpback Whale(ソングス・オブ・ザ・ハンプバック・ホエール)」がリリースされて大ヒットしたそうですよ。
2020/10/11 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、日本シェアリングネイチャー協会の「草苅亜衣(くさかり・あい)」さんです。

日本シェアリングネイチャー協会は、27年ほど前に日本ネイチャーゲーム協会として発足。その後、2013年に公益社団法人となり、現在はネイチャーゲームの普及に加え、「人が自然を尊重し、共生していく社会をつくること」を目的に活動しています。
ネイチャーゲームは、アメリカのナチュラリスト「ジョセフ・コーネル」さんが1979年に発表した自然体験プログラムで、世界各国で親しまれています。現在は179種のネイチャーゲームがあり、日本で生まれたものも多いそうです。

以前コーネルさんが来日されたときに、この番組に出ていただきました。その時のインタビューは番組ホームページに載っていますので、ぜひご覧ください。
◎THE FLINTSTONE HP:http://www.flintstone.co.jp/20161015.html
☆写真協力:日本シェアリングネイチャー協会

自然と遊ぶネイチャーゲーム
*たくさんあるネイチャーゲームは、いくつかジャンル分けされているのでしょうか?
「ネイチャーゲームはジャンルというものはないんですけれども、対象によって結構アレンジをしやすいことも特徴なんですね。例えば、幼児向けにちょっと工夫して、小さい子でも楽しめるように実践したりですとか、高齢者の方向けには記憶にアプローチするような、嗅覚を使ったネイチャーゲームがいいよねっていったようなことはあります。
それから私たちはシェアリングネイチャー・ウェルネスと呼んでいるんですけれども、日常的にセルフでじっくり自然と関わって行なうようなアクティビティを使って、自分自身の内面を見つめて整えていくような活動っていうのにも応用されています。
“自然とわたし”というネイチャーゲームがあるんですけれども、例えば、目の前にある大きな木を見つめて、その木に鳥がやってきたなとか、風で葉っぱが揺れてるなとか、ずっと見ているとそういった変化がありますよね? そういった変化を、膝に両手を押し当てた状態で静かに数えていくんですね。
私が体験した時に思ったのは、それまでいろんな雑念がやっぱり常にあるんですけれども、そのアクティビティをやっている時、あるいはやった後は、次のことを考えてないというか、今だけに集中している状態になっているんですね。それを日々、自分で継続的に続けていくことで内面を整えていくことができる。ヨガなんかでも同じ効果があるかと思うんですけれども、そういった活動になります」


●ちなみに秋におすすめのネイチャーゲームはありますか?
「やっぱり秋って言えば紅葉のシーズンですし、気候も安定してるので、色を楽しむ“森の色合わせ”っていうネイチャーゲームがあるんです。これはたくさんの色が描かれているカード持って、自然の中に入って、そのカードに描かれている色と同じ色を探すっていうネイチャーゲームなんですけど、1人でやってももちろん楽しいですし、一緒に行った方と、例えば赤を見つけたとしたら、同じものではなかったりするんですね。こういう赤もいいね! それも赤だね! っていう、人との感性の違いみたいなものも楽しめると思います。
“雲見”っていうネイチャーゲームもあるんですけど、雲を何秒間か見て、目を閉じて少し経ってからまた目を開けるっていう、シンプルなネイチャーゲームもあるんですけども、秋空を楽しむのもいいかなという風に思いますね」
●自分自身も自然に溶け込めそうですね。
「そうですね。あとは落ち葉に埋もれるネイチャーゲームっていうのも、“大地の窓”っていうんですけど、そういうのもあります。秋におすすめですね!」
*「草苅」さんおすすめのネイチャーゲーム、ほかにも「フィールドビンゴ」があるとおっしゃっていました。これは見る、聞く、さわる、匂いをかぐなど、様々な感覚を使って自然を楽しむビンゴゲームで、事前に用意したビンゴカードを持って、フィールドに出かけて遊ぶそうです。


身近な自然が大自然!?
※新型コロナウィルスの感染拡大に伴ない、日本シェアリングネイチャー協会のイベントや講習会なども中止となり、協会スタッフのみなさんも活動自粛となりました。草苅さんはお子さんがふたりいるママなんですが、活動自粛中はお子さんたちと、どんな風に過ごしていたのでしょうか。
「そうですね。やっぱり三密を避けて、人がほとんどいない神社に出かけたりとか、神社って結構穴場で、自然がいっぱいあるけど人は少ない環境なので、神社に出かけたり。あとは早朝に子どもたちを連れて、土手に自転車で行って過ごしたりしていました。
スタッフ同士でも話に出るんですけども、やっぱり気づいたらネイチャーゲームしていたりするので、そういう土手とか神社に行った先でいい匂いのものを探したりとか、腹ばいになって虫眼鏡で地面を探検してみたりとか、裸足になって歩いてみたりとか、ネイチャーゲームの要素をふんだんに取り入れて楽しんでいたなって思います」
●改めて気づいたこととかもありそうですね!
「やっぱり自然の大切さ、自然の存在の大きさを感じましたし、シェアリングネイチャーは必要だなっていうのを自分はすごく思いました。身近な自然がネイチャーゲームを使うことで、大自然みたいなスケールで楽しめるので、そのことをかなり実感しましたし、毎日すごく頼りに過ごしていた気がします。親としてもすごく感謝という気持ちでした!」
●色んな経験をもとにスタッフの皆さんとアイデアを出し合った中で、実際に始めたことって何かありました?
「スタッフで始めたというよりは、本当に全国のリーダー仲間の皆さんがそれぞれに工夫して活動再開されていく中で、一緒に進めているという感じなんですけれども、まずオンラインでいろんな情報発信を始めました。
有志で発足したプロジェクトで“ハッピーラッキーネイチャープロジェクト”という活動があるんです。これは身近な自然との関わりですとか、おうちの周りでも自然を楽しむ方法を、簡単な写真とか動画で撮影して SNSでタグ付けして紹介するっていう取り組みなんですけれども、これは3月の始めから今も継続して行なっています。
あとは当協会のホームページに“カワウソくんのフィールドノート”というコンテンツがあるんですけれども(笑)、その中でおうち時間を楽しめる活動をいろいろ紹介しています。さらに文部科学省が行なっている、子どもたちの自然体験を推進する授業があるんですけれども、私どもの団体もこれに参加しておりまして、全国各地でネイチャーゲームを体験できる自然教室を今まさに開催しているところです」

コロナに負けない外遊び
※日本シェアリングネイチャー協会では「ハッピーラッキーネイチャープロジェクト」の一環として「コロナに負けない外遊び」を発信しています。具体的にはどんな遊びがあるんですか?
「先ほどお話をしたような活動を通して、コロナ禍であってもネイチャーゲームやその要素を使うことで、身近な自然で思いっきり楽しめるような発信を行なっていきたいなと思っています。SNSや動画を見ていただくと、また、イベントに参加していただいたりすることで、帰ってからも身近な自然を楽しめたりとか、そのためのヒントをたくさん得ることができると思うんですね。そこが“コロナに負けない外遊び”っていうことで、チェックしていただきたいところです!
本当にたくさんアクティビティがあるので、ウェブとかももちろん見ていただきたいんです。例えば、これから秋で落ち葉がたくさん落ちていると思うんですけれど、“ジャンケン落ち葉集め”っていうアクティビティがあります。
例えば、親子でジャンケンして勝ったら落ち葉を1枚拾えるんです。負けたら拾えないんですけど、別のグループなら別の方とジャンケンする。勝ったら落ち葉を拾うっていうことを何回戦かして、手元に何枚か落ち葉が集まりますよね? で、みんなで集まって落ち葉を見せ合うんです。その拾った落ち葉、何気なく拾った落ち葉1枚1枚が、同じ樹種でも色が違ったり、穴空きだったり、形がいろいろ違ったり、本当に個性が豊かなんですよね。
そういう1つ1つの自然の違い、それから一緒にやった人の拾った落ち葉との違い、感じたことなんかをお互いに話したりして、すごくジャンケン自体も盛り上がるんですけど、あとからのシェアもすごく楽しいです。
“同じものを見つけよう”っていうアクティビティで、葉っぱとかどんぐり、木の実とか剥がれ落ちた樹皮とか、小枝とか、そういうものをちょっと集めておいて、15秒ぐらい見て記憶するんです。記憶して今度は隠しちゃいます。で、記憶したものを思い出しながら同じものを集めるっていう、ネイチャーゲームなんです。
これも本当に面白くて、同じもの集めてくる、こんな形だったとか、記憶を頼りにこのくらいの大きさの木の実だった、こんな色だった、葉っぱはもうちょっと茶色だった、みたいなことを思い出しながら同じようなものを集めてくるんです。集まってきたものをみんなで見せ合うんですけど、違うんですよね(笑)。
ちょっとずつやっぱり違っていて、すごく似ているものを見つけてくれたりとかして、それも面白いんですけど、すごいね!っていう本当に感動なんです。どれひとつとして、やっぱり同じものはないよねっていうような気づきもありますし、すごく学びが大きい。シンプルなんですけれども学びがあって、小さい子でも楽しめるので、ジャンケンができれば楽しいかなと思います」
●少しでもお子さんを外の空気に触れさせるっていうのは大事ですよね〜。
「そうですね。やっぱりどうしても家の中にいると閉塞感がありますので、子どもたちの心身の健やかな成長にとって、全身全感覚を働かせることができるので、やっぱり自然での外遊びは重要だと感じています」
おうちでもネイチャーゲーム!
*外に行かなくても、自宅でできるネイチャーゲームはありますか?
「プランターとか、窓から見える空とか景色でできるネイチャーゲームは、実はたくさんあるんです。例えば“森の美術館”っていうネイチャーゲームがあるんですけど、それは白い紙の内側をくりぬいて、枠のような形にして準備していただきます。
それを気に入った自然の前に置いたり、クリップで留めたりして設置するんですけども、それが額縁に収められた美術作品みたいに、本当に素敵に見えて楽しいんですよ! シンプルな工程でできるんですけど、すごくインスタ映えもするのでおすすめです。


それから、単純に耳をすませて音を数えるネイチャーゲーム“音いくつ”っていうものがあるんです。1分間ほど耳をすませて自然の音を数えていくっていう、本当にただそれだけのネイチャーゲームなんですけど、普段あんまりただ耳をすませるってないと思うんですね。今私もテレワークをやっているんですけども、そのテレワークの合間とかにやっていただくとリフレッシュにもなるし、おすすめだなって思います」
●ご家族で答え合わせをするのも楽しそうですね!
「そうですね。何が聴こえたかっていう話ができますし、あとは自分には聴こえなかったけど、一緒にやっている子供たちに聴こえたりとか。そんな音も聴こえたんだ! すごい!っていうそういうシェアもできますね」
●おうち時間を子どもたちと自然を感じて過ごせるヒントや、何かグッズなどあれば教えていただきたいんですけれども。
「私どもの協会ではネイチャーゲーム・ショップという物販も行なっているんです。そういうグッズばっかり扱っているので(笑)一度覗いてみていただきたいんですけれども、虫眼鏡が1つあるだけでもかなり自然との関わりが広がると思います。
今月発売になった“楽しく学ぶ動物のカード”っていうカードゲームがあるんですけれども、動物の生態を、体の大きさや棲んでいるところとか、食べ物など、そういったヒントと共に考えたり想像したりしながら学ぶことができるアイテムになります。
遊び方はいろいろあって、例えば神経衰弱みたいに遊ぶこともできるので、ネイチャーゲーム的な視点で動物のことを学べる、ネイチャーゲーム・ショップならではのカードゲームかなと思っています!」
INFORMATION
<全国一斉ネイチャーゲームの日、リーダー養成講座ほか>
毎年10月の第3日曜日は「全国一斉シェアリングネイチャーの日」ということでその日の前後に全国各地でいろいろな体験イベントが開催されます。その中から首都圏で開催されるイベントをいくつかご紹介しましょう。
10月17日(土)の午前10時から、東京都練馬区にある都立光が丘公園で秋の始まりを、目を閉じて感じる体験イベントが予定されています。参加費は無料。定員は20名となっています。同じく17日(土)の午前10時から、埼玉県・みずほ台中央公園でネイチャーゲームで遊ぼう!体験会!があります。こちらも参加費は無料です。
10月18日(日)の午前9時半から、神奈川県立・相模原公園で植物や昆虫を探す「秋の公園で自然と遊ぼう!」が開催されます。定員は30名。参加費は無料です。ほかにも全国各地で体験イベントが目白押しです。
なお、イベントは天候や諸般の事情で中止になることもあります。お出かけ前に、日本シェアリングネイチャー協会のオフィシャルサイトでご確認ください。

そして協会では、ネイチャーゲームのリーダーの資格を取得するための養成講座も行なっています。この講座では講習や実技を通して、自然と人を結ぶ、自然案内人のノウハウとスキルを身につけられます。18歳以上のかたなら、どなたでも参加できます。
これまでに4万人以上のかたが講座を受講し、現在1万人以上のかたがリーダーとして登録されているそうです。ぜひあなたも自然案内人になりませんか? 草苅さんがおっしゃるには「人生が豊かになる資格」だそうです。
SNSで情報発信している「ハッピーラッキーネイチャープロジェクト」にも注目です。
いずれも詳しくは日本シェアリングネイチャー協会のオフィシャルサイトをご覧ください!
◎日本シェアリングネイチャー協会HP:https://www.naturegame.or.jp/
2020/10/11 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. 赤黄色の金木犀 / フジファブリック
M2. Color of Life / Misia
M3. HAPPY NOW / ZEDD & ELLEY DUHE
M4. PLAY THE GAME / QUEEN
M5. LA・LA・LA LOVE SONG / JUJU
M6. 落ち葉のコンチェルト / ALBERT HAMMOND
M7. EVERYTHING IS GONNA BE ALRIGHT / THE SOUNDS OF BLACKNESS
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2020/10/4 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、自転車の旅人「坂本 達(たつ)」さんです。
坂本さんは1968年、東京都生まれ。早稲田大学卒業後、ミキハウスに入社。95年から99年に有給休暇をもらって、4年3ヶ月かけて自転車で世界一周、43カ国、55,000キロを走破。その後、出版した本の印税で、お世話になったギニアの村に診療所を建てたり、井戸を掘ったりと恩返し、そして国内での社会貢献活動にも積極的に取り組んでいらっしゃいます。
そんな「坂本」さんが今、家族と一緒に挑んでいるのが自転車による「世界6大陸大冒険」なんです。いったいどんな冒険なのか、このあと、じっくりお話をうかがいます。
☆写真:Tatsu Sakamoto Office

どうせ大変ならやってみよう!
*2015年に8年計画でスタートしたこの大冒険は、毎年3ヶ月かけて、自転車で旅をするスタイルで、第1ステージのニュージーランド編に始まり、スペイン、ポルトガルほかのヨーロッパ編、続いてカナダ・アラスカの北米大陸編、そしてネパール、ブータンほかのアジア編を経て、2019年の第5ステージ、北海道編まで終えています。
そもそもどうして、幼い子供と奥様を連れて、世界6大陸を自転車で巡る旅に出ようと思ったんですか?
「私が20代から30代にかけて単独で自転車で世界一周をしました。4年3ヶ月ほどかかったんですけれども、その時の経験とか感動とか景色とかそういうのを、今度は子どもたちに伝えたいという風に思いました。本とか写真とか言葉では伝えられても、経験してみないとわからないだろうと思いまして、思い切って今度は家族を連れて行こうと思ったのがきっかけです」
●とはいえ、実行に移すとなるとかなり準備も大変だったんじゃないですか?
「そうですね。まず会社の仕事もありますし、あとは妻の説得もありました。子どもに関してはまだ5歳と2歳だったので、お父さんは冒険家なんだよというところから、行くのが当たり前という風に言ってましたね。
会社に関しては、すでに4年3ヶ月の世界一周を会社員として単独でしていましたので、また坂本が2回目をチャレンジしようとしていると、まあその辺でなんとなく理解はあったんですが、やっぱりちょっと妻の方が大変だったかなと思います(笑)」
●世界を旅しよう! って言われて、奥様はなかなかOK出せなかったと思うんですけれども、どのように説得されたんですか?
「私が結婚する時に、いつか家族ができたら家族で世界を自転車で周りたいねっていうことを言ってたんですね。その時に妻もいいわねと言ってましたので、よっしゃ!と(笑)思っていたんですが。
いざ子どもが産まれ、ふたりも男の子がいると子育ても大変で、そんな日常の中、世界一周どころじゃないという状況ではあったんです。でも日々の子育ての中で思い切って海外に出てみれば、彼女も海外で暮らしていた経験がありましたので、いろんな人に助けられて、毎日同じ時間にご飯作ってお風呂入れて買い物に行って掃除してとかではなくて、全く新しい環境だけれども、どうせ大変なんだったら、やってみようと思ってもらえたのが良かったんだと思います」

毎日が試行錯誤
※2015年に始まった坂本家の「世界6大陸大冒険」は、第5ステージまで終わっていますが、いまどんな思いがありますか?
「私は自転車で単独で行くのに関しては長けていましたが、妻が実はママチャリしか乗ったことのないという女性でした。あとは子どもたちもまだ5歳と2歳というところで、ホームシックもありますし、毎日違う人と出会って違う場所に寝泊まりして、毎日同じなのは親の顔だけという、全く私にとっても初めての経験でしたので、試行錯誤の連続でしたね。
1日に走れる距離も単独だったら100キロ以上走れたのが1日15キロ とか20キロ、食べることと泊まることを考えながら安全面をケアするという、全くひとりの旅とは違うチャレンジでしたね」
●確かに安全面も含めていろんな所に気を使われたと思うんですけれども、一番どんな所に気を遣っていました?
「毎年夏に3ヶ月かけて8年計画で走っているんですけども、子どもがどんどん成長していきますので、だんだん、なんで自分だけ夏休みに友達と遊べないの?とか、キャンプに一緒に行けないの?とか、学校のプールも、だから1回も経験してないんですね。
そんな中で、なんで自分だけがこうなの?というのも感じるでしょうし、行きたい行きたくないに関わらず、行くことになりますので、自分たちがその冒険に関わっていると。やらされているんじゃなくて、自分もそのメンバーとしてこれを作っていく、要するに主体的に関わるような、ホームスクーリングではないですけれども、そういう仕組み作りって言いますか。
ただ旅行に行く、冒険に行くだったらできると思うんですけども、いかに子供から現地の様子を調べたりとか、現地の言葉に興味を持ったりとか、現地の子と関わったりとか、帰ってきてからそれをどう伝えるかとか、その辺の仕組み作りって言うんですかね?
ただの旅行で終わらせたくなかったので、子どもがいかにルート決め、期間を決める、どこに泊まる、そういうのに一緒に、判断に参加させようと、その辺に結構苦労しましたね」
●幼い頃から決断させるというのはすごく大きなことですね。
「本当に大事だと思いますね。やらされてると思うのと、自分が選んだらこうなったんだという、やっぱり成功だけじゃなくて失敗することってすごく必要ですし、失敗した後にどうフォローするか、次はどうしようかというのを一緒に共有することって、やっぱり人を成長させることだと思うので、意識してやっていたつもりです」
●旅をしている時って、お子さんたちにとっても非日常の世界ですけれども、日本に戻ってきてからの生活で、お子さんたちはどんなことを言ってましたか?
「あ、それはですね。遠征中は非日常ではなくて彼らにとって日常になるんですね(笑)。適応力がとにかくありますので、毎日走る、移動するっていうのが当たり前になるんですね。
ですので、帰ってきたら帰ってきた瞬間が非日常って言いますか。もちろんギャップがありますので、例えばお風呂に入れる、シャワーだけの所とか多いですし、トイレに座ったら暖かいとか、洋服箪笥を開けると服がいっぱいとか、そういう素朴な感動が最初はあります。でも子どもたちは別に何とも思ってないというか、ちょっと近くの熱海に旅行に行ったとか、その程度しかないんじゃないかなと思いますね(笑)」
王様に招待される!?

※坂本家の「世界6大陸大冒険」、ハプニングだらけの自転車旅だと思いますが、これまでの旅を振り返って、忘れられない出来事を3つ挙げていただきました。
「子どもたちとも話していたんですが、子どもたちも満場一致だったのが、ブータンを走っていた時にブータンの王様に招待されて、パレス(宮殿)に家族で招かれたことですね。
王様が実は自転車好きっていうのは、私は知っていたんです。また、以前ブータンにはいろんなプロジェクトで、幼稚園を作ったりとか個人的に関わりがあったので、もしかしたらお会いできるかもしれないと思って、(ブータンの)テレビとか新聞に出て、自分たちが王様に知ってもらって、もし機会があったら連絡くださいって言ってたら、帰国する前日に電話がかかってきまして、40分以内にパレスに来れますか?って。行きます行きます!って言ってですね(笑)」
●そうだったんですね〜!
「子どもたちは、本当に優しい王様で、とってもいい時間だったって日記にも書いています。普通の人で王様に会う機会はないと思うんですけども、いろんな美味しい飲み物とか食べ物とかアフタヌーンティーとか出してもらって、最後は記念写真を撮って。
王様の子どもが当時2歳ぐらいだったんですけれども、ちょっと子育ての話をしたりとか、王妃も出てきてくれたので、今度は家族で自転車で走れたらいいですね〜みたいな話をしました。それがいちばんでしたね!

続く2番目はスペインのキリスト教の巡礼路、サンティアゴコンポステーラを目指して約1ヶ月ですね、キリスト教の巡礼者と共に1日に20〜30キロ走るんです。巡礼者は歩くんですけれども、私たちは自転車でほぼ同じ距離を毎日走っていくんですね。
そうするとみんな顔見知りになります。その時は上の子の健太郎がまだ6歳でしたので、初の自分の自転車で漕ぐデビューだったんですね。彼も重たい自転車で慣れない中、みんなが、巡礼者が助けてくれて、上り坂は自転車が重たいので押してくれたりとか、それがもう何回も何回もありました。大人でもそれ結構リタイアする人が多い巡礼路なんですね。長い人はもう1200キロぐらい歩くんですよ、2ヶ月ぐらいかけて。
私たちは1ヶ月かけて550キロを、リタイアする人も多い中、子どもがみんなに励まされて、お前はすごい頑張ってる! お前はチャンピオンだ!って。家族だけだとやっぱり親がいくら励ましても限界がありますけど、 会う人みんなにお前はすごい!って励まされますので、ゴールした時はもうみんな家族。知らなかった人がみんなよく頑張ったね! 本当にすごかったね!って言って拍手をしてくれる、そんな感動があったのが忘れられない2番目かなと思いますね!」
(*忘れられない出来事の3番目はカナダ・アラスカの旅。広大な土地だけに、自転車で移動していても、ほとんど人に出会えない中、出会った人たちの優しさ、そして景色が忘れられないそうです。また、クマが生息している環境でのキャンプだったので、子供たちがクマを怖がっていたのも思い出されるそうです)

子供たちが自費出版!
*実は先頃、これまでの旅の軌跡が本になって自費出版されました。タイトルはズバリ! 『世界6大陸大冒険』。著者は坂本さんの息子さん、健太郎くん10歳と康次郎くん7歳のふたり。坂本さんが本にまとめようと言ったわけではなく、息子さんふたりが、今までの経験を本にしたい、そしてそれを売りたい、と言い出し、本づくりが始まったそうです。絵日記があったり、写真も豊富に掲載されています。食べ物や動物の話もたくさんあって、子供目線のレポートがとても新鮮です。
この本は坂本さんにとっても子供たちの成長が見て取れる本ではないでしょうか。

「はい、そうですね。やっぱり写真を見てるだけで、子どもがどんどん成長していきますね。1年目は次男の康次郎が後ろに座って、まだ2歳だったので、食べるか寝るかあと歌うかだったんですけれども、だんだん連結したトレーラーで自分で漕いだり、3年目にはもう自分の自転車で独走するようになりました。
長男の健太郎はもう4年目から後ろに荷物を積んで走るようになって、自転車も大きくなり荷物も持ってくれるようになりました。もう妻よりは上り坂はダントツで早いですし、本当にいろんな意味での成長が日本にいる時の10倍か20倍ぐらい、とにかく経験だなと思うんですよね。その辺はすごく成長してるなって感じますね」
●どんどんたくましくなっていくお子さんたちの姿にジーンとしちゃいました。
「ありがとうございます(笑)」
●旅を通して坂本さんと奥様ご自身も変化があったんじゃないですか?
「そうですね。まず私はやっぱり子どもが大きくなるにつれて、子どもたちに主体的に関わらせたいと思っています。できるだけ自分からテントの設営をしようよとか、荷物をパッキングしようとか言わない。
日本ではやっぱり忙しいので言わなきゃいけない時もあるんですけども、出発が遅れたらその分、暑くて距離を走れなくなる、そういうのを自分で考えて早く朝出発する、パッキングする。遊びたい時期なんですけども、自分から動けるような、それをどんどん割合を高くしていくように、できるだけ指示を出さないようにしていました。自分自身も我慢というか、大人がやったら全部早いですし、上手くいくんですけど。

今回の本作りも本の発送出荷も全部子どもたちがやっているんです。私たちがやれば一瞬で済むことをもうイレギュラー、トラブルの連続ですよね(笑)。ですけど、やっぱりそれって大事で、本が届いた人からお礼があったらそれを見て、自分が送ったものがこうやって喜ばれているんだとか、関わらないと分からないっていうことをさせたいと思って、私は関わっています。
妻も最初はやっぱり坂本達の奥さんだから、自転車の冒険に一緒に行かなきゃいけないっていう義務感で行ってたんですけども、やっぱり世界でいろんな人に出会って、自分の生き方ってどういうことなんだろうと。
同時に子どものその成長を客観的に見られるようになって、これまでこんなに頑張ってたんだとか、私は自転車に関してはどんなに辛くても何とも思わないんですけれども、妻はそのキツさを知っていますので、これだけ子どもたちが頑張って無理して、でも口に言わずに頑張ってきたんだとか、そういう子どもを客観的に見られるようになってきたところもあるかなって思いますね」
●この本『世界6大陸大冒険』を読まれた読者の方からはどんな反響がありましたか?
「子どもが書いた本なので、すごく幼い内容と思われるんですけれども、読んだ人は文字数も写真もたくさんあって読み応えがあるとか、お母さんの葛藤や悩み、苦悩が伝わってきて共感して涙が出ましたとか、本当に多く幅広い人にしっかり読んでもらっているなって感じてます」

まず動いてみよう!
※日本では幼い子供を連れての冒険は心配されることも多いと思いますが、海外ではどうなんでしょうか?
「子どもに冒険させるさせないっていうよりも、家族単位で1つのプロジェクトって言いますか、例えば家族で夏休みは自転車で南米を走るとか、家族単位でヨットで世界を一周する、その間学校はホームスクーリング、親が子どもの勉強を見ながら、学校とはパソコンで連絡を取り合うとか。
日本はなんとなくですけれども、周りがいろいろ言ってくる、それ危険じゃないの? それどうなの? 学校どうするの? とか。比較的外国は少ないんじゃないかなと、干渉されにくいのでいろんなことができる。
日本でもそれをやりたいけども、冒険しにくい。でも本当はやりたいんじゃないか? っていうのを、こういう活動してるとすごくいろんな方から応援のメッセージをもらったり。どうやって学校を休ませるんですか? 仕事はどうするんですか? という問い合わせをもらうので、実はもっとやりたいんじゃないか。でもそういう社会背景がそうさせてるんじゃないかなって思うので、思いは皆同じなんだなと思っています」

●確かに冒険に出てみたいと思う方は多いと思うんですけど、でもだからといって仕事は休めないよーとか子供の学校はどうするのとか、そうやって思ってしまう方は多いと思うんですよね。一歩を踏み出す勇気っていうのは、なかなか難しいと思うんですけれども、そういった方々に向けて何かアドバイスはありますか。
「そうですね。まず動いてみないと分からないので、仕事のことにしても子どもの学校のことにしても、できるできないって私たち考えちゃいますけど、できるできないよりも、まずやってみると。考えるとできなかったらどうしよう、だめだったらどうしようってやっぱり人間どうしても思いますのでまずやってみる。やってみたら意外に話がスムーズに進んだり、もちろんダメだったりするんですけど、じゃあどうしたらいいかっていう次の道が見えてきたりするんですよ。
私もやりたかったっていう人もいますし、幼稚園の時は園長先生が幼稚園に来るよりいいですから、坂本さん行ってきてくださいって、園長が言うんですよ。私たちすごく感動しまして、とにかく経験が大事だって。
小学校も校長先生に入学する前から、来年からこういう家族が入学してくるんですけれども、学校の勉強は全て親が責任持ちますので、ご理解いただけませんかっていうところから始まって。
授業でも教科書でやるよりも同級生が海外でこういうことをやって、時差のこととか動物のこととか文化のことを、健太郎くんはこういう所に行ってるんだよってのを授業で使ってもらったりして、先生もやりやすかったりとか。
いろんな人に理解してもらって応援してもらうためには、まず動いてみなければ分からない、考えているだけじゃ何も進まないというのが、私の経験からのメッセージかなと思います 」

INFORMATION
坂本健太郎くんと康次郎くんが作った本
『世界6大陸大冒険』

子供目線の素直な感想が微笑ましく、心身ともに成長している姿が見て取れます。坂本さんと奥さまのレポートも載っていて、我が子を思う親の愛情を垣間見られる本となっています。坂本家の思いがこもった自費出版の本をぜひお買い求めください。詳しくは、坂本達さんのオフィシャルサイトをご覧ください。
◎坂本達さんのHP:http://tatsuoffice.com/

2020/10/4 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. YOU ARE THE SUNSHINE OF MY LIFE / MACY GRAY
M2. EVERYDAY IS A WINDING ROAD / SHERYL CROW
M3. fanfare / Mr.Children
M4. Life / 藤巻亮太
M5. フォーエバー / D.W.ニコルズ
M6. HAPPY PEOPLE / R.KELLY
M7. HERO / MARIAH CAREY
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2020/10/4 UP!
◎森上信夫(昆虫写真家)『夜は昆虫写真家!?〜ノコギリクワガタとウルトラマン〜』(2020.09.26)
◎山本智之(海の潜水科学ジャーナリスト)『寿司ネタが獲れなくなる!? 〜温暖化が及ぼす海の異変〜』(2020.09.19)
◎かほなん(サバイバル・アイドル さばいどる)『さばいどる「かほなん」〜夢は無人島暮らし!〜』(2020.09.12)
◎木村由莉(国立科学博物館の研究員)『恐竜少女、夢の古生物学者に!』(2020.09.05)
2020/9/26 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、昆虫写真家の「森上信夫(もりうえ・のぶお)」さんです。
森上さんは1962年、埼玉県生まれ。子供の頃、おじいさまの影響で、虫取りなどの遊びを通して昆虫が大好きになった、まさに昆虫少年。そして立教大学在学中に撮影の技術を身につけ、現在は、昆虫写真家とサラリーマンを兼業、忙しい日々を過ごしていらっしゃいます。そんな森上さんが先頃、新刊『オオカマキリと同伴出勤〜昆虫カメラマン、虫に恋して東奔西走』を出されました。
きょうは、兼業だからこそのエピソードやベランダ昆虫園、そして昆虫への熱い想いなどうかがいます。
☆写真提供:森上信夫

オオカマキリと同伴出勤!?
※森上さんはサラリーマンとの兼業をされていますが、どうやって昆虫を撮影する時間を作っているのでしょうか?
「それはもう結局は、1日は24時間という上限があるので、寝る時間を削るしかないんですよね。
で、幸いにというか、昆虫の羽化とか孵化とか脱皮のような劇的なシーン、それこそ本で使うためにまさに撮らなければならないシーンというのは、天敵である鳥が寝ている時間、つまり夜に行なわれることが多くて、夜から明け方にかけてですね。だから自分が寝る時間を削りさえすれば、意外に撮れるものなんですよ。
日中にやられてしまうと出勤時間は動かせませんから、そこはどうにもならないんですけれども、夜にそういうことが起きることが多いので、単純に徹夜すればなんとかなるというケースが多いですね」
●でも、徹夜して次の日は普通に仕事に行くわけですよね?
「そうなんですよ。徹夜明けで出勤するというのは、なかなかつらいものがあるんですけれども、撮れた時はそれでも満足感いっぱいで電車に乗れますからいいんです。でも、撮れなくて出勤時間を迎えた時ですね。羽化、孵化、脱皮が起きると踏んで徹夜で待機したのに、結果的に何も起きなかった場合というのは、出勤する時の疲労感といえば相当なものですね(笑)」
●そうですよね〜。この本にも、僕を28時間待たせたオオカマキリ、という風にありましたけれども、本当に徹夜の撮影っていうのは当然のようにあったわけなんですよね。
「そうです。ちょうどお盆の時期だったので勤務先も休みで、28時間待てたことはある意味幸せだったんですけどね」

●オオカマキリと同伴出勤したのは本当なんですか?
「あ、これは本当なんです」
●これはどういうことですか?(笑)
「卵を産みそうなオオカマキリがいまして、お腹がもうパンパンに膨らんでいて、身重な感じだったんです。それで締め切りのある仕事で、オオカマキリの産卵シーンを撮らなければいけなかったんですよ。結局その時も一晩徹夜して朝まで見ていたんですけれども、夜のうちに産まなかったんですね。
スタジオで撮っていたわけですけども、これをそのままスタジオに放置して出勤してしまうと、昼のうちにおそらく産卵してしまうだろうということは予想できたので、もうこれは連れていくしかない! ということで、職場に小さな水槽に入れて連れて行ったんです」
●職場のみなさんはどんな反応されるんですか?(笑)
「それは分からないように、コンビニの袋に入れた状態でデスクの足元に置いて。それで職場で撮影できるわけではないので、何をしたかというと、そのコンビニの袋に入ったミニ水槽の上に足を乗せて、延々と貧乏ゆすりをしながら、上半身は普通に仕事をしているんですけど、下半身は延々と貧乏ゆすりをして、その水槽の中にいるオオカマキリがグラグラ揺れる中で産卵を始めないように、オオカマキリも落ち着かないですから、そういう形で産卵したいという気持ちを妨害し続けたんです」
●へ〜! で、無事に産卵シーンは撮影できたんですか?
「できました! その晩連れて帰って、スタジオの鉢植えに留めて、すぐに産卵するかと思ったけど、意外にそうでもなくて。まあオオカマキリにとっては激動の1日だったわけですから(笑)」
ベランダ昆虫園

※いつ、羽化や孵化、そして脱皮をするのかなど、なかなか予測できない昆虫撮影で楽しい瞬間というのは、どんなときなんでしょうか?
「それは2つあります。1つはそれこそ自分が思い描いていた通りの絵を撮れた場合、つまり目の前でまさに待機中にことが始まった場合というのは1つそうですね。
あともう1つは思い通りっていうのとは全く真逆の、思いがけない出会いがあったという時ですね。それは野外で思いがけない虫との出会いが思いがけない形であって、目の前で面白い行動を見せてくれた時なんていうのは、とても嬉しい瞬間ですね。こういうのは後からじわじわ嬉しさが来るタイプなんですけど」
●森上さんはご自宅にベランダ昆虫園があるということですけれども、それはどういったものなんですか?
「 趣味的に飼っているわけではなくて、スタジオ撮影のためのバックヤードという位置付けなんです。例えば水生昆虫、水に棲む虫がいますね。ゲンゴロウとかそうした虫というのは、野外ではカメラを水に沈めて撮るわけにはいかないので、結局水槽で撮るしかないんですね。
そうするとスタジオには撮影用の水槽があるんですけれども、その水槽で撮る虫を普段飼っておくバックヤードというのが、そのベランダの昆虫園なんです。同じ水槽にタガメが入ったりゲンゴロウが入ったりすることがありますけれども、そういういろんな虫をベランダで生かしているというのがベランダ昆虫園ですね」

●今、何種類ぐらい飼っているんですか?
「おそらく15〜16種類ぐらいいると思いますね」
●え〜!? そうなんですね。その昆虫の世話もしているんですよね?
「そうです、毎日結構な時間がかかりますね。1時間ぐらいは虫の世話で時間を取られます」
●ちなみにどんな昆虫がいるんですか?
「今は水生昆虫ではタガメ、タイコウチ、それからゲンゴロウの仲間が4種類くらいいまして、後は水生昆虫ではありませんけれども、カブトムシ、クワガタムシもやはり継続して飼っていて、それはやっぱり写真の需要が多いからなんですね。毎年新作を撮っておかないと、例えば去年使った写真と同じものは同じ雑誌には出せないっていうようなことがありまして、それでカブトムシ、クワガタムシも結構たくさん飼っています」

虫の感情を撮る!?
※森上さんの新しい本『オオカマキリと同伴出勤〜昆虫カメラマン、虫に恋して東奔西走』に載っている昆虫写真は、どれも表情豊かに見えるんです。何か心掛けていることがあるんでしょうか?
「そう言っていただけると嬉しいですね。それは特に気をつけて撮っていることなので。
昆虫というのは外骨格という体の構造をしていまして、要するに身体の外側に骨があるのと同じですから、表情を作ることができないんですね。要するに柔らかくないので。
そこで表情を感じていただけるというのは、言わばお面をした子ども、お面をしているから表情は分からないんだけれども、手足で何かアクションをとることで、お面の向こう側でどんな表情してるのかっていうことがある程度分かると思うんです。やはり昆虫の顔以外の、手足がどんな形をとってるかというポーズで、ある程度その表情というものを感じていただけるように努めて撮っているつもりなんです」
●へ〜! でも昆虫相手となるとなかなかお面を被った子どもと同じってわけにはいかないですよね?
「でもそこに僕はほぼ同じという認識があって、それは結局、昆虫カメラマンの仕事というのは、大人向けの本より児童書で使われることが多いんです。
そうすると、子どもというのはやはり虫に対して、自分と違う生き物というよりはかなり擬人化して捉えていて、自分との共通した感情とか表情を持つ生き物というような感じで捉えることが多いので、擬人化して見るであろう子ども達に、実際に喜びとか悲しみとか怒りとか、虫の感情を感じてもらえるような撮りかたを、努めてそうしているっていうところがありますね」
●へ〜そうだったんですね! 森上さんが一番好きな昆虫って言うと何になるんですか?
「はい、好きな虫はたくさんあるんですけども、そう聞かれることが多いので、一応ノコギリクワガタと。これは実際、嘘ではなくて、たくさん好きな虫が何種類かいる中で、無理に1位を決めるとノコギリクワガタかなという感じですね!」
●どうしてですか?
「それはね、かっこいいから!」
●そうなんですか〜(笑)
「非常に単純な理由なんですけれども(笑)、姿・形がかっこいいっていう、フォルムのかっこよさだけではなくて、クワガタムシって黒いものが多いんですけれども、ノコギリクワガタはワインレッドの体の色をしているんですよ。この美しい体っていうのがノコギリクワガタが他のクワガタムシより、ちょっと好きだなという理由だと思いますね」

昆虫はチャンピオン!?
※最後に・・・長年、昆虫の撮影を続けていて、昆虫からどんなことを感じますか?
「もともと鳥とか魚も含めて、生き物は何でも好きだったんですけれども、被写体として見た時にやっぱり昆虫が一番だなという感じです。他の生き物に興味が広がっていくタイプの人もいるんですけれども、僕の場合はその昆虫愛というものに収れんしてきたという感じで、どんどんその虫の魅力の奥深さに引き込まれてきたという感じがあります」
●その魅力ってのは何ですか?
「やはり虫の場合は多様性ですね。足が6本とか羽が4枚という、割と小学校の理科的な知識ですけれども、そういった昆虫の体の構造を決定づける制約の中でも、ここまでデザイン的に遊べるのかというような。
鳥とか魚というのは、見れば鳥であったり魚であったりということが、ある程度分かるレベルの多様性だと思うんですけれども、昆虫の場合、本当にこれ生き物なの? っていう、生き物かどうかすら見て分からないというような形の多様性があって、そこが昆虫の一番の魅力だと思いますね」

●本の中に「時として下から見上げるようなかっこいい存在だ」って書いていましたけれども、本当に崇拝しているような感じですよね(笑)
「はい、そう思います(笑)」
●ウルトラマンのような存在だとも書かれていましたけれども、とにかくかっこいいんだ! っていう思いがすごく伝わってきました。未だにかっこいいなって思われてますか?
「そうですね。だからよく虫って可愛いって目線で見る人もいて、どの虫が一番可愛いですか? っていう質問が非常に困るんですけども。可愛いと思ったことはなくて(笑)、それこそウルトラマンを可愛いとは言わないじゃないですか。ですから虫に対してリスペクトに近い感情もあって。
非常にこれは大雑把な分類ですけれども、背骨のある脊椎動物と背骨のない無脊椎動物という2つの生き物に分けると、人間がその脊椎動物という進化のチャンピオンにいるとすると、昆虫は無脊椎動物というもう1つのリーグのチャンピオンという感じがあって。
ですので、僕としてはセ・リーグのチャンピオン・チームが、パ・リーグのチャンピオン・チームを見てるような、そういった感じで昆虫という存在に一目置いてるという、そういう感じが昆虫を見るスタンスと近いかもしれないですね!」
INFORMATION
『オオカマキリと同伴出勤~昆虫カメラマン、虫に恋して東奔西走』
文章がメインの自伝的エッセイ。ご本人曰く、サラリーマンとの兼業写真家の、毎日のドタバタ劇ということですが、昆虫との生活がリアルに描かれていてとても面白いですよ! そして掲載されている昆虫の写真が生き生きとしているので、昆虫の表情にも注目しながらぜひ読んでください。詳しくは、築地書館のサイトをご覧ください。
◎築地書館HP:
http://www.tsukiji-shokan.co.jp/mokuroku/ISBN978-4-8067-1604-4.html
森上さんの活動についてはぜひオフィシャルブログを見てください。
◎森上信夫さんのHP:http://moriuenobuo.blog.fc2.com/