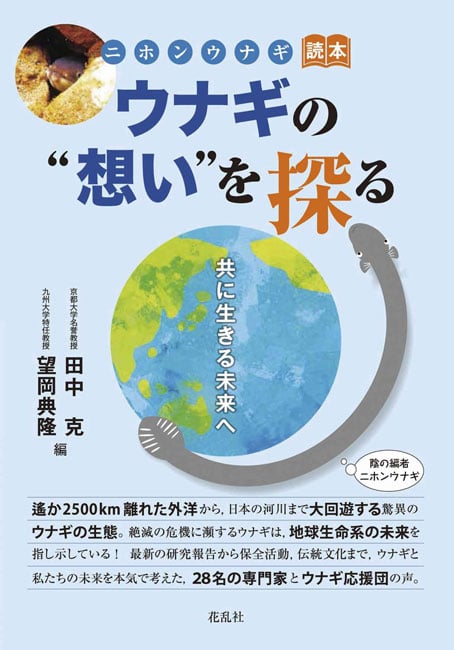2025/2/16 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、植物観察家の「鈴木 純(すずき・じゅん)」さんです。
鈴木さんは1986年、東京都生まれ。親御さんの影響もあって、子供の頃から野山が大好きだったそうです。そして東京農業大学で造園学を学び、その後、青年海外協力隊に参加し、中国で砂漠の緑化活動を行ない、帰国後、国内外のフィールドを巡り、植物への造詣を深めます。
そんな鈴木さんは、友達に植物の面白さを伝えたいと思い、気軽に集まれる街中での観察会を始めたそうです。そして2018年から「まちの植物はともだち」というテーマでフリーの植物ガイドとして、街中での植物観察会を実施。また、植物生態写真家としても活躍されています。
鈴木さんの新しい本が『冬芽ファイル帳〜かわいくて おもしろい 冬の植物たち』ということで、きょうは、暖かくなる春をじ〜っと待っている「冬芽(ふゆめ)」に注目! よ〜く見ると可愛くて個性的な冬芽の観察方法や楽しみ方などうかがいます。
☆写真:鈴木 純 出典:「冬芽ファイル帳」小学館

冬芽は赤ちゃん!?
※鈴木さんが「冬芽」をテーマにした本を出そうと思ったのは、どうしてなんですか?
「これは、”冬芽”っていう言葉は聞いたことがある人は、それなりにいると思うのと、なんとなく顔っぽいものとか、なんかそういうイメージ持っている人もいるような気はするんですが、冬芽を実際にどう楽しめばいいかみたいな本は、そういえばないなって、ふと気づきまして・・・。なので、ないから僕なりに紹介してみたいなと思って作ったというところですね」
●観察も簡単そうですよね。
「そう、それがいちばんポイントかなと思っています。そもそも冬に植物を見るっていうイメージがない中で、実は冬の植物観察がたぶん1年の中でいちばん簡単っていうことがあるんですよ。なんでかっていうと、ただただ枝の先端を見るだけなんですよね。極めてシンプルな観察ですね、冬芽は(笑)」
●初歩的なことなんですけれども、改めて「冬芽」っていうのは何なのかご説明いただけますか?
「冬芽は、ちゃんと定義していくと難しいんですけど、簡単にいうと冬に芽が休眠している状態を冬芽と呼ぶと捉えるのがいちばん分かりやすくて・・・。で、芽は要するに葉っぱとか花のもと、赤ちゃんみたいなものと捉えていただければいいのかなと思うんですね。葉っぱとか花の赤ちゃんが、冬に出てきてしまったら、寒さとか乾燥ですぐダメになっちゃうんですね。
なので、冬の間はまだ芽の中で待っていてもらいたいわけなんです。その時に休眠っていう状態になって冬をやり過ごすわけですね。で、春になっていい季節になったら、葉っぱとか花をパッと出す状況に姿が変わるわけです。冬の間、待機している状態の芽を冬芽という、そういうところをおさえればいいかなと思います」
●秋に葉っぱを落とす落葉樹だけが、冬芽をつけるんですよね?
「そのイメージがあるんですけど、実は葉っぱを落とすとか落とさないっていうのは関係なくて、冬に葉っぱを落とさない常緑樹でも冬芽は実はついているんです。ただ、葉っぱがついていると枝先が見えにくいんですよ。なので、常緑樹には冬芽がないって思いがちというだけの話で、別に常緑樹だろうが落葉樹だろうが冬芽はあるという感じです」

冬芽にキャッチコピー!?
●掲載しているそれぞれの冬芽にキャッチコピーがつけられているのが、すごく面白いなと思いました。例えば「今日も決まった!アフロヘア」とか、「頭抱えて、はや3ヶ月」とか、「枝先のアルパカ、休憩中」など、本当にその冬芽の特徴を捉えていて素晴らしいなと思ったんですけど、これは全部、鈴木さんが考えたんですか?
「そうですね。一応、原案は私が考えまして、これを編集者さんに投げるわけです。なので毎回毎回、大喜利みたいな感じで、これで編集者さんを笑わせてやろうという気持ちで考えていました(笑)」

●そうなんですね。いろんなものに例えると面白いですよね。
「そうですね。それがたぶん冬芽観察のいちばん簡単な観察方法で、名前がわかるのはやっぱりいいんですよ。樹木の名前がわかるのはいいんですけど、植物観察において名前を調べるということが、まず第一歩目のハードルになっちゃう人って結構多いんですよ。
だけど、冬芽の場合は見た目がユニークなので、名前がわからなくても楽しめちゃうんですね。で、自分でキャッチコピーをつけちゃえば、それでOKなので、そういう意味も込めて、全部にキャッチコピーをつけてみたということなんです(笑)」
●冬芽の写真をよーく見ると、本当に人の顔に見えるのがすごく不思議です。目とか口に見えるあの点のようなもの、あれは何なんですか?
「ありがとうございます。そこをちゃんと説明しないといけないですよね。実は冬芽っていうと、顔のように見える写真がよく紹介されるんですが、この顔は・・・顔といってもパーツで考えると、頭の、髪の毛とか帽子の部分と、それから顔の輪郭、あの目とか口がついている部分と、2パーツに分けられるんです。そのうち冬芽って呼んでいるのは、帽子とか髪の毛の部分のことで、顔の部分は実は冬芽ではないんですね。

これは”葉痕(葉痕)”といって、葉っぱが取れたあとに残る痕跡、葉っぱがついていた痕跡です。だから顔の輪郭自体は葉っぱの付け根の形ですね。で、その中にある点々は、葉っぱがついていた時に、葉っぱと枝の間を水分とか養分が通っていた、その通り道みたいな管があるんですけど、葉っぱが取れたあとにその管が名残として枝のほうに残るんですよ。
なので、目とか口の点々は、水分とか養分の通り道だった痕跡だと思っていただければってことですね」
●冬芽の大きさって木によってそれぞれ違うと思うんですけど、大体どれくらいなんですか?
「これが、ちっちゃいもので2ミリぐらい、2ミリって大変ですよね(笑)。すごく小さいです。で、大きいものでも2センチ程度かな、中には5センチぐらいの、もっと大きいものもあるんですけど、そういうのは稀なので、だいたい2ミリから2〜3センチっていうところだと思いますね」
(編集部注:冬芽の観察にはルーペがあったほうがいいとのことです)
ウロコ状の冬芽の正体
※『冬芽ファイル帳』に、ウロコのようなものに覆われた冬芽の写真もありました。あのウロコ状のものはなんですか?

「これが冬芽の結構大事なポイントで、冬芽は見た目で可愛いとか面白いとかで楽しめばいいっていうのがひとつなんですけど、もうひとつは冬芽が、要するに冬の間、春が来るのを待っている状態なので、寒さとか乾燥から身を守るための何かしらの仕組みがあるわけなんですよ。
その冬芽の周りにウロコがあるのは、そのウロコの中に芽が隠されているんですね。赤ちゃんの葉っぱとか花を隠しているわけです。それがそのまま枝先に芽の状態でついていたら、寒さとか乾燥にやられてダメになっちゃうので、その周りにウロコをくっつけて中身を守っているような器官っていうものになります。それがウロコですね」
●冬芽によっては毛が生えたようなものもありましたよね?
「そうそう、そのウロコにもいろいろあって、ツルツルなウロコで、しかも何十枚も、20枚とか30枚とかいっぱい重ねて、中身を守っているのもあれば、ウロコ自体の枚数は少ないんだけど、ウロコに毛が生えているってこともあるんですよ。そうすると毛は単純にあればあるほど、イメージ通りだと思いますけど、寒さとか乾燥対策になるので、それもやっぱり冬対策になっていると思います」

●中を守るっていうことですけど、その冬芽の中はどうなっているんですか?
「冬芽の中は基本的には3パターンって思うといいかなと思うんですね。中に花だけが入っている冬芽、花の芽って書いて”花芽(かが)”、あるいは葉っぱだけが入っている”葉芽(ようが)”、そして葉っぱと花が両方入っている、混合の芽と書いて”混芽(こんが)”。だから冬芽の中身は何ですかって言われたら、その3パターンです。花が入っているか、葉っぱが入っているか、葉っぱと花の両方入っているかっていう感じになります」
●樹木が冬芽を準備するのっていつ頃になるんですか?
「これは、どこからを冬芽って呼ぶか問題が出てきちゃうんですけど、簡単にいうと芽自体は、春に葉っぱが出てきた時にすでにもうあるんですよ。3月、4月の新緑の時期にすでに芽はある。だけど、ものすごく芽が小さいので、ルーペを使っても見えないんです、基本的には。
それがだんだん大きくなっていって、夏ぐらいになると私たちの目でも見られるぐらいの大きさになってくるんですよ。厳密にいうとその時点は冬芽って呼ばないんです。要するに冬芽は冬に休眠している芽のことをいうので・・・。だから冬芽のもと、みたいなものっていう話になっちゃいますけど、それ自体は夏ぐらいからは観察できるってことですね」
●では、冬じゃなくても観察は一応できることはできるってことなんですね。
「そうです。なので僕は大の冬芽好きなので、実は冬芽観察は夏から始めています。結構楽しいです! 夏の冬芽観察」
冬芽観察のコツを紹介
※この時期は冬芽の観察にいい季節だと思うんですが、観察のコツがあったら、教えてください。
「観察のコツは、とにかく近づくことですね、冬芽は。なぜならものすごく小さいので・・・。私は今回の本でいちばん懸念していることは、写真だと冬芽が大きく見えちゃうんです(笑)
なので、見つけやすいものかなって思っちゃうんですけど、実はものすごくちっちゃいので、枝先への近づき方、普通に考えているくらいの近づき方じゃ見えないので、ほんとに間近・・・目のすぐそばまで枝を近づけないと見えない。それがいちばんコツですかね。小っちゃいんだ! って思って近づいていくこと」

●なるほど~。
「あともうひとつは、要するに小っちゃいと思って近づいていくっていう意味は、そこに本当に(冬芽が)あるかどうかわからないで近づいていくんですよ。可愛い冬芽があるのかな~? ほんとかな~? って思いながら近づいていくんですが、それを信じる! っていうことですね。この枝先に可愛い冬芽があるはずだって、どれくらい信じられるかっていうところが結構大事かなって思いますね(笑)」
●ルーペと鈴木さんの本を持って行けば大丈夫ですね!
「そうですね。ぜひ私の本もお願いします(笑)」
●やっぱりひとつの冬芽でも見る角度によって表情も変わりますよね?
「変わりますね! ぜんぜん違うんですよ。今回の本は見やすい角度で写真を撮っているんですけど、これが違う角度で写真を撮ると、表情が全く変わってくるんですよね・・・なので、そこに冬芽観察していくことの楽しみが、たぶんあると思いますね。見る人によって違うものが見えると思います」
●それも面白いですね~。
「はい! 面白いと思います」

●スマホなどでつい冬芽の写真を撮りたくなっちゃいますね!
「そうなんです! それ、僕はおすすめだなと思いますね。最近スマホのカメラの性能がすごく上がっているので、意外と冬芽は撮れるっぽいんですよね。それでコレクションしていくと楽しいかもしれません」
●この本でもファイリングをすすめていますけれども、上手なファイリングの仕方とかあったらぜひ教えてください。
「僕自分自身でもやっているんですけど、Instagramで集めていくのが結構楽しいかも! っていうのは、一枚一枚の写真を見るのもいいんですけど、Instagramの(自分の)プロフィールのところにいくと、小っちゃい写真がばぁ~って並ぶじゃないですか、スクエアで。あの状態で冬芽がいっぱい並ぶとすごいんですよ(笑)。すごく可愛い状態のプロフィールができあがるので、あそこに集めていくのがいいんじゃないかなって今は思っています」
(編集部注:ほかに観察のコツとして、同じ場所の同じ木を観察するのもいいし、今年はこの樹木の冬芽を観察すると決めたら、街中にある同じ樹木の冬芽を見るのも、おすすめだそうですよ)
※冬芽を観察すると、春になったらどんなふうに芽吹くのか、見たくなりますよね?
「まさにそれがいちばんの効果かもしれないですね。冬の間ってほんとにすることないじゃないですか。ないじゃないですかって、ごめんなさい。これは植物の世界の常識を話しちゃったんですけど(笑)、植物の人たちは冬の間はすることがないんです。っていうのは、とにかく冬は植物が動かないわけなんですよ。休眠しているんでね、そもそも・・・。
だから、休眠している状態をず~っと見ていると、その芽の内側にある葉っぱってどんな形なんだろうな? とか、この花ってどういうのだっけ? とか、どんどん先の季節の想像が自分の中でわいてくるんですよ。そうするとやっぱり春が来ることの楽しみっていうのは、すごくどんどん増していきますね」

●芽吹きを見るのに、おすすめの樹木ってありますか?
「私は“ヤマブキ”が好きで、芽吹きとしては。っていうのは、街中にヤマブキはよく植えられているっていうのと、さっきの冬芽の中身って話でいうと、葉っぱと花が両方セットで入っているんですよね。なので、芽吹きの時に黄色いヤマブキ色の花と緑色の葉っぱが同時に出てくるんですが、まるで踊っているみたいな感じで出てくるんですよ。それが非常に観察しやすいのと可愛いっていう意味でヤマブキ、おすすめです!」
(編集部注:鈴木さんの本に「日本三大美芽(びが)」というのが紹介されていて、その三大美芽には「ネジキ」「コクサギ」そして「ザイフリボク」という樹木の冬芽が選ばれています。鈴木さんがおっしゃるには、どなたが選んだのかは不明だそうです)
植物に励まされる
※冬芽を観察していると、どんなことを感じますか?
「なんかやっぱり生きているんだってことですよね。樹木って葉っぱが落ちた状態で見ると、ほんと寂しいじゃないですか。“枯れ木”っていう表現もあるくらいですから、枯れたように見えちゃうけれども、枝先はしっかり生きているって思うと、なんか・・・僕は冬に限らず植物を見ていると、すごく励まされることが多くて・・・。
冬芽に関しては活動していないように見えるけれども、その内側は活動しているわけですよね。っていうのを見ているとなんかいいですよね。“今自分はちょっと足踏みしているんだけど、自分の中は実は次の熱いものが入っているんだぜ!“みたいな・・・そういう”だよね“っていうのを、樹木を見ながら僕は冬にすごく思っているわけなんです。そういうところが僕はすごく好きですね(笑)。いいなと思います」
●鈴木さんが思う冬芽のいちばんの魅力って何でしょうか?
「あ~やっぱり今言っちゃったことかな(笑)。その内側に答えがあるっていうのが魅力だと思いますね。
春から秋にかけての植物観察ももちろん楽しいんですけど、その時は植物の動きが早いんですよ。芽吹いたと思ったら花が咲いて、花が咲いたと思えば実になって、タネを飛ばしてって感じで、どんどん姿が変わっていっちゃうので、こっちは植物の動きについていくのに必死なんですよね。楽しんですけど、疲れちゃうですね(笑)。
冬だけはものすごくゆっくりやっていい。ゆっくりやっていいんだよっていう余地を与えられるところが、僕はすごく魅力的だと思います」
☆この他の鈴木 純さんのトークもご覧ください。
INFORMATION
鈴木さんの新しい本をぜひご覧ください。それぞれの冬芽の特徴を捉えたキャッチコピーが見事ですよ。例えば「はんなり美人」と「ハートツリー」。「はんなり美人」はナツツバキで、冬芽を覆うウロコの形がまさに着物のえりのように重なっていて、薄い緑を基調とした和風な色合いと形が美しいです。そして「ハートツリー」はニワウルシ、枝にくっきりと綺麗なハートのあとがあります。ぜひ本でお確かめください。

ほかにも街中や野山でもよく見られる樹木の冬芽が、豊富な写真とともに掲載。ひとつの冬芽が見開2ページで紹介されているので、見やすくて使いやすいですよ。冬芽観察の決定版! ぜひチェックしてください。小学館から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎小学館:https://www.shogakukan.co.jp/books/09311578
鈴木さんのオフィシャルサイト「まちの植物はともだち」もぜひご覧ください。
◎まちの植物はともだち:https://beyond-ecophobia.com