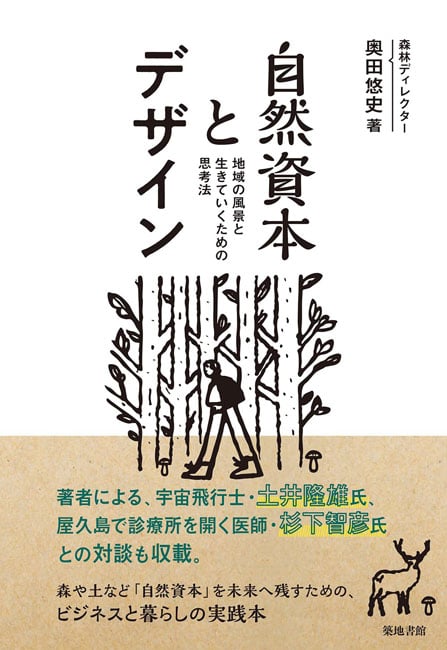2025/4/13 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、一般社団法人「日本フードリカバリー協会」の代表理事「植田全紀(うえだ・まさき)」さんです。
植田さんは地元埼玉でスーパーマーケットを営んでいた頃、大量に捨てられてしまう食品に愕然とし、なんとかしたいという思いから食品ロスの削減に取り組むことにしたそうです。
2022年 7月に設立された日本フードリカバリー協会は、効果的に食品ロスを削減するためには、生産から加工・流通、そして販売のそれぞれフェーズで食品ロスが発生している現状を踏まえ、すべてのサプライチェーンをつなぎ、情報を共有する必要性を訴えています。
そして、フードリカバリーやアップサイクル、そしてリサイクルをひとつの産業として、食品流通に組み込むことも提案されています。
きょうは「SDGs=持続可能な開発目標」の中から「貧困をなくそう」「飢餓をゼロに」そして「つくる責任 つかう責任」ということで、植田さんに廃棄される食品を活用する活動の一環として取り組んでいる「公共冷蔵庫」のお話などうかがいます。
☆写真協力:日本フードリカバリー協会

外れた食品を「流通に戻す」
※食品ロスの削減に向けた取り組みとして「フードバンク」があります。これは食品企業の製造工程で発生する規格外の食品を引き取り、福祉施設などへ無料で提供する活動で、全国に200以上のフードバンク団体があるそうです。
また「フードドライブ」という、家庭で余っている食品をスーパーや自治体などに持ち寄り、子供食堂や生活困窮者の支援団体などに寄付する活動も、ここ数年、全国で広まりつつあるそうです。
今回は新しい取り組み「フードリカバリー」に注目!
●協会の名前にもなっているフードリカバリーという言葉は、植田さんが考えたんですか?
「そうです。流通から外れた食品を流通に戻すっていうことで、そのまんまフードリカバリーです」
●食品ロスの削減に取り組むようになったのは、どうしてなんですか?
「そもそも15年前くらいからスーパーを経営していて、その途中でSDGsが始まって、食品ロスが社会問題であるっていうことをその時初めて知ったんですね。
自分のやっていることを振り返ってみたら、すごく捨てていたなっていうことに気がついて、スーパーとして社会問題になっていることに何かできないかっていうことで、食品ロスの削減に貢献するスーパーを作ろうと思ったのがきっかけです」
●廃棄品というのは、主にどういったものが多かったんでしょうか?
「いちばん多かったのは、やっぱり野菜ですね」
●野菜の中でも、これが多かったっていうのはありますか?
「基本的に市場に返品するものが大きなロスっていうか・・・にんじんの葉っぱの中に、ひとつふたつ腐ってました、みたいなものが入っていると、やっぱり臭いがついちゃうみたいなところがあるので、売り物にできないんですね。だから市場に返品するんですけど、でもそれは市場に戻されても困るから捨てといて、みたいになるので、やっぱりそういう印象が強いですよね」
(編集部注:植田さんはスーパーを経営されていた時に、流通に戻す試みとして、賞味期限が近いものや、規格外のものを安い値段で売る取り組みを行なっていたそうです)
寄付につなげる「公共冷蔵庫」
※協会として、現在どんなことに取り組んでいるのか、教えてください。
「協会としては今、“公共冷蔵庫”を広げていくことをやっています。流通から外れた食品の中でも、どうしても販売できないものを寄付につなげていこうっていうのをやっています」

●へ〜! それはいつ頃からの取り組みなんですか?
「これは(協会を)設立した時からなので、2022年の7月からやっています」
●協会が取り組んでいる公共冷蔵庫、これは「コミュニティフリッジ」と呼ばれています。具体的はどんな仕組みなんでしょうか?
「コミュニティフリッジは、企業さんから食品ロスになるものを集めて、プレハブの中に並べます。そこに児童扶養手当を受給しているような困窮世帯のかたたちに直接取りに来てもらうっていう、無人で食品の受け渡しをする倉庫みたいな感じです」
(編集部注:「コミュニティフリッジ」は「地域(コミュニティ)」と「冷蔵庫(フリッジ)」を組み合わせた造語で、10年ほど前にヨーロッパで始まった取り組みだと言われています。
ヨーロッパでは、地元のスーパーが閉店後に売れ残った食品をコミュニティフリッジに入れ、必要な人が持ち帰る。そうすることで、廃棄される食品が減り、環境にも優しい点が評価され、ヨーロッパのみならず、アメリカでも広まりつつあるとか。
日本ではこの仕組みに、デジタル技術を導入したコミュニティフリッジが2021年に岡山で誕生しています。地元のNPO「北長瀬エリアマネジメント」の代表理事「石原達也」さんが試行錯誤の末、生活に困っている人を支えるシステムを構築。
利用できるのは、事情がある生活困窮者だけで、事前にスマホで登録、倉庫のような入口には鍵がかかり、スマホで鍵を外して入場、持ち帰る食品は記録してもらい、在庫も管理できるシステムになっています。利用者には24時間、いつでも安全に、人目を気にせずに利用できるように配慮したそうです。
この取り組みは全国に徐々に広がりつつあり、日本フードリカバリー協会の植田さんも岡山で誕生したノウハウとシステムを学び、埼玉でコミュニティフリッジを始めたということなんです)

食品業界のルール
※ここで改めて、食品ロスの現状をお伝えしておきましょう。
世界で生産された全食品の内、年間、約40%に当たる25億トンの食品が廃棄されているそうです。
食品ロスはゴミとして廃棄されるため、焼却する際に温室効果ガスである二酸化炭素が大量に放出されます。その量はアメリカとヨーロッパで、自動車が1年間に排出する量のほぼ2倍に相当するとのこと。食品ロスが地球温暖化の要因にもなっているんですね。
ところで、日本の食品ロスの現状はどうなっているのでしょうか。
農林水産省によると、2022年度の年間の食品ロスは472万トンで、その内訳は家庭系が約236万トン、事業系が同じく236万トンとなっています。実は日本の食品ロスは減少傾向にあるんですが、それでもとんでもない量ですよね。
472万トンを、国民ひとり当たりの食品ロスに置き換えると、その量は一日約103グラム、お茶碗一杯分のご飯に近い量とされ、年間に換算すると、ひとり当たり、約38キロの食品を廃棄している計算になるそうです。
事業系の食品ロスの削減に向けては、国の取り組みとして「食品リサイクル法」などの法律が設けられているんですが・・・事業系の食品ロスが多く出てしまうのは、どうしてなんでしょうか?
「食品を扱う企業さんとしても、お客さんのために、というのがいちばんにあるので、どうしても賞味期限ギリギリの醬油を売るわけにはいかないですよね。賞味期限内に使い切れるような形で販売したいっていうのが、スーパーとしてもあるので、14日前には販売期限切れとして売り場から撤去しましょうみたいな形で、企業さんごとにルールを設定しているところだと思うんです」
●そういうルールがあるんですね。企業側も捨てざるを得ないということなんですね?
「そうです。それはもうお客様のためにです」
●ほかにも規格外の野菜が捨てられている現状もありますよね。これまで大きさだったり、形だけの問題で捨てられていたと思うんですけど、それはどうしてなんですか?
「それはですね・・・一回、小っちゃい玉ねぎを買って、料理をしてもらえればわかると思うんですけど・・・めんどくさいですよね」
●あ~小さいと・・・?
「はい、小っちゃい玉ねぎを、皮を何個も何個も(剝かないといけない)、大きいのだったら1個2個で済むのに、とにかくめんどくさい。ジャガイモの皮むき、あの小っちゃいのを剥くんですか? っていう・・・」
●確かに。
「やっぱり使いづらいですよね」
(編集部注:事業系の食品ロスの発生要因としては、いわゆる「3分の1ルール」などの商慣習が挙げられます。
これは食品小売業で「賞味期限の3分の1を超えたものは入荷しない」「3分の2を超えたものは販売しない」といった慣例のことなんですね。
これも植田さんの説明によれば、お客さまのため、ということなんですが、食べられるものが廃棄される現状を変えようと、「3分の1ルール」の見直しなどを検討する取り組みが関係省庁や食品業界で始まっているそうです。
賞味期限が迫っている食品を廃棄せずに寄付につなげたい、という植田さんの思いは、日本人の「もったいない」の心に通じますよね)

自治体が運営するコミュニティフリッジを
※今後、日本フードリカバリー協会として、特に力を入れたい取り組みはなんでしょうか?
「特に力を入れるのは、まずは自治体が運営する公共冷蔵庫、コミュニティフリッジを事例として作ることをまずやっていきたい。今目指しているのは、防災備蓄品の管理みたいな事業を委託されてコミュニティフリッジを運営する、その自治体にとっても損はないよねっていう、今まで使っていたコストを削減できるような形で提案したいなと・・・。
寄付が集まってきたけど、“配り切れなくて捨てちゃいました”っていうのが結構あると思うんですけど、そういう時に余らした物をコミュニティフリッジに入れて、被災した時には誰でも持って行っていいよ、みたいな・・・ちゃんとみんなに無人で配る、そういう時にはコミュニティフリッジが使えるのかなって思っています」
(編集部注:食品ロスを減らすには、私たちひとりひとりの心がけも大事です。
例えば、買い物は必要な分だけ、残さず食べる、注文しすぎないなど、きょうからすぐできることなので、みんなでやっていきましょう)
☆この他のシリーズ「SDGs〜私たちの未来」もご覧ください。
INFORMATION
植田さんが代表を務める「日本フードリカバリー協会」の取り組みに共感されたかたはぜひご支援ください。月額1000円からサポーターになれるそうです。また、寄付用の食品も募集中だそうです。詳しくは、日本フードリカバリー協会のオフィシャルサイトをご覧ください。
☆日本フードリカバリー協会:https://foodrecovery.jp