2025/7/20 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、農学博士の「小林貞夫(さだお)」さんと、お嬢さんの植物画家「奈々(なな)」さんです。
お父さんの小林先生は現在、なんと南米コロンビアで活動されていて、今回はコロンビアの首都ボゴタにいらっしゃる小林先生と、千葉県在住の奈々さんにオンラインでお話をうかがいます。
小林先生は1953年、千葉県生まれ。東京農工大学から東京大学大学院、そして理化学研究所などを経て、2012年にご自分から希望して国際協力機構JICAのシニア・ボランティアとしてコロンビアに赴任。
現在は現地の研究所で客員研究員として活躍。専門は植物病理学。野菜や果物が病気になる原因を探る研究を続け、これまでに10種類以上の新しいウィルスを発見しているそうです。
一方、奈々さんは子供の頃、お父さんから雑草の名前を教えてもらったり、家にたくさんある植物の本の、特に挿絵に惹かれ、多摩美術大学を経て、画家の道へ。現在は絵画教室を主宰するほか、美術講師としても活躍されています。
そんなおふたりは先頃『今日 誰かに話したくなる 野菜・果物学』という本を出されていて、文章はお父さんの小林先生、野菜などの絵は奈々さんが担当されています。
きょうは、野菜や果物の面白いトピックのほか、南米コロンビアの気候風土や人々の気質などうかがいます。

スペインで出版、その一部を日本向けに
※先頃出された本『今日 誰かに話したくなる 野菜・果物学』は、この本はどちらが出そうと、声をかけたんですか?
小林先生「私です。共作というのは2冊目なんですよ!」
●えっ!? 2冊目なんですね!
小林先生「実はコロンビアで、ひとりでも多くの子供が科学に興味を持って勉強することで、貧困から脱出して欲しいという思いで、『野菜と果物の図鑑』、スペイン語で『Verduras y frutas para todos』、日本語訳が『みんなの野菜と果物』という本を10年かけて作りました。
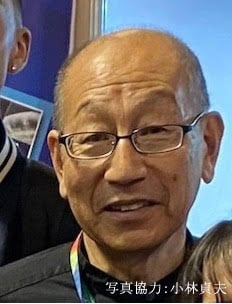
この本は560ページ、写真が2000枚、イラストが50枚あります。この本で奈々さんにイラストのほかに、タネから植物を育ててもらって、花や実の写真を撮ってもらったり、アイデアをもらったので、コロンビア人ふたりと共に共著者になっています。
このスペイン語の本の目的は、貧困からの脱出のために、何としてもコロンビアの図書館や学校に寄付したいと思っていました。そこで日本でクラウドファンディングを計画しておりまして、日本の協力者の人にこのスペイン語の本をちょっと訳して見せたところ、“面白いから日本で出版したら”と勧められました」
(編集部注:小林先生がおっしゃるには「エクスナレッジ」という出版社とご縁があり、出版することになったとのことで、スペイン語の本の一部を日本向けに書き直したそうです)
※奈々さんは、お父さんから本を出そうと言われて、どう思ったんですか?
奈々さん「本は初めてだったんですけれども、父が農薬関係の会社にいた時から、農薬のチラシに使うイラストを描いたりとか・・・。あと高校生ぐらいだったと思いますけれども、割と本格的な植物画的な絵でいろんな雑草の絵を描いて、それが除草剤の宣伝に(使われたり)そんなお仕事させてもらったりしていたので、父の仕事の関係でイラストや植物画を使うってこと自体は初めてではなかったんですね。
ただ、本の形になるっていうのは、私の中でちょっと大きな出来事だったので、本当にできるかな? っていうのと、実現するのかなっていうのも、少し心配ではありました」

●そんな奈々さんは、今回本に添える絵を描くだけではなくて、お父さんの専門用語まじりの文章をわかりやすくする作業も担ったそうですよね。これは大変だったんじゃないですか?
奈々さん「専門用語を簡単に翻訳するというのも、かなり難しい作業ではありましたね。私は植物の専門家ではないんですけれども、たぶん一般の人よりは植物に詳しいほうなので、これくらいは一般の人でもわかるだろうと思って書いた言葉が、編集さんから“もう一段階、説明が必要です”みたいなことがあったりしましたね。
で、専門家から見ても崩しすぎず、でも一般のかたが見て、対象は中学生以上ぐらいのかたを考えていましたので、中学生以上の興味のある子が読んで、ついていけなくならないような、割とわかりやすく平易に書くっていうのを心掛けました。
あとは父の文章が、長くスペイン語圏に暮らしていたので、だいぶ直訳調になっていました(笑)。その直訳調だったり、日本語では省いてもよさそうな、“それは”みたいな(言葉が)ついてしまうような文章もありましたので、そういうものをより読みやすくっていうのと、かつ読み物的に面白くするのを心掛けて作業いたしました」
1本のトマトの苗から2万6000個!?
※本の第一章「驚異の野菜と果物」で、とんでもなく大きかったり、驚くような外見の野菜や果物が紹介されています。例えば、丸っこい「桜島大根」、大きな大根として知られていますが、これはもともと大きかったんですか?

小林先生「もともと大きかったんですけれども、昔の人が例えば、大きな大根を探して、そこからタネを取って育てて、またタネを取って、大きい物を選んでタネを取って、また育てるということをずっとずっと繰り返したんです。ですから、それが大きくなった理由のひとつです」
●そういうことなんですね。同じ大根でも細長い「守口大根」というのがあるんですよね。その長さなんと190cmを超えたものもあったということなんですが、それだけ長くになるにはいろんな条件が必要なんですよね?
小林先生「何事も秘密がありまして、守口大根は、もちろんタネも長くなるような品種でなきゃいけないんですけれども、大根は食べる部分は根っこですね。土がポイントになります。土の中に小石がなくて自由に伸びることができるような細かい砂の土が必要なんです。もちろん生育に適した気候も大事です」
●なるほど。そして本を見て本当に驚いたんですけれども、1本のトマトの苗からなんと2万6000個ものトマトが採れたとありました。信じがたいんですが、これはどういうことなんでしょうか?
小林先生「『つくば科学万博』っていうのが昔、開かれたんですけども、巨大トマトの木が展示されまして、多くの人が驚いていました。このトマトは水耕栽培で育てられていまして、1本の苗から1万3000個の実がなりました。
これを参考にしたのが、この本で取り上げた2万6000個のトマトです。両者の秘密はまず水耕栽培と温室です。水耕栽培をすると収量が増えることが知られています。また温室で栽培することで、トマトの生育に最適な条件にすることができます。それもポイントです」

●なるほど。本当に可能性を感じますね。奈々さん、こんなすごいパワーがトマトにあるなんて知っていましたか?
奈々さん「私も水耕栽培の可能性というものは、知識としてはちょっと知ってはいたんですね。管理と条件を整えることによって、すごく効率的に1本の苗からたくさんトマトを採ることができるっていうのは知ってはいたんですけれども、さすがにそれだけの量が、2万6000個とか・・・採れるっていうのは知らなかったので、父が原稿を送ってきた時に、初めは自分の見間違いかなって、桁がちょっと違うのかなっていうふうに疑ってしまいました」
日本の農家のかたは優秀
※大きな野菜や果物は、もともと大きかったわけではなく、人が品種改良して作ったものが多いのでしょうか?
小林先生「はい、たくさんあります。甘いとか美味しい、たくさん採れるといったような、よい性質を持った品種はすべて人が見つけたり作ったりしたものです。
実はこの本を書くのにたくさんの文献を読みました。その中で日本の農家の人は、昔から鋭い観察眼を持ち、研究熱心な人が多いことに改めて驚きました。今日、私たちが食べているお米はそういう人達のおかげで品種ができています」
●日本はほかの国と比べて、新品種の作物というのは多いほうなんでしょうか?
小林先生「私は世界的に見て(日本は)品種数は多いほうだと思います。正確なデータを持っていないんですけども、日本には四季があります。それが理由のひとつです。四季があるといつでも食べられるわけじゃないので、いつでも食べられるように収穫時期の違う品種が必要なんです。
また日本人は品種へのこだわりがかなり強いです。もっと甘いもの、美味しいもの、という要求が強いんです。ですので、新しい品種が出てきます。それから先ほどもお話しましたけど、日本の農家のかたは優秀ですし、育種学者も大変優れた人が多いのが理由のひとつです」
人と人の距離が近いコロンビア
※ここでちょっと話題を変えて、小林先生がいま暮らしていらっしゃるコロンビアの首都ボゴタのお話をうかがっていきたいと思います。ボゴタでの暮らしはいかがですか?
小林先生「意外と刺激的で面白いです」
●刺激的!? 例えば、食べ物とかって、どういうものをコロンビアではみなさん食べるんでしょうか?
小林先生「食べ物はお米とか肉をよく食べますね。日本で馴染みのないものでは、調理用バナナ、あとキャッサバでしょうか。果物がとても美味しいです。こちらの人はあまり野菜を食べないので、“食べろ食べろ!”と言い続けています」
●ああ~やっぱり大事ですよね! コロンビアの人たちの気質、性格とかってどういう感じなんですか?
小林先生「気質はもちろんラテン系です。ところが意外に真面目で義理人情があります。面白いことに音楽が聴こえると自然に踊り出す人が多いですね。
あと人と人の距離が非常に近いです。朝、挨拶すると、ぎゅっとハグされて顔をくっつけて、“チュッ”って音をたてて・・・。ボゴタの場合は音だけなんですけど、地方に行くと本当に頬にチューされます」
●へえ~すごい!
小林先生「誕生日には、ハグされたまま耳元でお祝いを囁かれますので、素敵な女性だとドキドキしてしまいます。でもさすがに慣れました(笑)」
(編集部注:ちなみにボゴタは標高2600メートルほど。空気が薄いので、私たちが行くと息苦しくなるそうです。朝晩は寒く、日中でも20度くらいだそうですよ)

※奈々さんは、お父さんのいるボゴタに行ったことがあって、ビルが立ち並ぶ大都会だったことにびっくりされたとのこと。ほかにも奈々さんはコロンビアに行って、こんなことを感じたそうです。
奈々さん「アンデス山脈の少し山のほうに遊びに行った時、朝もやの中から現れた村人みたいな人が、インディオ系のかたでポンチョを着ていました。そういうかたが本当に普通に生活しているのを見た時に、地理の教科書か資料集か何かで見たアンデスの暮らしそのものに出会って・・・。
それからその辺りの空が・・・すごく抜けるような青空を見た時に、本当に写真で見たようなアンデスのイメージというか、その中に自分が立っているっていうのを感じて、本当にこんな所があって、今(私は)ここにいるんだなということをすごく感じました。
でもコロンビアに行って、いちばん驚いたのは、とても個人的な驚きなんですけれども、クリスマスツリーが広場に飾ってあって、その横の花壇に紫陽花の青い花が咲いていたのを観た時ですね。
紫陽花は当然、日本では梅雨の頃の花ですが、コロンビアは日本のような四季がないので、特にボゴタは一年中、日本の秋のような気候です。なので、秋が長かったり、花と実が同時に見られたりする話は聞いていたんですけれども、さすがにクリスマスツリーの横の紫陽花を見た時には、今自分がどこにいるのかっていうのと、今の季節は何だっけ? っていうのがすごく揺らぐような感じがして・・・。
同時に自分がいかに日本の歳時記というか、日本の四季の変化と共に生活してきたかとか、それを基準に季節や時間というものを認識していたか、ということを気づかされて・・・。
四季があるというのは当たり前ではないということと、最近は日本でも夏が長くなり過ぎているような気がするんですけれども、ある程度きちんと4つに分かれた四季があるというのは当たり前ではないですし、改めて四季のあるありがたみを感じる出来事でもありました」
スイカは果物、トマトは野菜
※初歩的な質問で恐縮なんですが、子供向けのなぞなぞで「スイカは果物? それとも野菜?」なんていうのがあったりします。スイカは野菜、ですよね?
小林先生「確かに植物として見たらスイカはウリ科なので、キュウリやカボチャと同じ科です。なので、野菜なんですけども、果物として食べますので果物になります」
●そういうことなんですね! ちなみにトマトは野菜ですよね?
小林先生「トマトは野菜として食べますので野菜になります」
●なるほど~。果物と野菜の違いって何なんでしょうか?
小林先生「すごくいい質問ですね。果物は果実を食べるもので、甘くてデザートとして食べるものを言います。多くはリンゴやミカンのように木になっているものです。一方、野菜は多くは木ではなく草で、食べる部分は果実もありますが、葉、茎、花、タネを採って調理して食事として食べます。これが違いです。
デザートとして食べるか、食事として食べるかですね。ですから日本で一般的な例えばバナナですが、調理用バナナは野菜になってしまいますけれども、一般的なバナナはもちろん果物です」
●そういうことなんですね! 私たち人間がどう食べるか、によって変わってくるんですね?
小林先生「はい、そうです」
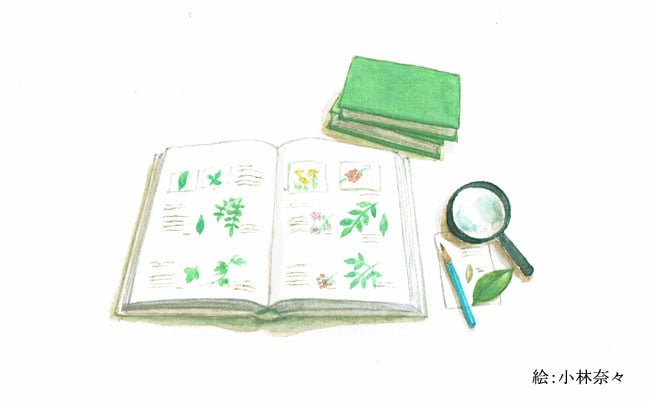
※では最後に、この本『今日 誰かに話したくなる 野菜・果物学』からどんなことを感じ取ってくれたら、著者としては嬉しいですか?
小林先生「植物が好きな人はもちろん、あまり関心ない人でもちょっと興味を持ってもらって、“え~っ!? そうなんだ! 面白いな”と思っていただけたら、すごく嬉しいです」
●ありがとうございます。奈々さんはいかがですか?
奈々さん「この本は、章ごとにかなり内容が違っていて、そこがちょっと編集さんを悩ませた点でもあったりはしたんですけれども、私は植物モチーフのコラージュみたいな本になったと感じています。
どの章からでもご興味のあるところから読み始めて、“植物のこと知らなかったけど、こんなことだったんだ“とか、”植物にはこんな力があったの“とか、あとはイラストも楽しんでいただけたらいいなと思っています」
INFORMATION
私たちの身近にある野菜や果物が、こんなに不思議で奥深いものなのか、発見の連続だと思います。美しい絵と写真がたくさんに載っているので、見ているだけで楽しくなりますし、なにより解説がわかりやすいので、すっと入ってきますよ。おすすめです。
エクスナレッジから絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎エクスナレッジ:https://www.xknowledge.co.jp/book/9784767834214
小林奈々さんのオフィシャルサイトもぜひ見てくださいね。
◎https://nana-kobayashi.jimdoweb.com








