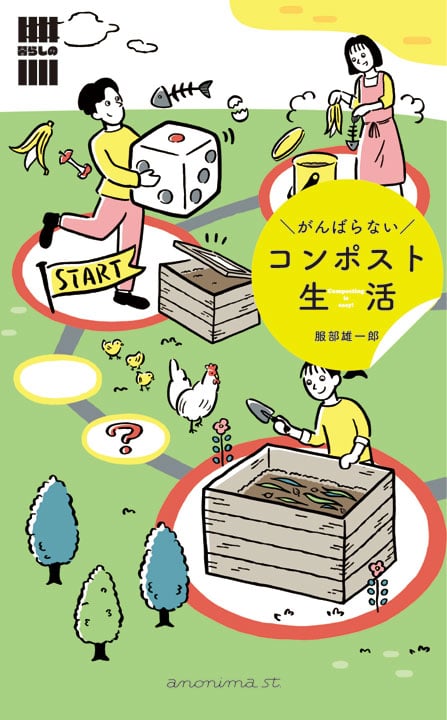2025/7/13 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、公益財団法人「日本財団」の常務理事「海野光行(うんの・みつゆき)」さんです。
海野さんは「海と日本プロジェクト」に長年取り組んでいらっしゃる海の専門家なんです。
今回は「海と日本プロジェクト」の一環として進めている「海のそなえプロジェクト」にフォーカス! 毎年のようにニュースで取り上げられる痛ましい「水の事故」、その実態調査から見えてきた、溺れてしまう意外な原因のほか、水難事故を減らすための取り組みについてうかがいます。

水難事故防止のための新しい「そなえ」
●今週のゲストは、日本財団の常務理事「 海野光行」さんです。海野さん、よろしくお願いします。
「はい、よろしくお願いします」
●現在、日本財団が進めている「海と日本プロジェクト」について、教えていただけますか?
「はい、プロジェクトの説明の前に、難波さんにお聞きしたいことがあるんですけど、難波さんは子供の頃、よく海には行かれましたか?」
●結構、行ってましたね。私が住んでいた家から車で5分ぐらいのところに、御前崎の海が広がっていたので、夏の期間は月1回ぐらいは行っていたと思います。
「そうですか。灯台があって岩場もあって・・・」
●お詳しいですね! そうなんです。
「砂浜もあって、ウミガメがたまに来る場所ですよね?」
●そうです! なんでそんなに(詳しいのですか)?
「私も(出身が)近くなんです!」
●えっ! 本当ですか?
「はい! 藤枝というところなんですけれども・・・」
●ええ~、そうなんですね。
「よく遠足とかで、藤枝の子たちは御前崎に行ったりするんですけどね」
●やっぱり海に行った記憶ってすごく残っていますよね。
「残っていますよね~」

●はい、そうなんですよ~。
「(難波さんは)ネガティヴではなくて、ポジティヴなイメージがしっかりと残っているということなんですね」
●はい、そうなんです!
「難波さんは、小さい頃から海と関わりがあったということで、いいことなんですけれども、今の子供たちは“海離れ”、要はなかなか海に行く機会もなくて、どんどん海と離れている、そんな状況なんですよね。
特に学校教育の中で臨海学校、林間学校ってありましたよね? 林間学校は山に行くほうで、臨海学校は海の近くへ行くほうなんですが、この臨海学校がどんどんなくなっているんです」
●へえ~、そうなんですね・・・。
「東北の津波の影響などもあって、やっぱり危ないから、ということで、親御さんも敬遠されているということもあります。また、子供たちも学校教育の中でどんどん外れていくというところがあって、ちょっと問題視しているんですけどね。
そういう状況の中でも、海への関心とか好奇心を持ってもらって、なんとか海の問題解決に向けてアクションの輪を、子供たちや大人も含めてどんどん広げようということで行なわれていますのが、この『海と日本プロジェクトになります。
9年間で2千万人ぐらいのかた、日本の人口の5分の1ぐらいのかたがたが参加してくださっているんですね」
●海に行く子供たちが増えてくれたら、嬉しいですよね! これから夏も本番に向かい、海に行く機会が増えてくると思いますけれども、『海と日本プロジェクト』の中には「海のそなえプロジェクト」というのがありますよね? これはどんなプロジェクトですか?
「はい、最近のニュースでもよく出てきまけれども、残念なんですが・・・海や川で毎年、水難事故が起きていますよね。この水難事故の減少を目指して取り組んでいるのがこの『海のそなえプロジェクト』になります。
水難事故を減らすためには、これまでにもいろんな対策が、みなさんのアイディアの中で行なわれてきたんですけれども、残念ながら成果が出ているとは、この(水難事故の)数を見る限りでは言えないというところがあります。
そこでまず、このプロジェクトでは常識を疑って、様々な調査研究をした上で、そこから得られた科学的データとファクト、事実に基づいた水難事故防止の新しいそなえの常識を作ろうということで始まったものになります。これをオールジャパンで取り組んでいるのが、この『海のそなえプロジェクト』になります」
(編集部注:海野さんによると、厚生労働省のデータでは、海や川などで溺れて亡くなった人の数は少しずつ減少していて、年間600人前後だそうです。ただし、海水浴客や釣り人の数は減っているので、海や川に行った人の割合で見ると増えている。つまり水難事故に遭う可能性は、以前より高くなっているとのことです)
溺れた経験のある1000人のヒヤリハット
※海や川で溺れた人の数に違いはありますか?
「昨年の夏の調査によりますと、溺れた人の割合というのは海岸が4割、河川が3割で若干、海のほうが多くなっているという事実がございます。そこに沖合や港、こういった場所を加えて海全体として計算し直しますと、だいたい6割が海で溺れているということになってきます。
河川が3割、残りの1割がプールだとか、あるいは湖や池、ため池とかで亡くなるケースってよくありますけれども、そういう場所になっています」
●へえ~、そういった割合なんですね。海でも川でも気をつけないといけないですよね。
「そうですね」
●溺れるというと、私は泳いでいる時のイメージがあるんですけれども、いったいどんな時に溺れてしまうんでしょうか?
「これも昨年の夏の調査によりますと、若いかたは泳いだり、川遊びで溺れてしまうというケースが多いんですけれども、高齢者のかたは意外なんですけれども、釣りで溺れる事故、これが多いという結果が出ています」
●釣りで・・・?
「今年はゴールデンウィーク中に短期の調査を行なったのですけれども、この調査でも、やはり高齢者の釣りの事故が多いという結果が出ています」
●なるほど~。ちなみに男性と女性ではどちらが多いとかってあるんですか?
「難波さんは、どちらが多いと思いますか?」
●助けに行って亡くなってしまうっていうニュースを聞いたりするので、それは男性なのかなと思いますね。どうなんですかね・・・?
「その通りでございまして、やはり女性よりも男性のかたが、どのくらいかというと、5倍溺れた人数が多いんです」
●えっ! そんなに違うんですね。
「しかも、どの年代を見ても女性よりも男性のほうが、溺れた数が多いという形になっています。で、難波さんもうひとつ質問をしたいんですけど、溺れの事故が発生しやすい時間帯って何時頃だと思いますか? 時間帯です。何時に溺れるか・・・」
●時間帯・・・わかんないですね〜何時だろう・・・波が高くなってきたり激しくなるのって、夕方のイメージがあるので、その時間帯ですかね?
「おっ、さすがです! 午前中よりも午後の発生数が2倍多いんだそうです」
●2倍も!
「その中でも何時かというと、午後4時が最も多くて、次に午後2時。“魔の時間帯”と言うんでしょうかね・・・午後4時と午後2時が多かったですね」
●なるほど。海や川であったり、男性、女性、年代、そして溺れが多く発生する時間帯などを知っていると、やっぱり溺れないように気を付ける意識が高まりますよね。
「そうですね。これだけでも意識が高まってくれるということで、嬉しい限りであるんですけども、ただ溺れの事故を減らすには、もう少し踏み込んでいく必要があるんですね。
これまでは救助されたり、あるいは亡くなるなどの事故にあった溺れのデータは、警察署とか消防署など、いろんなところから集められていたんですけれども、事故にならなかなった、事故未満っていう溺れのデータは、今まで集められていなかったんですね。
このデータを取るために、溺れた経験のある1000人のかたにアンケート調査を行ないまして、いつどんな時にどんな状況で溺れかけたんですか、という事故未満の具体的な要因を集めてみました。
1000人の溺れ経験のデータに基づいて、溺れにつながるものを、私たちは“ヒヤリハット”って呼んでいるんですが、このヒヤリハットを分析・整理、そしてこれまでの調査、報道の調査ですとか、あるいは行政のデータに基づいて、『これで、おぼれた「おぼれ100」』というコンテンツを作ってみました」
これで、おぼれた「おぼれ100」〜浮き輪でおぼれた!?
※『これで、おぼれた「おぼれ100」』について、もう少し詳しく教えていただけますか?
「これは重大事故、重大事故っていうのは、大きな事故の裏側には大体300件ぐらいのヒヤリハットが存在していると言われるんですね。これは“ハインリッヒの法則”なんですけれども、これをちょっと応用したものでございまして、100パターンの溺れの入り口をイラストで可視化したというものになります。
重大事故を未然に防ぐためにヒヤリハットの段階で、対策を意識してもらおうという意図もあるんですが、溺れの入り口を可視化することで、自分も経験があるとか、自分もやってしまうかもしれない、やったことがあるのかもしれないという、気づきや共感を得てもらい、自分事化してもらおうという願いを込めて調査、作ってみたというものでありますね」
●驚いたんですが、溺れのパターンって100もあるんですか?
「100以上あるんですが、数の多かったものを100にまとめてみたというものになります。この100パターンの溺れをそれぞれに“何で溺れたのか?”、それだけじゃしょうがないので、“どうしたらいいのか?”という情報も、実はこの“ヒヤリハット100”の中には入れ込んでいるんですね。
『海のそなえプロジェクト』のホームページやインスタグラムで公開していますので、ぜひリスナーのみなさんも覗いてみていただきたいと思います」
●100パターンって具体的には、どのような溺れがありますか?
「100紹介していると時間がありませんので・・・ひとつ多かった事例としては、意外なんですが、“浮き輪で、おぼれた”というのがあるんですね」
●浮き輪で溺れちゃうんですか?
「はい、1000人のヒヤリハットの調査で多かったものではあるんですけれども、“浮き輪”がひとつのキーワードとして上がってきました。浮き輪で溺れる状況って何か思い付きます?」
●溺れないようにするために浮き輪があると思っていたので、逆にどうやって・・・つかまっていたら溺れないのかと思うんですけど、どういう状況なんですか?
「そうですよね~、普通そうなんですけどね。なんで浮き輪で溺れるかと言いますと、浮き輪を使っていて、気づいたら風や波とか潮に流されて沖まで行ってしまったり、あるいは体に合ってないちょっと小さめの浮き輪を使っていて、沖に出てひっくり返って抜けなくなってしまう・・・それで溺れるケースもあるということなんですね。
浮き輪は浮いているから安心と思っている人もいるかもしれないんですけれども、意外に浮き輪で溺れた人は多くいる、という結果が出ています。浮き輪を使う人はそもそも水に慣れていない、泳げない人も多いですから、こういうことが起こるのかなと思いますね。
浮く物だと浮き輪だけでなく、最近流行りのフラミンゴとかシャチとかマットレスのような大型のフロート、今レンタルとかですごく出ているんですけれども、実はこれも注意が必要なんですね。浮き輪よりも表面積が広いので簡単に風で流されやすいですね。『おぼれ100』の中でも“フロートで、おぼれた”、あるいは“風に流されて、おぼれた”という形で注意を促しているものもあります」
スマホで、おぼれた!? 愛ゆえに、おぼれた!?
※「おぼれ100」の中に「スマホで、おぼれた」というのがあるとお聞きしました。これは、どういうことなんですか?
「スマホを見ている時って注意力が散漫になって、周りの変化に気づきにくいじゃないですか。それで浮き輪を使っている時にスマホを操作・・・海でスマホを操作するって、よほどのかたなんですけれども、そのまま高い波が来たりとかしてバランスを崩してっていう場合もあるようなんですよね。
スマホを落としそうになって、スマホを落としたらもう終わりですからね。だから必死になって(スマホを)拾おうとして、浮き輪からひっくり返って溺れてしまうというヒヤリハットもあるんだそうです」
●そういう状況なんですね~。
「この“スマホで、おぼれた”はイメージしやすかったかどうかはわかりませんが・・・これはどうですかね? “愛ゆえに、おぼれた”、愛ゆえにどうして溺れてしまったのか、想像つきますか? 私がこれを初めて見た時には“恋や愛に溺れる”とかって普通に表現しますから、なんかひっかけで言っているのかなと思いましたけれど、そうではなかったんですね」
●どういうことなんですか?
「実際に海で溺れていたんですけれども、フロートの話って先ほどありましたでしょ。フロートに乗っていると流れやすいんですよと・・・この“愛ゆえに、おぼれた”っていうのは、カップルでフロートに乗っていて溺れに繋がってしまうというケースなんですね。大型フロートにカップルで乗っていると、どうしても彼氏や彼女だけに目がいってしまいます」
●確かに・・・。
「周りが見えないですよね。そうなってくると、どういうことが起きるのか、ということなんですけど、想像がつきますよね」
●あ~(想像)つきました・・・。
「周りの波とか風の変化が見えなくなってしまい、フロートは風に流されやすいので、気づいたら砂浜が遠くに見えて戻れなくなってしまうという、こういうことがあるということなんです。これがもし離岸流なんかに乗ってしまったら、もうアウトですね」
●確かに。この話を知っているか知らないかで全然違いますね。私もきょう海野さんにこの話を聞くまでは、そんなので溺れるかな? っていうふうに思っていた事例もありましたけれども、実際にあったってことですよね?
「そうですね。このほかにも大人が気を取られている隙に、子供が溺れてしまうとか、目を離して溺れたっていうのもあります。
あとは毎年のように起こる事故なんですけれども、溺れている人を助けにいって自分も溺れてしまったり、助けに入り溺れた、正義感で溺れたっていうやつですね。あとは“青春(あおはる)で、おぼれた”・・・」
●あおはる? これは・・・?
「これは青春ですよね」
●あっ! 青春で・・・。
「若者が羽目を外してしまうんですかね。悪ふざけなのかわかりませんけれども、溺れたというのもあります。
海だけじゃなくて川の溺れ事故や、子供に向けたものや親に向けたものなどいろいろあります。『これでおぼれた「おぼれ100」』を見て、溺れの状況や対策を自分事化してもらえるとありがたいなって思いますね。
さらにその先には自分の溺れ体験を共有することによって、社会全体として“備えはみんなで作るんだ”という意識を、『おぼれ100』をきっかけに広げていきたいなって思っています」
●この『おぼれ100』では、自分の体験を投稿することもできるんですか?
「現在はインスタグラムのコメント欄で、みなさんの溺れ体験を募集しています。社会全体で備えを作っていくためにも、みなさんの溺れ体験を共有してほしいなと思っております」
「カヌー・スラロームセンター」で溺れ体験!?
※「海のそなえプロジェクト」では、この夏「そなえ」を体験できるプログラムを実施するんですよね。溺れる体験ができるということなんですが、これはどんなプログラムなんですか?
「こちらは東京2020オリンピックのカヌーの競技会場だった(葛西臨海公園の隣接地にある)“カヌー・スラロームセンター”を活用したプログラムを実施しようと思っています。
人工的に海や川の流れを作り出す装置がありますので、安全に海や川の水に流される感覚を体験できると・・・それを体験すると、どう助けるべきかっていうのも、ある程度わかってくるというのもあります。“サバイバル・スイム”という対処行動ですね。

もし溺れてしまった時にはどうするのか? こういったことを体験しながら、備えを学ぶことができる場所になっております。学校のプールでは得られない溺れのリアルな体験を通じて、命を守る判断力ですとか行動力を身につけるプログラムを用意しています」
●そのほかにも何か取り組みはありますか?
「もうひとつございまして、この夏、神奈川県の三浦海岸の海水浴場、“三浦FUN BEACH”というところがあるんですけれども、海開きから8月16日までの毎週土曜日に、様々なフローティング・アイテムを試着できる『海のそなえハウス』を設置します。

フローティング・アイテムっていうと、ライフ・ジャケットですとか、あるいはラッシュガードでも浮くラッシュガードがあったりだとか、ガジェットとして腕時計のように付けたものが、溺れそうになるとパッと浮き輪が出てくるようなものがあったりとか、そういう物を実際に体験していただこうというものであります。
海の楽しみ方や個人の能力、あとは価値観、好みがありますので、色とかいろんな物も準備しています。それぞれに応じたフローティング・アイテムを多数準備していますので、実際に着たり付けたりして楽しんでいただくことができます」

●購入ではなく、試着できる場所という感じなんですね?
「そうですね。試着をして体験してもらって、“これがよかった”とか“こういう部分が少し着づらかったよ”という意見を聴取して、次の開発に活かしていこうと、そういうものになっています」
●そういう施設があるだけで、そこに来ているみなさんの意識がグッと上がりますよね。
「そうですね。そういうところを入り口にして、海の備えをそれぞれ感じてもらえたら嬉しいなと思いますね」

●最後に水の事故を減らすために、多くのかたに心掛けて欲しいこと、リスナーさんへのメッセージをお願いします。
「ありがとうございます。きょうは“そなえ”をテーマにお話をしましたが、事故を防ぐ正しい知識と技能を身につけていれば、海や川という場所は決して怖いところではないんですね。
すべての経験が新しい学びにつながる『海は学びの宝庫』だと思います。ぜひ、事前にしっかり備えることで、今年の夏も海や川を思いっきり楽しんで欲しいと思っています」
☆この他の海野光行さんのトークもご覧下さい。
INFORMATION
<「日本財団:海のそなえプロジェクト」情報>
溺れの実態調査から見えてきた意外な溺れの原因、これをまず知ることが大事ですよね。そして、実際に溺れた経験のある1000人のヒヤリハットをもとにした「これで、おぼれた『おぼれ100』」、これもぜひチェックして、大切な家族や友人が水の事故に遭わないようにしていただければと思います。ぜひお友達にも教えてあげてください。

葛西臨海公園の隣接地にある「カヌー・スラロームセンター」を活用した体験プログラムや三浦FUN BEACHに設置された「海のそなえハウス」など、詳しくは「海のそなえプロジェクト」のオフィシャルサイトをご覧ください。
◎「海のそなえプロジェクト」:https://uminosonae.uminohi.jp
◎「これで、おぼれた『おぼれ100』」Instagram:https://www.instagram.com/obore100/
<「海の日」イベント情報>
今年は7月21日が「海の日」、そして祝日として制定されて30回目の節目の年です。
「海の日」は「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日」、ということで、当日の7月21日に東京国際クルーズターミナルで記念イベントが開催されます。
科学系人気YouTuberのサイエンスライヴや、日本財団の海野光行さんほかをお迎えした、海に関するトークショーのほか、海上自衛隊や海上保安庁の音楽隊によるコンサートなども予定されています。
◎「海の日特設サイト」:
https://c2sea.go.jp/uminohi2025/