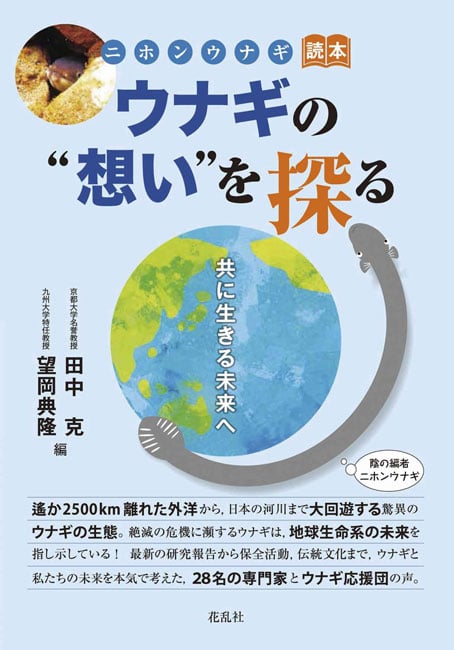2024/9/1 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. BORN TO RUN / BRUCE SPRINGSTEEN
M2. MONEY, MONEY, MONEY / ABBA
M3. YOU’RE MY BEST FRIEND / QUEEN
M4. LUCKY FELLOW / LEROY HUTSON
M5. MR.PERFECTLY FINE / TAYLOR SWIFT
M6. CLIMB EV’RY MOUNTAIN / PEGGY WOOD
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2024/8/25 UP!
◎中村姿乃(アロマセラピスト)
『私たちの心や体を元気に! 「植物療法」の可能性』(2024.8.25)
◎一日一種(イラストレーター/「いきものデザイン研究所」主宰)
『知っておきたい! 自然や生き物に関する法律やマナー』(2024.8.18)
◎鎌田悠介(自転車旅のエキスパート)
『生き方はいろいろ〜自転車一人旅 アイスランド編』(2024.8.11)
◎木村啓嗣(ヨットで単独 無寄港 無補給による世界一周の日本人最年少記録を樹立)
『木村啓嗣の「231日52,000キロの大冒険!」〜ヨットによる単独 無寄港 無補給 世界一周!』(2024.8.4)
2024/8/25 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、アロマセラピストの「中村姿乃(なかむら・しの)」さんです。
中村さんは子供の頃から植物好き。自宅の近くに大きな公園があり、お母さんやおばあちゃんとよく出かけ、植物の香りを嗅いだり、落ち葉を拾ったり、また植物図鑑も好きな、そんな子供だったそうです。
大学卒業後は、一般企業に就職。そんな中、30歳を過ぎた頃に、蚊に刺されると、熱が出たりするようになり、蚊の唾液によるアレルギーが判明。常に虫除けスプレーを持ち歩く生活になってしまったそうです。そんな頃、精油を使って自分で虫除けスプレーを作れることに気づき、会社勤めをしながら、週末、アロマの学校に通うようになったそうです。そしてアロマの素晴らしさを人に伝えたいと思うようになり、徐々にアロマにシフトしていったそうですよ。
そしてフランス・リヨンの専門学校でアロマテラピーなどの植物療法を学び、現在は都内でアロマテラピースクール&サロンを運営していらっしゃいます。また、先頃、新しい本『歴史や物語から楽しむ あたらしい植物療法の教科書』を出されました。
きょうはそんな中村さんに、植物療法の基礎知識のほか、香りを権力の象徴として使ったクレオパトラの逸話、そして音楽や絵本に登場するハーブのお話などうかがいます。
☆写真協力:関 純一

学びは「リヨン植物療法専門学校」
※専門の知識はフランスのリヨン植物療法専門学校というところで学んだそうですね?
「そうですね。最初は会社員時代は東京の学校でアロマの勉強して、日本のアロマの資格はいくつか取ったんですね。
会社員時代に何をしていたかというと結構面白い仕事をしていて、ジュエリーの仕事だったんですけれども、そのジュエリーのもとになる原石を売っている人たちに、世界中に行って取材をするっていうような仕事をしていたんです。
なので、アロマテラピーを始めた時も、エッセンシャルオイルのボトルの中に入る前の、植物を育てている人に取材してみたいって思うようになって、アロマテラピー発祥の地がフランスだったので、2014年ぐらいから定期的にフランスに行って農場とか精油メーカーを取材するようになったんですね。
で、そこのかたがたにお会いしたりすると、やっぱりフランスの植物学校ってすごくいいよとか楽しいよっていう話をうかがって、リヨンの植物学校に行き着いて勉強したいなっていうふうになりました」
●フランスにいろんな学校がある中で、そのリヨン植物療法専門学校を選んだのは何か理由があったんですか?
「そこはアロマテラピーだけじゃなくって、ハーブとかフラワーエッセンスとか、ペットのために植物を使うこととか、総合的に植物療法を教えている学校で、かなり規模も大きかったのと、私がお世話になっている農場のかたがたの何人かが、そこの学校の卒業生だったりとか講師をされていたりしたこともあったので、ここだったらいいかもっていうふうに思いました」
(編集部注:リヨンの専門学校は、実はコロナのパンデミックで、リアルな授業ができなくなり、それまでやっていなかったオンライン授業をスタート。中村さんはアロマテラピーの学科を1年間受講。授業はもちろんフランス語で、辞書を片手に格闘する日々が続いたそうです。それでも、日本で勉強するアロマテラピーの内容とは異なり、すごく面白かったそうですよ)

※どんな違いがあったんですか?
「例えば日本だと、『腕の痛みにおすすめの精油は何ですか? 理由とともに書きなさい』みたいな、そういう問題が多いと思うんですけど、なんかフランスだからか、すごく物語性があって、『62歳のモーリスさんは絵画をやっていて手を痛めてしまいました。彼はこの秋には個展を開くので、また絵画を再開したいと思っているんですが、お医者様に行ってもお薬では治らず困っています。あなただったらどんな精油をどんなふうに使うように、彼に総合的にアドバイスしますか』とかそんな感じで(笑)、情景が浮かぶようなレッスンとか・・・。
あとは植物について書かれたポエムが載っていたりとか、学習だけじゃなく感性も磨かれるようなレッスンで、それがすごく楽しかったですね」
●好きなことだからワクワクしそうですよね。
「本当にそうですね。フランス語つらいっていう思いもありつつ、やっぱり内容がわかると本当に楽しいっていうのがありました。終わったあとは本当に益々アロマとか植物のことが好きになれたかなっていう感じです」
まるごと一冊、植物療法

※ではここからは、中村さんの新しい本『歴史や物語から楽しむ あたらしい植物療法の教科書』をもとにお話をうかがっていきます。
この本は装丁が百科事典のように立派で、内容は植物療法の基礎知識から歴史、人物、物語など幅広く、読み応えがある、まさに教科書のような本なんです。中村さんはこの本を2年ほどかけて書き上げたそうですが、参考文献をたくさん読み込む日々でもあったそうですよ。
●こんな本にしたいというコンセプトのようなものはありましたか?
「この本のコンセプトというか、いちばんしたかったことがアロマテラピー、ハーブ療法、フラワーエッセンスとか、植物療法の中にもいくつかのジャンルがあるんですけれども、そのジャンルを敢えて分断しないで、横断的に見ていくっていうのがまずひとつのコンセプトだったんですね。
かつ、ハウトゥー本みたいな感じではなくて、植物療法全般の歴史とかそれに関わってきた人たちとか物語とか、背景の部分も楽しく読んでいけるっていうのがコンセプトでしたね。
私ももともとそういう本が欲しいなって思っていたところもあったので、それができるっていうのはすごく嬉しかったんですけど、結構プレッシャーもありました(笑)」
●勉強しながら作り上げていったっていう感じなんですね。
「そうですね。終わった今となっても本当にたくさんの学びがあったなっていうふうに思っています」
●すごく分厚くて難しそうな本かなって一見思ったんですけど、読み始めるとスラスラっと読めて楽しかったです!
「ありがとうございます! カラーで写真やイラストも入っているので・・・。4つの章に分かれているんですけれども、基本的にはどこから読んでいただいても大丈夫です。植物療法が初めてのかたは、パート1から読んでいただくといいかなと思うんですけれども、どこからでもお好きなところから読み進めて、ちょっとずつ読むっていうのでも全然大丈夫な本にはなっています」

植物療法の基礎知識
※では具体的に、本に載っていることをいくつかうかがっていきます。
まずは「植物療法の基礎知識」ということで、植物療法とは何か、教えていただけますか。
「植物療法って簡単に言うと、植物の力を使って、私たちがもともと持っている自然治癒力を高めて、病気の予防とか心や体のケアに使っていく。で、健康に導いていくっていうことなんですよね。
だから植物療法って聞くと、ちょっと難しく感じるかもしれないんですけれども、普通にお部屋の中でアロマ・ディフューザーで精油の香りを楽しむとか、ハーブティーを飲むとか、あとは森林に行って深呼吸するとか、植物を育ててすごく癒されるとか、そういうのも全部、植物療法のひとつになっていると思います」
●なぜ植物って癒す力があるんですか?
「細かく見ていくと、理由はちゃんとあるんですけど、植物って基本的には生まれてきた場所から自由に動くことができないので、そこで一生、生きていくために、長い歴史の中で、すごくたくさん進化をしてきているんですよね。
で、植物って常に有害なものから身を守る成分と、これからも地球上から絶えないようにするために、子孫を残す成分っていうのを作り続けているんですね。それが最近でも話題にはなっているんですけど、『フィトケミカル』っていうような成分もそれに含まれていて、それは植物の香りとか苦味とか色素とかを作っているような成分でもあるんですね。
なので、そういった成分に抗菌とか抗ウイルスとか抗真菌の作用があって、植物自身も守られるとともに、それを使った私たちも抗菌とか抗ウイルスの作用で感染症のケアができたりとか・・・。
あとは、そういう植物が作る成分って、紫外線をずっと植物は浴びているので抗酸化作用っていうのがあって、細胞が老化したり酸化したりするのを防ぐような成分が結構あるんですよね。そういうのを私たちが使うことで、ひいては老化の対策ができたりとか、そういったいろんな一面を植物は持っています」

●ひとくちに植物療法と言っても、本当にいろんな療法があるんですよね。
「そうですね。この本の中でもアロマテラピーだけじゃなくて、ハーブ療法とかフラワーエッセンス、森林療法 、園芸療法、ジェモセラピー、ホメオパシーなどなど、たくさんジャンルがあって、本のパート1では、それぞれの特徴もわかりやすく説明をさせていただいているので、ひとつかふたつは自分は知っているけど、ほかのはまだ聞いたことがないっていうかたも読んでいただけると、その違いがわかるかなと思います」
クレオパトラの香り!?
※中村さんの新しい本から、続いては、植物療法の歴史に少し触れたいと思います。本には紀元前3000年頃にはメソポタミアやエジプトで、すでに植物療法が用いられていたと書いてありましたが、どんなものが何に使われていたのでしょう?
「その頃はどちらかというと、もちろん治療的に使われていたこともあるかもしれないんですけれども、宗教とか儀礼的な舞台で植物の香りが利用されることが多かったみたいです。その頃の遺跡からはペースト状になった油に植物の香りがついた軟膏を入れていたような容器が、すごくたくさん出土しているんですよね。
なので、身分が高いかたが亡くなった時に一緒に棺の中にそういったものを納めたりとか、どちらかというと、暮らしの中で庶民が、っていうよりは、おそらく特別なかたがたが香りを重用していたのかなっていうような痕跡がみられるみたいです」
●歴史上の重要な人物も植物療法に関わっていたということで、例えば古代ギリシャの医者で、医学の父と言われているヒポクラテスは、植物療法の歴史においてどんな役割を果たしたんですか?
「ヒポクラテスが生きていた時代は、病気が神様の怒りに触れたりすることで、みんなに起こってしまうものっていうふうに信じられていたので、基本的に治療は神様の教えに従って神殿の中とかで行なわれていたらしいんですね。
で、ヒポクラテスはそういう呪術ありきの治療法に疑問を呈した人で、病気とか治療法は神様から与えられるものではなくて、理性に基づいた合理的で科学的な説明ができるはずなんだって考えて、彼は環境とか食事とか生活習慣とかが、人々の健康に大きな影響を与えるっていうふうに考えたようなんですね。
そんな中、彼は排泄を促すために下剤とか嘔吐剤とか利尿剤を薬草で作って、それぞれの人にアドバイスをしながら、それを渡したりとか、あとは生活習慣の中で薬草とか野菜とかオリーブオイル、ワイン、蜂蜜を積極的に食事の中に取り入れるといいよっていうようなアドバイスもしていたようなんですよね。
なので、今の私たちからすると生活習慣が健康を左右することになるっていうのは、もう当たり前って感じだと思うんですけれども、やっぱり当時のように長きに渡って病気と迷信がセットになっていた時代に、それを大きな声で発信していったっていうのは、すごく先進的な人だったのかなって思います」

※あのクレオパトラは、権力の象徴として香りを使っていたそうですね?
「彼女もすごく魅力的で頭が良くて、政治的手腕に長けたかただったようなんですけれども、彼女はとっても高価な香りのついた油とか香料をたっぷりと全身に塗ったりとかして、人々を魅了していたみたいなんですね。
特にバラとかジャスミンのお花がすごく好きだったみたいで、権力のある政治家とか軍人を晩餐会に招いた時には、くるぶしぐらいまでバラの花を敷き詰めて招待客を圧倒して、政治的な力を見せつけたっていうようなエピソードもあるみたいです」
●すごいですね〜! バラとかジャスミンのお花を浮かべたお風呂にも入っていたって、本に書かれていましたけれども・・・。
「本当に高貴なかたならではの、香りを使った処世術というか、すごいなと思いますね」
●華やかな香りがしたんでしょうね〜。
「香りがちょっと想像できるような、浮かんできますよね」
(編集部注:日本では、あの聖徳太子が医学や薬草の利用を広める重要な働きをしたそうですよ。興味のあるかたは、ぜひ中村さんの本を読んでくださいね)
ハーブは音楽や絵本にも登場!?
※この本では、植物と人の関わりが記された古典や文学、絵画や絵本、小説や映画、さらにはマンガやアニメなども紹介されていますが、実は音楽にも植物が登場するんですよね?
「そうですね。この本の中でもいくつか、音楽の中に紹介されている植物たちっていうのがあって、例えばサイモン&ガーファンクルの『スカボロー・フェア』っていう曲の中に、パセリとセージとローズマリーとタイムっていう4つの植物が出てくるんですけど、これが何を意味しているのかっていうのを考察してみたりとか・・・。
あとはエディット・ピアフの『バラ色の人生』とか、エド・シーランの『スーパーマーケット・フラワーズ』とか、いろいろな曲の中に出てくる植物と、それがいったい何を象徴しているのかなって、ちょっと考察してみたりしています」
●具体的な植物の名前を出すことで、歌の世界観がやっぱりググッと広がりますよね。
「そうですよね。植物って誰でもなにかしらの思い出があると思うんですよね。なので、植物の名前が出てくることで、自分の中の思い出スイッチみたいなのがちょっと刺激されて、きっとみなさん、心が動くところがあるんじゃないかなって思います」

●親近感にもつながりそうですね! 絵本でいうと「ピーターラビット」のシリーズにはいろんなハーブが出てきますよね。
「そうですね。ピーターラビットってすごく絵が可愛くて、みなさん多分、絵柄はご存知だと思うんですけど、結構、家庭環境が複雑なうさちゃんたちなんですね。
お母さんがひとりで4匹の子うさぎたちを育てていて、生計を立てるためにハーブをすごく使って、例えばハーブのお薬とかローズマリーのお茶とかを販売したりとか・・・。あとはうさぎタバコって言われるラベンダーを乾燥させたものを、みんなに分けたりとかして生計を立てているので、そもそもがハーブがベースになっている暮らしっていうのが描かれているんです。
そのピーターラビットのエピソードの中でも、ピーターがすごくいたずらっ子なので、畑に行ってどんどん野菜を勝手に食べちゃったりするんですけど、そこでピーターは自分で消化にいいハーブをちゃんと食べてケアをしたりとかしているんですよね。
なので、読んでいるとこれにこういう作用があるんだっていうのもわかるんですけど、すごく可愛らしくて、ハーブの情景も浮かんできて、とってもワクワクします」
スクール&サロン「野枝アロマ」
※中村さんが主宰されている都内・西荻窪になるアロマテラピースクール&サロン「野枝(のえ)アロマ」では、どんなレッスンをされているんですか?
「大きく分けると、フランス由来のアロマテラピーとか植物療法をお勉強していただけるレッスンと、あとは日本ならではのアロマテラピーを勉強することができるレッスンというのがあるんですね。
で、フランスの植物療法については、フランス由来のアロマテラピーで使う専用の成分とか、使い方をすごくわかりやすく深く勉強することができるNARD JAPANという協会の認定コースもやっています。あとは私自身がリヨンの植物学校で学んだ内容とか、農場とか精油メーカーを取材してきた内容を、スライドを見ながら楽しく勉強していただけるオリジナルのコースなんかもあります」

●一度だけ体験したいとか、そういうこともできるんですか?
「そうですね。体験レッスンもやっていて、そこでアロマテラピーの最初の一歩のお話をさせていただいたりとか、ルームコロンとか入浴剤とか美容オイルを楽しく作っていただいたりすることもできます。
あとはオンラインで説明会とかワークショップみたいなのをやることもあって、結構いろいろな地域から来ていただいたりもしているので、これからはもう少しオンデマンドの動画レッスンとかオンライン講座もちょっと充実させていきたいなと思っています」
●いいですね〜! フランスには今も定期的に行かれているんですか?
「はい、そうですね。1年に一回くらいは必ず行っています!」
●そうなんですね! で、精油とかアロマとかのメーカーだったり、ハーブの農場とかを周られているんですか?
「そうですね。必ず毎回訪れている農場とか精油メーカーもありますし、彼らに紹介してもらって、また新しい農場に行ったりすることもあります」

●近々行かれる予定はあるんですか?
「もうシーズンが一回終わってしまっているので、次に行くのはおそらく来年の5月6月ぐらいかなと思っていて、そこでは取材とともにリヨン植物療法専門学校で、私が日本のアロマテラピーについての授業もさせていただく予定です」
●そうなんですね、すごい! では最後にアロマテラピーを通して、どのようなことを伝えていきたいですか?
「とにかくアロマテラピーを始めとした植物療法は、私たちの心とか体を元気にしてくれる素晴らしい可能性を秘めているということと、やっぱり古代からずっと私たち人間に、一緒に寄り添っていてくれている植物のことを知ることは、とにかく楽しくて学び甲斐があることだっていうことですね。
なので、そういうことをみなさんにお伝えすることで、今まで何の気なしに見ていた植物に対して、ちょっと興味が湧いたりとか、自分とかご家族の健康に興味が湧いて、自分とか周りの大切なかたがたを植物で癒して元気になっていくきっかけになったら、すごく嬉しいなと思っています」

INFORMATION
中村さんの新しい本をぜひ読んでください。アロマテラピー、ハーブ療法、フラワーエッセンス、森林療法などの解説に加え、植物療法の歴史、人物、物語などなど読み応え、見応えがありますよ。フランスの農場などに行った取材レポートも写真入りで載っていますよ。おすすめです! 翔泳社から絶賛発売中です。詳しくは、出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。
中村さんが主宰されているアロマテラピースクール&サロン「野枝(のえ)アロマ」について詳しくは、ぜひオフィシャルサイトを見てくださいね。
◎野枝アロマ:https://noe-aroma.com
◎インスタグラム::https://www.instagram.com/noe_aroma/
2024/8/25 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. LIFE IS A FLOWER / ACE OF BASE
M2. PLANT LIFE / OWL CITY
M3. A HEALING COMING ON / THE CRUSADERS
M4. LA VIE EN ROSE / ÉDITH PIAF
M5. FLOWER SHOWER / ISLAND ETC.
M6. SCARBOROUGH FAIR / SIMON & GARFUNKEL
M7. SUPERMARKET FLOWERS / ED SHEERAN
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2024/8/18 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、「いきものデザイン研究所」を主宰するイラストレーター「一日一種(いちにち・いっしゅ)」さんです。
一日一種さんは、主宰するサイト「いきものデザイン研究所」に掲載する、生き物に関する4コマ漫画がとても人気です。また、日本自然保護協会NACS-Jの会報誌「自然保護」にも連載されています。
そんな一日一種さんには約3年前に、初心者向けのバードウォッチングの本を出された時にご出演いただいたんですが、今回は先頃、『いきものづきあいルールブック』という本を出されたということで改めて番組にお迎えすることになりました。
きょうは、海、川、山、そして公園などで、自然や生き物と関わるときに、知っておきたい法律やマナーについてわかりやすく解説していただきます。
☆協力:誠文堂新光社

楽しくライトに
※一日一種さんは、環境アセスメントなどを行なう会社に勤務し、野生生物などの調査員として活躍後、独立。現在はフリーのイラストレーターとして、マンガやイラストを通して野生生物の魅力を伝える活動を行なっていらっしゃいます。また、生き物に関する本も数多く出版されています。
そんな一日一種さんの新しい本が『街から山、川、海まで 知っておきたい 身近な自然の法律〜いきものづきあいルールブック』。
この本を出そうと思ったのは、良かれて思って野生動物を助けたのに、実はそれが法律を犯していた、そんなケースもあるので最低限、生き物や自然に関する法律は、知っておいたほうがいいのではないか、そんな思いがあったからだそうです。
法律やマナーというと、ちょっと難しいイメージがありますが、この本はマンガやイラストでわかりやすく解説。登場するキャラクターは、人間に化けて街中で暮らすキツネやタヌキ、そして架空の自治体の環境課に勤める、生き物好きの女性の課長というラインナップで、とても親しみやすくて、楽しく学べる本になっています。

●自然や生き物に関する法律などは、以前、一日一種さんがお勤めになっていた、環境アセスメントを行なう会社で、仕事の一環として学んだという感じなんですか?
「そうですね。仕事でもやっぱ調査業をやっていますと、動物を捕獲するために鳥獣保護管理法の許可が必要だったりとか、私有地に入って調査する時とかもあって、そういう時に許可が必要だったりとか、そういうことは確かにあって勉強にはなりましたね。ただ、本を見ていただくとわかるかもしれないですけど、網羅的に山から川、海までなんでも扱っている感じなので、結局新しく勉強したところが大きいですかね」
●この本を出すにあたって、いちばん苦心したのはどんなところですか?
「法律の解説は割と淡々と行なってはいるんですけれども、いちばん気を遣ったのはお説教みたいな感じにならないようにっていうところですかね。法律の本で、しかもマナーの話もするってなると、どうしてもお説教っぽくなってしまいがちだと思うんですね。
僕自身もそういう生き物警察みたいな絡み方はしたくないというか、そういうのが嫌なので、漫画を読んでいただくとわかるかもしれないですけど、できるだけ楽しくライトに、幅広い人に気軽に知ってもらえればな~っていう思いを込めて、なるべく説教臭くならないようにっていうところが、いちばん苦労したところかなって思いますね」
●本の最初にチェックするべき法律の内容は、大きく分けると「種」と「場所」そして「方法」の3種類があると書かれていました。どういうことなのか具体的に解説していただけますか?
「便宜的にそう分けるとわかりやすいかなと思って分けたんですけれども・・・というのは法律って結構たくさんあるじゃないですか。自然の法律もそうなんですけれども、いろんな法律があって、法律ごとにその目的とか規制している範囲っていうのがかなりまちまちなんですよね。
ある法律では種を対象に保護している、ある法律では面的に保護していると・・・。あと、ある法律では方法について、例えば漁業関係だったらこの用具を使って獲っちゃダメとか、これならいいとか。そういう方法についても規制している、それぞれの規制しているものが、種と場所と方法で分けるとわかりやすいかなって思って、そういうふうに分けましたね」
山は誰かのもの!? 海は密漁!?
※では本の中から、いくつか事例を挙げて、お聞きしていきたいと思います。
この本『いきものづきあいルールブック』ではフィールドを、例えば「街中と身近な自然」とか「山」「河川や湖」そして「海」など、いくつかに分けて解説されています。
夏休みということで、まずは「山」に関する事例から。初歩的な質問なんですが、山はどこでも入っていいんでしょうか?
「特に規制しているものがなければ、結構するっと入っていけちゃうし、入っていっていいと普通の人は思っているとは思うんですけれども、原則としてはそこは誰かのものではあるんですよね。国が持っているものにしろ、私有地にしろ・・・。
だから入ったことで即、法律違反とはならないんですけれども、例えば私有地だったら入っていった時に、そこで出てってくれって言われたら、もちろん出ていかないといけないですし、規制をしていたら、そこにロープとかで立ち入り禁止とかちゃんと表示がされていたら、それを乗り越えて入ることは不法侵入に確実にあたってしまいます。そういうところは注意しないといけないですね。
最近は“バリエーション・ルート”とか言って、いろんな場所を道なき道を行くような山歩きの楽しみ方とかもあるんですけれども、原則としてはそこは誰かの所有地であるので、歩くこと自体は基本的には問題ないけれども、いろいろと気を付けないといけないっていうのはあります」

●山は誰かのものなんだ! っていう意識を常に持っておかないといけないですね。
「はい、そうですね。それがないと歩いていって、そこの自然を傷つけちゃったりとか枝を折っちゃったりとか、勝手に何かを採っちゃったりとか、そういうことをしかねないので、どこを歩くにしろ、そこは誰かの所有地っていう意識があるとトラブルは少ないかなと思います」
(編集部注:山で見つけた山菜やキノコは原則としては採ってはいけないということです。個人で楽しむ程度なら、まだしも、大量に採って販売したりすると、「森林法」に触れて、森林窃盗になることもあるそうです)
※続いて「海」にいってみましょう。夏ということで、家族で磯遊びに行くかたも多いと思います。潮だまりにいろんな生き物がいて、観察するのも楽しいと思うんですけど、法律的に特に気をつけることはありますか?
「磯遊びとか、海辺で生き物を捕まえたりする時に気をつけたいのは、やっぱり漁業関係の法律ですかね。アワビの密漁とかアワビに限らず海産物ですね。ナマコだったりサザエだったりタコだったりとか、細かい種類はそこの地域地域によっても分かれていたりはするんですけれども、今言った海産物は、例えば自然観察のためにちょっと獲るぐらいでも、割とそれでアウトになってしまうこともありますので、基本的に気をつけたいですね。
持って帰るのはまず基本的にはやらないほうがいいっていうのがあるのと、あとはそこの海辺で特に厳しく規制されているものは何かっていうのは、事前に知っておいたほうがいいと思います。有名な磯遊び場だと看板がちゃんとあるので、それを見ておけば問題はないですね。「サザエ、タコ、アワビ 密漁ダメ!」みたいな看板が大抵あるので、それさえ気をつければ基本的には大丈夫ですね」

●釣り好きのかたは、夏に限らず海釣りに行くことも多いと思うんですけれども、特に守らなきゃいけないマナーとかって、どんなことがありますか?
「海釣りについて、よく問題視されているのは、立ち入り禁止の場所に勝手に入っちゃうっていうやつですね。川と違って、あんまり遊漁券とかないんで、割とどこでも自由に釣りができるっていう側面があるんですね。釣れる場所が堤防の先端のほうだったりして、そういう場所って大抵危険な場所なので、波に飲み込まれてしまったりとか、立ち入り禁止になっている場合が多いんですけれども、でも釣れるからって結構入っていっちゃう人が多いんですよね。
夏になるとニュースによく取り上げられて、“柵を乗り越えて勝手に侵入!”みたいなニュースになっていたりもするんですけれども、基本的に法律違反にはなってしまいます」
河川敷は自由に使える!?
※本に「河川敷は誰のもの?」とありました。これはどういうことなんでしょう?
「河川敷って割と誰でも自由に使える場所っていう認識があるかなって思って、そういうふうにタイトルをつけたんですけども、実際には法律もやっぱりちゃんとそこにあるし、やっちゃいけない行為もあるっていうのを知ってもらいたいなと思って、“誰のもの?”っていう言い方をしました」
●確かにジョギングしたりとかバーベキューしたりとか、河川敷って自由に使えるものだという印象もありましたけれども、そうではないってことですか?
「割とみんなのものっていうイメージもあって、自由にみんな使っているっていうのと、あと『自由使用の原則』っていうのが河川敷ではよく言われていて、誰でも自由にいろんなことができますよ! っていうのはあります。

その中でもやっちゃいけないことは河川法とか、そのほか生き物関係の法律とか、あと漁業関係の法律とかで規制されている部分はあるので、一般常識の範囲内であれば大丈夫と思っていただいて、今おっしゃったようなジョギングしたりとか運動したりとか、場所によってはバーベキューとかも許可が必要だったりするかもしれませんけれども、そういう細かいところは自分の住んでいる自治体の情報をチェックすれば大丈夫だと思います」
●河川での釣りはどうですか?
「川の釣りは大抵の場合は遊漁券が必要になっちゃいますね。なくてできる場所もあると思いますけども、大体釣りをやっている人は遊漁券を買って釣りをしています。
遊漁券っていうのは、全然釣りを知らない人には馴染みがないかもしれないですけども、生業としての釣りじゃなくて、遊びとしての釣りをやるための権利を漁業組合さんとか管理をしていらっしゃる人たちに一定のお金を払って、そこで釣りをさせていただくための権利っていうものですね。なので、河川で釣りをやる場合は一応法律に気をつけるべきっていうのは、あらかじめ知っておいたほうがいいと思います」
野鳥のヒナを見つけたら・・・
※街中でもいろんな生き物が暮らしています。以前、スタッフが公園で巣だったばかりのヒヨドリのヒナを見つけたことがあったそうです。親鳥と、はぐれたようだったということなんですが、そんな時はどうすればいいですか?
「結構ケース・バイ・ケースなところもあるんですね。原則としては見守るっていうのが大前提ではあるんですけれども、自然の摂理なので・・・。
まず、親とはぐれてしまったっていうことは、ほとんど人間にはわからないと思います。ヒナが落ちているとして、周辺に親がいないかを探してみて、見つかるっていうことはほぼないと思いますね。親鳥も人間に見つからないようにどこかに隠れていると思いますし、ちょっと距離をとっているかもしれないですし、それが親鳥ってわかるケースはほとんどないんじゃないかなと思います。親鳥は近くにいるだろうっていう前提で考えたほうがいいと思いますね。

あとはケガをしていたとしたら、それがなんでケガをしていたのかにもよって対応は変わると思いますね。人間のせいで交通事故にあってとかバードストライクにあってとか、人間活動が原因でケガをしていたのならば、自治体さんによってはそれを助けている、『傷病鳥獣救護』って言うんですけども、救護している場合もあります。そういう場合は自治体にまず連絡をしてみるっていう対応になりますね。
一方、野生動物同士の闘いとかでケガをしていたっていうのがあれば、かわいそうっていう人もいるんですけども、う~ん・・・自然の摂理ではあるので、基本的には、見守るだけ、何もしないっていうのが、いちばんいいんじゃないかなとは個人的に思いますね。
この本全体としても言っているんですけれども、野生動物にはむやみに人は関わらないっていうのが、まずいちばんの大前提になりますね。かわいそうだからとか、そういう理由で手を差し伸べてしまうと自然にとってよくないこともあるし、法律に触れてしまって自分自身の身も危ういこともあるので・・・まとめると、結構ケース・バイ・ケースであるんですけど、基本的には見守ろうっていうことですね」
(編集部注:公園でたまにハトにエサをやっているかたを目撃することがありますが、ハトの餌やりは、フンの害などもあって、大田区など、条例で禁止している自治体も増えているそうです。
そして、夏休みということで、近くの公園に出かけ、お子さんと一緒に昆虫採集をしている、そんなかたも多いと思いますが、禁止している看板などがなければ、基本的には大丈夫だそうです。ただし、東京都内の都市部の公園、新宿御苑や明治神宮の杜、国営昭和記念公園などは禁止です。お出かけになる前に昆虫採集が禁止されていないか、ホームページなどでチェックすることをお勧めします)
自分を守るためにも
※私たちが暮らしていく中で、最低限知っておいたほうがいい自然や生き物に関する法律はなんでしょう?
「やっぱり書籍の最初のほうに書いたやつがそうなんですけれども、普通に街で暮らしている人でも『鳥獣保護管理法』と『外来生物法』の、ざっくりした概要ぐらいは知っておいたほうがいいんじゃないかなって、個人的に思いますね。そのふたつだけは本当に生き物に興味なくても関わっちゃうことがありますし、特に外来生物法は最近結構、罰則が厳しいので、気をつけたほうがいいと思います」

●では最後に新しい本『いきものづきあいルールブック』で、いちばん伝えたいことはどんなことでしょうか?
「いろいろと厳しい法律はあるし、細かい法律をすべて覚える必要はないんですけれども、生き物を獲ったりとか、生き物に関わる場合はいろんな法律があって、自分が行動したことによって、割と重い罰則になってしまうこともあるっていう認識だけは、持っておいたほうがいいかなって思います。
自然を守るためというよりは、なんでしょうね・・・普通に優しい人が生き物に関わって、よかれと思ったことで(SNS で)炎上したりとか、本当に見ていて辛いので、そういうことがないように、生き物と関わる法律はいろいろあるんだよ! っていう認識だけは持っておいてほしいな~とは思います。それがいちばん伝えたいことですかね」
INFORMATION
『街から山、川、海まで 知っておきたい 身近な自然の法律 〜いきものづきあいルールブック』
一日一種さんの新しい本をぜひチェックしてください。生き物に関する法律やマナーがマンガとイラストでフィールド別にわかりやすく解説、生き物を飼うときのルールも載っていて、気になるところから読めますよ。誠文堂新光社から絶賛発売中です。詳しくは、出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。
◎誠文堂新光社:https://www.seibundo-shinkosha.net/book/science/85729/
一日一種さんが主宰している「いきものデザイン研究所」のサイトもぜひ見てください。
◎いきものデザイン研究所:http://wildlife-d.xsrv.jp
2024/8/18 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. CREATURES OF THE NIGHT / HARDWELL & AUSTIN MAHONE
M2. MORE THAN A LAW / AZTEC CAMERA
M3. FISH! / JEFFREY FOSKETT
M4. LET THE RIVER RUN / CARLY SIMON
M5. ANNIVERSARY / 大原櫻子
M6. SOMEONE’S WATCHING OVER ME / HILARY DUFF
M7. MY BEAUTIFUL CREATURE / CURLY GIRAFFE
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2024/8/11 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、自転車旅のエキスパート
「鎌田悠介(かまた・ゆうすけ)」さんです。
鎌田さんは1987年生まれ、福島県会津若松市出身。新潟大学在学中に総合格闘技を習い始め、ほかにも日本国内を自転車で旅するようになったそうです。卒業後は新潟の企業に勤め、その一方で28歳の時に総合格闘家としてプロデビュー。2016年には新人王を獲得。
そして2019年31歳でオーストラリア、2023年36歳でアイスランドを自転車で旅をされ、その時の紀行文が先頃『白夜疾走〜アイスランド自転車一人旅』として出版されました。
きょうはそんな鎌田さんに白夜の国アイスランドの旅や、自転車旅の醍醐味のほか、愛用している宙に浮くテントのお話などうかがいます。
☆写真協力:鎌田悠介

自転車旅、きっかけはお遍路!?
※アイスランドの旅のお話の前に、大学在学中に始めた日本国内の自転車旅について。旅に出る、なにかきっかけがあったのでしょうか?
「ひとつの本と出会いまして、それは四国でお寺を八十八箇所まわる、お遍路をするというような本でした。そういったものがあるんだなと気付いて四国まで(行きました)。当時新潟にいたんですけれども、四国まで何で行こうかと考えた時に、自転車で行こう! と考えまして、そこから自転車旅が始まりました」
●なんでまた旅の手段を自転車にしようと思われたんですか?
「単純に車がなかったのと、あと大学生らしくていいかなと思ったのと、夏休みを利用してというような形でしたね」
●実際に自転車で旅をされて、いかがでしたか?
「やっぱり車や公共交通機関では訪れることができないような町を訪ねることができて、普段は気づけないような景色とか出会いとか食べ物とか、そういったものに触れられるっていうのは、自転車旅のいいところなんじゃないかなと思っています」

●寝泊まりはどうされていたんですか?
「テントと寝袋を持って旅していましたので、野宿というような場合も多かったです(笑)」
●そういうアウトドアスキルみたいなものって、鎌田さんはどうやって身につけたんですか?
「それこそ自転車旅を通して身につけていきました。最初はわからずに、余計な物もたくさん持っていったりしていたんですけれども、やっぱり旅を進めていく中で、どうすれば外で生活できるかなっていうのを考えながら、必要なものを買い足してトライ・アンド・エラーしていったというような形で、最終的にアウトドアスキルが身についていったと考えています」
●暑かったり寒かったり、雨が降ったり風が吹いたりって、いろいろ天候にも左右されると思うんですけど、経験から身につけた対処法とかってあるんですか?
「え~っと、対処法というのはほとんどなくて、(自転車旅は)雨や風にさらされるしかないので、どちらかというと心構えを変えるとか、そういったことで対処していましたね。
はっきりと意識が変わった瞬間というのを覚えていまして、島根県の日本海側を走っていた時に、私、雨の日を走るのは嫌がっていたんですけれども、ほかに自転車で旅しているかたがいて、その人は“雨でも走るよ!”と言っていたので、その時に心境が晴れて、日本で旅している以上半分は雨なので、雨の日を嫌っていてもしょうがないなっていうふうにその時に思いました。それからは関係なく雨も楽しむようになっています」
(編集部注:大学生の時の最初の旅「四国」は、仲の良い友人とふたりで行ったそうですが、その後は日程などが合わず、一人旅になったとのこと。旅に出るときは、自転車にキャンプ道具のほか、自転車用工具なども積むことになり、なるべく軽くしたいけれど、そうもいかず、悩みどころだそうですよ)
アイスランド自転車旅
※ここからは、先頃出された本『白夜疾走〜アイスランド自転車一人旅』をもとにお話をうかがっていきます。この本は、去年の6月末から8月にかけて行なった旅を日記形式で綴ったものです。

アイスランドは日本と同じ島国で、火山があったり、温泉に恵まれていたり、水資源が豊富で漁業も盛ん、ということで、日本との共通点も多い国なんですね。自転車旅の行き先をアイスランドにしたのは、どうしてなんですか?
「理由としては、子供の時に地理の教科書とか資料集で見たアイスランドの写真が印象的で、こんな綺麗な場所があるんだなと思っていました。そんなちょっとくすぶっていた気持ちが大人になって、(アイスランドに)行ってみようっていうふうになって、ようやくこのタイミングで行けたというような形ですね」
⚫️ちょうど白夜の期間に旅をされていましたけれども、白夜に慣れるまで眠れなかったりとかしませんでしたか?
「はい、おっしゃる通り眠れませんでした。窓から差し込む日光の明かりが、顔に当たるとやっぱり眠れませんので、そういった時は服とか、着ていたダウンとかを顔にかけて、なんとか暗さを確保して寝るというので、慣れるのにちょっと時間がかかりました」
⚫️反対に白夜でよかったっていうこともありますか?
「やっぱり暗くならない! 見える! っていうところですね。自転車で走っていても、街灯とかはもちろんないんですけれども、日が沈まなければ視界が確保できるので走行できるというのと、あとテントとか設営する時も周りにどういったものがあるのかとか、地面に何があるのかとか、動物の気配があるのかないのかも確認できますので、そういった意味では非常によかったです」

⚫️アイスランドは、北海道よりもちょっと大きいくらいということですけども、本に載っていた地図を見てみると、(島内を)時計周りにぐるっと回られたんですね。このコースにしたのはどうしてなんですか?
「まず、首都レイキャビークは南西のほうに位置していまして、最初に北に向かいたいなと思いまして時計回りを選択しました。あと過去に北海道を一周した時に、私は反時計回り選択したんですけれども、ちょっと風向きが辛かった気がしたので、もしかしたら北半球だと時計回りのほうが楽なのかな〜というような仮説があって時計回りを選択しました。結果あまり関係なかったです(笑)」
(編集部注:アイスランドで、1日に走った距離は平均80キロから100キロ、全走行距離は2000キロを超えたそうですよ)

フィヨルド地形、厳しいアップダウン
※アイスランドは地形的にはどんな感じなんですか?
「私は海岸沿いをよく走っていたんですけれども、やっぱり氷河で作られたフィヨルド地形が多くて・・・落差がありまして、アップダウンがとてもあるコースとなっていましたので、毎日泣かされていました」
⚫️わ〜! アップダウンが激しいとなかなか厳しい旅でしたね?
「とても厳しかったです。せっかく登ったのにすぐに海抜0メートルまで降りて、またすぐに登るというような・・・ちょっともったいないなと思いながら(笑)」
⚫️そうなんですね。ため息が出るほど美しかった景色とかはありました?
「やっぱり毎日見ていましたけれども、フィヨルド地形は綺麗だなと思いながら見ていました」

⚫️どんな景色なんです?
「やっぱりまず、山なんですけれども、日本と大きく違うのは木がない点ですね。なので、日本の景色からは想像できないと思いますけれども、山肌がそのまま見えて、そこに川がどういう形でうねっているのかも遠目で見て分かりますし、こういうふうになっているんだと思いながら毎日感銘を受けて(自転車で)走っていました」
⚫️いいですね。あと氷河の湖の写真も本に載っていましたけど、氷の色が水色でしたよね?
「はい、あれは高圧で氷を作ると、あのような色になるとのことです」

⚫️氷河が溶けて湖になっていたっていうことですか?
「はい、氷河の後退で削られた地形に真水が溜まったものが氷河湖であると思います。海沿いだとそれが海水で満たされて、フィヨルドになるというようなところだと思っています」
⚫️立ち寄った町で思い出深い町ってありますか?
「やっぱり北西にあった『イーサフィヨルズル』という町がとてもコンパクトで印象的でした。二日間しか滞在はできなかったんですけれども、小さな町ながら、パン屋とかカフェとかスーパーとかまとまっていて、とても過ごしやすそうだなと思っています。また行く機会がありましたら、滞在してみたいなと思っています」
(編集部注:アイスランドは世界最大の露天風呂「ブルーラグーン」があることでも有名ですよね。鎌田さんが利用したキャンプ場なども、隣りに水着着用で入る温泉があったそうですよ。また、レストランで食べたお料理では、ラム肉がとても美味しかったとおっしゃっていました)
自然エネルギー大国「アイスランド」
※アイスランドは電力を100%自然エネルギーで賄っていて自然エネルギー大国と言われているそうですが、旅をしていく中で、そういうことを感じたりしましたか?
「はい、やはり地熱を利用しているという点がすごく賢いなと思っていました。地熱発電ではなくて地熱を利用してお湯を作って、そのお湯をそのまま建屋に引いて、暖房だったりそのまま調理用の水として使うというような場所もありました。これはわざわざ電気を介さないで使えますので、すごく賢いなと思っていました。蛇口から80度のお湯が出ますので、そのままコーヒーを作れるというような場所もありましたね」
●え~すごい~! アイスランドのかたがたの自然や環境に対する意識の高さみたいなものは感じました?
「特別に意識が高いかというと、そういうところはないのかなと思いますけれども、やっぱりとても自然が厳しい場所ですので、そういった意味で当たり前のように(自然に対して)敬意なり畏怖なり、そういったものは持っているんだろうなっていうのはなんとなく読み取れます」
⚫️宿泊先などで、環境に負荷をかけないような取り組みは何かありましたか?
「やっぱり“エネルギーは大事にしましょう!”というような張り紙があったり、“このお湯はガスで沸かしているから大事にしてください!”みたいな、そういった掲示はありました」
⚫️鎌田さんのYouTubeも拝見しましたけど、旅先でのゴミ拾いを心がけているんですね?
「はい、自転車で旅している中でまったく人がいないような場所にも、人工物のないような場所にも空き缶でしたりペットボトルが落ちていますので、そういったものを拾おうと心がけています」
⚫️ゴミから何か見えてくるものとか、感じることはありました?
「ちょっと大きな話になりますけれども、大自然の中に人工物があるのはやっぱりちょっと違和感がありますね。なので、ゴミっていうのはどうしても広がってしまうんだなっていうふうに感じてしまいます。捨てる人と拾う人がいるのかなと・・・それだったら拾う側になろうと」
宙に浮くテント「テントサイル」
※鎌田さんはアイスランドの旅で、宙に浮くテントを使っていました。また、YouTubeで使い方などを説明されています。この宙に浮くテントは、どこのメーカーのテントでどうやって設営するんですか?
「イギリスのメーカーの『テントサイル』と呼ばれるテントです。簡単に言いますと3支点型のハンモック状のテントになります。設営の仕方は、まず三角形になる支点となる木でしたり、まあ木が多いですね。木を探すというところから始まりまして、木がなければ固定できる三角形の支点をまず探すところから始めまして、そこにロープをくくりつけてテントを張っていくというような形です」
⚫️今は公認のマスターでもいらっしゃるんですよね?
「はい、公認のテントサイル・マスターとして・・・以前オーストラリアの自転車旅をした時に、このテントを使わせていただいて、大体60泊ぐらいしたと(SNSで)つぶやいたら、公認を受けました(笑)」
⚫️そうなんですね~! でも柱になるような木とかがないと設営できないってことですよね?
「はい、支点がないと設営できません」
⚫️結構(設置場所が)限られませんか?
「そうですね。そういった意味では若干、設営場所は制限をされます。支点になるものがある場所でないと建てられませんので・・・」
⚫️あと、宙に浮いているってことは、(テント内で)動くたびに揺れちゃって不便じゃないかなって思っちゃうんですけど、実際はどんな感じなんですか?
「揺れないってことが、私は最大のメリットだと思っています。二支点のハンモックだと横に揺れるような気はするんですけれども、これがやっぱり三角形で支えますので、どうしても中に入る時に多少は揺れるんですけれども、揺れとか風などにはとても強くて安定しています」

⚫️そうなんですね~。改めて宙に浮くテントの利点は、どんなところにあると思いますか?
「いま申し上げた、まず風に強いっていうのが最大のメリット、筆頭としてありまして、次に床の状況の影響を受けないことですね。岩場でしたり木の根っこがありましたり、あと水たまりができていたりしても関係なく設営ができます。また、斜面であっても水平が取れるので、そういった意味で床敷きのテントよりもメリットはあるかなと思っています」
(編集部注:「テントサイル・ジャパン」のサイトによると、宙に浮くテントサイルは、もともと災害用のポータブルテントとして日本に持ち込まれたそうです。テントを張るための支柱さえ確保できれば、地面がデコボコでも水たまりでも設営できるのはいいですね。詳しくは「テントサイル・ジャパン」のサイトをご覧ください)
☆テントサイル・ジャパン:https://tentsile-japan.com
※では最後に、新しい本『白夜疾走〜アイスランド自転車一人旅』を通していちばん伝えたいことはなんですか?
「やっぱりいろいろな選択肢があるんだっていうのをいろいろな人に伝えたいですね。私は格闘技をやっていたり、サラリーマンであったりと、いろんな経験があるんですけれども、そこからいろんなことをやってもいいんだ!と・・・で、そのためには本を通して、いろいろな場所があって、いろいろな人がいて、いろいろな生き方をしているっていうのを、読みながら感じてもらえればいいかなと思っています」

INFORMATION
鎌田さんの新刊は初めての国、初めての白夜に戸惑いながらも、およそ1ヶ月半、自転車で走り抜けた旅の記録が日記形式で綴られています。鎌田さんの目を通して、アイスランドという国を知ることができる、そんな本でもあると思います。ぜひ読んでください。文芸社から絶賛発売中です。詳しくは、出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。
◎文芸社 :https://www.bungeisha.co.jp/bookinfo/detail/978-4-286-25350-3.jsp
鎌田さんのSNSや、宙に浮くテント「テントサイル・ジャパン」のサイトもぜひご覧ください。
◎インスタグラム:https://www.instagram.com/yusuke.kamata_/
◎テントサイル・ジャパン :https://tentsile-japan.com
2024/8/11 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. BICYCLE / LIVINGSTON TAYLOR
M2. ON A BICYCLE BUILT FOR JOY / B.J. THOMAS&BURT BACHARACH
M3. JOGA / BJÖRK
M4. SVEFN-G-ENGLAR / SIGUR RÓS
M5. 自転車でおいで / 矢野顕子
M6. BICYCLE / RM(BTS)
M7. BICYCLE SONG / RED HOT CHILLI PEPPERS
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2024/8/4 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、ヨットで単独 無寄港 無補給による世界一周の日本人最年少記録を樹立した「木村啓嗣(きむら・ひろつぐ)」さんです。
木村さんは、大阪府高槻市にある環境ソリューション企業「浜田」の社員で、ヨットによる世界一周は「Go around Re-Earth~Renewable Challenge for the Earth.~」というタイトルが掲げられた会社のプロジェクトでもあったんです。木村さんは、ひとりで操船できるように改造した大型のヨットに乗り、去年10月22日に新西宮ヨットハーバーを出港、そして今年6月8日に無事に戻ってこられました。
世界一周にかかった日数は231日! 走った距離はおよそ52,000キロ! という、とんでもない大冒険だったんです。
今週は、そんな木村さんをお迎えし、およそ7ヶ月半にも及ぶたったひとりの航海や、大海原で目撃した絶景、そして今後のチャレンジについてうかがいます。
☆写真:(株)浜田 提供

日本人最年少記録を樹立!
●今週のゲストは、ヨットで単独 無帰港 無補給による世界一周を成し遂げた木村啓嗣さんです。きょうはよろしくお願いいたします!
「よろしくお願いします」
●木村さんは世界一周を24歳9ヶ月で成し遂げて、それまで海洋冒険家の白石康次郎さんの持っていた26歳10ヶ月という記録を塗り替えて、日本人最年少記録を30年ぶりに更新されました。すごいことですよね。おめでとうございます!
「ありがとうございます」
●そしてお帰りなさいませ!
「はい、ただいまです」
●無事に日本に帰ってこられて本当によかったです。出港地の新西宮ヨットハーバーに戻ってこられたのが今年の6月8日ということで、2ヶ月ほど経ちましたけれども、今の心境はどんな感じですか?
「帰ってきた瞬間はあまり実感がなかったんです。達成した、やりきったっていうのはなかったんですけど、その日、揺れないベッドで寝て、みんなからお祝いのメッセージや連絡がいっぱい来て、徐々に実感し始めて、雑誌やテレビの取材を受けて、徐々に実感がわいてきて、きょうここにいるっていうイメージなので、実感をかみしめているきょうこの頃です」
●231日間、およそ7ヶ月半ですね。
「長かったです」

(編集部注:実感を噛み締めている木村さんなんですが、なぜヨットで世界一周に挑戦しようと思ったのか、気になりますよね。木村さんによれば、偶然の重なりだったということなんですが・・・
大分出身の木村さんは、たまたま進学した高校にヨット部があって入部。ヨットの競技にのめり込み、選手として活躍。17歳の頃に海洋冒険家の白石康次郎さんが世界一周のヨットレース「ヴァンデ・グローブ」に挑戦することを知り、憧れたそうです。
その後、海上自衛隊に入隊。木村さんが乗る船が神戸の造船所で修理、その期間が延び、休みの日に再びヨットに乗るようになり、ヨット愛が再燃。
当時20歳前だった木村さんは、結婚するまでに伝説になりたい! 何者かになりたい! そんな思いを抱き、当時の最年少記録保持者だった白石さんの、26歳の記録を塗り替えるなら、あと6年ある。何者かになるなら、ヨットで世界一周だ〜! と思い立ったそうです。
そして、まずは資金集めだと思い、セイリング・クルーザーのオーナーが集まるコミュニティに相談に行き、そこで、現在木村さんが所属する株式会社浜田の社長さんに出会い、ヨットで世界一周をしたい! そんな思いをぶつけ、ついには、会社をあげてのプロジェクトになったそうです)

持続可能なチャレンジ
●株式会社浜田の社内には、木村さんをサポートするチームがあるんですよね?
「ヨットの世界一周のプロジェクトチームがあって、だいたい社内外含めたら23人ぐらいだったと思うんですけど、あります。
専門の気象のチームだったり、いちばん多いのがロールコールって言って、定時連絡を受け取る人、朝の9時、夜の9時に連絡を受け取る人たちがいるんですけど、その人たちだったりとか・・・。あとはメカニカルなところをアドバイスしてくれる人だったり、そういったチーム体制があって、ひとりで行くんですけど、ひとりではできないプロジェクトです」
●すごく心強いですよね。プロジェクトに掲げられていたタイトルが「Go around Re-Earth~Renewable Challenge for the Earth.~」ということで、これにはどんな思いが込められているんでしょうか。
「株式会社 浜田自体がスクラップ だったり産業廃棄物を取り扱う会社なので、やっぱり環境に非常にフォーカスしたプロジェクト名にしています。本来であれば『Go around Re-Earth』は、『Re』じゃなくて『The』のほうだと思うんですけど、あえて『再び』だったりとか『循環』をイメージするReという言葉を使っています。
地球を船に見立てて、環境をそのひとつの船に集約して、その中にある限られた食料、燃料だったりとか資源を含めて、それを使って地球を一周すると・・・。持続可能なチャレンジ、何度でもできるチャレンジであって欲しいよねっていう願いを込めて、プロジェクト名がそういうふうなっています」
●木村さんが伝説になりたい、何者かになりたいっていう20歳ぐらいの時にプレゼンをして、会社をあげてチャレンジしましょうっていうことになって、チャレンジが決まったところで、まず取り掛かったのはどんなことなんですか?
「まず普通に働きました。やっぱり社内の応援がいちばん大切なので、僕は営業部に所属して働いて・・・で、実際の船は1月に入社して4月ぐらいに中古艇を買うことになるんですけど、まずは普通に働いて、木村啓嗣がどういう人なのかっていうのをみなさんにわかってもらうために働きました」

最初は機器のトラブル!?
●最初のチャレンジは、一回断念した経緯があるんですよね?
「実はですね・・・一昨年、2022年11月に一回出発しているんですけど、結果的に帰ってくる形になってしまって・・・で、より強固なプロジェクトチーム、より強固な船、より柔軟なシステムで、僕自身の自信付けも含めて、かなりの練習を行ないました」
●2年前は何かのトラブルだったんですか?
「出航してからずっと荒天が続いて、水力発電に不具合が生じたんですけど、実際スペアを持っていたので、必ずしも戻る必要はなかったんです。
ただ200日以上を想定している航海で、最初の10日でスペアを使い切ってしまうことのメンタル的な負担だったりとか、いろいろ加味した時に、一度戻って、もう一度(物資を)乗せて行ったほうが最初の10日であれば、100日200日近く経ってきた頃にそういう状態になるのとはちょっと違うので、戻って再出発しようというふうに考えていたんです。
その時はコロナ禍ということもあって全然物が手に入らない、海外からの輸入品だったので・・・で、1年延ばすっていう苦渋の選択を迫られたわけです」
●葛藤とかはなかったですか?
「戻るにも僕の中で条件があって、誰かに助けてもらうことになると、自分がやりたいことをやっているのにもう一度行きたいなんて、関西人っぽく言うと“よう言わんなぁ”っていう状態になりまして・・・僕はそう考えるんですね。自力で戻れば必ず私はこの場所に戻ってこれると・・・伊豆諸島を越えたあたりの太平洋上で思ったんですけど、ここに戻ってくるには必ず自力で戻る必要があると思って、一度戻るんであれば、今戻るしかないと・・・。
ちなみにプロジェクトチーム内で協議があったんです。このままハワイまで行って、ハワイに到着するまでに物資を調達して、ハワイで補給をするかっていう話もあったんですけど、このプロジェクト、単独無帰港で無補給、何も補給せずにどこにも寄らずにひとりで世界一周にするプロジェクトだったんで、これをどうにか達成すべくハワイで(物資を)乗せるのはなしだということで一度戻りました」
●そうだったんですね・・・。で、船を修理して再チャレンジするっていうことになったわけですよね。モチベーションはずっと持ち続けていたっていう感じですか?
「そうですね。下がることは一切なかったです」
●その奮い立たせるものって何だったんですか?
「僕の中で世界一周というものは、浜田社長と出会ってから必ずや成功させるものという認識だったので、所詮4日間の荒天で船と私がダメになるはずがないという気持ちでしたね」
●かっこいいですね!
「かっこいいのかはちょっと・・・」
●いや〜すごいです!
(編集部注:木村さんと一緒に世界一周を果たしたヨット「ミランダ号」はデンマーク製の中古艇で、全長およそ13メートル、高さ20メートル、重さは8トンほどの船で、もともとは10人以上で乗る船なんですが、それをひとりで操船できるように、自分自身で改造。

これは海上自衛隊時代の、「KNOW YOUR BOAT」=「自分の船を知りなさい」という教えに従い、船の状態を隅々まで把握しておくために、機器の取り付けなどは自分で行なったそうです)
トレーニングは船で生活すること!?
※船が仕上がったところで、トレーニングをされたそうですが、どんなことをやったんですか?
「トレーニングでいちばん大きなトレーニングが、ハワイ・トレーニングというのがあったんですけど、ハワイを往復してくるトレーニングなんですね。いちばん重要なのは船に乗るというイメージよりも船で生活するということなんです。何もなかったように、陸上と同じようにご飯を食べる、歯を磨く、トイレに行く、船で寝るっていうのをやらないと、必ず体が耐えきれなくなって不調を起こしてしまうと。なので、いかに船に住めるか、というのが重要になってきました」
●確かに航海中でも生活しなければいけないんですよね。食事ってどんなものを食べていたんですか?
「佐藤食品さんにご提供いただいた“サトウのごはん”だったりとか、ほかはレトルト食品がほとんどです」
(編集部注:どこにも帰港しないので、食糧は多めに280日分を用意。もちろん飲料水と、海水を濾過する装置も積んでいったそうです)
ネガティヴ思考が最も大事!?
●2022年に一度チャレンジし、機器のトラブルで断念、そして再チャレンジ、ということで、去年10月22日に新西宮ヨットハーバーから出港しました。その時の気持ちはどうだったんですか?
「自信に満ち溢れていましたね」
●不安とか恐怖みたいなものは?
「僕は基本的にびっくりするぐらいポジティヴな人なので、そういうマイナスなイメージは(トラブルに)直面しないとないんですけど、これも出航してから心境の変化っていうのが起きるんですね。基本的にはポジティヴな根拠のない自信大得意なタイプなので、イメージ的にはもう男子中学生です」
●何があったんですか? 心境の変化っていうのは・・・。
「まず僕が世界一周から帰ってきて大事だなと思ったことは、ネガティヴ思考が最も大事なんです」
●そうなんですか!?
「はい、ポジティヴが最強だと僕は思っていました。なんですけど、ネガティヴ思考があることで、思いつくマイナスな状況っていうのは、すべて対策ができるようになるんですよね。
ネガティヴ思考でこれ起きたらどうしようって思うから、その不安材料を消すためにこんな対策をしよう、こんな準備をしようと・・・で、その準備をして対策ができて納得がいったら不安は消えるってなったら、ネガティヴ思考があれば、どんな不安定で危険な状況でも想像して対応することができる。
ネガティヴ思考は言ってしまえば、ポジティヴ思考の一個手前っていう、両極端な反対のものじゃなくて、ポジティヴ思考の一個手前がネガティヴ思考なんだなっていうイメージが、非常に僕の中で作られて世界一周から帰ってきました」
●なるほど。確かにネガティヴだと暗くなっちゃうってイメージがありますけど、ネガティヴ思考があるからこその準備ができるっていうことですね。航海中にそういうのが大事になったことがあったんですか?
「出航中はやっぱり怖いんですよ・・・もうめちゃめちゃ怖い! なんでかって言うと、10人乗っていたら対応できることでも、ひとりだったら全然できないです。風には太刀打ちできない、風を利用する立場ですけど・・・。なので、そうなった時にやっぱりこれ起きたらどうしよう、あれ起きたらどうしようって、いっぱい思うわけなんです。
普段通りの時はひとりでも全然乗れます。全く問題ないです。なんですけど、大丈夫じゃないことをやっぱり想像しちゃうんですよね、人間っていうのは・・・。なので、そうなった時に不安に思わないようにしなきゃと思っていたんですけど、発想の転換っていうんですか、これはある意味ラッキーなんだと! これに気づけている自分がいるということに喜んだほうがいいというふうに、ふとした瞬間に思って思考が切り替わる感じですね」
世界一周の条件、そしてルート
※今回の世界一周のルートを、かいつまんでご説明いただけますか?
「世界一周の条件があります。すべての子午線を同一方向に越えるというルールがあります。ちなみに補足情報でパナマ運河、スエズ運河・・・運河はすべて港扱いなので通ることができません。
出発した兵庫県西宮市の新西宮ヨットハーバー、場所としては甲子園球場があるところですね。そこを出発して、もちろん大阪湾がスタートですから、大阪湾を抜けて徳島県と和歌山県の間、紀伊水道を抜けてそこから太平洋に出ると・・・。
そこからはどーんと行くんですが、ハワイの近くを通って、なので日本から見て真東に向かって、その後赤道を越えて、運河を通ることはできないので、南米大陸のいちばん南側のホーン岬、チリの先端を通って大西洋に出ます。
で、世界一周中の最も難関と呼ばれているのがそのホーン岬、大体地球の半分に届かないところで迎えます。そこをなんとか乗り越え、地球の半分を走って、次はアフリカ大陸最南端の喜望峰を抜けて走って、それを抜けたら、その後はオーストラリアの南側を通過して、ニュージーランドとオーストラリアの間を通って北上が始まります。北上が始まった後、ソロモン諸島の島の間を抜けて、その後赤道を越えて日本まで戻ってくる、そんなコースです」

(編集部注:どこの港にも寄らない世界一周は、このコースしかないそうです。お話にもありましたが、ほかのコースは運河を通ることになり、運河は港扱いになるからなんですね。
ちなみに睡眠時間についてうかがったら、一回、15分から2時間くらいで、寝られる時は、それを1日何回も繰り返すとのこと。でも、風向きが変わったことを知らせるアラームが鳴ったりして、何度も起こされたそうです)
太陽と雲の共演!
●長い長い航海中の楽しみはなんでしたか?
「やっぱり普通に、陸と同じように生活するというイメージを持っているので、陸と同じご飯を食べる、トイレに行く、歯を磨く、寝る、歌を歌う、音楽を聴く、ウクレレを弾いてみるっていう、その日常生活に非常に楽しみを感じましたね」
●ウクレレなんてやる余裕があるんですね?
「最終的には全然なかったです(笑)。一応少しは練習しましたけれども・・・」
●そうなんですね~(笑)。航海中に見た景色で、忘れられない印象的な景色はありましたか?
「景色は雲と太陽の共演なので、基本的に同じ景色がほとんどないんです。全く雲がないところに太陽が沈んでいくのは、ほぼ同じ景色になるんですけれど、雲があると毎回全然違う感じになるんですよね。
いちばん忘れられないのは帰りの赤道付近の時に見た、ものすごく雷と雨と突風が吹いた時の夜明け、その後の夜明けの朝日! 半端なく綺麗でした!」
●どういう感じなんですか?
「いつにも増してオレンジ色で、海も嵐が過ぎて落ち着いているんですよね。風がなくて船が進まなくて、徐々に空が明るくなって、雲ってすごく太陽に照らされるんですよ。地球が丸い関係で最初、雲に光が当たるんですよね。
なんて言いますか・・・太陽があると影になって、自分のところはまだ明るくなっているだけだけど、雲はもう太陽に照らされているっていう状況があるんですね。それがめちゃめちゃ綺麗で、これを言葉にするのは難しいんですけれど、きょうはせっかくなので、僕の見た景色をちょっと言語化してほしいんですけど、これは非常に難しくてですね・・・」
●楽しみ!
「なので、(写真を)お見せすると・・・」
●ありがとうございます! あ、携帯電話に保存してある写真・・・うわぁ~!!
「こんな景色なんですね」


ヨットは人生が豊かになる乗り物
●今年6月8日に、無事に新西宮ヨットハーバーに戻って来られ、231日ぶりに陸にあがった時は、どんな気持ちでしたか?
「やっと終わった・・・というのも、世界一周の初日と最後の日がいちばん辛いんです。なんでかっていうと陸が近い、行き交う船舶が多い、特に帰りは疲れた状態でそれを迎えると・・・で、30時間ぐらい寝ないんです、最後・・・」
●え~~〜!
「オートパイロットの調子も悪くて、30時間ぐらいずっと舵を持っていないといけなくて、すごく疲れたので、世界一周してきた、っていうのは置いといて、その最後の30時間だけ見たら、やっと終わったっていう気持ちが非常に強いです」
●夢だったヨットで単独 無寄港 無補給による世界一周を成し遂げて、日本人最年少記録も塗り替えることに成功して、今後なんですが、夢や取り組みたいことは何かありますか?
「やっぱりこの世界一周というもの自体が、私ひとりで成し遂げられるものではなかったわけなんです。お金的にもそうですし、周りの人にも恵まれましたし、出航中も想定された嵐に出会うこともなく非常に運がよく・・・運がいいというと、一言で済ましちゃっている感じになってしまうんですけれど、とにかく運がよかった! 僕、去年、厄年やったはずなんですけど、逆に運がよかった人間なんですよね。
この結果、この成績というか功績というかわからないですけども、自分のものだけにせずに、やっぱり若い人たちだったり、学生たちに夢を・・・成功体験を語るっていうのは、ちょっと上から過ぎると思うので、人生を楽しく生きるヒントの共有というか、それをやっていきたいなと僕は思います。
夢を見ることの楽しさだったり、そのチャレンジングな人生の、チャレンジングな事柄に挑戦する楽しさというか・・・。なので、僕もヨットに限らず、自分なりにチャレンジしてみたいなと思います。
ほかの人は取れて当たり前のような資格を僕が頑張って取ってみたりとか、そういう自分にとってチャレンジング、これいちばん大事なんですけれど、自分にとってチャレンジングみたいなことをみんなにやってもらいたいなと思います」

●白石さんが今年再びチャレンジすることが決まった、世界一過酷なヨットレースと言われている「ヴァンデ・グローブ」に出てみたい! っていう気持ちはおありですか?
「あります! ちなみに白石さん、今回成功すれば地球5周目なんですね。ということは10年以内に一回は一周しているタイプの人間ですよね! 半端ない! で、僕、白石さんの記録を塗り替えたんですけど、白石さんが達成した時の30年前の状況と、今の状況を比べたら、明らかに僕のほうが恵まれているし、成功しやすいんです。単独 無寄港 無補給 世界一周っていうのを条件で見れば一緒ですけれど、白石さんのほうがかなり難しいんですよね。
なので、記録は塗り替えましたけど、白石さんを超えたなんて思いませんし、白石さんの尊敬・・・逆に地球一周するということがどんなことだったかを理解したので、より尊敬の眼差しは強くなったんですけど、恐れ多くも僕が今ここで喋っていいのであれば、僕もヴァンデ・グローブに出てみたいと思っています」
●改めてヨットという乗り物の魅力ってなんでしょうか?
「みなさんの中でいいものというのは、基本的に時間を忘れられると思います。美味しいご飯を食べている時、好きな人と過ごしている時、趣味をやっている時、基本的には時間を忘れられると・・・。僕にとってヨットは時間を忘れられる乗り物です。
クルージングに行った時に時計なんて必要ないですし、お腹が減ったらご飯を食べる・・・自然の中でより原始的な生活ができるものです。かつ海に出る時、大体エンジンのかかっている乗り物にみなさん乗られると思います。フェリーだったり釣り船だったりもそうですけど、ヨットはエンジンがないので、海の波切り音と風の音だけ聴こえる静かな乗り物なので、時間を忘れられる、人生が豊かになる時間を過ごせる、とってもすごい乗り物だと思います」
INFORMATION

この番組では「伝説になりたいチャレンジャー」木村さんを応援していきます。
世界一周の大冒険について詳しくは、株式会社浜田のオフィシャルサイトのほか、以下のSNSなどをご覧ください。
◎公式インスタグラム:木村啓嗣 Kimura Hirotsugu (@go_around_re_earth) – Instagram
◎公式ホームページ :株式会社浜田「Go around Re-Earth」
◎公式YouTubeチャンネル: 株式会社浜田「Go around Re-Earth」 – YouTube
2024/8/4 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. Beyond〜まだ見ぬ未来へ / 白井大輔
M2. Blow / 山下達郎
M3. SAIL ON / THE COMMODORES
M4. AROUND THE WORLD / MONKEY MAJIK
M5. HERE COMES THE SUN / THE BEATLES
M6. SAILING / CHRISTOPHER CROSS
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」