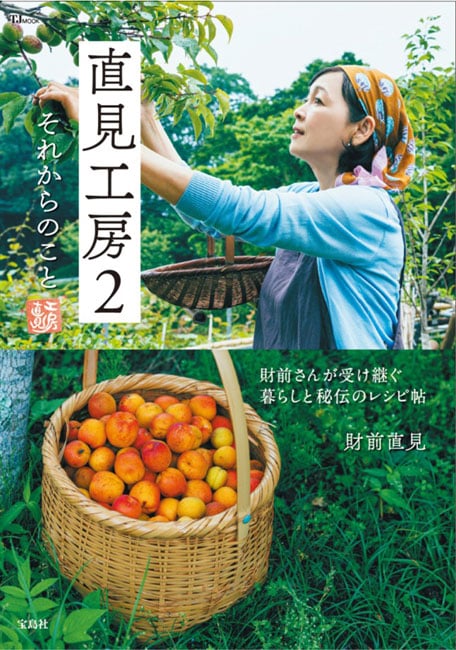2024/6/16 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. AIN’T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH / MARVIN GAYE & TAMMI TERRELL
M2. MOUNTAIN GREENERY / JACKIE & ROY
M3. RAIN / MADONNA
M4. EVERYBODY WANTS TO RULE THE WORLD / TEARS FOR FEARS
M5. MISTY MOUNTAIN HOP / LED ZEPPELIN
M6. TOP OF THE WORLD / THE CARPENTERS
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2024/6/9 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンは、シリーズ「SDGs〜私たちの未来」の第20弾! SDGsの17の目標から「住み続けられるまちづくりを」ということで、「シモキタ園藝部」の活動をご紹介します。
下北沢駅周辺は再開発が進み、小田急線が地下に移ったことで、東北沢から世田谷代田あたりまでの約1.7キロの線路跡地に「下北線路街」ができて、そこが緑地になっています。
一般社団法人「シモキタ園藝部」は「まちの植物を守り育てていく」ことを目的として2020年4月に発足。それまでの経緯をかつまんでご説明すると・・・小田急線が地下に入るということで、地上の線路跡地をどうするかという話し合いが世田谷区と市民グループの間で始まり、区長が交代したことをきかっけに、小田急や京王の電鉄会社も参加し、さらに活発化。
そして、市民グループからの提案などをもとに、ランドスケープ専門会社がグランドデザインを作り、イメージを共有。植物を中心に活動したいというグループ「緑部会」から現在の「シモキタ園藝部」になったそうです。
同園藝部は「循環」をテーマに、植栽の管理に加え、コンポスト事業、養蜂、植物の知識を身につけるための園芸学校、世話ができなくなった植物を引き取り、手入れして、新しい持ち主へつなぐ「古樹屋(ふるぎや)」、ワイルドティーなどが飲める「ちゃや」、そして活動の拠点「こや」を運営するなど、幅広い活動を行なっています。
「のはら広場」は子供たちが作った!?

※取材にうかがった日は5月の半ば過ぎで時折、日が射す程度の、そんなに暑くもなく取材日和。小田急線下北沢駅の南西口を出てすぐに、緑あふれる小道が続き、ここが下北沢!? と思うほどでしたよ。待ち合わせ場所の「こや」までは、小道を歩いてすぐなんですが、流れている時間が違うような、そんな感覚にも包まれました。
●それではまず、シモキタ園藝部ができる前から、再開発に関わってこられた「前田道雄(まえだ・みちお)」さんにご登場いただきましょう。

「こや」のすぐそばにある「シモキタのはら広場」は公園の植栽とはちょっと違う印象なんですが、どんなふうに手入れをしているんでしょうか?
「ただ単に植物を愛でるというよりは、小田急線が地下に入り、実際に育っている緑を植栽管理っていう形でメンテナンスしながら、よくある公園の植栽管理だと、あっさり伐採しちゃうというのが多いんですけど、(シモキタのはら広場は)丁寧に見ながら管理をしていく・・・そうすると例えば、そこに生えてきた草を全部採るとかじゃなくて、選択的除草と言って、これは残しておこうとか、その場その場で判断をしながらやっているので、やっぱりその地にあるような植物が残っていくのかなと思います。
あとは月に一度ぐらいイベント的に集まって、細かく管理をするので、ほかよりも丁寧に目を光らせてやっているんだけれども、一律に管理するっていうことではなくて、その場その場に相応しいやり方をみんなで考えていくみたいな形でやっています。それがほかとはちょっと違う植栽の状況になっているのかなと思っています。一般的な公園と違うのは、やっぱり草が多いですよね。
普通は樹木を植えるのが、公園の植栽のデザインとしては多いと思うんですけれども、それよりももっと草とかそういったものを中心に仕立てられていて、最初作るときは芝生を敷いたところにタネを撒いているんですね。タネを撒いて草がいっぱい生えてきて、その草地を子供たちに走ってもらって、道がだんだんできていくみたいな感じの作られ方をしているので、誰がデザインとしたというよりも子供たちが走り回ってできた道なんです。
そこで今、草地として残っているところに生えた草をちょっとずつメンテナンスしながら、しかもタネを蒔いて出てきたものだけじゃなくて、そのうち勝手に生えてくるものもあるんですね。それもこれはいいよねっていうものは残すみたいな形でやっています。だから毎年、1年目2年目3年目と、原っぱの雰囲気がだいぶ違いますよね。生えている植物も違うので、私もわからないものがまた増えちゃうみたいな感じですかね」
(編集部注:水やりや手入れは曜日を決めて、参加できる部員みんなで行なうそうですよ)

みんなで作る
※前田さんは、おもにどんな活動をされているんですか?
「私は仕事が建築系なので、どちらかというと今使っている拠点、『こや』と呼んでいる建物があるんですけれども、そこのメンテナンスというかとDIYいうか、ちょっと手を入れたりとか、そういったことをおもにやっていますね。
それも私だけじゃなくて、いろんなかたにお手伝いいただきながら、例えば外にあるデッキをみんなで作ったりとか、2階のテラスにあるデッキをみんなで敷いたりとか、あとは棚をみんなで作ったりとか、そんなことをやる時に、ちょっと専門的な知見でこうするといいよね!とか、こうすると危なくないよね!みたいなことをアドバイスしながら、みんなで作っていくのをサポートしている感じですね」

●本業とこのシモキタ園藝部の活動と、ふたつが重なることによって、何か変化はありましたか?
「すごく直接的に何か変わったというわけではないんですけれども、やはり仕事の中で、植物を植えたりとか、そういったことを考えることも多いので、その時の細かさが変わったかなと思います。
建築という、もう少し大きなスケールで見ると、樹木を何本、こういうふうに植えましょうみたいな、そういうスケール感で見ていたものが、その下に生えている草とか、そういったところも見えながら全体を考えるみたいな・・・少し細かさが出てきたような気がしています」
(編集部注:現在、シモキタ園藝部の部員は200人くらいで、年齢も幅広く、いろんな仕事をしているかたがたが集まっているそうです。世田谷区に住んでいなくても、だれでも部員になれるとのことですよ。興味のあるかたは、ぜひオフィシャルサイトhttps://shimokita-engei.jpをご覧ください)
雑草は宝物、循環は面白い
※続いてご登場いただくのは、コンポスト事業を担当する「斉藤吉司(さいとう・よしじ)」さんです。斉藤さんは、こんな動機でコンポスト事業のリーダーになったそうですよ。

「自分の自宅でも家の周りに雑草が生えているじゃないですか。それを抜くって本当に嫌だったのが、堆肥にできるって知った瞬間に雑草が宝物に見えてきてんですね。それで自身もコンポストをやり始めていたので、園藝部でもそういうのができるなと思ったら、自分の活動が広がるような感じがして、ぜひ自分にリーダーをやらせてください! って言って始まりました」
●まさに循環を実践されている感じなんですね。
「そう、面白い! 循環は面白いです」
●コンポストの維持とか管理は、斎藤さんをはじめ、何人ぐらいのかたでされているんですか?
「メインで活動しているのがだいだい15名ぐらいで、いろいろな関係で50人ぐらいのかたに関わっていただいています」
●何か所にコンポストを設置されているんですか?
「コンポストは、さっき見ていただいたコンポストを含めて3か所ぐらいですかね。(下北線路街が)1.7キロあるので、それぞれ(コンポスト)工場のほうに持ってきたら大変なので、やっぱり近くにコンポストが必要っていうことになって、それぞれの場所に作り始めています。なので、先ほどお話しいただいた前田さんも東北沢で『竹のコンポスト』を設計されて、すごく素敵なコンポストを作られています」
●堆肥化する落ち葉とか雑草は、下北線路街の植栽から発生したものですよね?
「そうですね。それとプラスして街の、例えばコーヒーかすだったりとか、おそば屋さんのそば殻だったりとか、あと世田谷区はエコな活動しているお店がすごく多くて、例えば果物屋さんが果物の皮を捨てるのがもったいないから、乾燥しているので使ってくれないかっていう提案をいただいたりとか、あとクラフトビールを作っているところは、ビールかすを使ってもらえないかとか、いろんなことがあって、そういうものを集めて堆肥を作っています」
●飲食店から出る生ゴミとかも堆肥化されているんですね。
「自分たちは宝物っていうんですけど、宝物をいただいて、それをまたさらに宝物にするっていう活動をしています」
●現在、年間にどれぐらいの量の堆肥ができるんですか?
「だいたい1回の積み込みでリンゴ箱20個分なんです。あれは50リットル入るんですね。なので1回で1000リットル、それが4回なので、合計で(年間)4000リットルできますね」
●その堆肥は下北線路街の植栽に使っているということですか?
「そうですね。やっぱり線路街はちょっと土がよくなかったりするので、そこに土壌改良的に入れてもらっていたりとか、今は新しい取り組みとして『下北の土』としてちょっと堆肥に土を混ぜて、必要なかたにお分けするっていうことを、これからやろうとしています。あと古樹屋さんでも植え替えの時に土を使ってもらっているということです」
<シモキタ園藝部のコンポストあれこれ>
シモキタ園藝部のコンポスト事業では、ミミズコンポストも含めて、いろんなタイプのコンポストを試していて、そのひとつが「キエーロ」というネーミングのコンポスト。これは、神奈川県葉山にお住まいの「松本伸夫(まつもと・のぶお)」さんが開発したもので、その特徴は、風と太陽と土を利用すること。
木の箱に生ゴミと土を入れるだけの、至ってシンプルな構造で、肝心なのは、雨が当たらないように屋根があること。太陽の光を取り入れたいので、屋根を透明にすること。そして、風通しを良くするために密閉しないこと。この3つに注意するだけ。土の温度を上げることで、微生物の活動を活発にする狙いがあるんです。この「キエーロ」は、臭いがしない、土の量が増えない、そしてランニングコストがゼロと、いいことだらけ。
シモキタ園藝部では、ワークショップで参加者にりんご箱の「キエーロ」を作ってもらったりするそうです。作りかたなどは「キエーロ」のオフィシャルサイトhttps://kieroofficial.wixsite.com/kieroに載っていますので、参考にされてみてはいかがでしょうか。
また、取材でお邪魔した活動拠点「こや」の2階には、「うみまちコンポスト」が設置してありました。これはコンポストとテーブルを組み合わせた実験的な家具で、なんと椅子の部分が、ロックを外すと回転するコンポストなんです。こうすることで中の土がよくまざり、微生物が元気になるんですね。

ほかにもコンポスト事業部では「発電するコンポスト」の実証実験も行なっています。これは「ニソール」という会社が考案した仕組みを取り入れているもので、コンポストの土の中に電極を差し込み、微生物などが発するエネルギーを電気として利用しようというものなんです。実際にクリスマスのイルミネーションなどを「発電するコンポスト」の電気で灯したことがあるそうですよ。
下北沢線路街で養蜂に取り組む
※続いてご登場いただくのは、シモキタ園藝部で「養蜂」を担当されている「杉山直子(すぎやま・なおこ)」さんです。杉山さんは園藝部の活動のひとつとして、養蜂をやりましょうと提案されたかたなんです。

なぜ、養蜂だったのか、それは杉山さんの知り合いで、田舎でニホンミツバチを飼っていたかたと話す機会があって、そこで養蜂に出会い、その蜜の味に感動したそうです。
ところが、ニホンミツバチは野生の生き物で採れる蜜の量が少ないため、セイヨウミツバチの飼育をやってみないかという話になり、そのためには技術と知識が必要ということで、埼玉の養蜂場にお邪魔し、養蜂家に弟子入りを懇願。およそ2年にわたって毎週のように通い、師匠にセイヨウミツバチの飼育方法をみっちり学んだそうです。
そして現在はシモキタ園藝部の活動として、下北線路街の2カ所に、計10箱の巣箱を設置し、養蜂に取り組んでいらっしゃいます。
セイヨウミツバチは、天敵のスズメバチから身を守る方法を知らないのでスズメバチが巣箱に侵入しないように、ネットを張るなどの対策を行なっているそうですが・・・ほかに養蜂でいちばん気を使うのはどんなことですか?
「今まさにこの時期なんですけれども、分蜂(ぶんぽう)・・・分かれる蜂と書いて分蜂と読むんですけれども、今新しい女王蜂が生まれる、活発に作ろう作ろうと蜂たちがする時期で、古い女王がいる巣箱に新しい女王が生まれてしまうと、古い女王が嫌がって一家の半分を連れて外に逃げちゃう。
そうすると、ものすごい数の蜂がわーって集まって、変な話ですけど、電信柱だったり木の幹だったりに、蜂球(ほうきゅう)を作るんですね。
そうすると、知らないかたが見ると蜂がかたまりになっているって・・・つい先だっても大谷翔平のドジャースタジアムで話題になったんですけど・・・本当にそれと同じ現象です。
その分蜂する蜂たちは新しい家を探しに出て行くので、お腹の中にしっかり蜜を溜めています。本当はものすごく大人しいんですけど、知らない人が見ると蜂がたくさんいる、怖い〜ってなって、警察沙汰にもなりかねないので、いちばんそこは注意して管理をしなければいけないんですね。ちょっとこまめに、内見と言って(巣箱の)中の様子を見る作業を通常よりは増やして行なっています」
蜂蜜で「下北沢」を味わう
●巣箱のあるエリアに花が咲いていないと、養蜂は成り立たないですよね?
「そうですね。蜜蜂は半径2キロのところを飛ぶんですけれども、もちろん近いところに蜜源の植物があるほうが蜂たちにとったらストレスが軽くなります。お陰様で、園藝部さんの植栽管理の地域が非常に近いところにあるので、私たちの蜂は豊かな花々に恵まれていると思っていて、しかもその花々の質が高い。それがすべて味に反映されていると感じています」
●どんな味がするんですか?
「特にやっぱり4月は桜の花のあとで一斉に花々が開花するので、まずひとくち舐めると桜の味を感じて、そのあとにまた違う、口の中で転がしていくと、違う花の味も感じますね。それで飲み込んだあとは、最後がまたちょっと桜とは違うというか、まるで香水のトップノートとミドルノート、そういうような変わり方をする味わいだと私は思っています」

●先ほど3種類の蜂蜜をいただきました。4月26日、5月11日、それから5月21日に集めた蜜ということで、本当に時期によって全然味って変わるんですね!
「そうなんですね、本当に。地域の花々から集めた百花蜜なんですけれども、その花の移り変わりでどんどん味が変わっていく。今年で3年目に入るんですけれども、1年目2年目の同じ時期の味ともちょっとまた違うし・・・となると気候によっても微妙に変わってきますし、まるでワインのヴィンテージというか、テロワールっていうんですか、下北沢を味わっている感じがします。
園藝部の植栽もさることながら、(下北沢は)割と古い住宅街で、お庭があってお花を育てていらっしゃるお家が非常に多い。あとは近くの公園だったり緑道だったり、東大駒場キャンパスなどにも豊かな蜜源があるので、そういうところから本当に様々な雑味のない蜂蜜というか、すべての採蜜日が外れたことがないというか、私たちは、それがありがたいですね」
●3種類、どれも本当に美味しかったです!
「自信を持っておすすめします。全く混ざりものがない非加熱の蜂蜜なので、蜂蜜の本来持っている大事な酵素とかビタミン、ミネラルがすべて生きたまま入っています。体にとっても非常にいいんですよね」
(編集部注:杉山さんが愛情込めて世話をしている、蜜蜂たちが集めた蜜は「シモキタハニー」として販売されているほか、蜜蝋も活動拠点の「こや」や「ちゃや」の椅子やテーブルなどのワックスとして使っているほか、シモキタ園藝部のワークショップなどでも活用しているそうです)
まとまり、つながり、循環

※それでは最後に、シモキタ園藝部の良さは、どんなところにあるのか、前田道雄さん、斉藤吉司さん、そして杉山直子さんにお聞きしました。まずは前田さんです。
「誰かが中心になって全部やっているというよりは、いろんなかたがいろんな興味に応じて手を加えているので、すごく統一感のある世界というよりも、少しバラバラなんだけれども、なんとなくみんなの意識が共有されているようなまとまりができているように思いますね。
それが『のはら広場』の(植栽が)バラバラだとしながらもまとまっている、なんとなく雰囲気があるみたいな感じ・・・それと同じように園藝部自体もいろんな人たちが集まって、みんなちょっとずつ違うほうを見ているんだけれども、全体としてはまとまりがあるっていうのがとても魅力的かなと思っています」
※続いて斉藤さんです。
「コンポストを2年間やってきて、いろんなかたとゴミを介してお会いできるし、そういうつながりがあって、自分たちもその刺激を受けながら、なんか新しいことがどんどん広がってくっていうのがすごく楽しいことですね」
※では最後は、杉山さんです。
「埼玉の(養蜂家の)師匠に弟子入りしたと同時に、やっぱり地元の下北沢で養蜂をやってみたいという思いがさらに強くなって、その間、下北沢で養蜂ができる場所を探していたんですけど、園藝部の先ほどお話しされた前田さんと、割と早い時期から活動されていた男性が私の小中学校の同級生で、たまたま道でばったり会った時に私の思いを伝えたんですね。
そうしたら実はシモキタ園藝部というのがあって、養蜂もいいよねと話していて、だから君、まず園藝部に入りなさいって言われて、即入部して、そこからみんなに呆れられるほどプレゼンをして、なんとか屋上を貸してくださるかたを見つけるまでに至りました。
園藝部のかたがたから言われたんですよ。私たちの巣箱を埼玉から下北沢に移動して、丸1年間か2年目に入ったぐらいの時から、花の付きが段違いでよくなったっていうふうに言ってくださって・・・。
蜜蜂による受粉活動で街の緑が豊かになっていく。それは私が最初に園藝部さんにプレゼンする時の第一の売り文句でもあったので、それを実感してくださる人たちがいるということに非常に感謝しておりますし、植物が豊かになってくれば、より多くの花が咲くので、蜜蜂たちの蜜源もそこで増えていくから、非常によい“循環”が生まれてくると思っています」
INFORMATION
シモキタ園藝部は活動のテーマが「循環」ということで、その循環の輪の中で、植物も蜜蜂も人も調和しながら、まわっているように感じました。また自治体、地元企業、そして市民が参加する再開発のモデルケースで、まさに「住み続けられるまちづくりを」を形にしていると思います。
下北線路街は緑あふれる素敵なエリアです。お洒落なカフェやお店も点在しています。まずはぜひ訪れてみてください。
シモキタ園藝部ではワークショップなどのイベントも定期的に開催。また「ちゃや」では採れたての野花を使ったワイルドティーを楽しめますし、天然はちみつの「シモキタハニー」も販売しています。詳しくは、シモキタ園藝部のオフィシャルサイトをご覧ください。
◎シモキタ園藝部 :https://shimokita-engei.jp
2024/6/9 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. 緑の町に舞い降りて / 松任谷由実
M2. WILDFLOWERS / TOM PETTY
M3. WALLFLOWER / DIANA KRALL
M4. Flowers / moumoon
M5. HONEY BEE / BENNY SINGS
M6. CIRCLE OF LIFE / ELTON JOHN
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2024/6/2 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、弘前大学の研究員で、
昆虫写真家としても活躍されている「工藤誠也(くどう・せいや)」さんです。
工藤さんは1988年、青森県弘前市生まれ。お父さんの影響もあって、子供の頃から昆虫好き。そして岩手大学大学院を経て、現在は弘前大学農学生命科学部の研究員としておもに魚や鳥など、生物が自然環境の中でどんなふうに生きているのかを調査・研究されています。
また、研究活動のかたわら、青森の野山をおもなフィールドとして昆虫の撮影を行ない、先頃、撮りためた蝶々、約200種を掲載した本『チョウごよみ365日』を出されました。
この本はタイトル通り、四季折々のフィールドで出会うチョウの写真を日めくり感覚で楽しめて、美しい写真に添えてある、撮った時の状況や、チョウの特徴を解説した文章に工藤さんのチョウへの思いが溢れています。また、カヴァーに載っている「寝ても覚めても チョウに夢虫」というコピーにもチョウへの愛を感じます。
きょうは、その本をもとに、同じ蝶々なのに翅(はね)の色を変える種や、アリを巧みに利用するチョウなど、意外と知られていない蝶々の生態についてお話をうかがいます。
☆協力:工藤誠也、誠文堂新光社


越冬する日本のチョウ
※日本には何種類くらいのチョウがいるとされていますか?
「240種くらいと言われることが多いです。ただ、いかんせんチョウは飛ぶ生き物なので、ほかの国で普段過ごしているチョウが台風とかで運ばれて、日本に飛んできて、まれに記録されたりだとか、毎年のように日本にはいるけど、実は冬に一度滅んでしまって、また次の年に来るっていうのを繰り返している種だとか・・・あと外来種とか、そういったものが結構多くあります。
記録のあるチョウをすべて数えたら300種を超えると思います。もっと厳密に昔から日本にいて、越冬しているみたいなやつだけを数えたら、200種よりちょっと多いくらいになるんじゃないかと思います」
●チョウというと、東京でも都市公園とか郊外の住宅地などで春から夏にかけてよく見かけますけれども、その頃が繁殖の季節ということなんですよね?
「春に出るチョウもいますし、夏に出るチョウも秋に出るのもいて、種数でいうなら夏が多いのかなとは思いますが、それぞれいろいろあると思います」

●工藤さんがお住まいの、メイン・フィールドの青森は冬の期間が長いじゃないですか。となるとチョウの活動期間は短くなっちゃうんですか?
「寿命自体は一個体一個体、そう大きく変わらないと思うんですが、どうしても春から秋までの時間や、夏自体も短くなりますので、いろんな種が同じタイミングで出てくる。で、たくさんの種が短い期間に一気に出てくるような状態になります。春から秋までの期間は、虫が見られる期間自体はちょっと短いですね」
●冬を越すチョウは結構多いんですか?
「日本に生息している都合上、何かしらの形では冬を越さなきゃいけないですね。成虫で冬を越すっていうことであれば、タテハチョウの仲間とか、シロチョウの仲間とかに一部成虫で冬を越す種がいて、そういった種が春早い季節に飛んでいます。あとは蛹とか、卵の殻の中で小っちゃい幼虫が冬を越すとか、卵で冬を越すとか、本当に様々な越冬体を持つものがいます」
同じ種なのに、翅の色を変えるのはなぜ?
※この本を読んで初めて知ったんですけど、季節の移り変わりで、翅(はね)の色を変える種もいるんですね?
「一個体の中で色や形が変わることは基本的にはないんですが、一生が短い生き物なので、春に出たあとの次の世代が夏に出たり、1年の中で多い種だったら5回とかそれ以上とか、発生を繰り返すような種が多々います。そういう中には、寒い季節に出現する時の色や形と、暑い時期に出てくる時の色や形が違っているものが結構います。
例えば、サカハチチョウっていう小ぶりなタテハチョウの仲間だと、春に出てくるやつは綺麗なオレンジ色ですし、夏に出てくるやつは、ほぼ真っ黒というとちょっと語弊があるんですが、かなり黒く地味なチョウになります」


●どうしてそういうチョウがいるんですか?
「季節で最適な色や形が違う。周りが枯れ草だらけのシチュエーションと、緑で覆われているシチュエーションで、色が違うのはひとつあると思います。
あとは、どうしても季節というか、世代によって個体の数というか、チョウの密度が変わってきますので、たくさんいる時はむしろ外敵に襲われにくいように地味な見た目をしているほうが有利だったり、逆に寒くてあまり生き残れないような時は、派手な身なりをして、異性の気を引いたほうがって言ったらいいんですかね・・・モテるような姿をしたほうが有利だったりということがあるんだと思います」
アリを巧みに利用するチョウ
※これも工藤さんの本で知ったんですけど、チョウの幼虫に餌を与えて育てるアリがいるんですね?
「そうですね。クロシジミとか、キマダラルリツバメとか、国内で知られているだけでも、その2種かな・・・アリから直接、口移しで餌を与えられて過ごします。特にキマダラルリツバメは、幼虫の最初から最後まで一貫して、アリから口移しで餌をもらって成虫になるはずです」


●チョウに尽くすアリっていう姿ですけれども、アリに何かメリットはあるんですか?
「シジミチョウの幼虫が背中に蜜腺と呼ばれるものを持っていまして、その蜜腺から名前の通り甘い蜜のようなものを出すんですよ。で、それをアリは好んで舐めるんです。なので、その蜜をもらえることがアリ側のメリットと言えばメリットです。
ただ、最近の研究で、必ずしもすべての種でそうなのか調べられているわけじゃないと思いますけど、少なくとも一部のシジミチョウが出しているその蜜は、アリ側からしたら好きであって、舐めている嗜好物質ではあるんだろうけど、舐めることで利益を得ていることになるのかはわからないし、どちらかというと寄生的な関係であるみたいなふうに言われることが多いです」
●なるほど〜。ほかにもアリを手なずけて、アリの巣に潜り込むチョウの幼虫もいるんですね。
「ゴマシジミの仲間は、ほかのクロシジミとか、さっきの口移しで餌をもらうシジミチョウ自体もそうなんですが、小っちゃい頃、別の植物を食べたり、アブラムシの汁を吸ったりして、小っちゃい幼虫時代を過ごして、ある程度まで大きくなったら、アリを呼ぶわけじゃないと思いますけど、うまいことやって、くわえてもらって、アリの巣に運んでもらう。
で、運んでもらって巣の中に入ったら、あとはしれ〜っと仲間のようなふりをして、ゴマシジミの幼虫だったらアリの幼虫を捕食しますし、さっき言ったクロシジミであれば、仲間のふりをして餌をもらうようなことを続けて育っていきます」

キラキラ光る、くるくる回る
※工藤さんが撮影している中で、いちばん驚いたチョウの生態はありますか?
「今言ったアリに寄生するシジミチョウの仲間は、特にすごい生態をしているチョウだと思います。それ以外にも、そうですね・・・ゼフィルスって呼ばれる翅が緑色にキラキラ光るミドリシジミの仲間がいるんですけれども、これなんかはそんなキラキラ光る必要があるのかな? って思うくらいキラキラ光る翅を持っています。

モルフォチョウとか、絵のモチーフになったりする青いチョウが海外にいますが、あれほど大きくはないですけれど、輝きの強さだけなら、それと肉薄するチョウが日本にもいます。
その仲間は成虫が一時期、限られた時間帯だけに陽の当たる空間に出てきて、1時間ぐらいだけ激しく飛び回って、オスとオスがお互いに追いかけ合った都合上、そうなるのかわかんないですけど、輪っかを描くようにって言ったらいいんですかね・・・くるくると二個体で追いかけ合って回るんです。それなんかを見ていると、なかなか不思議なことをする奴らもいるなと思います」
真っ赤なアカオニシジミ
※工藤さんの本の、12月30日のページに、この日は私の誕生日なんですけど、タイで撮影した「アカオニシジミ」というチョウの写真が載っていました。こんなに赤くてきれいなチョウがいるんですね。
「あれは東南アジアとか海外のチョウをひっくるめて、赤色のチョウの中ではトップクラスに美しい種のひとつじゃないかなと思います」

●南方に生息しているチョウは、びっくりするぐらいカラフルなんですね。
「そうですね。もちろん地味な種もたくさんいるんです。なんていうか昆虫はどうしても寒いところに行くと、種数が少なくなって同じ種がたくさんいて、暖かい地域に行くと、種数が多くなってその一種あたりの数が必ずしも多くないみたいな生き方というか生息をしているんですね。
暖かい地域に行くと、いかんせん種数が増えるので、その派手さのピラミッドみたいなものが、地味な種がとにかくたくさんいるけど、そのてっぺんにすごく派手なやつが少数だけいて、そいつらがかなり目立つみたいなところがあります。
例えば、大きくて緑色に光るトリバネアゲハの仲間であるとか、それこそ今言ったアオカオニシジミであるとかが、うわずみ的な存在にあたるのかなというふうに思います」
●日本で見られるチョウとの違いは、どんなところにあるんですか?
「いちばんの違いは、たぶん1年中何かしらいることだと、成虫が飛んでいることだと思います。あとは先ほど言った通り、少し一部派手な種がうわずみ的にいて目立ちますすね。
どうしても種数が多いので、ひとつの種が活動できる時間とか空間が限られてしまって、同じ場所に、例えば1日朝から晩までいても、30分ごとに違うチョウが現れるみたいな、すごく切迫したタイム・スケジュールの中で、いろんなチョウがひとつの空間に生息しているところが、熱帯とか暖かい地域の特徴かなと思います」
(編集部注:工藤さんは青森に冬がやってくると、海外へ。おもに東南アジアのタイ、ベトナム、マレーシア、台湾などにチョウを追い求めて出かけるそうです)
美しい翅は生き残るための進化
※工藤さんの本を拝見していて、改めて感じたんですが、チョウの翅の色や模様は、個性的で美しくて、まさに芸術ですよね。翅の色や模様を決定づける要因はなんでしょうね?
「チョウはどうしても弱い存在というか、生き物全般からしたら食べられて死ぬことがとても多い生き物だと思うんです。なので、そのチョウの色とか模様は捕食者に対する警戒というか・・・例えば、毒を持っているほかの虫に擬態するためのものであったりだとか、あるいは身を隠すためのものであったりすることが多いと思います。
あとは自分の配偶の相手を探すための標識的な模様であったりするとは思いますね。そういったところで自分の翅を綺麗に着飾ったり、あるいは地味に周りにとけ込むような斑紋を持つことで、うまく生き残るために進化した結果なんじゃないかなとは思います」
●では最後に、工藤さんにとってチョウの魅力とは?
「そうですね・・・昆虫の中ではチョウは、すごく大きい虫だと思うんです。シジミチョウは、チョウの中ではすごく小さい体のサイズのグループですけど、それでもちっちゃいもので1センチぐらいはある。でもほかの甲虫とかだと1センチだったら結構な巨大種なんですよ。なので、人の目で見て扱いやすいというか、分かりやすい体の大きさを持った分類群っていうのがまずひとつ魅力だと思います。
あとは色とか模様が鮮やかで目を引くことと、それからこれは体が大きくて観察しやすいっていうところにもちょっとつながる部分があるんですけど、昼活動するので、自分の目でそのチョウが実際に生きて活動しているところを見ることができるっていうのが魅力かなと思います。
例えば、蛾も僕は好きなんですけれども、蛾は夜何しているか実は知ることが難しくて、花に行って蜜を吸ったりする種もいるはずなんですが、ライトを当ててしまったらどうしても驚かれて、行動が変わってしまいます。自然な形で観察がなかなかできないというところがあるんです。
ただその点、チョウだったら、青空の下で花の蜜を吸ったりとか、交尾相手を探したりとかしますので、気軽にそういう姿を見ることができるのが魅力かなと思います」

(編集部注:工藤さんの撮影のメインフィールド、青森の野山でチョウが去年より少なくなっていると感じることはよくあるそうですが、多くなったり少なくなったりする「ゆらぎ」なのか、当たり外れなのかはわからないそうです。ただし、外れ年と思っていたら、いっこうに戻らない、復活しない。この十数年、そんな流れになっているとのこと。気候や環境の変化が蝶々にも影響を与えているのか・・・気になりますね。
また、今後撮りたいチョウについては、インドネシアやパプアニューギニアなどに生息している「トリバネアゲハ」を撮りたいとおっしゃっていました。てのひらサイズの大きなチョウで、翅の色も個性的で美しいので興味のあるかたは、ぜひネットで調べてみてください)
INFORMATION
工藤さんの新しい本をぜひご覧ください。四季折々のフィールドで出会うチョウの写真を日めくり感覚で楽しめて、美しい写真に添えてある文章にチョウへの思いを感じますよ。ページをめくるごとに、季節が進んでいく感覚も味わえます。「寝ても覚めても チョウに夢虫」な工藤さんの本、おすすめです! 誠文堂新光社から絶賛発売中! 詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎誠文堂新光社 :https://www.seibundo-shinkosha.net/book/science/85779/
2024/6/2 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. BUTTERFLY / BTS
M2. BUTTERFLY / DONAVON FRANKENREITER
M3. BUTTERFLY / R.KELLY
M4. BUTTERFLY / MARIAH CAREY
M5. Butterfly / 木村カエラ
M6. Butterfly / 笠井紀美子 with Herbie Hancock
M7. BUTTERFLY / GEORGE NOZUKA
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2024/5/26 UP!
◎田中 克(京都大学名誉教授)
『「森里海連環学」〜目に見えない「つながり」を紡ぎなおす。次世代の幸せのために』(2024.5.26)
◎本間希樹(ブラックホール研究の第一人者、「国立天文台 水沢VLBI観測所」の所長)
『ブラックホールとは!? 宇宙人はいる!? 暗黒物質はありがたい!? 〜宇宙は謎だらけ! だから面白い!』(2024.5.19)
◎後藤慎平(東京海洋大学の助教)
『自作の水中ロボットを持って南極へ。工学博士、奮闘す!』(2024.5.12)
◎『「モンベル フレンドフェアin九十九里」取材レポート!〜魅力的な九十九里エリアをもっと発信!』(2024.5.5)
2024/5/26 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、京都大学名誉教授の「田中 克(たなか・まさる)」さんです。
田中先生は1943年、滋賀県大津市生まれ。京都大学大学院と水産庁の水産研究所で、おもに日本海のヒラメやマダイ、有明海のスズキなど、稚魚の研究に40年以上、取り組んでこられたそうです。
そして、2003年4月に設立された「京都大学フィールド科学教育研究センター」の初代センター長に就任。ご自身の研究などから、森と海の関係性に着目し、「森里海連環学(もりさとうみ・れんかんがく)」を提唱。
現在も「森里海を結ぶフォーラム」や「“宝の海”の再生を考える市民連絡会」などで、精力的に活動されています。また「森は海の恋人」運動で知られる気仙沼の漁師さん「畠山重篤(はたけやま・しげあつ)」さんとは、活動をともにする同志的な関係でもいらっしゃいます。
きょうは、そんな田中先生に「森里海連環学」がどんな学問なのか、改めて解説していただくほか、有明海の再生を願う市民運動のシンボルにニホンウナギを掲げ、
「サステナブル・ウナギ ・ゴールズ」SUGsを提唱されているということで、そんなお話もうかがっていきます。
☆写真協力:田中 克

「森里海連環学」は『里』が肝心
※2003年から提唱されている「森里海連環学」とはどんな学問なのか、改めて教えていただけますか。
「ちょっと堅苦しい名前なんですが、基本的には森と海とは不可分につながっている。ところがその間の里は人の生活集団みたいなもんですから、その里の、都会も含めた人々の営みと、広くとっていただくと、その営みが海にも森にも少なからぬ影響を与えて、海と森の間の、命の最も大事な源である水の循環を壊してきていると。それが地球環境問題の根源のひとつで、それをもとのまっとうな形に直したいという思いの学問なんですね。
今までの学問というのは、客観的な事実を明らかにして論文にすれば、事が足りたと。でもここまで地球環境問題が深刻になってくると、研究者の役割もそこでストップするんじゃなくて、得られた科学的データを基にして、森とのつながり、自然の再生、それを壊してきた社会の仕組みの再生も含め、まっとうな方向まで戻す提案までできる学問になればということがひとつの思いですね。
それからもうひとつは、森は森、海は海、その間の里や、あるいは森と海をつなぐ川、それぞれ個別にこれまで研究も教育もされてきた。でもそれらは一体につながっていることがだんだん明らかになって、そういう個別細分化された学問じゃなくて、バラバラになった専門分野をもう一度つなげ直して、もうちょっと大きな視野で物を見て、物事が多様につながりながら地球が動いている、そういうメッセージを発したいという思いの学問になります」
●森と里と海は、川でつながっている。そのつながりを強く意識するようになったのは、何かきっかけがあったんですか?
「私は、もとは京都大学の農学部に在籍をしていたんですが、農学部はある面では総合学問領域で、森を研究する部門もあれば、海を研究する部門もあるし、里に関わる部門もあるし、川に関わる部門もある。でもそれぞれ10個ぐらいの学科で、森は森の林学科、海は海の水産学科・・・一切の交流がなかったんですね。
たとえば(農学部は)京都府にありましたから、京都府のいちばん代表的な森というのは、由良川という京都でいちばん大きな川の上流域に、森の研究や教育をする演習林、芦生研究林っていうのがあるんですね。そこから由良川が140キロぐらい流れて、若狭湾の河口近くに海の研究をする水産実験所がある。
同じ農学部であるのに何十年も一切、教育研究でつながりがなかったというのを、これはちょっとおかしいよっていうので、まずは森の教育研究施設と海の教育研究施設がもう一度、川を介してつながっているんだから、一緒にいろいろ進めましょうというのが思いのひとつにあります。
確かに森と海は川がつなぐんですが、最近の研究では見えない川があるんです。見えない川というのは地下水で、目に見えないつながりがある。ともすれば、見える川だけに注目しますけれども、地下水も含めて、本来は森と海を水がつなぐという意味では、森川海連環学でいいんですが、 そうではなくて、川の流域に住む私たちの暮らしのあり様、産業のあり様をもういっぺんちゃんと問い直すという意味で、間を『里』にしたんですね。そこが味噌になります」
「森は海の恋人」運動、畠山さんとは同志
※以前、この番組に「森は海の恋人」運動で知られる気仙沼の漁師さん「畠山重篤(はたけやま・しげあつ)」さんにも何度かご出演いただいています。畠山さんは牡蠣などの魚介類が育つには、川が運ぶ森の養分が欠かせないことに、いち早く気づき、気仙沼の海に注ぐ川の上流に、木を植える運動を長年続けていらっしゃいます。
田中先生は、畠山さんの活動に影響を受けた、そんなこともありますか?
「はい、結果的にはものすごく影響は受けているんです。畠山さんたちの、気仙沼の牡蠣やワカメの養殖漁師さんたちは、海が汚れてきて、それは自分たちが海を汚したわけではなくて、川の流域だとか森の荒廃だとか、そこに感覚的に気づかれたんです。それで漁師が山に登って木を植えようと。それが始まったのが1989年なんですね。それから2003年に京都大学に森里海連環学が生まれて、それまでは基本的には一切つながりがなかったんです。
私たち研究者が頭をひねって、これからこういう学問が大事だっていう思いを深めたら、既に現場の漁師さんたちは、そんなことは当たり前だと言って、行動に移されて10数年続けていた・・・。それでこれからは社会運動としての『森は海の恋人』運動と、それを支えながら協同する森から海までのつながりの学問、森里海連環学が、その後は一緒にお互いに助け合いながら動いてきた。ですから『森は海の恋人』のほうが先輩ですし、いろんな影響を受けております」

●では畠山さんとは、志を共にする同志のような関係なんですね。
「そうですね。(畠山さんとは)生まれも1943年で同い年ですし、それから私も、もともとは海の出身で、畠山さんたちは代表的な生き物として牡蠣を指標にして、牡蠣がまっとうに育つためには、森からの栄養分や微量元素が必要だということで、私は魚の研究でしたけれども、魚の子供たちが海辺の水際で育つのも全く一緒の原理だということで、思いはひとつですし、同い年だし、志が一緒ですから、むしろ私のほうが教えられながら一緒に歩んできているというのが現実ですね」
(編集部注:田中先生は、2011年3月11日の東日本大震災で壊滅的な被害を受けた気仙沼の、牡蠣やホタテなどの養殖業を1日でも早く復活させるために、全国の研究者に呼びかけたそうです。そして2011年4月に予備調査を行ない、5月には全国から手弁当で研究者が集まったということです。
畠山さんからは、牡蠣やホタテなどの養殖に欠かせない、植物プランクトンが回復しているかを調べてほしい、そんな要望があり調べたところ、予想以上の回復が確認され、養殖業再開への希望の明かりが灯ったとのこと。この調査は現在も続けられているそうですよ。
実は田中先生は、気仙沼の舞根湾(もうねわん)に2014年に設立された「舞根 森里海研究所」の所長でもいらっしゃいます。この研究所は、漁師さんが漁網などの道具を保管する小屋「番屋」を復活させる、日本財団の「番屋」の復興プロジェクトの一環として作られ、現在も研究者や学生さんの活動の拠点として大きな役目を果たしているそうです)

ニホンウナギのブックレット
※田中先生の活動はさらに加速し、2021年10月には「森里海を結ぶフォーラム」を発足。これは森の養分が海の養殖業を支えている仕組みは気仙沼に限らず、全国の主要な河川とその流域でも同じなので、森の人、海の人が一堂に介して相談や情報交換ができる場を作ろうということで、年に一回、フォーラムを開催。また、広場という名目で、隔月でオンラインでも開催しているそうです。
そんな田中先生は現在、「森里海連環学」を象徴する生き物といえるニホンウナギをテーマにしたブックレットを制作されています。企画と編集は田中先生なんですか?
「そうですね。一応、呼び掛け人的な役割をさせていただきながら(進めています)。ウナギというのはご存知のように、南の遠い海で生まれて、半年かけて日本にやってきて、川の入り口や汽水域や、場合によっては川の上流で、要するに森の中で育って、今度は子孫を残すためにふるさとに帰っていく・・・。どんなふうにして日本にやってきて、どんなふうにして向こうに帰るかっていうのはいまだに謎で、とっても面白い生き物だと。地球のことを我々人間よりもずっと長い年月をかけて、よく知っていると。
そういう大先輩を絶滅危惧種にしてしまった人間が彼らに謝って、彼らの賢さをもう一度学びながら、まっとうな自然や社会に再生したいと。そんなことで、ウナギはきっと迷惑でしょうね。そんな位置付けにされるのは、ほっといてくれって言われそうですけども・・・(笑)。
私たちに続く未来の世代がもうちょっと自然を楽しみながら、自然と共存できる、共生できる暮らしをするためには、最も身近な絶滅危惧種のウナギの、彼らが発信しているメッセージを聞き取って、そしてウナギと私たちが共に確かな未来を開こうよと、そういうことをまとめた本なんです。
(執筆者が)28名にもなると、いろんなかたがおられて、なかなか思うようには原稿が集まらないという・・・(笑)、でもほぼ集まりましたので、今年の土用の丑の日までにはウナギの声としての、いちばん端的には、野生の生き物ウナギにも、こんなに厳しい環境に追い込まれた彼らにも、裁判所に訴えて裁判ができるという、『自然の権利』と言って、今世界中でもそういうことが認知されているんです。
日本ではまだまだ認知度が低くて・・・ですからウナギ読本、ウナギ・ブックレットは、ウナギにもちゃんと自然をまっとうにしたいということを願う、訴訟する権利があるんですよって、そんな本なんです」
●その本は一般のかたでも入手可能なんですか?
「むしろ一般のみなさんにぜひ! 特に小学校高学年から中高生ぐらいの、これからの時代を担う人に、自然と共生するということの意味だとか、そういうことを世界に発信できる、そういう日本にしていきたいというので、むしろ若い世代の人に読んでもらいたいという本ですね」
「サステナブル ・ウナギ・ゴールズ」=SUGs
※去年の夏に長崎県諫早市で、「“宝の海”の再生を考える市民連絡会」という市民団体が発足したという記事がありました。この運動のシンボルが、ニホンウナギになっていますが、この市民連絡会の代表も田中先生なんですか?
「そうですね。これまで有明海、”宝の海”というのは本当に豊かな海だったんですね。貝も魚もエビもいろんなものがたくさん獲れて、獲っても獲っても獲り尽くせないぐらい豊かな海だったのが、いろんな問題が重なって、そういうものはだんだん獲れなくなってきた。

獲れなくなっただけじゃなくて、日本では有明海だけにしかいない魚介類が、これは中国大陸の沿岸に起源を持つ、氷河期の遺産的なすごく面白い生き物がたくさんいる。要するに生物多様性の宝庫なんですね。その生物多様性の宝庫で、漁業者にとっても暮らしが成り立つし、地域の経済も回る。そういう海が残念なことにこの半世紀の間にどんどんおかしくなって、今では”瀕死の海”と言われるぐらいになってしまった。
これまでは、そういうことに関心を持った地元のみなさんが、本当に頑張って再生を願っておられたんですが、裁判に訴えてもなかなか認められない。ですから、もう地元のみなさんだけの話ではなくて、この国が多かれ少なかれ関わった、そういう水際を大事にしてこなかったツケとして、今まで関わった人たちだけじゃなくて、もっと広くみなさんにというので、今進めつつあるということですね」
●目指しているのがSDGsならぬSUGs「サステナブル・ウナギ・ゴールズ」と記事に書いてありました。これにはどんな思いが込められているんですか?
「ひとつは有明海全体の、いちばん上に筑後川が流れて、その河口が柳川市なんですね。柳川市は堀割が巡らされて、そこにはいっぱい昔はウナギがいたと。今もウナギのせいろ蒸しで、すごく有名な場所なんですね。
有明海の、筑後川から流れた砂や水が最後に半時計回りに流れてたどり着くのが諫早湾で、諫早湾の湾奥には本明川という川があって、牡蠣とウナギがたくさん獲れて、そこもウナギがすごく大事な場所なんです。
でも堤防を作ったりすると、なかなかウナギが来なくなったというので、有明海の森とのつながりの、命の循環を考える上でウナギがいちばんわかりやすいし、しかも人間が絶滅危惧種にしてしまった彼らと共に生きることが、人間にとってもすごく大事ですよっていうので、SDGsのDはディベロップメントですよね。
これはやっぱり人間中心の人間のためのディベロップメント・・・そうじゃなくて、自然とともに共生するためには、野生の生き物の知恵を借りて物事を考えていくのが大事だというので、これまたウナギに無断でSUGsにしてしまったということです(笑)」

(編集部注:「“宝の海”の再生を考える市民連絡会」には共同代表として、元テレビキャスターの野中ともよさんや、ファッション・モデルのNOMA(ノーマ)さんも名を連ねているそうですよ)
シーカヤックで海遍路
※田中先生は70歳を前にシーカヤックを始め、高知大学の名誉教授「山岡耕作(やまおか・こうさく)」さんたちが2011年にスタートした、四国お遍路の海版「海遍路」に2年目から参加。東北、九州、三浦半島、山陰など、日本の漁村をめぐる旅を、いまもこんな感じで続けているそうですよ。
「年に1週間から10日間ぐらいですけれども、数人のグループ、カヤック2艘ぐらいで、すべての生活機材を積んで、たどり着いた漁村で泊まって自炊をしながら粗食に耐えていると、漁師さんがもの言わず“これ食べろ”って魚をくれる。そうすると自然な対話ができるんですね。もういっぺん、海からものを考えようという旅になっています」
●シーカヤックの魅力ってどんなところにあると思いますか?
「漁師の人から見れば、すぐにひっくり返ってしまうように見えるんですけど、意外に安定性もある。まずは自分の力で漕がないと目的地に行けない。でも頑張れば目的地にも行ける、そんなところですね。
要するに現代社会が失ってしまった、何かみんなレールの上に乗せられて、自分が行きたいとこじゃないところに連れていかれるようなこととは違う。その代わり危険なことも体感しながら、逆に新しい出会いがある、そんないろんな魅力がいっぱい! とても面白いですね。
もともと日本人がどこから来たかというのも、大陸説もあるし海洋説もあるし、かつての我々の大先輩もあんなボートの原型みたいなので、暮らしを切り開いてきたのかもしれない。
そんなことも思うというのと、もうひとつは、一般の船よりはお尻が水の中に入るぐらいの位置ですから、目線が言ってみればアメンボ目線みたいに・・・ですから本当に海の生き物たちと同じ目線でものが見られるというのも特徴かもしれませんね」

「つながり」をもう一度大事に
※「森里海連環学」を提唱されて20年以上が過ぎました。いまどんな思いがありますか?
「私自身は提唱して4年で現役を退職して、森里海のやっぱり”里”が鍵だと、我々自身の振る舞いですね。ですから、それを畠山さんたちと一緒に現場で取り組んできた。そういうのと、現役の京大フィールド研の研究者のみなさんは研究教育の分野、それが今、両方がかさ上げしながら少しレベルアップして、幸いなことに畠山さんのお力がすごく大きいと思いますが、テレビや新聞とかいろんなニュースにも森と海のつながりが、比較的当たり前のように出始めたというので、それは非常に喜ばしいんです。でも、それで私たちの行動がどう変わるかというのが次のステップで、それをもうちょっと頑張ってやれればという思いでいます」
●では最後に、リスナーのみなさんに特に伝えておきたいことなどがありましたら、お聞かせください。
「いろんなことが本当はつながっている。ところが目先の暮らしの利便性だとか直近の経済の成長とか、どうもそちら側に舵が切られすぎて、この世に自分たちが生まれてきてよかった! っていうような思いが、なかなか実感できない世の中です。
それは目に見えない、さっきの川じゃないですけれど、地下水が大事な役を果たしているように、縁の下の力持ち的な、目に見えないつながりをもう一度丹念に紡ぎなおす。そして同時に次の世代が幸せになるにはどうしたらいいかっていうのをいちばんに、物事を考えられるようになり行動できれば、地球ももうちょっとよくなるし、日本社会もよくなるんではないか・・・。ですから、いろんなことがつながっていることをもう一度大事にしましょうよ! というのが、いちばんの思いですね」

INFORMATION
ぜひ田中先生の活動にご注目ください。先生が代表を務める「森里海を結ぶフォーラム」や「“宝の海”の再生を考える市民連絡会」、そして畠山さんの「森は海の恋人」運動のサイトを定期的にチェックしていただければと思います。
◎森里海を結ぶフォーラム :
https://morisatoumi-forum.studio.site
◎“宝の海”の再生を考える市民連絡会 :http://www.einap.org/jec/subcategory/projects/49
◎森は海の恋人 :https://mori-umi.org
今年の「土用の丑の日」に出す予定で進めていらっしゃるニホンウナギのブックレット、発売日や入手方法については、分かり次第、この番組または番組ホームページでもお知らせします。
2024/5/26 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. OCEAN OF LIGHT / IN MOOD
M2. RIDE THE RIVER / J.J. CALE & ERIC CLAPTON
M3. OCEAN (FEAT. KHALID) / MARTIN GARRIX
M4. BOOK OF DREAMS / SUZANNE VEGA
M5. DROP IN THE OCEAN / MICHELLE BRANCH
M6. THE RIVER OF DREAMS / BILLY JOEL
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2024/5/19 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、ブラックホール研究の第一人者、「国立天文台 水沢VLBI観測所」の所長「本間希樹(ほんま・まれき)」さんです。
本間さんは1971年、アメリカ・テキサス州生まれ、神奈川県育ち。東京大学大学院から国立天文台の研究員などを経て、2015年より、現職。そして国際的なプロジェクト「イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)」の日本チームの代表としても活躍されています。
そして、そのEHTプロジェクトの大きな成果として2019年4月に世界で初めて、ブラックホールの画像を公開し、大変話題になりました。その時も取材が殺到する中、お電話でこの番組にご出演いただき、お話をうかがっています。
きょうは、そんな本間さんが出された新しい本『深すぎてヤバい 宇宙の図鑑〜宇宙のふしぎ、おもしろすぎて眠れない!』をもとにブラックホールや天の川の謎、そして果たして宇宙人はいるのかなど、宇宙や天文の、不思議や疑問をわかりやすく解説していただきます。
☆写真協力:講談社

宇宙でいちばん変な天体!?
※本間さんに、宇宙や天体の不思議や謎をうかがう前に本間さんが所長を務める「国立天文台 水沢VLBI観測所」について、少し説明しておきましょう。
岩手県奥州市にある、この観測所は120年以上前に設立され、その後、国立天文台の一施設となったそうです。観測所の名前にある「VLBI」とは、電波望遠鏡を使って、特殊な観測をする方法や技術を表わす専門用語。宇宙から来る電波を、岩手のほか、鹿児島や小笠原の父島、沖縄の石垣島などにもある観測所の電波望遠鏡がとらえ、総合的に分析するそうです。
本間さんいわく、複数の観測所を組み合わせることで「視力」があがり、遠くの小さな天体が見えるようになるそうです。このVLBIはもちろん、ブラックホールの研究にも使われています。
それではまず、本間さんのご専門ブラックホールとは、いったいどんな天体なのか、改めて教えていただけますか。
「ブラックホールは本当に謎めいた天体です。宇宙でいちばん変な天体だと言って間違いないんじゃないかと思うんですけど、とにかく重力が強いんですね。重力が強いからこそ、なんでもかんでも吸い込んでしまって、二度と吐き出すことがない。光が入っても出てこないし、物が入っても二度と出てこない。何も出てこないってことは真っ暗になるっていうことですよね。ブラックホールは英語で”黒い穴”という意味ですけど、まさに真っ黒な球体のような、なかなか難しい天体で、本当に宇宙でいちばん変な天体です」
●どんなものでも飲み込んでしまうんですね?
「どんなものでも吸い込んでしまいますね。で、入ったものは絶対出てこない。ほんとに不思議な天体ですね」
●画像として公開されたブラックホールはどこにあって、どれくらいの大きさだったんですか?
「いちばん最初に撮ったブラックホールは天体でいうとM87っていう、銀河の真ん中にあったブラックホールなんですね。M87をいちばんわかりやすくいうと、ウルトラマンの故郷だって言えば、たぶんいちばん馴染みがあるんじゃないかと思うんですけど、太陽みたいな星が1兆個ぐらい集まったような、とんでもなく大きな天体なんですね。その真ん中に巨大なブラックホールがひとつあって、それを世界中が協力したVLBIで 、むちゃくちゃ視力を上げてみたらブラックホールが見えた! それが2019年の発表ですね」
●どういう感じだったんですか?
「ドーナツみたいな写真を見ていただいたと思うんですけど、穴が開いている状態ですよね。真ん中は真っ暗になっているんですけど、その真ん中の黒い部分、ドーナツの穴の部分がブラックホールの影なんです。だから、なんでもかんでも吸い込んでしまう。天体だからそれ自身の写真を撮ることは、実は不可能なんですね。でも周りに光とか電波が漂っているのを背景にして、影として映し出したのがこのドーナツの写真なんです」
(編集部注:2019年4月に、世界で初めて公開したブラックホールの画像は本間さんが日本チームの代表を務める国際プロジェクト「イベント・ホライズン・テレスコープ」が成し遂げた、天文学の歴史に残る大きな成果なんです。
このプロジェクトには世界20カ国以上から、同じ夢を持った300人を超える研究者が集い、世界中の複数の電波望遠鏡を結合させて、地球を巨大な電波望遠鏡にするという、まさに地球規模の活動を行なっています)

ブラックホールを画像から動画へ
※現在、この「イベント・ホライズン・テレスコープ」では、どんなことに挑んでいるのでしょうか?
「ブラックホールは今まで写真が2枚撮られているんですね。M87と、もうひとつは私たちの天の川の、巨大ブラックホール『射手座Aスター』って呼ばれている天体なんですけど、そのふたつが静止画として撮られている状況なんです。
実は3つ目はないんです。地球と同じ大きさの電波望遠鏡を合成して、今見えそうなブラックホールはその2個しかないので、3つ目をやるっていう方向ではなくて、次は動きを見たいと、そういうことを考えていますね。
というのは、ブラックホールはなんでもかんでも吸い込む。だからガスがぐるぐる回りながら落ちていく。光もぐるぐる巻きつきながら吸い込まれていく。一方で完全に吸い込みきれなかったものが、一部『ジェット』っていうもので外に飛んでいくんですね。水鉄砲の水がシューって飛ぶような、あんなイメージを持っていただくといいんですけど・・・。
ということで、動きが非常に激しいはずなんですよ。なので、動きを見たいので、そうすると1枚の写真ではダメで、そのデータを積み重ねて何年もやって、あと解析も工夫すると、今度はガスの動きとかそういうものが見えてくるんじゃないかなっていうふうに期待しています」
●静止画だけでもすごく大変なことだったと思うんですけど、それで今度は動きとなると、またもっともっと大変なことになるんですよね・・・?
「大変ですよね。動画といってもみなさんが期待しているような、本当に綺麗な動画になるのは何年かかるかわからない。最初はコマ撮りで1コマ2コマ3コマって、ちょっと動いたかなっていうのが見えるかぐらいのところが当面目指していることですね」
●うわ~、でも動きで見られたらすごいですね!
「はい、それでちょうど、今年の1月に発表した成果として、2コマ目の写真が撮れたっていう・・・M87を2017年に観測した画像と、2018年に観測した画像、ようやく2枚目があって比べることができて・・・そうするとやっぱり1年でほんの少しだけ明るい場所が動いているんですね。これを見るとやっぱり動画にしたほうがいいよなっていうのが明らかになったので、あとは着実に頑張って続けていきたいなって、そんなふうに思っています」
●いや〜、なんか夢が広がりますね!
「子供の頃、教科書の端っこにパラパラ漫画とか描いたと思うんですけど、ようやく2個目が書き終わった、そんな状態ですね」
重力のない宇宙は、誰もいない宇宙!?
※ここからは、本間さんの新しい本『深すぎてヤバい 宇宙の図鑑〜宇宙のふしぎ、おもしろすぎて眠れない!』をもとにお話をうかがっていきます。
138億年前に誕生したとされる宇宙は謎だらけで、そんな宇宙の不思議を、一般のかたにわかりやすく解説してあるのが、本間さんの本です。まずはこんな話題から。
本に「宇宙でいちばん大事な力は重力」と書いてありました。これはどういうことなんですか?
「重力がないと天体が存在しないんですね。天体はすべて重力で引っ張られて一箇所に固まっていますから、重力がない宇宙はまず銀河ができません。それから銀河の中で星ができません。だから太陽もできない。地球も重力で一箇所にまとまって球体になっているので、重力がなければ地球もできないということで、重力のない宇宙は誰もいない宇宙ですね。本当に何も存在できない世界なので、それはやっぱり困りますよね」
●とっても大事な力なんですね!
「だから重力が・・・普段はどっちかっていうと、たとえば階段を上がって疲れるとか、ああいうのは全部重力のせいで疲れちゃうわけですけど、重力に逆らって上がるので・・・。だから普段は厄介な存在だなって、みなさんは思うかもしれないですけど、重力がないと僕らは存在しないですね」

●そうなんですね。天の川は本当に流れているというふうに、これも本に書かれてありましたけれども、どういうことなんですか?
「天の川、ご覧になったことはあります? 」
●いや〜ないですね〜。
「千葉だとこの辺は明るいから、なかなか見えないかもしれないですね。もっと暗いところに行って、月がない夜に夜空を見上げて、空のある部分が白くなっているんですけど、それは薄っぺらい、回転している銀河の中から見ているものなんです。
どう言えばいいかな・・・どら焼きと言ったら、ちょっと極端なんですけど(笑)、ああいう平べったいものを想像していただいて、それを横から見ているようなイメージですね。天の川も含めて銀河は回転していますので、ある特定の方向に星が動いているんですね。
もちろん僕たちの目では、それを見ることはできないんですけど、電波望遠鏡とか、先ほどのVLBIを使うと、たとえばきょうの星の位置と明日の星の位置は違って見えるので、みんなが天の川の向きに沿って、ある方向に動いていくんですね。
だから、そういう意味でいうと、流れているんですけれど、望遠鏡で見ないとわからないですね。でも昔の人は天の川を、本当に”川”という文字を当ててるぐらいですから、やっぱり流れを想像しながら見ていたと思うんです。人間の想像力ってけっこう当たっているので、すごいなと思いますよね」
●この本には「ダークマター」という言葉もありました。日本語にすると「暗黒物質」ということで、映画『スターウォーズ』の世界だなって感じたんですけど・・・。
「そうですね。暗黒って出てくると、ちょっと悪いやつに見えちゃうんですけど(笑)、英語でいうと『ダークマター』ですけど、これも天文学あるいは宇宙にまつわる最大の謎のひとつですね。
どういうことかっていうと、これは『見えない質量』。さきほど天の川の話をしましたけど、天の川はまず見上げると星が光って、白く光ったのは星で、その星の重さを全部足し上げたのと、天の川全体の重さを測ったのを比べると、星だけじゃ全然足りないんですね。どこかに見えない奴らがたくさんいるはずだっていうことで、その見えないもののほうが実は見えている星の重さよりずっと重いんです。
その見えない質量のことを暗黒物質、あるいはダークマターで、もう100年近くあるということはわかっているんですけど、みんなそれがなんだろう? って知りたいと思っているんですが、これはまだ決着がついていないんですね」
●もう謎だらけですね〜。
「謎だらけですね! さきほど悪役みたいにおっしゃったんですけど、実はダークマターはすごくありがたい存在で、もし宇宙にダークマターが存在しなかったとすると、その宇宙にはやっぱり重力が足りないので 、星も銀河もできないですね。だから、なんだかよくわからない。しかも名前からするとちょっと悪役に見える暗黒物質、ダークマターですけど、これは宇宙に天体が誕生して、最終的には人類が誕生した最大の立役者のひとつ、そんなふうに言っていいんじゃないかと思いますね」
宇宙人はいる? いない?
※ズバリ、お聞きします。宇宙人はいると思いますか?
「はい、これもみなさん気になりますよね!」
●気になります!
「これは僕の個人的な見解ですけど、必ずいるでしょうね」
●必ずいる! その理由は?
「宇宙人が存在するっていうことは、もうこの地球で証明されているんです。僕らは宇宙人なんですよ。宇宙人の一種ですね」
●私たちも宇宙人・・・!?
「宇宙人の一種なので・・・だから宇宙では、ある条件が満たされれば・・・地球の場合ですけど、地球のように適度な温度があって、適度な環境があれば生命が誕生し、それが進化して少なくとも地球人レベルの文明を持ったわけですね。これはもう間違いない事実としてあるので、あとはそれが本当に地球だけなんですか? ほかでも起きるんですか? っていう確率の話になるわけですね。
宇宙にはどれぐらい星があるかって考えると、天の川の話、私たちが住んでいる銀河でも、少なくとも太陽みたいな星が2000億個あると・・・。その周りに惑星もいっぱい見つかっているので、地球にしか生命がいないって考えるのはやっぱり変かなと・・・。しかも天の川の外に出ると今度はその天の川みたいな銀河が無数に、あと数千億とか、見える範囲だけでありますので、そこまで数えたら必ずどっかにいると・・・。
問題は彼らに会えるかどうかですよね。それは別ですね。UFOに乗ってここに来ているかって言われれば、まあ来てないだろなと・・・(笑)」

●なるほど! 宇宙開発がどんどん進んで地球以外の星に住めるようになったら、本間さんはどの星で暮らしたいですか?
「それもはっきりしていて、やっぱり地球ですね!」
●そうなんですね! どうしてですか?
「もちろん宇宙人が住んでいる星とか、生命がいる星はあると思うんですけど、たぶん地球人にとってはあまり住み心地がよくないんじゃないかと・・・。たとえば暑すぎたり寒すぎたり、あるいは全然違うシステムの生命がいたりして、やっぱり地球は僕らにとって素晴らしい環境であるのは、宇宙をくまなく見渡して探したとしてもこれほど住みやすい、僕らにとって住みやすいふるさとはないと思います」
●そうですね。地球がいちばん!
「(ほかの星でも)ちょっとどういうところか行ってみたり、様子をうかがってみたいなとは思いますけど、やっぱり自分の星がいちばん、それはもう間違いないと思いますね」
宇宙人、大発見!?
※本間さんがいま取り組んでいる研究はなんですか? やはりブラックホールでしょうか?
「そうですね。ブラックホールはもちろん! 一方で質問をいただいた宇宙人、これも科学としてやっぱり真面目にやりたいということで、宇宙人が何らかの理由で電波を出して、たとえば放送でラジオかテレビをやっていれば、電波が出てきますし、あるいはもっと積極的に地球人に気がついて、電波を送ってくれているかもしれないですよね、コンタクトを取ろうとして・・・。
そういうものをキャッチすることが、宇宙人を見つけるいちばんの近道だというのが今、天文学者の間で言われています。そうすると電波望遠鏡でいろんな星を順番に探していく、そういうことをやる。僕ら観測所でも試験的にですけど、そういう観測を始めていますので、こればっかりはいつ見つかるかは全くわからないんです。宝くじを買うような部分もあるんですが、ぜひ宇宙人がいるかっていうことを研究としてさらに発展させたいなと・・・」
●ぜひ解き明かしていただきたいです!
「見つかったら見つかったで、もちろん大発見だし、見つかんなかったら見つかんなかったで、地球っていうのはやっぱり本当に貴重なんだっていうことがわかるので、たぶんどっちに転んでも地球人にとっては非常に意味のあることだと思いますね」
●なるほど・・・。本間さんが好きな星空で、この季節とかあるんですか?
「僕は天の川に関わる研究をずっとしてきたので、やっぱり天の川という天体、星空の一部ですけど、それが好きですね。天の川って非常に大きいので、何座とかそういう星座では言えないんですけど、暗いところに行って、たとえば私は仕事で沖縄の石垣島に行きますけど、そこで見る天の川が本当に素晴らしいです。何度見ても心が洗われるというか、素晴らしいですね。
みなさんもちょっと暗いところ、街明かりから離れた場所に行くチャンスがあったら、ぜひ天の川を見てほしいですね。夏のほうが見やすいので、これから夏にかけて非常にいいシーズンになりますから」
●天文学を志す学生さんですとか、宇宙に携わる仕事がしたいと思っているかたに、ぜひアドバイスをお願いいたします。
「宇宙に関わる仕事をするときに、宇宙に対する思い、情熱だったり、あるいは愛情って言ったらちょっと変かもしれないですけど、やっぱり宇宙が好きで、その謎を解き明かしたり、あるいは宇宙に関わる何かを自分で開発したいってその思いですよね。
最後はそれが決めるので、若い人に宇宙を目指したいんだったら、宇宙に対する熱い思いをまず磨いてほしい。いろんなことに興味を持ったり、やっぱりそれが大事だと思います。ぜひ宇宙に対する思い、憧れ、そういうものを毎日、少しずつ育ててほしいなって、そんなふうに思います」
INFORMATION
『深すぎてヤバい 宇宙の図鑑〜宇宙のふしぎ、おもしろすぎて眠れない!』
この本では宇宙と生命、太陽系、星と銀河などに関する不思議や謎がわかりやすく解説。好奇心をくすぐられる見出しとともに、写真やイラストを豊富に掲載。見開き2ページで完結するので、とても読みやすいし、興味のあるところから読めますよ。漢字にはふりがながふってあるので、お子さんにもおすすめです。
講談社から絶賛発売中! 詳しくは出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。
◎講談社 :https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000379061
本間さんが所長を務める「国立天文台 水沢VLBI観測所」のサイトも見てください。
◎国立天文台 水沢VLBI観測所 :https://www.miz.nao.ac.jp
2024/5/19 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. FANTASY / EARTH, WIND&FIRE
M2. GALAXIES / OWL CITY
M3. STARS / SIMPLY RED
M4. DARKSIDE / ALAN WALKER
M5. 瑠璃色の地球 / 松田聖子
M6. SPACE COWBOY / JAMIROQUAI
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」