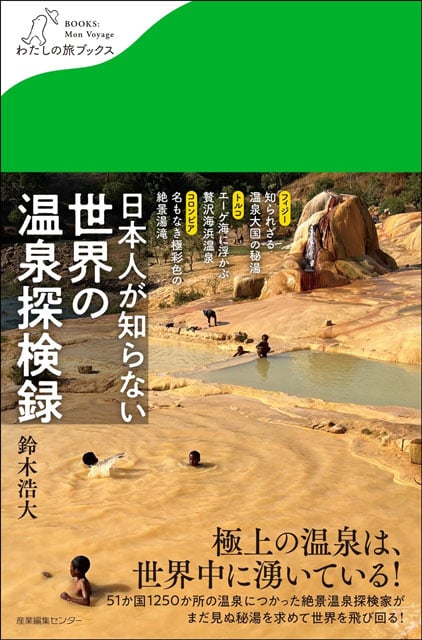2023/8/13 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、苔クリエイターの「石河英作(いしこ・ひでさく)」さんです。
石河さんは1977年、東京都生まれ。もともと植物好きだった石河さんは2013年に苔の専門ブランド「道草michikusa」を立ち上げ、ネットで苔テラリウムを販売しているほか、you tubeの道草チャンネルでその作り方や育て方などを発信されています。
そして先頃、『はじめての苔インテリア〜苔テラリウムから苔玉、苔盆栽まで』という本を出されました。きょうはそんな石河さんに、初心者向けに見ているだけで癒される苔テラリウムの作り方などをうかがいます。
☆写真協力:石河英作

道端の苔に日の目を
※石河さんは、もともと植物に関係するお仕事をされていたそうですが、苔を専門にしようと思ったのは、どうしてなんですか?
「卒業してから贈答用の胡蝶蘭とか、ああいう蘭のお花を開発している会社に勤めていたんですよ。蘭のお花って華やかで、ギフトでもらってとか、そういうイメージがあるじゃないですか」
●存在感もありますしね。
「存在感もあるし、高級っていうような・・・そういうのはそういうので楽しくやっていたんですけど、あれは育てるっていうよりは、胡蝶蘭も開店祝いとかでいただいて、そこで一回終わってしまうみたいな感じがして・・・自分で何か植物の仕事を始めるなら、育てることをやりたかったんですよね。
で、そういうふうに考えた時に、蘭の足元にも苔を使ったりとかっていうのがあるんですよ。それって苔が脇役っていうか添え役というか、蘭の日陰にちょっと使うだけっていう感じがするじゃないですか。でも苔って日本にいっぱい生えているし、国歌にも歌われているのを考えた時に、もっと日の目を当ててあげることができたら、みんな楽しめるのかなと思ったりとか・・・」
●確かに国歌にも出てきますね!
「出てきます。苔のむすまで、って・・・」

●そうか、そうですね!
石河さんが立ち上げられた苔の専門ブランド『道草michikusa』、すごく素敵なネーミングだなと思ったんですけど、どんなコンセプトなんですか?
「ふたつの思いを込めています。ひとつは本当に道端の草、ありふれているものって、その辺にも生えるんで、強いじゃないですか。そんなに育てる対象にされてない、それを何か工夫してあげるとかっこよく見えたりとか。
実は日の目を浴びてないんだけど、この器に入れてあげたら、すごく引き立つものって多分まだまだ溢れていて、そういったものに注目したい、道端に生えている草にも注目したいっていうのがひとつと・・・。
あとは、都会で働いていて疲れちゃうみたいな、日々忙しくてっていうことがあるのを、育てるだけじゃなくて、道草するように植物に触れて・・・今メインでやっている、ガラスの中で育てるテラリウムも、自分で作って育てるみたいなのが楽しかったりするので、それって自分の生活の中で、すごくスローな時間だと思うんですよね。
苔とかそういう小さい植物って、成長していくのもすごくゆっくりで、日々見ていても全然変化がなくて、1ヶ月2ヶ月ぐらいすると、ちょっと大きくなっていたぐらいのペースの成長の仕方なんですよ。それってこの都会の忙しさと時間軸が違うっていう感じがあって、そういう部分で道草するようにこの植物を愛でていただきたいなっていう、そういう思いとそのふたつが込められています」
(編集部注:小さな植物「苔」には、一般的な植物のように、水や栄養を吸い上げる根などがなく、葉っぱや茎から直接、細胞に取り込むそうです。根の代わりに「仮」の「根」と書く「仮根(かこん)」という器官があり、それを使って石や木に体を固定しているとか。
そんな苔植物は「蘚類(せんるい)」「苔類(たいるい)」そして「ツノゴケ類」という3つのグループに分類され、園芸用に育てられているのは「蘚類」に属する種類だそうですよ)

ジメジメ好き、カラカラ好き!?
※日本には何種類くらいの苔がいるんですか?
「日本に生えているものでも毎年(新種が)見つかるので、正確な数は言えないんですけど、現在1800種類超えぐらいな感じですね。世界を見ると18000種類ぐらいいるそうです」
●どれも同じように見えますけど、違うんですよね。
「プロの人が見ても、実は区別がつかないぐらいわずかな差だったりするんですよ」
●なのにたくさんの種類があるんですね。
「それも面白いですよね。種類を見るのにまずはルーペ、虫眼鏡を使って観察するのはマストですね。その先に細かい種類まで見ていこうと思うと、顕微鏡で葉っぱの形とかを見たりして、種類を特定していくっていう、すごく狭いジャンルですね」
●花は咲いたりしないと思うんですけれども、どんなふうに増えていくんですか?
「そうなんです。苔は花は咲かない植物で、胞子を使って基本は増えていきます。胞子っていうのは、苔には基本オス、メスみたいな、雄株と雌株・・・たまに合体している同種っていうのがいるんですけども・・・雄株と雌株があって、それが受精すると胞子体っていう球状のものがぴょこんと出てきて、その胞子体の中にはすごく細かい胞子って呼ばれるものが詰まっています。
その胞子が風とかでパーッと飛ばされて、いろんな場所に行き着くんですよね。その場所がたまたま 苔にとって生えやすい居心地のいい場所だと、そこから胞子が発芽して新しく苔が増えていくというような増え方をしています」
●繁殖力は強いほうなんですか?
「どう言ったらいいんだろう・・・みるみるどんどん広がっていって、この敷地を埋め尽くすみたいな、空き地に雑草が生えるみたいな意味での繁殖力っていうのは、そんなに強い植物ではないんですね。逆にほかの大きい植物が生えないような場所、そういった場所にも適応できるっていうのは苔のすごさです。
海浜幕張の駅からここに歩いてくるまでの間でも、道路脇とかをよく観察すると、日当たりがいいところにも生えていたりします。苔はすごくジメジメしたところだけってイメージがあるんですけど、日本に1800種類いる中には、ジメジメが好きなやつもいれば、カラカラが好きなやつもいたりします。
大きい植物が生えるような草地とかにいっちゃうと、体が小さいので苔って負けちゃうんですよ。いろんな隙間隙間、ほかの植物が来ないところとか・・・で、苔同士の中でも争いがあるわけです。同じ石の上にいろんな苔の胞子が落ちた時に、誰がいちばん勝つのかみたいなところの争いがあって、その争いに勝つために、ほかの苔にはやれない場所に、俺はやれるぜみたいなところで居つけるというのが特徴ですね。
だから繁殖力っていう意味でいうと、ほかの植物が行けないところに行けるので、すごく繁殖力があるみたいなイメージもあるんだけど、ほかの植物が居心地のいいところでは完全に負けるっていう・・・」
(編集部注:街中でよく見られる苔は、ジメジメしたところが好きな「ゼニゴケ」、そして道路脇など日当たりの良い場所を好み、乾くと銀色に見える「ギンゴケ」、その2種類だそうです)
テラリウムの語源は、ラテン語で「テラ」は陸地、「リウム」は場所を意味する造語で、密閉された透明なガラスケースの中で、陸上の生き物を育てる方法のことを、テラリウムと言うそうです。
その起源は19世紀のヨーロッパで発明されたガラスの容器、その名も「ウォードの箱」。当時、世界中の珍しい植物や、役に立つ植物を探し求めて、プラントハンターが中南米やアジアに渡っていました。移動手段は船だけだったので、長い船旅の間、満足に水やりもできず、また潮風にさらされることもあり、採取した植物を生きたまま持ち帰るのは、とても難しいことでした。
それを解決したのが、イギリスの医師ウォードで、ガラス容器の中では水分が循環することを発見し、「ウォードの箱」を開発したそうです。テラリウムにはそんな歴史があったんですね。
初心者向け「苔テラリウム」の始め方
※石河さんが先頃出された本『はじめての苔インテリア〜苔テラリウムから苔玉、苔盆栽まで』には苔テラリウムの作り方などが載っています。初心者におすすめの苔や作り方を教えてください。まずは、どんなガラス容器を用意すれば、いいんでしょうか?

「蓋ができるガラス容器・・・初心者の方だとあんまり小さすぎると、ピンセットで植えるので、結構器用じゃないと大変なんですよ。雑貨屋さんだとか100円ショップでも、小さめ小瓶とか買えるんですけども・・・だいたい8センチから10センチぐらい直径がある、口が広い容器のほうが手も入るのでいいですね。それで蓋ができるもの。テラリウムは容器の中に湿気を保てるのがポイントになりますので、蓋ができるものを選んでください」
●道具はどんなものが必要ですか?
「道具は最低限、ピンセットとハサミと、水やりをするのに霧吹き、この3つがあれば大丈夫です」
●すごく手軽に始められそうですね。
「そうですね」
●初心者にはどんな苔がおすすめですか?
「苔の種類も本を見ていただくといっぱい出ているんですけど、種類によって育ちやすい育ちにくいが当然あります。初心者の方だと『ヒノキゴケ』っていう種類と『ホソバオキナゴケ』って種類、この2種類が特に丈夫なのでおすすめです。
ホソバオキナゴケはちょっと背が低くて、テラリウムで芝生とか草原っぽいようなイメージで植えるのに向いているものですね。ヒノキゴケはちょっと背が高めの種類なので、(その2種類を)合わせると、草原の中に木が生えているみたいな景色を作ったりとかもできるので、このふたつをまず覚えてもらうといいと思います」

●これは、販売されている苔を使うんですか?
「そうですね。今おすすめした2種類もそうなんですけど、テラリウムに使える育てやすい苔は、どちらかというと街中に生えている苔よりも森の中、常にしっとりした環境に生えているものが育ちやすいんですね。
街の中って公園とかでも、じめっとした時間もあれば、結構ドライになる季節とかドライになる時間もあるじゃないですか。そういったところに適している苔が生えているので、瓶の中に安易に入れてしまうと、結構すぐダメになります。だから苔だからなんでも瓶の中に入れたらいいのかっていうと、そうでもないんですよね」
●なるほど〜! 日頃のお世話の点で注意すべきことってありますか?
「基本のお世話は、だいたい2週間に1回ぐらい霧吹きで、シュッシュぐらいじゃダメなので、よく湿るぐらい水をかけてあげる・・・苔を植える時に下にテラリウム用の土を敷くんですけれども、その土もしっかり湿らせるぐらいに水をあげるんですが、それも毎日あげる必要はなくて、2週間で忘れそうだったら、毎週1回は苔を観察する日 みたいなのを設けてもらって、苔の様子を見ながらシュッシュッシュって水やりをしてもらう・・・」
●湿っているかは、目で見てわかるものですか?
「慣れてくればわかります。土も乾いてくると湿った時と色合いが変わってきますので、それがわかるぐらい、できれば毎日見てもらいたいっていうのが本当の気持ちです」
(編集部注:石河さんによると、街中に生えている苔を持ってきて、ガラス容器の中に入れると、虫がわいてきたりするので、苔テラリウム用に販売されている苔を使ってくださいとのことです。
また、ガラス容器内の苔はレースのカーテン越しの光や、LEDライトでも育つので、直射日光と暑さは禁物だそうですよ。

石河さんの新しい本には、数種類の苔を使った寄せ植えの苔テラリウムも紹介されています。コツとしてはタイプの違う苔を組み合わせること。
また、苔玉の作り方も掲載されていますが、石河さんがおっしゃるには、苔玉は苔テラリウムと違って、基本は屋外で育てるものだそうです。詳しくはぜひ本をご覧ください)
自然の景観をテラリウムで再現
※日本の苔テラリウムは、テラリウム発祥地ヨーロッパほか、アジア圏でも大人気だそうです。人気があるということはニーズがあるということで、自然界から勝手に苔を持ってきてしまう、そんな問題も起こっているとか。石河さんは苔を愛するひとりとして、こんな指摘をされています。
「苔ってその辺にもありふれているように見えるものじゃないですか・・・っていうのもあったりして、街中でも(苔を)安易に採ったり、あとは旅行先の山でも、いっぱい生えているんだから、ちょっとぐらいいいんじゃない、苔なんてただみたいなもんでしょ、みたいな感覚で採られてしまうのが、やっぱりここ数年特に苔の人気が出てきてから起こっていますね。
当然のことながら、他人の敷地で採ったりだとか、山も国定公園、特に苔の景勝地っていうか自然な景観が守られているところって国定公園になっていたりするので、そういったところは苔を含む動植物を採取すること自体が、法律的にNGだったりするんですよ。
そういったところで、わずかなひとつまみの苔であっても、そこの中に生態系があったりするので、安易に採るのは当然よくないことですし、大きい塊の一部を採ったことによって、綺麗に塊になっていた(苔の)一部から、なんて言うんですか・・・ここに小さい世界が作られているので、採られた一部がきっかけで、全体が枯れてくるみたいなことが苔ってあるんですよ。塊になっているから、ちょうどいい水加減を塊で保っているみたいなところがあります。
安易な行動が、あとの人たちも見に行きたい景観を壊してしまったりみたいなことがあったりするので、できるだけ自然な中のことは目に焼き付けたり、写真に撮ったりして、その風景をあらためて家で、テラリウムとかを作って再現するみたいな楽しみ方をしていただきたいなと思います」

「東京苔展2」開催
※9月に苔のイベントを計画されているそうですね。どんなイベントなのか、教えてください。
「『東京苔展2』というイベントです。板橋区立熱帯環境植物館で、苔の企画展を予定しております」
●どんなイベントになりそうですか?
「苔が好きな人って、今でこそテラリウムは少しずつ認知されてきているんですけど、まだまだ“私、苔が好きなの!”ってカミングアウトしづらいようなところが、実は苔好きの中ではあるんですね。密かに通学途中とか通勤途中に苔が生えているの、いいよねって思っているんだけど、職場とか学校でも友達とかに言っても“何?”とかって言われちゃうんで、言えないっていう人が結構いるんですよ。
そういう人たちが東京とかこの近郊にもいるんじゃないかなっていうので、そういった方々が“苔好きだよ!”って言える場所みたいなのを作りたくて、企画を始めたんですよ。
そういう一般の方とか愛好家の方の投稿してくれた写真を展示したりだとか、あとはテラリウムの作品はプロのテラリウムの作家さんが作ったものだとか、そういったのを並べたり展示したりします。
(会場の)植物園の中に温室がありまして、その中にもやっぱりちょこちょこと苔が生えているので、普段は大きい植物とかお花が、試作植物を飾ってある植物園なんですけども、そのお花とか木は見ないで、足元の苔だけを見て回りましょうっていう苔マップとか。あとはツアー動画も作りまして、その動画を見ながら足元を這いつくばって歩いてもらうっていう企画を考えていたりします」
●楽しそうですね〜! いいですね! 以前、苔役者の石倉良信さんに番組にご出演いただいたことがあるんですけれども、石倉さんも参加されますか?
「石倉さんも参加します。その観察動画は石倉さん出演です」
●そうなんですね! 石河さんは苔を通してどんなことを伝えていきたいですか?
「やっぱり出だしが(苔を)育ててもらいたいっていうところから始まっているので、苔って身近に生えていてすごく小さい植物なので、まだ植物を育てていない人でも気軽に置いてもらいやすい大きさだと思うんですよ。
テラリウムだと2週間に1回ぐらい水やりすればいいっていうと、働いていて忙しい人でも始めやすいじゃないですか、っていうところで、部屋に植物はないんだけど、何か植物を置いてみたいなって言った時に、まず苔から始めてみようって思ってもらえたら嬉しいなと思います。
で、その先に次のステップでいろいろな植物を育ててもらってもいいですし、そのきっかけが作れたらいちばん嬉しいですね」
●改めてになりますが、石河さんを虜にしている苔のいちばんの魅力とはなんでしょう?
「いちばんの魅力は、ぱっと見たら苔って緑の塊で、もう苔でしかないんだけど、ぐっと近づいてルーペとかを覗いた時に、種類が無数にあって、本当に小さな苔の森が広がっているように見えるんですよね。その違いを、遠目で見た時と近くで見た時の違いっていうのがすごく面白いので、ぜひ(苔に)近づいてみてもらいたいです」
INFORMATION
『はじめての苔インテリア〜苔テラリウムから苔玉、苔盆栽まで』
初心者に向けて、苔テラリウムや苔玉などの作り方が豊富な写真でわかりやすく解説してあります。全編カラーなので、みずみずしいモスグリーンを見ているだけで癒されますよ。この本を参考にあなただけの「苔インテリア」を作ってみませんか。家の光協会から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎家の光協会:https://www.ienohikari.net/book/9784259567620

石河さんが立ち上げた苔の専門ブランド「道草michikusa」のサイトでは素敵な苔テラリウムも販売。また、9月12日から10月1日まで板橋区立熱帯環境植物館で開催される「東京苔展2」の案内も載っています。詳しくは「道草michikusa」のオフィシャルサイトをご覧ください。
◎道草michikusa :https://www.y-michikusa.com/blog/topics/7472/
2023/8/6 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、絶滅の危機に瀕しているユキヒョウを守る活動をされている双子の姉妹、木下こづえさん、さとみさんです。
おふたりは「ユキヒョウ姉妹」というユニット名で活動をスタート、2013年に任意団体「twinstrust」を設立、主に中央アジアでフィールドワークを行ない、ユキヒョウの保全活動に取り組んでいらっしゃいます。
お姉さんのこづえさんは現在、京都大学大学院 アジア・アフリカ地域研究研究科の准教授。専門は動物の保全・繁殖生理学。ユキヒョウの研究には2006年から取り組んでいらっしゃいます。
そして妹さんのさとみさんは、九州大学大学院を経て、現在は電通でコピーライターそしてCMプランナーとして活躍されています。
そんなおふたりが先頃『幻のユキヒョウ〜双子姉妹の標高4000m冒険記』という本を出されました。この本は、ユキヒョウを守る活動10年の奮闘ぶりがそれぞれの視点で書かれています。また、ユキヒョウを追い求めて訪れたモンゴルやラダック、ネパールやキルギスなど、辺境の旅の記録でもあるんです。
きょうは、調査・研究からわかってきたユキヒョウの興味深い生態や、現地と日本をつなぐ活動のお話などうかがいます。

ユキヒョウってどんな動物?
※まずは、動物の研究者でいらっしゃる、こづえさんにお聞きします。ユキヒョウとはどんな動物なのか、特徴も含めて教えてください。
こづえ「まず、ユキヒョウは大型のネコ科動物です。アジアの高山地帯、中国の西側をぐるっと囲むように、南はネパール、北はロシアというふうに12カ国にまたがって生息しています。
大人の個体は3000頭ほどとされていて、多く見積もっても(全体で)8000頭ぐらいと言われているんです。基本的には高山の、人が足を踏み入れるのも難しいところに生息していますので、いったい何頭いるのか分かっていません。
世界中のユキヒョウを、例えば阪神甲子園球場に連れてきたとしても、アルプススタンド片側分、高校野球でいうところの応援(スタンド)1個分ぐらいにしかならない頭数が12カ国に散らばっていると思っていただけたらいいのかなと思います。
高山にいるので、岩山や雪山を駆け巡れるように毛が長くて、密度が高いんですけれども、足裏にもぎっしり毛が生えていて、尻尾が長いのが特徴です」
●そんなユキヒョウを研究するようになったきっかけは、何かあったんですか?
こづえ「もともと私が兵庫県出身で、神戸大学で繁殖学を学んでいたんですね。神戸大学の隣の駅には神戸市立王子動物園があるんですけど、その動物園がユキヒョウの繁殖に力を入れていたので、一緒に研究をしませんか と、動物園のほうからお声かけいただいたのが始まりでした」
(編集部注:ユキヒョウは現在、国内の9つの動物園で合わせて20頭が飼育されているそうです。首都圏では多摩動物公園で見られます。幻のユキヒョウが国内で見られるのは奇跡的なことかも知れませんね)

●さとみさんは、コピーライターのお仕事をされていますが、伝えるプロとして、ユキヒョウのキャラクターや歌を作ったんですよね?
さとみ「たまたま会社の飲み会がありまして、そこに歌もののCMソングとかを作るのが得意な先輩がいらっしゃったんですね。その飲み会で、うちの姉はこんなことをしているんですと話したんです。
毎日(動物園に通って)行動観察をしているけれども、通りすがる来園者のかたがユキヒョウを見て、チーターとかジャガーだ〜って、いやこれ、ユキヒョウなんですけど〜って、なんでユキヒョウって知られていないんだろう、悲しいなって話を(姉から)聞いて、それを話していたら(先輩から)自分でユキヒョウの歌を作ってみたらいいんじゃないって言われたんですね。
君が歌詞を書いて、僕が歌を作るからって言ってくださったので、じゃあ歌詞を書いてみようかなということで、姉にユキヒョウの特徴を聞いて歌を作り上げました。まだ駆け出しの頃で自分の作品って言えるものがなかったので、何かひとつ形になったのはすごく嬉しかったですね」
(編集部注:さとみさんが作詞した歌のタイトルは「ユキヒョウのうた」、歌っているのはCMソング「まねきねこダックの歌」で知られる「たつや」くんです)
ユキヒョウ姉妹、ユキヒョウ親子を撮る!?
※おふたりが設立した任意団体「twinstrust」、これはさとみさんが作ろうと持ちかけたんですか?
さとみ「はっきりした記憶はないんですけど、団体って言っても私たちふたりが中心になって、ほぼふたりでやっているような形なんですね。
せっかく歌が出来上がったので、それを野生のユキヒョウに還元したいね、つなげたいねっていう姉の思いもあり、ちょうど姉が大学に席を置くタイミングと一緒だったので、お世話になった動物園に挨拶回りをしていたところ、私も一緒について行ったんです。
何かこの歌でできることはありませんかって、おうかがいしていた時に、ちょうど旭山動物園の坂東園長が野生と動物園をつなぐ活動されていたので、何かヒントがあるのではないかと感じていました。
その時に坂東園長から、生活の中で意識を変えないと環境保全にはつながらないよって教えていただいて、会社員である私にも何かできるんじゃないかなというので、ふたりでタッグを組みました」
※最初の具体的な活動としては、調査・研究のためには赤外線カメラが必要だということを知り、クラウドファンディングを募り、集まった支援金でカメラ8台を購入。みんなで買ったカメラで撮れた写真を、支援してくれたかたに戻す、そんなコンセプトのもと、ふたりで初めて調査に向かったのが、2013年11月のモンゴル。このときは赤外線カメラをユキヒョウがいそうな山の数カ所に設置する作業がメインでした。

●どこに設置するのかがポイントになってくると思うんですけど、何か目安のようなものはあったんですか?
こづえ「初めに動物園でずっと観察していたので、ユキヒョウが自分のテリトリーをアピールするために、尿や糞でマーキングをすることはわかっていました。(尿の)スプレーを吹き掛けたりしてマーキングをするんですけれども、そのマーキングを探して、そこに仕掛ければ、ユキヒョウの行動が撮れるんじゃないかなと思っていましたね。
実際に(モンゴルの山に)行ってみると、動物園もそうなんですけれども、ちょっと岩場がハングしているところに尿スプレーをするので、その岩場を見つけて、実際にスプレーをした跡があったので、まずはそこに仕掛けてみようと思ったのが第1号の初めての赤外線(カメラの)トラップでした」
●さとみさんにとっては、この時が初めてのフィールドワークだったそうですけれども、実際やってみてどうでしたか?
さとみ「そうですね。私もいわゆる観光地にしか海外は行ったことがなかったんですけど、ほぼ同じ体、同じ 体力の姉がフィールドワークとして行なっているならば、私もできるんじゃないかなという思いで行きました。

あとは最初の土地がモンゴルだったということもあり、書籍でも触れているんですけど、私たちはユーミンが、松任谷由実さんが大好きで、13歳の多感な時期に見たユーミンのテレビ番組がちょうどモンゴルを訪れるという・・・都会的なユーミンじゃなく、野生的なユーミンの魅力に惹かれたきっかけの場所でもあったので、そこに行けるのかという冒険心のほうが勝っていましたね」
※ユーミンがいざなってくれたとさえ思えるモンゴル。その大地に連なる山に設置した、ユキヒョウ姉妹の思いがつまった赤外線カメラのデータは、現地の研究者から8ヶ月後にこづえさんのもとに届いたそうです。
●最初の調査で大きな成果があったんですよね?
こづえ「そうですね。先ほどのハングしていたところに仕掛けたカメラなんですけれども、私たちが仕掛けた数日後にユキヒョウがやってくるんです。1頭ではなくて親子連れで、ちょうど巣穴から出てきたぐらいの小さな子供のユキヒョウが写っていました。
匂いを嗅いでフレーメンっていう行動をするんですけど、フレーメンはちょっと笑っているような、口角を上げて詳しく匂いを嗅ぐんですけれども、それを母親がやっている姿を真似て、子供が同じようにフレーメンをしているのが写っていました。で、小さい山なので、ユキヒョウはいないっていうふうに考えられていたんですけれども、繁殖する場所としても有用な場所なんだよってことがその1枚で分かりました」

●さとみさんは、こづえさんから写真が撮れてたよって連絡を受けて、すぐに見に行かれました? どうでした?
さとみ「SDカードでモンゴルから姉の元に届いたんですね。なので私はデータを送ってもらって見たんですけど、本当に誰も何もいない、生き物の気配すら感じないところだったので、本当にいるのかなと思っていたんです。
自分が立っていた同じアングルで、数日後にユキヒョウが立っている写真が撮れているっていうのは、なんか不思議な感じがしました。本当にいたんだな、もしくは、どこかから見ていたんじゃないかなっていう気持ちになりましたね」
ユキヒョウとの共存共生
※モンゴルに続いておふたりは、2016年に、インド北部の山岳地帯ラダックに調査に行かれました。標高がおよそ3500メートルということで、体を慣らすのが大変だったそうです。そんなラダックでなんと、野生のユキヒョウに遭遇したんです。どんな状況だったんですか?
こづえ「一生に一度、研究者でも会えたらいいほうと思っていたので、会えないかなと思っていたんですけども、到着した時にユキヒョウが村の家畜を襲ったということが、現地の共同研究所に連絡が入ったので駆けつけました。
山の中奥深くに(ユキヒョウが)いるのかなと思ったんですけども、いた場所はその村の民家の裏山で、民家のベランダから見えるぐらいのようなところに、ユキヒョウが崖からひょっこり顔を出していて、野生の猫っていうより里猫のような感じでいるのがかなり意外でした」

●さとみさんはどうでした?
さとみ「あくびをしたり伸びをしたり、時より動物園で見せるような可愛らしい姿を見せてくるので、なんだかちょっと勘違いしそうにもなるんですけど、ただこちらを警戒しながらも家畜を襲いに来ている状況ではあったんですね。
民家の家畜を狙っている状況で、少し時間が経ったあと、私たちは部屋に入って晩御飯を食べていたんですけど、その時に(ユキヒョウが)牧羊犬を狙いに来ました。その牧羊犬が襲われた時、断末魔のような叫ぶ声が聴こえてきた時に、私はなぜかポロポロと涙が出てきてしまったですね。
家で犬を飼っているからなのかなと一瞬思ったんですけど、そうではなくて、生と死の重なりを目の当たりにしたと言いますか・・・ユキヒョウを守りに来ているのになんで泣いているんだろう・・・じゃあ何を守りに来ているんだろう、私は・・・みたいな複雑な気持ちで、初めて言葉にできない涙が流れた出来事だったなっていうふうには思います」
※村人にとっては家畜は財産なので、ユキヒョウに対する報復心は強いと、こづえさんは感じたそうです。
現地では、ユキヒョウが人里に出てきたら、政府機関に通報し、麻酔を打って捕獲、遠くへ移送することにはなっているそうですが、ユキヒョウの獲物になるヤギの仲間アイベックスなどが民家の裏山にいたりするので、ユキヒョウにとっては狩り場になり、どうしても村人の生活空間と重なってしまうということだそうです。

●ユキヒョウと人の共存・共生を目指す上で、どんなことが大事になりますか?
こづえ「人との共存共生って言った時に、私たちが日本にいてイメージするのは、おそらく野生動物とそこに暮らしている人たちっていうふうに、ちょっと遠いところの存在で捉えがちだと思うんですけれども、実はユキヒョウはアジアに生息していますし、生息しているいろんな国々と日本は密接な関係を持っている、同じアジアですので、より密接につながっています。
この地球上に暮らしている以上、必ず何かの形で、遠くの野生動物、遠くの人々ともつながっています。やっぱり今私たちが手にしているもの、食べているものは、何かを享受して成り立っているので、それはいったいなんなんだろうっていうことを考えることが大事なのかなと思っています。
自然から乖離(かいり)して暮らしている人ほど、都市部の人たちほど、遠くの自然を享受して生きていたりもするので、どこから来たんだろうっていうのを考えることが、いちばんのスタートになるのかなと思っています」
匂いのコミュニケーション

※現在、調査の主なフィールドは、中央アジアの山岳国キルギス。首都のビシュケクは都会的な街並みで、ぐるりと4000メートル級の山々が囲み、街ゆく人たちの顔立ちは日本人によく似ていて、なんだか不思議な魅力に溢れている所だったそうです。
キルギスでの調査で、同じ場所にいろんな野生動物がマーキングをすることがわかり、研究者のこづえさんは、彼らは匂いでコミュニケーションをとっている、そんな仮説を立てていらっしゃいます。これについて説明していただけますか。
こづえ「私たち人間も霊長類で、視覚的な見える世界に頼って、実は生きていて、嗅覚の能力はだいぶ弱っているんです。ネコ科動物は匂いの世界で生きているっていうのは私もわかっていて、繁殖を研究していたので、マーキングを使って密度の薄いところで、ぽつんと暮らすユキヒョウたちが、どうやってユキヒョウ間でコミュニケーションをとっているのかを興味を持って研究をしていたんですね。
野生に行ってみて実際にカメラを仕掛けると、そのカメラはいろんなユキヒョウを写すことはほぼなくて、ユキヒョウはマーキングにやっては来るんですけれども、基本的にはオオカミだったりクマだったりキツネだったり、いろんなほかの動物たちがやってくることに気づかされて・・・。
あっ、そうか! と。実際彼らはユキヒョウへのアピールも大事だと思うんですけれども、そこで生きていく以上、同じように肉食動物で狩りをしているオオカミに対してのアピールであったり、匂いを嗅ぐことで餌動物は、ここにユキヒョウが来たんだっていうことを知って、活動時間帯を変えたりとか・・・行ってみると何にも動物がいないような閑散とした場所なんですけれども、彼らは匂いですごくコミュニケーションをとりながら、そこで生きているんだっていうことに気付かされました」

※「twinstrust」で行なっている「まもろうPROJECT ユキヒョウ」の一環として、キルギスでぬいぐるみ「ユキヒョウさん」を作っていますよね。どんな活動なのか教えてください。
さとみ「キルギスにいらっしゃるJICAのかたが運営している『一村一品プロジェクト』というのがあるんですが、その一村一品プロジェクトとコラボしてユキヒョウさんグッズを制作しています。
その一村一品プロジェクトは、キルギスの伝統文化であるフェルトとかを使って、首都から遠く離れた村の女性たちが一針一針フェルトを作ってくださっています。田舎の村のほうで使われなくなった学校を改装して職場にして(フェルトを)作っていらっしゃいます。
昔は女性は遠くに出稼ぎに行かないと、なかなか稼げないっていうことがあったんですけど、JICAのかたがその村で、家族と暮らしながら現金収入を得られる、女性の地位を高めるという意味での一村一品プロジェクトをされていました。
去年、実際に私たちもその村を訪れたんですけど、本当に何もないところに急にポツンと学校が現れまして、中に入ると、あれだけ誰もいなかったのに学校の中には女性たちの賑やかな明るい声が溢れていて、こんなところから一針一針、手作業で作られて届いているんだなってことを感じました」

●同じく新商品としてユキヒョウさんのスノーハニーというハチミツがありますけれども、これもキルギス産なんですよね?
さとみ「そうですね。白いハチミツもキルギスの遊牧民に長年愛されてきた伝統文化です。実際に私たちも去年その花畑を訪れたんですけど、遠くにユキヒョウが生息している山が見えるんですね。私たちが調査している山、あそこ! っていう感じに見えるんです。
そこにいるミツバチたちが・・・高山植物のエスパルセットっていう植物が蜜元なんですけど、本当にその生態系の中で採れたハチミツだなということで、それを動物園だったり、雑貨屋さんで売っていただいています」
ユキヒョウは平和の親善大使
※「twinstrust」を立ち上げて、およそ10年が経ちました。こづえさんはユキヒョウの研究者として、今後明らかにしたいことはなんでしょう?
こづえ「まずやはり何かを守ろうって思った時には、人と人もそうだと思うんですけれども、守る相手を知らなければ、正しく守ることはできないと思うんです。そもそも私自身も生物学の研究者として、ユキヒョウの生態そのものをまだまだわかっていないので、彼ら自身を知りたいと思って、10年前(調査活動を)スタートはしたんですね。
ユキヒョウが暮らすいろいろな国に行くと、ユキヒョウっていうのは人々の文化や宗教、時には紛争にも関わっていたりもして、そこに暮らす人々のことを知らなければ、ユキヒョウのこともわからないってことがわかってきたので、今はユキヒョウを通して人々の文化も明らかにしながら、動物を守るっていうことの実態を明らかにしていきたいなと思っています」
●さとみさんはこの『まもろうPROJECT ユキヒョウ』の活動で、今後やっていきたいことってありますか?
さとみ「具体的にこれっていうようなことではなく、曖昧ではあるんですけど、いろんなご縁をつないでいきたいなと思っています。
最初、研究者の姉とコピーライターの私、全然違う職業のふたりがタッグを組むことで、予想もしなかった展開があったように、自分たちが面白がって双子でやっていると、いろいろ面白そうだねって、この指止まれ、じゃないんですけど、人が集まってくるので・・・今回のラジオもそうです。なんかそういった人との関わりとか、化学反応を楽しんでいきたいなと思っています」
●では、おふたりにとって、ユキヒョウとはどんな存在ですか?
こづえ「ユキヒョウは高山にいるので珍しいと思うんですけど、彼らは国境をノー・ボーダー、ノー・パスポートで縦横無尽に走り回っている、その姿がやはり魅力的だなって感じています。そのユキヒョウに出会えたおかげで、いろいろな国の人たちの文化を知ることができたので、私たちにとっては本当に平和の親善大使だなっていうふうに思っています」
●さとみさん、お願いします。
さとみ「ユキヒョウを好きになったことで、私もこんなにも世界が広がりました。自分でも歌詞に書いたんですけど、”好きな動物はなあに? 僕はユキヒョウ”っていう、好きな動物を好きになることは、本当に入り口で、好きになったら、その動物はどこに棲んでいるんだろうとか、どんな人との関わりがあるんだろう、自分にどう関わってきているんだろうと、どんどん見える景色が変わっていくので、好きになった動物、ただ好きで終わりではなくて、そこから広げていく面白さをユキヒョウは教えてくれたなと思います」

(編集部注:ユキヒョウが減っている原因は、WWFジャパンのサイトによれば、特に山岳地帯で急速に進む地球温暖化の影響や、ユキヒョウの獲物である草食動物の減少。そして家畜を襲ったユキヒョウが人間によって殺処分されていること。ほかにも、違法取引のための密猟などもあって、毎年最大で450頭ほどのユキヒョウが犠牲になっているそうです。幻のユキヒョウが、本当に、幻にならないようにしたいですね)
INFORMATION
ユキヒョウを守る活動10年の奮闘ぶりと、ユキヒョウを追い求めて訪れた辺境の地、モンゴルやラダック、ネパールやキルギスの旅、そして人々との出会いが、自然体の文章で書かれています。ぜひ読んでください。もちろん、野生のユキヒョウの貴重な写真も載っていますよ。
扶桑社から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎扶桑社:https://www.fusosha.co.jp/books/detail/9784594094010
手作りのぬいぐるみ「ユキヒョウさん」などのグッズは、以下の動物園で販売しています。
旭川市旭山動物園/札幌市円山動物園/盛岡市動物公園ZOOMO/那須どうぶつ王国/いしかわ動物園(近日販売開始)/神戸どうぶつ王国/大牟田市ともだちや絵本美術館(大牟田市動物園内)*動物園によって、販売している商品は異なります。
また、盛岡市動物公園ZOOMO、那須どうぶつ王国、神戸どうぶつ王国のネットショップでも購入できます。
詳しくは「まもろうPROJECT ユキヒョウ」のオフィシャルサイトをご覧ください。
◎まもろうPROJECT ユキヒョウ:https://www.yukihyo.jp
2023/7/30 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、南アフリカ政府公認のサファリガイド「太田ゆか」さんです。
太田さんは1995年、アメリカ・ロサンゼルス生まれ、神奈川県育ち。小さい頃から動物が大好きで、将来の夢は獣医さんになること。そんな少女は、動物を守れるような仕事をしたいと思い、立教大学在学中に、環境保護に関わるボランティア活動を国内外で体験。
そして、野生動物ならアフリカ! そんな思いから、アフリカ大陸南部・ボツワナ共和国でのサバンナ保全プロジェクトにボランティアとして参加。その時に人生を決定づけるガイドという仕事に出会い、現在は、南アフリカ政府公認のサファリガイドとして活躍されています。そんな太田さんが一時帰国されたときにお話をうかがうことができました。
今回は新しい本『私の職場はサバンナです!』をもとに、クルーガー国立公園でのサファリツアーや野生動物の保護活動のお話などお届けします。
☆写真:日本人サファリガイド 太田ゆか

サファリガイドの訓練学校
クルーガー国立公園は、南北およそ350キロ、東西およそ65キロの広大なエリアには哺乳類、野鳥、爬虫類、両生類など多種多様な生き物が生息している、まさに動物の王国!
そんな国立公園内には、およそ2000キロ以上にわたり、道路が整備されていて、車でめぐるサファリツアーが大人気なんだそうです。ちなみにサファリとはスワヒリ語で「旅」を意味するそうですよ。
広大なサバンナには、ライオンやハイエナ、アフリカゾウやサイ、キリンやインパラなどが暮らし、まさに「ライオン・キング」の世界が広がっているそうです。

動物が大好きでも、そう簡単にはサファリガイドにはなれないと思うんですが、どんな道のりを経て、ガイドになったのか教えてください。資格も取得されているんですよね。
「そうですね。私の場合は・・・訓練学校が現地にあって、サファリガイドになりたい人たちのための学校みたいな環境になっていて、そこに入学して1年間、訓練を受けて、試験に受かると実習に進めるんですね。
で、実習を無事に終えると、南アフリカ政府が公認しているサファリガイドの資格を取得できるっていうような感じなんです。資格の取得自体は試験にさえ受かっちゃえば、みなさんなれるんですが、実際に働ける場を見つけるのは、やっぱり外国人として、すごくハードルが高かったですね」
●太田さんは、そこをどのようにされたんですか?
「サファリガイドは、やっぱりコネクションがすごく大事な、すごく狭い業界なんですね。私が今滞在しているのはクルーガーなんですが、クルーガー国立公園の周辺エリアで、業界の人たちにたくさん会って、信頼関係を築いて、なんとか活動できる場を見つけられたっていうような感じです」
●そのクルーガーは南アフリカのどの辺りになるんですか?
「南アフリカがアフリカ大陸のいちばん南にあるんですが、その中でも結構、北のほうにリンポポ州っていう州があります。その州の中にクルーガー国立公園っていう国が持っている土地があって、その周りにもたくさんサバンナが広がっていて、そこは市営保護区になっています。
その市営保護区も国立公園も柵なしで、どっちもつながっているので、南アフリカの中の、北のエリアには本当に広い生態系が広がっていて、その中に今私は住んでいます」
●衣食住を含めて、どんな暮らしをされているんですか?
「食べ物に関しては意外と結構普通で、もちろん住んでいるのはサバンナなので、毎回毎回、町まで1時間ぐらいかけて(車で)行って、買い物してみたいな感じです。飲み水だったりとか、食料は週に1回とか2週間に1回とか、1回の買い出しでまとめてゲットするみたいなイメージなんですけど、ゲットできるものは、あまり日本と変わらないかもしれないです。
もちろん日本食はないですけど、普通にお野菜だったりお肉とか、そういうものも売っている田舎の街が、サバンナの近くにもあるような感じですね。でもやっぱり電力に関しては、サバンナっていうところもあって、南アフリカは停電がずっと続いていて、そこだけは今も結構苦労しています」
●治安とかはどうなんですか?
「治安は、大都市ヨハネスブルクとかケープタウンとかダーバンとか、そういう大きい都市になると、やっぱり治安がよくないところもあるのは事実なんですが、サバンナまで行ってしまえば、人もいないので治安はものすごくよくて(笑)、気をつけるのは動物だったりとか、それぐらいかなっていう感じで、すごく安全な場所になっています」
サファリドライブの醍醐味

※サファリガイドになって7年くらいだそうですが、具体的にはどんなことをされているのか、1日のスケジュールも含めて、教えてください。
「基本的には太陽と一緒に暮らしていくようなスケジュールになっていますね。太陽が出てきたら、その時間に合わせてサファリドライブをスタートして、サバンナに出て行って野生動物を探してっていう・・・サファリドライブは朝、行なっていますね。
いちばん暑い昼間の時間帯になると、ずっとサバンナの中に出ているのも大変になってくるので、そうすると私が住んでいるロッヂ、家に戻ってきて、パソコン系の作業をしたりみたいな・・・。で、夕方サバンナの気温が下がってきたら、またサファリドライブに出かけて野生動物を探すのが、基本的な1日の動きにはなっています。
でも、動物に合わせてスケジュールも変わっていくので、罠にかかっている動物が見つかったってなると、普段のお仕事は置いといて、急にそっちに出動することもあるので、結構違う毎日を過ごしています」
●ツアーのルートは、ある程度は決まっているんですか?
「国立公園とか市営保護区の中で、どういうふうに動いていくかは全く決まっていません。やっぱり野生動物は動物園と違ってどこにいるか、その時になるまでわからないので、広大なサバンナの中から探し出すってなると、その動物が残してくれる足跡だったり糞だったり、そういった痕跡をたどりながら、動物の場所を探していく、辿っていくような感じなので、毎回違うサファリの内容になります」
●同行するガイドは、基本は何人なんですか?
「同行するガイドは基本、私がオープンサファリカーを運転して、私ひとりでガイドさせていただいているんですが、時々私が担当していない保護区にツアーに行ったりもする時があって、そういった時はそこにもガイドさんがいるので、現地ガイドと私が二人三脚でガイドしたりしています」
●ツアー客のみなさんは、車の上から動物を観察するっていう感じなんですよね?
「そうですね。基本的にはサファリドライブは車に乗っての移動になるので、車に乗りながら動物を探して観察してっていう感じではあるんです。でもやっぱり(痕跡を)辿って、動物を探し出すのが、サファリドライブの楽しさでもあるので、いい感じのフレッシュなライオンの足跡とかがあったら、サファリカーを降りて実際にその足跡を見てみたり、手を並べてみて大きさ感じてみたりっていうことはやったりします。周りが安全であることを私たち(ガイド)が確認したあとではあるんですが・・・。
あとは、サファリドライブは1回3時間とか4時間とかになったりするので、途中で1回車を降りて足を伸ばす休憩タイムをとります。そこでジントニックだったりワインを飲んだりとか、そんなドリンク休憩を挟むこともあります」
●そうなんですね〜! 太田さんがガイドする時に心がけていることってありますか?
「やっぱりいちばん感じてほしいのは、動物が可愛かった、すごかったで終わってしまうのではなくて、ここの動物はこんなふうにほかの動物と、生態系の中でつながっているんだとか、まさにこの番組(のテーマ)と同じように、人間も自然の一部だよねっていうのを感じて欲しいメッセージとして私も持っています。
そういったことを実際にサファリドライブを通して、身をもって感じてもらえるような、人間もずっとここに暮らしていたんだ、動物たちと一緒に暮らしていたんだっていうのを感じてもらえるような、ガイドができたらなって思っています」

(編集部注:サファリカーにお客さんを乗せて案内するなかで、日々いろんな動物と遭遇している太田さんですが、やはり赤ちゃんに出会うと幸せな気持ちになるそうです。
たとえば、ハイエナの赤ちゃんは好奇心が旺盛で、向こうから車に近づいてきてくれて、いろんな行動を見せてくれるので、見ていてまったく飽きないとか。また、ガイドになって間もない頃、大きなクロサイに遭遇、その影に小さく動くものを見つけたそうです。実はそれが生まれたばかりの赤ちゃん! 絶滅危惧種のクロサイが命をつないでいることに感動を覚えたそうですよ)
アフリカゾウはキーストーン種
※アフリカといえば、ゾウを思い浮かべるかたも多いと思うんですけど、アフリカゾウの数が一時期、激減したというニュースがありました。現状はどうなんでしょうか?
「そうですね。アフリカに生息しているゾウは、実は1種類ではなくて2種類いて、マルミミゾウと、いわゆる私たちの知っているアフリカゾウがいるんですけど、アフリカ大陸も広いので、地域によって全然状況は違います。
それこそマルミミゾウは、中央アフリカとかそういった熱帯雨林のようなジャングルみたいなところに棲んでいるゾウさんなので、そこは結構今でも密猟の影響があったりして、数がなかなか増えていなくて、大変な状況にはなっているんですね。
南アフリカとかボツワナとか南部アフリカのエリアでいうと、私たちのクルーガー国立公園は、特にアフリカゾウは今すごく増えていて、クルーガー国立公園全体が日本の四国と同じぐらいの大きさなんですけど、その中に2万頭が生息しているっていうふうに言われています。
これは今のところ統計上、記録がとられ始めてからいちばん数が多いんですね。なので、生息地がどんどん減ってしまっているのに、その残された生息地の中でゾウは増え続けています。生息域がずっと広くあればよかったかもしれない数なんですけど、現状もう(ゾウが)行ける場所がないのに、その中で増えてしまっているのが今最大の問題になってしまっています」

●そういう現状なんですね。本にアフリカゾウはキーストーン種と書いてありましたけど、このキーストーン種とはどういったものなんでしょうか?
「キーストーン種は、生態系にもたらす影響が大きい種だったりとか、いろんな動物とつながって、その生態系の中ですごく重要な役割を果たしている動物のことを言うんです。特にゾウさんはサバンナの自然を形作っていると言われるぐらい、いろんな動物といろんなバランスの中で生息しています。
たとえばゾウさんは、たくさん食べてたくさん移動するので、移動距離が多い分、ゾウさんが食べた植物の種子が遠くまで運ばれて、そこで(糞と一緒に)出てくると、それは植物に対して種子散布の役割を果たしていたりします。
あとは、水溜まりの中に魚がたくさん卵を産んでいたりするんですけど、そういう卵をゾウさんが体にくっつけて移動して、違う所に行ったりすると、そのお魚(の卵)を運んでいたり・・・なので、実は哺乳類の中だけでなくて、魚類だったりとか植物だったり、いろんな動物とつながって、今のサバンナのバランスを保ってくれているのがゾウさんです」
●サバンナにとってゾウは大切な存在なんですね。
「そうなんです! 大切な存在なんですけど、やっぱりたくさん食べる分(ゾウが)いすぎても影響は大きいので、そこが難しいところではありますね」
深刻なサイの密猟
※アフリカでは密猟が横行しているというニュースを見たりすることがあります。やはり、そうなんですか?
「南アフリカでいうと、アフリカゾウの密猟は結構今は少ないんですけど、今いちばん問題になっているのは、サイの密猟です。かなり深刻で、毎年たくさんのサイが、そのツノのためだけに殺されてしまっているっていう現状が起きています」
●対策としては、どんなことをされているんですか?
「サイに関しては、ツノがそれこそ東南アジアとか中国とかでは漢方薬として使えるとか、病気が治るみたいないろんな迷信があって、実際は人間の髪の毛や爪と同じケラチンなので化学的効果はないんですけど、そういうふうに信じられて消費されているのですごく価値が高くなっています。お金儲けのためにサイのツノを密猟している、ツノのためだけにサイが殺されてしまっているっていう状況なんです。
ツノは髪の毛と全く同じなので、別に切っても痛くないんですね。人間が爪とか髪を切っても痛くないのと同じように。なので、今なんとかこの密猟を食い止めるために、獣医さんと一緒に麻酔を打って眠っているサイのツノを短くして、密猟する動機をなくさせる・・・ツノがなければ、サイも殺される理由がなくなるので。なるべくそういうふうにして、本来の姿を変えてしまうっていう意味では理想ではないんですけど、もう今はほんとに一刻を争う事態なので、少しでも多くのサイが生き延びれるようにツノを短くしています」
(編集部注:サイのツノは、人間の爪や髪の毛と同じだということで、また生えてくるんですね。太田さんによれば、2〜3年でもとに戻るそうです)

ゾウにGPSを付けて追跡
※日本でも野生動物が街中に出てきたり、収穫前の作物を食べてしまうような食害の問題があったりします。人と野生動物の軋轢というか・・・その辺、南アフリカではどうですか?
「私たちが今行なっている活動のひとつで、ゾウさんでいうと、場所を求めて、保護区の国立公園のエリアから出てしまって、村に入ってしまったりとか、畑に入ってしまっているので、GPSをつけて彼らの動きをモニタリングできれば、ゾウさんがどういう動きをしているのか、どこの通り道を通っているのか、そういうことがだんだん分析できるようになってきて、ゾウさんが出て行ってしまうことを未然に防げるようになったりします。
結構おっきい首輪なんですけど、それにGPSが付いていて、それをゾウさんの首に付けさせてもらうと、そのゾウさんが保護区を出てしまう前にわかるので、そうするとヘリコプターを飛ばして、(保護区の)中に追いやったりとか。
やっぱり1回出てしまうと戻すのが大変なんですね。射殺されてしまったみたいなことになっちゃうんですけど、出るのを防げればどっちもハッピーでいられるので、このGPSを付けることによって、なんとかしようっていう活動を今行なっています。
ただやっぱりヘリコプターを飛ばしたり、GPS自体もすごく費用が高いので、今それでクラウドファンディングを行なっていて、ゾウさんの保護活動を日本で応援してくださるみなさんと現地で実現しようとしています」

人間も自然の一部
※太田さんが暮らす南アフリカ・クルーガーエリアの大自然や野生の生き物たちから、どんなことを感じますか?
「これはやっぱり私がみなさんに感じてもらいたいことなんですけど、このクルーガーのエリアを歩いていたりとかガイドしていると、結構ゴロゴロと人間がそこに暮らしていたんだなっていう形跡が本当にたくさんあります。それこそ旧石器時代の人たちの石器の道具だったりとか、あとは岩場に残っている壁画だったりとか、本当に人がこうして動物と一緒に暮らしていたっていうことを、身をもって感じることのできるすごく貴重な自然だと思うんですね。
やっぱりそういったところを感じてもらえると、私としてはすごく嬉しいし、それが環境保護だったり、みんなが長く平和に野生と共存できるような世界につながっていくのかなと思うので、なるべく多くの方にサファリツアーに来てもらって、人間が生態系の一部っていうのを、いちばん感じてもらいやすい環境で、みんなに感じてもらいたいと思っています」

●太田さんがサファリガイドとして、最も伝えたいことを教えてください。
「重ねてにはなってしまうんですが、人間がちゃんと自然の中で、生態系の中で役割を果たしていた時代が、過去にあったっていうのを踏まえて、今人間は結構(自然に対して)悪みたいな言い方だったり考え方になってしまうこともあると思うんですけど、でも本来は人間も生態系の一部としてずっと成り立ってきた存在だと思うんです。
現在もアフリカの中にはそうやって暮らしている先住民の人たちってたくさんいるので、そういう人たちを目の当たりにすると、今の私たちも少しずつ工夫していくことで、少しでも彼らの生活の仕方に近づけるんじゃないかなって思うんですね。
やっぱり伝えたいことってなると、人間も自然の一部っていう考えを、なんとか取り戻すことによって、みんなが少しずつ環境にいい暮らしに変化していくんじゃないかなっていうふうに思います」
●では最後に太田さんの夢を教えてください。
「長期的な夢でいうと、本当に死ぬまでサバンナにいるってことなんです。近くの短期間の夢でいうと、今日本のみなさんに応援していただいている、クラウドファンディングの支援金を使って、南アフリカで保護活動を成功させることですね。日本から応援したい、でもどうしていいかわからないっていう方たちが、意外といるんだなっていうのが最近わかってきて・・・。なので、そういった方たちと助けを必要としている現地の人たちをつなげるような存在になりたいなっていうふうに思っています。
やっぱり直近の夢でいうと、そうやって応援してくれているみなさんの協力を得て、大きな保護活動を南アフリカだったり、ほか(の場所)でもいいんですけど、アフリカのサバンナの環境で、日本のみんなと現地の人たちをつないで、大きな保護活動を実現できたらいいなって思っています。
まずはゾウさんにGPSを付ける保護活動を8月に予定しているので、それが大成功に終わるように頑張らなくてはいけないなと思いつつ、現地のNGOだったり研究者だったり、獣医さんと話しながら準備を進めています」

(編集部注:太田さん曰く、アフリカゾウの群れに囲まれても、彼らがリラックスしていると、とてもピースフルな雰囲気になるそうです。野生動物には不思議な力があって、癒されるそうですよ。
太田さんは休みの日は、すっかりハマってしまった野鳥観察に出かけるそうですよ。これまでに400種以上の野鳥に出会ったとか。鳥を知るとサファリが倍楽しくなるとおっしゃていました)
INFORMATION
サバンナに生息する野生動物の生態や、保護活動の最前線、そして人と野生動物が共生していくためのヒントなどが書かれています。大好きな動物を守りたいという太田さんの強い意志も感じる一冊。ぜひ読んでください。
河出書房新社から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎河出書房新社:https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309617510/
お話に出てきたクラウドファンディング、現在は、ナミビアの砂漠で生き抜く幻のライオンを保護するための支援を募っています。
また、太田さんがガイドしてくださる魅力的なサファリツアーや、なんと、サファリガイドの訓練学校を体験できるサファリ・スタディーツアーも企画されています。詳しくは太田さんのオフィシャルサイトをご覧ください。
◎太田ゆか:https://yukaonsafari.com
2023/7/23 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、植物観察家の「鈴木 純」さんです。
鈴木さんは1986年、東京都生まれ。子供の頃、親御さんが小笠原に連れて行ってくれたり、夏休みには、自然の中に身を置く旅にいざなってくれたりということもあって、野山が大好きな少年だったそうです。そして東京農業大学で造園学を学び、その後、青年海外協力隊に参加し、中国で砂漠の緑化活動を行ない、帰国後、国内外のフィールドを巡り、植物への造詣を深めます。
そんな鈴木さんは、友達に植物の面白さを伝えたいと思い、野山での観察会を企画したところ、人が集まらなかったそうです。野山に行くにはウエアやシューズ、持ち物などそれなりの準備が必要で、それがハードルになることに気づき、それなら気軽に集まれる街中だ!と思い、まずは友達向けの観察会をスタート。
そして2018年からフリーの植物ガイドとして、街中での植物観察会を行なっていらっしゃいます。また、植物生態写真家としても活躍。
そんな鈴木さんが『まちなか 植物観察のススメ』という本を出されました。きょうは、街中で植物観察をするときのコツや、植物を見分けるポイントなどうかがいます。道端に咲いている花や樹木のことをちょっとでも知るといつもの道がきっと楽しくなると思いますよ。
☆写真協力:鈴木 純

木の葉っぱ、鋸歯を覚える!
※植物の名前をなかなか覚えられない、そんなかたは多いと思います。植物のどこに注目するのがいいのか、ポイントがあるんですよね。
「そうですね。とにかく植物は多分全部そうなんだと思いますけど、形を見ることがすごく大事なポイントになるので、まず初めは漠然と見ないで、形を見るんだっていう意識をちゃんと自分につけることです。慣れてくれば、そんなことを考えなくていいんですけど、初めは形に注目、意識するっていうことがすごく大事だと思います」
●この本には植物の名前を覚えたいなら、まず木がおすすめっていうふうに書かれていました。でもなんだか草花のほうがわかりやすいかなって思ったんですけど、木がおすすめっていうのはどうしてなんですか?
「これは僕が木から覚えたっていうのもあるんです。草と木の違いは、僕なりに思っているところがあって、草は結構短命なんですね。1年で枯れちゃったりするので、そういう短命な生き方は、植物にとって多少環境が悪くても、小さいまま花を咲かせたりとかするわけですよ。
そうすると環境がいいところでは、大きく育っていた植物が、こっちでは小さい形で生きているとかっていう感じで、草は形が結構不揃いになるんですね。ただ、花の形は同じなんですけど、この話は後でまたしますね。
見るべきポイントが葉っぱだとすれば、草は葉っぱを見るといろいろ混乱しちゃうけど、木の場合は長生きなので、長生きな植物は結構形が安定しているんですね。なので、葉っぱとかをヒントに植物の名前を調べるのであれば、そういう比較的形が安定している木から始めるほうが、意外と始めやすいんじゃないかなと思いますね」
●木の葉っぱは、どこに注目するのがいいんですか?
「僕がおすすめなのは、まず言葉を覚えるっていうところで、たとえば葉っぱをよく見ると、葉っぱの縁のところにギザギザが付いていたりするんです。そのギザギザには実は呼び方があって、これを”鋸歯(きょし)”って言うんですね。まずこの鋸歯って言葉を覚える! これを僕はおすすめしています。
というのは、葉っぱの縁にギザギザがあるなって思っていると、このギザギザに鋸歯って言葉があるんだって思うと、僕は学生の時にギザギザに鋸歯があるって聞いた時にすごく感動したんですよね。鋸歯っていう言葉があったのか! って感動しまして、そうしたら葉っぱのギザギザがよく見えてくるようになっちゃったんですよ。
なので、まずこのギザギザは鋸歯だっていうことをまず覚える! 自分で鋸歯っていう言葉を発してみる、これが大事ですね。何気にどこの葉っぱでもいいので見ながら、鋸歯があるな、鋸歯があるな、鋸歯があるなって、ひたすら鋸歯っていう言葉を発してみる。そうするとどんどん鋸歯が気になってくる、そういうことをまずやっていくのが僕のおすすめです」

(写真右)マンリョウ 丸い鋸歯
葉っぱの付き方~互生、対生
※街中の公園などでよく見る木で、この木の葉っぱを見ると面白い、というのはありますか?
「僕ね、葉っぱを見るのは簡単だと思いながら、難しいと思っていることもあって・・・っていうのは、今僕がたとえば、エノキの葉っぱ面白いんですよって言ったところで、まずはいろんな葉っぱの比較をしておかないと、どの葉っぱが面白いかっていうことがわからないんですよね。
なので、たとえばエノキだったら、鋸歯が葉っぱの根元の部分、半分は鋸歯がないんですよ。その半分より先に鋸歯があるっていう形をしていて、僕にとってはすごく面白いけど、果たしてそれを面白いって思う人がどれくらいいるのかというところなんですよね。
これは植物の葉っぱを、いろんな種類を見ていると、どんどん面白くなっていくっていう、そういうタイプの楽しみなんですよ。なので、なんというか、あまりどの葉っぱが面白いですかっていうのはなくて、言っちゃえば全部面白いんですよ。なぜなら全ての葉っぱが、どの葉っぱとも違う形をしているから・・・なんだけど、この面白さを伝えるには、まずひとつひとつの葉っぱを知る必要があるんだよね。急に楽しめないっていう、そこが僕は奥深いなと思っているところなんですよね 」
●葉っぱの付き方にも、いろいろあるんですよね?
「ありますね。これも面白いですよ! これもやっぱり言葉遣いがあって、たとえばいちばん多いのが”互生(ごせい)”って言って、これは枝に葉っぱが右、左、右、左って交互に付いているパターン、これを互生って言うんですね。

で、これはよくあるパターン、互生はよくあるやつなんです。だから互生の木が出てきても、そんなにテンションが上がんないわけですね。互生か!って感じだけど・・・テンションが上がる葉っぱの付き方は、”対生(たいせい)”ってやつで、枝の一箇所から2枚出てくる、対になって出てくるっていうやつですね。対生の木はちょっと互生よりは少ないんですよ。なので、名前を知るためのヒントにはしやすいものになるんですね。
種類によって、互生の木があったり、対生の木があったりする、葉っぱの付き方に違いがあるなんて、全く思わないわけじゃないですか、普通は。だけど意外とよく見ると違いがあるっていうところに面白みがあって、かつ対生であれば、互生よりも対生の樹木のほうが少ないことがわかっていれば、図鑑も引きやすくなるんですね。結構葉っぱの付き方を見るのは、大事というか面白いし、役に立つものですね」

(編集部注:鈴木さんによると、対生の樹木で、街中でよく見られるのは、クチナシ、キンモクセイなど。アドバイスとして、花が咲いているときに葉っぱをよ〜く見ておくと、花がないときでもすぐにわかるようになるそうです。
ほかにも、蜜が出る葉っぱの代表的なものとして、ソメイヨシノを教えてくださいました。詳しくは鈴木さんの新しい本をぜひ見てくださいね)
草は花を見る
※続いては、草を見るときのポイントです。草の名前を覚えるには、花に注目するのがいいそうですが、それはどうしてなんですか?
「これは、草は短命で環境に合わせて、すごく小っちゃいまま、花を咲かせたりとかしちゃうから、葉っぱの形とかがあんまり信用できなかったりするんだけど、面白いことに花の形は整っているんですよ。なので、花の形は信じられる。
これは、本当は木も一緒なんですね。木も一緒なんだけど、木の花は結構高いところに咲いていたりとか、意外と小っちゃかったりとかして、結構観察するのが難しいんですよ。でもその点、草は自分の背丈もないですよね。足もとに咲いているので、かがめば見られるっていうものなので、そういう意味で形が安定していることと、観察しやすいっていう意味で、花を観察するのがいいかな」
●この7月、8月にかけて咲く花で、この花を観察すると面白いよっていうのはありますか?
「いろいろあるんですが、ひとつテーマとしておすすめなのが・・・夏って暑いですよね。そうすると植物も昼間はあまり咲いてないんですよね。いつ咲いているかっていうと、早朝か夕方以降に咲いているんですよ。夏は結構、開花する時刻が決まっている植物が多いんです。
ツユクサだったら、自分たちが起きてくる時間にはもう咲いていますし、オシロイバナは夕方4時から咲き始めます。夕方6時ぐらいからカラスウリの白い花が咲き始めたりするので、この開花の時刻をテーマに観察すると、面白いものが夏はいっぱいあるかなと思いますね」

オオバコの時間差戦略!?
※鈴木さんの新しい本に、めしべとおしべを時間差で出すオオバコという草の話が載っていました。なぜ時間差で出すのか、教えてください。
「オオバコって夏に見ると花茎(かけい)が伸びているんですよ。シュッと縦に伸びて、その軸をよく見るといろんなものが付いているんですね。
そもそも知っておかないといけないのは、オオバコってひとつの花の軸に花がひとつだけ咲いているんじゃなくて、小っちゃい花がいっぱい付いている、その軸のところにぷつぷつって大量に・・・だから花の集合体なんですよね、そもそもオオバコってね。
その花の集合体がどう振る舞うかが面白くて、まずつぼみの状態のオオバコがあったとしたら、小っちゃいつぼみがいっぱいあるっていう意味ですね、要するに。そのつぼみが下のほうから咲き始めるんですよ。下のほうから咲き始める時に最初はめしべだけを出すんですね。めしべだけ下のほうからバーっと上に向かってどんどん出していくわけです。
めしべだけを出すってことはメスの状態ですよね。1回目のメスの状態になる。そうしたら今度はまた下からおしべがどんどん出てくる。メスの状態がだんだんメスとオスが一緒にいる状態になって、最終的にオスだけの状態に変わっていくっていう、オスとメスのタイミングをずらすっていう方法があるんです。

これはすごく巧妙で、オオバコは風に花粉を運ばせるタイプの植物なんですけど、もしも同じ花の中で、おしべとめしべを同じタイミングで出しちゃったら、自分のおしべから出る花粉が、自分のめしべにくっ付いちゃう可能性があるわけです。
植物も結構、実はほかの株と受粉したいと思っているわけですよ。メスとオスのタイミングがずれていれば、たとえば初めは、めしべだけが出てきてメスの状態になっていれば、ほかの花から花粉が飛んでくるのを受け取るだけになるわけですね。そうすれば、自分の株の中では受粉しないですよね。
次におしべが出てくると、オスの状態になりますよね。この時は自分の花粉をほかの株に運ぶだけの状態になるってわけなので、そのオスとメスの熟すタイミングをずらすことのメリットがそこにあるわけですね」
(編集部注:ほかにおしべとめしべを時間差で出す植物で、夏に観察しやすいのはキキョウだそうです。最初はおしべが出て、それがぺた〜となったら、次にめしべが出てくるそうですよ。花の中心だけが変わるのが面白いと、鈴木さんはおっしゃっていました)

夏は「つる性」植物が面白い
※新しい本に森の環境に欠かせないのが「つる性」の植物と書いてありました。それはどうしてなんですか?
「つる植物って基本的に自分では自立しないわけですよね。自分の力では立てない。だからほかの植物に寄りかかったり、絡みついたりして伸びていくわけですけど、そういう生き方をするってことは、森があった時に森のいちばん端っこを覆っていくように成長していくっていう意味なんですよ、自然界の中ではね。
そうすると、よく『森のカーテン』なんて言うんですけど、森の端っこをつる植物が覆ってくれると、そのつる植物によって強風が吹いても森の中に風が入ってこなかったりとか、林内の環境が安定するって言われているんですよね。温度も湿度も適当な状況に保たれるというところで、林内の環境を安定させるために役立っていると言われています」
●つる性と言ってもいろんな巻き方があるんですよね。
「あります! 夏以降はとにかく、つる植物を観察するのがおすすめですね。街中だったらフェンスを見ればいいので、フェンスをひたすら見る。そうすると自分のつる本体が巻きついていくっていう方法もあれば、自分のつるの本体から別の巻きひげってやつをぴろぴろって出して、その巻きひげでペタペタとしがみつきながら登っていく、なんかロック・クライミングしているみたいな感じですよね。
そういう感じで登っていくつる植物もあるし、あるいは巻きつかないで、巻きひげの先を吸盤みたいにして、その吸盤で壁にペタペタ張り付いて伸びていくっていうのがあったりとかして、これも様々なんですよ」

植物の魅力は、動かないこと!?
※初歩的な質問で恐縮なんですが、植物はなぜ「緑色」なんでしょう?
「これは植物は光合成して生きていく・・・これ、極めて大事な話なんですけど、私たちは移動しますよね。何かほかのものを食べたりするわけですよ。そういう生き方をしているわけですけど、植物は移動しない! その場所で生きていかないといけないっていうところで、太陽光を集めて、そこから生きるエネルギーを作り出せるっていう、そういう生き方をしているわけですよね。
なので、とにかく光合成をすることが非常に大事な行為になるわけですけど、光を吸収する必要があるわけです。その時に役立つのが葉緑素、クロロフィルってやつですね。それが要するに緑色をしているということです。あの色は植物が光合成をしているんだなっていう色なので、葉っぱって緑色じゃないですか。だから葉っぱで光合成しているんだなって思えるわけですよね。
そう思うと草の茎とかって緑色をしているじゃないですか。ああいうところにも実は葉緑素が入っていて、茎も光合成していると言われているです。なので、植物のどこが緑色なのかを見ると面白いかもしれないですね。意外といろんな発見があるかもしれない」
●鈴木さんをこんなに虜にしている植物の、いちばんの魅力ってなんでしょう?
「やっぱり(植物は)移動しないっていうところが、本当に面白いなって思っていますね。とにかく僕たちとは全く違うんですよね、生き方が。移動しないって僕たちからすると、非常にデメリットに感じるじゃないですか。今ここで生きてろって言われても困っちゃいますよね。だけど、植物は別にそれでいいんですよね。
だから移動しないためのいろんな工夫があって・・・たとえば、移動しないで誰かに食べられちゃったら、どうするのかなって・・・植物には芽っていうのがあるんですよ。もし体の一部が食べられても、芽が残っていれば、芽からまた新しい葉っぱが出てくるんですよ。
そもそも移動しなくても生きていられるようになっているから、そういうのを見ていると、僕たちはつい植物は移動できないから、みたいなことを言うけど、逆に植物側からするとお前たちはなんで移動してるんだと・・・大変じゃないか、移動するのは、っていうふうに思われても、しょうがないよねって思うわけですね。
そうすると自分はどういう生き物なんだろうとか、そういう視点が出てくるわけですよ。常に僕は植物を見ているけど、植物側から何かを投げかけられているっていうような気がするわけですね。そこに僕は魅力を感じているんですよね」
INFORMATION
鈴木さんが主催する大人気の観察会を漫画で再現してあるので、参加者になったような感覚で楽しく読めますよ。きょう教えてくださった葉っぱや花のことなどもわかりやすく解説。さらに街中で見られる樹木や草の図鑑も載っています。この本を持って、街中の植物観察に出かけましょう!
小学館から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎小学館:https://www.shogakukan.co.jp/books/09311536

鈴木さんが主催している街中での植物観察会は現在、年間講座のみとなっています。駅前でも30種ほどの植物を観察できるし、基本的には同じルートを巡って、季節によって変化する植物たちを観察するそうです。植物の変化に気づくと人生がより楽しくなるともおっしゃっていましたよ。
鈴木さんの活動については、オフィシャルサイト「まちの植物はともだち」をご覧ください。
◎まちの植物はともだち:https://beyond-ecophobia.com
2023/7/16 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、「海の日」を前に、東京湾でコンブを養殖し、活用している「幸海(さちうみ)ヒーローズ」の共同代表「富本龍徳(とみもと・たつのり)」さんです。
東京湾でコンブが育つの!? っと疑問に思ったかたもいらっしゃるかも知れませんが、実は立派に育つそうですよ。
そんなコンブは水中で光合成を行ない、二酸化炭素を吸収。その吸収率は、なんと、杉の木のおよそ5倍の量だそうです。
富本さんは、私たちが直面している地球温暖化などの環境問題にコンブが大きな役割を果たしてくれると期待しています。
きょうは、地球を救うかもしれない、コンブの可能性に迫ります。
☆写真協力:幸海ヒーローズ

横浜市金沢区でコンブ養殖
※SDGsはご存知の通り「SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS(サステナブル・デベロップメント・ゴールズ)」の頭文字を並べたもので、日本語にすると「持続可能な開発目標」。これからも地球で暮らしていくために、世界共通の目標を作って、資源を大切にしながら経済活動をしていく、そのための約束がSDGsです。2015年の国連サミットで採択され、全部で17の目標=ゴールが設定されています。
今週は「SDGs=持続可能な開発目標」の中から「気候変動に具体的な対策を」、
そして「海の豊かさを守ろう」ということで、東京湾でコンブを養殖し、活用している富本龍徳さんの活動をご紹介します。
富本さんは2016年にコンブの養殖に取り組み、2年ほど前に「幸海ヒーローズ」として活動を再スタートさせました。「幸海ヒーローズ」の「幸海」は、実は「里海」のミスプリントが発端になっているそうです。
富本さんは「幸海」という響きに惹かれたのと、「海の幸」という言葉があるように、海は私たちに海産物という恵みを与えてくれる。その一方で「海にとっての幸せとは何だろう」、そんな思いもあって、「幸海ヒーローズ」と名付けたそうです。
●「幸海ヒーローズ」では、具体的にはどんな活動をされているんですか?
「ひとつはコンブ養殖を通して、温暖化対策とか生態系の保全ということで、神奈川県横浜市金沢区の漁師さんと一緒にコンブ養殖をしながら、作ったコンブを水揚げして、利活用するっていうところまでをやっている団体です。
コンブが海の中にない期間は、たとえば環境教育っていう観点で、小学校中学校に行ってコンブとか海の話をしたり、コンブを取り扱いたいっていうレストランさんがいたら、そこにコンブの説明に行ったりとか、そんな感じですね」
●東京湾でコンブ養殖しようと思っても、そう簡単ではない気がするんですけど・・・。
「そうですね。いろいろ権利関係とか法律関係とか難しいこともあるんですけど、そもそも本当にコンブが東京湾で育つのか、みたいなところは、ずっとドキドキしていたんです。でも意外とすごく豊かに立派なコンブができるんですよね」
●もともとコンブがない場所で、コンブを養殖することに対しては、何かためらいみたいなものはなかったですか?
「もともとコンブの原種は横浜にあるわけではないので、北海道の方たちから、タネを分けていただいて養殖しているんですけど、だんだん年数を重ねていく上で、ほかの環境団体さんから「君たちのやっていること、大丈夫なのか?」とか「いいのか? それで」って厳しく言われた時期もありました。
やっぱりそういう連絡がくると、葛藤っていうのはあるんです。そもそも水温が上がってくると、コンブ自体も海の中で枯れたり、溶けちゃうっていう表現をしているんですけど、枯れたりもしますし・・・。あとはコンブって赤ちゃんを胞子として出すんですけど、胞子が出る前に(コンブを)水揚げしているので、そこは今のところ問題にはなってないという状況ですね」
●自分たちを信じてやり続けてきたっていう感じなんですね
「そうですね」

●養殖しているエリアは、どれぐらいの広さなんですか?
「今やっているのが、僕たち畑とか柵とかって言い方をするんですけど、
今のところ20メートル×20メートルの柵を作って、それが2面分ですね」
●収穫量でいうと、どれぐらいですか?
「コンブの収穫量でいうと、だいたい6トン前後ぐらいが毎年の水揚げになりますね」
(編集部中:海の藻と書く「海藻(かいそう)」の仲間、コンブ。日本で採れるのは10種ほどで、その90%以上が北海道産だそうです。コンブには水溶性食物繊維、ミネラル、そして、うまみ成分のグルタミン酸など、栄養素が豊富に含まれています。さらに、番組の冒頭でもご紹介しましたが、光合成によって、樹木よりもたくさんの二酸化炭素を吸収してくれる特性にも注目が集まっています)

コンブに強い衝撃!?
※東京都出身の富本さんは食のコンサルティング会社を退職したあと、フリーランスとして、地方の産物を東京で販売する営業支援などを行なっていたそうです。
●そもそもなんですが、コンブとは、どうやって出会ったんですか?
「秋田県の三種町っていう町のイベントに参加した時に、東京で物産展をやった時に、たまたま三種町の隣町で、アワビの陸上養殖っていう技術でアワビを販売されていた会社さんがあって、お昼休みに“きょうの売り上げ、どうです?”みたいなそんな世間話をしていたんですね。
その時にアワビがコンブとか海藻を食べるってことも知らなくて・・・(コンブは)アワビが食べるだけじゃなくて、環境にもすごくいいんだよっていうことを言われた時に、なんか雷が落ちてきたような強い衝撃があったんですよ。
で、調べたらコンブって使い方が無限にあって、今自分が遠くの遠くの存在に感じている環境問題に対しても、こんな身近な素材でアプローチできるのかと思ったら、すごくスイッチが入っちゃって、そこからずっとやっていますね」
●具体的にコンブのどんなことがわかったんですか?
「もちろん人間が食べて健康にいい部分もありますし、ミネラルがたっぷりなので、たとえば畜産の牛とか豚とかの飼料にもなったり、肥料として作物にプラスになったりとか・・・。
ほかには銭湯さんとコンブ湯っていう取り組みをやっているんですけど、肌にも良かったりとか、本当にいろんな汎用性があって、すごく面白い素材だなと日々思っています。」
●コンブはすごい! というのを感じたとしても、それに人生をかけようと思うのはなかなかないと思うんですけど、やってみようって思えたのはどうしてなんですか?
「やっぱり今お伝えしたように、可能性がすごく無限にあるなっていうところに携われたら、きっといろんな方とコミュニケーションできて、そんなに楽しい仕事はないんじゃないかなと思って・・・」
●でもすごいですね~、コンブをいちからやってみようって思われたわけですね。で、今につながっているということですね。
「そうですね」
(編集部注:「幸海ヒーローズ」では「ぶんこのこんぶ」というブランド名で、商品展開。生のコンブほか、クッキーやアイスクリームなどを作っているそうです)

コリコリ食感、香りと色味が若い!?
●コンブというと北海道の寒い地域の特産品っていうイメージがあるんですけど、横浜市の金沢漁港で養殖されているコンブには、どんな特徴があるんですか?
「いい質問ありがとうございます。実際、横浜のコンブは種類としては真コンブっていう出汁のよく出るブランド・コンブのタネで養殖しているんです。期間的に北海道のコンブと違うのは、北海道は海がずっと冷たいので2年ぐらい養殖できたりもして、10メートルぐらいの巨大な長さになって、厚みも出てくるんです。
そうすると食物繊維だったりがぎゅっとしてくるので、それは乾燥コンブに適したコンブなんですけど、僕たちがやっているのは11月から12月ぐらいにタネ付けして、水温が上がってくる4月ぐらいには水揚げするので、どちらかというと薄いコンブなんです。
それでも2〜3ミリの赤ちゃんコンブからスタートしたコンブが、4か月後には4メートルにも育つんですね。たとえば食感でいうと、すごくコリコリした歯ごたえのある食感で、若いコンブなんで香りが強かったり・・・あとは色味がとっても鮮やかなところが特徴になりますね」

●自然相手の作業じゃないですか。難しいなって感じることはないですか?
「それがですね、お陰さまでコンブの収穫量は結構安定しています。畑と違って海がコンブ育ててくれるので、草むしりする時間もいらないですし、肥料を与えることもないんですね。なので、ほとんど手がかからないっていう・・・」
●そうなんですね! コンブに人生かけてみようって思われて、初めて収穫した時はどんなお気持ちでした?
「やっぱりすごく嬉しかったですね、純粋に。それでこんなにも巨大な、生で見るのもその時が初めてだったんですけど、すごいフォルムというか、形には圧倒されました」
●どんな感じなんですか? 収穫の時のコンブって見たことがないので・・・。
「そうですよね。僕たちが多分一般的に見ているのは、スーパーに並んでいる緑色のワカメとかだと思うんですけど、まず(コンブの)色は茶色なんですよね。海の中に入っている間っていうか・・・その茶色の物体が目の前に現れた時には、本当になんかクマが目の前に現れたぐらいの衝撃でしたね」
コンブのお風呂!?

※都内の銭湯で「コンブ湯」というのを展開されているそうですね。これは、湯船にコンブが入っているんですか?
「まさしく、そういうことです。なので見方によっては、おでんの具材になったみたいとか(笑)、出汁の気分になったみたいっていうこともあるんですけど・・・」
●たしかに!(笑)
「いちばん最初にコンブ湯をやったきっかけは、ヨーロッパに行くと、タラソテラピーっていう海水とか海の泥とか海藻とかと人間とで、長いお風呂の歴史があるんですけど、日本でタラソテラピーをやろうと思ったら、多分高級ホテルのエステでとか、すごくお金も高いですよね。
そういうことをもっともっと身近に感じられることはないかなと思って、スタートしたのがきっかけで、日本には公衆浴場の文化があると思って、それで(銭湯の)門を叩いたのがコンブ湯のきっかけですね」
●お湯加減とかってどういう感じなんですか?
「わかりやすくいうと、たとえば中華料理の、あんかけのチャーハンとか、あんかけのラーメンっていつまでも熱いじゃないですか」
●熱いです!
「それと一緒で、コンブのヌルヌルのとろみというか、ヌルヌル成分がお湯に溶けた時に、あんかけと一緒でお湯が冷めにくいというか、そんなこともあって保温効果があるんじゃないかと思います」
●そうなんですね~、みなさんの評判はどうでした?
「SNSを見ても、みなさん面白いリアクションをしてくださって、本当に出汁になったみたいとか、結構ポジティヴな反応があって、結構、常連さんもできてきたような企画になっています」

(編集部注:お風呂つながりでいうと、富本さんは繊維会社と一緒にコンブを練り込んだ繊維を開発、なんと「サウナハット」を作っちゃったんです。このサウナハット、吸水性と保湿性に優れているので、サウナ室で髪の毛をしっかり保護してくれるそうですよ)
コンブのバスボム!?
※ほかにも、海外のブランドとのコラボレーションが実現したそうですね?
「みなさんがわかりやすいブランドさんとコラボレーションさせていただいた、いい事例なんじゃないかなと思っているんですけど、イギリスの大手コスメ・ブランドのLUSHさん」
●あの入浴剤とかバスボムとかの? え~、私、使っています!
「使っていますか! 香りもすごくあっていいですよね! LUSHさんの入浴剤に今回コンブの原料を採用していただいています。LUSHさんもサステナブルの素材を探されていらっしゃる中で、僕たちの環境保全だったりっていうところの観点が共鳴したというか、そういったところもあって、今回使っていただいたんじゃないかと思いますね」

●そのバスボムもスタジオにも持ってきていただきましたけれども、とってもいい香りですね!
「本当に(お風呂に)入っているだけで、すごく心地良くなります。ここにもコンブが含まれていて、やっぱりお風呂に使っていただくと、ヌルっとしたような感触がありますね」
●とってもカラフルでこれがコンブというのは、全く見た目ではわからないですけれども、原料としてコンブが使われているということなんですね。
「はいそうですね」
コンブは地球を救う
※次のコンブの収穫はいつ頃なんですか?
「次は、また来年の4月に予定しています」
●一般の方が収穫に参加できたりするんですか?
「そうですね。みなさん北海道に行ったりしないと、コンブの収穫の時期も限られていますし、行かないと多分そういう体験とか見ることってできないと思います。それを逆に一般の方に、今海って大変な状況だよとかっていうことも伝えつつ、実際に採れたてのフレッシュなコンブを、しゃぶしゃぶにして一緒に食べたりとか、そういうことをしながら、ちょっと海について考えてみようっていう時間を設けて、一般の方に来てもらえるような、開けた収穫の場になっています」
●いいですね! 富本さんはコンブと出会って人生がガラリと変わりましたけれども、やっぱりコンブで世界は変わりますか?
「そうですね。本当にこのコンブの素晴らしさ、可能性に気づいてくれる人が増えて、一緒にコンブは面白いから何かやろう!っていう方が増えていけば、海の問題も解決していきますし、僕たちにとって健康的にもいいですし、地球がどんどん良くなっていくんじゃないかなと思います」
●コンブは地球を救ってくれますか?
「そうですね! コンブは地球を救うと思います」

☆この他の「SDGs〜私たちの未来」シリーズもご覧ください。
INFORMATION
富本さんが英国のナチュラル・コスメ・ブランドLUSHと開発したバスボム、一箱に3個入っていて、そのひとつに富本さんたちが養殖したコンブが使われています。商品名は「涼の一服」。販売価格は1,400円です。お買い求めはLUSHのサイトから、どうぞ。
◎LUSH:https://www.lush.com/jp/ja/p/ippuku-ryo-gift
富本さんの活動については「幸海ヒーローズ」のサイトをご覧ください。
◎幸海ヒーローズ:https://sachiumi.com
2023/7/9 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、旅とサーフィンをこよなく愛するシンガーソングライター「東田トモヒロ」さんです。
東田さんは1972年生まれ、熊本市在住。2003年にメジャーデビュー。旅とサーフィン、スノーボーディングをこよなく愛し、自然に寄り添った暮らしや、旅をモチーフにして生まれる曲と、オーガニックなサウンドが多くのファンを魅了しています。
そんな東田さんは、いち早くエネルギーと食べ物の自給自足に取り組んでいるほか、福島県相馬市の保育園にお米や野菜を届ける活動もされています。
そして6月7日にデビュー20周年、通算16作目となるアルバム『Rough Morning』を発表されました。「ラフ・モーニング」というタイトルは、東田さん曰く、英語にはない言葉だそうですが、ある日、ライヴが終わって、海のそばに車を止め、ライヴの余韻や疲れもあって、そのまま寝てしまい、朝を迎えた時に、なんとなく車の中がちらかっていることがあったそうです。
そして曲を作り始めたら、メロディとともに思いついた「ラフ・モーニング」というフレーズを口ずさんだところ、その言葉がしっくりきたので、残すことにしたそうです。
そんな東田さんに熊本での暮らしぶりなどうかがうほか、デビュー20周年を記念するオリジナル・アルバム『Rough Morning』から旅をテーマにした新曲もお届けします。
☆写真協力:東田トモヒロ

曲のアイデアは旅先で
※東田さんは旅をモチーフに曲作りをすることも多いそうですが、今回の20周年記念アルバムに収録されている曲も、旅で出会った景色や人からインスピレーションを得て作ったとか、そんな感じなんですか?
「そうなんですよ。だいたい自分の場合、スタジオとか自宅でギターを持って、さあ曲を作ろうっていうんじゃなくて、ふとアイデアとして思い浮かぶんですね。それがどういう時が多いかっていうと、移動している時が多いんですよ。
車で移動していて、走っている時になんとなくメロディを思いついて、それでボイスレコーダーで、そのアイデアを録っておいて、あとで聴き返す時にピアノの前に座ったり、ギターを持ったりして、あの時思いついたメロディにはどんなコードが合うんだろうとか、そうやって作っていくんですよね。
だからツアーの途中で曲を作って、ひとつのツアーが終わったら、なんか1曲アイデアが残っていて、その結晶がアルバムっていうか・・・今回のアルバムもそうやって作りましたね」
●旅先で見た景色とか出会った人とか、そういったところからインスピレーションを得ていらっしゃるんですね。
「まさにその通りです。 『Traveling』っていう曲は・・・よく覚えているのが四国で信号待ちしている時にメロディを思いついて・・・あ、これいいぞと思って、ちょうど旅の途中だったから『Traveling』っていうテーマで書いてみようと思って、 四国を旅している間に作りましたね、歌詞まで全部。それをよく覚えていますね」
●ヘぇ〜! 四国だったんですね。
「愛媛でどこかの信号待ちしている時に・・・そうそう(笑)」
(*放送ではここで「Traveling」を聴いていただきました)
みんなで田植え、チャリティ米
※東田さんは地元熊本で農家さんから田んぼや畑を借りて、4家族でシェアし、役割分担しながら、お米や作物を育てているそうです。毎年育て方などを勉強し、10年ほど続けているそうですよ。今年も田植えを行なったそうですが、イネの苗は手植えなんですか?

「もう今ほとんど使われなくなったんだけど、手押しの田植え機っていうのがあって、それはもうほとんどの農家の方が使っていないので、余っているんですよね。だから安く譲ってくださったり、あるいはくれたりする場合があるんですけど、それを使っているのと、もうひとつ別の場所は(田植えをする時に)毎年呼びかけるんですよ、ワークショップとして。30人ぐらい集まってくださったりします。
そこはなんでそういうふうにしているかっていうと、手植えでやるんですよね。手で植える体験を子供たちとか、大人もやったことない人たちを募って、総勢30人から40人ぐらいで手で田植えをしています。
で、しかもそこの手で植えた田んぼで収穫したお米は、チャリティ米にして、福島の南相馬の保育園に送っているんですね。南相馬はまだ、飼料米しか作れないということで、給食のお手伝いをできたらなと思って、それも10年続けているんですけど、その手植えのゾーンはチャリティ田んぼにしていますね」
●九州の季節の野菜や果物とかも届けていらっしゃるんですよね?
「それも一環で『チェンジ・ザ・ワールド』っていう活動をやっているんです」
●その保育園の子供たちに、お米や野菜を送ろうと思ったきっかけは、なにかあったんですか?
「そこの保育園は原発の事故のあと、地域のものがほとんど食べられなくなって、僕らは安全な食べ物を食べられているんだけど、それで困っているというか必要とされているところに、なんか手伝いできたらなということで、東日本大震災のあと、1年後からそういう活動を始めたんですよね」
●そうだったんですね。
「そうそう、それを今でもお米という形で、毎年お米を作って送ることを続けています」

自然とつながる安心感
※今年、野菜は何を育てているんですか?
「もうね、野菜は諦めました(笑)」
●あれ!? どうしちゃったんですか?(笑)
「 あのね、野菜はやっぱり、毎日そばにいる人じゃないと無理かも・・・。だから、野菜はやめて果物とお米だけにしました! もう本当にね、大変ですね! 何でもかんでもやろうとすると・・・。やっぱり本業は音楽だから(笑)、無理しないでできることをやらなきゃなと思ったんですよ」
●果物とお米にしたんですね。
「果物とお米だったら、そんなに毎日見ていなくても大丈夫じゃん。オクラとか一回植えて、旅から帰ってくると、もうなんだろ、あれ・・・すっげえ巨大なハサミみたくでかくなって、もう固くて食べられないみたいになっちゃうから・・・」
●そうですね。お世話が大変ですよね(笑)。
「だから果物だったら、この時期! って決まっているじゃないですか。そこだけいれば、美味しく食べられるし、田植えも稲刈りもそんな毎日やるもんじゃないから・・・だから田んぼは意外とミュージシャン向きなんですよ、やったほうがいいと思う、ミュージシャンみんな」

●食べるものを自分で育てるとか、自給自足に近い生活を送るっていうのは、なにか理由があるんですか?
「いや、特に理由はないんですけど、単純に楽しいっていうのと、お米もそれまで長いこと食べてきたけど、どうやって作られているかって実際やってみるまで知らなかったから・・・。で、やってみたら、なかなか言葉では、ロジックでは説明しづらい、安心感っていうか、そういうものが得られるんですよね。
自分が大地とつながって存在しているというか、それはすごくサーフィンと似ていて、海に入る時っていうのは本当に自分の身ひとつで、サーフボードはもちろんあるんですけど、すごくシンプルな形で自然とつながれるじゃないですか。
太陽があって海があって砂浜があって、自分がこの地球というか自然の中に存在しているとすごく実感できるんですよ。田んぼとか、それこそ果樹を置いている山の一部、そういうところにいるだけで、自分がちゃんと自然とつながった存在としてあるっていう、それはすごく安心する要素なんですよね。
自分を肯定できるというか、自分を確認できるし、あと静かに自分に自信が持てるというか、なんかそんな気がするんですよね。だからこれはやっぱり自分のために続けるべきだなというふうに思って、きっかけは些細な、ちょっとやってみたいなくらいのことだったんだけど、サーフィンと似ていて、気づけば自分のライフワークというか、欠かせない活動のひとつになっていますね」
(編集部注:東田さんが育てている果物は、この時期はプラムがたくさん成るそうですが、野鳥にも食べられてしまうので、どっちが先に採るか、鳥と格闘しているそうですよ。またこれからは、ブルーベリーの時期になるので、朝、実を採って食べる新鮮なブルーベリーの味は最高だとおっしゃっていました)
ソーラー発電は音がいい!?
※熊本のご自宅でソーラーによる自家発電を行なっているそうですが、なにかきっかけとかあったんですか?

「そういう暮らしを、オフグリッドっていう暮らしをしている人がいるっていうのは長年知っていたんですね。それこそ完全に自給自足しているというか、僕の友達にもいるんですよね。煮炊きは全部薪でやって、電気は僕と同じようにソーラー発電で蓄電して、電気をバッテリーから取って、それを使って山の水を引いて暮らしている、その人は完全にオフグリッドで阿蘇のほうに暮らしているんですけど、さすがに(僕は)そこまではできないなと思って・・・。
でも自分の暮らしの中で、一部そういうスタイルでやれたらいいかもな、自分にはそのぐらいでいいかもなというか、それで電力の一部を自分で賄おうと思って、そういう暮らしをしている人にアドバイスをしてもらったんです。

それを導入して、今自分が使っているスタジオが、小屋みたいなところがあって、そこにドラムセットとかアンプとかスタジオの機材を全部置いているんですが、そこの電気と、もうひと部屋ぐらいは全部ソーラーで賄っていて、スタジオは完全オフグリッドですね。
なので、今回のアルバムも太陽の光でできた電力で作りましたね。6枚の(ソーラー)パネルがあって、バッテリーはゴルフ場のカートで使っているやつを4台置いていて、1200ワットは発電しているんですよ。十分にレコーディング機材はそれで動くんですよね」
●雨とか曇りの日はどうされているんですか?
「さすがです! そうなんです。だから曇りの日が3日続くと、さすがにバッテリーに負荷がかかっちゃうから、4日目はもう使わないようにしているんだけど、だいたい日本は4日目に晴れるんですよね~、いや〜わかんないけど、多分、多分ね(笑)」

●スタッフから聞いたんですけど、私がパーソナリティーになる前に、この番組にシアターブルックの佐藤タイジさんにご出演いただいた時に・・・
「あー、タイジさん!」
●ソーラー発電の電気で録音すると、音が良くなるっておっしゃっていたみたいなんですけど、それは東田さんもそう感じることはありますか?
「それはわかんないですけど(笑)、あ〜、タイジさん、多分メンタルから入っていると思う(笑)、これは音がいいぞ!って。でも確かに彼が言っていることも一理あって、バッテリーから割とロスがなく、発電した場所から距離がほとんどないから、そこでロスが生まれずっていうのは聞いたことはあります。
だから(音が)ピュアだっていうふうに言っている人がいたのは覚えていますね。あとノイズが少ないとかね。そういう意味では、もしかしたらいいのかもしんないけど、エビデンスが(笑)、佐藤タイジの言っていることのソースとエビデンスがほしい(笑)」
スリランカでサーフ&ライヴ!
※東田さんのナチュラルなライフ・スタイルは、やはり音楽にも現れていると思います。その辺は意識されていますか?
「そこをなるべく意識しないように音楽に落とし込めたらいいなと思っているんですよね。意識しないでも、やっぱ出ちゃうでしょうね、音には。
例えばジャック・ジョンソンとか、彼はそこまで意識せずとも、やっぱハワイの空気感って出ているじゃないですか。きっとノラ・ジョーンズだったらノラ・ジョーンズの暮らしの、ニューヨークなのかもわかんないけど、ちょっと都会的な雰囲気とかね。
だから多分、自分も普段の暮らしとか、旅をしている時に感じていること、見聞きしていることっていうのは、やっぱり知らず知らずのうちに出るっていうのがいいんだろうなと思って・・・音楽と向き合う時はかえって意識しないようにしていますね。そしたらちょうどいい塩梅になるんじゃないかなというか・・・」

●デビュー20周年のアニヴァーサリー・イヤーの最後12月に、インド洋に浮かぶ美しい島、スリランカでライヴを行なうんですよね? なぜまたスリランカだったのですか?
「そうなんですよ。これね、スリランカでライヴをやります! っていうと、そういう名前のカレー屋さんでやるんですか? って言われる時もあるんですけど(笑)、本当にスリランカでやるんですよ!」
●あの、スリランカですよね?
「あのスリランカですね。これ、なんでかって言うと、一度行ったことあるんです、実は。プロモーション・ビデオの撮影で、『LIFE MUSIC』っていう曲の・・・それ今YouTubeにはもう(ビデオは)なくなっちゃっているんですけど、もう一回スリランカを旅する映像を撮りたいなっていうのがあるのと、どこかで(ライヴを)やりたいって思った時に、記念の年だし、そういう記念になるようなところ、例えば、憧れているライヴ会場とか、そういうのもいいなと思ったんだけど、なんかそれってありきたりだなと思って・・・。
やっぱちょっと面白いことやりたいと思って、サーフポイントのすぐそばで(ライヴを)やりたいな~、しかも海外でやったら面白いんじゃないかなっていうのが(笑)、なぜって言われたら、たぶん面白そうだからとしか答えようがないですけど・・・」
●サーフトリップの聖地のひとつであるスリランカには、サーフィンをやりに行くんですか? ライヴをやりに行くんですか?(笑)
「両方ですね! だから日本から行きたいっていう方とは(スリランカに)一緒に行って、サーフィンをやったことない方がもしいらっしゃったら、僕も友達と一緒にサーフレッスンしようかなと思っているし・・・」
●えっ! すごい! 贅沢ですね~。
「ライヴは一回だけなので、あとは全部多分サーフィンしているんで、一緒に波乗りしましょうっていうツアーですね」
●もうサーフィンツアーですね(笑)
「ですね!」
(*ここで「Everything」を聴いていただきました)
☆この他の東田トモヒロさんのトークもご覧下さい。
INFORMATION
東田さんのデビュー20周年を記念するオリジナルアルバム『Rough Morning』にはきょうお届けした「Traveling」と「Everything」を含め、全部で7曲収録されています。ソーラー発電の電力を使って、自宅スタジオでレコーディングした曲はいい意味で力が抜けていて、聴いていると、とてもリラックスできます。旅気分満載のナチュラルなサウンドをぜひお楽しみください。お買い求めは東田さんのオフィシャルサイトから、どうぞ。
また、東田さんは現在、『Rough Morning』リリース・ツアーを行なっていて、7月14日から北海道ツアーに突入します。
そして、アニヴァーサリー・イヤーのファイナルとして12月6日にスリランカでライヴを行なうことが決まっています。
12月5日から4泊6日のツアーが組まれていて、滞在は、ビーチとサーフィンで有名なスリランカの南海岸「ミリッサ」のホテルだそうです。旅行代金など含め、詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
◎東田トモヒロ・オフィシャルサイト:http://live.higashidatomohiro.jp
2023/7/2 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、薬膳・発酵料理研究家の「山田奈美(やまだなみ)」さんです。
編集者、そしてライターとして活躍されていた山田さんは「東京薬膳研究所」の「武 凜子(たけ・りんこ)」さんと出会い、薬膳に共感し、武さんからマン・ツー・マンで基本を学びます。その後、北京中医薬大学の日本校で本格的に薬膳を勉強し、資格を取得。そして、おばあちゃんやお母さんから教えてもらった発酵食の知識と、薬膳を組み合わせた、体に優しい季節の食を伝える活動を行なっていて、幅広い世代から支持されています。
また「食べごと研究所」を主宰され、神奈川県葉山町の古民家をアトリエに、和食薬膳教室や発酵教室などを開催されています。
そんな山田さんが先頃、『いつもの食材と調味料で 体が整うごはん』という本を出されました。
きょうは、その本をもとに、薬膳と発酵のふたつの知恵を組み合わせた、手軽で、なにより体にいいお料理や、夏野菜のおすすめレシピなどうかがいます。
☆写真協力:山田奈美、福井裕子、ナツメ社

薬膳のもと、陰陽五行理論
※この本には薬膳と発酵食品を組み合わせたレシピなどが載っています。改めてなんですが、薬膳とはなにか教えていただけますか。
「薬膳というとちょっと難しいイメージがあって、漢方薬の生薬を使ったようなお料理じゃないかっていうイメージがあると思うんですけど、実際は普段使っているような、身近な食材ひとつひとつにも働きがちゃんとあるので・・・全部覚えるのは難しいんですけど、体を温めるとか冷やすとか血の巡りをよくするとか、そういう働きをなんとなく踏まえて、毎日の食べ物で健康を維持するっていうようなものが薬膳になります。
難しいことは何もないですね。体に入ってきて、影響を与えない食べ物はひとつもないので・・・やっぱり自分の体質を知るのが大事になってくるんですけどね。その体質とか季節に合った食べ方をしていくと、本当に病気を防ぐことができると思います」

●薬膳のもとになっている理論があるんですよね?
「そうですね。ちょっと難しいんですけど、陰陽五行理論(いんようごぎょうりろん)というものがあります。陰陽論と五行論が組み合わさったものなんですけれども、古代中国に生まれた哲学のようなものなんです。
陰陽論は、ちょっと聞いたことがあるかもしれないんですね。陰がちょっと冷たいとか暗いとか水とか、下に下がるようなエネルギーとか、そういうものです。陽は明るいとか暖かいとか、太陽のような・・・そういうふたつの相反するエネルギーを、陰と陽とに分けているのが陰陽論ですね。すべての食べ物も、宇宙にあるすべてのものも、この陰と陽に分けているんですね。それが陰陽論になります。
で、五行論。五行は、木火土金水(もくかどこんすい)って言うんですけど、木・火・土・金・水という5つ元素みたいなものを言います。そしてこの“行く”っていう字は、巡るとか循環するっていう意味なので、5つの元素が巡ることによって、あらゆるものが生まれたり、変化していくのが、五行論になります」

陰陽五行理論〜五味・五性
※食物も「五行」に分類されるということですが、本に、五つの味と書く「五味(ごみ)」のことが載っていました。体の中に入ってきたときの働きも含めて、ご説明いただけますか。
「五味というのは酸味・苦味・甘味・辛味、あと塩辛い味の鹹味(かんみ)と言うんですけど、その5つが五味と言います。それぞれ五臓と密接に関係していて、酸味のものは肝臓の働きを補うというか、整えるような働きを持っていて、苦味は心臓、甘みは脾胃(ひい)と言って胃腸ですね。
で、辛味は肺とか大腸の働きにつながっています。鹹味、塩辛い味は腎臓とか膀胱につながっていると言われていますので、それぞれの味を食べることによって五臓を補うことができると考えるのが、五行論の五味ですね」
●つながっているんですね〜。5つの性質と書く「五性(ごせい)」というのも、
山田さんの本に載っていましたね。
「これは食べ物を5つの、温めるとか冷やすとかっていう性質に分けたものなんですね。五性は、熱・温・平・涼・寒と言って、熱性・温性・平性・涼性・寒性・・・平性というのは、温めも冷やしもしない中間の性質です。
涼性はちょっと冷やす、寒性は寒いのでかなり冷やすという性質なんですけど、食べ物によって、冷やすものだったり、温めるものだったりというのがありますので、自分が例えば 冷え性だなと思ったら、できるだけ温めるものを摂っていくと、冷え体質も少しずつ改善されていくことになります」
消化を助ける発酵食品

※薬膳の知恵と、お味噌やお醤油などの発酵調味料を組み合わせることで、どんなメリットや効果が生まれるのでしょうか?
「発酵調味料のメリットとしては、消化がすごく良くなるってことが、まず第一にあげられますね。日本人は、基本的には消化力が弱い人がとても多いんですね、胃腸が弱い人がね。胃はどうしても湿度に弱い、水分に弱いんです。日本は海に囲まれていて、木も多いし、川も多いので、どうしても湿度が高い環境になって、そこに(日本人は)暮らしているので、胃が弱くなりやすいんですね。
大陸の乾燥した所で育っている、中国とかアメリカの人たちと比べると、体温も低いですし、胃の働きがやっぱり弱いので・・・向こうの人たちは本当にガツガツ食べても大丈夫なんですが、日本人は割と胃を壊しやすいんですよね。ちょっと限度を超えるとね。
胃腸が弱いので、それを補ってくれるのが発酵食品になります。発酵食品をちょっとプラスしてあげるだけで、消化を助けてくれるっていう感じになります」
●本当に日本人の体質に合っているんですね。
「そうですね。和食は本当に発酵調味料をいっぱい使うものが多いし、日本はもともと発酵文化なので、やっぱり日本人の胃腸の弱さを補うために、昔から使われてきたんじゃないかなと思いますね」
●そうだったんですね〜。薬膳の働きと発酵調味料を組み合わせる時の、なにかコツみたいなものはありますか?
「できれば、全部じゃなくてもいいんですけど、ちょっと事前に漬け込んでおくとより消化が良くなりますね。お肉類ですね・・・特にタンパク質は消化に時間がかかるものなので、お肉とかお魚もそうですけど、少し10分とか15分でもいいので、塩麹とか味噌に漬けるとかね。そういうのに漬けてから加熱してあげると、より消化は良くなります」
血を巡らす料理〜ナスを皮ごと!?
●山田さんの新しい本『いつもの食材と調味料で 体が整うごはん』に、こんな不調を感じている時は、全身が冷えているから体を温める料理がいいですよとか、疲れやすくて元気がない時は、気を補う料理がおすすめですよという、そんなページがありました。
「不調から見るあなたのタイプは?」というふうに、いろんな設問が載っているので、私もやってみたんです。私は手足が冷えやすいとか、目の下にクマができやすいとか、肩こりがあるということで、血を巡らす料理がいいですよ、と出ていたんですけれども、これからの季節、夏場ですと、どんなお料理がおすすめですか?
「そうですね。血を巡らすのはやっぱり女性にはすごく必要で、血の滞りやすい冷えている人が多いですね。そうすると血の巡りが悪くなりやすいので、そういう人には血を巡らす料理がとてもいいと思います。
あと、温める料理もいいと思いますので、それをミックスしていくといいんです。例えば、夏の血を巡らす(食材)だと、意外かもしれないんですが、ナスはいいですね。血を巡らします。でもちょっと冷やすんですよ」
●冷やすイメージがありますよね。
「ナスはできるだけ皮ごと、皮の紫色のところに一応、血を巡らすような働きとかがありますので、皮ごと食べていただいて、プラス薬味をいっぱい入れてあげるといいですね。だから焼きナスにしたりとか、蒸しナスにしてショウガとかシソとかをたっぷりのっけて、しょうが醤油とかで食べてあげるとか・・・簡単ですがいいと思います」
●早速、ナスを買って帰ります(笑)。夏は外が暑いですけど、電車とかオフィスは寒いじゃないですか。冷房で体調を崩しちゃうこともあると思うんですけど、そういう時はどういうレシピがいいですか?
「やっぱり自律神経がバランスを崩しちゃうことが多いんですよね、寒暖差があると・・・。その時、自律神経は肝臓と考えるんですね、中医学(ちゅういがく)だと。肝が神経を、自律神経を担うので、肝臓にいいのは緑のものとか酸味のものがいいと言われています。
例えば、緑のツルムラサキとか、夏だったらモロヘイヤとか、ゴーヤもいいですよね。そういう緑のものにちょっと酢の物の酸味をプラスしてあげると、自律神経を補う肝の働きを助けることができると思いますので、いいと思います」
和食の基本「さしすせそ」

「納豆と青梗菜、牛肉のオイスター炒め」。
ご主人がご飯をおかわりするほど、美味しくできたそうです。
※私は去年結婚して、毎日、夫のために献立を考えて夕飯を作るようになったんですけど、主婦の知恵として、この発酵調味料さえ使えば大丈夫、というようなコツがあれば、教えていただけますか。
「和食だと『さしすせそ』の基本の調味料がほとんど発酵食品になります。『さ』は昔は砂糖もみりんだったと言われていますので、みりん、酢、醤油、味噌ですよね。その基本の調味料を毎日使って、(みなさん毎日)だいたい使うと思うんですけど、そういうのを使っていれば、基本的には発酵調味料は摂れていると思います。あとそこにプラスして塩麹とか醤油麹とかがあると、より料理の幅が広がるっていう感じがしますね」
●山田さんの本を読んでいて、塩麹がいろんなレシピに使われているなっていう印象を持ったんですけど、やはり麹はいいですか?
「麹は日本の国菌(くにきん)って言われているぐらい日本ならではの菌だと思うので、(日本人の)体にも合っていると思いますね。なので、麹でいろんなものが作れるのでとてもいいと思います」
●具体的に麹を使った料理でいうと、なにかありますか?
「塩麴ですか? 塩麹ね・・・いろいろ使っているので・・・」
●塩麹をどう使うと美味しいよ、とか、おすすめだよ、とかあれば、ぜひ。
「鶏肉とかにちょっと塩麹をつけて、それで煮込んでもいいし、唐揚げとかにしちゃっても、とても柔らかくなって美味しいですね。煮物にするときは醤油麹にしてあげると、醤油系の煮物にはとても合いますので、いいと思いますね」
●やっぱり夏には夏の、秋には秋の、旬の食材をお料理に取り入れるのがいいですよね?
「基本そうですね」
●夏野菜でいうとおすすめは?
「おすすめは、そうですね・・・これから暑くなってくると、あまり使わない人も多いんですけど、冬瓜(とうがん)とかね。薬膳ではとてもいい食材だと考えられていて、(冬瓜は)水を出してくれるんですよね 。
この時期、だんだん湿度が高くなると、体の中に水が溜まりやすいんだけど、水が溜まってくると冷えるし、肩こりになったり頭痛がしたりとか、いろんな不調につながっていくので、とにかく水は綺麗に出してあげるのが大事なので、その時に冬瓜とかトウモロコシとか、そういうのがとてもいいです。

私の新しい本だと、冬瓜のエスニックスープが載っているんですけど、冬瓜も体を冷やすので、ちょっとエスニック風の黒酢とかナンプラーとかショウガとか、そういうものを入れて、温める食材をプラスして、スープにしてあげると、とてもいいと思います」
(編集部注:山田さんはご自宅でお醤油や米麹、納豆やオイスターソース、そしてお味噌などもご自分で作っていらっしゃいます。初心者でも作れる発酵調味料をお聞きしたら、塩麹と醤油麹を勧めてくださいました)
常に幸せを感じながら
※山田さんのお料理は「旬の食材をシンプルに調理」が基本なんですよね?
「そうですね。旬の食材で美味しい野菜だと、本当に何もしなくてもとても美味しいですね。ただ茹でただけとかでも美味しいので、できるだけ手をかけないっていうか、味を濃くしないで素材の味が出るようにすることを心がけています」
●無意識にあれ食べたいなって思う時があったら、それは体がそれを欲しているっていうことですか?
「そういうふうに感じていただけるといいと思います。あまりわからない人も多いんですけど、欲していることを感じられるのはすごくいいことですね。
甘いものを食べたいなっていう時は、けっこう疲れている時だと思うので、それに従って、お砂糖の多いものじゃなくて、穀物とか芋類とか小豆とか、そういう甘みのものを摂っていくといいと思いますね。体の欲しているものを食べるのは、基本的にとてもいいことだと思います」
●体を整えるにはやっぱり体の声を聞いて、必要なものを摂っていくことが大事になりますか?
「そうですね。とても大事だと思います。あとは季節に合うものですね」
●旬のものとか?
「そうですね」

●山田さんは1日の中で、幸せだなって思う時は、どんな時ですか?
「なんかもう、常に幸せっていうかなぁ~(笑)。あまり嫌だなって思う瞬間がないので・・・」
●素晴らしいですね~!
「好きなことをやっているからかも知れないんですけど、基本的に日々毎日、常に幸せを感じられていると思っています(笑)」
INFORMATION
山田さんの新しい本、おすすめです! お話にあった陰陽五行理論について、わかりやすく載っていますよ。そして、普段の食材と発酵食品を組み合わせた手軽で美味しいレシピが、おかず、汁物、ご飯と麺、そして保存食に分けられ、全部で84のレシピが、豊富な写真とともに紹介。どれも美味しいそうで、作りたくなっちゃいますよ。薬膳と発酵の力を知る一冊、ぜひあなたのおうちにも常備してください。ナツメ社から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎ナツメ社:https://www.natsume.co.jp/books/18012

山田さんが葉山のアトリエで行なっている「和食薬膳教室」は現在は、4月スタートの年間コースとなっているそうです。空きがあれば、体験で参加することもできるとのこと。ほかの教室のことなども含め、詳しくは「食べごと研究所」のオフィシャルサイトを見てください。
◎食べごと研究所:http://tabegoto.com
2023/6/25 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、セーリング・チーム「MILAI」のスキッパー「鈴木晶友(まさとも)」さんです。
稲毛ヨットハーバーのジュニアヨット教室に参加したことがある鈴木さんは、ヨットで地球を一周したい、そんな夢を抱き、なんのツテもなく、単身フランスに渡り、地道な活動を経て、ついにはセーリング・チーム「MILAI」を結成します。
このチームはスキッパーの鈴木さんのほかに、セーリング・パートナーとして「中川絋司(なかがわ・こうじ)」さん、そしてフランス人の女性ふたり「エステル」さんと「アン」さん、イタリア人の「アンドレア」さんの、5人から成る国際チームなんです。

そんなセーリング・チーム「MILAI」が挑戦したのが、初開催となった「Globe 40(グローブ・フォーティー)」。全長12メートルのヨットにふたりで乗って、地球を一周する外洋ヨットレースなんです。
2022年6月にモロッコのタンジェをスタート、途中7箇所の港に寄り、8つのレグ(区間)を、およそ9ヶ月かけて、ゴールのフランス・ロリアンに戻る大冒険です。総距離はおよそ55,000キロと想像を絶します。
今週は、そんな壮大なレースに挑戦し、見事完走を果たしたセーリング・チーム「MILAI」のスキッパー、鈴木晶友さんをお迎えし、「Globe 40」の激闘に迫ります。
☆写真協力:Team MILAI

第1レグはトップ! 第2レグは嵐!?
● 前回のご出演がちょうど1年前の6月ということで、その時はリモートでお話をうかがったんですけれども、今回はこうしてスタジオにお越しいただきました。ありがとうございます!
「初めまして! 今さらになりますが、よろしくお願いします」
●いや〜やっとお会いできました! よろしくお願いいたします。帰国後、いろいろ報告会とかも開催されたそうですけれども、いかがでした?
「思っている以上にみなさんが歓迎してくださって、やっと帰ってきてくれたねって言っていただきました」
●私たちもですよ~。
「ありがとうございます。ベイエフエムのみなさんにも歓迎していただいて、嬉しいです。 本当に自分が帰ってこられたなっていうのを嬉しく思います」

●鈴木さんがチームを組んで挑戦された、地球を一周する外洋ヨットレース「Globe 40」を振り返っていきたいと思うんですけれども、結果としては当初の目標だった完走を見事果たして、総合3位でフィニッシュしました。本当にお疲れ様でした。
「ありがとうございました。思っていた以上に地球は大きかったですね(笑)。でも本当に3位でフィニッシュすることができて、ただただ嬉しいです。
もちろんもっといい成績を狙えたかもしれないんですけれども、私たちは地球一周を達成するということが目標だったので、今回しっかりと、こうやってフィニッシュできて、みなさんにいい報告ができて、本当に嬉しいですね」
●第1レグ、これはモロッコのタンジェからアフリカのカーボベルまでの区間でしたけれども、トップでゴールされたんですよね!
「そうなんですよ」
●これは思い通りのレースでしたか?
「手応えよくて最初からよかったですね。カーボベルまではだいたい貿易風に乗るまでの海域になるので、基本的に追っ手の風で走っていけるんですね。距離も3,000キロなかったかな、2,500キロぐらいだったので、最初の第1レグとしては、慣らし運転ってわけじゃないですけど、無理しないで行こうと思っていたんです。すごくいい走りができたので、本当にいい第1レグを走ることができました」
●幸先のいいスタートでしたね。
「そうですね」
●続いて第2レグは、カーボベルデからモーリシャスまでのレースでした。ここが今回の大会でいちばん期間が長いんですよね?
「そうですね。全体で39日間かけて、アフリカ大陸をぐるっとまわって、モーリシャスまで行きました」
●1ヶ月以上ということですね。
「海の上で1ヶ月以上ですね」
●これはやっぱり難しいコースでもあったんですか?
「8月だったので、まだ南半球は真冬なんですよ。その真冬にアフリカ大陸の下をぐるっとまわるのは、結構大変なコースだったので、すごい嵐もありましたし、あと潮の流れも速くて、すごく難しくて、きついレグでしたね」

●で、この第2レグでトラブルに見舞われたんですよね。
「早速ね(苦笑)」
●何が起こってしまったんですか?
「南アフリカのケープターンをまわる直前に嵐にあいまして、その時に、ヨットの下にぶら下がっている、船のバランスを保つための、2トンの鉛が付いている『キール』っていう重りが、船の揺れでちょっと動き出してしまったので、急遽ケープタウンに入港して確認をすることを決めました」
●その「キール」が機能しないと、どうなるんですか?
「転覆しちゃうんですよ」
●えっ~~〜!
「キールが機能しないで、下手したら落ちてしまうと、もう船はバランスを失って
転覆してしまうので、いちばん大事なパーツなんですね」
●それで、どうやってリカバーしたんですか?
「最初にキールが動き出してしまって、ちょっと危ないなと・・・ただこのまま走ることもできるかもしれないってことだったんですけど、まだ地球一周、先が長いので・・・」
●そうですよね。
「とりあえずここで1回確認をしようということで、一時的に緊急入港して確認をして、応急処置をして、またスタートしたっていう感じですね。2日間ケープタウンにいました」
第6レグで、最大のアクシデント!?
*第2レグでアクシデントに見舞われたMILAIでしたが、レースに復帰後、本来の実力を発揮し、ニュージーランドのオークランドからタヒチのパペーテまでの第4レグと、パペーテからアルゼンチンのウシュアイアまでの第5レグは再びトップでゴールしたんです。

これは、2年かけて、セーリング・パートナーたちとの練習や、船の整備も含めて、いい準備ができていたから、ということなんですが・・・
今回の「Globe 40」で最大の危機がやってくる、ウシュアイアからブラジルのレシフェまでの第6レグです。今年1月にスタートして、アルゼンチン沖でまたもやアクシデントに見舞われてしまうんですよね?
「スタートして4日目にアルゼンチンの沖で、未確認浮遊物体に衝突しました。これは、本当に何にぶつかったかわからないです。 生き物なのか、コンテナなのか、木なのか、わからないですね。
明け方に急に船が(何かと)衝突して、船が止まってしまいました。まずは船の状態を確認しようということで、全部確認をしたらかなりの損傷だったので、一度レースから離脱しようということを決めました」
●ケガとかは、なかったんですか?
「ケガは大丈夫でした。実は私は寝ていたんです。寝ていた時に急な衝撃で起きて、船の中はガラスファイバーが壊れる臭いというか・・・」
●じゃあ、また再び修理をしてっていうことですよね?
「そうです。いちばん近い岸がおよそ1,000キロの距離で、マル・デル・プラタ(*)という港があることがわかったので、4日間かけて、まずはマル・デル・プラタを目指すことにしました。とはいっても、船は結構損傷が激しかったんですね。4日間、船の修理をしながら陸に向かっていましたね」
(*アルゼンチンのブエノスアイレスにある港湾都市)
●壊れた状態で4日間過ごしていたんですね。
「そうなんです」
●不安もありましたよね?
「またもや、キールなんです」
●またですかー!?
「キールがぶつかってしまったので、船から取れて落ちる状態に近くなってしまったんですね。なので、船の中でできる補強をしながら、船のまわりにコンビニとかないから、船にあるものだけを使って修理をしながら岸を目指しました」

●修理をして、またレース続けようっていう決断をされたわけじゃないですか。そう簡単じゃないと思うんですけど・・・。
「まずは入港したマル・デル・プラタに、ヨット・レース用のヨットを修理する設備がなかったんですね。なので、その設備を作るところを探したり、船を乗せる台を作ったり、人を見つけたり・・・で、全部で1か月以上かけて船を直すことになったんです。
自分が知らないところで、本当にここで船を直せるのかなっていう・・・直したあとに、またあと1万2000キロも走んなきゃいけないんですよ。 大丈夫かなっていう決断をするのは難しかったですね」
●もうやめようって思うことはなかったですか? 諦めちゃおうって・・・。
「100回ぐらい思ったかも(笑)」
●そうですよね~。
「やめて、それこそ貨物船に船を乗せて、フランスに帰るっていうことも、本当に何回も考えたんです。でもヨットの成績は置いといて、レースの成績は置いといて、自分たちの目標は世界一周を達成することなので、その可能性を探り続けて、これならしっかり船を直してフランスまで帰れるなっていうのを、自分で確認して修理することを決めました」

●そういう思いが支えになったわけですね。
「あとね、応援してくださる方々がたくさん、本当心配してくださって、エールだけでもなくて、いろいろアドバイスをくれたりとか、ここに聞いたらいいんじゃないかとか・・・やっぱり日本の方々からの、そういったサポートもすごく嬉しかったですね」
(編集部注:鈴木さんたちはおよそ1ヶ月かけて、船を修理したわけですが、当然その間もレースは続いていて、結果、鈴木さんたちは第6レグから第8レグまでは「リタイア扱い」になったんです。
それでも完走し、総合3位になったのは、鈴木さんの説明によると、「Globe 40」は地球を一周するレースなので、設定したコースを通ってゴールのフランス・ロリアンに戻ってくれば、完走扱いになるとのこと。
また、8つのレグのうち、第1レグから第5レグまでの間に3回トップになり、その時点で総合2位だった、つまり貯金があったので、後半3つのレグをリタイアしても、ロリアンに戻ってきたので、総合3位と認められたそうです)
楽しいセーリング、そして喜ぶ顔
※再スタートを切って、ロリアンまでの航海は、気持ち的にはどうでしたか? レースというよりは、外洋の航海を楽しむ感じになったんじゃないですか?
「途中で、それこそちょっとルアーを作って釣りをしてみたりとか・・・もちろんレースじゃないですか。今回はレースではあるけれども、ほかのレース艇はいなくて、無事にフランスに帰ることが大切なので、風がない時はそうやって少し、自分でルアーを作って(海に)流してみたりとか・・・釣れなかったですけどね(笑)」
●でもちょっと(航海を)楽しむ余裕みたいなものもありましたよね?
「初めて! 余裕を持ったセーリングができたっていうのは、本当に初めてでしたね。いつもやっぱりライバル艇と1分1秒を競って、少しでも早く走んなきゃいけないっていうのがあったんですけど、今回は無理せずに、無理しすぎずにフランスに帰ることが第一目的だったので、少し気持ち的な余裕もあって楽しかったですね」
●船の上で出会った、忘れられないシーンはありますか?
「いちばん印象に残っているのは・・・やっぱり生き物が世界一周、地球を一周してく上でたくさんいるんですよ。たとえば、鳥。僕はそんなに鳥に興味はなかったんです、正直に言うと・・・。
でも地球を一周していく中で、鳥の種類、大きさ、色、性格が移動していくごとにどんどん変わっていくんですよ。きょうの鳥はちょっと色が変わったなとか、なんかきょうは種類が変わったなとか・・・それを地球の上を移動しながら、その変化を見てこられたのが、僕の中で、すごくいいもの見たなって思いましたね」
●ある意味忘れられないレースになりましたね。楽しめたレースというか・・・。
「はい、最後の大西洋、フランスまでは、本当に楽しいセーリングでした」

●最終的には当初の予定よりは1カ月遅れになりましたけれども、最終ゴールのフランス・ロリアンに無事に戻ってこられて、その時のお気持ちはどうでした?
「ただただ嬉しかったですよ。僕ら船の上で無線をいつもオンにしているんですね。船同士、走るための、話すための無線をオンにしているんですけれど、フランスに近づいてきて、久しぶりに無線からフランス語が聞こえてきた時に、あっ、帰ってきたんだなっていうのを感じましたね。
やっぱり世界一周していると、その国の言語なんですよね、無線が。なので、久しぶりにフランス語を聞いて、あっ、本当に帰ってきたな、いよいよだなって思いましたし、フィニッシュ・ラインが見えた時に、お迎えの人たちがボートで来てくれて、すごく嬉しかったですね」
●奥様も喜ばれたんじゃないですか?
「ねっ! 本当にみんな喜んでくれて、なんだろう・・・僕以上に自分たち以上に家族だったりとか、あとはレースを応援してくれたフランスの方、日本の方、現地に来てくれた日本の方々がすごく喜んでくれたので、みなさんの喜んでくれる顔を見られて嬉しかったですね」

メンタルをポジティブに
※レース中は、睡眠はパートナーと2時間交代でとって、天候が荒れたら食事もとれないですよね。そんな中、毎日どんなことを考えていたんですか?
「もちろん船のセーリングを、しっかり安全なセーリングをしなきゃいけないので、船を走らせることをまずは考えるんですけども、それプラス、やっぱり(レグの)期間が長いじゃないですか、1ヶ月間かそれ以上・・・。

船の中では、2〜3畳間くらいのスペースにふたりでずっといるので、メンタルをちゃんとキープしようと・・・。お互いの、ふたりの雰囲気もよくしないといけないし、自分自身の気持ちもよくしなきゃいけないので・・・いちばんメンタルをキープしやすいのが、あと何日でゴールできるかなっていうのを、僕はずっと頭の中で計算してましたね」
●カウントダウンということですね。
「たとえば1ヶ月、30日間かかるレグだとしても、3日終われば、これで10分の1、終わったんだなとか。たとえば5日目とかになると、もう6分の1終わったんだなとか、ポジティブにポジティブに考えながら、日々過ごしていましたね」
(編集部注:ちなみに天候が安定しているときは、読書をしたり、映画を見ることもあったそうです。でも、気持ちはどこかオンのままだったとか)
自然のサインを読み取る!?

※ヨットレースは、刻々と変化する気象を読んで、いかに風をつかむかが大事だと思うんですけど、これは経験を積むとわかるようになるんですか?
「最初は、インターネットが海の上でも使えるんですよ。飛行機の機内wi-fiみたいな形でインターネットにつながるので、そこで天気のデータをダウンロードして、1週間2週間先までの自分たちの航海計画は毎日立てるんですね。
ただやっぱり予報なので、海の上で天気がガラッと変わったりするんですね。その時はやっぱり勘かな、経験かな・・・雲を見たりとか、途中、たとえば湿気が多くなってきたなとか、匂いが少し違うなっていうのを・・・」
●匂いまで!?
「体で感じて、それで早めに、セイル(帆)を小さくしたり、大きくしたり、方向転換したり・・・予報が外れた場合は、自分の勘で(船を)走らせるっていう感じですね」
●そういったわずかな自然のサインをすべて感じ取るんですね。
「そこがすごく大切です。それをちゃんと感じないと、船が壊れちゃうかもしれないし、そうしたら自分の力でゴールできないかもしれないので、そこが大切なところですね」
もう1回、地球一周したい!
※今回初めて開催された外洋ヨットレース「Globe 40」に挑戦し、そして完走を果たした今、鈴木さんの中にどんな思いがありまますか?
「本当にありがたいことに、この「Globe40」を通じて、世界一周を体験することができたので、日本全国のヨットをやっている方、何かに挑戦したいなと思っている方に、この体験、経験をお話しさせていただきたいなと思っています。
まずはこの1年、2年かけて、日本全国をまわって、世界一周の体験をいろんな人にお伝えしようと思っています。あとはこの世界一周の体験がすごく楽しかったし、自分自身も挑戦することが好きなので、まだ今は明確には決まってないですけど、次の挑戦を決めて、それに向けて活動したいなとも思っています」
●漠然と、なんとなくはあるんですか、次の目標が?
「ねえ~何かな・・・はっきりとは言えないけど、やっぱりセーリングが好きですし、地球一周もすごく楽しかったので、もう1回、地球一周したいなと!」
●またお話を聞かせてくださいね、その時に!
「ぜひ!」
●では鈴木さんにとって、ヨットとは?
「難しい質問ですね(笑)。ヨットとは・・・まぁ僕そのものかな。自然の力で自分の力で、大陸と大陸の間にある海を横断できる、地球の上を移動できる、それを叶えさせてくれるのがヨットであるし、それに乗れるのが自分であるので、これからもヨットに乗り続けていきたいなと思います」

INFORMATION
セーリング・チーム「MILAI」や「Globe 40」の激闘の模様、そして近況についてはオフィシャルサイト、または「MILAI」のfacebookをご覧ください。
◎「MILAI」HP:https://milai-sailing.com
◎「MILAI」Facebook:https://www.facebook.com/milai.aroundtheworld/
2023/6/18 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、芸能界きってのアウトドアズマン「清水国明」さんです。
清水さんには毎年一回、この番組にご出演いただき、そのとき、どんなことに夢中になっているのかをお聞きする定点観測を続けさせていただいています。その定点観測、今年でなんと28回目! つまり28年以上前からこの番組にお付き合いいただいているんです。
今回は、結成50周年を迎えた伝説のフォーク・デュオ「あのねのね」のツアー情報ほか、茨城県常総市に整備したキャンプ場「くにあきの森」や「笑顔食堂」プロジェクトのお話などうかがいます。
☆写真協力:kuniaki.plus
全国ツアーの前にリハビリ・ライヴ!?
●毎年この時期にご出演いただいて行なっている定点観測、今回で28回目となります。本当に長いお付き合いありがとうございます!
「ありがとうございます。よろしくお願いします」

●まずはなんといってもこの話題からです。伝説のフォークデュオ「あのねのね」が今年で結成50周年なんですよね。おめでとうございます!
「ありがとうございます! めでたいのかどうか、まあ50年も続けばね・・・昔、原田(伸郎)が言っていたけれど、中途半端に古いと値打ちはないけども、このくらい古くなると、骨董品としての値打ちが出てくるとか言うてましたね(笑)。
自分で言うのもおかしいけど、レジェンドっていうようなことを各局で言われるようになってね。あ、俺レジェンドなんだとかって、思いますけれども、そのくらい(長く)やらさせていただいているということは、確かなことなのでありがたいです」
●その50周年を記念して全国ツアーを行なうんですよね?
「これはね、本番の50周年のコンサートがあるじゃないですか。それに向けてのリハビリ・ライヴということで・・・実は40周年をやりました。その頃の感を取り戻すために・・・この10年間やっていないようなものなんでね。
生きてはいたんですけど、もちろん解散もしていないんですけれども、活動もしていなかったものですから、あのねのねとしてのトークであるとか、歌の間とか音程とか、そういったことをリハビリしないと、みっともないことになるぞということで、ライヴをやろうやないかという思いで、リハーサル代わりにやっているわけです」

●全国ツアーの前にリハビリ・ライヴってことですね。
「そうですね。だから何箇所かやってきたんですけれども、もちろんぐしゃぐしゃなんですよ。演奏して歌を忘れるし、音を外すしで、まあ本番で頑張ろうやとか言いながら・・・それをお金を出して見にきた人にはえらい災難ですけどね。まあそんなふうに全国でやらさせてもらっています。
みなさんの評価は、すごく楽しかったとかっていうのと、それから元気になったとかも・・・それは確かにわかるんですよ。俺72歳だし、原田も71歳の爺さんふたりが、50年も前と同じような感じで、キャッキャ言いながらアホな歌を歌ったりしているわけだから・・・。同世代の人たちに見にきていただいたんですけれども、あ〜我々もまだできるなという、そういう励みにはなったかもわからないです」
あなたまかせのキャンプ場

※清水さんは先頃、茨城県常総市の「ふるさと大使」に就任されました。常総市のほうから、キャンプ場を作って欲しいという要請があり、それを受けて、「くにあきの森」というキャンプを整備、今月グランドオープンを迎えたそうです。どんなキャンプ場なんですか?
「あのね、水とトイレと電気、これはやっぱりいるなと思って・・・トイレも、僕はアウトドアズマンと言われていますが、ウォシュレットがないとだめなもんですからね(笑)。洗浄便器をくっつけたトイレはしっかりあるんです。あとは何にもなしのとりあえず森、雑木林ですね。
何があるか、いるかというと、クワガタとカブトムシ。これは、そこを開発しようと思って、ユンボをガーーーっと・・・草ボーボーで薮とか竹とか茂っていて、ガガガガッと3〜4メートル入った瞬間に、カブトムシの幼虫が5〜6匹ポロポロって出て、いや〜すげー!って、もう一気にそこが気に入りましてね。
それまでも隣の柏市で杉林を開発して(キャンプ場を)作っていたんですけど、その時はそういう昆虫はいなかった・・・ところが雑木林ってすごいね。入り口にそれだけいるってことは、奥のほうにはもうてんこ盛りにいるんじゃないかと思って勇んで行ったら、奥にはあんまりいなかった(笑)」

●あははは(笑)
「そういう虫がいっぱいいる場所で、クワガタ、カブトムシの森というのも施設として作ろうかなと思っています。で、自然が豊かなのと、それから自由が豊かっていうか、自由がいっぱいある、ほったらかしの・・・キャンプ場の前に“あなたまかせ”というフレーズをつけたんですよ。
いろいろ設備だったり、グランピングとか、いろいろどうじゃーってなっているけど、あれは方向性として違うなと思っているんですよ。
なんにもなしで、自ら然(しか)るって『自然』ってそういうことで、自分でやる、自分で決める、自分で楽しむっていうのが、キャンプであり自然だと思うから、ほったらかしです。
なんでも自由にしてください、自己責任ですよと。自他自由と言っているんですが、あなたも自由だけど、他人も自由だから、他人の自由を犯す自由はないよ、みたいな・・・それから自修自得って言っているんですが、自分で楽しめよと。
なんやここなんにもないから、つまんないっていう人は自分で楽しんでないです。ここ何でもできるなって自分で喜びを作りだせる人は、これ以上のところはないと思います。もうほったらかしですからね。そういう自由がある自然な森をキャンプ場というふうに捉えていただければいいんじゃないかな」
●あなたまかせのキャンプ場、面白いですね!
「このあいだね、ホームページを作っているやつからね、“チェックイン、チェックアウトの時間はどうしたらいいですか”って質問がきたから、“あなたまかせ”って(笑)、好きな時に出てって好きな時に入ってちょうだいって(笑)」
●いいですね〜(笑)

笑顔食堂、あした笑顔になあ〜れ
※清水さんはほかにも「笑顔食堂」というプロジェクトを進めていらっしゃいます。これはどんなプロジェクトなんですか?
「これはですね・・・ご存知のように子供食堂っていっぱいあるじゃないですか。日本に7300ぐらいあるんですって」
●全国いろんなところにありますよね。
「それをやっている人は庄野真代さんとか、うちの会社グループもふたつぐらいやってるんですけど、いいことやってんなと思いながらも、あんまりそれに関心を示さなかったんです。
私は毎日の食事を用意するっちゅうなことは、いちばん苦手なんです。ぽっと瞬間的にそういうことするのはできるんだけども・・・だから子供食堂はできないなと思っていたんですが、それっていわゆる社会が子供たちを育てるという形なんですね。自分の子供だけ育てればいいっていうわけじゃないなと思い始めたんですよ。
72歳ということは、そろそろエンドがちらほらと見えてくるわけですよ、終活というかね。もうこの先、俺も72だからせいぜい生きて、あと60年ぐらいですか(笑)。だからそろそろ亡くなった後、あ〜、あの人、ひどいことしていたけど、こういうこともやってたんだっちゅうなこともやらないかんからね。
それと、人さんのお子さんを育てるということは、今まで考えてなかった・・・自分の利益、自分の家族の幸せというものを中心に考えてきた・・・けど、今度うちのライヴでもやってくれる、ナオちゃんっていうハーモニカのミュージシャンがいるんですが、その人がね・・・“ナオちゃん、家族どうなってんの?”って、“今、里子(さとご)がいます”って言って里親になって、それも二組目なんですって! いや〜偉いねって・・・考えてみたら、俺そういうことしてこなかったなということで、無関心だった・・・。
無関心ってのは、愛という言葉の裏返しが無関心だそうでね。これは愛のない日々を過ごしてたなということで、だから『笑顔食堂』・・・ちょっと話が長くなりましたけど、『笑顔食堂』というのは、自分ができることをやろうと思って、キャンプ場をいっぱい作ってますから、そこに来てもらって自由に遊んでもらう・・・それはもうただで来てください、中学生までですね。ただで遊んでもらって、お父さんお母さんも来てくださいよと・・・で、『笑顔食堂』の食事作りを手伝ってくれたら、大人は入場料半額ですよっていうことで、なるべくみなさんが来やすいようにね。

つまり、子供の支援っていうか貧困というのは、経済的なものと時間的なものと、それから愛情の貧困って、いろいろあるらしいのね。そういう意味では、食べ物は我々もやりますけれども、子供食堂があるけれども、自然体験とか親子の触れ合う時間とか、自然の中でのびのび、というものを提供できる・・・そして子供たちが今苦しくても、あした笑顔になあ〜れって言ってるんですが、あした笑顔になれるような、そういう取り組みをやろうというふうに思いたったわけです」
(編集部注:「笑顔食堂」プロジェクトのキックオフ・イベントが10月5日に東京国際フォーラムのホールAで開催予定だそうです。清水さんは、みんなが楽しむためのフェスティバルにしたいと、いろいろ構想を練っているようですよ。もちろん「あのねのね」も出演するとのことです。楽しみですね)
遊びも仕事も、常に全力!
●河口湖にある自然体験施設「森と湖の楽園」、瀬戸内海の無人島リゾート「ありが島」、あとは3年ほど前に千葉県鴨川の杉林を開拓して作られた「かもがわ自然楽校」、そして今回の「くにあきの森」がありますが、ご自分で汗を流して切り開いて何かを作るっていうのは、アウトドアズマンである清水さんの得意とするところだと思うんですけど、改めてどうですか?
「あのね、この28年間で何回か言ったかもわかりませんが、ある人の評価で“清水さんの頭の中は、おもちゃ箱をひっくり返したようになってる”・・・それでよく言われるのは“どこまでが仕事で、どこまでが遊びか、そのメリハリがない”・・・ずっ〜と遊び、ずっ〜と仕事みたいな感じで、自分の人生を使い切って終われたら幸せやなと思ってるんですね」
●常に全力ですよね。全力で遊ぶ! 全力で仕事する!
「多分ね、中途半端に何かをやった時、中途半端な感動しか得られないからね。思いっきり、おら〜って言った時は、おりゃーという喜びがあります。それはもう何回か繰り返してきてね。
”楽(らく)”と”楽しい”は違うって言いますよね。楽(らく)しちゃうと、本物の感動は得られないんじゃないかなと思って、わざわざしんどいほうを選ぶ・・・僕はリスクテイカーとも言ってるんですが、リスクのあるほうに飛び込んでしまう・・・体質がMなんでしょうね。これね〜、そういう生き方を貫いていると、ややかっこいいですけど、そんなことやってますね」
生きる力が退化!?
※清水さんが、自然体験のできる施設やキャンプ場を作っているのは、やはり多くのかたに「生きる力」を身につけて欲しい、そんな思いがあるからなんでしょうか。
「今の生活プラス生きる力というよりも、生きる力がものすごくなくなってきたような気がするんですよ、大人も子供も。つまりスマホで全部解決してしまうから、地図を覚えないしね。
俺、東京のテレビ局とかラジオ局に行ってても、そこから帰る時、必ずナビ入れてしまうもんね。そんなもん、もう100回ぐらい通ってんやから、それなしでも帰れそうなのに、でもなぜかナビを入れてしまう・・・。
それと漢字が書けなくなってきたんですよね。それとか、なんか調べ物するにしても、自分の頭の中にある記憶を取り出そうとせずに、ついスマホで調べてしまう・・・スマホ依存症ということらしいね。
そのくらい、子供と大人も、やっぱり今の便利なものにどんどん飛びついて、そして生きる力っちゅうか、工夫する力、自分で考える、思い出すというようなところを手放してしまってる・・・人類ってどんどん成長してるように思うけど、実はどんどん退化してるんじゃないか・・・その退化しているのは何かというと、やっぱり何もないとこでも、生きていけるような生きる力というのがない。
それを補填してくれるというか、読み出してもう1回リスタートしてくれる、そのスイッチを入れてくれるのは、自然の中の、これもずっと言い続けてると思うんですが、そういう中で得られる『熱い、寒い、臭い、痛い』みたいなものを得ることによって、むくむくっと出てくるんじゃないかなと・・・最後のリハビリというか立ち直るには、その環境が本当に外せないなと思うわけですね」
●今年の後半は「あのねのね」の50周年全国ツアーに全力投球だと思うんですけれども、その先はまた新しいことにチャレンジするとか考えていらっしゃるんですか?
「はっきり言えるのは、60周年はないということ! ってことは最後だと・・・この50周年のライヴがですね。だから生で『あのねのね』というものを・・・噂で聞くか、ちらっとお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんが言ってたなみたいな『あのねのね』を、生で見られる最後のチャンスなんでね、ぜひ(ライヴに)来ていただいきたいなと思います」
INFORMATION
「あのねのね」結成50周年を記念したツアー情報リハビリ・ライヴを終えた「あのねのね」は6月24日・京都、11月5日・東京でコンサート。ほかにも7月23日・神戸、9月10日・福岡、10月15日・長野でライヴを行なうことになっています。ぜひ、生で「あのねのね」のライヴをお楽しみください。会場によっては、すでにソールドアウトになっているところもあるそうです。
詳しくは「あのねのね」の公式Facebookでご確認ください。
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089085037073
茨城県常総市にある「くにあきの森」については、以下のサイトをご覧ください。
◎くにあきの森:https://www.kuniakinomori.com
清水さんの近況はFacebookをご覧ください。
◎清水国明さんFacebook:https://www.facebook.com/kuniaki.shimizu2/?locale=ja_JP
2023/6/11 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、水生生物の研究者「中島淳(なかじま・じゅん)」さんです。
中島さんは1977年、静岡県生まれ、東京育ち。幼少の頃から、生き物全般が好きで、特に淡水に棲む魚と昆虫に興味を持っていたそうです。
その後、九州大学に進学し、大学院を経て、現在は、福岡県保健環境研究所の専門研究員でいらっしゃいます。専門は淡水魚と水生昆虫の、生態学と分類学。これまでに新種としてドジョウ類12種、そして水生昆虫4種に名前をつけたそうですよ。
研究の傍ら、生き物の観察会や講演会の講師としても活動。また、ネット上では「オイカワ丸」という名前でも活動されていて、淡水魚が好きな人には、お馴染みのかたかも知れません。
きょうはそんな中島さんが先頃出された本『自宅で湿地帯ビオトープ! 生物多様性を守る水辺づくり』をもとにいろいろお話をうかがっていきます。
☆写真協力:中島 淳

湿地帯と生物多様性
※まずは「ビオトープ」とはなにか、改めてご説明しておきましょう。
ビオトープはドイツ語なんですが、もともとはギリシャ語で「命のある場所」、つまり「生き物が生息している場所」のこと。森や川、海岸など、生き物が生息している場所はすべてビオトープになります。そういう意味では地球そのものも、巨大なビオトープと言えますね。
中島さん曰く、湿地帯ビオトープには4つの大事なキーワードがあるそうです。その4つとは、湿地帯、生物多様性、外来種、そしてエコトーン。
それではひとつずつ詳しくうかがっていきましょう。まずは湿地帯なんですが、水辺全般を湿地帯と呼んでもいいのでしょうか。
「そうですね。大きな意味では、海は除くんですけれども、だいたい水深6メートルより浅い沿岸域、だから潮の満ち引きの影響があるところ、そこから陸域にかけてですね。河川とか、ため池とか湖とか田んぼ、あと地下水、こういったものは湿地帯と定義されます」
●やっぱり、かなり重要な場所なんですよね?
「はい、そもそも人間は水、淡水を飲まないと生きられません。その淡水の主要な供給源がこの湿地帯になるわけです。また湿地帯で生きている生き物は、例えばアサリとかでもそうですけれども、食べ物として非常に重要ですね。本当に大事なビオトープ、生息場のひとつというのが湿地帯だと私は思っています」
●湿地帯ビオトープを作ると、それは生物多様性を守ることにつながっていくんですか?
「そうですね。森にも砂浜にもビオトープはあるんですね。それぞれ特有の生き物が暮らしているので、どこの環境も非常に貴重なんですけれども、特に日本では湿地帯、身近な水辺の環境がかなり破壊されています。
そういうところに暮らす生き物の多くが絶滅したり、絶滅危惧種になってしまっているということで、そういった湿地帯を想定したビオトープ、生物の生息場所を増やしていくというのは、生物多様性に大きく(貢献し)、特に日本で広くつながると考えています」
●生物多様性が失われてしまうと、私たちの生活に具体的にはどんな影響が出てきてしまうんでしょうか?
「いちばんわかりやすいのは、握り寿司ですね。お寿司とか好きかなと思いますけれども、種類がいろいろあるのが、お寿司の楽しみのひとつだと思うんです。これがまさに生物多様性の恵みそのものですね。生物多様性が失われると、寿司ネタが一品ずつ減っていくというようなことになります」

外来種とエコトーン
※大事なキーワードの続き、外来種とエコトーンについて。湿地帯ビオトープを作るときに、もっとも注意しなければいけないのは、外来種を育ててしまうことなんですか?
「育てることが問題ということではないですね。どちらかというと、育てた外来種が野外に出て行って、それがそこに、もともといた生き物とか生態系に悪影響を与える、これが問題だということですね。
外来種というのは、人が持ち込んだものという定義ですけれども、その定義で言えば、稲とかカボチャとか、野菜の多くは外来種ですね。それが問題だというわけではないということですね。それがコントロール不能になって野外に出て行って、生物多様性を破壊してしまうことがあるわけですね。そういうことにならないようにすることが重要だということです」
●エコトーンという言葉を、私は初めて知ったんですけれども、詳しく教えていただけますか。
「エコトーンは端的に言えば、異なるふたつの環境です。それが少しずつ変化しながら接する場所という意味で、水辺に関して言えば、陸と池・・・その陸と水の間、陸から徐々に水の中に入っていくような・・・一見、陸だと思って踏み込んだら、ズブズブと足が沈んでしまうような、そういった場所がエコトーンということになります」
●ちょうど狭間のようなものっていうことですね。エコトーンこそ湿地帯ビオトープの要と言えるんですか?
「そうですね。ビオトープという言葉は古くからある言葉ですけれども、あえてタイトルに“湿地帯”を付けたのも、そういった概念として、連続的に変化するような環境を含めて、ビオトープ化して楽しむことができないかなと思って付けたものです。
そういう意味で湿地帯というのは、エコトーンを含むような意味合いとして、湿地帯ビオドープという一連の言葉は、これは造語だと思いますけれども、それで今回、本の名前として付けたものになります」
●エコトーンで暮らしている生き物って、どんな生き物がいるんですか?
「身近でよく知られているもので言えば、ドジョウという魚ですね。あるいはサンショウウオとかトノサマガエルみたいな両生類ですね。こういったものはエコトーンを重要な生息場にしている、田んぼとかでよく見られるような生き物ですね。
こういったものは、完全に干上がらない川とかは好きじゃないんですけれども、陸もダメで、陸と水の間のときどき干上がったりはするけれども、割と常に水があるような環境、そういった場所じゃないとうまく繁殖できなかったり、生きられなかったりするような生き物になりますね」

湿地帯ビオトープの作り方
※中島さんの本によると、実際に自宅に湿地帯ビオトープを作るには、水と陸、そしてその境であるエコトーンを作ることがポイント。用意するのは、水を貯めておくための防水シート、プラスチックのコンテナ、そして小型の睡蓮鉢など。小型のコンテナや睡蓮鉢は手軽なのでマンションのベランダでも活用できるそうです。容器に入れる土は、ホームセンターなどで売っている赤玉土など。
湿地帯ビオトープの作り方について、詳しくは中島さんの本をご覧いただきたいのですが、小さなビオトープだったら、数時間で作れるそうですよ。

さあ、生き物たちが暮らせる場所が整ったところで、育てる水生生物や植物はどうすれば、いいのか、中島さんにお聞きしました。
「植物についても本の中でいくつか詳しいことを書きました。外来種の話を本の中でも解説しているんですけれども、ビオトープから外来種が出ていって、野外に行ってしまうという構造の場合は、やっぱり変な外来種の植物は入れないほうがいいわけですよね。
ただそうじゃなくて(外に)出にくいような構造であれば、ある程度自由に、売られているものを入れてもいいかなと思いますが、真に生物の保全につなげるためには、できれば住んでいる家の、まずはビオトープを置く場所の、周囲の川から取ってきたものを中心に入れるのが、いちばんいいかなと思います。
それから動物、魚なんかは、メダカであれば、買ってきて入れるということも、やむを得ない場合もあるかなと思いますが、そんな場合もメダカが逃げ出さないように、逃げ出すとそれが外来種になってしまいますので、そういった点には注意する必要があります。
あとは水生の昆虫類なんかは、実はゲンゴロウとかトンボとか、いろんな種類が日夜、我々の頭上を飛び回っているんですね。なので、いい水辺があれば、棲みつくようになります。 いろんな昆虫が突然現れたりするので、それを楽しむというのがいちばんいいかなと思います」

●本には何も入れない湿地帯ビオトープっていう説明もありましたけれども、何も入れなくても、いずれは生き物たちが暮らすビオトープになるっていうことなんですか?
「はい、実は水草というか水生植物の中でも、タネが空を飛んでいるような種類は結構多いんですね。タネがうまく発芽するようなエコトーン、これがあれば、実は何らかの植物は、意外と生えてくるものですね。場を作って粘り強く待つという楽しみ方もひとつあります」
●場所だけ作っておいて、何も入れなくても、生き物たちってやってくるものなんですね。
「そうですね。周辺の環境にもよりますけれども、粘れば何かしらくるのは、日本の場合は間違いないだろうと思います」
(編集部注:先ほど、近くの川から植物や生き物などを持ってくるというお話がありましたが、なんでも持ってきていいという話ではありません。中島さんによれば、魚などは各都道府県が定める規則に従わなくてはいけないとのこと。また、植物や土、石は河川法という法律によって、個人が自由に採取することは禁じられているそうです。
とはいえ、採取する量が極めて少ない、または常識の範囲内であれば、問題にはならないそうですが、個人での判断が難しいときは行政の担当部署に問い合わせてくださいとのことです。詳しくは中島さんの本に載っていますので、ご確認いただけければと思います)
人間は自然を再生できる

※中島さんのご自宅の庭には、10年ほど前に作った湿地帯ビオトープがあります。現在はメインのビオトープのほかに、埋めるタイプのコンテナ・ビオトープが5つ、睡蓮鉢ビオトープが2つ、それらを管理しているとのことです。
勝手に飛んできたトンボ類やアメンボなどの水生昆虫がどんどん増えているそうですよ。どんな湿地帯ビオトープなのか、これも本に載っているので、ぜひご覧ください。
お休みの日にご自宅の湿地帯ビオトープにいると、どんなことを感じますか?
「植えた植物もあるんですが、勝手に(池に)やってきた昆虫はやっぱり嬉しいですよね。場を作ってその生き物に選んでもらえたというところですね。この池がなければ、その虫はここで増えることはなかったわけですから、そういう意味では生物の保全にもつながる新しい場作りができたし、そういったのを呆然と眺めているのは楽しいですね」

●首都圏でおすすめのビオトープってありますか?
「生息場として、いい湿地帯はたくさんあるんですけども、本でも紹介しましたが、エコトーンに注目するのであれば、やはり東京の井の頭池ですね。あそこはかなり意識的にエコトーンを再生するということをしています。
エコトーンというものをこの本でちょっと読んで、どんなものかなと脳内にイメージを置いて、改めて井の頭池だけ見てみると、あ〜こういうことをしているのかというのがよくわかってきます。
実際あそこは生き物も多いので、私も何度も行きましたが、そういう知識があると解像度が上がると言いますか、あ~なるほどというので全く見え方が違ってきて、面白いんじゃないかなと思いますね。町の真ん中にありますので、そういう中でもこういった場を作ると、これだけ生き物が棲めるようになるんだということがよくわかって、東京都周辺では井の頭池はおすすめポイントですね」
●では最後に、この本『自宅で湿地帯ビオトープ! 生物多様性を守る水辺づくり』 を通して、いちばん伝えたいことを教えてください。
「伝えたいことはたくさんあるんですけれども、そうですね・・・場を作ることですね。人間は自然を再生することができるっていうことに気付いてほしいなというところがあります。
家にエコトーンを含む湿地帯を作ってみて、それを維持したり管理したり開発したりする、そういった経験を持った上で、今度は野外の池とか川とかを見て、その実態を見る、解像度というか見る目、それが上がっていく、そういった経験を楽しんでもらえるといいなと思います」
(編集部注:お話にあったおすすめの井の頭池は、都立井の頭恩賜公園の中にあります)
INFORMATION
自宅の庭やベランダに湿地帯ビオトープを作るためのノウハウが、写真やイラストとともにわかりやすく解説。また、湿地帯ビオトープの生き物図鑑ほか、入れてはいけない外来種も写真入りで掲載されています。大和書房から絶賛発売中です。
詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎大和書房HP:https://www.daiwashobo.co.jp/book/b618603.html
中島さんのオフィシャルサイトもぜひ見てくださいね。
◎中島淳さんHP:http://kuromushiya.com/koushiki/top.html
<全国砂浜ムーブメント2023> 以前番組でもご紹介しましたが、日本自然保護協会のキャンペーン「全国砂浜ムーブメント」が今年も始まりました。海や砂浜のことを楽しく学べる特製の「砂浜ノート」や専用のアプリを使って砂浜を守る3つのアクションにぜひご参加ください。砂浜にいる生き物調査や、ゴミ拾い活動を多くの人たちと共有します。
詳しくは「日本自然保護協会」のホームページをご覧ください。
◎日本自然保護協会HP:https://www.nacsj.or.jp
<オンライン講座「身の回りのマイクロプラスチックと、私たちにできること」> 現在、マイクロプラスチックがどのような問題を引き起こしているのか、環境ジャーナリストの「栗岡理子(くりおか・りこ)」さんが解説します。開催日時は6月29日(木)午後7時から8時10分まで。Zoomを使用、参加費は無料、定員は先着300名です。
詳しくは「日本野鳥の会」のホームページのお知らせをチェックしてください。
◎日本野鳥の会HP:https://www.wbsj.org
<#リユースでラブアース> 国際環境NGOグリーンピース・ジャパンのリユースを広めるSNS投稿キャンペーン。マイタンブラーやマイ容器の写真を、ハッシュタグ「#リユースでラブアース」をつけ、メッセージを添えて、インスタグラムに投稿してください。期間は6月30日まで。集まった画像はメッセージとともにカフェや企業に届けることになっています。
詳しくはグリーンピース・ジャパンのホームページをご覧ください。
◎グリーンピース・ジャパンHP:https://www.greenpeace.org/japan/