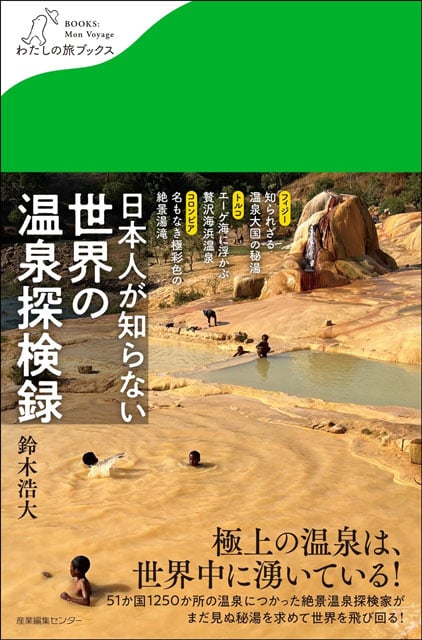2023/6/4 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、千葉大学准教授で古生物学者の「泉 賢太郎」さんです。
泉さんは1987年、東京都生まれ。子供の頃から、地球や生き物に関心があり、ざっくりいうと「昔」が好きで、歴史本や図鑑、博物館に置いている石などに興味を抱く少年だったそうです。
その後、東京大学大学院で地球惑星科学を専攻し、2015年に博士課程を修了。専門は、古生物の活動の痕跡である「生痕化石(せいこんかせき)」に記録された生き物の生態の研究など。
泉さんは、チバニアンの研究チームで活躍するなど、その活動が注目されている若き古生物学者です。
ちなみに古生物学とは、泉さんによると遥か昔、地球上に生息していた生き物の暮らしぶりなどを、化石や今生きている生き物の研究を通して推論する学問だそうです。
そんな泉さんが先頃、『化石のきほん』という本を出されました。きょうはその本をもとに、ティラノサウルスのものと考えられている超巨大なウンチ化石や、チバニアン含め、地質や地層と化石の密な関係についてお話をうかがいます。
☆資料協力:『化石のきほん』泉 賢太郎 著、 菊谷 詩子 イラスト(誠文堂新光社)

糞の化石を研究!?
※まずは、化石の基礎知識。
化石は大きく2種類に区分されます。ひとつは、恐竜の骨や歯、アンモナイトなどの古生物そのものの痕跡で、「体の化石」と書いて「体化石(たいかせき)」。
もうひとつは、足跡や巣穴、糞など、古生物の活動の痕跡である「生痕化石」。
1万年より古いものを化石と呼ぶことが多いそうです。
泉さんは、化石の中でも「生痕化石」に着目されていて、中でも糞の化石、いわゆるウンチ化石を研究されています。
もっとも化石にならないと思われる糞が、化石として残っているというお話に驚いたんですけど、この本『化石のきほん』に、ティラノサウルス類のウンチ化石と推定されるものが発見されたと書いてありました。どこで、どれくらいの大きさの化石が見つかったんですか?
「これは、数は少ないんですけど、カナダで見つかっています。大きさは、いちばん大きいやつで、長さが60センチぐらいで、幅というか太さが20センチですね」
●巨大ですよね〜。
「巨大ですよね。両手で持って、たぶん崇めるみたいな、そんなものだと思うんです。実は私も対面したことがなくて、そういう意味でも貴重な化石標本なんですけど・・・」
●でも、それがティラノサウルスのものだというのは、どうやってわかるんですか?
「そこがすごく個人的には興味持っているところです。論文もしっかり端から端まで読んでみると、だいたい3本の推論の柱みたいなのがありますね。
イメージ的には事件現場に残されたあらゆる痕跡を頼りに、その容疑者が自分がやりましたって言わない限りは、厳密には証明できないので、同じようなジレンマを持っているんですけど、なんとか可能性の高い仮説を出したいというので、ひとつめの証拠がまずそのサイズですよ、でかい!
でかいだけだと、でかい動物だろうということにしか絞れないんですけど、次は中身ですね。でっかいウンチの一部を切り出して、プレパラートみたいなのを作って顕微鏡で見てみると、中に骨の断片とか(見つかると)肉食性のでかい動物だろうというところが第2段階ですね。
第3段階が状況証拠・・・アリバイっていうんですかね。化石は、ウンチ化石でも骨の化石でも、必ず地層の中にもともとは埋まっているんですね。なので、登場人物を洗い出すっていうイメージで、その当時の同じ地層にどういう化石が見つかるか、いろいろ登場人物を洗い出すんですね。
その中でこのふたつの特徴、大きいかつ肉食動物の化石の中で、いちばんでかいのはティラノサウルスだよねと! そんな感じで推論されています」
(編集部注:なぜ糞が化石になるのか、不思議ですよね。糞は、一般的には微生物などで分解されてしまうんですが、例えば、水中とか酸素が少ないところに落ちて、その後、なんらかの作用が働き、鉱物化してしまったのではないかということなんです。でも、実際のところはわかっていないそうですよ)

化石と地層の密な関係!?
●泉さんの新しい本『化石のきほん』の最初のところに、地質年代表っていうのが掲載されていました。やはり化石と、地質や地層は非常に密な関係にあるということなんですね。
「そうなんです。おっしゃる通りです。この『化石のきほん』でひとつ重点的に意識したのが、”化石のきほん”というタイトルなんですね。
その化石の文脈っていうんですかね・・・地層の中に埋まっているので、その化石からいろいろ読み解いていくためには、文脈ごとにやっぱり知る必要があるんです。化石と地層の関わりはすごく意識して書きました」
●化石の中にはいろんな情報が込められているんですね?
「そうなんです。ただ地層から取り出して、綺麗な化石だけの状態になってしまうと、見た目は美しくなるかもしれないんですけど、文脈が失われてしまうので、その途端に情報量が激減してしまうんですね。
古生物の研究者は私も含めて、いろんな研究対象とかいろんな目的があるので、全員というわけじゃないんですけど、地層ごと化石の資料を取るということが多いんですね。
そうすると、化石とまわりについている地層を同時に観察することができるんです。文字通り、本当に切っても切り離せないというか(情報が)埋まっているので、そこを化石だけ取り出すことができる場合もあるんですけれども、大半はこの本の表紙のようにまわりの地層ごと化石を取り出します。
たとえば、アンモナイト化石が地層の岩石に埋まった状態のイラストが、表紙に載っているんですけど、これもこだわりのひとつです。ここに生物学を代表する有名化石のアンモナイトが、アンモナイトの化石単体じゃなくて、地層に泥岩に埋まっているこの状態を、やっぱり出したかったんですよね、表紙に」
●化石だけじゃなくて、地層ごと取る化石っていうことですね。
「まさにおっしゃる通りです。そこに地層をなくしちゃうと、化石から見ための情報は増えるかもしれないんですけど、どういう時代に生きていたのか、どういう環境にいたのかと、そういった背景にある文脈の情報が一気に失われてしまうんですね。
目的次第なんですけれども、完全に化石のことを知るために、化石だけを見るっていうよりも、一般的には地層も含めて見たほうが、より広範囲にわかるかなと思います」

「チバニアン」誕生に貢献
※3年ほど前に、地質年代にラテン語で「千葉の時代」を意味する「チバニアン」が誕生し、一大ニュースになりました。泉さんも協力されたということですが、どんなことをされたんですか?
「専門のひとつである生痕化石ですね。地層に生痕化石が何種類ぐらいいるんだろう、どんな種類がいるのかなというのを観察することで、その当時の生態系の様子を推定したりですとか・・・。生痕化石も、地層がどんな環境でできた地層なんだろうっていうのを推定するのに一役買っているんですね。
見た目は本当に何の変哲もない川沿いの崖って感じで、調査に行ってみたら、その辺の崖って感じでしたね(笑)。その辺の崖と言っても、なかなか人によってイメージが違うかもしれないんですけどね。そんなところで、文字通り這いつくばるというか、壁にぺたっと(はりついて)生痕化石を探したんです。
こういう種類とこういう種類がいるってことは、たとえば水深帯だったら、これぐらいでとか、こういう環境でできた地層じゃないかなと・・・そういったデータを出して、それが研究プロジェクトの中のひとつの立ち位置っていうんですかね。
地層の成り立ちを、やっぱりその由来を知らないと、ここの地層がいいと言っても、どういう理由でいいのか、どんなことがわかっているのか、なにがわかっていないのかとか・・・。ほかと比較するとこの辺がやっぱり優れていると、一個一個証拠を出すということで、生痕化石の観察というところでは、うまくひとつデータを出せたかなと思っています」
●あの一大ニュースの裏には化石が活躍していたわけですね!
「ほかにも目に見えないぐらいちっちゃくて、顕微鏡じゃないと見えない、微笑の微に化石と書いて“微化石”って言って・・・」
●微化石!?
「それはそれで顕微鏡から広がる形も多様で、いろいろ見た目も綺麗なんですけれども、そういったちっちゃい、人知れず崖の中の泥とか砂粒の粒子と同じぐらいの大きさの、そういうのを一個一個取り出して調べて、どれぐらいの年代だったんだろうとか、あとどういう環境でできたりするのかなとか、そういうのを調べたんですね。ということで、千葉の名前が世界中に、地質学の中でもひとつ認知されたと・・・。
たとえば有名な地質時代、ジュラ期っていうのがあると思うんですけど、『ジュラシックパーク』『ジュラシックワールド』のジュラシックが、”ジュラ期の”っていう意味なんです。あれも地名なんですよね。ジュラ山脈っていうヨーロッパの地名から来ているんですね。ジュラ期とかジュラシックが有名になりすぎて、地名に由来しているんだっていうこと自体が逆に(知られていないと・・・)。
けっこう地名が由来となっている場合が多くて、ほかにもペンシルバニア期とか 、“ペンシルバニアン”って言いますし、意外と地名由来っていうところがあったりします」
(編集部注:泉さんによると、古生物学の研究が盛んなのは、太古の地質が残っているヨーロッパで、国でいうと、ドイツやイギリス、フランスなどだそうです。一方、恐竜の化石が多く見つかっているのは、アメリカやカナダ、中国あたりだそうですよ)

化石は意外と日常に!?
※化石は意外と私たちの身近にあったりしますよね?
「“近すぎて見えない化石”と呼んでいるんですけど、たとえば珪藻土(けいそうど)、吸水性がいいので、よくバスマットとかに使われていますよね。あれも珪藻って植物プランクトン、目に見えないちっちゃいプランクトンがガラス質の殻を持っているんです。
そのプランクトンの本体の、アメーバ状の部分は化石に残らないんですけど、そのまわりを覆っている殻が化石になって、たくさん集まっていると・・・化石の殻にいっぱい穴が開いているんですよね。吸水性がいいってのはスカスカなんですよね、珪藻土のマット自体。なので、水が効率的に染み込んでいくということなんです。
本当に感動しますよね。足を乗っけてすぐ乾いている、みたいな! 緻密な岩石で、中にスカスカの空間がほとんどないやつだと、水がベチャってなったまんまっていうのがあると思うんですけど、珪藻はガラス質で穴がたくさんあるスカスカな化石がいっぱい詰まって、そのスカスカの部分がいっぱいあると水がすぐ浸透していくと、そういうことが起こります。
あとはビルの石材とかですかね。デパートの白っぽい壁や床に大理石が使われたりとか。そういうところにアンモナイトの化石があったりすることもありますね。
個人的には、お寺の石碑っていうんですかね。黒っぽい文字が刻まれたりしているんですけど、そこにむしろ生痕化石を見ちゃうと。文字は読めないけど、なんて書いてあるかわかんないけど、生痕化石はあるな! みたいな、そういう体験もします」
●素人の私たちが、なにか見つけるコツがあったりしますか?
「あると思います。一応こういうやつがいるかも知れないよみたいな、いくつかの鑑定ポイントみたいなのはありますね。ただ日常生活だとやらないぐらい(石碑に)近づかないと・・・。触れられないところでも見ることはできると思うので・・・生痕化石のひとつのいいところって、見て楽しめるっていうんですかね。採取禁止みたいなところでも、あ〜こういう生痕化石があったと・・・そこから僕も話が盛り上がっていきますよね」
(編集部注:お寺の石碑などに生痕化石が見つかることもあるということでしたが、見つけるコツはまわりと違う模様や構造を探すことだそうですよ。じっくり根気よく見るしかないですね。ちなみに泉さん自身は、化石探しはうまくないとおっしゃっていました)

ワクワクする気持ちを大事に
※最後に、古生物学を勉強したいと思っている子供たちや、学生さんに向けて伝えたいことがあれば、ぜひお願いします。
「これはですね、いちばんここが本でもこだわったところで、ページ数としてはあまり割いていないんですけど、ぜひ興味を持ち続けて、それで目の前の勉強に一生懸命取り組んでくれればいいかなと思っています。
というのも私自身も・・・ほとんど過去の自分に向けて言っているような感じになっていますけど、いわゆる同じぐらいの世代で、めちゃめちゃ詳しくて経験もあって、化石のこともよく知っていて発掘もしていてっていう人がいると、どうしても、比べたくなくても比べちゃって、こんな自分でもやっていけるのかなって思うかもしれない。
研究はまた別の枠組みだなとすごく感じています。そこは過去の経験の差が生きることもあるかもしれないですけど、思っているほど関係ないのかなと・・・ちゃんと目の前の勉強を一生懸命するとか、目の前のことに取り組む。
あと何よりも、古生物学の研究をやってみたいな、そういう研究者になってみたいなと思っているのであれば、その気持ちを持ち続けて欲しい。研究をやり始める前にやっぱり自分には無理だっていう子がすごく、もしかしたらいっぱいいるのかもしれない。それってすごくもったいないなと思うんですよね。
経験がなくても好きだ、興味があるっていう気持ち自体が、ひとつ素晴らしいことかなと思います。化石発掘とかよく知らないからダメなんだじゃなくて、なんかよくわかんないけど、ワクワクするっていう気持ちがあったら、それは大事にしてほしいなって思いますね。
ただそれだけでやっていけるわけでもないので、やっぱりちゃんとした学校の勉強とか、そこは本当に礎かなと思うのでしっかりと、まあ世代にもよるんですけど、勉強を頑張るといいかなと思います」
INFORMATION
『化石のきほん~最古の生命はいつ生まれた? 古生物はなぜ絶滅した? 進化を読み解く化石の話』
チャプター1の「ようこそ、化石の世界」からチャプター5の「めざせ、古生物学者」まで5つの章に分かれていて、全部で60項目ありますが、見開き2ページで完結しているので興味のあるところから読めますよ。イラストも豊富で楽しめます。化石の入門書的な一冊、ぜひチェックしてくださいね。
誠文堂新光社から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎誠文堂新光社HP:https://www.seibundo-shinkosha.net/book/science/78757/
泉さんのオフィシャルサイトもぜひ見てください。
◎泉 賢太郎さんHP:https://www.cn.chiba-u.jp/researcher/izumi_kentaro/
2023/5/28 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、漫画家でイラストレーターの「荻野千佳(おぎの・ちか)」さんです。
荻野さんは富山県出身、現在は東京の郊外にお住まいです。2016年から家庭菜園を始め、すっかりハマってしまい、ついには、日本家庭園芸普及協会認定のグリーンアドバイザーの資格を取得されています。
そして先頃、『野菜づくり、はじめます!〜マンガと図解でわかる! 一番やさしい家庭菜園の本』を出されました。
きょうはそんな荻野さんに、超初心者に向けて、おもにベランダ菜園で必要な道具、失敗しないコツ、そして、すぐ収穫できるおすすめの野菜のお話などうかがいます。
☆写真&イラストレーション:荻野千佳

短期間で収穫できる野菜がおすすめ!
●荻野さんが先頃出された本を拝見いたしました。
「ありがとうございます!」
●可愛いイラストでわかりやすく、野菜の育て方が描かれていて、これなら私も始められるかもと思いました。読んでいて、すごくワクワクしました。
「ありがとうございます! 嬉しいです」

●私は家庭菜園には興味はあるんですけど、実際に育てたことがあるのはミニトマトとか、あとは豆苗で再生栽培するぐらいで、本当に全くの初心者なんです。やはり野菜作りと聞くと作業が大変で、なんか難しいイメージがあるように思うんですけど、実際はいかがでしょうか?
「なんか大変そうっていうお気持ち、すごくわかります。外で一生懸命やるのかなって思われるかと思うんですけど、基本、誰でも簡単にできる、自然と遊べるエンターテイメントだと私は思っているんですね。
私の場合ですと2016年から自宅の狭い庭で、夏野菜を育て始めたのがいちばん最初なんですけれども、素人ながら今年で8年目になるんですね。今は自宅の庭でプランター栽培をやっていまして、あとは農業体験農園っていう貸し農園のグループに参加して、そこで家庭菜園をやっています。
経験上なんですけど、育てるのが難しい、失敗したって、なってしまう理由として、収穫までの時間が長くかかる野菜を選んでしまっているんじゃないかなと思うんですね。収穫まで時間がかかると、いろんな虫に食べられちゃったりとか、急に台風が来たりとかして・・・。
例えばスイカは、タネから始めて収穫までに4ヶ月かかってしまうんです。その間に収穫直前に大雨が降って(スイカが)割れちゃったとか、そういうことがあるかもしれないなと・・・。なので、最初のうちは収穫までの時間が短い野菜を選ぶと、作業も簡単で心配いらずで、収穫までを楽しむことができるかなと思います」

道具はジョウロ、ハサミ、スコップ
※私はマンション住まいなんですけど、まず何から始めたらいいですか?
「ちなみに何の野菜を育てたいとかって、ご希望はあります? 例えば、できれば気軽に始めてみたいなっていう感じもあるかと思うんですけど・・・」
●それが最優先です!(笑)
「そうですよね! 先ほど小尾さんが、豆苗の再生栽培をなさったことがあるっておっしゃっていたんですけど、実はタネからも(栽培は)できるんです。
たぶん再生栽培ってことは、買ってきたものをチョキンと切って、料理で使って、もう1回伸ばしたっていう形だと思うんですけど、豆苗はタネから発芽させて、いちばん最初の、売っている状態まで育てられるんです。
それが私の中でいちばん簡単な家庭菜園かなと思っております。これだと100円ショップに水切りかごっていう、ちっちゃな二重に重なった、お皿なんかを入れて乾燥させるような、上部が網で下がかごになっているのがあるんですけど、それがあれば(豆苗の栽培は)できますね」

●道具は、ほかに何か必要なものはありますか?
「サラダに使いやすいような葉物、ベビーリーフなんかをもし気軽にやりたいなっていう場合ですと、3つの道具だけで始められるんですね。それはジョウロ、ハサミ、スコップ、この3つだけが、まずは道具としてはあれば十分です」
●土はどんなタイプのものを用意したらいいのでしょうか?
「土は、ホームセンターなんかでいっぱい並んでいると思うんです」
●いっぱいありますよねー。
「私も最初はどれがいいのか、わからなかったですね。腐葉土とか赤玉土とか鹿沼土とか、もっと細分作化された、なになに用の土とかって売っていると思うんですけども、プランターに使う土であれば、袋に培養土と書いてあるものがあれば、それには土の中に最初から肥料が含まれているのでベストだと思います。袋に野菜用の培養土と書いてあるものであれば、全然問題ないですね。
また、培養土の重さに配慮した、軽い培養土もあるんですね。これは運ぶのは楽ちんですごく便利なんです。私も最初はそれをよく使っていたんですが、経験上、便利は便利なんですけれども、背が高くなる野菜、例えばミニトマトなんかを植える時に、プランターに軽い培養土を入れてしまうと、(プランターの)移動は楽なんですけれども、土台が不安定になってしまって、風で倒れちゃうっていうようなこともあったので、軽い土をお使いになる時はご自分の環境によって、プランターが倒れないように、ちょっと縛るなり、何か工夫をなさったらいいかなと思います」

おすすめはニラ!
※荻野さんおすすめの野菜はありますか?
「めちゃめちゃおすすめは、ニラなんです(笑)」
●ニラ! へぇ〜!
「これも繰り返し収穫できるんですね。収穫のやり方として、発芽して成長して収穫する時に、地ぎわから3センチぐらい残して、ちょきんと切って収穫します。そして「お礼肥(おれいごえ)」って言うんですけど、ある程度肥料を足したあとに、新しい芽が出てくるんです。それがまたもとの高さぐらいになって、また収穫するっていう、そういうのを3年ぐらいは繰り返せるんですよ。
冬場はさすがにちょっと緑はないんですけれども、私は庭のプランターでいつもニラを育てているんですね。手軽にちょっと庭に出てチョキンと切ってスープに使うっていう感じです。切ったあとにニラ特有の匂いがして、なんか気分が良くなるというか、やってるわ〜みたいな感じで楽しいですね」
(編集部注:いつ植えるのがいいのか、初心者にはわからないことのひとつだと思いますが、野菜全般について言えるのは、春か秋に植えることが多いそうですよ)

水やりのコツを伝授
※水やりも初心者には難しいと、よく聞きますよね。基本的に地植えは、土が乾いていなければ、水やりの必要はなし。一方、プランターは水やりが大事になってくるそうです。何かコツのようなものはありますか?
「ポイントとしてジョウロで水やりをする場合は、ジョウロの先についている穴があると思うんですけれども、あれは取り外しできるんです。あの部分を『ハスクチ』って言うんですね。あれを下のほうに水が出るように180度逆にして付けて、葉の上からジャバジャバではなくて、植わっている土の辺りにかけるようなイメージで、水やりなさるといいかなと思います」
●なるほど。葉っぱ自体にはかけちゃいけないっていうことですか?
「そうですね。葉っぱにかけちゃうと泥はねとか、土の中にいる雑菌が野菜の葉っぱに付着しちゃって、病気の原因になるっていうことがありますので、上からじゃなく株もとにたっぷりやるのがコツとなりますね」
●わかりました。水やりは朝とか夕方とか決めておいたほうがいいんですか?
「タイミングと季節にもよるんですけれども、例えば春先にタネまきをして、その時、水やりをするとなると、まだ気温が低いので、午前中のちょっとポカポカした時に、水道水をそのままじゃっと出しちゃうと、水の温度も低いので、できればちょっと(水を)汲み置きして常温になっている水をあげるといいですね。
野菜のタネって発芽温度っていうのがあるんです。だいたい25度前後なんですが、そこに冷たい水をかけちゃうと発芽率に関わってしまうので、できれば常温のお水をあげたほうがいいかなと思いますね。
で、逆に6月以降の真夏のようなカンカン照りの時は、朝か夕方が最適ですね。
朝と夕方、1日2回の水やりは、仕事が忙しくてできないっていう方で、1日1回ならなんとかっていう方には、夕方をおすすめします。
というのも夕方ですとそのまま夜になりますので、水持ちしている時間が長いわけなんですね。朝(水を)やっちゃうとそのまま、がっと温度が上がって、すぐなくなっちゃうので、夜の間ですと、ゆっくりゆっくりなくなっていくようなイメージなので、夜がおすすめです。
最後にこれ重要なんですけど、真夏のプランターの水やりは、真昼には絶対していただきたくないことなんですよ。真夏のお昼にプランターに(水を)やりますと、あっという間にプランターの中でお湯になってしまって、野菜が傷んでしまうんですね。なので、絶対に夜か夕方あたりにしていただけたらいいかなと思います」
(編集部注:真夏にプランターへの水やりは要注意というお話でしたが、直射日光が当たるようなベランダは、熱を和らげるためにウッドパネルや人工芝、よしずなどを設置して環境を整えてあげてくださいともおっしゃっていましたよ。

また、肥料についてなんですが、最初に肥料を与える「元肥(もとごえ)」と、あとで追加する「追肥(ついひ)」というのがあるそうです。ちなみに、培養土には最初から有機物が入っているので、元肥の必要はないとのことでした)
自然からの贈り物
※野菜作りを始めて、8年ほどということなんですけど、荻野さんは、野菜と向き合っている時に、どんなことを感じますか?
「やはり自然からの贈り物としての野菜は、ありがたいなっていうことにつきますね。やっぱり人間ですから、食べないと生きていけないので、感謝しながら収穫しているっていうところですね。
あと野菜は成長がすごく早いので、成長している姿に気づいた時・・・数日前は背が低かったのに、あれっ! こんなに伸びているってなった時に、ちょっと恥ずかしいんですけれども、”うわっ! 君は頑張っているね、ありがとう!“みたいなことを、本当に声に出して話しかけてしまうことも、ほかの方がいらっしゃらない時になんですけれども(笑)ありますね」
●もう我が子のような感じですよね〜。
「確かにそんな感じですね〜」
●これから収穫を迎える野菜っていうと、どんな野菜になるんですか?
「まさに今楽しくてしょうがない、収穫期を迎えたなって感じなんですけど、やっぱり夏野菜ですね。代表的なのはトマト、ナス、キュウリといったもので、みなさんも(家庭菜園を)やっていらっしゃる方はもうワクワクが止まらないと思うんですけれども・・・。
あとは春にタネをまいて収穫が終わったような、春菊のような葉物はもう終わっちゃった頃なので、少し空いている土地があれば、9月までに収穫まで終われるような、新しい野菜を育ててもいいかなと思います」

家庭菜園は体力がつく!?
※ご自分で野菜を作るようになって、食に対する意識が変わったりしましたか?
「例えばスーパーマーケットで売られている野菜を見て、自分も育てているので、この野菜はアタリかハズレかっていうのが判断できるようになりましたね。
例えば大根なんですけど、食べる白いところをよく見ると、ちっちゃいくぼみの穴みたいなものが、てんてんてんと並んでいると思うんですよ。あれが両サイドに2列並んでいるはずなんですね。
その並び方がまっすぐであればあるほど、中の組織も揃っているって目安です。成長の段階で問題なくすくすく育った証なので、そのてんてんのくぼみがまっすぐ並んでいるものを選んでいただけたらと思います」
●覚えておきます(笑)。野菜作りの生活を続けていて、ご自身の中で心身の変化とかもありましたか?
「やっぱり自分で育てて収穫する分、野菜をめちゃくちゃ食べるようになりましたね。旬の野菜をその時期にたくさん収穫することができるので、育て方の勉強に加えて調理法も畑の仲間に聞いたりとかして詳しくなりましたね。
あと圧倒的に体力がつきましたね。私の場合、畑にいると土を踏んで作業するので、自然に体幹が鍛えられるといいますか・・・。あと自動車を持っていなくて自転車で行きますので、収穫期には行ったり来たりしながら運ぶっていう、まあ楽しい作業の中で自然に体力がつくようなこともあるかなと思います」

●そうなんですね。これから家庭菜園で野菜作り始めてみようと思っている方に、ぜひアドバイスをお願いします。
「自分で育てた野菜を収穫して食べる楽しみはもちろんなんですけれども、野菜を見ていて癒されるとか、仲間や家族で楽しむとか、育てるだけじゃない、いろんな楽しみ方があると思うんですね。遠出しなくてもできる、日常に寄り添ったアクティヴィティなんじゃないかと思っています。
収穫したてのトウモロコシとか枝豆は、お子さんも好きだと思うんです。甘みが強くて非常に美味しいので、遊びながら食べるっていうような身近な楽しみ方のひとつかなと思うので、簡単ですのでぜひ始めてみていただけたらいいかなと思います」
INFORMATION
『野菜づくり、はじめます!〜マンガと図解でわかる! 一番やさしい家庭菜園の本』
野菜作りを始める前の荻野さんに、8年後の荻野さんが野菜作りのアドバイスをするというストーリー仕立てになっています。全編マンガなので、絵を見てすぐ理解できます。また、図解による野菜の育て方や、野菜のミニ知識も掲載。超初心者に向けた野菜づくりの入門書です。ぜひお買い求めください。
SBクリエイティブから絶賛発売中。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎SBクリエイティブ:https://www.sbcr.jp/product/4815618438/
荻野さんのオフィシャルサイトもぜひ見てくださいね。体験農園や、日々の野菜作りのレポートも載っていますよ。
◎荻野千佳さんのサイト:https://ogichika.com
2023/5/21 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、愛知県犬山市にある「日本モンキーセンター」の学芸員「綿貫宏史朗(わたぬき・こうしろう)」さんです。
「日本モンキーセンター」は、公益財団法人が運営する霊長類専門の動物園で、先月末の時点で56種、およそ750頭のサルのなかまを飼育・展示していて、サルのなかまに特化した動物園としては世界最多を誇ります。
そんな「日本モンキーセンター」の飼育員さんたちがイラストや解説文を手掛けた本『飼育員がつくったサルの図鑑〜かならず会いたくなっちゃう56のなかまたち』を出されたということで、きょうは解説文を担当された綿貫さんに、オスとメスでデュエットするテナガザルや、女性飼育員に恋するゴリラなど、飼育員さんだからこそ知っている、サルたちの興味深いお話をうかがいます。
☆写真&イラスト協力:公益財団法人「日本モンキーセンター」

サルたちを通して、地球と人を研究
※愛知県犬山市には、日本の霊長類学の研究をリードしてきた、現在は名称が変わっていますが、京都大学の霊長類研究所があります。そのお隣にある「日本モンキーセンター」は、実は霊長類研究所よりも早く、60数年前に開設され、飼育員のほかに調査・研究する学芸員がいる、日本の動物園としては珍しい施設です。
そんな学芸員のひとり、綿貫さんは、1986年生まれ。ご本人曰く、熊本の山奥で育ち、子供の頃から動物好き。そして漫画「動物のお医者さん」に影響を受け、東京農工大学に進学、その後、獣医師の資格を取得。
現在は「日本モンキーセンター」のほか、京都大学の研究員として「大型類人猿情報ネットワーク」プロジェクトに携わり、日本国内で飼育されているゴリラやチンパンジーなど、貴重な研究対象の情報を集める活動もされています。
ちなみに綿貫さんは、日本の動物園水族館協会に加盟するおよそ90の動物園を数年前に制覇、海外の動物園にも出かけるほどの動物園マニアで、ご自分で「動物園学研究家」を名乗っていらっしゃいます。

●世界的にも珍しい霊長類専門の動物園「日本モンキーセンター」が目指していることって、どんなことですか?
「やはりサルのなかま、霊長類は、私たち自身もその一員であるということで、私たちにいちばん近い存在の動物たちなわけですよね。
私たちにいちばん近い、いわゆる隣人というか、そういう動物たちを通して、地球環境ですとか、人がどういうふうに誕生して、どういうふうにこの地球上で生きているのか、そんなことをみなさんに知っていただくために研究をしていく、そういうような場所としてやっていきたいと、そんなことを目指しています」
愛のデュエットをするテナガザル
※先頃発売された『飼育員がつくったサルの図鑑〜かならず会いたくなっちゃう56のなかまたち』は、「日本モンキーセンター」の現役の飼育員さんがイラストを描き、綿貫さんが飼育員さんたちから集めた、とっておきのネタやサルの雑学を原稿化した本なんです。

その中からいくつか気になったことをお聞きしていきたいと思います。シロテテナガザルは歌を歌うと書いてありますが、ほんとなんですか?
「はい、シロテテナガザルはテナガザルのなかま、私たち人に比較的近い類人猿と呼ばれる手の長いサルなんですけど、その手の甲の部分がどんな個体も真っ白なんですね。それでシロテテナガザル、白い手のテナガザルってそういう意味なんですけれど、歌を歌うんです。
テナガザルのなかまはシロテテナガザルに限らず、歌を歌うんですね。オスとメスがペアになってデュエットで」
●へぇ〜〜!
「実はサルのなかまでもテナガザルはちょっと珍しくて、あまり大きな群れとか作らないんですね。オスとメスとその子供たちっていう、人間でいうところの核家族みたいな、そういう単位で暮らしているサルのなかまなんです。

で、いわゆる夫婦、オスとメスのペアの絆を確認するためだとか、あるいは単位が非常に小さいので、ご近所関係はあまりよくないんですね。隣の家族にここは私たちがいるところだから、あまりこっち来ないでねって、アピールしているっていうふうにも言われているんです。
そういうことで非常に大きな声で歌を歌って、オスとメスがそれぞれ違うパートを歌って、重ね合わせてデュエットするという、そういう特徴があるんですよね」
●大声ということは、かなり迫力がありそうですよね。
「はい、テナガザルの中でもいちばん大きなのがフクロテナガザルといって、全身は真っ黒なんですけれど、喉の下に自分の顔と同じぐらいの大きさの喉袋があって、そこを膨らませて声を共鳴させて大きい音を出す。それがサルのなかまでいちばん大きな声を出すと言われているんですね。だいたい4キロぐらい遠くまで聴こえると言われています。
なので、日本モンキーセンターでもフクロテナガザルが、ちょうどこの収録の直前まで鳴いていたので、収録に影響が出ないかなって心配していたんです(笑)。犬山駅がちょっと離れたところにあるんですけど、その駅前でもたまに風向きによって、声が聴こえたりすることもある、すごく大きな声ですね」
●そうなんですね! 近くで聴いたら本当にものすごく大きな声なんでしょうね。
「そうなんです。園内でガイドしている時に、ちょうどそのデュエットが始まったりすると、私たちのガイドの声が来園者の人たちに聴こえないこともあったりします。そういう時は歌が止むのを待ってから、”これがお聴きいただきました通り、テナガザルの歌です”なんて、そんな話をしますよ」
女性飼育員に恋するゴリラ
●ほかに顔の色が派手なマンドリルというサルがいるんですよね。鼻筋が赤くて、その両脇が水色でとっても綺麗ですけれども、これは生まれた時から派手なんですか?

「実は、生まれた直後の赤ちゃんの顔は真っ白なんですね。成長と共にだんだん色がついていって、初めは真っ黒い感じの顔になって、それから成長とともに鼻筋がうっすら赤くなり、顔のこぶのところが青くなる感じです。
大人のオスですと顔が非常によく目立つんですけれど、金色のヒゲが生えたりとか、あとお尻がピンクから紫にかけた、なんとも言えない絶妙なグラデーションの色になったりとか、非常にカラフルで目立つ 動物ですね」
●顔だけじゃなくてヒゲもお尻も派手なんですね。あと、ニシゴリラのタロウくんには、お気に入りの女性飼育員がいるということで、男性飼育員が一緒にいると怒るっていうふうに本に書いてありましたけど、本当なんですか?
「そうですね。やはりなんか嫉妬みたいなものがあるようなんですね。実はうちのタロウさん、先日4月20日にちょうど50歳になったところで、日本国内のオスのゴリラとしては最高齢なんですよ。

非常に長寿のゴリラなんですけれど、実はドイツの動物園で生まれていて、16歳の時に日本に来ているんですね。
お母さんが育てられなかったということで、50年も前のことなので確かな記録もないんですけれど、女性の飼育員の方が子供のタロウさんを育てたという逸話が口頭で残っています。それで女性の飼育員に特に愛着を持っているというふうに語り継がれています」
●そうなんですね〜。ちゃんとそういうふうに認識しているんですね。
「お気に入りの女性飼育員を取っていきそうな人が近くにいるのは、やっぱりちょっと不安になったりするのかもしれないですね」
焚火にあたるニホンザル
※「日本モンキーセンター」では屋久島に生息するニホンザル「ヤクシマザル」を130頭ほど飼育しているそうですが、その群れが、冬になると焚き火にあたるって、ほんとなんでしょうか?

「日本モンキーセンターの冬の風物詩ということで、『焚き火にあたるサル』っていうのを毎年開催しているんです。実は屋久島のニホンザル、ヤクシマザルなんですけれど、今飼育している個体はすべて、犬山市生まれなんですね。屋久島から来た世代から数えると、だいたい8世代ぐらいの子孫たちっていうことになるんです。
かなり歴史を遡るんですが、大昔この辺に伊勢湾台風という大きな台風が来た時に、近くを流れている木曽川に大量の木材とかが流れ着いたりしたそうです。
当時ヤクシマザルたちは、ここモンキーセンターの、今ある場所ではなくて、木曽川沿いにあった『野猿公苑』っていうところで飼育をしていたんですね。そこで台風の時の木材を焚き火として燃やしていたら、そこにサルたちがいつの間にか集まってきて、暖を取るようになってきたと・・・。
火は、焚き火は、本来だったら動物は怖がるはずですけれども、怖いよりも多分暖かくて、いいものだっていう認識になったんでしょうね。それがいわゆる群れの文化っていう形で、親から子に焚き火はいいものなんだよ、みたいな・・・教えはしないですけど、そういうものが個体から個体にどんどん学習して伝わっていったと言われています」
5つの環境エンリッチメント
※「日本モンキーセンター」では飼育方法の工夫のひとつとして、「環境エンリッチメント」という手法を取り入れているそうですね。どんなことなのか、教えていただけますか。
「環境エンリッチメントっていうのは、平たくいうと飼育している動物たちの暮らしを豊かにして、できるだけ幸せになってもらいたい。そのために飼育担当者が行なう、あの手この手の工夫のことを環境エンリッチメントと言っています。
環境を改変することで、間接的にその動物たちの行動が変わって、それで暮らしが豊かになるという、動物の行動に直接影響させるんではなくて、環境を変えようという、そういうのを環境エンリッチメントと呼んでいます」
●具体的にはどんなことがあるんですか?
「これは本当にいろんな種類があるんですけれども、私たちの動物園では分類をしていて、5つの種類があります。
ひとつは採食と言って食べ物に関するものですね。どんな動物も基本的に食べ物に非常にモチベーションが湧きますから、例えば1日1回決まった量だけをどさっと与えるのと、何回かに分けて、しかもそれを頑張って探してっていうのでは、食べ物にかける時間が全然違ってきますよね。
野生だとやっぱり動物は、食べ物を探すために森の中をウロウロするとか、いろんな行動をしているわけなんですけど、動物園だとどうしても上げ膳据え膳になってしまうのを、できるだけそうしないように、野生と同じように食べ物を探す行動をやってもらいたいということで、取り組んだりするんです。そういうのも『採食エンリッチメント』って言っていますね。
ほかにも飼育している場所、それ自体をいろいろ改変する『空間エンリッチメント』ですとか・・・それから動物たちにはいろんな社会性があります。ひとりで暮らしたり群れで暮らしたり、テナガザルみたいにペアで暮らしたり・・・そういう動物にはその動物それぞれに適した社会的な刺激、ほかの動物と一緒に飼育する、同じ種類だったり別の種類だったり・・・そういう動物との社会的な刺激を作ってあげるという『社会エンリッチメント』ですね 。
それから感覚、視覚とか聴覚とか嗅覚とか、そういうものを刺激するような機会を与える『感覚エンリッチメント』ですとか。あるいは認知。動物もやっぱり大かれ少なかれ、みんな自分で考えて行動しているわけです。その知能を使うような機会を発揮する『認知エンリッチメント』と、今ご紹介したような5つの種類に分けて実施することが多いですね。
環境エンリッチメントは、日本の動物園の中ではメジャーな手法になっています。たいていどこの動物園でも飼育動物に対してはやっているという、そういう状況になっていますね」
●さまざまな工夫が施されているんですね。
「例えば、動物園に行ったりした時に、動物を展示しているエリアの中になんか見慣れない人工物みたいなものが入っているぞ、なんていう時は、実はよく観察しているとそれがエンリッチメントのための道具だったりすることがあります。
動物がそれを使って、いろんな行動が引き出されて、いろんな行動を見せてくれたりするかもしれませんので、動物園に行った時にはただ漫然と動物を眺めるだけじゃなくて、そういう飼育上の工夫がどこかしらに隠されているんじゃないかなと思って見ていただけると、動物園の見方がより面白くなるんじゃないかなと思いますね」

(編集部注:飼育員さんたちの大事な仕事のひとつとして、サルたちの健康管理があるそうです。そのためには個体識別が重要で、一頭一頭、顔と名前を照らし合わせて、動きや餌の食べ具合などをチェックしているそうです。サルたちへの愛情がないと続かない仕事ですね)
便利な暮らしの裏側に
※気候変動や生息環境の減少などが野生動物にいろいろな影響を与えていると言われています。綿貫さんがいちばん気になっていることはなんですか?
「やはり人間の活動がサルたちが暮らす環境を脅かしているということで、サルは基本的に暖かい地方に棲んでいる動物なんですけれども、熱帯雨林とかっていう環境が今どんどん壊されているわけですね。
そういう熱帯の森は、例えば先進国である私たちの普段の暮らしの中で使う、家を建てる木材だとか事務所で使うコピー用紙だとか、そういうものを作るために熱帯雨林の木々が伐採されていると・・・。
伐採した後、裸になった地面にもう1回、森を育てるのではなくて、我々が普段の食生活の中で意識せずに口にしている植物性油脂、それを採るためのヤシ油のヤシの木を育てるプランテーションになっているんですね。
私たちの見えないところで、サルたちの暮らしがどんどん脅かされているっていう現状があるわけですね。
と言っても、今すぐにこの暮らしを全部変えるのは非常に難しいですけれども、どこか意識の片隅で、我々のこの便利な暮らしの裏側に、そういうことが起きているって意識して、日々できるところから、ちょっとずつ行動を変えていくことが重要になってくるのかなと思うんですね。
そういう我々の活動が野生で暮らしているサルたちの環境を脅かしているのが、気になっているところですね」
●「日本モンキーセンター」のサルたちに会いに行こうと思っている方々に、綿貫さんからここを見てほしいっていうポイントがあれば、ぜひ教えてください。

「当園、非常にたくさんの種類のサルたちを飼っていて、みんなそれぞれちょっとずつ違うんですね。その違いをよく観察して、体の違い、行動の違いを見て、楽しんでいただきたいですし、できるだけサルたちが幸せに暮らせるようにと、私たちは常に配慮して飼育に取り組んでいますので、動物たちが快適に暮らしている様子を楽しんでいただきたいなと思います。
そういう様子を含めて、サルたちと同じ時間を過ごしていただいて、彼らが野生で暮らしている環境に思いを馳せていただきたいと、そういうふうなことを願っています」

INFORMATION
『飼育員がつくったサルの図鑑〜かならず会いたくなっちゃう56のなかまたち』
「日本モンキーセンター」の現役の飼育さんたちが作った本です。サルたちの特徴をよくとらえたイラストが素晴らしいです。飼育員さんだからこそ知っているサルの裏話や、綿貫さんによるサルの雑学は面白いですよ。ぜひお子さんと一緒に見ていただければと思います。
くもん出版から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎くもん出版:https://shop.kumonshuppan.com/view/item/000000003396
公益財団法人「日本モンキーセンター」のオフィシャルサイトもぜひ見てください。
◎日本モンキーセンター:https://www.j-monkey.jp
2023/5/14 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、宇宙開発や宇宙旅行に詳しいフリーエディターの「鈴木喜生(すずき・よしお)」さんです。
出版社の編集長から、現在はフリーのライター、そしてエディターとして活躍する鈴木さんは、生まれた年の1968年にアポロ8号が史上初めて月の周りをまわり、翌年にはアポロ11号が月面に着陸する偉業を達成。また、小学生の頃に映画「スターウォーズ」や「エイリアン」、「宇宙戦艦やまと」や「銀河鉄道999」などに影響を受けて、宇宙や宇宙船に憧れる少年時代を過ごしていたそうです。
そして現在は、宇宙に関連する本をたくさん出していらっしゃいますが、宇宙開発の情報を常にストックしておくために、アメリカのNASAや、日本のJAXA、そしてヨーロッパの宇宙機関ESA、さらには、民間の宇宙開発企業が発表するプレスリリースを日々、入念にチェックされているそうです。
そんな鈴木さんが先頃出された『宇宙の歩き方〜太陽系TRAVEL BOOK』は、これまで人類が宇宙に放った無人探査機などから得られた貴重なデータをベースに書いてあるので、半分はフィクションでも、まったくあり得ない話ではないそうですよ。
きょうは近未来の宇宙の旅ということで、宇宙旅行日帰りプランや宇宙ホテル滞在プラン、そして月面史跡めぐりツアーのお話などうかがいます。

無重力体験、ひとり45万ドル!
※本のチャプター1で「宇宙パッケージツアー」として「お手軽日帰りプラン」が3つ紹介されています。そのうち、2つは既に実施されているんですよね?
「この第1章だけは、いわゆるほんまもんと言いますか、ガチの宇宙旅行ガイドなんですね。以前、前澤(友作)さんが宇宙に旅行したじゃないですか。あれが2021年なんですけども、あの頃まではロシアのソユーズっていう宇宙船を使っていたんですよ。
過去にだいたい延べ12人ぐらいが自己資金でISS国際宇宙ステーションに個人旅行しているんですけども、ご存知の通りロシアがウクライナに侵攻したことで、そのサービスが今止まっちゃっていると・・・。
では、今どうしても宇宙に行きたい人はどうすればいいかというと、今言われたそのふたつのサービスがあって、ひとつは有名なリチャード・ブランソン氏が立ち上げたヴァージン・ギャラクティック社、ここの『スペースシップ2』という宇宙船があります。
もうひとつは、みなさんご存知のアマゾンを立ち上げたジェフ・ベゾス氏、彼が立ち上げたブルーオリジン社の『ニューシェパード』というこのふたつが、今お金を出せば、宇宙に行けるツールであるということになっています」
●それぞれどんなツアーなんですか?
「地球のまわりをくるくる周回する、いわゆる地球周回軌道に乗るわけではなくて、例えばボールを空に投げると、そのまま放物線を描いて落ちてきますけども、それと同じ飛び方をするんですね。
つまりはその宇宙船がいちばん高いところに行ったところが宇宙であると・・・。いちばん高いところで宇宙に到達するんですけど、だいたい4〜5分の間、無重力が体験できるという、弾道飛行って言うんですけども、そういう飛び方をします」
●体験してみたいです!
「非常に時間は短いんですけども、ヴァージン・ギャラクティック社の『スペースシップ2』が、ホームページ にちゃんとお値段が出ていて、(ひとり)45万ドル、1ドル130円で換算するとだいたい5800万〜5900万円ぐらいです。今都内のマンションの平均価格が6000万ちょっと超えているぐらいなんで、マンション1室を買うのは諦めれば、5分間の無重力体験ができるというそんな感じですよね」

巨大なバルーンで宇宙旅行!?
※本では「お手軽日帰りプラン」の3つめに、巨大なバルーンに乗って高度30キロから地球を見るツアーが紹介されていて、驚いたんですけど、こんなツアーがあるんですね?
「これ僕、いちばんおすすめです」
●巨大バルーンで・・・!?
「これ実は、高度30キロなんで宇宙には到達しない、つまりは成層圏を漂うんです。一般的に宇宙っていうと、だいたい高度100キロぐらいから上が宇宙とされているんですね。ただ30キロまで上がると、もう上を見ても空が青くなくて真っ暗なんですよ。星が見えるんですよ。で、その下を見れば、例えばISS国際宇宙ステーションから見た時みたいに地球が見えるっていう、その眺めが体験できます。
もうひとつは、さっきお伝えした宇宙船は打ち上がる時と、降りてくる時にすごくGがかかるんですよ。重力がだいたいいちばん高いと6Gぐらい。つまり寝そべってその上に自分が6人乗るぐらいの重力がかかるんですけど、このバルーンの場合は1Gのまんま。つまりなんの負荷もかからないで2時間かけてゆっくり上がって、高度30キロのところに2時間留まって、また2時間かけて降りてくるんですよ。で、この機内に入るとまずバーカウンターがあって・・・」
●びっくりしました。本に載っていてびっくりです!
「ソファーがあって、普通のトイレがあって、機内は高速wi-fiが飛んでいます(笑)。(スペース・パースペクティブ社の)ホームページを読むと書いてあるんですけど、要するにドリンク、アルコールも飲めるし、軽食もサービスで付くと・・・この前報道されたんですけど、ベンチャー会社の勢いのある社長さんが、これを社員のためにひとつチャーターしたみたいです」
●実際、いつからツアーが始まるんですか?
「来年から本格スタートだったと思うんですけども・・・2024年下期ですね。(料金は)おひとり12万5000ドルなんで、まあ1500万円ちょいなのかな、こちらは。だから高い車1台買うのを我慢すれば6時間遊べるという、お手軽価格です」
ヒルトンが監修する宇宙ホテル!
※『宇宙の歩き方〜太陽系TRAVEL BOOK』には、国際宇宙ステーションISSに接続する、史上初の宇宙ホテルが紹介されています。ほかにも、ホテル大手のヒルトンが監修する宇宙ホテルが載っていました。これはどんなホテルなんですか?
「簡単に説明すると、今NASAはいわゆる国の組織なんで、税金で宇宙開発しているんですけども、徐々に民間に仕事を開放しているんですね。で、在米の企業に宇宙ホテルを作れる会社ありますかって募集をかけて、応募してきてくれた会社のプランを見て検査して、それで良さげなものには補助金を出して開発に当たらせるという・・・。
今は3社が選ばれて、その3社に基礎設計の協力金を出しているっていう状態で、またその次のステップで審査があるんですけども・・・。だから今アメリカではISSに接続する宇宙ステーションと、あと3機、宇宙ステーションを開発しているということです。
そのうちのひとつが、ヒルトンが提携しようとしている『スターラブ』っていう宇宙ステーションなんですね。このスターラブ、いちばん面白いのは1回の打ち上げで、もう完成しちゃうと・・・。つまりはモジュールをひとつ 打ち上げて、あとはそこに空気を送り込んで、風船みたいに膨らませるんですよ。で、そこが居住区画になって4人が滞在できるんです」
●定員4名ということなんですね。
「その内装のデザイン、管理をヒルトンと提携してヒルトンがやると・・・。だからこっちはもう本当にお客さん目当てというか、そういう演出が効いている宇宙ステーションということになりますよね」
月面史跡巡りツアー!?
※アメリカの起業家イーロン・マスク氏率いる宇宙開発企業「スペースX」社は、全長120メートルの史上最大の宇宙船「スターシップ」で月のまわりを回るツアーを計画。また、NASAが中心となって進めている国際的な月面探査プロジェクト「アルテミス計画」も注目されています。月は地球人にとって、宇宙開発の象徴のような天体と言えるかも知れません。
鈴木さんの本に「月面史跡巡りMAP」が載っていて、近い将来、史跡を巡るツアーが現実になるかも知れないと思ったんですけど、こんなツアーがあったら、面白いだろうな〜というのを紹介していただけますか。
「僕は宇宙、宇宙と言っても天文からロケットマニアからいろいろな(タイプがあって)要するに電車マニアもすごく細分化されているじゃないですか。それと同じように宇宙も、すごくここが好きっていうふうに分かれるんですけど、僕はどちらかというと、天体というよりはロケットとか宇宙船が好きなんですね。月に行っても多分、殺風景ですぐ飽きちゃうと思うんですよ。
ですから、今までにアメリカとかロシアとかソビエトとか中国とかが(月に)いっぱい探査機を送り込んでいて、それが要するに風化しないもんですから、月面は風も吹かないし、空気もないから、その当時のまんまバッテリーが切れた状態でポツンとあるはずなんですよね。
それを1個ずつ巡るとまあ面白いのかな・・・記念品でちょっと部品を持ってこようかなみたいな・・・要するにトレジャーハントだと思うんですけど、そういうのは面白いかもしれないですよね」
●月面から美しい地球を見たいなって思うんですけど、絶景ポイントってありますか?
「ご存知の通り月って、片面が常に地球に向いているじゃないですか。ずっと同じ面を向けて地球のまわりを回っているんで、そちら側にいると常に真っ青な地球が見られるんですよ。ただその裏側、月の裏側に行くと何が起こるかというと、真っ暗になるわけですね、基本的に。そうするとものすごく星が綺麗に見えるはずなんですよ」
●あ〜そうだ〜!
「それも見てみたいですよね」
火星旅行〜山と峡谷!?
※実はイーロン・マスク氏の「スペースX」社は火星に人を送るプランも進めているほか、NASAも有人の火星探査を計画しているそうです。
近い将来、月まで行ったら、火星旅行もしたくなりますよね。火星で見逃せないポイントと言ったら、何がありますか?
「火星は見所がふたつあって、太陽系でいちばん高い『オリンポス山』、これがだいたい22キロぐらいの標高があるんですね。だからエベレストの3倍くらいはあるのかな。
もうひとつは『マリネリス峡谷』、火星のよくある写真を見ると、左下に見えるんですけど、すごく深い亀裂みたいな、傷みたいなのがあるんですよ。そこがすごく深くて総距離が4000キロぐらいある峡谷なんですね」
●巨大な峡谷!?
「はい、今火星のまわりの周回軌道を無人探査機がくるくる、一生懸命いろいろ観察して、観測して調べているんですけども、それの電磁波もしくはレーザー照射で調べたところ、このマリネリス峡谷に水があるらしいということになってます」
(編集部注:火星に水があるかも知れないということですが、もしあれば、今後の宇宙開発にとって、重要な意味を持つそうです)
地球を大切にしましょう
※鈴木さんが宇宙旅行に行くとしたら、どの星に行ってみたいですか?
「僕はね、地球がいいですね!」
●えーっ!(笑)地球ですか!?
「宇宙に行くと現状、お酒を飲めないんですよ。多分、宇宙に行くと血が頭のほうに均等に上がってきちゃうんで、顔がパンパンになって、足は細くなるんですけど、おそらくその状態でアルコールを飲むと、すごく酔っ払うと思うんですね。 あとお風呂に入れないでしょ!」
●はい(笑)
「ただね、1個だけ(行ってみたいのは)木星の衛星で『ガニメデ』っていうのがあるんですね。その表面は、おそらく岩石と氷に覆われているんですけど、中に海があるんですよ。内部海って言うんですけど、ESA欧州宇宙機関がそこに向けて『ジュース』っていう無人探査機を打ち上げたばっかりなんです。
それを周回軌道から観測して、もしかしたらその海に生命がいるかもしれないということを探索するんですけど、ちなみにそこに(ジュースが)到着するのが8年後なんですね。だから結果を僕が見られるかどうかはわかりませんね」
●いやいや、でもすごいですね。また新しい発見につながるかもしれないってことですね。鈴木さんは地球人として、地球という星にはどんな思いがありますか?
「太陽系のほとんどの惑星、衛星はかなり詳しく分かるようになってきたんですね。最近、写真も撮れているし、探査機も到達しているし・・・やっぱり地球ほどいい星はないんですよ。
氷ばっかりだったりとか、木星とか土星はガスですからね。表面にほんのりアンモニアが乗っかっているわけですよ、多分行ったら臭いんだと思うんですけど・・・。だからそういうのと比べて考えると、地球みたいにいいところは、おそらくないので、みんな大切にしましょうね、地球を! っていう感じでしょうかね」
INFORMATION
この本には、実際に行ける宇宙旅行パッケージツアーほか、月や火星エリア、水星や金星の岩石惑星エリアなどが豊富な写真やデータとともに紹介。
QRコードが載っていて、スキャンするとYouTubeで貴重な動画も見られます。NASAが撮ったISSから見るオーロラや夜景、宇宙旅行日帰りプランでご紹介したバルーンから見る景観を動画で再現してあったりと、見所満載です。ぜひチェックしてください。
G.B.から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎G.B.: https://gbeshop.thebase.in/items/69825180
もう一冊、鈴木さん執筆の最新刊。軌道上の宇宙望遠鏡80機以上の詳細な解説と、最新画像を豊富に掲載した240ページにも及ぶ豪華本です。見たこともない壮大で神秘的な写真に圧倒されます。こちらもぜひ!
朝日新聞出版から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎朝日新聞出版:https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=24201
2023/5/7 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、気象予報士の「わぴちゃん」こと「岩槻秀明(いわつき・ひであき)」さんです。
子供の頃から自然や気象のことが大好きだった岩槻さんは、小学校高学年の時にニュースで気象予報士という国家資格があることを知り、さっそく勉強を始めたそうです。そして絶対に合格するという強い意志のもと、高校2年生の時に、3回目のチャレンジで見事合格!
そんな岩槻さん、現在は気象予報士、そして自然科学系ライター、さらに千葉県立関宿城博物館の調査協力員としても活躍されています。
そして先頃、『空を見上げるのが楽しくなる! 雲の図鑑』を出されました。このムック本には、100種類以上の雲の写真が掲載されていますが、そのほとんどが岩槻さんの撮影なんです。
きょうは雲博士、岩槻さんに雲の不思議や種類、そして珍しい雲のお話などうかがいます。
☆写真協力:岩槻秀明

雲のメカニズム
※改めてなんですが、雲はどのようにしてできるのか、そのメカニズムをなるべくわかりやすく解説していただけますか?
「天気の現象で、雲はどうしてできるの?とか、雨はどうして降るの?とか、風はどうして吹くの?って、小っちゃな子供たちからも出てきそうな質問なんですけど、その仕組みを説明するとなると、すごく複雑なんですよね(笑)。なので、いつも大変苦労はしているんですけれども、雲ができるメカニズムはいくつかのポイントがあります。
まずひとつは空気、その中に目に見えない水蒸気が含まれている。これがひとつポイントですね。空気の中にある水蒸気は空気の温度、気温が高くなるほど、水蒸気をいっぱい持つことができるんですよ。
で、気温が下がって冷たい空気になると、あまり水蒸気を持つことができなくなるので、持ち切れなくなった水蒸気が追い出されて、小っちゃな水とか氷の粒になって出てくるんですね。ひとつはこれなんです。
もうひとつは、空気がなんらかの理由で、下から上に持ち上げられると、ふわっと膨らむんですよね。下はすごく空気がいっぱいあって、ぎゅうぎゅうに押し込められた感じなんですけど、上のほうは空気が薄いので広がっていく。まわりから押さえつけられる力がなくなるので、わーっと広がる。で、広がる時にエネルギーを使うんですね」
●エネルギー!?
「はい、膨らむのにエネルギーを使うんですよ。熱のエネルギーを使ってしまうので、使ってしまった分、冷たくなるんです。
だから今のふたつの前提がありまして、まず空気中に水蒸気を含んだ空気があって、それがなんらかの理由で持ち上げられると、もわっと膨らんで、その時に熱エネルギーを使うので冷やされる。冷えてしまうと、空気は水蒸気をあまり持てなくなるから、その持ち切れなくなった水蒸気が水の粒とか氷の粒になって漂う、それが雲です」
(編集部注:雲の正体は、とても簡単に言ってしまうと、水蒸気が冷やされてできた小さな水滴や、極めて小さな氷の結晶の集まりだそうです)

雲は何種類!?
※雲を分類するにあたって、何か基準になるものはあるんですか?
「雲の分類、昔の人はよくやりましたよね。昔、最初にやろうとした人の中には、そんな無駄なことはやめて、別のもっと役に立つことをやれって諌められたっていう話があるくらいで、よくやったなと思うんですけどね。とりあえず今は10種類に分けておりまして、その視点があるんですね。
まずは浮かんでいる高さ。雲は地上から上空だいたい1万3千メートルくらい、対流圏っていうところで、できるんですけれども、それを3つに分けるんですね。5千から1万3千メートルくらいの間の対流圏上層、それからちょっと被っているんですけど、2千〜7千くらいの対流圏中層、あと2千メートルより低い下層、その3つに分けて、上層にできる雲か、中層にできる雲か、下層にできる雲かっていうのが、まずひとつの視点。
もうひとつは雲の形というか性質というか、モクモクって上に向かって伸びる性質があるタイプなのか、横にベタ〜っと広がる性質がある雲なのか、あとは筋みたいにシュッシュッシュッてなるタイプなのかという3つ。あと雨を降らせるかどうか、これの組み合わせで10種類になっている感じですね」

●本の中で面白い説明が付いている雲を見つけました。「羽根雲(はねぐも)」って言われている雲がありましたよね。これはどんな雲なのか教えてください。
「文字通り、鳥の羽根みたいな形(笑)」
●それは普通に私たちも見ることができる雲ですか?
「時々出ていますね。筋みたいな『筋雲(すじぐも)』って呼ばれる雲がいっぱい広がっている時に注目して見ると時々できていますね。これがよく出やすいのが飛行機雲ができて、その飛行機雲が時間と共に変化するパターンですかね」
キャッツアイ/猫の目雲
●あと「キャッツアイ」っていう雲もありましたよね?
「ありますね。波頭雲(はとううん)という雲ですね」
●これはどんな雲なんですか?
「これまた、言葉で説明するのが難しい雲なんですけど(笑)」
●さきっぽがくるんって巻いてあるというか、波にようになっていますよね。
「はい、よく言われるのが日本画に出てくる波!」

●あ〜はいはいはい! まさに波打っている波っていう感じですよね。
「くるん!となった、鎌みたいなというか、それがいくつも並んだ状態で、正式には『ケルビンヘルムホルツ波』っていう舌を噛みそうな名前の風の波、それに雲が巻き込まれてできるものなんですけれども、ケルビンヘルムホルツ波が時間と共にくるっと巻いていますよね。先がどんどん巻いていくんですよ、くるくるくるって・・・。
最終的には猫の目みたいな形になるので『キャッツアイ/猫の目雲』って言われるんですけれども、そこまでいくまでに崩れちゃうことが多いので、私は綺麗な形の猫の目は見ていないんですよね」
●先ほどもちょっとお話に出ました飛行機雲ですけど、何か定義はあるんですか?
「はい、すごくざっくり言っちゃうと、飛行機によってできる雲なんです。今回のこの雲の本でも使っている国際的な基準があるんですね。雲の分類の『国際雲図帳(こくさいうんずちょう)』っていう、全世界で使われている基準みたいなものがあります。度々改定が重ねられてきて、私が生まれてからつい最近まで、ずーっと同じのが使われていたんですけれど、それが2017年版で改定になったんですね。
改定前までは飛行機雲って、すごく宙ぶらりんな位置付けだったんですよ。とにかくそれこそ飛行機によってできる雲くらいの位置付けしかなくて・・・今回2017年版できちんと明記されたというか、どうなったかって言いますと、やっぱり10種類のどれかに位置付けることになったんですね。
氷の結晶でできて、シュッシュッてしているから『巻雲(けんうん)』、人工的なメカニズムでできた巻雲ということに位置づけられました。ただちょっと条件がついたんですよ。飛行機が通ってから10分以上雲として残り続けたら、人工的な巻雲、飛行機の巻雲として認めますよって・・・」
●確かに毎回、飛行機雲って出現するわけじゃないですよね?
「そうですね。空気が乾燥しているとすぐ消えちゃったりとかしますね」
(編集部注:岩槻さんの『雲の図鑑』には、出会える頻度「レア度」がAからDの4段階で表示されています。Aはよく見られる、Bは時々見られる、Cはたまに見られる、そしてDは極めて稀。お話にあった「キャッツアイ」はレア度はCでした)
滝のように溢れ出る雲
※5月から7月にかけて、よく見られる雲はありますか?
「意外に雲って例えば、モクモクした雲は夏の雲で、筋みたいな雲とか羊雲は秋の雲だとか、よくイメージはあるんですけれども、意外に季節的な傾向はありそうでなくてですね」

●そうなんですか?
「そうなんですよ。だから今この季節だから、この雲は出ないなんてことはなくて、多分1ヶ月毎日、丁寧に見ていれば、十種雲形の10種類はちゃんと揃えられると思います。これから夏休みの季節でも十種雲形を集めようと思えば、多分毎日ちゃんと見ていれば、集まると思います」
●自由研究とかいいですね?
「あっ、いいですよね。その中でも5月から7月って梅雨時なので、梅雨にまつわる雲が出やすいかもしれないですね」
●こういう雲が出てきたら雨が降るとか、そういう雲が出てくるってことですか?
「雨雲系ですからね。世間一般的にはあまり嬉しがられない、乱層雲みたいなしとしと雨を降らせるやつ・・・あとは5月くらいだと、まだ冬の名残りみたいな寒波が上空に流れ込んできたりすることがあるので、積乱雲が発達することがありまして、雷雲が見られます。
5月6月って実は意外に雹(ひょう)が多い季節でもあって、雹の災害に気を付けなきゃいけないんですね。なので積乱雲とかそういった梅雨時の乱層雲とかが比較的よく見られる雲かもしれないですね」
●今まで岩槻さんが見てきた中で強く印象に残っているとか、珍しかったなって思う雲はありますか?
「実はもう数えきれないほどいっぱいありまして(笑)、どれを出そうかってすごく悩むんですけれども、やっぱりいちばん印象に残っているのは、とあるテレビのロケで行った滝雲(たきぐも)。

秋の終わりぐらいの冷え込んだ朝に霧が出ることがあるんですけれども、その霧が山と山の窪みの盆地みたいなところに溜まるんですね。その霧がまるで盆地の入れ物から溢れるように、滝のように溢れ出るような感じで動く雲、それを滝雲って言うんですけど、それをテレビのロケで見に行ったんですね。それでロケ日にぴったりと、わーっとダイナミックな光景が見られたのですごかったです」
(編集部注:地形の影響で出現する滝雲、岩槻さんは新潟県の南魚沼で目撃したとのことですが、調べてみると魚沼市にある「枝折峠(しおりとうげ)」が滝雲の有名なスポットで、息を呑むほどの神秘的な光景を見られるそうですよ)
自然と触れ合う、雲をそのきっかけに
※雲は天気の変化や、季節の移り変わりを知らせてくれるメッセンジャーかも知れませんね。
「その通りですよね。まずその季節の変化も感じますし、昔の人はそれで天気の予報をしていましたしね。あとこれからの季節で、いわゆるゲリラ豪雨って呼ばれているような天気の急変、雷雲とか前兆となる雲があります。それを知っていれば、あの雲が出てきたから、ちょっと早めに撤収しようかって逃げることもできますし、まさにメッセンジャーですよね」
●岩槻さんは仕事柄いろんな雲をご覧になっていると思うんですけれども、純粋に雲を見てどんなこと感じますか?
「これは雲の種類とかにもよって変わりますけれども、綺麗な雲を見たら素直に綺麗ってなりますよ。 で、綺麗な雲を見つけた時って、滅多に見られない雲とか憧れの雲を見つけた時って、カメラを構えるんですけど、手が震えるんですよね。だから意外に、あれっ?あれっ? みたいな感じで撮れていないとかなっちゃうっていう、結構冷静なようで感情的に見ているなって・・・(笑)」
●でも、それだけ心揺さぶられるものがありますよね?
「揺さぶられますね〜」
●では最後にこの本『空を見上げるのが楽しくなる! 雲の図鑑』を通して、いちばん伝えたいことを教えてください。
「みなさん、外に出たら・・・なかなか今は、まわりを見渡すとスマートフォンの画面をご覧になっちゃっているかたのほうが多いんですね。それはそれでもいいんですけれども、ぜひ空を見たりとか、あと肌で空気を感じてみたりとかね。
それから身のまわりの、雲の流れ、風の動き、自然の振る舞いとか、いろいろ感じてみるのもいいと思いますので、外に出た時は自然と触れ合える、雲はそのひとつのきっかけ、ひとつの要素として、ぜひ雲も取り入れてみていただけると嬉しいななんて思っていたりします。
あと、第二第三の私みたいな雲の図鑑を作るような雲博士が登場して、どんどんこの業界を盛り上げてほしいななんて思っていたりもします」

INFORMATION
岩槻さんが出されたムック本には、100種類以上の雲の特徴が網羅されています。ほかにも雲のメカニズムや眺めるときのポイントなどがわかりやすく解説、写真が大きいので雲の形がよくわかりますよ。マキノ出版から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎マキノ出版HP:https://www.makino-g.jp/book/b620661.html
◎岩槻秀明さんのオフィシャルサイト:http://wapichan.sakura.ne.jp
2023/4/30 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、南極地域観測隊の元調理隊員「渡貫淳子(わたぬき・じゅんこ)」さんです。
渡貫さんは第57次・観測隊の調理隊員として、2015年12月から2017年2月まで
およそ1年3ヶ月にわたって、南極の昭和基地に滞在、隊員30名の食事を毎日作るミッションを担っていらっしゃいました。
そんな南極での活動をまとめた『南極の食卓〜女性料理人が極限の地で見つけた暮らしの知恵』という本を出されたということで、番組にお迎えすることになりました。
きょうは、隊員たちの胃袋を満たす毎日の献立や、私たちの生活に通じる、ゴミを出さない調理の知恵などうかがいます。
☆写真協力:渡貫淳子

毎日30人分の食事を朝・昼・晩!
※渡貫さんは青森県八戸市(はちのへし)生まれ。料理の専門学校を卒業後、その学校に就職。結婚・出産のため、退職するも、家事や子育てをこなしながら、飲食業界で調理の仕事を続けていたそうです。
そして30代後半に、南極に行ってみたいという夢を抱き、3度目のチャレンジでついに合格!ちなみに渡貫さんは、昭和基地史上ふたりめ、民間人としては初めての女性調理隊員だったそうですよ。
正式に隊員になった渡貫さんの、最初の大きな仕事は、南極に持って行く食材の発注、仕入れ、そして船への積み込み。その量たるや、隊員ひとり1年間で1トン、それが30人分ですから、トータル30トン以上にもなるんです。
調理隊員はふたり、ということで、相方さんと一緒に入念に準備、電卓をたたいて計算し、発注したあとも、これで足りるかな〜という不安が常にあったそうですよ。
日本での準備が整った渡貫さんたち南極地域観測隊の隊員は、まず、飛行機でオーストラリアに入り、先に日本を発った「南極観測船しらせ」と合流し、いざ、南極へ。そして、およそ3週間の航海を経て、昭和基地に到着したそうです。

●これは何度も聞かれていることだと思うんですけど、南極にやっと着いた時、どんな気持ちでしたか?
「それがですね、意外とあっけないというか、一面の銀世界じゃないんですよ。南極に着く時はちょうど夏の時期にあたるので、意外と雪がなくて、岩が露出してゴロゴロしていて、茶色! って感じです」
●へ〜〜、想像とちょっと違うという感じだったんですか?
「はい、なんか岩山に来たぞ! みたいなそんな感じなので、イメージとしては何もない真っ白い世界と思っていたのがちょっと違うんです(笑)」
●いざ南極での生活が始まって、越冬隊員30人分の食事を調理担当のおふたりで作るわけですよね?
「そうですね。私たちが作るものしか逆に食べ物がないので・・・日本だったらちょっと缶コーヒーを買いにとか、コンビニに行ったりとかできると思うんですけど、もちろんそれはないので、とにかく食べるものを用意してあげないと、みなさん食べられない・・・ですから、常に作っているそんな日常ですね」
●私も去年結婚して、きょうの夜は何を作ろうって日々思っているんですけど、渡貫さんの場合はそれが朝・昼・晩ですし、しかも30人分ですよね。どうやってこなしていたんですか?
「それがですね・・・私の感覚からすると、そんなに大変じゃないと言ったら怒られそうですけど・・・例えば、おうちでご家族の食事を作っていらっしゃる方も同じだと思うんですよね。家族のために1日3食であったりお弁当であったり、あとおやつを作ったり、みなさんされていることだと思うんです。
それが人数が少ないか、30人かっていうだけで、私としては普段から飲食業界で、すごく多い人数の食事を作っていたので、全然抵抗なくこなすことができたかと・・・。
あとは主婦で毎日作り続けることには慣れていたので、ある意味、そこは主婦のスキルが活かせたんじゃないかなって思います」
●とはいえ、南極に持って来た食料の中からやりくりするっていうことですよね?
「まぁそれしかないので・・・(笑)。でも意外と諦めがつくというか、欲しいものがあっても届ける術もないですし、なのであるもので・・・ですから冷蔵庫の中を見てどうしようかなっていうそういう毎日ですかね」
●まず何から使っていくとか、そういったセオリーはあったんですか?
「実はセオリーはないんです。そもそも30〜40トンの食料を一気に運んでしまうと、とにかく段ボールの山なんですよ(笑)。なので正直どこに何があるかを探すのが大変。
ですから最初のうちは手前にある段ボールを開けて、そこにある食材からとにかく作っていく。時間の経過とともにだいたい冷蔵庫の中身が把握できてくるので、そこからこの材料はちょっと多いから、ここから消費していこうかなみたいな感じで、本当に冷蔵庫の中と相談しながら献立を考えていくという形なので、メニューは考えていかないんですよ」

人気の献立は普通の定食!?
※朝・昼・晩の定番メニューみたいなものはあったんですか?
「基本的には朝ご飯は、食べる人、食べない人がいらっしゃるので、ビュッフェスタイルで、ご飯食もあり、パン食もあり、ビジネスホテルの朝食みたいな感じですね。
お昼はやはりみなさん、仕事と仕事の合間に取る食事になるので、さっと食べてまたすぐ仕事に戻れる、もしくは少しでも休憩が取れるように、麺類とかどんぶりだったり、そういったものが多かったかなと・・・。夜は定食のようなご飯とお味噌汁に、メインと小鉢があってみたいな大体それが日常の食事ですね」
●なるほど。渡貫さんの得意料理はなんですか?
「なんですかね・・・実は私もともと和食が専門だったこともあって、そんなにカレーライスを作るほうではなかったんですけれども、 南極だと1週間に1回カレーライスなんですね。カレーライスの時にはやはりみなさんご飯の消費量もすごく多いので、逆に南極に行ってカレーを作るのが得意になったかなとは思います(笑)」
●そうなんですね(笑)。
「あと意外だったのは、やっぱり時々お誕生日とか、何か行事食っていうことで、パーティーのようなお料理を作ることもあるんですけれども、それ以上にきょうのご飯は良かった! とか、美味しかった! って言ってくださるのは、普通の焼き魚定食みたいなものだったり、本当に飾らない日常の食事のほうが反応はよかったなと思います」

リメイク料理「悪魔のおにぎり」!
※渡貫さんが先頃出された本に生ゴミを出さないための知恵として「リメイク料理」が載っていました。どんな料理なのか、教えてください。
「そもそもゴミを(南極から)日本に持って帰らなければいけないんです。 もちろん、生ごみを生ごみとして持って帰るわけではなくて、最終的にきちんと処理をした状態で、灰にして持って帰ってくるんですけれども、やはり持って帰る以上、ゴミの量を極力減らさなければいけない。そうすると日常で出てくる食事の残り物を減らさなきゃいけない。
じゃあどうしようかなと思った時に、その日に出した料理をちょっと形を変えて別のものにしてあげて、次の料理につなげていく。そういったことが環境に負荷をかけないためにも必要だったっていう、そんなこともあって生まれた料理かなと思います。
日本だったらシンクに流せる液体も、なかなか南極ではそのまま処分できないので、たとえば缶詰でしたら、缶詰の固形のところは料理に使う、液体のところはまた別の料理にしてあげるという形で、極力全部、余さず残さず作るような工夫が南極では必要でした」
●そのリメイク料理で有名になったのが「悪魔のおにぎり」ですよね。日本に帰ってこられて、某コンビニチェーンで商品化されましたけれども、考えたのは渡貫さんだったんですよね?
「考えたと言ってもね・・・材料は天かすと天丼のタレのようなものと、青さのりだけなので、そんなにたいそうなおにぎりではないんですが(笑)、私が夜食用に作っていたおにぎりがもとになりました」

●本に載っていたレシピをメモらせていただきました(笑)。改めてどんなおにぎりか教えていただけますか?
「私はいつも厨房で、残った材料を使って、夜食のおにぎりを作っていたんですね。実はいろんな種類のおにぎりがあったんですが、唯一そのおにぎりだけ名前がつきました。
お昼ご飯に天ぷらうどんを作った日だったんですけれども、その日は余った材料が天かすしかなかったんですよ。どうしようかな〜と思って、とりあえず白いご飯はあるので、そのご飯に天丼のタレのような、ちょっと甘じょっぱいタレで味をつけて、天むすのエビが入ってない感じっていうんですかね・・・そんなのを作ろうと思って天かすを入れて混ぜたんです。
なんかちょっと物足りないんだよなと思って、厨房に余っていた青さのりを入れたんですけど、青さのりのおかげで、すごく香りがよくなって、なんでしょう・・・天かすが入っていて油っぽいのに食べやすい、食べ進むっていうことで、みなさん結構好んで食べてくださったんです。
ただ問題は、このおにぎりを私が出す時間が22時とか23時なんですよ。夜の時間帯に食べるには、ちょっとこれ、夜に食べちゃいけないよね(笑)。ですけど、みなさん美味しさはわかっているので、どうしても負けてしまう、葛藤しながらも結局負けて食べてしまうので、悪魔的なおにぎりだということで、食べていた人が名前をつけてくださいました」
●それほど、食が進むってことですよね(笑)。
「ちょっと夜中には危険なおにぎりだったと思います」
(編集部注:渡貫さんの仕事は、朝昼晩の食事を作る以外に、日帰りで作業に出かける隊員のためにお弁当作りもありました。冷たくなると美味しくないので保温機能の付いたお弁当箱を持たせたそうですよ。
忙しい日々を送っていた渡貫さんが、南極でいちばんの癒しスペースと表現している場所が昭和基地の中にあるんです。その場所とは「グリーンルーム」! 野菜を育てるための小さな部屋で、南極で緑が見られるのは、ここだけだそうです。
実は南極には環境を守るための保護条約があって、土や植物のタネは持ち込めません。そのため、事前に環境省に申請し、許可されたタネを持っていき、水耕栽培で、トマトやキュウリ、モヤシや水菜などを育てたそうです。
隊員たちにとって、新鮮な生野菜はいちばんのご馳走で、食卓に並ぶと、みんなテンションがあがっていたとおっしゃっていましたよ。
渡貫さんの本『南極の食卓 女性料理人が極限の地で見つけた暮らしの知恵』には、グリーンルームや収穫した野菜の写真なども載っていますので、ぜひ見てください)

便利なこと=幸せなのか
※およそ1年3ヶ月にも及ぶ南極・昭和基地での活動を終えて、帰国されてから、なかなか普段の生活になじめなかったそうですね。
「見事に社会不適合になって帰ってきました」
●それはどんなことに違和感がありました?
「まず、いろんなものが溢れているんですよね。物もそうですし、食べ物もそうですし、あと情報も・・・交差点に立った時に、いろんな音が耳の中にうわーっと入ってきて、頭が整理できなくなって、(南極に行く)前は普通にできていた日常生活がこんなにストレスを感じるのかっていうのが実感でした」
●そうなんですね。当たり前すぎて、特に気にしたことはなかったです。
「それが普通の生活だと思っていたんですが、逆にいろんなものに制約があって、必要最低限のものだけで生活をしていた・・・そこから何不自由ない便利な生活に戻ったら、逆に便利なこと=幸せとはちょっと違うのかなって、私は思うようになってしまいました」
●一方で南極滞在中に身についた習慣で、今もやっているよっていうようなことはありますか?
「やっぱりゴミに対する躊躇する感覚は今も抜けないので、いかに自分の日常生活でゴミを減らせるか・・・あとは危険予知と言って、やはり何が起こるかわからない生活だったので、ひとつのことを行なうにしてもいくつかの方法を準備するんですね。
日本に帰ってきても、たとえば電車が遅延した時にどの手段で目的地まで行くかっていうルートをいくつか用意したり、携帯電話の電源が切れてしまったら、できなくなることがいっぱいあるじゃないですか。なのでメモを取ったりですとか、ちょっとアナログな部分でも同時並行で必ずバックアップ体勢を作るように、これはもう無意識に身についた術なのかなと思います」
●南極での生活は、私たちの今の日常とつながっているんですね。
「多分みなさん、きっと別世界だと思っていらっしゃると思うんです」
●思っていました。
「実はすごく近いというか、逆に災害時の備えにつながったりとか、すごく日常生活に活かせることが多かったと思います」
●食品ロスについてもそうですよね。いろんな知恵がいっぱいありますよね。
「そうですね。みなさん食品ロス削減って言われると、すごく難しいテーマに捉えられがちなんですが、実は本当に日常のちょっとした工夫で減らせることって、いくらでもあるんじゃないかなとは思います 」

南極での経験を活かして
※では最後に、南極生活から得た経験を今後、どう活かしていきたいか、教えてください。
「それだけのチャンスをいただいて、日本では得られない、ありがたい経験をさせていただいたなっていうのがまずひとつと、これをせっかくなので、日本の生活でも(活かして)、そのままもとに戻るのはもったいないなと思います。自分ひとりができることってたかが知れている小さなことだと思うんですけど、その小さな積み重ねがいつか大きな変化につながれば、そんな思いでこれからもいろんな活動ができたらなと思います」

(編集部注:渡貫さんは、屋外でペンギンを観察したり、魚を釣ったりという活動もされていたそうです。渡貫さん曰く「ドアの向こうは、むき出しの自然」だったそうですよ。
ちなみに渡貫さんたちの観測隊が、巨大な魚を釣りあげ、それがニュースになったことがあったそうです。その魚の名前は「ライギョダマシ」、全長はなんと157センチ! 観測隊史上最大の獲物だったということで、日本に持ち帰り、現在は葛西臨海水族園に展示されているとのことです)
INFORMATION
南極での生活や奮闘ぶりを垣間見られるほか、南極大陸や昭和基地内の写真、そして献立の写真なども豊富に掲載。主婦でお子さんもいらっしゃる、ひとりの料理人の挑戦の記録とも言える一冊です。食品ロスを減らすヒントもありますよ。
家の光協会から絶賛発売中です。ぜひ読んでください。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。この番組のホームページにリンクをはっておきます。
◎家の光協会HP:http://www.ienohikari.net
渡貫さんは食品ロスや防災に関する講演活動なども行なっていらっしゃいます。ぜひネットで検索してみてください。
2023/4/23 UP!
SDGsという言葉、ここ数年で随分浸透してきたように思いますが、いかがでしょうか。SDGsはご存知の通り「SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS(サステナブル・デベロップメント・ゴールズ)」の頭文字を並べたもので、日本語に訳すと「持続可能な開発目標」。
これからも地球で暮らしていくために、世界共通の目標を作って資源を大切にしながら経済活動をしていく、そのための約束がSDGs。2015年の国連サミットで採択され、全部で17の目標=ゴールが設定されています。
この番組、ベイエフエム / ザ・フリントストーンでは「SDGs〜私たちの未来」というシリーズ企画を立ち上げ、これまでにSDGsに取り組んでいる事例をいろいろご紹介してきました。
今週は、そんなシリーズの第12弾! SDGsの17の目標=ゴールから「つくる責任 つかう責任」ということで、「ロスを減らす、なくす」をテーマにお花の「ロスレスブーケ」、そしてカラーコスメをアップサイクルしたクレヨン「ハロヨン」をクローズアップ!
今までにないシステムを作り、イノベーションを起こした、ふたりの女性起業家、「FLOWER」の小室美佳(こむろ・みか)さん、「COSME no IPPO」の大澤美保(おおさわ・みほ)さんにご登場いただきます。
☆写真協力:FLOWER、COSME no IPPO
可愛くてお得!

※まず、ご紹介するのは「FLOWER」という会社が提供している「ロスレスブーケ」です。このサービスはいろんな種類のお花の、可愛くてヴォリュームのあるブーケがお手頃な価格で利用できる、とても優れたサービスです。
それでは、このサービスを企画し、展開している「FLOWER」の小室美佳さんにお話をうかがっていきます。
この「ロスレスブーケ」というネーミング、ポイントは「ロスレス」なんですよね。そのことも含め、どんなサービスなのか、ご説明いただけますか。
「ロスレスブーケは、私たちが作った新しいワードなんですけども、端的に言いますと、数量限定で売り切り販売をすることで、そもそも破棄とかロスになる花を生み出さずに販売するサービスです。なので、ロスゼロブーケでもいいんですけど、ゼロに近づける努力をするっていう意味でも、ロスレスブーケと名付けております。
一般的にはお花屋さんは、やはり(お花は)生物ですし、仕入れた時に花の状態も個体差、人間と同じで生き物なので、個体差がありますし、すべてが売り切れる前提で販売はしていないのが当たり前の業界なんですね。
いちばん(お花が)綺麗な状態でお客様に届けるって意味でも、仕入れたお花の中でも綺麗なものを選ぶし、かつ売り切れなかった場合に関しては、その分も考慮して売価にちょっと転換させて、お花を売るのが業界の、そういうものだよねっていう考え方があったんです。
もっと手軽に、もっと新鮮に、もっと可愛いものを人に届けるにはどうしたらいいのかなっていうところを、私たち含めて改めて考えた時に、じゃあ仕入れた分を数量限定で売り切っちゃって販売をすることで、何か新しい仕組みにならないかなって考えた上で、このロスレスブーケが誕生しました」
●確かにサイトに載っている、ロスレスブーケのいろんな種類のお花を見ると、残りわずかっていう表示が出ていますよね。
「そうですね」
●いちばんのセールスポイントは、どんなところにあるんですか?
「いちばんのセールスポイントは、やはり可愛いっていうところなんですけど、もうひとつ・・・いちばんがふたつあるんですけど(笑)、お得っていうところです。可愛いブーケがお得に手に入るっていうのがセールスポイントです」
(編集部注:気になる販売価格は、10本前後のお花のブーケが送料込みで2,200円くらいから。ほかで購入すると3,500円から4,000円ほどのお値段になるブーケだそうです)
お得だけじゃダメ!?

※もともとお花の業界とは無縁だった小室さんが、なぜこのサービスを始めるに至ったのか、それは以前、在籍していた会社の仕事が多忙を極め、深夜、家に帰って寝るだけという生活を送っていた頃、ある時、友人の結婚式でお花をいただき、持ち帰って部屋に飾ったところ、そのお花に癒され、「自分の時間」を取り戻すことにつながったそうです。
そこで「小室」さんは、お花のある暮らしを多くのかたに、手軽にリーズナブルに提供できないかと考え、試行錯誤のすえ、1年半ほど前に「ロスレスブーケ」のサービスを始めたそうです。
●小室さんは、お花の仕入れにも関わっているんですか?
「はい、そうです。もともと定期便(*)も含めて、別の会社のフローリストさんにも入ってもらったりしたんですけど、今回のロスレスブーケってお得だけじゃダメなんですよね。やっぱり可愛くてお得! それを私がなんとなく抱いている、可愛いみたいなものを言語化して、実際に売るところを別の方にやってもらった時期もあったんです。
でも、うまく伝わらなかったり、やっぱり(花は)生き物なので、実際に思うようにいかなかったりしたこともありましたね。
私も割とぱっと行動しちゃいたい人間なので、私やってみるか、みたいな感じで・・・経験はなかったんですが、それまでもずっと毎日、花のことを考えているような人だったので、気づいたら知識とかも増えていたこともありまして(やるようになりました)。
私が仕入れとあと、当日の撮影ですとか、実際に(お客様に)アプリを見てもらう時に、ブーケの(写真に添える)タイトルにも、とてもこだわっているんですけど、そういう編集まわりも含めてやっています」
(編集部注:小室さんの会社「FLOWER」では「ロスレスブーケ」のほかに「ポストに届く定期便」(*)というサービスも行なっています。「ロスレスブーケ」に関しては、毎週90種ほどの新作が登場しているそうですよ)
お花のある暮らし

※部屋にお花があるだけで、ぱ〜っと明るくなるというか気持ちまで晴れやかになりますよね。
「いちばん気軽に自分のテンションを高めてくれるというか、花が目に入った瞬間、風速早く、可愛い! ってなるのって、実は花しかないんじゃないかなと思っています。花か私だったら自分の子供か、みたいな・・・ケーキとかコスメとかも含めて、私のまわりは可愛いものに溢れているんですけど、手軽にかつ可愛いキュン! って思うものは、もしかすると花の力なのかなって最近思っています」
●リスナーさんたちがロスレスブーケが欲しいと思ったら、どのようにしたらよろしいですか?
「嬉しいお言葉です。その場合は、今『FLOWER』というアプリをiOSとandroidでダウンロードできるようになっていますので、検索していただいてアプリをダウンロードいただくか、あとは最近WEBでも注文ができるようになりましたので、まずはちょっとWEBからやってみようかなという、そういう方に関してはインターネットで検索していただいて、そこからご注文いただけます」
●ロスレスブーケのサービスを通して、いちばん伝えたいことを教えてください。
「いちばん伝えたいこと・・・いっぱいあるんですけど(苦笑)、やっぱり私、1ユーザーとして思うのは、花がきっかけで、花のある暮らしを続けることで、自分の時間が好きになるというか、今の私いいじゃん! じゃないですけど、自分の暮らしが好きになるなと思っています。
それのいちばん手軽な存在で、かつロスレスブーケの場合はお得っていうところもあるので、ハードル低く、自分の理想的な状態を実現できる素敵なツールだと思っています。
みなさんがなんとなく抱いているお花のある暮らしっていいよね! っていうものを続けることが、もし『FLOWER』で出来るのであれば、すごく素敵な時間を毎日生活の中で続けられるんじゃないかなって、今信じてやっているので、そういう時間がみなさんに増えたら嬉しいなと思っています」
<食品ロスの現状>
私たちの生活を見てみると、「食品ロス」も大きな課題ですよね。農林水産省のホームページによると、日本では1年間におよそ612万トンもの食料が捨てられているそうです。これは東京ドーム5杯分とほぼ同じ量で、国民ひとりあたりに換算すると、毎日お茶碗一杯分の食料を捨てていることになるとか。
一方、世界では、まだ食べられる食料が年間およそ13億トンも廃棄されているそうです。
日本での食品ロスの原因は、大きく分けてふたつ。ひとつはスーパーマーケットやコンビニなど、小売店の売れ残りや返品、飲食店での食べ残し、売り物にならない規格外品などの事業系食品ロスが328万トン。
もうひとつは、家での料理の作りすぎや、買ったのに使わずに捨ててしまうなど、家庭系食品ロスが284万トンとなっています。
環境への影響や、世界的な人口の増加による食糧危機を考えると、食品ロスの削減は緊急な課題といっても過言ではありませんね。
そんな中、日本でも自治体や企業での取り組みが広がりつつありますが、私たちにもすぐできることがあります。例えば、買い物に行く前に冷蔵庫の中やストックしている食材を確認し、無駄な買い物をしない。
それから、お腹が空いている時やイライラしている時に買い物に行くと、買う予定になかったスイーツやお惣菜など、余分な物を買ってしまうので買い物に行くタイミングを見計らうのも大事かもしれません。
ほかにもご家庭で、そしてひとりひとりが出来ること、たくさんありますよね。ひとりの小さなことでも、1000人が、10000人が続ければ、大きな削減につながるはずです。
カラーコスメをアップサイクル!

※ここからは、カラーコスメをアップサイクルしたクレヨン「ハロヨン」をご紹介します。この「ハロヨン」は、大澤美保さんが進めているプロジェクト「COSME no IPPO」から生まれたアイテムで、使われなくなったカラーコスメを回収し、クレヨンに生まれ変わらせた画期的な商品なんです。
一箱に5色入っていて、持つと手に馴染む独特なフォルム、そして、箱ごとにクレヨンの色が違うのも特徴なんです。見た目も可愛いし、発色もいいし、中にはラメが入っているクレヨンもあるんです。さらに一般的なクレヨンは1本1本を紙で巻いていますが、「ハロヨン」は巻紙がないのでゴミにならないのもいいな〜と思いました。

そんな「ハロヨン」を開発した大澤さんにお電話でお話をうかがいました。まずは「ハロヨン」というネーミングに、どんな思いが込められているのか、お聞きしました。
「大好きなコスメをアップサイクルして、クレヨンという新しい価値に変えていくっていうことで、その新しいクレヨンに、こんにちは、っていうような意味で、ハロー、それにクレヨンをくっつけた造語です」
●ハローとクレヨンで、ハロヨンなんですね〜。
「はい! そうなんです」
●改めてCOSME no IPPOとは、どんなプロジェクトなのか教えていただけますか?
「美容業界のゴミゼロを目指して活動しているんですけれども、具体的にはお役目を終えた、もう使わなくなったアイシャドウとかチークとか口紅などのカラーコスメを、クレヨンにアップサイクルしてお届けしているというプロジェクトになります」
ワクワクの循環
※カラーコスメをクレヨンにするという発想が素晴らしいなと思っているんですが、そのアイデアはどこからきたのか、お話しいただきました。
「私自身、すごくコスメが大好きなんですけども、やっぱりカラーコスメは何にワクワクするかっていうと、色や発色だったりすると思うので、それを捨ててしまって、さよなら! にしてしまうのではなくて、何かに活かしたいなと思ったんですね。
(私には)娘がふたりいるんですけれども、娘たちが絵を描いていることとか、世の中を見渡してもアートという業界が盛り上がっていることなどもあって、絵を描くものに変えたいなと考えまして、そこからいろいろ試行錯誤した結果、あの形になっています」
●コスメは、例えばアイシャドウとか最後の最後まで使い切ることって、私自身はなかなかなくって、かといって捨てるのもっていう感じで、どんどん溜まっていってしまうんですけど、悩ましいですよね〜。
「そうなんです。ワクワクして買ったものをワクワクした形に変換するという『ワクワクの循環』というふうに呼んでいるんですけれども、喜んでくださるお客様も多くいらっしゃるので、まだまだもっと多くの方に知っていただきたいなと思って活動しているところです」

(編集部注: カラーコスメの回収方法なんですが、「COSME no IPPO」の公式インスタグラムからコンタクトしていただくか、百貨店のイベントでも回収しているそうです。
「ハロヨン」はプレゼントとして、とても人気で、お子さんだけでなく、大人の女性も使っているそうですよ。大澤さんは今後「ハロヨン」で描いた絵の展覧会を開催したいとおっしゃっていました)

INFORMATION
<「ロスレスブーケ」「ハロヨン」情報>
「ロスレスブーケ」を取り寄せてみたいと思われたかたは専用のアプリ、またはサイトからご注文いただけます。お値段はブーケによって異なりますが、送料込みで2,200円ほどから購入できます。詳しくは「FLOWER」のオフィシャルサイトをご覧ください。
◎「FLOWER」:https://flowr.is
「ハロヨン」は一箱5色入り、箱ごとにクレヨンの色が違うのでどんな色が入っているか、開けるときのワクワク感もあります。価格は一箱税込で1,980円。ご注文は「COSME no IPPO」のオフィシャルサイトから、どうぞ。
◎「COSME no IPPO」:https://cosmenoippo.official.ec

応募はメールでお願いします。
件名に「プレゼント希望」と書いて、番組までお送りください。
メールアドレスはflint@bayfm.co.jp
あなたの住所、氏名、職業、電話番号を忘れずに。
番組を聴いての感想なども書いてくださると嬉しいです。
応募の締め切りは4月28日(金)。
当選発表は発送をもって代えさせていただきます。
たくさんのご応募、お待ちしています。
応募は締め切られました。たくさんのご応募、誠にありがとうございました。
2023/4/16 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、おもにウミガメやクジラなどの海洋動物を研究されている「きのした・ちひろ」さんです。
きのしたさんは岡山県生まれ。子供の頃から生き物が大好きで、虫や魚をつかまえて、おうちで飼ったり、動物園や水族館に行くのが大好きだったそうです。そして東京大学大学院から東京大学・大気海洋研究所を経て、2022年から名城大学に特別研究員として在籍されています。
専門は、生き物の行動を、繁殖の視点で研究する「行動生態学」、そして水中に潜る動物の体内で、何が起こっているのかを明らかにする「潜水生理学」ということで、おもにウミガメや海鳥を研究。その一方でイラストレーターとしても活動されています。
きょうはそんなきのしたさんに、生き物の不思議で面白い行動や生態についてうかがいます。
☆写真&イラストレーション協力:きのしたちひろ

「バイオロギング」という手法でウミガメを研究
※実はこの番組できのしたさんを知ったのは、葛西臨海水族園のイベント情報で、「ウミガメの研究者で、イラストレーター」と紹介されていて、ぜひお話をうかがいたいと思ったからなんです。
きのしたさんのおもな研究対象がウミガメなんですよね。どんな研究をされているんですか?
「私は野生のウミガメの、海の中の行動や生態について8年間ほど研究しています。特にアカウミガメという種類のウミガメを対象としているんですけど、ウミガメはマッコウクジラなどと同じように肺呼吸動物であるにもかかわらず、数時間、息をこらえて潜ることができます。
潜ってそこで何をしているのか、あるいは体の中はどうなっているのかっていうことについて興味を持って調べています」
●水族館では水槽の中を泳ぐウミガメを観察できますけれども、海を広く泳ぎ回って潜ったりするウミガメはどんな方法で研究するんですか?
「(海を)広く泳ぎ回るウミガメたちを、生身の人間が追うのは非常に難しいっていうか無理なので、私たちのチームはウミガメにできるだけ負担にならないような、小型の機械でカメラが付いた、深度とか泳ぐ速度が分かるような装置、データロガーって言われるものなんですけど、これを取り付けて、海の中の行動を追うバイオロギングと呼ばれる手法を使って研究をしています」
●バイオロギング!? その研究方法からどんなことが分かってきたんですか?
「本当にたくさんあるんですね。例えば、私たちはずっと岩手県でウミガメの研究をしているんですけど、そこに来るアカウミガメは結構広い範囲を泳ぐんです。日付変更線を越えるぐらいまで泳いで行ったりとか。
あるいは、ウミガメは暖かいところにいるイメージがあると思うんですけど、移動経路を見てみると、北方領土の歯舞諸島とかあの辺まで泳いで行っている個体もいることが分かりました。今まで想像していたのより広いなっていうことが分かりましたね(笑)」
(編集部注:きのしたさんによれば、ウミガメは日本にはアカウミガメ、アオウミガメ、ヒメウミガメ、オサガメ、タイマイの5種とアオウミガメの亜種としてクロウミガメが生息しているそうです。ちなみに、千葉県はアカウミガメの産卵の北限にあたり、一宮あたりの砂浜で産卵することがあるそうですよ)
論文のエッセンスをイラストに
 <
<きのしたさんが先ごろ出された本『生き物「なんで?」行動ノート』を拝見させていただきました。論文で発表されているような内容が元ネタになっているんですね。本には昆虫、魚、鳥、哺乳類など生き物全般の、その行動の理由などがイラストと手書きの文字でとても分かりやすく載っていましたけれども、これだけ多くのネタを集めるのは、すごく大変だったんじゃないですか?
「全部で52個プラス、細々としたコラムが8〜9個くらいあるんですけど、ネタ集めに関しては、学会に参加してすごく面白いと思った話とか、あるいは専門書を読んだりとか、あとは学術雑誌のサイトがあるので、そういったものを行ったり来たりしている間に自然に集まったのかなという気がします(笑)」
●そもそもこの本を出そうと思ったきっかけは、何かあったんですか?
「生き物の不思議とか面白さを取り上げた本は結構あるんですけど、その生き物の不思議がどうやって明らかにされていくのかっていう、そのプロセスに注目した本があまりないなっていうか、多分当時ほとんどなかったと思うんです。
そういったものを解説するのに、学術論文の流れというのが非常にいいのかなと思っていて、それらのエッセンスだけを抽出して、全部イラストにしてみたら、もしかしたら子供から大人まで楽しめるんじゃないかなっていうので、思い切ってやってみた感じです」
ザトウクジラの「トラップ・フィーディング」!?
※それでは、きのしたさんの本『生きもの「なんで?」行動ノート』から、面白い生き物の生態を、いくつか解説していただきましょう。
まずは「あせった魚をだますザトウクジラ 」、これはザトウクジラのフィーディング、つまり、どうやって獲物をとって食事をするか、なんですが・・・説明していただけますか?
「ザトウクジラは世界中にいるクジラなんですけど、場所によって、いろんな餌の採り方をします。有名なのが『バブルネット・フィーディング』です。泡を出してカーテンみたいなものを作って、そこに小魚を閉じ込めて、下からまるのみして食べる、そういった食べ方が有名なんですね。
それ以外にも海底を(あごで)ねこそぎスコップみたいな感じで掘り出して、海底の生き物を食べたりとか、魚が集まっているところに突っ込んで食べたりとか、結構多彩なことをしているんですけど、実はアクティヴに動かないやり方があって・・・(笑)。
口をぼーっと開けているだけで、魚が口の中にピュンピュン入っていくみたいな・・・『トラップ・フィーディング』って言うんですけど、そういうフィーディング方法が報告されつつあります。
口を開けると何が起こっているかっていうと・・・そのトラップ・フィーリングをしている場所は、海鳥に追い込まれているような魚たちが多いんです。クジラが影になってやることによって、ここだったら海鳥から襲われない避難所だと思って、魚が勝手に(開けている口に)入ってしまう、それをクジラが食べる、そういったトラップ・フィーディングというやり方が報告されていて、面白いなと思って取り上げました」

●クジラと言えば、ヒソヒソ声で話すミナミセミクジラも本に載っていましたよね。
「そうですね。クジラは沖合にいるだけじゃなくて、割と浅瀬のほうにも寄ってくるんですね。親子で結構コミュニケーションをとっているのが、ミナミセミクジラと呼ばれるクジラなんです。コミュニケーションをとっているのは、それはそれでいいんですけど、その海域にはシャチもいて、シャチは天敵なんですよね。
見つかると本当にやばいんで、声をできるだけ、親子間ぐらいで聞こえる範囲の、すごくヒソヒソした声で、シャチにギリギリ見つからないぐらいのコミュニケーションの取り方をしているのが、面白いなと思って紹介しました」
●あんなに大きなクジラが小さく囁いているんですね。
「水中はすごく音が通ってしまうので、本当に小っちゃい声だと思います」
フルーティーな匂いでメスを誘惑!?
※きのしたさんの本『生きもの「なんで?」行動ノート』から、続いては「ワオキツネザルの魅惑の体臭」。生き物にとって、匂いは大事なんですよね。
「そうですね。ワオキツネザルが面白い動きをしているのは、結構前から言われていたんですけど、尻尾を手でこすって何をしているんだろう? っていうのをしっかりと調べた研究がありました。
手の付け根にフローラル・フルーティーの香りがする、臭腺(しゅうせん)みたいな匂いが出る腺があるんですけど、そこから匂いを出して尻尾にこすりつけて、尻尾をブンブン振ることによって、メスにアピールしているというような・・・香水をふるような感じですかね、人間で言うと・・・」
●人間の男性もアピールするためにコロンをつけたりとかしますけど、まさにそんなような感じですよね?
「はい、同じ感じだと思います。(フローラル・フルーティーは)結構いい匂いなのかな? 私も実際嗅いだことはないんですけど・・・」

●へぇ〜、嗅いでみたいですね。ほかにも本にメスのライオンの狩りの話が載っていて、得意なポジションで集団ハンティングをするんですよね?
「これも非常に面白いというか、サッカーとかラグビーのポジションみたいなのが、実はメスのライオンが狩りをするときにはあって、センターとか左右のウイングに分かれているってことが報告されている論文なんです。
獲物を追い立てる時にみんなが散りじりになるんじゃなくて、それぞれに馴染みのポジションがあって、そこにきちっとハマった時には、狩りの成功率がすごく高まることが分かったっていう研究です」
●本当にスポーツみたいですね。ポジショニングされているんですね!
「本当にそうですね。かっこいいです」
●あと本には、ぐるぐる回る海洋動物の謎というのもありましたね。海の生き物は観察が難しいと思うんですけど、どんな生き物がぐるぐる回ることがわかったんですか?
「ぐるぐる回っているのは本当に理由は謎なんです。機械みたいにぐるぐる回っている動物としては、アオウミガメ、キングペンギン、ナンキョクオットセイ、アカボウクジラ、ジンベイザメ、イタチザメっていうふうに、魚から哺乳類までバラバラで、いろいろと考察はされているんですけど、本当に謎の行動っていうことで紹介しています」
●なんで回るんですか?
「もう本当にこれは、なんで? っていうのはめちゃくちゃ難しいんですけど、(ぐるぐる回るのは)潜水艇とちょっと似ているかなと思っています。潜水艇が深海に潜っていく時に、どっちが北でどっちが南か、方位を定める時にぐるぐる回りながら補正をしていくという動きをします。
結構それに似ていて、特にアオミガメは生まれた砂浜に卵を産みに行くんですけど、方向転換が必要な要所要所でぐるぐる回っていたので、もしかしたら方向を定めるようなナビゲーションに使っているのではないかと考えているんですね。でも明らかにするのはこれからで、分からないっていうのが今の段階です」
研究とは、研究者とは
※生き物の世界は謎だらけ、だと思うんですけど、だからこそ、面白いんでしょうね。
「そうですね。例えば、夕方になると公園とかにコウモリが飛んでいると思うんですけど、一晩のうちに1000匹近く蚊を食べていて、すごい頻度だと思うんですね。そんな身のまわりで繰り広げられている生き物のドラマ、そういった行動が分かるようになってくると、散歩するだけでも非常に幸せな気持ちになるというか・・・。
あとは目の前の生き物はいろんな進化の過程があって、今ちょうどここにいるっていうわけなんですけど、例えばこれが少しでも過去のシナリオが違っていたら、全く別の状況になっていたことを妄想するだけでも、すごく楽しいし奇跡的だなと思ったりもします」
●今、研究者としていちばん明らかにしたい謎はありますか?
「動物たちは環境によって、体の中の状況をすごく柔軟に変えることが、クジラやウミガメ、そういったものを通してわかってきました。 例えば餌の少ない環境にいると、人間でもそうなんですけど、飢餓状態みたいになって、体を維持するためのカロリー量とかエネルギー量がどんどん少なくなって、調節されていくことが知られています。
こんなふうに環境変動に対して、動物がどんなふうに体の中の状況を変えていって、地球温暖化や気候変動とかに対応できるのか、対応しているのか、そういうことを今後明らかにしていきたいなと思っています」
●では、最後にこの本『生き物「なんで?」行動ノート』を通して、どのようなことを伝えたいですか?
「この本では、おっしゃっていただいた通り、生き物の行動の面白い謎をたくさん紹介しているんですけど、それに加えて研究とは何かを本の中でアピールしています。
研究者は最近、メディアとかにも出演されることが多いと思うんですけど、その研究者たちの普段の研究のプロセスとか、あとは研究者がどういう生活をしているのとか、どうやって研究者になるのとか、そういったものを良くも悪くも知ってほしいなと思って、本の中にコラムをたくさん入れています。
例えば、お子さんが突然、”僕は生き物の研究者になりたい! 目指したい!”って言ったら、多分困惑される親御さんは多いと思うんですけど、そういった親御さんにも見ていただいて、あっ、こういうものなんだっていう現状を知ってもらいたいっていう、そういうメッセージがあります」

INFORMATION
この本では、小さなアリから大きなクジラまで、いろいろな生き物のユニークな行動や不思議な生態が、可愛いイラストと手書きの文字で紹介されています。とてもわかりやすいし、楽しめますよ。おすすめです!
SBクリエイティブから絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎SBクリエイティブHP:https://www.sbcr.jp/product/4815612382/
きのしたさんのイラストレーターとしての活動などについては、オフィシャルサイトを見てくださいね。
◎きのしたちひろさんHP:https://lunlundi.com
2023/4/9 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、海洋冒険家の「白石康次郎」さんです。
世界一過酷なヨットレースと言われている「ヴァンデ・グローブ」は、第1回大会は1989年から1990年にかけて行なわれ、その後、4年に一回開催されています。スタートとゴールはフランスのレ・サーブル・ドロンヌという海辺の町。コースは南半球を一周、およそ4万8千キロ! 速いヨットで80日間ほどで走破!
世界一過酷と言われる由縁は、単独・無寄港・無補給! つまり、たったひとりで、どこの港にも寄らず、補給も受けないという条件のもとで実施されるからなんです。
そんなヨットレースの前回大会に参戦し、見事、アジア人として初めて完走したのが、海洋冒険家の白石康次郎さん。白石さんは、これまでにヨットによる世界一周をなんと4回も成し遂げている、日本が世界に誇るトップセーラーなんです。
そんな白石さんが来年、再び「DMG MORIグローバル・ワン」のスキッパーとして「ヴァンデ・グローブ」に挑戦します。ということで、きょうは「白石」さんをお迎えし、再挑戦する熱い思いに迫ります。
☆写真協力:DMG MORI SAILING TEAM

水平線の向こうに
●今週のゲストは海洋冒険家、白石康次郎さんです。初めまして、小尾渚沙と申します。3年ほど前からこの番組「ザ・フリントストーン」を担当しております。よろしくお願いいたします。
最初から私事で恐縮なんですけれども、白石さんはTUBEの前田亘輝さんとも親しいんですよね?
「そうなんですよ。兄貴と呼ばせていただいて、何曲かヨットの歌を作っていただいているんですよ」
●実は私もゆかりがあって、私が生まれた当時、父がレコード会社に勤めていて、担当していたのがTUBEだったんですね。
「あ、そうなんですか!?」
●そうなんです! で、女の子が生まれたら「渚沙」にしようって、前田さんが名付けてくださったんです。
「そうなの! ソニー(ミュージック)の!?」
●そうです、そうです!
「そうでしたか! それで渚沙なんですね。名付け親なんですね(笑)。それは素晴らしいね!」
●男の子だったら、忠犬ハチ公の「忠」に武士の「武」で、「忠武(ちゅうぶ)」だったんです(笑)。
「へぇ〜、女の子でよかったんじゃないんでしょうかね〜(苦笑)」
●(女の子で)よかったです(苦笑)
「今度、前田さんに会った時にちょっと言おうかな」
●ぜひぜひ! 白石さんにこの番組に初めてご出演いただいたのが、1994年の10月だとスタッフから聞いているんですけれども、もう30年近くこの番組にお付き合いいただいているっていうことですよね。
「いや〜、こちらこそ! 最初に世界一周したあとですね。つっぱっている頃だったので、本当にお声がけいただいて、ザ・フリントストーンさんとは、なんていうかな、成功も失敗も共に歩んできましたね」
●嬉しいです。94年に世界一周の最年少記録を樹立されたんですよね。
「そう、最初の世界一周でしたね」
●この世界一周は、レースというわけではないんですよね?
「そうです。僕、世界一周したいっていうのは、子供の頃からの夢で、やるんだったらひとりで、つっぱっている頃なんでね(笑)。世界一周してやろうということで、やったのが最初でしたね。で、2回失敗してね。もう、コテンパンにやられて、3回目でやっと成功してね」
●何度も聞かれていると思うんですけど、そもそもどうしてひとりで、ヨットで世界一周しようって思われたんですか?
「これは好奇心です。好奇心です、はっきり言って。僕、子供の頃、鎌倉で育ったんですよ。海岸に立った時に、みんな海を見て何を思うんだろうなって・・・。
僕は水平線の彼方に思いを馳せて、当時、外国旅行なんかまだまだできない時代で、とにかく好奇心だね! この水平線の向こうには、何があるんだろうっていうのが動機で、飛行機とかいろんな方法あるんだろうけど、僕は船で世界一周したい! というのが夢だったんです」

船が飛ぶ!?
●今年の1月には、来年の「ヴァンデ・グローブ」出場と、その先のチームの目標について発表されたということで、来年も「ヴァンデ・グローブ」に「DMG MORIグローバル・ワン」のスキッパーとして出場されるんですよね。どんなお気持ちですか?
「今回5回目のチャレンジで、チームを立ち上げて2回目になるんですけれども、前回の2020年はセイルを破ってしまって、うまいこと走れなかったので、今回はもうちょっとうまく走りたいかな。船ともコミュニケーションが取れてきたので、もう少し前回よりうまく走れるんではないかと思っていますね」
●前回2020年は、白石さんにとっては初めての新艇で、しかもオーダーメイドだったんですよね?
「そうです、そうです。フォイル艇で、今は船が飛ぶんですよ、半分」
●船が飛ぶ!?
「水中翼船みたいに、風の力で」
●羽があるってことですか?
「そうなんですよ、羽があるんですよ。今の船は特殊で、本当にレース艇ですね。それに初めて乗りました。僕にとっては初めての新艇だったのね。それで出場して完走して、次はそれを改造して、さらにもうちょっと上の順位で回れればなと思っていますね。
さらに2028年はまた新しい船を作ると・・・僕らのチームは長期計画なので、それに向かって一歩一歩前進していきたいと思っていますね」
●すごいですね〜、夢がありますよね。羽が生えている船は具体的にどれぐらいの大きさなんですか?
「船の長さは18メートル60フィート、大きいです。マストの高さが28メートルだから(建物でいうと)7階建てぐらい。一般にみなさんが思うヨットよりも大きいですね。そのヨットをひとりで、世界一周すると非常にスピードも出ます」
●もうすでに、共に荒波を乗り越えてきたわけですよね。
「そうです、そうです」
●もちろん愛着もすごくありますよね?
「そうですね! いい船ですよ「グローバル・ワン」は」

自然に敬意を
白石さんが所属する「DMG MORIセーリング・チーム」はスキッパーが女性を含めて5人、ほかにエンジニアなどのスタッフが10数名、総勢20人ほどの国際的なチームだそうです。
ベースはフランスのロリアンという港町にあり、そのロリアンには、世界中のトップチームが集結しているそうです。白石さんがおっしゃるには、フランスはヨットが盛んでフランスの国技といってもいいそうですよ。
●ヨットや海から学ぶことも多いんじゃないですか?
「多いです。今SDGsで、持続可能なっていうことをやっていますよね。あれ何かって言ったら、やっぱり人間は自然との関わりなくして生きられないんだよね。簡単にいうと海、山、川ってあるでしょ。これは人間が創り出したものじゃないでしょ、海も山も川もね。だからそこにやっぱり敬意を持っていないと、人間はどんどん苦しくなってくるんだよね。
それがちょうど今、変革期で、僕なんかの時代は物がなくて、作ろう作ろうという時代だったんだけど、これからはもっと地球とコミュニケーションを取って、我々は地球の外では生きられないので、もう少し地球と共にという考え方がやっと芽生えてきたんじゃないでしょうかね。江戸時代は、そういうのはあったんですよ」
●江戸時代!?
「そうそう、そのものがSDGsだったから、持続可能なものだったんだけど、そうだな〜、産業革命があって石油が掘り出されて、それからちょっと変わってきたかな。今振り返ってみると、ゴミは多いよねとか、僕なんかの時代そうだったのね、公害時代だから・・・。
でも今やっぱり綺麗のほうがいいよね、多少不便でも。おいしい空気の方がいいよねとか、綺麗な海の方がいいよね、ということで、多分どうでしょうかね・・・みなさんの時代の方が意識は高いんじゃないかな。みなさん今若い人たちは、ファッションもすごくシンプルでしょ」
●そうですね。
「そうそう、ミニマリストみたいに。何も物のない時代で育った人は、物があって幸せになんだよ。で、みなさんみたいに物がある時代に育った人は、別に物があっても驚かないんだよね」
●当たり前だったわけですよね。
「それより大人しく綺麗に生きようっていう、ちょうど今、時代の変わり目、風が変わってきたね。いいことだと思いますよ」
世界一周は日常!?
●「ヴァンデ・グローブ」は、ひとりでどこにも寄らずに長時間レースをしているわけじゃないですか。その間に寂しいなとか、感じたことはないですか?
「僕を見て寂しいと思いますか?」
●まったく思わないです(笑)
「思わないですよね! このまんまですね!」
●でもずっとおひとりなわけじゃないですか、夜も。
「ひとりは面白いよ! あの満天な星を独り占めです、最高だねぇ〜。だから海にたったひとり、地球という最大の星で、地球の最小単位のひとりでいるわけよ。これが素晴らしいわけです」
●ほんとに独り占めですね。
「独り占めでしょ! でね、連絡はなかなかできないので、今、都会でいちばん難しいことができるんだよ。自分と会話、自分との向き合い方が長いね」
●どんなこと考えるんですか?
「何も考えてないです(笑)。早く帰りたいな、ぐらいしか考えたことないんだけど・・・そうそうだから、考えない時間を作るっていうのは、いいね」
●贅沢かもしれませんね。
「今はもう(みなさん)考えすぎ!」
●考えすぎていますね、みんな確かに。
「情報過多、外からの情報が多いんだよね、今の人はひとりでいると。だからみなさんは情報処理が得意なんだよね。携帯電話もなんでもそうでしょ。僕の場合はうちから外へ出す情報発信が多いんですよ。そこがヨットでひとりの魅力かな。寂しいことは何にもないです」
●そうなんですね。でも、聞くところによると、随分昔、レース中に海の上から奥様に何度か電話されたそうですね。
「いやいやいや(電話が)かかってくるのよ!」
●あれぇ〜(笑)
「去年は1回だけかかってきました。僕からかけることほとんどないんだよ。1回なんかね、電話かかってきたわけ。何? って聞いたら”銀行のパスワード教えて”。それから前回の大会は”あんた車検どうすんの?”っていうのが1回かかってきたね。
その前の大会は”引っ越ししたから”って(世界一周の間に)引っ越しされました! そういう電話が大体、世界一周で1回かかってくるんですよ。来年はなんだろうね(笑)」
●面白い〜(笑)。来年「ヴァンデ・グローブ」に挑戦することを知って、奥様はなんとおっしゃっていたんですか?
「え、何も・・・うちら家族、娘もいるんだけど、娘が生まれてからもう3回世界一周しているかな。だから世界一周が日常なんですね」
●わぁ〜かっこいいですね。すごいことですよね。
「お父さんは世界一周して帰ってくる人なので・・・」
●ずっと家にいるのは、もう考えられないっていうことなんですかね。
「はい、だから世界一周して帰ってきても(娘は)携帯電話を見ながら”おかえり!”、それだけですね、以上ですね」
(編集部注:白石さんのご家庭では、ヨットレースの話は出ないそうですよ。きっとそれは奥様の心遣いだと思いますが、白石さんがヨットレースに夢中になれるのは、やはりご家族の存在が大きいのではないでしょうか。今後、できるなら、奥様やお嬢さんにもお話をうかがってみたいですね)
世界一周は「確かめること」
※白石さんは、世界一周を果たしたあとに、何を学びましたか?と、よく聞かれるそうです。そんなとき、白石さんはこう答えるそうです。
「確かめたんですと、これでいいんだと。世界一周は確かめることなんです、学ぶことではないんですね。だから人生はよく学びだっていう人がいるんだけど、僕はちょっと違った考え方で、学びは知らないことを知ることじゃない? 僕は自分は何者であるか、確かめるのが人生ですよ! って言っているんですよ。
(それぞれ)すべてを持っていて、すべてがあるんだよね。それを確かめることで、学ぶことではないんですよ。自分以外にはなれないってことを覚えといて、自分らしくないと苦しいんです」
●人と比べてしまったりとか・・・。
「そう、そうすると孤独を感じるんです。だから海の上でも(僕が)孤独を感じないのは合っているんだよね。合っているんですよ、それでいいんですよ」
●やっぱり夢の力っていうのも大きいですよね?
「大きい大きい。だから苦しいことをやっているわけではないんです。苦しいことをやった先に何があるかっていうと、もっと苦しむんだよ。みんな勘違いしちゃダメよ。苦しさの先に楽があるんじゃないんだよ。楽しさの先に楽があるんだよ。
だから間違って苦しんでいる人はすごく多くて、苦しいでしょ。何を言っているかって、それ違いますよってサインなんだよ、苦しいってことは。違っているのに、さらに頑張って苦しくなっちゃうんだよね」
●白石さんは厳しいレース中も、心身ともに楽しいってことですか?
「そうそう、要するに(ひとりで世界一周は)大変ですよ。たったひとりで眠る時間もないし寒いしね。でもやりがいがあるんだよね。で(自分に)合っているから乗り越えられるんで、これは人に頼まれたわけではないんですよ」
●やりたいと思っているからってことですよね。
「人に頼まれたら、まず乗り越えられないです、苦しくて。たったひとりで海が楽しいと思う人と、孤独って思う人がいるんだよね。これ解釈なの。たったひとりでも人によって違ってくるんだよ。ここがポイントなんだよね。あんまり無理しないで自分らしくあるってことかな」
●26歳で初めて世界一周を果たした白石さんは、今でもヨットや海に対する思いはまったく変わらないですか?
「変わらないですね。まだ幼稚園を卒園してないですよ。何も変わらないですね。おもちゃの大きさだけです、変わったのは。おもちゃがどんどん大きくなっただけで、それだけですね」
●では、最後に来年も世界一過酷なヨットレースと言われる「ヴァンデ・グローブ」に出場する白石さんにとって、最高のレースとはどんなレースでしょうか?
「前回は、結構トラブルが多かったので、なんていうかな・・・気持ちよく走りたいね。気持ちよく走るのが最高のレースじゃないかな。みんな楽しく、思いっきり「ヴァンデ・グローブ」を楽しみたいなと思いますね。次は何が待っているんだろうね。
僕がトラブれば、トラブルほど、まわりが喜ぶんだ、またこれが! 喜ばせたくないね! つまんないって言わせたいの! 僕の夢はまわりに”白石さん、つまんなくなりましたね!”って言わせたいね(笑)」
●またお話を聞かせてください。期待しています!
(編集部注:今後、白石さんは予選会のようなレースに出場しながら、ヨットを調整、来年11月10日スタート予定の「ヴァンデ・グローブ」に備えることになっています。今後の動向に目が離せません)
INFORMATION
白石さんが所属する「DMG MORIセーリング・チーム」ではセーリング・アカデミーを開設、外洋セーリング界で活躍できる人材発掘と育成を目的に若手の登竜門といわれている大西洋横断レース「ミニトランザット2027」への出場・完走を目指す研修生を募集しています。
募集人員は4名、応募の締め切りは4月30日。年齢、性別は問わないとのことですので、ヨットレースにチャレンジしたいというかた、ぜひご応募ください。
◎「DMG MORIセーリング・チーム」HP:
https://en.dmgmori.com/company/dmg-mori-sailing-team-jp
白石さんの最新情報含め、詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
◎白石康次郎オフィシャルサイト:
https://kojiro.jp
2023/4/2 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、冒険ライダー、そしてNPO法人「地球元気村」の大村長「風間深志」さんです。
風間さんは1950年生まれ、山梨市出身。1982年に日本人として初めて「パリ・ダカールラリー」に参戦、さらに、バイクによる史上初の北極点と南極点に到達など、前人未到の大冒険に挑戦され、輝かしい記録を残されています。
そんな風間さんが1988年に仲間と設立したのが「地球元気村」で「人と自然が調和している社会」の実現を目指して作られたプロジェクトです。
きょうは、人も地球も元気になる活動の最新情報などうかがいます。

番組タイトルに込めた願い
風間さんにお話をうかがう前に、新年度ということで、改めて番組タイトルについてご説明しておきましょうね。
「フリントストーン」は「火打石」という意味がありますが、実は1960年代に日本のテレビでも放映されたアメリカのアニメーション「原始家族フリントストーン」にもあやかっています。原始時代は人間が自然を壊さず、その恵みをいただきながら、ともに生きていた時代、ということで、今も、そしてこれからも、そうあって欲しい、という願いが込められています。
そんな番組「ザ・フリントストーン」のシンボルが風間深志さんなんです。
それでは風間さんにお話をうかがっていきましょう。
地球元気村の思い
●今週のゲストはこの番組の記念すべき第1回目のゲスト、冒険ライダーそして地球元気村の大村長、風間深志さんです。よろしくお願いいたします。
「はい! よろしくお願いいたします。大村長っていつも言ってくれるんだ、毎年ね。何が大村長かなと思うんだけど、大村長の風間です!(笑)よろしくお願いいたします」
●こちらこそ、お願いいたします。この番組「ザ・フリントストーン 」がこの4月から32年目に入ったんですけれども、風間さんが仲間とともに作ったNPO法人「地球元気村」は今年で35年目になるんですよね?
「はい、もう35年、あっという間ですね」
●あっという間ですか?
「35年前と今は変わんないから面白いね。自然っていうものに対してのテーマ、みんなやっぱり自然が好きだね。
昔は自然を好きになってくれっていうメッセージを、広く訴えていこうってことで始まったけど、今は空前のキャンプブームだよね。なんかもうアウトドアの洋服とか、そういったものを普通に街でも着るのが当たり前になったしさ。そういう意味ではすごく普及したけど、人は自然が常に好きだなっていう感じは、今も昔も変わんないなと思って見ています」
●風間さんには、毎年4月の第1週目にご出演いただいているんですけれども、30年を超える長いお付き合いということで、本当にありがとうございます。
「昔ね、4月1日に、むちゃくちゃホラ話をしたのよ(笑)っていうのが思い出。俺は太平洋でトビウオになるとか言っちゃってさ(笑)。トビウオになってどうするんですか? アメリカまでトビウオで行くのさ!(笑)みたいな、そんな話をよくしたよね(笑)。今は通用しないんだよ、そんな話。いいよ!(きょうも)嘘話でも」
●ダメです、ダメです(笑)
「ダメですか。きょうはちょっとリアリティを持っていくんですね」
●お願いします。改めて地球元気村のテーマを教えてください。
「そういう意味では、昔より今のほうが馴染んだかも知れないね。要するにもともと足もとにある自然と、もうちょっと仲良くしながら、会話をしながら、文明文化を進めていきましょうよっていうメッセージなのね。
(「地球元気村」を設立した)当時1988年、思いっきり工業化とか、思いっきり生産力を高めていくっていう、国とか世界中はそっちの方向に必死になっていた時代で、時はバブルという時だったんだよね。
そんな時にやっぱり足もとをもうちょっと見て、そして人間は自然に触れながら、子供を育てたりとか、やっぱり伝統文化っていうものをもうちょっとちゃんと継承しながら、人間らしくっていうと変だけど、何が人間らしくだよっていう感じになるけどね。やっぱり人間には自然は不可欠だし、自然との調和社会を目指していきましょうっていうわけで・・・。
折に触れて自然との触れ合いで・・・アウトドアのことが最初はちょっと多くて、なんだか俺はアウトドアの伝道師みたいだなって・・・。
別にアウトドアに限ったことはなくて、村祭りにしても郷土芸能にしても、そういった日本の古き良き文化を、みなさんに伝えながらいきたいなと。でも結果、みなさんが好きだったのは、自転車に乗ったり、川で釣りしたりとか、そういうのが好きだから、アウトドアをメニューにしながら、自然と触れ合うきっかけをここまで作ってきました」
(編集部注:「地球元気村」といっても特定の場所があるわけではなく、豊かな自然が残る市町村と連携するなどして、自然体験型のイベントを開催してきたそうです。風間さんは「地球元気村」をひとつの「理想郷」と表現されていました)
地球元気村ファーム「天空のはたけ」
●地球元気村のホームページや会報誌を拝見すると、ここ数年、風間さんは農業に視線を向けていらっしゃるのかなって感じるんですが、どうですか?
「あ、見てくれた? ありがとうございます。まあそうだな・・・地球元気村の真髄は結局(シンボルマークの)地球元気村の焚き火の炎みたいなのがあるでしょ。あれはとりあえず焚き火の炎なんだけど、実は命の炎なんだよと、命のときめきを表していまして、それは元気の証拠でもあるよね。
人間が醸し出す、元気や喜びや幸せは、どっから来てるかって、やっぱり自然から来ていて、足もとの土をいじって、そこに作物を育てて、それを食して、人間は命から命をつないでいくっていう、その循環がうまく、滞りなくスムーズにいくことが健康のひとつの循環ね。
みなさん(お店で)買ってくれば(手に入る)ホウレン草やネギを自分で作って、そしてそれは土から生まれて、土の元気がネギの葉っぱに伝わって、その葉っぱを食べることによって、僕らに元気が伝わってくるっていう循環型ね。そういったことを意識してもらうために農業をやっているんだけどね。
もうちょっと言えば、そこで見てもらいたいのは、命なんですよね。命は、スプーン一杯の土の中にも70何億の微生物がいて、生命なんだよね。その生命そのものが、強い生命力を持っていることが、我々の元気であるっていうことを考えようよということだよね。分かり切っているけど、なかなかこれは忘れちゃうんだよね」
●そうですね。山梨市に地球元気村ファーム「天空のはたけ」というものがありますよね? それはどんな畑なんですか?
「それはね、天空のはたけなんですよ!(笑)」
●あははは〜(笑)。広さはどれくらいあるんですか?
「えっとね、どんぐらいあるかな・・・3000坪ぐらいあるかな。畑が46区画あって、標高が700メートルぐらいの、ちょっと高いところにあるのね。そこから見下ろすと時々、甲府盆地がたなびく雲の下に見えたりとか、正面には富士山がどんと五合目以降、顔を出して、おーい、こんにちは! みたいな感じで挨拶ができるわけ。だからそこを『天空のはたけ』って名付けたんですよ。
みなさんすごく喜んでくれて、そこが嫌だっていう人は誰もいない、大人も子供を喜んで、その大空間の中で、心も体も羽を広げるっていう気分なんだよね」
(編集部注:お話に出てきた「地球元気村」のトレードマークは焚き火の炎で、ロゴも含めて制作されたのは、段ボール・アートで知られるアーティスト、現在は東京芸術大学の学長でいらっしゃる「日比野克彦」さんなんです。どんなマークとロゴなのか、ぜひ「地球元気村」のホームページを見ていただければと思います)
美味しいは農業から

※山梨市にある地球元気村ファーム「天空のはたけ」では、ジャガイモやサツマイモなどを育てているそうです。去年は、オリーブの木も植えたそうですよ。ほかにも村民のみなさんと味噌作りを行なったり、秋には収穫祭を開催し、大地の恵みをわかちあっているということですが・・・天空のはたけで作物を育てたり、収穫したりする作業からどんなことを感じますか?
「畑に来るってことは、土をいじるってことは、命とちょっと触れ合うってことになるんだけど・・・そうだね〜“美味しい”を感じるね! いつも畑に行くとね、昼飯が美味しいんだよね。それに入れ込む大根にしても、人参にしても作るからね。だから特に美味しい。なんだろ・・・農業から始まんのかな、美味しいは! 本当に汗をかいて、美味しくて、作業をして、語りをして、大人も子供も跳ね回ると、この世の楽園ですね!」
Jomonさんがやってきた!
※「地球元気村」では、縄文大工「雨宮国広(あめみや・くにひろ)」さんのプロジェクトを応援されています。以前、この番組にも出てくださった雨宮さんは、縄文時代の人たちがそうであったように、石斧(いしおの)だけで木を倒し、加工する特別な大工さんなんです。
そんな雨宮さんが進めているのが「Jomonさんがやってきた!」というプロジェクトなんですが、どんなプロジェクトなのか教えてください。
「あのね、もう元気村と同じね。縄文時代は1万数千年続いたんだよね。それだけ長く続いたのは、平和で安定した時代だったんだろうと。その人たちのライフスタイルが何かっていうと、自然と密接につながって、自然の摂理とか原理原則みたいなところから、はみ出していないライフスタイルをやってきたから、長く続いたわけ、無理がないからね。
人間は物を作るから、そういう時に手に持ったものは、鉄のアックスじゃなくて石の刃に枝をつけて、それで木を倒したりね。言ってみれば、石斧(いしおの)の文化だね。それを通じて人間本来の、縄文時代にやっていた人間の生き方、それから生き方による考え方、方向性をもう1回考えてみましょうよっていうメッセージなんだよね。
雨宮さんが何をやっているかっていうと・・・例えば、鉄斧(てつおの)は石斧よりか9倍とか10倍の威力を持ったわけだ。つまり作業が早くはかどるわけ。その分、手返しっていうか、早い分、人間はそれに追いつくために無理をするんだよね。
人間には人間のサイクルがあるよね。つまり人間にはひとつの一定した心拍があり、生きてくための呼吸は1分間に何回しているとか・・・それを早い機械を使うと、例えばチェーンソーを使うと(石斧の)200倍とか伐っちゃうわけ。それに合わせようとするから、せせこましくなるわけだね。
作業効率とか、きょう中にこれを作ろうってなってくると、本来の人間の動きから飛び出したことになって、それでいいのかってことをやっぱり雨宮さんはすごく感じているんですよ。
彼は今、日本縦断をやっているんですね。丸木舟を、北海道から沖縄まで、毎週どっかの都道府県に持って行って、子供たちと一緒に(石斧で)コンコンやって深く掘り下げているんですよ。僕も今まで3回ぐらい行ったけどね。コンコンやっていくと、なんかいいんですよね」
全国ネットワーク「テラなび」
※「地球元気村」の会報誌に全国ネットワーク「テラなび」の記事が載っていました。この「テラなび」はどんなネットワークなんですか?
「テラは地球、なびはナビゲーション、地球をナビゲートしていこうっていう、そのためにはどういう考え方で、どういう見地が必要なのかを、みんなで考えようっていうひとつの委員会なんですよ。
それを今まで地球元気村をやった全国の市町村の元首長さんとか、自然学校を専門にやっている学校の校長先生とか、あるいは大学のそういうことを専門に研究している人とか、そういう人たちに集まってもらって委員会を作ったんですよ。そこからもう1回出直そうかっていうための、準備のためのシンクタンクも去年作りまして、真剣にやっていこうと思っています。
ずっと考えているんですよ、実はここ10年ぐらい、次の一手はなんだろうと・・・以前キャンプはむちゃくちゃ流行ったし、今も流行っているからね。今度、次の一手はなんだろうなって考えていますね。
しかし、SDGsって言葉がむちゃくちゃ流行っているよね。それでなんか答えが出ましたかってこと・・・。それはひとつの一環で、取り組みのひとつですっていうことであって・・・いずれにしても物作りだったり、会社のひとつの事業やひとつの指針だったりするよね。その言葉を使うことによって、みんなそれで気が済んでいる部分もあるけど、実際に生活を少し変えていくってことは、やっぱり容易なことじゃないよね。
そこも含めて、変えていけるようなインパクトを与えられたらいいなっていうふうに、地球元気村はもう30何年考えているからさ。パイオニアとして見本を見せるような活動とか、メッセージが発信できればいいなって思っています」
●最後に、今後、風間さんとしては、どんなことに挑戦していきたいと考えていらっしゃいますか?
「そうですね・・・僕もいい歳になったんですけど、歳を忘れながら、地球元気村を本当にブレイクさせていきたいなと思っています。 次の世代につなげていくような、何か伝えて手渡してくような、何かを手にしたいなと思っています。
一方、僕個人とすれば、何年も前から言っていますけど、ダカール・ラリー、これに出るために、今、国際ライセンスを取っていますね。去年は国内Bを取ったんだけど、今年は国際ライセンスを、4輪ですよ、今取っています。
2026年あたりに行ってみようかなと思っていますけどね。そうしたら何歳だっていうと、やばいんですけどね(笑)。そんなことを忘れて、いろんなことをやるのがいいんですよね。歳を考えているうちは、まだダメだね」
●また、来年お話をうかがえるのを楽しみにしています。
「まあ、生きていたら(笑)お会いしたいと思います」
●ありがとうございました!
「はい、どうも、ありがとうございました!」

INFORMATION
「地球元気村」
お話に出てきた山梨市の「天空のはたけ」では5月中旬くらいにサツマイモの植え付けや、梅の畑で小梅の収穫を行なう予定です。また、「地球元気村」では、山梨県山中湖村の村営山中湖キャンプ場を運営しています。時々鹿が出てくるような森の中のキャンプ場だそうですよ。どなたでもご利用になれます。
そして「地球元気村」では随時村民を募集中です。プレミアム村民は会費が年間10,000円、村民になると年4回、会報誌「地球元気村」が届くほか、イベントの参加費が割引になるなどの特典がありますよ。
詳しくは「地球元気村」のオフィシャルサイトをご覧ください。
◎https://chikyugenkimura.jp
縄文大工の「雨宮国広」さんのプロジェクト「Jomonさんがやってきた!」もぜひ応援してくださいね。
◎https://jomonsan.com