2022/5/6 UP!
今日は、なんと千葉大学の教授と学生がそのクラフトビールを作ってしまったというお話をご紹介します。1994年の酒税法改正により、ビールの製造免許取得に必要な最低製造量が年間2000キロリットルから60キロリットルに大きく引き下げられたことにより、全国各地で、少量生産の地元に根付いた個性的なビールが作られるようになりました。千葉にもブルワリーがたくさんあり、それぞれの地域の特産品を 生かして個性的でおいしいビールが作られています。
この大学発のビールプロジェクトの中心人物である千葉大学の教授、萩原学さんに、作り始めたきっかけを教えていただきました。

萩原教授
専門は数学情報数理学という分野です。単純に私はビールが好きだっていうのがあります。学会とかで世界中を旅すると、世界中のクラフトビールを飲めて、それを飲むたびに美味しいなあと思ってました。で、周りの研究者の人と話していると、非常にビールに詳しい人も多くて、よりビールに興味を持っていました。理系の人で、ビールを作る人が多いということを知って、もしかしたら、自分も何か作れるチャンスがあるんじゃないかなというふうに思っていました。一番大きかったのは千葉市と栃木県の足利市というところが、百周年を同じ日に迎える。 ってことを知った時ですね。私が千葉市で仕事をしていて、そして生まれたのが、栃木県の足利市というところで、何かその運命的なところを感じてお祝いをしたい。お祝い事だったら何かみんなでお酒を飲んで楽しく過ごすというのがいいんじゃないかと思った。だったらもう百周年記念ビールを作ってみたらいいんじゃないかっていう風に考えました。
その醸造を行ったのは幕張にある幕張ブルワリー株式会社。限定クラフトビール「あしたのみち」(足楽味千)を千葉大学、潮風ブルーラボ合同会社と共同で開発・醸造しまして、2021年6月に約2,000本の数量限定で販売。あっという間に売り切れになったそうです。そして、このプロジェクトを知った他の学生たちからも「一緒に作りたい」との声があり、第2弾、「Chiba Dorado 0」が、開発されました。こちらは習志野にあるブルワリー「むぎのいえ」の協力のもと、今年の3月7日から 提供されて、すでに完売しているそうです。
このプロジェクトに参加している学生の皆さんのことについても伺いました。
萩原教授
いろいろな人たちの参加があって、それでいろいろな人たちの思いを込めたいっていうところが、まずありました。特に大学生は熱い思いを持って活動している人たちも多いですから。その学生たちが実際に麦をこう煮込んでいったりとか、材料を混ぜたりとか、その後の掃除をしたりとか。実は一回目のビールのときに、ラベルのデザインも瓶にビールを詰めるところもすべて実際、学生たちが関わってます。で、そういった思いは、やっぱり自分ひとりではなくて、たくさんの人たちの思いが集まるほうが、よりいいものができると思っていて。で、そこに学生たちがすごく賛同してくれたというのがありますね。今まで二回ビールを作っていますが、四つの学部、さらにその中でも、学科がバラバラになっています。実は私の研究室から参加してきてくれた学生は合わせて二人だけで、他はみんな、他の学部・他の学科から参加してくれてます。法学部の学生が来たり、教育学部の学生が来たり、工学部の建築系の学生が来たりと、かなりバラバラになってます。
学生さん、1作目では、ラベルのデザインや瓶詰なども担当されたいうことですが、2作目では「味」を決めるのに大事なホップの種類を、高校までには教わらない数学のテクニックを使って決めたそうなんです。2つのチームに分かれてどの系統のホップを使うのかを検討して、共通する味の方向性を取り入れてブレンドしたりレシピの制作にも深くかかわったそうです。ほかにもホップを量ったり、タンクの掃除や材料や搾りかすの運搬などの作業を通じて、ビール製造の工程への理解も深まったようですよ。
その学生のお一人にもお話を伺いました。
ビールが大好きという吉田優芽(千葉大生)さん:
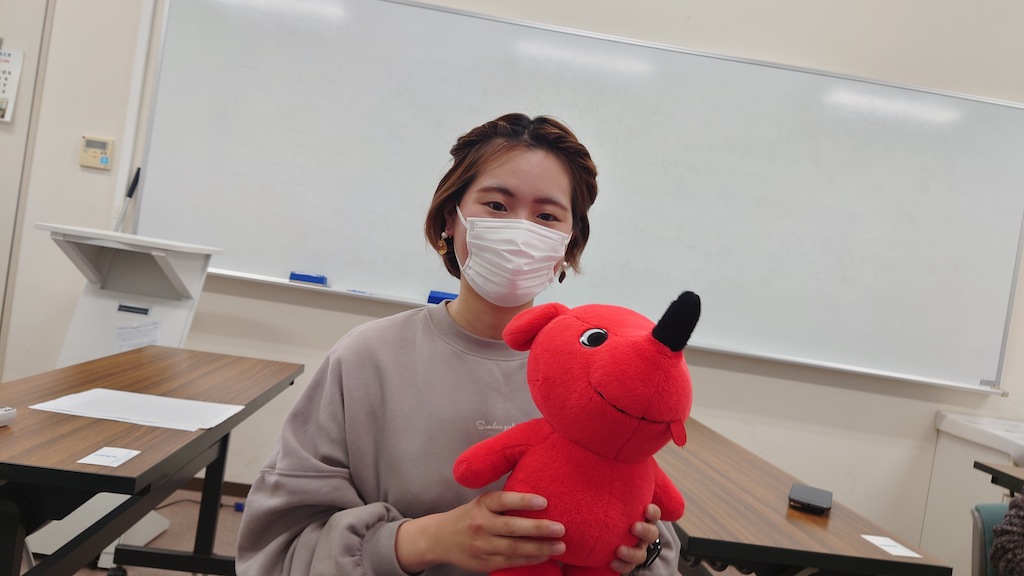
ツイッターで萩原先生がクラフトビールの勉強会のメンバー募集してたので、ちょっとビールに興味あったので、思い切って応募しました。本当、イチからビールのことを教えてくださって、ビールにはこういう種類があって、ビールはこうやって作るんだよとかいうことから始まり、勉強してたことが形になるとは思ってなかったんで、まずはびっくりしたんですけど、協力してくれた「麦の家」さんにあの感謝で、今はいっぱいですね。お酒に興味があるけど、どうやって勉強したらいいんだろうっていう人たちが多くて、みんな好奇心、お酒に対して好奇心が強かったんで、色々情報交換したりとか楽しく過ごしてます。千葉大学内に醸造所を作りたいなって、ちょっと考えてまして。私が考えているだけじゃなくて、大学の偉い人たちも良いよって言ってくれそうなんで、本当につくっちゃいたいなと思ってます。
学生たちはビールづくりを通して、「多くの人に喜んでもらえる味とは何か?」や自分たちが思い描いていたものが実際にできるかなど、非常に熱心に取り組んだそうで、萩原教授もその熱意に感じるところがあったそうです。最後にこれからの展開についてお話しいただきました。
萩原教授:
学生たちも私もそして今回ビールの醸造を手伝ってくれた醸造所の人たちも、新たなステップを踏みたいというふうに実は考えています。それに合わせて、次の勉強会の開催ももう予定しています。新メンバーも参加したいという声も上がっていますので、何かどんどん広がる予定ではあります。実は、ビールには色々な科学が携われるチャンスがあります。で、今回私は数値計算という意味で、その数学的なところ。更に数値では絶対置き換えられないような香りであったりとか、ノーブルな雰囲気であったりとか、そういったものも扱える、大学でしか、実はですね高校までに教わらない特別な数学なども適用してます。数学もこういった実は身近なところで、しかもビールっていう 楽しいところで何か貢献できるんだっていうところを より何か広げていけたらいいなと思っています。数学がビールに役に立つっていうのは、ほとんどの人が考えてなかったんじゃないかと思うので、良い刺激になってたらいいなと思ってます。楽しい味、おいしいビールもっと作ってみたいと思ってます。
学生の吉田さんもおっしゃっていましたが、この勢いでいくと、千葉大学でできたビールがレギュラーで楽しめるようになるかもしれませんよね。例えば近畿大学の研究から生まれた近大マグロみたいに「千葉大ブランドビール」が日本を席捲する日が来るかもしれません。現在3作目も企画中で、ビールがおいしくなる夏、8月頃に次を発表したいと動いているそうです。 こちらも楽しみですね!








