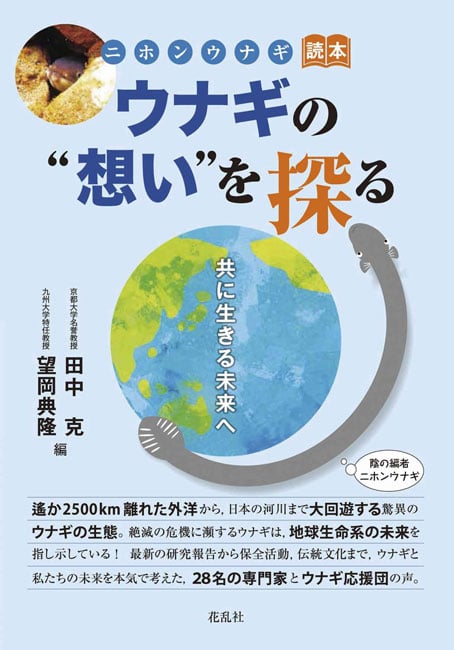2024/12/8 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、公益財団法人
「宮城県 伊豆沼(いずぬま)・内沼(うちぬま)環境保全財団」の研究室長
「嶋田哲郎(しまだ・てつお)」さんです。
宮城県北部にある「伊豆沼・内沼」は、毎年たくさんのガンやカモ、ハクチョウ類が飛来する国内有数の越冬地で、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」通称「ラムサール条約」に登録されています。
千葉県市川市出身の嶋田さんは働きながら、「マガンの越冬生態と保全」というテーマで論文を書き、博士号を取得。縁あって、研究者を探していた財団に勤務することになったそうです。

「宮城県 伊豆沼・内沼 環境保全財団」は1988年に設立された公益財団法人で、沼の自然環境の保全や研究、そして環境教育などの啓発活動を実施。普段はガンやカモなど、水鳥の個体数のモニタリングや外来魚の駆除なども行なっていらっしゃいます。
現在、嶋田さんは伊豆沼・内沼にやってくるハクチョウを調査する「スワン・プロジェクト」に力を入れています。いったいどんなプロジェクトなのか、じっくりお話をうかがいます。
☆写真協力:宮城県 伊豆沼・内沼 環境保全財団

渡り鳥たちが安心して暮らせる越冬地
※まずは、宮城県北部にある伊豆沼・内沼について。沼自体はどれくらいの大きさなんですか?
「面積は559ヘクタール、東京ドームでいうと110個分ございます」
●おっきいですね~。
「はい、周辺は農地に囲まれています。(沼は)いちばん深いところで1.6メートルというとても浅いって特徴があって、広くて浅い、そういう地形をしています。浅いので、夏になりますと沼一面にハスが咲くんですね。ハス祭りなども開催されています」

●そちらの財団のホームページを見ると、この伊豆沼・内沼は、秋から冬に極東ロシアからやってくるガンやカモ、そしてハクチョウなどの貴重な越冬地と書かれていました。ほかにも越冬する場所はたくさんありそうな気がするんですが、どうしてこの伊豆沼・内沼にやってくるんでしょうか?
「人も食住というのが大事なように、実は鳥も同じなんですね。伊豆沼には10万羽ほどのマガンですとか非常に多くの鳥が来ます。マガンは沼周辺の農地で、稲刈り後の田んぼに残っている落ちもみを食べています。また、ねぐらとなるこの伊豆沼は凍りにくい特徴があって、天敵となる哺乳類が入って来にくいんですね。そのため安全です。ですので、食もあり安心なねぐらがある、食住が安定しているということが理由で、たくさんの鳥が集まってきます」
●渡り鳥たちは毎年いつ頃やってきて、いつ頃までいるんですか?
「9月の下旬頃に初雁(はつかり)と言って、最初のマガンの初飛来があって、それからどんどん数が増えていきます。だいたい2月上旬には北帰行(ほっきこう)と言って北へ帰る、そういった動きが始まります」
●毎年どれぐらいの数の渡り鳥たちがやってくるんですか?
「年によっても少し異なるんですけども、伊豆沼・内沼ではマガンなどのガン類が10万羽ほど、ハクチョウ類で3000羽、カモ類で4000羽ほどが越冬しています」

●すごい数ですね。そんなにたくさんだと、渡り鳥たちの食べるものとかなくなっちゃうんじゃないかなって心配になっちゃうんですが・・・。
「沼周辺には非常に広大な農地があって、そこにはたくさんの落ちもみがありますし、実はオオハクチョウはレンコンを食べています。先ほどのハス祭りの後に、ハスが枯れて地中にレンコンができます。それを食べていて、そういったいろんな食物が豊富なので、これだけ多くの鳥を支えていると思います。
鳥というのは、生態系の食物網の頂点にいる生き物です。つまりこれだけ多くの水鳥がいるということは、それを支えている植物や魚類を含めた生態系が豊かなことを示しています。最近では特にオオクチバスの駆除による保全の成果が見られてきまして、沼の魚が回復してきています。
また、沈水植物といった水の中に生える植物も増えてきていますので、生態系が回復してきています。こういったことも鳥たちの生活に大きく貢献していると思います」
カメラ付きGPSロガー「スワンアイズ」
※ここからは現在、嶋田さんが進めていらっしゃる「スワン・プロジェクト」についてうかがっていきます。まずはどんなプロジェクトなのか、教えてください。
「このプロジェクトは2023年12月に始まりました。我々の財団ですとか、中国のドルイドテクノロジーといった会社を中心に始まったプロジェクトで、カメラ付きのGPSロガー、通称『スワンアイズ』と呼んでいますけども、それをオオハクチョウ10羽、コハクチョウ10羽に装着して追跡しています。
これまでなかった最大のオリジナリティが、カメラによってハクチョウ目線の画像を見られるってことです。そして位置情報とか画像を一般公開しています。市民のかたがそれを見てハクチョウを見守ろうという、そういった国際共同プロジェクトです」
●野鳥に認識番号付きの足環を付けたりとか、発信器を付けたりするのは聞いたことがあったんですけど、カメラ付きっていうのは画期的ですよね。
「カメラ付きGPSロガーっていうのは、たぶん世界初だと思います」

●重くないんですか?
「これはちゃんと計算しておりまして、GPSを中心にふたつの小型カメラがついていて、カメラの全体の重さは130グラムです。この重さはオオハクチョウの体重の2%以下ということになっていて、とても軽量なんですね。鳥の行動に影響しない重さで作られています」
●負担はそんなにない感じなんですね。
「はい、ほぼないです」
●(スワンアイズは)自然に外れるものなんですか?
「そうですね。やはり野外でずっと使っているものですので、劣化してだいたい2〜3年で脱落することになっています」
●ハクチョウにカメラ付きのGPSロガー「スワンアイズ」を付けるためには、捕まえる必要がありますよね? どうやって捕まえたんですか?
「なかなかこれが簡単ではないことなんです。オオハクチョウは水と一緒に食物を食べる、漉(こ)しとって食べるので、水があるところが食べやすいんですね。ですので、農家さんのご協力をいただきまして、田んぼをお借りして、そこに水を張ります。そして1ヶ月前から餌付けをするんです。餌付けをしてハクチョウを集めておいて、集まってきたところを網で被せて捕まえるってことをします」
●へぇ~、でも大きい鳥ですから、なかなか大変ですよね?
「大変です。本当に大変です。翼を広げると2.4メートルありますし、体重も10キロ、結構重いんですよ。本当に捕獲作業は泥だけになって、オオハクチョウと格闘しなければなりません」
●格闘の末にカメラを付ける作業になりますけれども、ハクチョウのどこに付けたんですか?
「首です。首についていますので、本当にハクチョウの、若干目線が下がりますけど、ハクチョウ目線に近い形で(撮られた)画像を見ることができます」

●なんか蝶ネクタイみたいな感じですよね。
「はい、そうです」
●捕獲してスワンアイズを付けるということですけれども、許可は得ているんですよね?
「もちろんです。これは環境省にちゃんと申請をして許可証をもらった上でやっています。また農地は私有地なので、当然その農地のかたに許可をもらってやっていて、全て手続きを済ませた上で実施しています」
ハクチョウ目線の画像に感動!
※「スワン・プロジェクト」のサイトを見ると、ハクチョウそれぞれに名前を付けていますよね。それはなにか意図があるんですか?
「このプロジェクトは、樋口広芳(ひぐち・ひろよし)*先生に顧問になっていただいているんですね。樋口先生はこのスワン・プロジェクトの10年前に、実は“ハチクマ”という鷹の位置情報を一般公開する『ハチクマ・プロジェクト』をやっておられるんです。先生からのご助言で、“愛称をつけたほうが市民に親しみが湧くんです”というアイデアをいただきまして、それでそうさせていただいたんですが、まさにその通りでした!」
(*鳥類学者。東京大学名誉教授。当番組にも出演)
●確かに愛着が湧きますよね! スワンアイズからは、定期的にデータが送られてくるっていう仕組みなんですか?
「そうです。携帯電話通信を用いているんですけども、それで位置情報が1日6回、画像が1日4回取得されて、定期的に送られてきます。少しタイムラグがあるんですけども、ほぼリアルタイムで位置情報とか画像を見ることができます」

●送られてきたデータで、これまでにどんなことがわかってきたんでしょうか?
「やはり位置情報と画像がセットになっているので、ハクチョウがいつどこで何をしているかっていうのが非常によく理解できます。レンコンを食べているとか、田んぼにいるとかっていうこともわかります。それから、飛んでいる画像がありますので、飛行場所の特定できるんですね。どう飛んでいるかっていう、そういったこともわかります。
さらには、当然ハクチョウは群れで暮らしていますので、同じハクチョウの仲間ですとか、同じガン科の仲間を(カメラが)写します。そうすると、ほかの種や、ほかの個体も映るので、時期とか地域に応じて、異なる鳥同士の関係性が見えてきます。非常に面白いです!」
●ハクチョウが見た景色を画像で見られるってすごいですよね?
「はい、私もやってみて、こんなにすごいとは思ってなくてですね・・・私自身が感動しているところがあります。きっとそれを見ている多くの市民のかたも感じておられると思います」
●私も見せていただいたんですけど、雄大な自然の中を飛んでいる時の画像がありましたよね?
「あれはびっくり! びっくりです!」

●すごいですよね~! ハクチョウの羽も映っていますし、一緒に飛んでいる6羽の仲間たちも映っていて、本当に感動しました!
「なかなか見られないですよね! 私も感動しました!」
●すごい写真ですよね~。実際、最初に送られてきた写真を見た時は、どんなお気持ちでした?
「思わず声が出ましたね! おぉ~って!(笑)」
●人間じゃ撮れない写真ですからね~。
「そうです! その通りです!」
一般のかたも追跡調査!
※嶋田さんが進めている「スワン・プロジェクト」のサイトにアクセスすると、どなたでも、ハクチョウの位置情報や画像が見られるようになっています。このプロジェクトには、一般のかたも参加できるんでしょうか?
「はい、もちろんです。そのためにX、旧twitterでスワン・プロジェクトを立ち上げています。Xでは、“スワン・プロジェクト”と検索すると、そこのページに行くんですけれども、多くのかたが位置情報を頼りにハクチョウを探しに行っています。探しに行って写真を撮って、その写真を投稿いただいたりとかしているんですね。
そういったことは観察記録にもつながってくるんです。ですので、多くの市民のかたに関心を持っていただいて、近くにいれば行っていただいて、写真を撮って投稿いただくっていうのは、非常にありがたい話です」
●「スワンアイズ」をつけたハクチョウを見つけました! っていうふうに、Xに写真を投稿するのは積極的にやってほしいっていう感じですか?
「できればやってほしいです。というのはハクチョウ目線の写真はわかるんですけど、全体像がわかんないんですよね、逆に言うと・・・。それを撮っていただくことによって全体像、こういう田んぼにいるんだとか、こういうところにいるんだっていうのがわかるので、とても助かるんです」
●カメラ付きGPSロガー「スワンアイズ」をつけたオオハクチョウたちは、いずれは(越冬を)終えて極東ロシア方面に戻っちゃうんですよね。戻っちゃったらこのデータっていうのはどうなるんですか?
「携帯電話通信を使っていますので、当然圏外だと通信できなくなります。北へ戻ってロシアの繫殖地にいると当然、通信網がないので一定期間通信できなくなります。今年の場合で見るとだいたい6月から9月までは一切通信が入ってきませんでした。だけども日本に帰ってきて携帯電話通信網に入ればまた回復します。そうするとそれまでの間のデータが全部取得できるんですね」
●なるほど・・・。
「それによって、ロシアでの素晴らしい繁殖地の景色なども見ることができました」

鳥の世界を楽しんで!
※去年から始まった「スワン・プロジェクト」、今後はどんな展開になりそうですか?
「今年も(オオハクチョウなどの)捕獲と装着をやります。このスワン・プロジェクトに関心を持っていただくために、捕獲地なども少し広げたいと思っていますし、これからも続けていきたいなと思っています」
●今後、何年ぐらい続ける予定ですか?
「そうですね・・・まず今年はやります! 今年の様子とか去年の装着した状況とか、今年これからやることは状況を見ながら、いろいろ検討していきたいと思います」
●この「スワン・プロジェクト」でどんなことを伝えたいですか?
「お陰様でXの投稿数ですとかフォロワー数が増えているんですね。これは多くの市民の方に関心を寄せていただいているからだと思っております。位置情報や画像をもとに多くの市民の方がハクチョウを追跡して、Xに投稿していただいている、こういったことは鳥に関心を持つことにつながりますし、または生態の面白さの気づきになると思うんですね。ゆくゆくはそういった研究につながっていって、鳥の世界をお楽しみいただければなっていうふうに思っています」
INFORMATION
「スワン・プロジェクト」にぜひご注目ください。オフィシャルサイトにアクセスすると、ハクチョウに装着されたカメラ付きGPSロガー「スワンアイズ」から送られてくる位置情報や画像を見ることができます。
また、嶋田さんもおっしゃっていましたが、一般のかたも調査に参加することができます。特に東北や北海道にお住まいのかたは、位置情報を頼りにハクチョウを探して、その個体がいるフィールドの写真を撮って投稿いただくと、観察記録になるということですので、ぜひご協力をお願いします。
◎スワン・プロジェクト :https://www.intelinkgo.com/swaneyes/jp/
◎スワン・プロジェクト「 X」アカウント:
https://x.com/swaproj?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
「宮城県 伊豆沼・内沼 環境保全財団」のサイトもぜひ見てくださいね。
◎http://izunuma.org
嶋田さんは3年前に緑書房から『知って楽しいカモ学講座』という本を出されています。ぜひチェックしてください。
2024/12/1 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、漁港で魚の赤ちゃん 幼魚を、網で採って研究されている岸壁幼魚採集家の「鈴木香里武(すずき・かりぶ)」さんです。
金髪に白いセーラー服というトレードマークの香里武さんは、魚の研究者、経営者、プロデューサー、タレント、番組パーソナリティ等々、幅広い分野で活躍中。
そんな香里武さんに、漁港で採取する幼魚や、館長を務めている「幼魚水族館」、そして先頃出された本『水の世界のひみつがわかる! すごすぎる 海の生物の図鑑』から、変態するお魚、農業をするお魚など、魚に関連する面白いお話をたっぷりうかがいたいと思います。
☆写真協力:鈴木香里武、幼魚水族館、KADOKAWA

名付け親は「明石家さんま」!?
●今週のゲストは、岸壁幼魚採集家の鈴木香里武さんです。鈴木香里武さんは先頃『水の世界のひみつがわかる! すごすぎる 海の生物の図鑑』という本を出されています。後ほどそのお話もうかがいます。よろしくお願いいたします。
「よろしくお願いします。ごきげんようぎょ! これを言わないと始まらない(笑)」
●ごきげんようぎょ!(笑) よろしくお願いいたします! まずはプロフィール的なお話から。どうしても気になるのでお聞きしたいんですが、鈴木香里武さんというそのお名前は本名でいらっしゃるんですか?
「はい! 芸名だとよく思われるんですけど、これ本名なんですね。“スズキ”も魚の名前ですよね」
●確かにそうですね~!
「“香里武”がカリブ海からとられた名前で、3月3日生まれの魚座なので、全部揃っているという(笑)、作ったような話なんですよね」

●海のために生まれてきたみたいな感じですよね!
「ちなみに“香里武”って名前をつけてくださったかたも、魚にまつわる人なんですよ」
●どなたなんですか?
「明石家さんまさん! “さんま”、やっぱり魚ですね!」
●え~~〜っ! どういう経緯で?
「これは、うちの両親が当時さんまさんに仕事ですごくお世話になっていまして、(両親が)新婚旅行でカリブ海に行ったんですね。そのお土産を持って、さんまさんのところにお届けに行った時に、子供の話が出たらしくて、“名前はどうするんだ?”みたいな話が出たと・・・。
両親は海が好きなので“、海にまつわる名前をつけたいです!”って言ったら、さんまさんなりにいろいろ考えてくださるわけですね。“オホーツク”とか“エーゲ“ “カスピ”とかいろいろと出るわけです。でもふと(さんまさんが)思い出して “カリブ海に行ったんやろ? だったらカリブでええやん“って、その”ええやん“の一言で決まったのが僕の名前でございます」
●そうだったんですね~。名付け親は、さんまさんだったんですね!
「そうなんですね。ここまで魚と海に囲まれたら、もう魚のことをやるしかないですよ」
●運命ですね! では子供の頃から海とか魚には興味があったんですか?
「そうですね。生まれた時から家には魚を飼う水槽がありましたし、両親も海が好きなので、休みの日になると僕を連れて海辺によく遊びに行ってくれていたんですね。なので、魚のいない生活は逆にしたことがないです」
●なるほど。魚のことをどなたかに教わったりはしたんですか?
「当時はね・・・今32歳なので、32年前は今ほど魚の情報ってなかったんですよね。もちろん魚図鑑で勉強したりはしましたけれども・・・。いちばん衝撃的だった先生との出会いは、“さかなクン”かなぁ~と思います」
●お~〜、そうなんですか?
「小学校3〜4年生の頃かな、初めてお会いしたのが・・・その時に衝撃を受けました。それまで魚の先生と言えば、白衣を着て顕微鏡を覗いているような大学の教授、もしくは水族館の職員さん、そんなイメージだったんですよね。でもご本人がそのまま、魚の使者みたいな人が登場して、すごくびっくりして、もう嬉しくなっちゃって、こんな人いるんだと思って憧れて、(さかなクンの)あとをくっついて歩いていた時期がありました」
(編集部注:実は香里武さん、学習院大学大学院で心理学を専攻し、「観賞魚の癒しの効果」というテーマで、魚を見たときの人の心理を研究。そして現在は、北里大学大学院の海洋生命科学研究科に籍を置き、魚の一生、特に幼魚が漁港で人工物をどのように利用して生き抜いているかを研究されています)
「岸壁幼魚採集家」とは?
※ところで、肩書きの「岸壁幼魚採集家」も気になりますよね。この肩書きにしたのは、どうしてなんですか?
「聞き慣れない言葉ですよね~」
●漢字がたくさん並んでいる感じ(笑)
「これを本業だと言い張っている人は、たぶん世界でも僕しかいないと思うんです。やっていることはものすごくシンプルで、”タモ網”っていう柄のついた網を持って、それで漁港に行って・・・岸壁っていうのは漁港の壁面のことですね。そういう港で這いつくばって、上から海面にいる魚たちを覗いて、そこにいる幼魚をすくうと・・・壮大な金魚すくいみたいなもんですね。

それをやる人のことを『岸壁採集家』っていうふうに一部のジャンルとしてあったんですよ。趣味としてやっている人がいたんですね。その中でも幼魚に特化して本業にしよう! っていうことで、こんなまどろっこしい肩書をつけております」
●インパクトがありますよね~! 漁港に魚の赤ちゃんっているんですか?
「そう! これもね~結構灯台もと暗しっていう感じで、漁港だけに灯台もと暗しですけど・・・そんなことはどうでもよくて(苦笑)。みなさん、釣り糸を垂らしたりしていますよね。その足元に実はいるんですよ、幼魚って・・・」
●たくさんいるものなんですか?
「たくさんいるんです。ただあまりにも小さかったり、透明になって身を隠していたり・・・。あとは擬態と言って、枯れ葉そっくりだったり岩そっくりだったり、生き物らしからぬ、いろんな姿で身を潜めているんですね。それは大きな魚に食べられないためだったり、上から狙っている海鳥のカモメとかに食べられないためだったり、身を守るために見えなくて当然な姿しているんですね」
●へ~〜っ!
「だから言われないと気づかないですね」

●そうなんですね~。今まで何種類ぐらいの幼魚に出会えたんですか?
「どうかな・・・700(種類)は超えていると思うんですけど、もはや数えられないですね」
●季節的にはいつ頃がいいとかあるんですか?
「春夏秋冬、朝昼晩いつでも面白いんですよ。魚がいちばんたくさん見られるのは夏から秋にかけて、南のほうからもカラフルな幼魚がやってきたりするので、とても楽しいんですね。
でも今の季節、冬12月ですね。冬になると深海魚の赤ちゃんが上がってきたりもするんですね。水温が低くなるので、冷たい海に暮らしている深海魚も浅いところまで上がってきて泳げるようになってしまう・・・そうすると普段はなかなか生きた姿を見られないような、幻の深海魚たちに足元で出会えるっていう、これまた興奮の連続の季節がやってきます」
●これまで採集した幼魚で、特に印象的だった幼魚っていますか?
「う〜〜ん・・・『リュウグウノツカイ』かな~。深海魚で体長5メートルぐらいある、ものすごく長い体を持った深海魚がいるんですね。時々成魚が砂浜に打ち上がったりして・・・。そうするとあまりにも珍しいので全国ニュースになったりする、それぐらいの魚なんです。
そのリュウグウノツカイの幼魚、最初に出会ったのは7センチぐらいのちっちゃい子だった・・・その子に漁港で初めて出会ったのが、僕はたぶん人生の中でちゃんとした深海魚の赤ちゃんに、足元で出会った最初の経験だったんですね」
●へ~~〜っ!
「その時に衝撃を受けて・・・僕は幼少から深海魚が大好きだったので憧れていたんだけど、いつも僕が見ている水深0メートルの世界では到底出会えない、本当に遠い世界の存在っていうイメージだったんです。それが実は0メートルにも現れる、それを体感した時に、海って横にも繋がっているし、縦にも繋がっているんだっていうことをすごく感じて、感激した瞬間だったんですね」
変態する魚!? 農業をする魚!?
※香里武さんは先頃『水の世界のひみつがわかる! すごすぎる 海の生物の図鑑』という本を出されています。この本には、可愛いキャラクターが登場したり、イラストや写真もたくさん載っていて、お子さんを意識した作りにはなっているんですが、専門用語もまじえ、魚の生き様を紹介。香里武さん的には、すべての世代のかたに「海の世界へのパスポート」として読んでほしい、そんな思いを込めたそうです。
それでは、本に載っている75のトピックから、いくつかピックアップしてお話をうかがっていきます。まずは「美しき変身ヒーローと、愛すべき変態たち」という見出しのトピックがありますが、これはどういうことなんでしょうか?
「これは、海の生き物って卵から生まれて、そして一生を終えるまでの間、ずっと同じ姿をしていることって少ないんですね。それは生活のスタイルを変えるので、それに合わせて姿もガラリと変わるんです。それが変身ぐらいだったらまだしも、昆虫と一緒で体の構造を全く変えてしまう、変態をするような生き物もいるので、ドラマチックな変わりっぷり! これをぜひ知っていただきたいなと思って書きました」
●幼魚から成魚になる時に大変身するってことなんですね?
「そういうのもいますね」
●たとえば、どんな魚が・・・?
「たとえば、渦巻き模様のお魚で『タテジマキンチャクダイ』いうお魚がいるんですね。とっても見た目が可愛らしくて水族館でも人気の幼魚なんですけれども、このウズマキちゃんが成長すると名前の通り、縦じま、縞々模様に大変身しちゃうんです」

●模様が変わっちゃうんですね?
「色もディープブルーな色だったものが、黄色と青のストライプになっていくんですね」
●全然違いますよね?
「全然違います! たぶん言われないと同じ魚だとは思えない。これもちゃんと意味があって、彼らは親同士の縄張り争いが激しいんですね。なので、同じ柄の別の個体を見ると攻撃を仕掛けるわけです。
でもその攻撃を幼魚にまで仕掛けてしまうと、幼魚はまだデリケートな存在なので、種の保存っていう意味ではよろしくないわけですね。やっぱり自分たちの種類を繁栄させなきゃいけないから、子供は守んなきゃいけない。そこで一目瞭然で喧嘩の対象外だってわかるように、親子で全然柄が違うんじゃないかっていうのが、今の主流で言われている説です」
●面白いですね!
「本当かどうかは、本人に聞かなきゃわかんないです(笑)」
●それから「地道に農業をする魚」!
「これも面白いですよね~」
●「クロソラスズメダイ」という魚ですけど、農業するってどういうことなんでしょうか?
「いるんですよね~、草食で草なんかを食べるお魚なんですけれども、お気に入りの海藻があるわけですね。イトグサっていう海藻が大好き! そればっかり食べる。
でもイトグサは放っておくと、ほかの海藻のほうが強いので負けちゃって、ほかが生えると、雑草がいっぱい生えちゃうと、本物のイトグサさんが枯れてしまうっていう問題がある。そこで、このクロソラスズメダイは岩の表面をせっせと手入れして、イトグサ以外の雑草むしりを常にやっている。イトグサがたくさん生える環境を整えて、自分の畑を耕して、それで大切に育てたイトグサを最終的には食べちゃうわけなんです」
●食べちゃうんですね!
「それもすごく面白い関係だなと思いますね。イトグサはイトグサで、クロソラスズメダイが面倒を見てくれないと育たない海藻なので、ある意味ではwin-winの関係・・・結局食べられちゃいますけどね(笑)」

サメのために、あのKISSが洋上ライヴ!?
※では、本に載っているトピックのお話を続けましょう。
●おしまいは、ホホジロザメのためにライヴをしたロックバンドということで、これはどういうことですか?
「意味がわかんないですよね(笑)。世界的に有名なロックバンドのKISSっていう、あのメイクしているKISSが2019年に船の上でライヴをやったことがあるんですね。オーストラリアの海かな・・・。そのライヴは人に向けてのライヴではなくて、実はサメを呼び寄せるためのライヴだったんですよ」
●面白いことをしますね!
「船の下から水中に音が出るようにスピーカーつけて、それでハードロックをオーストラリアの海に響かせたわけですね。なんでそんなことやったかっていうと、ホホジロザメをはじめとするサメの仲間は、低周波の音に反応する習性があるんですね。重低音と言えばロックだろう! それで本当にサメが来るんだろうかっていうこの面白い企画をやった人がいて・・・結局(サメは)来なかったんです(笑)」
●来なかったんですね~。
「来なかったんですけど、でもこの企画に乗ったKISSのメンバーのロック魂には拍手です」
●確かにサメに向けてライヴするって、すごいことですよね!
「面白い発想ですよ〜。でも、お笑いでやっているわけじゃなくて、ちゃんとそこにはサメという生き物ならではの習性があって、彼らが海のハンターと呼ばれるゆえんは、そういう周波数とか、ちょっとした電波みたいな、電気みたいなものとかを感じ取る器官がすごく発達しているから、だからああやって、かっこいい姿で海の王者になっているわけなんですよね。そんなことを感じられるエピソードかなと思います」
幼魚に特化した水族館

●2022年7月に静岡県駿東郡清水町に「幼魚水族館」がオープンして、香里武さんはそこの館長さんでもいらっしゃるんですよね?
「はい、そうです!」
●この水族館では、香里武さんが採集された幼魚が見られるそうですね?
「僕をはじめとするスタッフたちが、夜な夜な近くの漁港まで行って、その季節に出会える幼魚をすくってきて展示しているので、どの季節に行っても今の駿河湾を見ることができるんですね」
●現在どれぐらいの数の魚を飼育・展示されているんですか?
「大体100種類、150匹ぐらいは泳いでいますね」
●オフィシャルサイトを見ると、魚の展示だけじゃなくてユニークな展示もされているんですね?
「そうですね。いろいろ海で僕がいつも上から海面を覗いているので、横からだけじゃなくて上から覗くことができる水槽を作ってみたりとか・・・。
あとはどうしても、一生懸命育てていても死んでしまう幼魚もいるので、そういう死んじゃった子たちも、もう1回見てもらいたいっていうことで透明標本という形で・・・、中部大学の武井(史郎)先生というかたが作られているその特殊な技術で、生きたままの姿で透明化することができるんです。そうすると生きている時は見えなかった体の中の構造も間近で見ることができるので、新しい形でまた“第2の魚生”を歩んでいただいています」
●ほかの水族館と比べて、いちばんの違いってどんなところですか?
「そもそも魚の赤ちゃん、幼魚に特化した水族館は世界で初めてなので、これはほかではなかなか幼魚って見られないと思います」

●確かにそうですよね~。
「あとは、幼魚ならではのこととして、どんどん成長していくんですね。成長すると姿形がさっきの変態のように変わっていくので、その様子を飼育員だけじゃなくてお客さんも一緒に見届けることができる。そして成長して幼魚ではなくなったら『卒魚式(そつぎょしき)』っていうのをやります。今度は、別の水族館に成魚として無償提供するんです。ちゃんと式典をやるんですよ、1時間の!」
●そうなんですね~。
「来た時はこんなだった子がこんなに大きくなりましたっていう成長記録を発表したりとか、ちゃんと町長さんまで来て祝辞をいただいたりとかですね。そうやってお客さんと一緒に育てた幼魚たちを、お客さんと一緒に見送って、別の場所で今度は成魚として別のお客さんに感動を届けてもらいたいと、そういうふうにストーリーを繋げています」

海の変化、海洋ゴミ〜自発的なSDGsに
※日頃、岸壁幼魚採集家として活動されていて、海の変化を感じたりすることはありますか?
「あ~〜ものすごく感じますね。ここ10年ぐらいだけでも、かなり変化したかなと思っています。たとえば、ちっちゃい頃だったら、春先になると漁港の足元には海藻が青々と茂っていたんですね。それが最近暖冬が続いて、温暖化で海水温が下がらなくなって海藻が育たなくなってしまったんですね。
そうすると、春先にもう海藻はないし、その海藻に身を隠していた幼魚たちも忽然と姿を消してしまう。逆に夏になると昔は見られなかったような、沖縄あたりに暮らしているカラフルな魚たちが黒潮っていう海流に乗って、こっちまでやってきて、それが秋、冬とずっと生き延びている姿を見るようになりました。
昔だったら冬を越せなかった子たちが、今は暖冬で冬を越すようになっている。新しい魚が来たってことは、もともといた魚がいなくなっているってことなので、そういう足元で出会える魚の種類の変化からも温暖化は感じますね。
あと、漁港の隅って海洋ごみがたくさん打ち寄せられるんですよ。風に乗ってゴミが流されてきて結構汚いんですね。いかにゴミが海に多いかを知る場所としても漁港はいいのかなと思っていて・・・年々ゴミの量も増えています。でもそのゴミさえも、敵から身を守るために利用して、ゴミの下に隠れている幼魚がいたりなんかするんですね。
そういう姿を知ると、ゴミを拾いに行きましょう! っていうのと、ちょっとまた違った入り口が広がると思っています。そのゴミの周りにいるたくましく健気な幼魚たちの生き様を見て、彼らの暮らしている海を汚してはいけないなと、綺麗にしたいなっていう気持ちがわいてくれば、義務としてのSDGsではなくて、自発的なSDGsに繋がっていくのかなと思っています」

●幼魚たちの調査や研究をされていて、ワクワクするのってどんな時ですか?
「まだ出会ったことがない幼魚に出会った時ですね。32年やっていてもあるんですよ、初めての出会いが・・・。今年も8月に『イシガキフグ』っていう、世界で誰も幼魚を見たことがない(その幼魚を)すくったことがあって、成魚はいっぱいなのに幼魚を誰も見つけたことがない・・・。でもそうやって、毎年のように新しい出会いがあるから、これはやめられないですね」
●「岸壁幼魚採集家」として、いちばん伝えたいことはどんなことですか?
「思っているより魚たちは身近にいるっていうことですね。海に潜っていかなくても沖に出なくても、足元をちょっと覗くだけで魚に出会える。これは日本の豊かさでもあるし、海全体の豊かさなのかなと思います」
INFORMATION
香里武さんの新しい本をぜひ読んでください。香里武さんの視点で取り上げた、魚や海に関する75のトピックを掲載。イラストや写真がたくさん載っていて、見開き2ページでひとつの話が完結しています。見出しを見て、面白そうなページから読めますよ。おすすめです!KADOKAWAから絶賛発売中! 詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎KADOKAWA :https://www.kadokawa.co.jp/product/322404001466/
鈴木香里武さんのオフィシャルサイトもぜひ見てくださいね。
◎鈴木香里武:http://karibu-collabo.main.jp/top/?page_id=7
静岡県にある「幼魚水族館」にぜひお出かけください。展示内容やアクセス方法など、詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
◎幼魚水族館:https://yo-sui.com/
2024/11/24 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、鹿児島市にある平川動物公園のコアラ飼育員「落合晋作(おちあい・しんさく)」さんです。
落合さんはもともと生き物好きで、子供ころから釣りに明け暮れ、九州の大学で魚の勉強をしたあと、水族館に勤務。その後、ご両親が鹿児島に暮らしていることもあって、平川動物公園に転職。ゾウやカワウソなどの飼育を7年ほど担当したあとにコアラの飼育担当になっています。
コアラを5年ほど担当されている落合さんは、日々コアラに接する中で、可愛いという感情より、コアラはすごいぞ!と思うことが多く、そんな思いが込められた本『すごいコアラ! 〜飼育頭数日本一の平川動物公園が教えてくれる 不思議とカワイイのひみつ』が先頃出版されました。
きょうはコアラの知られざる生態や、赤ちゃんの秘密、そしてエサになるユーカリ栽培への取り組みなどうかがいます。
©新潮社 写真協力:鹿児島市平川動物公園

コアラは北方系と南方系!?
※コアラが日本に来たのが1984年10月25日、今年で来日40年! ちなみに10月25日は初来日を記念して「コアラの日」となっています。
日本では現在、7つの施設で飼育されています。首都圏では東京都日野市の「多摩動物公園」「埼玉県こども自然動物公園」そして横浜市の「金沢動物園」の3つの施設で見ることができますが、コアラの飼育頭数で日本一を誇るのが、鹿児島市にある「平川動物公園」。現在はオス8頭、メス10頭、合わせて18頭を飼育。コアラの初来日から飼育が始まり、通算105頭の飼育実績があるそうです。
2021年には新しいコアラ館がオープン! ガラスなど遮るものがなく、高さがおよそ8メートルある館内のガラス窓からは日の光が降り注ぎ、またユーカリも植えられていて、より自然な感じでコアラを見ることができる、ということで、とても人気なんだそうです。

●まずはコアラがどんな動物なのか、基本的なことをいろいろうかがっていきます。コアラはオーストラリアの固有種ですが、どのあたりに多くいるんですか?
「オーストラリアという国は、だいたい日本の21倍の面積があるんですね。おそらくコアラはオーストラリアのどの地域にもいると思われているかたが多いと思うんですけど、オーストラリアの地図を正面から見た時に、右の海岸線のふち側・・・ケアンズがあって、下にシドニーやメルボルンがあるんですけれども、このふちの辺りの森とか林があるところにいるんです。
言ってみれば、国土の20分の1ぐらいのところにしか生息していないんですよね。そういうところにいる動物ですね」
●何種類かいるんですか?
「みなさん、コアラ、コアラとおっしゃっていますけど、コアラという動物は1種類なんです。厳密に言うとふたつの系統、グループに分かれています。シドニーの少し下ぐらいからを境に、北のほうにいる北方系のコアラ、ちょっと小柄でグレーの色が強いコアラですね。
南半球なので、南のほうに行けば行くほど寒い国ですから、寒いところにいるのが南方系のコアラ、通称『ビクトリア・コアラ』って言われているんですけど、これがちょっと大きくて濃い色をしていますね。
見た目は2種類を並べると全然違うコアラということになりますね。当園では北方系、ちっちゃいほうのコアラ、あったかいところにいるコアラを飼っています」
●サイズ感も色も違うんですね〜。
「そうですね。オスの体重で言うと1.5倍ぐらい違います。北方系がだいたい8キロから9キロ、南方系が最大で15キロぐらいになりますから、すごく大きいですよね」

●へ〜! 体全体は灰色ですよね?
「そうですね。頭から背中にかけて灰色、お腹側、お尻が若干白く見えますよね」
●そういう毛の色にも何か意味ってあるんですか?
「はい、みなさん、コアラの餌っておそらくユーカリっていうのを知っているかたは多いと思うんです。ユーカリは、ホームセンターとかお花屋さんに行くと売っていますよね。で、だいたいグレーがかったシルバー色したユーカリが多いと思うんですね。
で、ユーカリってだいたい1000種類ぐらいあるって言われているんですけど、ユーカリの森はグレーの葉っぱがあったり、木の樹皮が白っぽいんですよね。そういったところにグレーの色の動物が木に乗っかっていると、いわゆる擬態、周りの風景と溶け込んで見えるので、こういう色をしていると言われています」
●意味があるんですね、色にも!
「そうですね。で、お腹側が白いのは木の下から上を眺めたときに、白っぽいと太陽の光とかと同化しちゃうんですよね。こういう動物、魚も多いんですけど、こういうことを彼らは生きていく中で獲得した、ありのままの彼らが暮らしやすい姿、色になっていると思います」

(編集部注:落合さんによると、基本的に野生のコアラは単独で生活していて、一頭のテリトリーは狭くて100メートル四方、広いとなんと10キロ四方。
オスは自分のテリトリーにほかのオスが侵入すると、食べ物のユーカリやメスを奪われまいと、可愛い姿からは想像できない猛獣のような声「テリトリー・コール」をして威嚇するそうです。
*コアラの鳴き声は、平川動物公園のサイトで聴くことができますよ。
https://hirakawazoo.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/koala1.wav
また、マーキングをするオスは、胸にある「臭腺(しゅうせん)」からとても臭い液を出して木にこすり付けます。そのため、オスの胸のあたりはいつも汚れているそうですよ)
鋭い爪、大きな耳と鼻
※コアラの体の特徴でいうと、木の上で生活していますから、手や足のツメが鋭かったり、筋力が強かったりして、可愛いコアラのイメージとは違いますよね?
「そうですね。よくお客様にもコアラってどうですか? って聞くと、可愛いっておっしゃるんですね。で、可愛くないところってあるのかなっていう話をするんですけど、その代表的なところはやっぱり爪なんですね。

指の本数は我々人間と一緒です。前も後ろも5本指なんですけど、本当に爪が長くて、鎌のように曲がっていて先が尖っています。爪が1本でも木に引っかかっていれば、落ちることはないですね。その爪を立てながらひょいひょい登っていくんですよ。
当然握る力もやっぱり強いです。で、ラジオ番組なのでお見せできないんですけど、私の腕は本当にコアラの爪の跡、服を着ていても服の上から爪が刺さっちゃうので、もう傷だらけです」
●鋭いんですね〜! 耳とか鼻も大きいですよね?
「そうですね。耳は特徴的な可愛らしい大きな耳をしています。先ほど縄張りの話をしましたけど、コアラって鳴くんですよね。寝てばっかりのイメージですけど、結構大きな声で鳴くんですよ。猛獣のような鳴き声、本の中には”ゲップ”とか”ゴゴゴ〜”とか、そういう音で表現しているんですけど、すごく大きな声で鳴いて、数キロ先まで届くって言われているんですね。ほかのコアラがいるかいないかを、臭い以外、音でも聴かないといけないので、やっぱり大きな耳をしているんですね。
で、もうひとつの特徴として大きな鼻がありますよね。体重は8キロ前後とお伝えしましたけど、鼻の大きさで言うと我々人間と変わらないです。で、やっぱりこの鼻も非常に重要で、ほかのコアラの臭いを嗅ぐにしてもすごく大事なんですけど、いちばんは彼らが食べているユーカリの葉っぱの好き嫌い、選り好み、どれが美味しいのか美味しくないのか、食べられるのか食べられないのかも鼻ですべて感知していると思います」
長い睡眠時間には理由がある
※コアラは木の上でじーっと動かないイメージがあるんですけど、寝ている時間が長いということですよね?
「こればっかりは、もう本当に(睡眠時間が)すごく長くて、ほとんど動かないんです。だいたい20時間から22時間ぐらい、睡眠・休息に費やしていると言われていますね。本当に動かないです」

●なんでそんなに寝るんですか?
「なまけているんじゃないのとよく言われるんですけど、実はそうではなくて、寝るにはちゃんと理由があるんですね。先ほどからコアラの餌はユーカリと何度もお伝えしていますけど、このユーカリって植物が実はポイントになっています。
葉っぱは、新芽と言われる柔らかいところ以外は硬くて繊維が多いんですね。こういったものを食べると、消化にすごく時間かかるんですよ。で、極めつけは毒が入っているんですね。この毒の分解にも時間がかかります。
ただでさえ栄養価の少ない葉っぱを食べていて、極めつけに毒も入っているってことなので、一生懸命動いてしまうと、お腹を動かすためのエネルギーもなくなるんですね。動けば動くだけどんどん痩せます。ですから、じーっと動かないようにしてユーカリの消化吸収に全力を注いでいると思ってください。そういうふうに進化してしまったので、寝ざるを得ない動物になってしまいました」
●木から降りて地面を歩き回ったりすることもあるんですよね?
「もちろん歩くんですよ。で、地面っていうか地上にはやっぱりコアラの外敵となる動物もいたりしますから、基本的に木から木へはジャンプして移動することが多いんですけど、どうしても移動できない距離だと地面に降りて歩くんですね。でもそんなに走ったりすることは、できるんですけど、そこまで長続きしないっていうか、やっぱり歩いているときは危機感を感じてるような気がしますね。早く木に登らないとっていう、そういう仕草を見せてくれます」
妊娠期間は35日!
※平川動物公園でのコアラの繁殖に関してうかがいたんですけど、発情期は一年に何回かあるんでしょうか?
「野生の動物ってだいたい年に1回とかが多いんですけど、コアラの場合は、基本的に通年発情はするんですよ。ただメスがオスを受け入れるタイミングってだいたい春と秋が多いんですよね。この時期に我々もコアラの様子を見ながらペアリング、繁殖させるようにはしています」
●平川動物公園では積極的にペアリングに取り組んでらっしゃるそうですね。相性とか発情期間とか、いろいろ見極めるのも大変なんじゃないかなって思うんですけど・・・アプローチするのはオスなんですか?
「そうですね、基本的に・・・。メスは結構受け身が多いんですけど、言ってみれば発情してないのにオスとペアリングしても、オスもメスにあまり向かわなかったり、メスは当然受け入れないんですよね。
その発情の見極めってすごく大事で、しかも個体によって差があるんですよね。人と一緒で性格があるので、ガツガツしている女の子は、言ったら肉食系の女の子はすごく積極的にオスにもアプローチするんですよ。
逆にオスがそれを受け止めきれない(笑)、草食系って言ったらおかしいんですけど、ちょっとガツガツしている女の子は、苦手だなっていうオスもいたりするので・・・。本当にガツガツしている女の子でも、ちょっと大人しそうなタイミングで、草食系の男の子と一緒にしてペアリングしてみたりとか、ガツガツしている女の子でも大丈夫な男の子をペアリングにあてがったりとか、相性を見ながら繁殖っていうかペアリングさせていますね。
ここは長年の経験とか勘がだいぶ頼りになってくるので、本当に飼育の醍醐味でもありますよね。今だったらいけるんじゃないかとか、そういったのを日々見極めながら見ていますね」
●ペアリングが見事うまくいってメスが妊娠すると、出産はどれぐらいあとになるんですか?
「我々人間の妊娠期間は10ヶ月程度って言われていますけど、コアラの妊娠期間はわずか35日なんですよ」
●え~っ!
「担当者の目の前で交尾させますから、そのあと35日後に生まれてきます。ずれても1日ぐらいなんですよ。この間、コアラの様子を見ながら出産するかしないかを見極めたりするんですよね。ただストレスを与えることはできないので、出産のタイミングに立ち会うことはほぼありません。っていうか、できないですね、なかなかできないです、これは」

赤ちゃんは一円玉!?
※生まれてくる赤ちゃんの大きさは、どれくらいなんですか?
「例えるなら、大きさは1円玉です」
●え~っ!
「1グラム1センチって表現するんですけど、本当に1円玉の大きさです。ただ形は、実はコアラの形をしていなくて、夏休みにカブトムシを飼うお子さんもいらっしゃると思うんですけど、カブトムシの幼虫とよく似た形です。本当にちっちゃくて一見すると何の動物かもわからない、そういう赤ちゃんが生まれてきます」
●そういう状態の赤ちゃんが、いわゆるコアラの形になるにはどれぐらい時間がかかるんですか?
「はい、まず生まれてすぐ、そのままだと毛も生えていませんし、目も見えてないので、すぐ干からびて死んじゃうんですよね。ですから、生まれた赤ちゃんは5分から10分かけてお母さんのポケットに移動するんですよ。
ポケットは後ろ足の付け根についています。そのポケットに自分の力だけで這いつくばって進んでいきます。先ほど紹介した通り、爪が鋭いので、お母さんがつまむと赤ちゃんは亡くなっちゃうわけですよね。ですから、お母さんもじっと我慢しているんですね。
ポケットの中に入ると、中におっぱい、乳房がふたつついていますから、この乳に吸いついてどんどん大きくなっていきます。で、コアラっぽくなるにはだいたい4か月ぐらいかかります。4ヶ月経ってもまだ毛は生え揃ってないので、なんとなくこれコアラの赤ちゃんじゃないの? っていう感じになるんですね。
だいぶ時間はかかりますね。おっぱいに吸いついて簡単に離れてしまうと、また乳房を探さないといけないので、お母さんの乳房に子供がくっつくと抜けなくなるんですよ、取れなくなるんですよ。これがだいたい3〜4か月取れない時期が続いて、そこからは自分のタイミングで(ミルクを)飲めるようになるんですね。それがだいたい4か月ぐらいから始まるって感じですね」
(編集部注:落合さんによると、コアラの赤ちゃんは半年ほどで、お母さんのお腹側にある「育児のう」と言われるポケットから出てくるんですが、子育ては1年くらいは続くそうですよ。
赤ちゃんにとって、ポケットから出るタイミングで、その後、生きていくために必ずやらなければいけないことがあるんです。それはお母さんのフンを食べること。フンに含まれている腸内細菌を獲得し、繊維が多くて毒のあるユーカリを消化できる体を作るためで、落合さんは、コアラの世界では当たりことだとおっしゃっていました。なんでもコアラのコロコロとしてフンはユーカリの匂いがするそうですよ)
ユーカリは1日100キロ、年間34トン!?
※野生のコアラはユーカリしか食べないそうですが、平川動物公園では何種類のユーカリを与えているんですか?
「ユーカリはたくさん種類があるんですけど、コアラが食べているのってだいたい80種とか90種ぐらいって言われているんですね。登園ではそのうちの13種類から14種類ぐらい栽培していますかね」
●本に、平川動物公園で飼育しているコアラ18頭が、年間に消費するユーカリの量がおよそ34トンと書かれていましたけれど(笑)、本当なんですか?
「そうですね。だいたいイメージとしては毎日100キロのユーカリの枝と葉っぱを使っています」

●凄い! 「ユーカリを制するものはコアラ飼育を制す!」と、本にも書かれていましたけど、大事なんですね!
「そうですね。もうこれしか食べませんから、ユーカリの供給が滞ると(コアラの)食べ物がなくなってしまうことになるので、ユーカリの栽培と供給態勢にはすごく気を遣っていますね。
八百屋さんとかで(ユーカリが)売っていればいいんですけど、売ってないんですよね。だからコアラを飼っている動物園はすべて、コアラのユーカリは栽培して供給できる態勢にしています。ないと終わってしまいますからね、すごく大事にしています、ここは」

●敷地内にユーカリ畑があるんですか?
「動物園の中にもユーカリの畑は何か所かあるんですけど、実は賄い切れないんですよ、動物園の畑だけだと・・・。当園では2万本ぐらいのユーカリを管理していまして、畑の数が40か所ぐらいあるんですよね。当然、動物園だけじゃなくて、遠くは鹿児島のロケットの発射基地がある種子島にあったり、温泉で有名な指宿にもあったりします」
●分散させているんですね。
「そうですね。これには理由があって、ひとつは台風が来た時にユーカリの葉っぱが飛んでしまったり、枝が折れてしまったりするんですよね。1か所にすべて植えていると、その畑が集中的に被害に遭ってしまうと、(コアラに)あげるユーカリがなくなってしまうので、リスク分散も込めて、たくさんの所、住宅地の中にある畑もあれば、山の中にある畑もあって、風の当たり方が違ったりするので、リスク分散で分けているっていうのもあるんです。
あと、今からどんどん寒くなりますよね。やっぱり温暖な場所を好むユーカリを栽培していますので、いくら鹿児島と言えども、たまに雪が降ったり霜が降りたりするんですよ。そうなるとやっぱりいい状態の葉っぱが手に入らないので、あったかい種子島や指宿といった、あったかい地域にもユーカリを植えています」

(編集部注:落合さんいわく、コアラの飼育でいちばん気を使うのは、健康管理。寝ている時間が長いコアラは体調の変化がわかりにくいため、寝ている姿勢やユーカリの食べ方、そしてフンの観察など注意深く見て、ちょっとしたことでも「疑って」かかるそうです)
尊いコアラに学ぶ
※日本では、コアラの繁殖のためにどんな取り組みがありますか?
「コアラっていう動物は、やっぱりユーカリの管理とか供給がすごく大変というか、ほかの動物と違うので、どこの動物園でも飼える動物ではないんですよね。今(国内では)7つの動物園で飼育しているんですけど、ひとつの血統だけ残してしまうと、仮にその血統が病気に弱かったりとか、小型な血統だったりすると、本来のコアラっていう動物を残せなくなるんですよね。
ですから、いろんな血統、血筋、遺伝子を取り込みながら増やしていきたいなと思っているんです。それには実を言うと100頭ぐらいの個体がいたほうが、20年30年先を見据えると、それぐらいいたほうがいいよねっていう話になっているんですね。
そうなってくるとやっぱりある程度、ほかの動物園さんと協力しながら、いきなり100頭は無理なんですけど、現状54頭ぐらい国内にいるので、これがまずは70頭ぐらいに増やして、そこから先はいろんな飼育園とか飼育施設を拡充して、コアラという動物を安定的に未来に向かって残していけるような態勢を協力して残していけたらなとは思っていますね」

●コアラの飼育を担当されて5年ということですけれども、日々コアラと接して何かコアラから教えてもらったみたいなことってありますか?
「毎日コアラを見ていて、彼らって、可愛いイメージが先行していますけど、やっぱり生きることにすごく貪欲なんですよね。ユーカリひとつ食べる仕草にしてもそうですし、繁殖する時のオスの猛々しい鳴き声とか、そういった姿を見ていると、挑戦しているじゃないですけど、彼らってやっぱり日々当たり前のように必死になって生きているっていうのが感じるんですよね。
で、可愛いんですけど、そのひとつひとつの仕草が非常に尊いというか尊敬できるなと思うんですよね。そういった仕草とか、コアラっていう動物を日々見ながら、(私たちも)一生懸命生きていかないといけないっていうわけじゃないんですけど、もっと挑戦的、チャレンジしていかないといけないのかなっていうのは、本当に感じるかな、っていうか、感じていますね」
●将来の夢があったらぜひ教えてください。
「今、動物園でコアラを多くのかたにご覧いただいているんですけど、当園の特徴としてコアラがいる空間に入っていける施設があるんですね。ガラスがなくてそのままの空間でコアラをご覧いただけるんですよ。
そこには、コアラが暮らしている現地の植物を植えていたりとか、当然ユーカリも植えているんですけど、動物園に来てコアラが暮らしている現地の森を、来園者のみなさんに体験してもらえるような施設にできたらなと今思っているんです。
まだまだその時点には達してないんですけど、そういった空間でコアラを見てもらって、野生のコアラを少しでも感じていただけるような場所にできたらなと思っています」

(編集部注:オーストラリアの固有種コアラは現在「国際自然保護連合IUCN」の絶滅危惧種に指定されています。減っているおもな原因は、気候変動や森林火災による生息地の減少で、市街地にまで進出し、交通事故で命を落とすコアラも数多くいるとのことです。
落合さんは以前、オーストラリアの施設を視察したことがあって、その時に感じたのは、平川動物公園の飼育態勢は、晴らしいといえるレベルにある。やってきたことは間違っていなかったと自信にもつながったそうです。平川動物公園のコアラ館、ぜひ行って見学したいですね)
INFORMATION
『すごいコアラ! 〜飼育頭数日本一の平川動物公園が教えてくれる 不思議とカワイイのひみつ』
動物園のアイドル的なコアラの可愛い写真が満載。一頭一頭、名前がついているのでそれを見て、コアラ館に行くと、推しが見つかるかも知れません。コアラの生態がわかりやすく解説されているほか、なにより、飼育員のみなさんの奮闘ぶりやコアラへの想いを感じる一冊です。
新潮社から絶賛発売中! 詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎新潮社:https://www.shinchosha.co.jp/book/355861/
鹿児島市にある平川動物公園のサイトもぜひ見てください。

◎平川動物公園:https://hirakawazoo.jp
2024/11/17 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、石川県立大学・生物資源環境学部の准教授「北村俊平(きたむら・しゅんぺい)」さんです。
北村さんのご専門は植物生態学で、植物と動物のつながりを「種子散布」の視点で研究。調査のメイン・フィールドはタイの熱帯の森で、果実と動物たちのつながり、おもにクチバシの大きな「サイチョウ」という鳥が植物のタネまきに、どんな役割を果たしているのかを調べていらっしゃいます。
そして先頃、『タネまく動物〜体長150センチメートルのクマから1センチメートルのワラジムシまで』という本を出されました。
この本は、ツキノワグマの研究で知られている東京農工大学大学院の教授「小池伸介(こいけ・しんすけ)」さんと北村さんのおふたりが中心となって編集・執筆。
おもに今後の研究を担う学生のために「種子散布」の最新研究や知見がまとめられています。原稿を寄せているのは、北村さん、小池さんを含め、その道の研究者、総勢18名。
このように説明すると、難しい本なのかなと思われるかも知れませんが、タネをまく哺乳類、鳥、そして昆虫などの小さな生き物、その3つのカテゴリーに分けて、それぞれの最新研究などをわかりやすく解説してあるので、手軽に読めますよ。
また、以前この番組にご出演いただいたイラストレイター「きのしたちひろ」さんの、可愛くて親しみやすいイラストが添えられていて、そのページで伝えたい内容がひと目でわかるようになっているのも特徴です。
きょうは北村さんに「種子散布」の最新研究を含め、植物と動物のディープな関係についてうかがいます。
☆写真協力:北村俊平、イラスト協力:文一総合出版

種子散布〜「動物散布」
※この本では種子散布でも、いろんなタイプがあると書かれています。改めて、教えていただけますか?
「今回、本で特に取り上げているのは、動物の助けを借りてタネをまくグループで、それをまとめて『動物散布』と呼んでいます。で、大きく3つグループがありまして、『被食散布』『貯食散布』、それから『付着散布』に分けられます。
順番に説明すると、最初の被食散布は、タネの周りを例えば甘い果肉なんかで覆って、タネを運んでもらう報酬として、魅力的な食べ物を動物に提供するような仕組みになります。私たちが普段、果物として食べている果実をイメージしていただけるといいかなと思います。これがひとつ目です。
ふたつ目の貯食散布は、哺乳類だとネズミやリスの仲間、鳥だとカケスとかホシガラスっていう鳥が含まれるんですが、タネを食べ物として利用する動物の行動を利用した仕組みになります。
ネズミやリスはあとで食べるために、食べ物を蓄える行動をとるんですが、隠したものを全部食べるわけではなくて、一部のタネが食べ残されるようなこともあります。この食べ忘れたタネから発芽することによって、タネまきを成功させるような仕組みになります。
最後の付着散布は、ちょうどこの時期だと、みなさん野山を歩くとズボンとか靴下に植物のタネがいっぱいくっつく経験をしたことがあると思いますが、こういった動物が気がつかないうちにタネをその動物の体にくっつけて、要はただ乗りしてしまうような仕組みを持ったものになります。

で、最初に紹介した被食散布と2番目の貯食散布は、動物にとっても植物にとってもメリットがある、ウィンウィンの関係になるわけですが、最後の付着散布は動物側はただタネを運ぶだけなので、そういったメリットはないです。
今説明したのは動物が絡む話なんですが、もうひとつ動物の助けを借りないグループもあって、ひとつは風の力を利用してタネを飛ばすようなグループで、多くのタネは風に乗るわけで、ちっちゃくて軽い特徴があります。
風を捉える仕組みとして、タンポポの仲間みたいに綿毛が発達しているものだったり、モミジの仲間みたいにタネに翼がついたものとか・・・あとはランの仲間はすごく小さいタネを作るので、何も仕組みがなくてもふわふわっと風で飛ぶようなものになっています。
あとは水の力を利用するようなグループもあって、例えば雨粒が当たった衝撃でタネをばらまくようなものだったり、川の水の流れとか、ヤシの実のように海の流れ、海流によって運ばれるようなものもあります。
最後にホウセンカっていう植物がいるんですけど、ああいう植物では果実がぱっと割れる時に、その時の勢いでタネが弾き飛ばされる、『自動散布』と呼ばれるような仕組みなんかもあります」
タネまく動物の代表、ツキノワグマ

※大きな動物というと、日本にはツキノワグマがいますよね。クマはやはり「種子散布」に貢献しているんですよね?
「そうですね。日本の森でタネをまく動物の代表選手で、この本の編集者でもある小池さんが長年にわたって研究しています。
クマというと、肉を食べている肉食動物のイメージを持っている人が多いんじゃないかなと思うんですが、実際は食べているものの大部分は植物です。特に夏以降になると果実がほとんどを占めていて、それらの果実のタネをまくことが知られています」
●冬眠前にたくさん食べるイメージがあるんですけど、主食は何になるんですか?
「今の時期、ちょうどこれくらいの季節になってくると、やっぱりドングリが主食と言われていて、ツキノワグマは冬眠前にたくさん脂肪を蓄える必要があるんですが、秋にはそのドングリをおもに食べているようです」
●ドングリ以外だと、どんなものを食べるんですか?
「クマは多分ドングリをいちばん食べたいんですが、実はドングリの仲間は、年によってたくさん実る年とそうじゃない年、よい年と悪い年があることが知られていますね。ドングリの実りのよい年にはドングリを食べまくっているんですが、実りが悪いと、本当はドングリ食べたいんですけど、ドングリがないので、ほかの果実をたくさん食べるようなことになります。
ドングリの実りのよい年に、クマのフンを拾ったりすると、中にはクマに噛み割られたたくさんのドングリが入っているんですが、今年はたまたま私のいる石川県では、ツキノワグマの主食になるブナのドングリの実りが、あまりよくない年になります。
で、数日前にも調査地のイチョウの木の下に(フンが)いくつかあったんですけど、それを見てみるとドングリは全く入ってなくて、イチョウの木の下で多分イチョウ(の実を)食べたんでしょうね。たくさんの銀杏ですよね。
それからあと、山の中にキウイフルーツの仲間でサルナシっていう植物が、ちっちゃいキウイフルーツみたいなものなんですけど、その小さいタネがたくさん入っていました」
●クマの種子散布で特徴なことっていうと、どんなことになるんでしょうか?
「ひとつは、クマってやっぱり大きな生き物ですので、大きな体を維持するためにたくさん食べるっていうことがあります。で、野生のサクラの仲間だと一度に数千個、人間が食べるサクランボほど大きくはないですけど、野生のサクラの仲間も小さなサクランボみたいな実を付けます。そういうのを数千個、一度に食べたりします。
野生のサクラの果実ってクマだけではなくて、ニホンザルとかヒヨドリみたいな鳥も食べたりしますけど、植物からするとクマがやってくると、実らせた果実を非常にたくさん食べてくれる、だからクマが来てくれるかどうかで、たくさんのタネが運ばれるかどうかが決まってくるので、結構大事な存在になりそうですね」
(編集部注:北村さんによると、クマの糞に含まれている数百から数千のタネは、ネズミにとってはとても魅力的で、ほとんどネズミが食べてしまうそうですよ)

※ニホンザルも森の世代交代に関係しているそうですね。このあたり、ご説明いただけますか?
「リスとかネズミは、先ほど貯食散布っていう、タネを隠したりすることでタネまきに貢献している話を少ししたんですが、ニホンザルも実はいろんな果実、果実が非常に好きな動物のひとつですね。先ほど紹介したツキノワグマと比べると、やっぱり1頭あたりの大きさはずっと小さいわけですけど、サルはクマと違って群れで行動する生き物です。
30頭から50頭くらい、きっとそれぐらいの数がひと群れになって移動しているわけです。サル1頭自体が食べてタネをまく数はクマと比べれば、ずっと少ないんですけど、群れ全体にするとそれが 30倍とか50倍っていうことになるので、一度にたくさんの個体がやってきて、結果的にたくさんの果実を食べてタネをまく点では、ツキノワグマに匹敵、もしくはそれ以上の果実を食べてタネをまくようなことになっているのかもしれません」
「日本中でタネをまく」ヒヨドリ
※鳥がタネを運ぶことは知られていると思いますが、都会の公園や住宅地でもよく見るヒヨドリ、この本では「日本中でタネをまく」と書かれていました。そうなんですか?
「ちょっとオーバーな表現でもあるんですけど、ヒヨドリは多分みなさんどこかで姿を見たことがあるだろうし、今ちょうど外でもヒヨドリが鳴いているんですけど・・・ひとつの特徴としては、日本国内で木があるところだったら大体どこにでもいて、そこの自然環境を利用していて、そこに生えている植物の、非常に多くの植物のタネをまいている点がひとつの特徴だと思います。
ヒヨドリが実際、どれぐらいの数の植物のタネをまいているのかを調べた研究があるんですけど、少なくとも200種類以上の果実を食べていて、そのタネをまいていることが知られています。
でももっと狭い範囲、大学のキャンパス内とか、そういった狭い範囲で見ても少なくとも50種から80種ぐらいの果実を食べていることが知られていますので、一種類の生き物が食べる種数としては、すごく多い種類の果実を食べています」

●植物側からしたらヒヨドリって、やっぱりありがたい存在っていうことなんですか?
「そうですね。すごくいろんな果実を食べている理由としては、ひとつはヒヨドリは1年中日本にいる鳥で、春から冬までずっといるので、年間を通して果実を食べている、それからヒヨドリは果実をすごくよく食べるんですけど、日本で果実を食べる鳥の中では比較的大型のほうになります。
鳥の場合は、先ほど話したクマとかニホンザルみたいに、手を使って果実を食べることができずに、くちばしでついばんで、それをぐっと飲み込むしかないんですね。だから口の大きさがすごく大事になってきて、大きな鳥のほうがいろんな大きさの果実を食べることができるっていう点がひとつ特徴です。
飛び方もヒヨドリってすごく器用で、“ホバリング”って言って少し羽ばたいて空中で止まるような飛び方もできるので、普通の鳥だと枝先でつかめないような果実までしっかり利用することができたりします。
多分ヒヨドリは日本にいる鳥の中で、いちばん果実が好きな鳥なんじゃないかなと思います。ちょっとしか実ってないような果実でも、”それを食べに行くんだ!” っていうような形でやってきて、しっかり食べていくこともあります。
今の時期、秋から冬にかけて、森の中はすごくいろんな植物が果実を実らせているわけなんですけど、地面の近くの、すごく小さな木だったりすると、数個しか果実が実っていないような場合があるんです。そういった果実でも、自動撮影カメラを設置しておいて、どんな動物が食べに来るのかなって調べてみると、ずっと誰も来ないなと思っていたら、ある日突然ヒヨドリがやってきて、残っていた果実を全部食べて飛んでいく姿が写ったりします。
住宅地の庭なんかにも、お正月の縁起物で使われる、赤い実をつけるマンリョウとかオモトっていう植物があるんですけど、そういった果実にも、カメラ置いといてみると、やっぱりヒヨドリがやってきて果実を食べて、タネを運んでいたりするような姿が撮影されたりしています」

(編集部注:ヒヨドリのほかにも、身近な鳥としてメジロやカラスも果実を食べ、結果的に種子散布に協力していることになるそうです。
植物にとって、空を飛べる鳥は遠くまでタネを運んでくれる、ありがたい存在だと思いますが、アホウドリやカツオドリなどの海鳥も、陸地に降りた時に羽毛にタネがつくことがあるので島から島へタネを運ぶ、これも「付着散布」になるんですね)
カタクリのタネを運ぶアリ
※昆虫と植物の関係でいうと、この番組のスタッフからアリがカタクリのタネを運ぶという話を聞きました。アリには何かメリットはあるんですか?
「アリは基本的には雑食性で虫を食べたり、ほかの生き物を捕まえて食べたりするんですけど、花の蜜に来たり果物の果肉も食べたりするのと同じような形で、地面に落ちているタネも食べ物として巣に運ぶことがあります。
その場合はタネそのものを食べてしまうので、ほとんどアリに食べられてしまって、あまり植物にとってはいいことはないんですけど、今話に出てきたカタクリは、実はちょっと変わった植物です。カタクリみたいな植物、一部の植物なんですが、小さなタネに“エライオソーム”って呼ばれている、お弁当みたいなものがついているんですね。
そのエライオソームの成分を調べてみると、動物性の脂肪分みたいなものが入っていて、アリにとっての栄養分になると同時に、なぜかわからないんですけど、アリがそのタネを運びたくなるような成分が入っているみたいです。
たからアリさんは、エライオソームに惹かれてタネを持って巣まで運んでいって、このエライオソームだけを食べて、残ったタネの部分は巣の中とか巣の外のゴミ捨て場みたいなところに捨てられることで、タネまきが完了するような仕組みになっています。
エライオソームを実際食べることができたアリと、できなかったアリを比べると、アリの巣で生まれてくるアリの数がどうも増えたような事例もあるみたいですので、栄養として十分そのアリにとっても役立っているみたいです」

●メリットはあるんですね~。
「そうですね~。アリがちゃんと食べることでアリ側も増えているんだよっていうことがわかっている、こういう例はすごく珍しいですね。動物側が果肉を食べてどれぐらいメリットがあるのかは、実はよくわからないことが多いんですけど、アリの例ではそういうふうな形で、ちゃんとアリの数が増えていることが示されているようです」
●この本に、カタツムリとかナメクジもタネを運ぶって書かれていましたけれども、本当なんですか?
「一見するとそんな感じはしないんですよね。もともと研究が進んでいるヨーロッパの事例になるんです。先ほどアリがタネを運ぶ事例で紹介した、エライオソームがついた植物のタネ、それを大型のナメクジ、10センチぐらいあるナメクジの仲間がタネとエライオソームを食べて、タネだけ排出するっていうふうな形でタネをまいているそうです。
で、私、日本でもそういう事例ないかなと思って調べていて、日本の事例だと、うちの近所に“ノトマイマイ”っていう大型のカタツムリがいるんですが、その一種がヘビイチゴとか、ヤブヘビイチゴっていう植物のタネを、どうも運んでいる可能性はありそうです」
(編集部注:北村さんによると、研究室での実験では、カタツムリがヘビイチゴのタネを食べ、糞として出されたタネをまくと発芽したそうです。実験的にはタネを運んでいる可能性はあるだろうとのことでした)
温暖化でタイミングがずれる!?
※今年の夏も、酷暑といえるような日が続きましたね。地球温暖化は当然、植物にも影響を与えていると思いますが、種子散布にも影響は出ていますか?
「今年の夏とても暑くて、その影響がどういった形でこの種子散布に影響するのかっていうのは、すぐにはわからないんですが、少なくとも地球温暖化で平均気温は徐々に上がっているのは間違いないわけです。
例えばその結果として、日本だと秋とか冬にたくさん果実が実るようなことになっているんですが、そういった秋に実る果実の数とか、あと果実が熟すタイミング、気温によって早く熟したり、遅く熟したり、もしくは気温が下がらないと熟さないパターンがあったりするんですけど、そういったタイミングが変わってくることは予想されます。
そうなるとその果実をたくさん食べていた鳥たち、渡り鳥、今ちょうど夏鳥は南に帰って、冬鳥が北からやってくるような時期になるんですけど、そういった渡り鳥の移動パターンとか、そもそも通っていた所が変わったり、タイミングも変わってくるんじゃないかってことは考えられます。
今まで秋の果実と渡り鳥の間で見られていたつながりが変化していくことは考えられるんですが、じゃあどう変わるの? って言われると、なかなかすぐには予測ができないのが今のところの現状です」
●今回この本のおもなテーマになっている「動物散布」で、世界の研究者が注目していることってどんなことなんでしょうか?
「ひとつは、先ほどもあったような地球温暖化との関係で、温暖化することによって、そのスピードについていける速さで、自ら動くことのできない植物が移動することができるのか? だから動物がタネを運んでくれるのか? っていうことになります。
植物は動けないので、今までよりも生息環境の気温が上がると、より涼しい場所、例えば標高の高いところとか、あと日本であれば、より北のほう、そういった方向に向かって移動する必要があるんですけど、地球規模の環境変動に植物側なり、そのタネを運んでいる動物が対応していくことができるのかっていうところになると思います。
もうひとつは、私がタイでやっている研究とも少し関係するんですけど、タネを運ぶ動物がいなくなってしまうことで、生態系にどういった影響が及ぶのかっていうことの評価になります。具体的にいうと、タネをまく動物が絶滅していなくなると、その動物にタネまきを依存していた植物にも影響が及ぶんじゃないかっていうことが心配されています。
私が研究していたサイチョウっていう大きな鳥もそうなんですけど、大型の動物は私たち人間の、例えば狩猟対象になったり、あと森林伐採みたいな生息環境が破壊されることで絶滅しやすいグループになります。
こういった動物がおもにタネをまいていた植物は絶滅せずに、残っている動物が絶滅した動物と同じようにタネをまくことができるのか。それともやっぱりタネをまくことができずに、その植物が絶滅していくのか・・・で、そういった植物がいなくなると、結局その場所の植物の種類も多分変わっていくことになると思うんですけど、そういったことが起きていくのかが、多分興味を持たれているところじゃないかなと思います」
(編集部注:植物と動物の関係を、種子散布の視点で20数年研究している北村さんですが、それでもわからないことが多い、だからこそ、やりがいのあるテーマだとおっしゃっていましたよ。今後は今までタネをまく動物と考えられてこなかった生き物たち、例えばカメやトカゲなどの爬虫類、ナメクジやカマドウマなどの無脊椎動物などを調べてみたいそうです。
最新の研究では、ワラジムシやダンゴムシもタネをまいていることがわかってきているそうですよ。植物と動物の関係を明らかにすると、生物の多様性を理解するのにもつながる、そうおっしゃっていました。今後の研究に期待したいと思います)
INFORMATION
『タネまく動物〜体長150センチメートルのクマから1センチメートルのワラジムシまで』
植物がタネをまく「種子散布」の中から、おもに「動物散布」に焦点を当てた一冊。原稿を寄せているのは北村さん、小池伸介さんを含め、その道の研究者、総勢18名。タネをまく哺乳類、鳥、そして昆虫などの小さな生き物、その3つのカテゴリーに分けて、それぞれの最新研究や知見をわかりやすく解説してあるので手軽に読めますよ。イラストレイター「きのしたちひろ」さんの、可愛くて親しみやすいイラストにも注目です。ぜひ読んでください。
文一総合出版から絶賛発売中! 詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎文一総合出版:
https://www.bun-ichi.co.jp/tabid/57/pdid/978-4-8299-7255-7/Default.aspx
2024/11/10 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンは、シリーズ「SDGs〜私たちの未来」の第22弾! 今回はスポーツ編として、ふたつのプロジェクトをクローズアップ!
まずは、廃棄されるゴルフボールをマーカーやピアスなどにアップサイクルする「NEP!! GOLF」、そして、役目を終えて捨てられるバスケットやバレーのボールを加工してポーチやコインケースなどに生まれ変わらせる「RE:BALL PROJECT」をご紹介します。
☆写真協力:NEP!! GOLF、八橋装院
「NEP!! GOLF」〜ロストボールをサップサイクル!
※まず、ご紹介するのは、廃棄されるゴルフボールをアップサイクルする「NEP!! GOLF」。これは、広告代理業務などを行なう会社「6G」が進めているプロジェクトです。
代表の「村岡光太郎」さんによると、ゴルフ場で発生するロストボールは回収され、半分は再販売されるそうですが、残りの半分は、汚れや傷があると売り物にならないため、廃棄されます。その方法は燃やすか埋めるか、当然、処理費用がかかります。
そこで村岡さんたちは、その課題に取り組み、3年ほど前から廃棄されるロストボールのアップサイクルを進めていらっしゃいます。

●プロジェクト名「NEP!! GOLF」のNEPには、どんな意味があるのでしょう?
「これは“Nude Earth Project”を訳して「NEP(ネップ)!!」にしています。(NEPの)後ろにドッキリマークがふたつありますが、これはヘルプみたいな、“助けて”の意味で、ドッキリマークをふたつ付けているんです」
●なるほど・・・。
「“Nude Earth Project”ってどういうことかっていうと、“裸の地球”っていうのをより人っぽくしたくて・・・裸の地球っていうと正しくは、“Naked Earth”って言い方をするみたいなんですけど・・・。
僕がイメージしたのは、地球自体は人間が何もしなければ、自然にずっと継続していけるものなのかな〜と、勝手にそう思っています。でもゴミを捨てる、二酸化炭素を出す、木を伐採して森をなくしていくとか、いろいろやると、それだけで地球ってころころ違う運命をたどっていくじゃないですか。
“裸の地球”って要は、地球自体は何もしてないよ、僕らがなんかしているから、結果が変わっていっているんだよって考えて、Nude Earthは“裸の赤ちゃんの地球”みたいなイメージで考えています。それにドッキリマークをつけて、“助けて!”っていう意味で、裸の地球を助けたいよね、だからなんとか、もとに戻していく方法はないだろうかっていうプロジェクトです。
“GOLF”に関しては、今回はゴルフボールっていうテーマでアップサイクルをして、ゴミを減らしていこうって思ったので「NEP!! GOLF」なんですけど、これが違うアイテムが見つかれば、“NEP!!OOOO”に変えてやっていこうとは思っています」

●なるほど、いろんな意味が込められているんですね~。サイトを拝見したんですけど、年間再販できないロストボールが国内だけで約7500万球も出るって書かれていて、そんなに多いんですね。驚いちゃったんですけど・・・。
「そうですね~。一応、ゴルフ人口の話があると思うんですけれど、どこからこの数が出ているかっていうと、一般社団法人『日本ゴルフ場経営者協会』っていうところが毎月のラウンド数を出しているんですよ。どれぐらいラウンドがあったかっていう・・・。
たとえば先月だと800万ラウンドぐらい、(国内の)ゴルフ場は2170か所あるんですけど、800万ラウンドありましたよと。1年間、平均すると、あんまりやってない日もあるので、トータルすると2021年の時は大体7500万ラウンドぐらいだったんですよ。
7500万ラウンドあるってことは、僕なんかはこの間(ゴルフ)デビューした時に、ボールを12球ロストしたんですけど、みなさんも1球2球はなくすと思うんですよね」
●失くしちゃいます。
「そうすると、すごく少なく見積もっているんですけど、大体年間7500万ラウンドから8000万ラウンドあると、ひとりが2球OBした場合、(ロストボールが)1億6000万球出ますと。(回収する)ボール屋さんが、1億6000万球の中で “半分くらいはロストボールとして出せるよ!”っておっしゃっていたんで、半分は出せない、っていうことは捨てるものなんですね。で、当然(ゴルフ場内で)見つかってないボールもあるので、これ以上あることは間違いないんです。
ゴルフ場内で出ているロストボールは、多分2億球とか言ってもおかしくないんですけど、そのうちの1億球ぐらいは、再販できないからゴミになるか、そのままゴルフ場の中で土に埋もれていくかっていうような状態になっているところから7500万球っていう・・・」
●確かに売られているロストボールもありますけれども、再販できないロストボールの場合は現状捨てられちゃっているっていうことなんですね。
「そうですね」
(編集部注:村岡さんによると、ゴルフボールの素材は外側はウレタン、内側は合成プラスチックで、メーカーによって材質が違うため、粉砕したとしても、それをそのまま再利用することは難しいそうです)
端材も再利用、無駄なく使う
●アップサイクルして商品化されたアイテムって本当にどれも可愛いですね。
「ありがとうございます」
●きょうはスタジオにたくさんお持ちいただきました。ありがとうございます! たとえばサボテンのポットですけど、ゴルフボールの上を削って、中をくり抜いてあるんですね?
「そうですね。少しだけくり抜いています」

●つまり、このサボテンの鉢がゴルフボールってなっているってわけですよね。これ(中に)土を入れているんですか?
「これは挽き終ったコーヒー(のカス)ですね」
●コーヒー! え~っ!
「近所のちょっと有名なコーヒー屋さんで乾燥してもらって、それをいただいています。捨てるものなんで・・・」
●そこにもちゃんとエコというこだわりがあるんですね!
「そうですね」
●この土台となっている黒い丸い部分は何ですか?
「これは靴修理会社さんの、かかとの修理とかに使うソールの部分なんですね。大きな正方形からソールも切り抜くんですけど、その時にやっぱり四隅に端材が出るんですね。それを捨てているっていう話だったので、じゃあそれを土台にさせてもらおうっていうことで、くり抜いてもらってます」
●すごい! じゃあこの製品はすべてに無駄がないということですね。
「そうそう! 上のもの以外は!(笑)」
●ピアスとかもあるんですね。ゴルフボールの表面の素材をそのまんま小さくカットしたものですけど、ゴルフ女子にはたまらないですね~、可愛い!!
「ぜひ使ってほしいです!」

●それから、グリーン上で使うマーカーもゴルフボールの表面がそのまんまで、くり抜いてありますけれども、どれも可愛いですね~。
「ありがとうございます!」
●商品化するときのアイデアとかデザインは、みんなで話し合って決めるんですか?
「はい! もちろんみんなで考えるんですけど、うちの会社自体が男しかいないんです」
●はいはい(笑)
「なので、なかなかそういう可愛らしいものを考える時に、どうしたらいいかな? っていうのはあったんですけど、まず最初はキーホルダーから始まりました。
キーホルダーって付けてはくれるんですけど、“それ以外になんかないの?”って聞かれることが多くて、買ってくれたかたたちからアイデアを貰いながら、できそうな商品を作っていくという形になっていますね」
●お客さんからの声も反映されているんですね。
「そうですね」
(編集部注:村岡さんによると、現在、カラーボールを使った新商品を開発中で、緑を増やすための、寄付につながる仕組みを検討しているそうです)

※ゴルフボールをカットするなどの作業は社内で行なっているそうですね。その時に出た端材などは、どうされているんですか?
「その端材を集めて、最初はバイオ燃料がいいんじゃないかってことで、いろいろプラントを作って燃やすと、燃焼効率がすごくいいって思ったんですけど、二酸化炭素とかいろんなこと考えると、燃やさないでそのまま活かしたほうがいいんじゃないかっていう考えがあって・・・。
で、(きょうはスタジオに)靴のソールを持ってきているんですけど、靴のメーカーさんと相談して、(ゴルフボールの)削りかすを7パーセント混ぜているソールなんですね。たまたま先ほど言った、土台になっている靴の・・・これですね」
●サボテンの土台になっている?
「サボテンの土台を作っている靴屋さんがソールも作られているって話だったんで、ちょっと(ソールに)混ぜてもらえません? って言って作っているソールなんです」
●ちょっと触ってみてもいいですか? 弾力があってフカフカですね。ベージュが基本となっていて、中に小っちゃな、ピンクとか白とかオレンジとかありますけど、これが・・・?
「ゴルフボールの中の“コア”って言われるゴムの部分ですね。(ソールは)白とか黒のゴムでも作れるんですけど、そうすると見えなくなってしまうので、あえてこのラバーのそのままで作っているんですね」
●端材もちゃんと次の商品につながっているってことですね。
「そうですね。次の商品、何かに使えないかっていうのは日々考えています。むしろ、聴いているかたで誰か教えていただければ・・・協力してもらえるとありがたいんですけどね」
ゴルファーの意識
※ロストボール問題は、やはりゴルファーひとりひとりの意識が大事だと思います。その辺はいかがでしょうか?
「むしろ、みなさんがどう思っているかですよね。ゴルフボールのことを考えたことはありますか? って思わないですか。僕なんかはゴルフやったばっかりですけど、ボールのことなんて考えてないですもんね。自分が打った後にOBしちゃった、“いいから早く次、打ってよ!”って言われて打つじゃないですか。その時にロストボールのことって考えないですよね。
だからそういうことを考えると・・・(ロスとボールが)ずーっと発見されなかったら、土に還らないんで置きっぱなしなんですよね。それってゴミじゃないですか。今、廃タイヤとかいろんなゴミが問題になっていますけど、スポーツの中で、球技の中で、ボールのゴミって多分圧倒的にゴルフボールが多いと思うんですよ。
そこを意識しろって言っても、これまでの期間、そういうことがなかったので、なかなか意識するのは難しいと思うんです。ただ現状それがよく思われてないことは、みんなうっすら、ご年配のかたたちは知っていて、山が汚れているよねとか・・・イメージ的にですよ。
だから僕らは、それをちょっと気づいてもらえるようになればいいかなと思って、この事業やっているんですね。だからこのラジオを聴いていただいたかたが、 “ロストボールで再販できないものもあるんだ!”って知ってもらって、そのままゴミになって、そのゴミが有害なんだなとか、そういうゴミって減らしたいなって思ってくれたら、ちょっと嬉しいなっていうふうに思っています」
(編集部注:「NEP!! GOLF」で販売しているマーカーやピアス、キーホルダーなどの商品はオンラインで購入できます。やはりゴルファーに大人気で、コンペの賞品やお父さんへのプレゼントなどに利用されているケースが多いそうですよ。商品のラインナップなど、詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください)
「RE:BALL PROJECT」〜思い出のボールをアップサイクル !
前半では、ゴルフボールのアップサイクル・プロジェクト「NEP!! GOLF」をクローズアップしましたが、後半は役目を終えて捨てられるバスケットやバレーのボールを加工して、新たなグッズに生まれ変わらせる「RE:BALL PROJECT」をご紹介します。
これは、広島市にある衣服の縫製会社「八橋装院」が進めているプロジェクトです。1959年に創業された八橋装院は現在、国内有名DCブランドの縫製を手掛けるなど、長年、日本のファッション産業を陰で支え続けています。
2013年には自社ブランド「FUKUNARY」を立ち上げ、人工皮革やレザー、帆布などを使ったお洒落なバッグや財布などを製造・販売。さらに、競技用のボールを主力商品とする地元の企業「MIKASA」とコラボして、ボールの生地を素材に、軽くて耐久性のあるバッグなどのファッション・アイテムを開発、「FUKUNARY feat. MIKASA」として展開されています。

そんな中、この番組が注目したのが、八橋装院が取り組んでいる「RE:BALL PRO-JECT」です。
※それでは、そのプロジェクトを立ち上げた八橋装院の社長「高橋伸英」さんにお話をうかがいます。

●「RE:BALL PROJECT」のサイトを見ると、使い古されたバスケットボールやバレーボールの素材をそのまま裁断して作った、ポーチやコインケースが載っていました。ボールのキズなども活かされていて、メモリアルなグッズになっているな〜と思ったんですが、どうなんでしょうか?
「『RE:BALL PROJECT』に関しては、使い古したボールを使うことがマストです。私たちがターゲットにしている、想定しているところはやっぱり部活動だったりするんですね。だから学生時代に、中学校、高校、大学でプレイしていた人が・・・ボールには寿命があるので一定数廃棄されます・・・その廃棄されるものを活かして、その人たちの思い出作りに寄与できたらいいなっていうビジネスなんですね。当然、古いボールを活かす以上はキズが残っていたりとか、チームの名前が入っていたりとかっていうのもありますよね。
但し(ボールから生地を)取る位置が、ある程度決まっているので、(チームの)名前が入る入らないは指定はできないんですけど、使った証(あかし)というか、キズがついたところはいくらかは入るというか、全体的にキズがあれば入ってしまうんですね。
それがペンケースだったり、眼鏡を入れるケースだったり、コインケースになって、自分のバッグの中に入っている、手元にある、それを見ることで、昔、頑張った自分を思い起こして、私はこれで頑張っていた、俺はこれで頑張っていたんだって、社会に出た時にまた力を与えてもらえるものになればいいなっていう思いで、この『RE:BALL PROJECT』をやっています」

●夢中に、がむしゃらに頑張って部活をやっていた、その時の思い出がポーチなどになって身近にあるっていうのは、すごく嬉しいことですよね!
「そうですね。プレイヤーにとってみたら嬉しいと思います。だから後輩だったり父兄さんだったりが依頼してくることが多いんです。ほとんどが送り出すほうのかたからの依頼ですね」
(編集部注:高橋さんによると、バスケットやバレーのボールは中にゴムがあるので、商品づくりがとても大変で手間がかかるそうです。
衣服の縫製とは違って、相手はボールですから、職人さんの優れた技術やノウハウがあって、やっとできあがるんでしょうね。)
もっと広めたい「RE:BALL PROJECT」
●この番組のリスナーさんが、自分が持っている思い出のボールからグッズを作って欲しいと思ったら、どうすればいいですか?
「作れるものには制約がありまして、先ほども言いましたペンケースであったりコインケースが主軸にはなるんですけども、弊社ホームページに注文サイトがあります。そちらに必要事項を書いてメールをいただきたいですね。あとはそこに注意事項がありますので、よく読んでいただいて注文していただけたらと思っています」
●今後、何か新たに取り組みたいこととか、今後の「RE:BALL PROJECT」の展開はありますか?
「SDGsに関わる『RE:BALL PROJECT』がなかなかできていないっていうのがありますね。これがもうちょっとみなさまに認知いただいて、いいサイクルをもたらしていると感じてもらって、日本だけではなく世界中に広められるような形になれば嬉しいですけど・・・まあ、理想です! 日本から出すっていうと、なかなかハードルが高いので、今のところ、国内でもうちょっと広まって、認知されたらいいな~っていうところですね。で、捨てられるボールが少しでも減れば嬉しいかなと思います」
INFORMATION
今週は、シリーズ「SDGs〜私たちの未来」の第22弾!スポーツ編。「SDGs=持続可能な開発目標」の中から「つくる責任 つかう責任」ということで、廃棄されるゴルフボールをアップサイクルするプロジェクト「NEP!! GOLF」、そして役目を終えて捨てられるバスケットやバレーのボールを、新たな商品に生まれ変わらせる「RE:BALL PROJECT」をご紹介しました。
「NEP!! GOLF」そして「RE:BALL PROJECT」について、詳しくはそれぞれのオフィシャルサイトをご覧ください。
◎「NEP!! GOLF」:https://www.nep-golf.com
◎「RE:BALL PROJECT」:https://yahashisouin.com/reball/
◎八橋装院 :https://yahashisouin.com
2024/11/3 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、秩父でメープルシロップを製造・販売する「TAP & SAP(タップ・アンド・サップ)」という会社の代表「井原愛子(いはら・あいこ)」さんです。
井原さんは地元秩父の豊かな自然に魅せられ、会社を起こし、現在はメープルシロップ作りのほか、いろいろなプロジェクトに取り組んでいらっしゃいます。
きょうはそんな井原さんに秩父のカエデの森や、秩父産メープルシロップの特徴のほか、森づくりやエコツアーのお話などうかがいます。

メープル農家さんを訪ね、本場カナダへ!
※秩父には、もともと20種ほどのカエデが自生していて、地域活性化の事業として、その樹液を採取し、商品を作る取り組みが20年ほど前から行なわれていたそうです。
●井原さんは、秩父のご出身だそうですが、どんな経緯でメープルシロップを作って、販売することになったのでしょうか。
「私が社会人になって、一度、地元を出て横浜で働いていたんですね。そんな時、地元で自生しているカエデの樹液を採取して、メープルシロップとかに商品化しているっていう動きがあるのを知って、その活動に関わっているNPO団体の活動に参加したんです。
ただの面白い取り組みをしているっていうことだけではなくて、将来の森づくりをしているっていうところに感銘を受けて、私も森づくりをすることで地域を活性化していったりとか、森の恵みをみなさんに届けることで、こういう活動を多くのかたに知っていただきたいと思って、思い切って会社を辞めて(秩父に)Uターンしました」

●メープルシロップを作りたい! って思ったとしても、秩父産メープルシロップの製造・販売の拠点作りには資金とかノウハウが必要ですよね?
「そうですね。実は私、最初(秩父産の)メープルをより多くの人に知ってもらいたいって思ったんですが、自分が(メープルシロップを)作るっていうふうには、実は思ってなかったんです。メープルシロップは知ってはいたけど、そこまでメープルシロップが好きというわけではなかったんです。
正直、秩父のみなさんと一緒に活動していくには、やっぱり本場を知らなければと思ったので、まだその時は会社に所属していたんですが、有給を使ってカナダに渡って、現地のメープル農家さんを訪ねる旅をしたりしたんですね。
そこで出会ったのが、今は(秩父に)『MAPLE BASE』がありますけれど、“シュガーハウス”という、カナダのカエデの森の中に小屋がありまして、そこに集めてきた樹液を持ってきて、煮詰めてメープルシロップを作る場所、小屋になりますね」
●本場カナダでは、どんなことを勉強されて、どんなこと体験されたんですか?
「カナダは(メープルシロップの)一大産地ですので、秩父とは本当に次元が違う形になっています。森の中にはパイプラインが張りめぐらされていまして、ポンプで全部集約して小屋まで(樹液を)持って来るっていう(仕組みです)。(煮詰めるのに)ちょっと旧式なんですが、薪を(専用の機械に)くべて湯気が立ち昇る様子が真冬の極寒のカナダで風物詩になっています。
たとえば(メープルシロップ作りの)様子を、スクールバスが乗り付けて、子供たちに見学してもらえるようになっていたりとか、あとはお気に入りのメープル農家さんに、できたてのメープルシロップを買いに行くのが習慣であったりとか、メープル・フェスティバルが各地で開催されていたりとか、地域に根づいている様子でありました。
そういうことを見て、秩父もせっかくメープルを作っているのだから、ただ商品を売ることだけではなくて、そこに来れば、メープルのことを知ったり食べたりしてもらえる、そういう場所作りが必要なんじゃないかなと思うようになりました」
(編集部注:井原さんが参加したのは、NPO法人「秩父百年の森」が主催するエコツアーで、その時、自然の豊かさに驚き、もっと森の恵を届けたいと思い、会社を辞めて地元に戻った井原さんなんですが、周りの人たちは、無謀ともいえる決断にびっくり! NPOの活動では食べてはいけないよと心配されたそうです。

それでも井原さんの本気と熱い思いに応えようと、地元の組合などが協力、地域活性化の事業のひとつとして進み始めます。そして、秩父ミューズパークにあった空き家のログハウスを改装し、2016年に日本初のシュガーハウス「MAPLE BASE」をオープン。本場カナダから輸入した、樹液を煮詰める機械を使って、秩父産のメープルシロップを製造するなど、「MAPLE BASE」を拠点に秩父の森の豊かさを発信されています)
50分の1? 66〜67度?
●井原さんの会社「TAP & SAP」で販売されているメープルシロップと樹液、私も取り寄せて試食、試飲させていただいたんですけれども、樹液はほのかな甘さで、水のようなとっても爽やかな感じがしました。一方、メープルシロップは濃厚でコクのある甘さがあって、鼻に抜ける香りもすごく甘くて美味しかったです!
「はい、ありがとうございます!」

●改めて、カエデから採取した樹液がメープルシロップになるまでの工程を教えていただけますか?
「みなさん、樹液という名前を聞くと、どうしてもクヌギとか、カブトムシが食べるようなペトペトしたような甘いものを想像するかと思うんですね。カエデの樹液は、春先の大体2月が最盛期になるんですが、カエデの木が芽吹くための準備として、根から地中の水分をどんどん吸い上げて、枝葉のほうに行き渡らせようとする栄養の水になります。
もともとは水分なので、そこに甘みはないんですけれども、やはり極寒の冬の秩父は、マイナス十数度っていうのはざらにあります。通常それぐらい木の中に水分があると凍ってしまいますよね。 ただの水だと結構、膨張してしまうかと思うんですが、樹液の成分のデンプン質を糖に変えて甘くすることで、よくシャーベットとかだと膨張はせずに、ちょっとシャリシャリしたシャーベット状になるかと思います。
カエデの木の内部は、ちょっとシャーベット状のようになって、その時期にカエデの木に少し穴を開けるとポタポタその樹液が滴り落ちてきます。春に向けてどんどん気温が上がっていく中で、内部のシャーベット状のものが溶け出して樹液として外に出てくる、私たちはその一部をいただいています」

●樹液の段階では、ほんのり甘いぐらいですけれども、それがメープルシロップになるとすごく濃厚な甘さになるっていう、それもすごく不思議だったんですが・・・。
「そうですね。カエデの樹液自体は糖度が大体1.5度から2度ぐらいという、本当に薄っすら甘いぐらいなんですけれども、それを煮詰めていくことで、大体(糖度が)66度から67度になります」
●何時間ぐらい煮詰めるんですか?
「そうですね・・・半日ぐらいはかけて煮詰めていくんですね。メープルシロップを作るまでに工程的には3日間とか、準備まで含めると4日間とか、本当に時間をかけて作っていて、大変手間のかかるものとなっています」
●たとえば、瓶1本のメープルシロップ作るには、どれぐらいの量の樹液が必要になってくるんですか?
「その時の樹液の糖度次第で高ければ少なくて済みますし、糖度が低いとたくさん必要になってくるんですね。今私たちが販売しているメープルシロップが60グラムなので、大体50分の1ぐらいまで煮詰めて作っています。樹液としては3キロぐらいですかね。なので、たくさん樹液が採れて、たくさん作れるぞと思っても、50分の1ぐらいの量になってしまうので、本当に少なくなってしまいます」
まるで黒糖!? 和の味?
※秩父産メープルシロップはカナダ産と比べて、どんな特徴がありますか?
「カナダのメープルの木は、シュガーメープル『サトウカエデ』というんですけれども、私たちは『イタヤカエデ』っていう日本の固有のカエデであったり、モミジと呼ばれるものなど、様々な木を使っています。
味わいの特徴としては、ちょっと黒糖のようなコクのある、和な味がするってよく言われます。そして秩父の土地柄もあるとは思うんですが、カリウムやカルシウムなどのミネラル成分が、カナダのものと比べても多いっていうことがわかっています」

●樹齢何年ぐらいのカエデから樹液を採取するんですか?
「私たちは木の直径が20センチ以上25センチとか、ある程度大きく成長した木からしか採らないというルールを設けています。あまり小さい木からは採らないので、樹齢としては50年〜100年以上というか、本当に立派な木からも採っています」
●そういう木から、どうやって樹液を採取するんですか?
「木に少しだけ穴を開けて、そこに管を通してポリタンクに貯めて、それでポリタンクを順次回収していくっていう形ですね」
●樹液を集めて運ぶだけでも重労働ですよね?
「そうですね。今私たちが(樹液を)採っているカエデは自生しているカエデなんです。やはり私たちがアクセスしやすいような場所にある木は、ほとんどがスギやヒノキなんですね。逆にカエデの木はとても根を張るので、たとえば、ここの木を切ったら崖が崩れるとか、ある意味ハードな場所にカエデの木たちは残っています。正直、私たちが採取する時もちょっと崖をまず降りて、川を渡って対岸の急な斜面を登りながら採っていったりとか、場所もバラバラだったりするので、大変手間暇がかかります」
●継続的に樹液を採取するためには、カエデの手入れだったりとか植林だったりとか、森づくりがやっぱり大事になってきますよね?
「そうですね。私たちの特徴としては、ただ採るということではなくて、やっぱり植林することを大事にしています。NPO法人『 秩父百年の森』という団体が、カエデを苗から畑で育てて、ある程度大きくしてから山に返すという、かなり手間暇のかかる作業を行なっています」
新しいハチミツ!? 「第3のみつ」!?
※井原さんが2015年に立ち上げた会社「TAP & SAP」という名前には、どんな思いが込められているんでしょうか?
「まずTAPは、スマホをタップするとか・・・ “タップ・ザ・ツリー”で、実は樹液を取る時に木に穴を開けて、とんとんとんってするのがその由来なんですね。で、SAPが樹液なので、どちらも言葉としてはカエデの樹液とか、カエデの木にまつわるものになっているんです。そういった恵みをより多くの人に届けて、食べてもらって、森づくりにつなげていきたいっていう気持ちを込めて、この名前をつけました」
●メープルシロップの製造・販売のほかに、どんなプロジェクトを進めていらっしゃるんですか?
「この活動や、食べてもらったりするのも大事なんですが、やはり現地を見ていただいたりですとか、そういったこともやっていきたいなと思いまして、エコツアーの開催、コロナ禍でここ数年できてない状態だったんですけれども、そういった活動でみなさんと交流をしたり、現地を見ていただいたりっていうことも行なっています」

●エコツアーは、具体的にはどんなツアーなんですか?
「樹液を採っている場所が私有地になるので、誰でもいつでも入っていいよっていうものではないんです。そういったところにご案内して、実際、樹液が出ている様子を見ていただいたりとか・・・。あとはMAPLE BASEで、いろいろランチを食べたり、樹液からシロップってどうやって作っているの? とか、いろんなワークショップを開催したり、結構盛りだくさんの1日で、参加されたかたには好評となっております」
●井原さんご自身がガイドをされたりするんですか?
「そうですね。私もそうなんですが、あとは森づくりをしているNPOのメンバーたちにもガイドをしてもらいながら、一緒に冬の森を歩くことも行なっています」
●あと、プロジェクトのひとつ「第3のみつ」についても教えていただきたいんですが・・・。
「はい、メープルシロップも天然の甘味料として有名ですが、もうひとつはハチミツで、実は私たちの活動からちょっと珍しいものが生まれました。それが『第3のみつ』になるんです。実はメープルシロップは春先に近づけば近づくほど、その樹液で作ったメープルシロップって甘いんですけど、エグみがどうしても出てしまうんですね。
まず、最初のきっかけは、このプロジェクトに関わった地元の高校生が、ちょっとエグさがあるメープルシロップを、ハチにあげたら食べるんじゃないかっていうところで実験したところ、ハチさんがエグみのあるメープルシロップを食べて、それで蜜を作ったんですね。
その蜜を埼玉大学の先生に分析をしていただいたら、ハチミツなんですけれども、メープルシロップの成分がきちんと入っている蜜ができたと・・・。なので、これはちょっと新しいハチミツなんじゃないかっていうところで盛り上がったんですけど、厳密にはハチさんに餌をあげて作る蜜は、ハチミツと呼んで売ることができないんです。
それで、その製造等で特許も取りまして・・・メープルシロップは今なかなかたくさん採れるわけではないので、果実とか野菜とか、一般の生のもので販売できないのを、よくジュースにしてしまうと思うんです。そういったものを無駄なく使えるということで、そのジュースをハチに与えることで、そこからできた蜜を! というので、いろんな野菜、果物で実験したところ、ハチさんがいちばんよく食べるのがリンゴジュースだったんですね。
リンゴジュースをハチに与えてできた蜜っていうことで『第3のみつ』の商品化ができるようになりました」

(編集部注:「第3のみつ」商品名は「秘密」の「秘」に 蜂蜜の「蜜」で『秘蜜(ひみつ)』なんです。どんな味がするのか、気になりますよね。「TAP & SAP」のオフィシャルサイト(https://tapandsap.shop-pro.jp)から購入できますよ)
人間が関わる森づくり
●2013年に井原さんが、秩父のカエデの森を歩くエコツアーに参加されたことが、まさにターニングポイントとなって、劇的に井原さんの人生が変わったと言っても過言ではないと思うんですけれども、その時に抱いていた思いは今も変わらずにありますか?
「そうですね〜生まれ育った地元で暮らしていた時には、なかなか感じなかった、自然の豊かさとか森の気持ちよさとか、そういうものは実はもともと自然にあったということではなくて、いろいろな人が気持ちいい森にするために手入れをしていたんですね。
このメープルシロップも目を向けなければ、誰にも気づかれず、日が当たらずにいたものが、みなさんが苦労して頑張ってきたことで、地域の特産となって、今に至っていると思うんです。
そういうことを続けていかないと、結局途絶えてしまうものだと思うので、森づくりもそうなんですが、より若い世代を巻き込みながら続けていけるような、そういう形で今後も活動していきたいと思います」
●メープルシロップは秩父のカエデの恵みだと思いますけれども、30年後、50年後の秩父の森にどんなビジョンをお持ちですか?
「今、秩父のみならず日本全体がそうかと思うんですが・・・半分が人工林のスギやヒノキで、そのほかの半分は広葉樹なんですが、どんな木があるかっていうのはほとんどの地域で知られてないかと思います。私たちが一度関わってしまった森は放置していたら、いつかはもとに戻るかもしれないんですが、それはかなり長い時間を要するんですね。
私たちが今やっているのは、人間が関わっていける森づくりをしたいっていうことで、そのひとつとして、カエデの木を育てて植樹をして、そのカエデの森から将来的にもっとたくさんメープルシロップを作れたり・・・私たちが関わり合い続ける森づくりを一緒にしていきたいと思って活動しています。ですので、森づくりをより多くの方と協力しながら行なっていければと思っています」
INFORMATION
秩父ミューズパーク内にある日本初のシュガーハウス「MAPLE BASE」では、本場カナダから輸入したメープルシロップを製造する機械を見学できるほか、パンケーキなどを食べられるカフェや、メープルシロップなどの商品を購入できるショップもありますよ。

11月23日(土・祝日)には「MAPLE BASE」の芝生エリアで「秩父の森ジャンボリー」を開催、大人も子供も楽しめる催しを予定しているそうですよ。ぜひお出かけください。詳しくは「MAPLE BASE」のオフィシャルサイトをご覧ください。
◎MAPLE BASE:https://tapandsap.jp/maplebase/
井原さんが取り組んでいる「第3のみつ」やエコツアーなどのプロジェクトについては「TAP & SAP」のサイトを見てください。オンラインで樹液やメープルシロップなどの商品を購入できます。
◎TAP & SAP:https://tapandsap.jp

2024/10/27 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、アウトドアズマン「清水国明」さんです。
清水さんは、1970年代から80年代にフォークデュオ「あのねのね」、そして芸能界で大活躍! 90年代からはアウトドア活動に夢中になり、その後、河口湖に「森と湖の楽園」、瀬戸内海の無人島「ありが島」に自然体験施設を開設。そして去年は茨城県にキャンプ場「くにあきの森」を整備するなど、実業家として、いろいろなプロジェクトを手がけていらっしゃいます。
今回は、先頃立ち上げたばかりの団体、災害時に助け、助け合う「日本セルフレスキュー協会」について、じっくりお話をうかがいます。

日本セルフレスキュー協会 JSRA
●今週のゲストはアウトドアズマン、清水国明さんです。毎年ご出演いただいて行なっています定点観測、今回で29回目となります! 長いお付き合い、ありがとうございます!
「よろしくお願いします。まあそんなに長いことね・・・どこにもないですよ! 私の関係でね、29年も・・・。実は29年間付き合っている人も少ないですよ。嫁さんも取り替えているしね」
●あははは(笑)。きょうもよろしくお願いいたします。
「はい、よろしくお願いいたします」
●前回は、結成50周年を迎えた伝説のフォークデュオ「あのねのね」のツアーですとか、茨城県常総市のふるさと大使に就任されて、常総市にキャンプ場「くにあきの森」を整備されたりだとか、あとは笑顔食堂プロジェクトのお話など、うかがいました。
今回のメインの話題は先頃、清水さんが創設されました、災害時には助け合いましょうという「日本セルフレスキュー協会」JSRAについてなんですけれども、この協会を作ったのは何かきっかけがあったんですか?
「阪神淡路大震災の時から今日まで、災害が起きると、のこのこ出かけて行って、あまり役に立たないかもしれないけれども、支援物資を運んだり、あとその町の賑わいを取り戻すまでのことに、ずっと関わってきたんですね。それの延長で、東京都知事選にも出て、そういうことをみなさんにアピールして・・・つまり、つながることが安全になると・・・。
いろいろ支援をやらしてもらったんだけども、何しに来たの? っていうか、余計なおせっかいみたいなこともあるのよ! ですから、いちばんいいのは友達から助けてとか、支援物資をちょうだいって言われた時に、よっしゃ! って言って出かける時があるんですけど、その時がいちばんモチベーションも高いんですね。で、やったかいもあるし、向こうも喜んでくれる・・・。
だからね、支援の仕方もすごく難しい・・・ですから、先ほど言った、知り合いを助けるという、知り合いからのSOSで動ける、動き始めるというか・・・。だから助けますけども、助けてももらうという、つながりを全国ネットで広げたいというのがいまの取り組みなんですよ。
この日本セルフレスキュー協会は、自分で自分の命を救うと同時に、自分たちで友達を助けるというような、そういう協会を立ち上げたわけです」
(編集部注:「日本セルフレスキュー協会」JSRA(https://www.jsra.life)には、理念に共感されたかたならば、どなたでも入会できるとのことです。月会費は税込1920円。会費は、災害時の出動経費、コンボやショベルカーなどの重機や支援物資の備蓄などに使われるそうです)
誰かの役に立ちたい
※清水さんは阪神淡路大震災から、直近の能登半島地震まで災害時の救援活動にこの30年来、取り組んでいらっしゃいます。その原動力になっているものは、なんでしょう?
「自分でも分からないんですけれども・・・この間の能登半島(地震)の時ね、1月1日、元旦じゃないですか・・・いろいろ東京でごちゃごちゃした仕事があって(終わって)、そのまま無人島に行ったんです。
瀬戸内海の『ありが島』って島を持っているんですけど、そこで船から釣り糸を垂れてゆっくり魚釣りしてたら、”地震があった! すごい被害だ!”ってニュースが携帯に入って、その瞬間に釣り道具をばたばたって片付けて・・・。31日に(ありが島に)着いて、正月に食べるための餅とか、てんこ盛りに持っていたのにひとつも食べないうちに、気が付いたら能登半島に向かっていて、30時間かかったけどね、車で行くのにね。
そういう意味では気が付いたら、やっていたみたいなところもあるんですけどね(笑)。まあ日頃ろくなことをしてないっていうのもあるんだけど、誰かの役立ちたいっていうか喜んでもらいたいっていう・・・。
基本的には褒められ育ちだから、人に褒めてもらってなんとかしている人生なんで、そういう意味では誰かが困っている時に、何かをできるということは、自分の根本なのかな。そういうふうに生きたいなと思っているんじゃないか・・・そんな大した人間じゃないけどね」
●いやいや・・・でもそういった30年の救援活動の知見とか経験が、この日本セルフレスキュー協会に活かされているってことですよね。
「確かにそうですね。いろんなことをやってきて、結局、民間と行政っていうか、公(おおやけ)が協力をしないと災害ってのは復興、復旧しないと・・・。この間の台湾の災害の時に、国とか地方自治体と民間のボランティアがものすごく上手くやっていた。
日本は特に石川の時なんか、行っている最中に、ボランティアは来ないでください、みたいな風潮になってきたもんだから、行っている俺らがなんか悪いことしてんのかよ、みたいな後ろめたさを感じるくらい・・・。
でも、行ったことによって多くの人に喜んでもらえたし、“お腹すいたよ〜”って言いながら支援物資の倉庫に、おばあちゃんと小っちゃい女の子が来たんだけど、“いや、これは渡せないんです。ここは倉庫だから、体育館で配りますから、それまで待ってください”って・・・けど、女の子はお腹がすいて、うえーんとか泣いているから、俺らボランティアが用意したお弁当を食べてもらったの、それで解決ですよ、それは。
そういうルールとか平等とかね、そういうのはやっぱり、公の人は仕方ないですよ、その人が悪いわけじゃなくて、ルールはルールだから・・・けど、民間だったら目の前の子が泣いていたら、できるじゃないですか。そのフレキシブルというか柔軟性が、やっぱり民間の力が必要になってくると思ったから、我々は民間で救うとこまで、救助から延命、そういうところまで関わるべきだなという・・・これは長いことやってきた結論ですけどね。それでそういう組織でとりあえず、つながりましょうということをいまやっています」
(編集部注:清水さんとしては、自分で自分の身を助ける「自助」、共に助け合う「共助」、国や地方自治体の「公助」に加え、友達同士で助け合う「友助」を担おうとされている、ということなんですね)

技術者の集まり「災害友助隊」
※先ほどからお話をうかがっていると、「つながり」というのが、ひとつのキーワードになっていますよね?
「だから、つながりがあるか、ないかだけが非常に命にも関わるし、安心にもつながることなので、ぜひ友達になってくださいと。で、いつでも助けに行きますよっていう人が全国におるわけですよ、助けに行きますよ! って言っている人が・・・。地震とか洪水とかでやられた時に“うわ~、やられちゃった”ってことを本部に言ったら、すぐに近くの人が駆けつけるわけです!
公的な体育館とかで避難していると、支援物資はいっぱい届くんですけど、自分のちょっと崩れた家とか納屋とか、ビニールハウスとかに避難している人も結構、災害の時は多いんですね。そこには支援物資って届かないわけですよ、公的なとこじゃないんでね。
そういうところに友達として、ビニールハウスにいまいるんや~っていうことになったら、よっしゃ!って・・・。そこにドコドコドコっていっぱい全国から届く、“なんであの人ばっかりあんなに支援物資が届くねん?”って近所で話題になるぐらい・・・“それは日本セルフレスキュー協会に入っているからですよ!”っていうような現象が起こると思いますね」
●心強いですね~。「災害友助隊」っていうのが相互救助チームですよね?
「そういうことですね」
●つながっている仲間たちと組んでいるチームっていうことですよね?
「はい。もしね、小尾さんが災害でひどい目に遭った時に、家が潰れたり流されたり、今夜どうしようっていうような時には、思い浮かぶでしょ、あの人とこの人に電話しようと・・・ガーっと駆けつけてくれる人は何人いますか? そういう人?」
●そうですよね・・・いざという時に・・・。
「いざという時に、親戚も遠くだったり高齢だったりしたら、助けに来てくれないけど、ピチピチしたやつ、そういう人助けが趣味みたいなやつが、ムキムキだとしたらね(笑)、それのほうが会員同士だから、仲間同士だから、気兼ねなくしてもらえるんじゃないかな~と思いましたね」
●しかも、災害友助隊には、いろんな職種のかたがいらっしゃいますよね?
「そうなんです! うちはね・・・いま私のメインの仕事はキャンプ場作りなんですけど、重機で木を伐採したり、道を作ったり、高いところにツリーハウスを作ったりとか、そういうことばっかりなんです。
そうすると設備屋さんもいるし、水道工事もできたりトイレも作れたり、そういう工作隊なんですけどね。それがほとんど家を作ったりビルを建てたりする時の、ひと通りの技術者が集まっているわけですよね。それプラスやる気ですよ。そんな人が集まっているチームなんで結構心強いですわね」
自分の生存力を高める
※清水さんが茨城県常総市に整備したキャンプ場「くにあきの森」で、災害友助隊のキャンプ・イベントを行なったんですよね? どんなイベントだったんですか?
「結局100回、防災訓練するよりも1回サバイバル・キャンプをしたほうが身につくと、私は日頃から言っていて、そんな本も出したりしているんですね。
火を起こしたり雨、風、寒さ、暑さから身を守ったり、それからそこで食べ物を調達して作るという、基本的に衣食住とかね。体温を上げても体温を下げても死んじゃうわけですから、保温という基本をキャンプで学んでもらったり・・・。
それからどんな状況でもたくましい生きる力、その生きる根性を失わない体験というのが、非常に重要だと思うんですね。これが自分で自分の命を救う、そして自分にとって大切な人の命を守るということにつながりますので、自分の生存力を高めていくっていうことが、安全な強靭な日本になる術だと思っていますよ」
●そのイベントで「国明式 災害生存術」という冊子を配布されたということですけれども、どんな内容なんでしょうか?
「これ、いま手元にあるんですけど、ペラペラのもんですが、結構いままでの災害の時に学んだことを自分のエピソードとしていっぱい書いているんです。“いまいずみひろみ”っていう漫画家がうちの工作隊の仲間におりまして、そいつが漫画を描いてくれたわけです」
●カラーの漫画で、すごく読みやすいですね~!
「4コマ漫画で、私の文章に漫画をつけたという前提でスタートしたんですが、いまやこの漫画に文章もついているという主客顛倒っていうのかな(笑)。けどね、それぐらい面白いように一生懸命(漫画を)描いて、僕も一生懸命、文章は書きましたけども、いまいずみも命かけてやってくれましたから、これは一家に一冊、生存するための術として、ぜひ備えていただきたいなという、そういうものでございます」
(編集部注:清水さん書き下ろしの冊子「国明式 災害生存術」は、「日本セルフレスキュー協会」に入会すると、いただけるそうです)
「体験家」としてチャレンジ!?
●清水さんは今月10月15日に74歳になられました! おめでとうございます~!
「わ~お! めでたいのかどうか、わかりませんけれども(笑)」
●いやいやいや~! 若々しくって、これまでにいろんなことに全力で挑戦されてきたイメージあるんですけれども、今後新たに挑戦してみたいことは何かありますか?
「挑戦だな、挑戦するんだろうな・・・俺はね、基本的に冒険家ではないんですよ。冒険しないで、チャレンジはしますけども、つまりね、体験したいだけなんですよ。だから冒険家ではなくて、今後は“体験家”という、そういう名前でいこうかな〜(笑)。
誰かに評価してもらいたいわけじゃなくてね。たとえば芸能界の界でしょ、それからレース界とかアウトドア界とか、ビジネス界もやっているんですよ。この前は政界までやりました。そしたらその界を渡り歩くごとにいろんな物差しがあって、いろんな発見があって・・・新たに体験したいことがあったら、またやろうかなと思っています。やりたいことは、これ、突然現れるからね!」
INFORMATION
「日本セルフレスキュー協会」以外の近況としては、瀬戸内の山口県・周防大島町に準備していた5Gを導入したワーケーション施設の運用が試験的にスタート。町とタッグを組んで、島全体をデジタルアイランドにする構想もあるとか。
また、まだ決まっているわけではありませんが、日本全国にキャンプ場を作る事業に参入するかもしれないとのこと。さらに歌とおしゃべりのライヴツアーも計画中。清水さんのチャレンジは、まだまだ続きそうです。
次回の定点観測も楽しみですが、その前に「日本セルフレスキュー協会」JSRAにご注目いただければと思います。入会方法など、詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
◎「日本セルフレスキュー協会」JSRA :https://www.jsra.life
清水さんのFacebookもぜひ見てくださいね。
◎https://www.facebook.com/kuniaki.shimizu2/?locale=ja_JP
2024/10/20 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、牛写真家の「高田千鶴(たかた・ちづる)」さんです。
大阪府泉大津市に生まれた高田さんは、子供の頃から動物が大好きで、小学4年生のときに、引っ越した先の近くに農業高校があり、そこで牛との運命の出会いがあったそうです。
ある日、友人の家に遊びに行こうと、たまたま農業高校のそばを通ったら、牛の「モー」という声が聴こえ、牛がいる学校は楽しそう、中学を卒業したら、その高校に進学すると決めたそうです。そして大阪府立農芸高校に入学。農業の基本を学びながら、畜産を専攻し、「大家畜部」通称「牛部(うしぶ)」で3年間、牛舎の掃除、堆肥作り、餌やり、乳搾りなど、まさに牛まみれとなって、大好きな牛の世話に取り組んでいたそうです。
卒業後は、酪農ヘルパーとして、2年ほど活躍。365日、休みなく働く酪農家さんの仕事を手伝っていたそうですが、日々、一袋10キロもある餌を運んだり、一輪車で重い牧草を運ぶなどの作業で腰を痛めてしまい、泣く泣く、酪農ヘルパーを辞めることになってしまったとのこと。
大好きな牛から離れて、心にぽっかり穴が空いたような状態だった高田さんは、ある時、たまたま牛好きな友人が発した「牛の写真集があったらいいのに」というひとことに、それだ! と思い、高校生の頃から、ずっと牛の写真を撮っていたこともあり、作品として牛の写真を撮るために、一眼レフを購入。
牛の写真集を作ることを目標に、ついには牛写真家として歩み始め、現在は全国の牧場をめぐり、牛の写真を撮り続け、酪農や牛、食と命などをテーマに写真や文章で発信されています。そして先頃、新しい本『牛がおしえてくれたこと』を出されました。
きょうはそんな高田さんに「食と命」をテーマに酪農のこと、経済動物といわれる牛のこと、そして東京の郊外にある、高田さん憧れの牧場のお話などうかがいます。
☆写真協力:高田千鶴

牛乳は、子牛が飲むはずのお乳
※私たちは牛のお乳を「牛乳」としていただいているわけですが、牛がお乳を出すためには、妊娠と出産が必要なんですよね? 普段私たちは、そのことを忘れてしまっている、そんな気がしているんですが・・・。
「ホルスタインは白黒の、いちばんよく見かける牛だと思うんですけれども、オスでもメスでも、お乳が出るって思っているかたもいらっしゃるんですね。でも、本当に人間と同じで、牛が出しているお乳も子牛に飲ませてあげるためのお乳なので、出産しないとお乳も出ません。
そういった意味では、私たちは子牛が飲むはずのお乳を分けていただいているっていうのを、改めて酪農と関わるようになって感謝の気持ちと言いますか、やっぱりすごいことだなと思っています」

●すごくありがたみを持っていただかないといけないですよね。牧場で飼育されている牛ってほとんどが人工授精なんですね?
「そうなんです。私は人工授精の資格も実は持っているんです。オスって本当に大きいと1トンぐらいになるんですね。とても扱いが難しいですし、酪農家さんはオスをいっぱい飼うということもできないんですね。それで人工受精っていう形が取られているんです。
中には牧場の中でオス牛を飼って自然交配しているところもあるんですけれども、やっぱり近親交配が続いてしまうのもいけないので、そういった意味でも人工授精を取り入れながら飼育しています」
●妊娠してから子牛が生まれるまでは、どれぐらいの日数がかかるんですか?
「それも人間と同じで280日、約10ヶ月間なんですね。お腹の中に10ヶ月間いて、人間だと3〜4キロぐらいで生まれてくるところ、牛だと30〜40キロぐらいで生まれてくる、本当に10倍ぐらいの大きさで生まれてくる感じですね」
(編集部注:高田さんは酪農ヘルパー時代に、より深く酪農の仕事に関わりたいと思い、「家畜人工授精師」という資格を取得されています)
乳牛の一生
※酪農家さんにとっては、生まれてくる子牛がオスなのか、メスなのか、そこがポイントになってきますよね?
「そうですね、酪農に関して言えば・・・。やっぱり酪農ってお乳を絞るっていう仕事ですので・・・。メスだと大きくなってから、人工受精して出産して、初めてお乳を出してくれるようになるので、メス牛が生まれると、そのまま牧場で育てていくということになりますね。
でも、メスばっかり生まれて欲しいっていうわけでもなくて、(メスばかりだったら)だんだん牧場も牛が増えすぎてパンクしてしまいます。なので、オスもメスも生まれてくるんですけど、酪農家さんとしては、いい牛の遺伝子を継いでいるメスの子牛が生まれてきたら、やっぱり嬉しいというのはありますね」

●お母さん牛って毎年、子牛を出産するんですか?
「そうなんです。本当にこれも人と同じなんですけれども、やっぱり赤ちゃんが生まれて2〜3ヶ月ぐらいで、乳量のピークと言いますか、お乳がいっぱい出るようになって、そこからはだんだん減っていきます。
牛だと1年ぐらいしかお乳は出ないので、また1年後に出産して、お乳を出してもらうというサイクルが理想的とされていますね。そのために出産のあと、しばらくしたら人工授精して、10ヶ月後に生まれるようになって、それがちょうど1年、12ヶ月くらいになるようなペースで考えられています」
●メスは乳牛となってお乳を出してくれますけれども、生まれた子牛がオスだった場合はどうなっていくんですか?
「オスの子牛は肥育農家さんで飼われて、そこで2年ぐらいですかね・・・大きくなるまで育てられて、そのあと出荷っていう感じになりますね」
●乳牛となったメスでも年を重ねると、お乳って出なくなっちゃうものですよね?
「そうですね」
●だいたいどれぐらい・・・平均で何年とかってあるんですか?
「初めて出産するのが成牛、成人みたいな感じで、大人の牛として出産するのがだいたい2歳ぐらいなんです。そこから1年に1回産んでいくペースで3〜4回、多くて5〜6回、もっと長く生きる牛もいるんですけれども、だいたい5〜6回ぐらい出産したとしたら、それプラス2年で7〜8年ぐらいですかね。で、出荷されるっていうのが多いかもしれないです」
●最後はメスでもお肉になっちゃうということなんですね。
「そうですね」
牛との別れ、葛藤
※高校生の頃や酪農ヘルパー時代、牛を可愛いと思って世話をしていても、いずれはお肉になってしまう・・・何度も葛藤があったんじゃないですか?
「そうですね。それは本当にすごくあって、私もやっぱりお肉を食べることに躊躇していた時期もあったんです。(私が通っていた)農業高校も乳牛が多かったんですけれども、肉牛がその時は1頭だけいて、それを先輩から引き継いでお世話をしていたんです。2週間ぐらいしかお世話はしていなかったんですけれども、出荷される日に最後、見送りたいと思って、その子がいるところまで行ったら、もうトラックに乗っていたんですね。

今まさに屠殺場に向かうトラックに乗っていて、私が聞いたことないような声で鳴いていたんですね。私がトラックの荷台に足をかけて、ほっぺたを撫でてあげると、すごく静かに私のことを見返してきて・・・本当に今でも思い出すと、ちょっと泣いてしまうんです・・・それで撫でて落ち着いて、でももうトラックが行くっていうんで、私も降りて、そうしたらまた大きい声を出しながら遠ざかっていく和牛を見送ったんですけれども、その時に可哀想だから食べられないとか言ってられないなと思って・・・。
出荷された先でお肉になって、みんなが食べてくれるならいいですけど、余ってどこかで捨てられるぐらいだったら、全部自分が食べたいぐらいに思って・・・何て言うのかな・・・最後にできることって、その命に責任を持って大切に食べるっていうことしかないなと思ったので、可哀想だから食べないっていうよりかは、自分はちゃんと食べようって思ったっていうのがありますね。
やっぱり消費者としてはスーパーに並んでいる状態が、初めて会うところっていうのが多いと思うんですけれども、その前に生きている牛っていうのも知ってもらいたいというか、もっと身近である存在なのになんか遠い存在、みたいなところを埋められたらなっていう思いはありますね」
牛と人の幸せな牧場
※東京都八王子市に、高田さんが特にお世話になっている牧場があって、今回の本には、そこで撮った写真が多く載っているそうですが、どんな牧場なのか、教えていただけますか?

「磯沼牧場っていう磯沼正徳さんっていうかたがオーナーとして(運営)されているんです。磯沼さんが『牛と人の幸せな牧場』っていうのを大切にされていて、放牧とかもしていたりして、牛も本当に幸せそうで、そこに来る人たちも笑顔になれるような牧場ですね。
観光牧場ではないんですけれども、オープン・コミュニティーファームとして開放していて、誰でも来て見学することができるっていう、本当に東京になくてはならない牧場だなっていうのをいつも感じていて、すごく家族でもお世話になっているところです」
●その磯沼牧場では、何頭ぐらいの牛が飼育されているんですか?
「子牛とか全部合わせると100頭ぐらいいるんです。磯沼牧場の、私のいちばんの推しのポイントは、7種類の牛がいることなんですね。日本で言うと、99%以上はホルスタインっていう白黒の牛が乳牛としては多いんですね。それに加えて、ジャージーとブラウンスイスとエアシャー、ガーンジー、ミルキングショートホーン、モンペリアルドっていう牛7種類を飼っているんです。
それってすごいことで、ひとつの牧場で7種類も飼っているのは、本当に磯沼牧場だけで、それが酪農の盛んな北海道ではなく東京にあって、消費者に近いところにあるっていうのが本当にすごいなって思っています。
私はいつも、もっとこのすごさを伝えたいってすごく思っているんですね。本当にここ東京なのかな? っていう・・・今はカフェができて(牧場の)上のほうまで牛は来ていないんですけれども、カフェができる前はいちばん上まで牛が来ていて、(道路を)車で走っていると、“えっ!? 牛?(笑)”みたいな、信号待ちしている人がみんなびっくりして、え~! って見るぐらい・・・八王子なので都会とは言えないんですけれども、ここが東京なのか! っていう、すごくいいところなんです」

(編集部注:磯沼牧場のサイトを見ると、里山の緑の中に牛が放牧されていて、ほんとにここが東京!? と思ってしまう、のどかな風景が広がっているんです。ぜひオフィシャルサイトをご覧ください。
☆磯沼牧場:https://www.isonuma-milk.com)
カウボーイ・カウガール
※磯沼牧場では、子供たちが酪農の仕事を体験する「カウボーイ・カウガール」というスクールをやっているそうです。そのスクールに高田さんのお子さんが小学校3年生の時に友達と一緒に参加したそうですね。牛の世話をしているお子さんを見て、どんなことを感じましたか?
「私は高校で酪農を、というか畜産を学んでいたんですけれども、子供に関しては大事なことを牛から教わっているなっていうのをすごく感じましたね。私たち大人が“食べ物を大事にしなさい”とか“命を粗末にしてはいけないよ”とか、口で言うことよりも、牛と触れ合って自分自身で命の大切さを、牛から教わって学んでいるなっていうのをすごく感じました」

●高田さんご自身も、磯沼牧場から学ぶことっていうのは多いですか?
「そうですね。磯沼さんがおっしゃっていた、私の好きな言葉があって、“同じ釜の飯を食った牛は、やっぱり仲間のことをよく覚えている”っておっしゃっていたんです。
息子がカウボーイ・カウガール・スクールに入って、名前をつけた子牛がいるんですけれども、同時期に生まれた牛にお友達が名前をつけて、その子たちを見ていると、やっぱりいつも寄り添っているというか、ずっと一緒にいて、生きている牛には感情があるんだなっていうのを改めて思い出させてくださったというか・・・。
あと磯沼さんは、すごくチャレンジ精神の旺盛なかたで、そういうところは本当に見習いたいなっていうのをいつも感じています」
(編集部注:磯沼牧場の「カウボーイ・カウガール・スクール」は現在、磯沼さんのご都合で開催していないそうです。
高田さんによると「酪農教育ファーム」という活動があって、これは一般社団法人「中央酪農会議」という団体が認定した全国各地の牧場で、地域の子供たちに酪農を体験してもらったり、牧場から小学校へ牛を連れて行き、乳搾りなどで触れ合ってもらい、子供たちに食や命の大切さを伝える、そんな取り組みだそうです。「酪農教育ファーム」については、高田さんの新しい本に詳しく書かれていますので、ぜひ読んでください)
牛が笑っている!?
●高田さんが撮った牛の写真を、この本でもたくさん拝見しました。本当に可愛い顔をしていますよね~。
「そうですよね~(笑)、ありがとうございます! そうなんです。私、酪農家さんに言っていただいた言葉で、ちょっと嬉しかったなって思うのが、“高田さんが撮った牛は、すごく笑っているように見える”って、“自分たちが毎日見ている牛とは、また違った顔をしている”っておっしゃっていただいたんです。“それは多分、写真を撮っている時に高田さんが笑っているからなんだろうな“っていうのを言っていただいて・・・。

思い返してみれば、やっぱり可愛い! と思っている瞬間を切り取っているので、それを見て可愛いと思っていただけたら、すごく嬉しいなっていうのを思いながらいつも撮っています」
●牛の写真を撮っている時に、どんなことを牛から感じますか?
「本当に牛って表情が豊かだなっていうのを感じるんですね。私が撮った牛を可愛いって思ってくださるとしたら、その可愛い表情になるのは、牛がやっぱりリラックスしていて、穏やかな気持ちでいられるっていうことなので、酪農家さんが大切に育ててくださっているんだろうなっていうのを感じながら撮っていますね。
あと本当に酪農家さんがいなければ、私の仕事も成り立たないですし、大好きな全国の牛に会いに行けるのも、酪農家さんが本当に大変な思いをされながらも(牛に)向き合って、頑張ってくださっているからだなっていうのをいつも感じながら撮影しています」

●では最後に、新しい本『牛がおしえてくれたこと』を通して、いちばん伝えたいことはなんでしょうか?
「そうですね・・・私、農業高校に入学したのがちょうど30年前なので、本当に30年間、牛と向き合ってきて、自分自身もそうですけれど、やっぱり息子が体験しているのを見て、本当に牛から教わることってすごく多いし、すごく大事なことを、『食と命』っていう、人間が生きていく上でどうしても必要な部分を・・・それを牛は教えてくれているつもりはないかもしれないですけれども、すごく教わることが多いなって思います。
この本をもし読んでくださったかたがいらっしゃったら、牛に興味を持って、じゃあちょっと家族で牧場に行ってみようかとか、その行った先でたくさん牛と触れ合って、酪農家さんとお話されたりとか・・・そういった意味で、牛乳を飲んでいただいたりとか、酪農のファンになってくれたらいいなっていうのを思っています」
(編集部注:私たちの食と健康を支えてくださっているといっても過言ではない酪農家さんたちなんですが、全国の牧場をつぶさに見てこられている高田さんによると、今年2月の時点で、全国の酪農家さんは約1万2千戸、それがどんどん減っていて、もしかしたら年内に1万戸を切るかもしれないそうです。
そのおもな原因は、ロシアのウクライナ侵攻による世界的な餌不足や円安など。飼料価格の高騰が酪農家さんを直撃しているとのこと。酪農家さんの減少は、酪農発祥の地、千葉県でも例外ではなく、ここ数年、全国的につらい状況が続いていると心配されていました)
INFORMATION
高田さんの新しい本をぜひ読んでください。高田さんの牛への愛情や、酪農家さんへの思いに溢れた本です。牛の可愛い写真が満載! ほんとに笑っているように見えるから不思議です。漢字には全部、ふりがながふってあるので、ぜひお子さんと一緒に見ていただければと思います。緑書房から絶賛発売中です。詳しくは、出版社のサイトをご覧ください。
◎緑書房 :https://www.midorishobo.co.jp/SHOP/1644.html
高田さんのオフィシャルサイトも見てくださいね。
◎高田千鶴:https://ushi-camera.com
2024/10/13 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、東京都青梅市で「lala farm table(ララファームテーブル)」という農園を営むハーブ農家の「奥薗和子(おくぞの・かずこ)」さんです。
奥薗さんはドイツのお花屋さんで働きながら、専門の学校に通い、「マイスター・フローリスト」の資格を取得。その後、日本に戻ってからは有機農業を学び、2019年に青梅市にハーブ農園を開園されています。そして先頃、『ドイツ式 ハーブ農家の料理と手仕事〜育てる、味わう、丸ごと生かす』という本を出されました。
きょうはそんな奥薗さんに、ドイツのマイスター・フローリストの資格やハーブを使った意外なレシピ、そして里山にあるハーブ農園のお話などうかがいます。
☆写真:高木あつ子、協力:山と渓谷社

マイスター・フローリストの専門学校へ
※奥薗さんは、日本でフラワーアレンジメントの教室に通っていたそうですが、理論がしっかりしている本場ドイツで、アレンジメントを学びたいと思い、2002年にドイツに渡ります。
そして、ご本人曰く、チンプンカンプンだったドイツ語を習得するために、半年ほど語学学校に通い、その後、フローリストとして、ドイツ国内3つの街のお花屋さん、いちばん長く働いていたのは、ベルリンにあるお花屋さんで7年ほど、2014年に帰国するまで働いていたそうです。
そんな奥薗さんは「ドイツ・マイスター・フローリスト」の資格を持っていらっしゃいます。
●これはドイツの国家資格ですよね?
「はい、ドイツの国家資格です。ドイツ人がドイツでお花屋さんを開きたい時に、その資格がないとお店を開けないんですね。そのマイスターの資格になります。私たち日本人とかは、そこで学べる実技だったり理論が、より高度なものなので、それを求めてマイスターの資格を取りにドイツの学校に行きました」
●マイスター・フローリストの資格を取るための、専門学校のようなスクールがあるんですか?
「マイスター学校も各地に何校かあるんですけれども、そこで教えてくださる先生がたが違いまして、その先生の作風だったりとか、教え方とか、どういうものを教えてくれるかで、その学校に通って学べることが全然違ってくるんですね。
理論とか基本的なものは統一されているんですけれども、私はやはり自然素材を使ったアレンジメントがすごく好きだったので、そういうナチュラルなアレンジメントが得意な先生がいる学校を選んで、そちらに通いました」

●何年ぐらい通われたんですか?
「1年半から2年間ぐらいの間になりますね。そこで寮生活を送りながら、授業がある時期はマイスター学校に通って、授業がない時期はお花屋さんで働いていました。働きながら通える学校だったので、そこに通いながら1年半から2年ほどの間で資格を取りました」
●どんな勉強をされたんですか?
「科目が結構いろいろありまして、基本的なドイツのフラワーアレンジメントの理論だったり、お花の素材についてとか、色彩学だったり・・・。あと作品を作るためのデッサンも必要になってくるので、スケッチの授業があったり・・・。あとは実務的なところで、経営学や簿記、お店のレイアウトを考えたり、デザインするとか、そういう授業などがありました」
●すごい! 多岐にわたっていろいろ学べるんですね?
「そうですね。お花屋さんを開くための学校なので、実際に開くときに、必要なことをすべて教えていただけるっていうことで・・・そう! 農薬の扱い方も学んだりとかして、その資格も取りに行きました」
(編集部注:ドイツの国家資格マイスター・フローリストの試験は2日間にわたって行なわれ、花束やリース作り、空間装飾などの実技と、法律や簿記などに関する筆記試験があり、とても難しかったそうです。奥薗さんは過去に出された筆記試験の問題を、ドイツ語と格闘しながら、必死に暗記し、なんとか乗り越えたとおっしゃっていましたよ)
ハーブが身近にある暮らし
※ではここからは、奥薗さんが先頃出された本『ドイツ式 ハーブ農家の料理と手仕事〜育てる、味わう、丸ごと生かす』をもとにお話をうかがっていきましょう。

この本には、ハーブやお料理のレシピのほか、ドイツでの日々の暮らしで体験したことなども書かれています。ドイツのかたは、暮らしの中にいつもハーブがある、そんな感じなんですか?
「そうですね。やはりいちばんよく感じたのは、お花屋さんでお花と一緒に鉢物も一緒に販売するんですけれども、ハーブの季節になるとお花屋さんの店頭でもハーブをいろいろ売ったりします。あとスーパーとかマルシェとかに行きますと、お野菜と一緒にハーブがたくさん売られていて、みなさん、週末に作るお料理のお野菜を買う時に一緒にハーブを買いに行くっていう光景をよく見ておりました」
●ドイツのみなさんは、暮らしにハーブを取り入れているっていう印象が強いっていうことなんですね?
「そうですね、はい。職場やお花屋さんでも給湯室にハーブの苗が置いてあって、お仕事しながら休憩時間に給湯室に置いてあるハーブをちょっと摘んで、それをマグカップに入れて、お湯を注いでハーブティーを飲んでいたりとかしていましたね。
朝は目覚めのコーヒーを飲み、午後からはハーブティーを飲んだりとか・・・。カフェインで夜眠れなくなるから、その代わりにハーブティーを飲んでいますっていう同僚も多かったですね」
●へぇ~いいですね。職場の給湯室にハーブってすごくおしゃれですね!
「そうなんですよ!(笑)」
●ぜひ日本の職場にもそれが普及したらいいですね~。
「すごくいいと思います!」

●この本では代表的なハーブ20種類の説明、育て方、そしてそのハーブを使ったお料理のレシピなどが紹介されていますけれども、レシピ本としても楽しめる本だなというふうに感じました。
「ありがとうございます」
●初心者がベランダなどでも育てられるおすすめのハーブってありますか?
「そうですね・・・例えば、チャイブだったり、あとミントだったり、そういった繁殖力が強いものは比較的、植えても育てやすいですね」
●この時期、10月頃に種まきして、年内に収穫できるハーブはあるんですか?
「寒くなる前までに収穫できるハーブを植えるといいと思うんですけれども、もしくは苗を買ってきて、それを植えてあげたほうが年内に収穫できると思います。
例えば、ディルだったり、イタリアンパセリだったり、あとルッコラとか・・・ルッコラも一応ハーブとしてのカテゴリーに入るので、そういう葉物を育ててあげると、年末頃まで収穫できて楽しめると思います」
ハーブオイル、ハーブマヨネーズ、ハーブバターの作り方
※奥薗さんの新しい本に載っているお料理のレシピ、どれも美味しそうで気になったんですが、ハーブの活用法として、オリーブオイルにハーブを漬け込んだ「ハーブオイル」、お塩などと混ぜた「ハーブソルト」、さらには「ハーブマヨネーズ」に「ハーブバター」が紹介されていました。
とっても興味があるので作り方を教えていただけますか。まずは、ハーブオイルからお願いします。
「これはとっても簡単です。今回本でご紹介しているハーブオイルは、本当にどんなハーブでもいいんですけれど、お好きなハーブを細かく刻んでいただいて、それにオリーブオイルを注ぐ、それでちょっと時間を置いてあげるだけで、ハーブの香りがオリーブオイルにしっかりつきます。

それをドレッシングで使ったりだとか、パスタを作る時の仕上げにしてもいいですし、ペペロンチーノとか何かパスタを作る時にニンニクを入れてオリーブオイルに香り付けしますよね。そういう時にそれを使ってあげると、すごくおいしいパスタが簡単にできます」
●いいですね~。お肉とかお魚とか、なんでも合いそうですよね。
「ほんとになんでも合います。トーストに合わせても美味しいですし、食パンにそれが染み込む、バター塗るみたいな感じでハーブオイルを塗ってあげると、とっても美味しくなります」
●瓶に詰めておけば、保存もできますし、いいですよね~。
「1回仕込んでおくと、逆に忙しい時、お料理する時に、このハーブオイルを使うと、あっという間に美味しいお料理ができちゃうので、これはおすすめです」
●それからハーブマヨネーズなんですけれども、これはどうやって作ったらいいんでしょうか?
「はい、これも簡単で、本ではマヨネーズを作るところからご紹介しているんですけれども、それが大変だったりするので、市販のマヨネーズを使っていただいてもいいです。
市販のマヨネーズに刻んだお好きなハーブ、これは本当にどんなハーブでも合うので、刻んだハーブを入れて、そこに少しレモン汁とか、ワインビネガー、お酢など入れてあげて、少し塩と胡椒で味を調節してあげると、それだけでとってもおいしいハーブマヨネーズができて、ワンランクアップしたお料理になると思います」
●ドイツのかたは、これを何につけて召し上がっているんですか?
「ドイツのかたもよくチャイブ、セイヨウアサツキっていうふうに日本名は言われているんですけれども、ちょっと小ネギに似たもので、そのチャイブを刻んだものをマヨネーズに混ぜてあげて、それをサンドイッチとかに塗ったりして、よく使われていますね」
●ハーブバターっていうのもありましたけど、これはどうやって作るんでしょうか?

「はい、これも簡単で(笑)、好きなバターを少し常温に戻していただいて、そこに刻んだお好きなハーブを入れていただいて、少しお塩とかで調整してあげてもいいですし、味を変えたいなっていう時には、レモンの皮を少し擦って入れてあげると、ちょっとレモンの香りがするハーブバターができるので、それを混ぜて冷やしてあげるだけで簡単にできます」
約7000平米のハーブ農園
※奥薗さんが2019年4月に開園されたハーブ農園「lala farm table(ララファームテーブル)」は、どんな農園なんですか?
「lala farm tableはハーブと、ハーブに合うお野菜もお作りしています。もともと青梅にありました里山を生かした農園なっていますので、栗林とか田んぼとか、そういったところもあるんですね。それを含めまして全体で約7000平米ぐらいの広さになります」

●スタッフは、何人ぐらいいらっしゃるんですか?
「今現状ひとりで、あとお手伝いしてくださるかたが来てくださったり・・・最近ですと研修で来られたかたもいらっしゃるので、そういったかたのお力をお借りしながらやっております」
●現在ですと、何種類くらいのハーブや野菜を育てていらっしゃるんですか?
「秋冬になるんですけれども、40〜50種類ぐらいはある感じになります」
●開園する前に有機農業の研修もされたということですけれども、どこでどんな勉強をされたのですか?
「有機農業は山梨県の上野原市というところで、ちょっと中山間地にある山あいの有機農家さんで研修させていただきました。そこではやはり自然に沿った形で野菜を育てる方法を学びました」
●なんかすごく有機農業って手がかかるイメージがあるんですけど、どうですか?
「はい、やはりかかりますね。農薬も使わないので除草作業をしたりとか、あとやはり害虫とか、そういうものがどうしても自然の中だと出てくるので、お野菜が食べられないように守ったりする作業をしたりとか、真夏はすごく暑かったりするので、そういった中でお野菜とかハーブが育ちやすいように草を抜いてあげる作業とか大変でした」
●奥園さんが育てたハーブや野菜を購入したいと思ったら、どのようにしたらよろしいんでしょうか?
「通常、私のほうはオンラインショップでハーブの定期購入をやっておりまして、そのほかにはお野菜やハーブの旬の時期に“お任せセット”みたいな形で販売をしております」
1日のスイッチにローズマリー
※農園で作業をされていて、いちばん好きな季節や時間帯はありますか?

「難しいですね〜。いろんなシーンやいろんな瞬間にやっていてよかったな~とか、すごく好きだなっていう時はあるんですけど、いちばんって言われますと、例えば5月や6月にハーブのお花だったり、野菜のお花が一斉に農園で開くっていう時があります。その時期はいろんな香りに包まれるので、作業していてもとても癒されますし、見た目的にも農園が素敵になるので、すごく気に入っている季節です」
●暮らしにハーブを取り入れるようになって、奥園さんご自身に何か変化ってありました?
「やはりハーブ自身を触ってあげるとか収穫してあげるとか、そこにあるだけで気持ちや心がすごく豊かになれるんですね。で、それだけじゃなくてハーブティーにしてあげて、一緒に身体にも取り入れてあげる、そうすることによって、心も体もすごく優しくなれるというか、体がすごく優しい体になれたような感じがします」
●特に好きなハーブって何かありますか?
「そうですね・・・農園で育てているハーブは、自分の好きなハーブを植えているので(笑)、どのハーブも好きなんですけど、いちばん好きなハーブって言われましたら、やはり定番のローズマリーがすごく香りが好きなので、農園の入り口のところに植えて、毎回通るたびに少し手で触ってあげて、香りを楽しみながら、“よし! きょうも作業を頑張るぞ!”みたいな感じで(作業を)始めています」

●いいですね。スイッチになっているんですね~。
「そうですね」
●では最後にハーブ農家として、今後やってみたいこと、または夢などがありましたらぜひ教えてください。
「もともとフラワーアレンジメントをやっていたので、ハーブ農家になったのも、やはり自分で育てたハーブやお花を使ったブーケとかアレンジメントを作りたいっていうことがありました。
なので、もう少ししっかりハーブを育てて、それをブーケにしたりとか、農園に実際に来ていただいてお客様に摘んでいただいて、それをその場で束ねていただけるような、なんかそういうワークショップを、農園に漂うハーブの香りや空気を感じながら、そういう制作とか、農園で安らいでいただけるようなことをやっていけたらいいなというふうに思っております」
INFORMATION
『ドイツ式 ハーブ農家の料理と手仕事〜育てる、味わう、丸ごと生かす』
奥薗さんの新しい本をぜひチェックしてください。ドイツ流のハーブの使い方や活かし方のほか、人気ハーブ20種の育て方のコツや、お料理のレシピなどが豊富な写真とともに紹介。お話にもありましたハーブオイル、ハーブマヨネーズ、ハーブバターのレシピも載っていますので、ぜひ参考になさってください。山と渓谷社から絶賛発売中です。詳しくは、出版社のサイトをご覧ください。
◎山と渓谷社 :https://www.yamakei.co.jp/products/2823450680.html
「lala farm table(ララファームテーブル)」のオフィシャルサイトも見てくださいね。奥薗さんが育てたハーブや野菜などがオンラインで販売されています。
◎lala farm table:https://lala.farm
奥薗さんは今月、丸の内や日比谷、有楽町、豊洲で開催される「東京味わいフェスタ2024」に出店される予定です。「lala farm table」のブースは日比谷に出店予定。開催日程は、10月25日から27日までの3日間。詳しくは「東京味わいフェスタ2024」のサイトをご覧ください。
◎東京味わいフェスタ2024:https://www.tasteoftokyo-ajifes.jp
2024/10/6 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、標本画家の「川島逸郎(かわしま・いつろう)」さんです。
標本画とは、科学的な裏付けのもとに描かれ、図鑑や科学論文に掲載される動植物の絵のこと。川島さんは、専門家たちが一目置く標本画の第一人者で、先頃新しい本『標本画家、虫を描く〜小さなからだの大宇宙』を出されました。
きょうはそんな川島さんに、極細のペンを使って「点と線」だけで描く昆虫、まるでモノクロ写真のように見える精密な標本画についてお話をうかがいます。
☆協力:川島逸郎、亜紀書房

必ず本物を見ながら描く
※川島さんが標本画を描くようになったのは、大学に入ってからで、かれこれ30年ほどになるそうです。標本画は例えば昆虫なら、その昆虫の標準的な姿を描くようにすることが大事で技法はいろいろあるものの、基本的に点描画が多いとのこと。
川島さんも、点と線だけで描く技法に取り組んでいらっしゃいますが、点を打つにしても線を引くにしろ、細かい作業を強いられるので、さぞかし大変かと思いきや、ご本人曰く、根気はいるけれど、30年もやっているので慣れてしまったとか。
心がけているのは、描くことに熱中し過ぎると実物から離れてしまうので、時々その標本に立ち戻ることだそうです。使っているペンは、漫画家さんが使う丸ペンと、製図用のペンでペン先の直径が0.1ミリから0.3ミリを使っているとのこと。
また、標本画はモノクロが多いそうですが、何を伝える絵なのかによって、例え、色彩を伝えるためなら色をつけたり、形を示すのであれば、モノクロに留めておくなど、情報を詰め込まず、目的によって使い分けているそうです。
●川島さんが先頃出された本『標本画家、虫を描く〜小さなからだの大宇宙』にカブトムシのオスの標本画が掲載されています。体の黒い色や光沢、そして丸みがかったフォルムなどまるでモノクロ写真のようなんですが・・・これは標本を見ながら描いたんですよね?

「そうですね。標本、実物ですね。それ以外から描くってことは、まず、ほぼないですね。必ず本物から描きます」
●細かい部分は顕微鏡で見ながら描くんですか?
「カブトムシは、そうは言っても昆虫の中では巨大なもんですから、顕微鏡も使うんですけれど、そういった場合には触覚だけを見るとか、口の先っちょだけを見るとか、爪の先だけを見るとか、そういった時には使います。全体的には普段私、巨大な虫あまり描かないもんですから・・・。
カブトムシの場合は、測る道具があるんですけども、コンパスみたいな道具があるんです。それであちこち測っといて、大まかな形を描いといてから、細かな部分は顕微鏡で確認してからということになりますね」
●なるほど・・・。このカブトムシの標本画を完成させるまでに、どれぐらいの時間がかかったんですか?
「え~っと10日ぐらいですね。昔だと大体2日か3日で描いたんですけれど、やっぱりそう描けなくなってきて(苦笑)、10日かそれ以上かかるようになってきましたね」
●細かい作業ですよね~。この絵の対象になる昆虫の標本は、川島さん自身が採取してきた昆虫なんですか?
「私自身が自分で採取することもあるんですけれども、例えば絵を描いてくださいって言われた時に、その虫の専門家が頼んできたりってことがあるもんですから、それはその専門家が採取したものだったり、あとは各地の博物館に収まっているものをお借りしたりとか、それは毎回状況は違います。
自分でもなるべく捕るようにはしているんです。ただ、昆虫ってのは膨大ですから、自分のところですべてあるってことはあり得ないです」
●海外の昆虫を描く場合はどうしているんですか? 写真を見て描くんですか?
「写真を見て描くことは100パーセントないですね。必ず標本、本物、実物なんですけども、大体その場合はそれを持っている研究者だったり、それを収蔵している博物館だったり研究施設だったり、そういったところからこれを描いてくださいっていう形でお借りすることになって、それで描くわけです」
●なるほど。必ず標本をもとにされているんですね。
「そうですね~。はい」
職人技のスケッチ
※絵にする昆虫の大きさとか、頭や胴体、足などの長さは正確じゃないとだめですよね? どうやってスケッチするんですか?
「昆虫の場合は、やはり外側が硬くて外骨格、海老とかカニと同じで、外側が硬いもんですから・・・比率とか長さとか、みんなちゃんと種類ごとにある程度決まっているので、そこが正確じゃないといけなくて、分かれている節の数とか・・・。
そういった場合に顕微鏡で写生するんですね。全くお聞きになったことはないと思いますけれども、『描画装置』っていうのがあります。顕微鏡をイメージしていただくと、目で覗く部分がありますよね。レンズがあります。『接眼レンズ』っていうんですけれども、そこの手前にそれをはめるんです。はめるとプリズムだったり、斜めになった鏡がついていて・・・私は右利きなんですけれども、右利きのペンを持った手と、覗いた虫が一緒に重なって見えます。それでなぞってトレースしていくわけです」

●へぇ~、そういう装置があるんですね。掲載されている標本画の多くは真上から見た構図になっていましたけれども、それはいわゆる昆虫標本と同じようにされているっていうことなんですか?
「そうですね。全身像を描く場合には、大体真上からっていう場合が多いです。虫によっては、トンボとかハチみたいなものは、側面から見たほうが特徴があって、そこに(その対象の)情報があるので、そういった場合には横向きにしますけれども、大体全身を示す時には背中、真上から見ることが多いですね」
●標本画を描かれている時にその昆虫の体の構造などから、新しい気づきだったりとかってあったりしますか?
「それは非常に多いですね。私たちが例えば、見慣れている蝶々だったりしても、飛んでひらひら舞っている姿はよく見ますけども、例えば口がどうなっているかとか、そういったところを初めて知ったっていうことは、いつもいつも毎回どんな虫でも、身近な虫であっても(気づきがあるので)、それが楽しみでもあるんですけども・・・」
●描く作業されている時は、どんなこと考えていらっしゃるんですか?
「描く作業している時にはあまりものは考えない・・・考えられないってこともあるかもしれません。ただ、例えば点を置いたりしますけれども、そういった時には点をひとつひとつ置きながら、次にどこに点を打つかというようなことは、半分無意識的なんですけど、ここに打ってここに打ってみたいな、その連続ですね」
●へ~〜、次のこと考えながら点を描いているんですね~。
「次に点を、ひとつの点を置く位置を見ながら、次はここに置こう、ここにっていう・・・」
●へぇ~すご~い、職人技ですね~!
「うん、そうですね。それは職人技って言えるじゃないかなと思います」
(編集部注:実は川島さん、30代の頃に目を患い、人工レンズを入れたことで意のままに見えなくなったそうです。画家としてはとても辛い状況になり、絵を描くために、対象である昆虫を顕微鏡で見ることになったそうです。最初はピント合わせがうまくいかず、慣れるまで大変だったそうですが、いまでは当たり前にこなせるようになったとおっしゃっていました)
線一本引くにも根拠がある
※標本画に向き合って、うまくいかないこともあると思いますが、あと少しで完成、というときに描き損じたりしたら、そのときはどうするんですか? いちからやり直すこともあるんですか?
「これは、いちから描き直しだなってくらい大きな失敗はまあ・・・まずない。ところが近年、一度もなかったような大失敗をしたことがあって、それは今回の本に書いたんですけれど、それも(いちから)描き直ししないで、その部分だけ切り取ってっていうことはしましたけども、そのぐらいですね。

あと部分的には紙にインクがにじんだりとか、そういうことがあったり、昆虫の毛を描くときに先がシャープに細くなっていたりっていうか、ちょっと失敗することがあって、非常に細かいんですけど、そういうのは普通に白い絵の具で塗って修正はしますね。でもそれは普通なことなんです」
●すごく緊張感のある作業ですね。
「そうなんですけど、私自身は楽しいんですね。ここを白で修正しなきゃみたいな、それをやってるのも、ものがちゃんと出来上がっている感じで、すごく楽しい!」
●本来、絵は描く人の自由な発想とか表現方法があって、自由奔放なものなのかなって思うんですけれども、川島さんが向き合っている標本画は、正確に昆虫を再現する制約があるように感じるんですが、描くときによりどころにしているものとかってありますか?
「例えば生き物の絵もそうなんですけど、そういった自由自在な、まあ絵っていうのは本来自由自在で、そこが楽しいんですけども、たまには線一本引くにも、これはなぜここの線を引かなければならないか・・・みたいな、そういった根拠がある絵って言うのが、今本当になくなっているんですね。
逆にそういった絵があってもいいな~と思って、必ずここには理由があって、なぜこう描いているかっていうのは、必ず背景に基づくんですよっていう根拠があるんですね。それが(今)なくなってきただけに、それが生き甲斐っていうんですかね。そういうのを自分は取り込み続けてもいいんじゃないかなっていう、それがよりどころですかね」
●川島さんは大学時代に昆虫を研究されて、現在は「日本トンボ学会」や「日本昆虫分類学会」の会員でもいらっしゃいます。川島さんにとって標本画は、研究に近いことなのかなって思ったんですけれども、いかがですか?
「はい、ほぼ研究ですね。それが私の絵らしさの、おおもとになっているもんですから、やっぱりそういった研究的な視点で対象を見て、それをいかに他者に伝えるために表現するかっていうことが、やりがいっていうんですかね。でも楽しいことではあるんです」
人懐っこい「サラサヤンマ」
※川島さんがいつ頃から生き物の絵を描くようになったのか・・・川崎市に生まれ育った川島さんは、幼稚園に入る前から昆虫が大好きで、当時まだ川崎近辺には武蔵野の名残があり、田んぼなども残っていたことから、トンボやカエルを捕まえたりするような子どもだったとか。

また、絵を描くのも大好きで、図鑑を見ながら、昆虫の絵を描いていたそうです。そして中学・高校では野鳥にも興味を持ち、自宅で鳥を飼うような少年だったそうですよ。
●川島さんは、大学では昆虫の研究をされていたそうですね?
「そうですね。大学に入る時に、私もあまり学校の勉強ができたほうではないので、絵を描くかどうするかなって思った時に、昆虫の絵をしっかり描くには、絵は後からでも勉強できるかもしれないけども、昆虫学っていうのは必ずこれは知ってないと描けないなって、その頃からちょっと思っていたんですね。なもんですから昆虫を学べるところにっていう経緯ですね」
●どんな研究をされていたんですか?
「ただ、そうは言っても学生ですから、特に私なんかあまり・・・周りには優れた学生がたくさんいたんですけどね。
私はトンボが好きだったもんですから、その頃、熱中していたトンボがいました。それはまだどんなふうに育っていたのかわかっていなかったもんですから、せっかくだから調べてみようって・・・研究っていうか観察日記の延長みたいな、そのくらいのことしかしてなかったんですね」
●ちなみになんていうトンボなんですか?
「それは、サラサヤンマっていう、ちっちゃいオニヤンマなんです」
●サラサヤンマは、どんな特徴があるんですか?
「ヤンマって言うと、普通は例えばオニヤンマだったり、大きなトンボを想像されると思うんですけれど、(サラサヤンマは)すごく小さいですね。それが水辺っていうか、山の谷あいの湿地みたいなところに棲んでいるんですけども、すごく人懐っこいって言うんですかね。
普通トンボって言ったら、例えば(人間が)近づいていくと逃げていきますよね。ところがサラサヤンマは湿地に棲んでいて、変わっていて、暮らしぶりもわかってない・・・。成虫に向き合った時に、オスは縄張りを張って、ずっとじーっと空中の一点で止まって、縄張りを飛びながらですね。
例えば写真を撮ろうとしますよね。そしたらレンズに止まろうとして、追っ払っても払っても・・・私は飛んでいるところを撮りたいんですけど、手で追い払ってもまたレンズに止まりに来ちゃうような、そんなところがあったもんですから・・・。
解明されてなかったことも多かったし・・・すごく色も綺麗なんですね、『サラサ』って名前つくぐらいですから。黄色と緑のちっちゃい波紋が体全体に散りばめられたようなトンボなんです」
●人懐っこいんですね!
「そうですね。ほかのトンボとちょっと趣が違うんですね」
(編集部注:川島さんは、2012年から神奈川県立生命の星地球博物館、2014年からは川崎市青少年科学館で、学芸員をやっていたこともあるんです。学芸員時代にトンボの特別展に向けて、先輩学芸員からポスター用の絵を描くように言われ、手がけたこともあるそうですよ。
そんなこともあり、自然に生き物の絵を仕事にするようになった川島さんは、時代の変化に伴い、手描きの標本画がだんだん消えていくのを憂い、その素晴らしさを伝えるために、最後の生き残りになっても、標本画を描き続けたい! そんな気持ちを抱くようになったそうです)

ハチとトンボはわかりやすい!?
※よく質問されることだと思いますが、いちばん好きな昆虫はなんですか?
「一番目はハチですね。二番目ぐらいがトンボですね」
●えっ、ハチですか? そうなんですね。トンボがいちばんなのかと思いました。ハチがいちばん好きな理由っていうのは?
「小さな頃は、川崎で採取、虫取りしていた頃は、例えばクワガタムシなんかをやっぱり最初は捕るんですね。ところが同じのしか捕れないんですよ。ハチは非常に種類が多くて、形も様々で綺麗な斑紋を持っていたり、それがもう捕っても捕っても次の種類が捕れる、それが非常に楽しかったってことと・・・。
あと私が大きくなってからは、標本だけじゃなくて野外での虫の生態、それも知ってないと、やっぱり描く大事な要素になりますので・・・。虫の写真を撮った時に、ハチとトンポは、虫が何したいかってのがすごくわかりやすい・・・。野外で昆虫の暮らしを見ていた時に、例えば獲物を狩りたいんだなとか産卵したいんだなってのは、すごくわかりやすいわけです。それが非常に野外で虫の生活を見ていて楽しかったんですね。
例えばそれがセミだったら、ミンミン鳴いていますけれども、なかなかいつ産卵したいのかなって、表情が鳴いている以外はわかりにくいんですね。今は私でもわかるようになったんですけども・・・。ところがハチとトンボは、見て何したいんだなってわかりやすいってのが、すごく親近感を覚えるっていうか、楽しさもあります」
●昆虫をよく見て絵を描くっていうのは、その昆虫を、ひいては自然を知ることにもつながりますよね? 是非、子どもたちにもやってほしいですよね。
「そうですね。それが例えば虫ではなくても、その虫を描くっていうのではなくても、身近に共に生きている生き物、あとは自然環境ですね。
それがすごくわかりやすいって言うんですか、虫を見ることによって自然のありよう、環境のありようってのもわかりやすいもんですから、その自然感を一般の人にも持ってほしいなっていうのは、(以前)博物館にも勤めたもんですから、よくそのようなことを考えていました」
●では最後に、川島さんにとって昆虫とは?
「そうですね・・・昆虫がそうしてくれているわけではないんですけれども、人に例えるならば、恩人ですね。私のひとつのキャラクターを形づくってくれたっていうんですかね。虫がなければ、私らしさってのも出せなかったかもしれませんので、そういった意味ではその恩があります」
INFORMATION
川島さんの新しい本には専門家が一目置く、点と線だけで描いた緻密な標本画が100点掲載されています。また、文章からは自ら描いた標本画と昆虫に向き合う生き様を感じ取ることができると思いますよ。ぜひ読んでください。亜紀書房から絶賛発売中です。詳しくは、出版社のサイトをご覧ください。
◎亜紀書房 :https://www.akishobo.com/book/detail.html?id=1176&st=4
川島さんのオフィシャルサイトも見てくださいね。学芸員時代に特別展のポスター用に描いたトンボ「ヤブヤンマ」のカラーの絵も見ることができますよ。
◎川島逸郎オフィシャルサイト:https://www.kawashima-itsuro.com