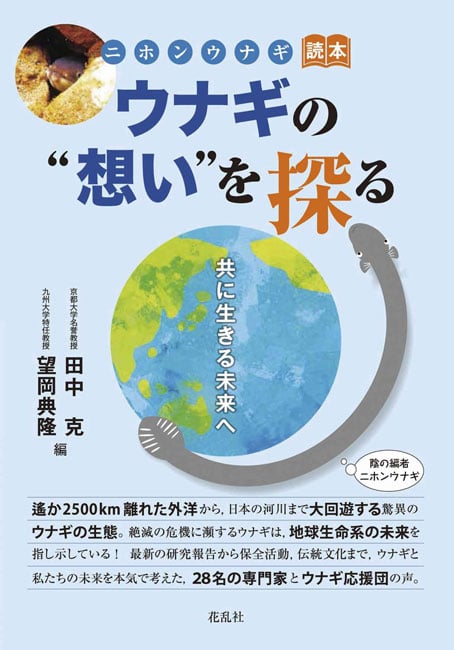2025/2/16 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、植物観察家の「鈴木 純(すずき・じゅん)」さんです。
鈴木さんは1986年、東京都生まれ。親御さんの影響もあって、子供の頃から野山が大好きだったそうです。そして東京農業大学で造園学を学び、その後、青年海外協力隊に参加し、中国で砂漠の緑化活動を行ない、帰国後、国内外のフィールドを巡り、植物への造詣を深めます。
そんな鈴木さんは、友達に植物の面白さを伝えたいと思い、気軽に集まれる街中での観察会を始めたそうです。そして2018年から「まちの植物はともだち」というテーマでフリーの植物ガイドとして、街中での植物観察会を実施。また、植物生態写真家としても活躍されています。
鈴木さんの新しい本が『冬芽ファイル帳〜かわいくて おもしろい 冬の植物たち』ということで、きょうは、暖かくなる春をじ〜っと待っている「冬芽(ふゆめ)」に注目! よ〜く見ると可愛くて個性的な冬芽の観察方法や楽しみ方などうかがいます。
☆写真:鈴木 純 出典:「冬芽ファイル帳」小学館

冬芽は赤ちゃん!?
※鈴木さんが「冬芽」をテーマにした本を出そうと思ったのは、どうしてなんですか?
「これは、”冬芽”っていう言葉は聞いたことがある人は、それなりにいると思うのと、なんとなく顔っぽいものとか、なんかそういうイメージ持っている人もいるような気はするんですが、冬芽を実際にどう楽しめばいいかみたいな本は、そういえばないなって、ふと気づきまして・・・。なので、ないから僕なりに紹介してみたいなと思って作ったというところですね」
●観察も簡単そうですよね。
「そう、それがいちばんポイントかなと思っています。そもそも冬に植物を見るっていうイメージがない中で、実は冬の植物観察がたぶん1年の中でいちばん簡単っていうことがあるんですよ。なんでかっていうと、ただただ枝の先端を見るだけなんですよね。極めてシンプルな観察ですね、冬芽は(笑)」
●初歩的なことなんですけれども、改めて「冬芽」っていうのは何なのかご説明いただけますか?
「冬芽は、ちゃんと定義していくと難しいんですけど、簡単にいうと冬に芽が休眠している状態を冬芽と呼ぶと捉えるのがいちばん分かりやすくて・・・。で、芽は要するに葉っぱとか花のもと、赤ちゃんみたいなものと捉えていただければいいのかなと思うんですね。葉っぱとか花の赤ちゃんが、冬に出てきてしまったら、寒さとか乾燥ですぐダメになっちゃうんですね。
なので、冬の間はまだ芽の中で待っていてもらいたいわけなんです。その時に休眠っていう状態になって冬をやり過ごすわけですね。で、春になっていい季節になったら、葉っぱとか花をパッと出す状況に姿が変わるわけです。冬の間、待機している状態の芽を冬芽という、そういうところをおさえればいいかなと思います」
●秋に葉っぱを落とす落葉樹だけが、冬芽をつけるんですよね?
「そのイメージがあるんですけど、実は葉っぱを落とすとか落とさないっていうのは関係なくて、冬に葉っぱを落とさない常緑樹でも冬芽は実はついているんです。ただ、葉っぱがついていると枝先が見えにくいんですよ。なので、常緑樹には冬芽がないって思いがちというだけの話で、別に常緑樹だろうが落葉樹だろうが冬芽はあるという感じです」

冬芽にキャッチコピー!?
●掲載しているそれぞれの冬芽にキャッチコピーがつけられているのが、すごく面白いなと思いました。例えば「今日も決まった!アフロヘア」とか、「頭抱えて、はや3ヶ月」とか、「枝先のアルパカ、休憩中」など、本当にその冬芽の特徴を捉えていて素晴らしいなと思ったんですけど、これは全部、鈴木さんが考えたんですか?
「そうですね。一応、原案は私が考えまして、これを編集者さんに投げるわけです。なので毎回毎回、大喜利みたいな感じで、これで編集者さんを笑わせてやろうという気持ちで考えていました(笑)」

●そうなんですね。いろんなものに例えると面白いですよね。
「そうですね。それがたぶん冬芽観察のいちばん簡単な観察方法で、名前がわかるのはやっぱりいいんですよ。樹木の名前がわかるのはいいんですけど、植物観察において名前を調べるということが、まず第一歩目のハードルになっちゃう人って結構多いんですよ。
だけど、冬芽の場合は見た目がユニークなので、名前がわからなくても楽しめちゃうんですね。で、自分でキャッチコピーをつけちゃえば、それでOKなので、そういう意味も込めて、全部にキャッチコピーをつけてみたということなんです(笑)」
●冬芽の写真をよーく見ると、本当に人の顔に見えるのがすごく不思議です。目とか口に見えるあの点のようなもの、あれは何なんですか?
「ありがとうございます。そこをちゃんと説明しないといけないですよね。実は冬芽っていうと、顔のように見える写真がよく紹介されるんですが、この顔は・・・顔といってもパーツで考えると、頭の、髪の毛とか帽子の部分と、それから顔の輪郭、あの目とか口がついている部分と、2パーツに分けられるんです。そのうち冬芽って呼んでいるのは、帽子とか髪の毛の部分のことで、顔の部分は実は冬芽ではないんですね。

これは”葉痕(葉痕)”といって、葉っぱが取れたあとに残る痕跡、葉っぱがついていた痕跡です。だから顔の輪郭自体は葉っぱの付け根の形ですね。で、その中にある点々は、葉っぱがついていた時に、葉っぱと枝の間を水分とか養分が通っていた、その通り道みたいな管があるんですけど、葉っぱが取れたあとにその管が名残として枝のほうに残るんですよ。
なので、目とか口の点々は、水分とか養分の通り道だった痕跡だと思っていただければってことですね」
●冬芽の大きさって木によってそれぞれ違うと思うんですけど、大体どれくらいなんですか?
「これが、ちっちゃいもので2ミリぐらい、2ミリって大変ですよね(笑)。すごく小さいです。で、大きいものでも2センチ程度かな、中には5センチぐらいの、もっと大きいものもあるんですけど、そういうのは稀なので、だいたい2ミリから2〜3センチっていうところだと思いますね」
(編集部注:冬芽の観察にはルーペがあったほうがいいとのことです)
ウロコ状の冬芽の正体
※『冬芽ファイル帳』に、ウロコのようなものに覆われた冬芽の写真もありました。あのウロコ状のものはなんですか?

「これが冬芽の結構大事なポイントで、冬芽は見た目で可愛いとか面白いとかで楽しめばいいっていうのがひとつなんですけど、もうひとつは冬芽が、要するに冬の間、春が来るのを待っている状態なので、寒さとか乾燥から身を守るための何かしらの仕組みがあるわけなんですよ。
その冬芽の周りにウロコがあるのは、そのウロコの中に芽が隠されているんですね。赤ちゃんの葉っぱとか花を隠しているわけです。それがそのまま枝先に芽の状態でついていたら、寒さとか乾燥にやられてダメになっちゃうので、その周りにウロコをくっつけて中身を守っているような器官っていうものになります。それがウロコですね」
●冬芽によっては毛が生えたようなものもありましたよね?
「そうそう、そのウロコにもいろいろあって、ツルツルなウロコで、しかも何十枚も、20枚とか30枚とかいっぱい重ねて、中身を守っているのもあれば、ウロコ自体の枚数は少ないんだけど、ウロコに毛が生えているってこともあるんですよ。そうすると毛は単純にあればあるほど、イメージ通りだと思いますけど、寒さとか乾燥対策になるので、それもやっぱり冬対策になっていると思います」

●中を守るっていうことですけど、その冬芽の中はどうなっているんですか?
「冬芽の中は基本的には3パターンって思うといいかなと思うんですね。中に花だけが入っている冬芽、花の芽って書いて”花芽(かが)”、あるいは葉っぱだけが入っている”葉芽(ようが)”、そして葉っぱと花が両方入っている、混合の芽と書いて”混芽(こんが)”。だから冬芽の中身は何ですかって言われたら、その3パターンです。花が入っているか、葉っぱが入っているか、葉っぱと花の両方入っているかっていう感じになります」
●樹木が冬芽を準備するのっていつ頃になるんですか?
「これは、どこからを冬芽って呼ぶか問題が出てきちゃうんですけど、簡単にいうと芽自体は、春に葉っぱが出てきた時にすでにもうあるんですよ。3月、4月の新緑の時期にすでに芽はある。だけど、ものすごく芽が小さいので、ルーペを使っても見えないんです、基本的には。
それがだんだん大きくなっていって、夏ぐらいになると私たちの目でも見られるぐらいの大きさになってくるんですよ。厳密にいうとその時点は冬芽って呼ばないんです。要するに冬芽は冬に休眠している芽のことをいうので・・・。だから冬芽のもと、みたいなものっていう話になっちゃいますけど、それ自体は夏ぐらいからは観察できるってことですね」
●では、冬じゃなくても観察は一応できることはできるってことなんですね。
「そうです。なので僕は大の冬芽好きなので、実は冬芽観察は夏から始めています。結構楽しいです! 夏の冬芽観察」
冬芽観察のコツを紹介
※この時期は冬芽の観察にいい季節だと思うんですが、観察のコツがあったら、教えてください。
「観察のコツは、とにかく近づくことですね、冬芽は。なぜならものすごく小さいので・・・。私は今回の本でいちばん懸念していることは、写真だと冬芽が大きく見えちゃうんです(笑)
なので、見つけやすいものかなって思っちゃうんですけど、実はものすごくちっちゃいので、枝先への近づき方、普通に考えているくらいの近づき方じゃ見えないので、ほんとに間近・・・目のすぐそばまで枝を近づけないと見えない。それがいちばんコツですかね。小っちゃいんだ! って思って近づいていくこと」

●なるほど~。
「あともうひとつは、要するに小っちゃいと思って近づいていくっていう意味は、そこに本当に(冬芽が)あるかどうかわからないで近づいていくんですよ。可愛い冬芽があるのかな~? ほんとかな~? って思いながら近づいていくんですが、それを信じる! っていうことですね。この枝先に可愛い冬芽があるはずだって、どれくらい信じられるかっていうところが結構大事かなって思いますね(笑)」
●ルーペと鈴木さんの本を持って行けば大丈夫ですね!
「そうですね。ぜひ私の本もお願いします(笑)」
●やっぱりひとつの冬芽でも見る角度によって表情も変わりますよね?
「変わりますね! ぜんぜん違うんですよ。今回の本は見やすい角度で写真を撮っているんですけど、これが違う角度で写真を撮ると、表情が全く変わってくるんですよね・・・なので、そこに冬芽観察していくことの楽しみが、たぶんあると思いますね。見る人によって違うものが見えると思います」
●それも面白いですね~。
「はい! 面白いと思います」

●スマホなどでつい冬芽の写真を撮りたくなっちゃいますね!
「そうなんです! それ、僕はおすすめだなと思いますね。最近スマホのカメラの性能がすごく上がっているので、意外と冬芽は撮れるっぽいんですよね。それでコレクションしていくと楽しいかもしれません」
●この本でもファイリングをすすめていますけれども、上手なファイリングの仕方とかあったらぜひ教えてください。
「僕自分自身でもやっているんですけど、Instagramで集めていくのが結構楽しいかも! っていうのは、一枚一枚の写真を見るのもいいんですけど、Instagramの(自分の)プロフィールのところにいくと、小っちゃい写真がばぁ~って並ぶじゃないですか、スクエアで。あの状態で冬芽がいっぱい並ぶとすごいんですよ(笑)。すごく可愛い状態のプロフィールができあがるので、あそこに集めていくのがいいんじゃないかなって今は思っています」
(編集部注:ほかに観察のコツとして、同じ場所の同じ木を観察するのもいいし、今年はこの樹木の冬芽を観察すると決めたら、街中にある同じ樹木の冬芽を見るのも、おすすめだそうですよ)
※冬芽を観察すると、春になったらどんなふうに芽吹くのか、見たくなりますよね?
「まさにそれがいちばんの効果かもしれないですね。冬の間ってほんとにすることないじゃないですか。ないじゃないですかって、ごめんなさい。これは植物の世界の常識を話しちゃったんですけど(笑)、植物の人たちは冬の間はすることがないんです。っていうのは、とにかく冬は植物が動かないわけなんですよ。休眠しているんでね、そもそも・・・。
だから、休眠している状態をず~っと見ていると、その芽の内側にある葉っぱってどんな形なんだろうな? とか、この花ってどういうのだっけ? とか、どんどん先の季節の想像が自分の中でわいてくるんですよ。そうするとやっぱり春が来ることの楽しみっていうのは、すごくどんどん増していきますね」

●芽吹きを見るのに、おすすめの樹木ってありますか?
「私は“ヤマブキ”が好きで、芽吹きとしては。っていうのは、街中にヤマブキはよく植えられているっていうのと、さっきの冬芽の中身って話でいうと、葉っぱと花が両方セットで入っているんですよね。なので、芽吹きの時に黄色いヤマブキ色の花と緑色の葉っぱが同時に出てくるんですが、まるで踊っているみたいな感じで出てくるんですよ。それが非常に観察しやすいのと可愛いっていう意味でヤマブキ、おすすめです!」
(編集部注:鈴木さんの本に「日本三大美芽(びが)」というのが紹介されていて、その三大美芽には「ネジキ」「コクサギ」そして「ザイフリボク」という樹木の冬芽が選ばれています。鈴木さんがおっしゃるには、どなたが選んだのかは不明だそうです)
植物に励まされる
※冬芽を観察していると、どんなことを感じますか?
「なんかやっぱり生きているんだってことですよね。樹木って葉っぱが落ちた状態で見ると、ほんと寂しいじゃないですか。“枯れ木”っていう表現もあるくらいですから、枯れたように見えちゃうけれども、枝先はしっかり生きているって思うと、なんか・・・僕は冬に限らず植物を見ていると、すごく励まされることが多くて・・・。
冬芽に関しては活動していないように見えるけれども、その内側は活動しているわけですよね。っていうのを見ているとなんかいいですよね。“今自分はちょっと足踏みしているんだけど、自分の中は実は次の熱いものが入っているんだぜ!“みたいな・・・そういう”だよね“っていうのを、樹木を見ながら僕は冬にすごく思っているわけなんです。そういうところが僕はすごく好きですね(笑)。いいなと思います」
●鈴木さんが思う冬芽のいちばんの魅力って何でしょうか?
「あ~やっぱり今言っちゃったことかな(笑)。その内側に答えがあるっていうのが魅力だと思いますね。
春から秋にかけての植物観察ももちろん楽しいんですけど、その時は植物の動きが早いんですよ。芽吹いたと思ったら花が咲いて、花が咲いたと思えば実になって、タネを飛ばしてって感じで、どんどん姿が変わっていっちゃうので、こっちは植物の動きについていくのに必死なんですよね。楽しんですけど、疲れちゃうですね(笑)。
冬だけはものすごくゆっくりやっていい。ゆっくりやっていいんだよっていう余地を与えられるところが、僕はすごく魅力的だと思います」
☆この他の鈴木 純さんのトークもご覧ください。
INFORMATION
鈴木さんの新しい本をぜひご覧ください。それぞれの冬芽の特徴を捉えたキャッチコピーが見事ですよ。例えば「はんなり美人」と「ハートツリー」。「はんなり美人」はナツツバキで、冬芽を覆うウロコの形がまさに着物のえりのように重なっていて、薄い緑を基調とした和風な色合いと形が美しいです。そして「ハートツリー」はニワウルシ、枝にくっきりと綺麗なハートのあとがあります。ぜひ本でお確かめください。

ほかにも街中や野山でもよく見られる樹木の冬芽が、豊富な写真とともに掲載。ひとつの冬芽が見開2ページで紹介されているので、見やすくて使いやすいですよ。冬芽観察の決定版! ぜひチェックしてください。小学館から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎小学館:https://www.shogakukan.co.jp/books/09311578
鈴木さんのオフィシャルサイト「まちの植物はともだち」もぜひご覧ください。
◎まちの植物はともだち:https://beyond-ecophobia.com
2025/2/9 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンは、シリーズ「SDGs〜私たちの未来」の第24弾! 「SDGs=持続可能な開発目標」の中から、「貧困をなくそう」
「働きがいも経済成長も」「人や国の不平等をなくそう」そして「陸の豊かさも守ろう」ということで、「森と生きるチョコレート」をクローズアップ!
ゲストは「mamano chocolate(ママノチョコレート)」の代表「江澤孝太朗(えざわ・こうたろう)」さんです。
江澤さんがなぜチョコレート店をやろうと思ったのか、そのきっかけは、知り合いがエクアドルから買ってきてくれたアリバカカオで作ったチョコを食べたところ、ライチのようなフレーバーと味に感動!
もともと環境や人権の問題に関心のあった江澤さんは、先住民が「チャクラ農法」という自然農法で作るアリバカカオに魅力を感じたそうです。当時、起業するために会社を辞め、宮城県南三陸でボランティア活動をやりつつ、どんな事業をやろうかと考えていたタイミングだったこともあり、アリバカカオなら、その希少性や美味しさだけで勝負できると思い、チョコレートの事業をやろうと決断したそうです。
といっても、まったくの素人だった江澤さんは、チョコの作り方をYouTubeなどで必死に勉強し、試行錯誤しながら、アリバカカオのチョコをついに製品化。そして2013年に赤坂見附に「ママノチョコレート」をオープンすることができたそうです。ちなみに、エクアドル産のアリバカカオは、世界でわずか2%の希少品種だそうです。
きょうは江澤さんに、おすすめのチョコや、現地のカカオ農家を支援する活動のことなどうかがいます。
☆写真協力:mamano chocolate

希少なアリバカカオ
※お店の名前「mamano」にはどんな意味があるんですか?
「mamanoはスペイン語で、ママとマノの造語なんですけど、ママがお母さん、マノが手で、お母さんの手という意味でつけていますね」
●ママノチョコレートでは、エクアドル産の希少なカカオ「アリバカカオ」を原材料にして、チョコレートを作っているということなんですけれども、アリバカカオっていう豆がどれくらい希少なのか、あまりイメージがわかないんですね。どのぐらい希少なんですか?
「先ほど世界で2%とご紹介いただいたんですけど、基本的にはエクアドルの固有種で、ほかの国だとあまり育てることができないとずっと言われていて、(他の土地に)持って行っても香りが変わったりとかするので、基本的にはエクアドルの、そんなに大きくない国の中で育てられているものだけですね」
●エクアドルには、どれくらいの数のカカオ農園があるんですか?
「カカオ農園の数はわからないんですけど、アリバカカオの量でいうと10万トンとか・・・世界のカカオ豆は460万トンぐらいだと思うんですけど、10万トンから20万トンぐらいがアリバカカオと言われている品種だと思いますね」
●ほかのカカオと比べて風味とか、どんな特徴があるんですか?
「風味はまず圧倒的にフローラル、華やかっていうのが特徴ですね。本当にお花を想起させるような、白いお花とか黄色いお花とか、そういうのを想起させるような香りが特徴です。あまり酸味もなく渋味も強くなく、っていう感じで食べやすいチョコレートですね」

●江澤さんご自身もエクアドルに買い付けに行かれるっていうことですよね。
「そうですね。現地にひとりパートナーがいて、2013年から一緒にやっているんですけど、私自身も年に1回か2回、行ったりします」
●初めて買い付けに行かれたのは、いつ頃だったんですか?
「初めて行ったのは、実はお店を始める前ではなくて、お店を始めてから3年くらい経ってから行きました。
最初はお店でチョコレートを作るのに必死で、(買い付けは)現地のメンバーに任せて・・・その時は知人が手伝ってくれていたので、買い付けのほうは任せて、自分はチョコレート作りに必死になっていましたね」
●へぇ〜! でもそんなに希少な豆っていうことは、買い付けして輸入するのも大変なんじゃないですか?
「そうですね。品種だけじゃなくて、高いクオリティで安定的に輸入するのがすごく大変ですね。アリバカカオだけであれば、山ほどあるというか、例えば発酵させないでもアリバカカオはアリバカカオだし、品質の悪いものであれば、いくらでも調達できるんですけど、気候変動の影響もありますし、去年からカカオの急騰も始まったので、そういう時でも常に安定的にいいものを買うのは結構大変ですかね」
スタジオでチョコレートを実食!
●きょうはスタジオに、ママノチョコレートで製造販売されているチョコレートをご用意いただきました。美味しそうですね!
「アマゾンアリバ」「58%アリバカカオとアマゾンバニラ」そして「70%野生クリオロ」という3種類をご用意いただいたんですけれども、パッケージもとてもおしゃれで可愛いですね! ギフトにもすごくいいですよね。
「そうですね。お店も赤坂にあるので、お土産で使っていただくことが多いですね」
●では、どれからいただこうかな・・・まずは「アマゾンアリバ」から。この「アマゾンアリバ」とはどんなチョコレートなんでしょうか?

「アマゾン地域のアリバカカオを使ったチョコレートで、これはカカオ70%に仕上げています。ちょっと珍しいのは5日発酵とか、チャクラ農法とか、かなり細かくそのカカオの出元を(パッケージに)書いているのがひとつ特徴です。
味としては、ザクザク食感に仕上げているチョコレートで、アリバらしい華やかな香りと、何ていうんですかね・・・コンチングっていう練る工程を通していないので、香りが全然飛ばずに、ぎゅっと凝縮した香りを楽しんでいただけるチョコレートです!」
●見た目は小さくて薄い板チョコのような感じですけれども・・・ではちょっといただきます〜!
「ザクザクした感じですかね」
●んん〜! 本当だ! ザクザクの食感が楽しいですね! 噛むごとにいろんな香りがする感じがします!
「感じますか!? バナナとかワインとか・・・」
●確かに! ナッツのような香りもするし・・・。
「そうですね。同じアリバカカオでもアマゾン地域で育ったアリバカカオは、だいたい100作物ぐらいと一緒に育っているので、すごくいろんな香りが混ざってくるっていうか、やっぱりテロワールが、土地の香りが影響してくると思いますね」
●優しい甘みで美味しいです! 続いて「58%アリバカカオとアマゾンバニラ」、これはどんなチョコなんでしょうか?

「これは、アマゾンバニラも現地でしか採れないバニラ、珍しいバニラビーンズを使っていまして、これを結構たっぷりとアリバカカオに練り込んだチョコレートです。こちらはなめらか系です」
●では、いただきます。
「どうぞ」
●んん! 口溶けが滑らかですね! バニラの甘い香りが美味しいです! 「アマゾンアリバ」と全然違いますね!
「そうですね。同じカカオを使っても結構表現は変わりますね」
●バニラの甘みが濃厚で美味しいです!
「かなりたっぷり練り込んでいます。これは10年くらい前に無農薬栽培をスタートした現地の固有種のバニラですね」
●最後が「70%野生クリオロ」、クリオロっていう名前はあまり聞かないんですけれども、このクリオロってなんですか?

「クリオロっていう品種がカカオの中にありまして、それこそアリバカカオよりもさらに希少性が高いと言われている品種ですね。エクアドルのアマゾン地域、カカオの発祥の地でもあるので、いろんな野生のカカオがあります」
●へぇ〜! 色は先ほどの2種類と比べると、ちょっと明るい茶色っていう感じですね。
「そうですね。これは、カカオのタネの中身がもともと白いタネで、それを使っているのですごく珍しいんです。なので、ダークチョコレートでも色がミルクチョコレートみたいなチョコレートになります」
●では、いただきます・・・んん!? 美味しい・・・えっ、これなんの香りだ・・・? なんか紅茶のような!
「あ、そうです! 和紅茶っぽい感じ、ストレートティーを飲んでいるような感じ」
●ええ〜っ! チョコレートなのに和紅茶というか!
「香りますね、和紅茶の感じ」
●美味しいですね、これも!
(編集部注:「ママノチョコレート」では板チョコのほかに、生チョコ、ひと口サイズのチョコドロップスなど、いろんなチョコを販売、ぜひオフィシャルサイトでお確かめください。
https://mamano-chocolate.com)

国際協力NPO「ママノアマゾニア」
※江澤さんは去年、国際協力NPO「ママノアマゾニア」を立ち上げました。これはどんな目的で設立したNPOなんですか?
「これは、活動地域は同じエクアドルのアマゾン地域なんですけれども、熱帯雨林の保全と、先住民キチュア族のチャクラ農法を広めていく、そのキチュア族の農法を実践している農家を支援していくのが主な目的です。
ママノチョコレートでずっとやってきたことと近いんですけれども、こっちのNPOに関しては、短期的に収益が出なくても長期的に支援していきたいこと、そして公益性が高いこと、たとえば植樹の活動とか、そういうことをやっていこうということで立ち上げました」
●なるほど。具体的に現地でどんな活動されているんですか?
「具体的には・・・まだNPOの正式登記がそれこそ今月なんですけど・・・活動内容としては、最初は国土緑化推進機構と協力をして、まず野生クリオロカカオの保全活動をやります。この地域がだいたい1400ヘクタールくらいのジャングルなんです。その中に野生カカオの木が何百本かあるので、そのタネを集めて苗木を3000本ぐらい育てたあとに、野生カカオの苗木をジャングルに植え戻すっていうのをやっていく予定です」

●現地にはメンバーがたくさんいらっしゃるんですか?
「オフィシャル社員みたいなのはひとりもいないんですけれども、現地の先住民組合のメンバーとか、ママノチョコレートと共通なんですけれども、現地のメンバーがNPOでも理事を兼ねていて、そのメンバーでやってもらっていますね」
●植樹してカカオ豆を収穫できるようになるまでには、だいたいどれぐらいの時間がかかるんですか?
「これは野生カカオと、栽培しているアリバカカオでは期間が違うんですけど、アリバカカオは3年くらいで収穫開始できます。野生カカオはまだ実績がないし、正式な品種特定というところもこれからなので、3年で育つのか5年かかるのかわからない状況ですね」
●未知の領域なんですね。
「そうですね」
●でもその間ずっと(カカオの)木の管理というかお手入れはされるわけですよね?
「そうですね。あとはこの野生のクリオロカカオと一緒に育っているいろんな樹木、熱帯雨林の樹木も3000本くらい一緒に植えていくので、それがいわゆるシェードツリーといって、カカオの(木に)影を作ってくれるような役割を果たします。なので、シンプルにカカオを増やしたいということではなくて、しっかりとお金になる、野生のカカオの木も育てながら、もう一回、熱帯雨林を豊かにするっていうのがコンセプトですね」
「チャクラ」は“森のような農園”!
※前半のお話にも出てきた、エクアドルの先住民「キチュア族」の伝統的な「チャクラ農法」とは、具体的にどんな農業なんでしょうか?
「チャクラ農法は、もう少しよく知られている言葉だと、“アグロフォレストリー”。“アグリカルチャー”と“森”、農業と森を合わせた言葉で、“森のような農園”を指す言葉ですね。
現地のキチュアの人たちにとっては、チャクラは自分たちの裏庭みたいな意味で使っているので、“うちのチャクラ、見ていく?”っていう感じで誘われたり、“うちのチャクラはこんな植物が生えているよ!”っていう言い方をしたりするので、“裏庭”って意味もあるし、“森のような農園”っていう意味もあります。
だいたい最低でも20作物くらい、多いところだと100作物くらい育っていて、自分たち家族が食べるものもあるし、ユカとかバナナとかパイナップルとか、あとはお金になるカカオ、グアユサ茶っていうお茶とか、それこそバナナもお金なるものなんですけれども・・・。病気になった時に病院代わりに薬草みたいなものをたくさん使っていますので、いろんな意味がチャクラにあってすごく重要ですね。
現地のキチュアの人たちにとって、もともとは熱帯雨林を摸倣して、模倣しながらでも自分たちに役に立つようにチャクラを組み立てていくんですね。もちろんナタで雑草も刈ったりしますし、農薬とか肥料を基本的に使わないですね。
虫が(作物に)付くこともあるので、そういうのもしっかりケアしていますね。カカオの木に関しては剪定したりとか、そういうことはしますけど、それでもいろんな作物があることで、虫も集中して(ひとつの作物に)食べに行くこともないので、一気にカカオだけやられるとか一気にバナナだけってことがなくなるのも、このチャクラのいいところですね」

●チャクラ農法は、気候変動に対して効果的なシステムとして注目を集めているそうですね。どんなところが効果的なシステムなんですか?
「論文とかも出ているんですけれども、数字でいうと農園の炭素蓄積量が通常のカカオだけを栽培している農園だと80トンくらいです。このチャクラ農園だとバラつきもあるんですけれども、だいたい200トンちょっとなので、2倍から2.5倍くらいの炭素蓄積量があるそうです。
CO2を吸収して、土であったりとか落ち葉であったりとか、木に蓄積していくことができるので、チャクラ農園が広まればトータルの炭素蓄積量が増える、ということで気候変動の観点から注目されていますね」
(編集部注:「チャクラ農法」は「アマゾン・チャクラ・システム」として国際連合食糧農業機関FAOに「世界農業遺産」として認定されているそうですよ。
また「ママノチョコレート」は2023年に世界で初めて「チャクラ認証」の取得企業になっています。このチャクラ認証は、エクアドルの非営利法人「チャクラコーポレーション」が発行する認証だそうです)
エクアドルと日本をつなぐチョコレート
※活動場所の、エクアドルのナポ県というエリアは、どんなところなんですか?
「ナポ県はアマゾン地域で、先住民キチュア族の人たちが人口の半分以上を占めている県、エクアドルでも先住民の人口比率って県によって違うんですけれども、このナポ県は半分以上が先住民なので、先住民の権利を守る運動もかなり活発ですし、政府に対してどんどん意見も言ってきますね。
それこそ、やっぱり自然を守る価値観が、彼らは“宇宙観”、それを言うんですけど、そういう宇宙観を持っているので、すごく自然を大事にしているし、コミュニティを大事にしているっていうイメージがありますね」
●気候的には、どんな感じなんですか?
「気候的には30度超えるくらいで、基本的には常に暑くて、もちろん雨期には大雨が降ったり止んだりして、寝るときには20度まで下がるので、エアコンもいらず、とにかく気持ち良い気候ですね」
●現地に滞在される時って、どうされているんですか? 寝泊りとか?
「寝泊りとかは、ちょっとロマンがなくて申し訳ないんですけど、ロッジに(笑)」
●そうなんですね(笑)
「普通に泊まっているので割と快適で! 先住民って言葉だとイメージが・・・いろんな先住民がいるので、普通に町は町であるので、きれいなロッジ泊まっています」
●治安はいいんですか?
「全然いいですね!」
●食事はどんな感じなんですか?
「食事は・・・まあそうですね・・・“セビーチェ”ってエクアドルだと有名、ちょっと酸っぱい食事なんですが、それも美味しい、基本的にさっぱりすっきりしたものが多いですね。珍しいものだと、“チョンタクロ”っていうコガネムシの幼虫みたいなものを、チャクラの農園で倒した木の中で育てて食すっていう文化はあるので、それは食べさせてもらいますね」
●美味しいんですか?
「美味しいです。美味しいと思います・・・(笑)。日本でも蜂の子とか食べますよね。似たような感じかなと思いますね」
●最後に、ママノチョコレートを通して、どのようなことを伝えていきたいですか?
「エクアドルのアマゾンと、日本に住んでいるお客さんをつないでいくっていうのが、やりたいこととしてはすごくあるんですよね。もちろんカカオのいい品質のもので美味しいチョコレートを作るのが大前提の上ですけれども。
アマゾンの価値観とか生活を日本のみなさんにも見てみてもらいたいですし、逆にオンラインでつなぐことで、日本のチョコレートのお客さんがどういうふうにその豆を評価しているのか、どういうチョコレートを作って喜んでくれているのかを、現地のみんなにも知って欲しいので、つなぐことをどんどんやっていきたいなと思っていますね。
あとは現地の友人というか、彼はキチュア族ではなくてシュアール族なんですけど、ファン・カルロス・ヒンティアチュさんていうかたがいて、2023年のノーベル平和賞の候補にもノミネートされていました。やっぱり先住民の権利の運動とか自然保護がすごく密接に結びついているっていうことでノミネートされていたんですけど、彼の言葉で感銘を受けたのが『人は川であり森である』っていう言葉です。仏教の考え方と通じる部分はすごくあるなと思っています。
自分自身も自然と一体になっているというか、自然に生かされているなっていうのはすごく感じるんですけれども、それを説得力を持った言葉で言える、自信を持って言えるっていうのは・・・自分はこの言葉をまだ自信を持って言えないなぁと思っていますね。
“自然に感謝しています”というようなことは言えるんですけれども、自分自身が“川であり森である”みたいなことまではやっぱり言えない・・・けど、それを素直な表現で言えるってところにやっぱり、接していて日々感動がありますね」
INFORMATION
「ママノチョコレート」では、エクアドルのカカオ農園と日本をオンラインでつないで、月一回程度、どなたでも無料で参加できるセミナーを開催。次回は2月22日(土)の午前7時30分からの予定。興味のあるかた、ぜひオンライン・セミナーにご参加ください。
きょうご紹介したチョコレートなど、販売しているラインナップについてはぜひママノチョコレートのオフィシャルサイトをご覧ください。もちろん、オンラインで購入できますよ。

赤坂見附のお店にもぜひお出かけください。赤坂見附駅から徒歩2分です。アクセス方法などもオフィシャルサイトを見てくださいね。
◎ママノチョコレート:https://mamano-chocolate.com
ママノチョコレートの活動は各種SNSで見ることができます。
◎Facebook:https://www.facebook.com/mamanochocolate
◎YouTube:https://www.youtube.com/@mamano_chocolate/about
◎X:https://x.com/mamanoofficial
◎Instagram: https://www.instagram.com/mamano_official/
◎Note: https://note.mu/mamanochocolate
国際協力NPO「ママノアマゾニア」の活動にもご注目ください。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
◎ママノアマゾニア:https://mamano-amazonia.org/
2025/2/2 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、旅行作家の「石田ゆうすけ」さんです。
石田さんは自転車で7年半、一度も帰国せずに世界一周の旅を行なった自転車旅のスペシャリストで、現在は物書きとして、定期的に自転車の旅に出て、その紀行文を雑誌などに書かれています。
そんな石田さんが先頃『世界の果てまで行って喰う〜地球三周の自転車旅』という本を出されました。きょうは、世界の旅で出会った激うま絶品メシの中から、思い出深い麺類や、素朴で美味しいパンのお話などうかがいます。
☆写真:石田ゆうすけ

世界一周9万5千キロ! 87か国!
※石田さんには20年ほど前、世界一周の旅を綴った本『行かずに死ねるか』を出されたときに、この番組に出ていただき、それ以来、定期的にご出演いただいていますが、まずは基本的なお話から・・・。
●およそ7年半かけて、一度も帰国することなく、自転車で世界を一周されたということですが、なんでまた、自転車で世界を旅しようと思ったんですか?
「僕の実家が和歌山の白浜ってところで、けっこう旅行者が多くて子供の頃から自転車旅行者を見ていたんですね。自転車にでっかい荷物を積んで、かっこいいな~と思って・・・。15歳の時に和歌山県一周やって、それが面白くて次に近畿一周、大学に入って日本一周やって、次は世界一周っていう簡単な・・・(笑)」
●簡単じゃないです~(笑)
「単純な動機です。もっと広い世界を、って感じです」
●でも7年半、ずーっと海外ってすごいですよね?
「(旅を)やっているともう生活になりますからね。なんということはない、冒険でもなんでもなく、ただ自転車を漕いでいるだけです」
●いや〜すごいです! 親御さんの反対はなかったんですか?
「最初は、反対されるのは見えていたんで、(世界一周の旅には)黙って行こうと思ったんです。親子の縁を切ってでも行こうと思って(笑)。ただ、友達から“それはよくないよ”って説得されて・・・。
その頃、僕はサラリーマンで広島に住んでいたんですけれども、長い手紙を書いて、それを読んだら反対できないような、なんでこういうことをするのかとか、この夢にどれだけかけているかとか。あとその後の人生、そういったことも理路整然と手紙でまず伝えて・・・それから(実家に)帰って、もう帰った頃にはそれを読んでもらっていたんで理解してくれていたと・・・」
●(旅の)期間っていうのは初めから決まっていたんですか?
「一応、予算の関係もあるので3年半、最初にどういうルートで(世界を)まわるかを出して距離を測って、3年半で走れるやろうと思ったんですけれども、そんなことはなかったという(苦笑)」
●結果的に7年半ということで、4年延びたのはどうしてなんですか?
「そうですね・・・ゆっくり(期間が)延びていった感じですね。出発から2週間ぐらいで、ユーコン川っていうカナダの川があるんですけども、そこに行って、川のほとりにテントを張っていたら、“うわっ!ここをカヌーで下りたいな!”と思って・・・。
時間とかなかったけど、いいやと思って、カヌー下りを2週間かけてやったのかな。そのあたりからどんどんずれ込んでいって、景色の綺麗なところで、ずっとそこに居続けて見続けていたり、そんなこんなで結局、蓋を開けば7年半・・・」
●興味のあるところには積極的に立ち寄ってとか、そんな感じだったんですか?
「そうですね~。自分で人生の一定期間、自由を与えたわけで、予定に縛られるのはちゃうな!と。今この感動を大切にしたいと思っているうちにどんどん延びていきましたね」
●そうだったんですね~。
「あと行きたいところもどんどん増えていくんですよ。いろんな人と知り合って“あそこがいいよ!ここがいいよ!”って。そういうのを聞いているうちにどんどん距離も延び、時間も長くなったということですね」

(編集部注:当初3年半の予定だった旅、その資金はサラリーマン時代に食費などを切り詰めて貯め、旅の途中からは雑誌に記事を書くようになり、その原稿料を足しにしながら、旅を続けたそうです。
世界一周のルートは、まずアラスカに渡り、そこから北米・南米大陸を縦断。そしてヨーロッパを一周し、アフリカ大陸へ。続いてユーラシア大陸を横断し、中国から韓国、そして日本に渡り、下関から、ふるさとの和歌山県・白浜でゴールを迎え、7年半の旅を終えたとのこと。
走った距離はおよそ9万5千キロ、巡った国は87か国! 自転車には衣食住のための荷物が満載、その重さは自転車を含め、なんと75キロ! これも慣れれば、なんてことない、とおっしゃっていました。
言葉は、英語が通じないエリアも多くあるので、現地語の辞書を買い求め、挨拶の言葉や「美味しい」などの単語を手に書いて、ペダルを漕ぎながら暗記していたそうです。
そんな石田さんの新しい本のタイトルが『世界の果てまで行って喰う〜地球三周の自転車旅』なんですが、毎日ペダルを漕ぐ、体力勝負の自転車旅は「食」が特に大事になってくると思います。
実は、食べることが大好きな石田さんは、グルメライターの顔もあり、台湾に「食」の取材で行った時に、自転車旅が「走るために食べる」から「食べるために走る」に一変! 食べることがいちばんの目的になっていったそうです)
日本の水に「助かった!?」
※今回の本は世界で出会った食がテーマになり、タイトルが『世界の果てまで行って喰う』になったようです。
それでは、本に掲載されている31編の旅行記から、いくつかお話をうかがっていきましょう。本では「水」「お米」「麺」「肉」などにジャンル分けされています
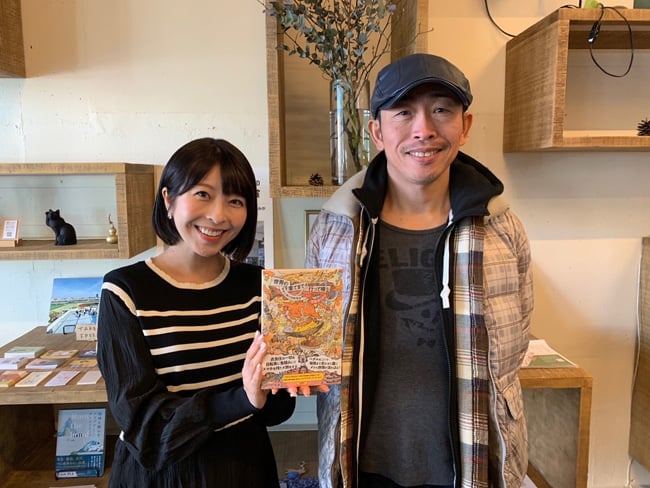
●まずは、水にまつわるお話から。やっぱりこれがないと旅は続けられないですよね?
「そうですね~。僕が日本に帰ってきて、いちばん日本って素敵だな~と思ったのが水なんですよね。すべての町の背後に緑豊かな山があって、走っていると水場があちこちにあるんですよ。岩場からパイプを通して水が流れていて、ヒシャクがあってカップがあって、ご自由にどうぞ!って感じで、天然水があちこちで汲まれていて、その水がどこで飲んでも美味しくて!
世界はけっこう硬水が多いんですよ。硬いんですよ、水が。ところが(日本では)あちこちで軟水の柔らかくて甘い水が滴り落ちていて、そのことがとにかく輝いて見えて、最初にそれを見て飲んだ時に、体の奥から“助かった!”って声が聞こえたんですよ。
っていうのは、僕の体感ですけど、世界をまわって7割ぐらいは乾いた土地だったですよね。砂漠も多くて、いつも町に着いたら、次の水場まで何キロだって聞くことが習慣になっていて、水をどれだけ積むかって・・・。本当に命にかかってきますので・・・当時情報もなかったですから、常にそのことに気を張っていた。
日本に帰ってきたら、あちこちに美味しい水が流れていて、潤っている大地を見ながら、“助かった!”って思った時に、よっぽど渇きに対する恐怖が自分の中に蓄積されていったんだなって、改めて思ったことがあったので、この旅の本では、まず水っていう大きなテーマを取り上げたんです」
●本を読んでいて喉が乾きました!(笑) 荒野を走っているシーンとかで、(喉が)カラカラになりました! 走る地域とか距離とかにもよりますけど、何リットルぐらいのお水を積むんでしょうか?

「いちばん乾いていたところで20リットルぐらいですね」
●生水は飲めないんですよね?
「いや、基本、現地の人と同じことをやっていたんですよ。現地の人が飲んでなかったら飲まないし、飲んでいたら生水を飲む。もう慣れていくので、体が・・・」
●南米大陸の最果てパタゴニア、ここは荒涼とした大地が広がっているイメージありますけれども、水がとても豊富なエリアがあるんですね?
「そうですね。南のほうに行くと森林地帯があって、大体そういうところでは、氷河から流れている水があるんですね。氷の水って柔らかい軟水なので、パタゴニアの水はうまかったですね」
●「甘い水の桃源郷」と表現されていましたけど、それくらい素敵な場所だったんですか?
「そうですね~。僕の体験だけの話なので、ほかに(水が)うまいところがあるかもしれませんけど、僕の中ではパタゴニアが、水がうまかったところではいちばん甘い!と思いましたね」
●なぜ甘いんですか?
「ずっと硬水を飲んできていたから、氷河の水を飲んで、久しぶりの軟水だったせいで柔らかい、その舌ざわりが甘く感じるっていうところがあると思います」

いちばんはモロッコのパン!
●続いて石田さんの好きなパンの話題に入りたいと思うんですが、パンの消費量が世界一の国ってトルコなんですね?
「らしいですよね~」
●意外だったんですけど・・・。
「そう、僕もあとで調べてわかったことなんですけど・・・振り返るとトルコ(の人)はほんとパンを食べています!」
●パン屋さんが多いってことですか?
「各町にありますね~、焼きたてパンを売っている(パン屋さん)」
●どんなパンが定番なんですか?
「定番はフランスパン、バゲットをちょっとずんぐりむっくりにしたような形のパンですね」
●お味は?
「うまいっすよ! 本当に! やっぱり、まあまあバゲットの味に近いかな? でもバゲットよりもずんぐりむっくりしているので、もっとふわっとしていて、小麦の味がブオンとくるというか・・・」
●いろんなパン屋さんがあるんですね?
「各町にあって、夕方に着くと、けっこう夕方のイメージがあるんですけど、パンの香りが町中から漂ってくるみたいな感じで、腹が減っていましたね」
●石田さんの中でいちばんのパンが、モロッコのバゲットだったということですけど、それはどんなパンだったですか?
「やっぱり(モロッコは)フランス統治だったので、フランスの食文化が流れているおかげで、地元アラブの丸いパンもあるんですけれども、バゲットが主流だったイメージがありますね。
フランスのバゲットより、もっと細長いパンで・・・僕が美味しいと思ったのは、田舎の手作りで焼かれているようなパンを、おっさんが自転車の前カゴに突き刺して売りに来ていて、湯気が立っているんですよ。
それをもらってかぶりつくと甘いんですよ、ものすごく! なんか似ているなと思って、バターとハチミツをつけて食べたら、これやっぱりホットケーキだ! バゲットなんだけど、パリッと皮のはじける快感と香ばしさもありながら、ホットケーキのようなしっとりした柔らかさと甘さもある、それが砂糖の甘さじゃなくて、小麦粉の甘さ。
このネタというか本の記事が最近ネットに出たんですよ、Yahooのニュース。僕正直この話を書くのをビビってたんですよね。っていうのは、モロッコのパンが美味しいっていう話ってあんまり聞かなくて・・・。僕の記憶の中では圧倒的に1位だったんですけど、これを書いて“ヤフコメ”でまたさんざん叩かれるんだろうなとか思っていたら、これが出たよと思って、その“ヤフコメ”を見たら、けっこういたんですよ、(パンが美味しいのは)“モロッコ”っていう人がけっこういて・・・やっぱりそうなんだと、すごくほっとしましたね」
涙ぼろぼろ、ウズベキスタンのうどん!
●では麺にいってみましょう。やはり麺といえば中国ですよね?
「そうですよね~」
●地域ごとにいろんな種類の麺があるようですけれども、どこで食べたどんな麺が印象に残っていますか?
「ほんとに美味しいのは中国の、特に僕が好きなのは、ウイグル自治区の“ラグ麺”っていう、うどんにトマトとか羊の肉を炒めたものをぶっかけたような料理なんですけど、味で言えば、それなんですね。

思い出に残っているという麺で言えば、ウズベキスタンで食べた、これは“ラグマン”っていう、おそらくつながりはあるんですけど、料理は全然違っていて、それもうどんなんですけど、汁にすごく浸かったうどんで、そういうのを食べているってまったく知らずに、イランからウズベキスタンに入って(現地の)食堂に入ったら、それをみんな食べていてびっくりしたんですよ。
っていうのも、さっき申し上げたルート上で、初めてそこで汁の麺に出会うんですよ。そこまで6年かかっているんですよ! すごく興奮して“これ、くれ!”って言って指差して・・・食べたら、ほんとうどんなんですよ、麺は。味はトマト味のちょっとシチューみたいな汁に浸かっていて、それをずるずるって吸い上げる感覚とか、うどんの小麦粉の香りとか、噛む食感とか、そういうのが体に入った瞬間に体の奥から帰ってきた!と思ったんですね。
その途端にバーって自分の背後に6年分の道のりが見えた気がしたんですね。それまで各大陸にゴールがあって、たとえばアフリカだったら喜望峰という南の端っこがゴール、そこまで向かって(自転車を)漕ぐわけなんですけど、そこに着いて喜望峰のモニュメントを見たところで感動しないんですよ。見るだけじゃ入ってこないっていうか、視覚って脆弱なんだなと・・・。
ただ、うどん“ラグマン“を食べた時に体中で味覚、触覚、嗅覚全部で、体全体で味わった時に、初めてこの旅が長かったなと思ったんです。6年分が見えた気がして、やっと帰ってきた!って心の叫びが聞こえて、その時に生きて帰ってきた!っていうことを初めて実感できて、ぼろぼろ涙が出てきたんですよ。
それまでほんとに旅は一瞬一瞬があるだけ、その時の一瞬一瞬があるだけなんですよ。生きている時に自分の人生を振り返って、長かったなって思わないじゃないですか、今の一瞬一瞬があるだけで・・・。旅も一緒で6年旅していても長いなんて感じないんですよ、その日その日があるだけで・・・。
ただ(ラグマンを)食べた瞬間に6年の道のりが見えた時に、長いこと旅してきたな〜、よくぞ生きて帰ってきたなって思えて、ぼろぼろ泣きながら食べて、その味が忘れられないってのはありますね」
(編集部注:石田さんの本には、もちろん「肉料理」のお話も載っています。石田さん的にいちばん印象に残っているのが、アルゼンチンの国民食ともいえる「アサード」だそうです。これは牛肉の赤身をBBQで食べるものなんですが、アルゼンチンのかたは、毎週末に必ずといっていいほど「アサード」を楽しむそうですよ)
料理は現地で食べてこそ!
※いろんな食のお話をうかがってきましたが・・・その土地の食べ物は、その場の気候や風土と密接につながっていますよね?
「今回の本って“地球三周の旅”って副題がついている通り、三周分まわっているんですけれども、僕が世界一周7年半の旅でまわったのは二周半分なんですよ。残りの地球半周分はそのあとの旅なので、今こういう仕事をしていますから、その世界一周の時に走れなかった国を攻めて、自転車で走っているんですね。

その中にミャンマーという国があって、そこで食べた“モヒンガ”っていう麺料理が本当に美味しくて! これを持って帰って日本で本気でやれば、第二のタピオカになるんちゃうか?(と思って)けっこう本気で考えたりしたんですよ。
で、帰国して、それから今そんなことしなくても、高田馬場に“リトルヤンゴン”って言われているような、ミャンマー人街があるんですね。ミャンマー料理がたくさんあるので、レストランに食べに行ったんですよ、その“モヒンガ”を。そしたらなんか違和感が・・・。
こっちに住んでいる、ミャンマー人用に作られているレストランなので、完全に本当の味なんですけれども、その味を日本で食べたら・・・“モヒンガ”ってナマズを出汁にしているんですね。旨味がすごく強いんですけど、魚のにおいもけっこう強くて・・・だから日本で食べると(においが)強いんですよ。あんなにミャンマーで食べて美味しかったものが、日本だとこれは流行らないな~って正直思ったんです」
●やっぱり(モヒンガは)ミャンマーで食べるから美味しかったってことですか?
「そう、そういうことは旅しているとよく感じるんですけど・・・特にお酒。お酒も現地で飲んで美味しいと思って、帰ってきてこっちで飲んだら、あれ? っていうのはよくあるんです。その時に思ったのは、やっぱり料理って現地の食材を使って水を使って、現地の環境、空気のにおいとか、そこで食べて最上になるように作られている、当然のことながら。
なので、そこで食べてこそ本来のうまさを味わえる。それをそのまま持ってきて東京で食べたところでやっぱり違う、違和感が先に来るから。やっぱり食文化ってそういうことなんだなって。そこで食べるからこそ地域独特の味ができあがるし、そこで食べるのが最上なんだなって感じましたね」
サラダと白ワイン〜幸せの感度
※世界を7年半もかけて巡ったあと、日本に帰ってきてからの、いちばんのご馳走はなんでしたか?
「本の最後にも書いているんですけれども、サラダなんですよ」
●生野菜!
「生野菜! それは7年半、世界をまわって最初申し上げた通り、7割ぐらい乾いた土地だったので、生野菜を食べる地域もそんなにないんですよね。そういうところをずーっと走ってきて、日本に帰って幸せだと思ったのは、水だったってことは最初申し上げましたけど、やっぱり食べることで言えば、フレッシュな生野菜とワインを一緒に口に入れる、生野菜のシャリシャリした感覚、舌触りとかみずみずしさとか、それを白ワインでマリアージュしながら広がっていくうまさとか、それが本当に今幸せで・・・。
この感覚って、南極越冬隊の人たちにとって、いちばんのご馳走は何かって、千切りキャベツらしいんですよ。みんな言うらしいんですね。それはやっぱり生野菜に飢えているから。キャベツがいちばん日持ちするから、半年に1回(食料の)補給があるらしいんですけれども、最後まで生野菜を食べられるのはキャベツらしいんですね。
それが(食堂に)出るのがみんな楽しみらしくて、隊員たちはそういう話を書いているんですね。僕の友人で世界をやっぱり自転車でまわった友人、そういうことする人はいっぱいいますから、何人もいるんですけども、彼が同じことを言っていたんですよ。やっぱり“生野菜が自分にとっていちばんのご馳走だ”って言っていて、やっぱりそうなるよねって、盛り上がりましたね」
●日本にいると当たり前に生野菜を食べちゃっていますね。やっぱり世界に行くことで、日本の良さっていうのも気づきますよね。
「改めて感じるっていうことと、あとこの本で何が言いたかったかっていうと、世界各地の料理にこんなことがあるよ! こんな料理があるよ! っていうことを冒険活劇を読むように楽しんでもらいたいっていうことが、ひとつあるんですけれども、もうひとつ、ものすごく大げさに言えば、人にとって幸せって何やろ? っていうところを自分なりに追求した本だと思っていて・・・。
それはやっぱり自転車に乗っているとめちゃくちゃ腹が減るんですよ! もう食べることしか考えられなくなる、獣のように食べるんですね。
でもガツガツ食らっている時のその恍惚に、さらに現地でのいろんな人との出会い、そういうスパイスがあって、食べることの幸せっていうのが、もうこれ以上のものはないなっていうことをずっと体験してきて・・・。
僕がこの旅をしたことで何を得た・・・得たって変なんですけど、何か変わったなっていうことがあるとすれば、幸せに対する感度が高くなった。つまりちょっとしたことで幸せになれるだと思える。当たり前に食べていたものでも、サラダひとつとっても、それまで感じなかった歯触りだったり、食物繊維がほどけていく感覚とかに意識が向くんですよ。それは食べられなかったから、海外で当たり前に食べられなかったから、そういったことで幸せに感じる。
だから僕は今すごく小さなことでも幸せだなって思える。それはなぜかと言えば、こういう旅をしてきたから。(旅を)やったからこそ、今まわりにたくさんある幸せに気づけたっていうのは、すごく大きいなと思っていて・・・そういったことを食というものを通して、読んだ人が読んだ後に見える世界が変わっていたらいいなって・・・おそらく幸せっていっぱい転がっていて、それに気づけるかどうかが大事なんじゃないかなと思うんですね」

☆この他の石田ゆうすけさんのトークもご覧ください。
INFORMATION
石田さんの新しい本をぜひ読んでください。食にまつわる31編の旅のエッセイは、どれも絶品! その場の風景や人、気温や湿度、さらには、においまでも感じる描写に圧倒されます。きっとそのページで紹介されている食を食べたくなると思いますよ。新潮社から絶賛発売中! 詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎新潮社:https://www.shinchosha.co.jp/book/355751/
オフィシャルブログ「石田ゆうすけのエッセイ蔵」もぜひ見てください。
◎石田ゆうすけのエッセイ蔵:https://yusukeishida.jugem.jp
2025/1/26 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、認定NPO法人「JUON NETWORK(樹恩ネットワーク)」の事務局長「鹿住貴之(かすみ・たかゆき)」さんです。
JUON NETWORKは都市と農山村をつなぎ、地域と自然を元気にする活動を行なっています。大学生協を母体に設立されたJUON NETWORKがなぜ、都市と農山村をつなぐ活動を始めるに至ったのか、その背景には、大学生協が過疎化の進む地域の廃校、小学校をセミナーハウスとして再生したこと。
そしてもうひとつの大きなきっかけが、1995年1月に発災した阪神・淡路大震災。
被災した大学生たちのために、仮設学生寮を作ることになり、その際、徳島の林業関係者から間伐材で作った組み立て式のミニハウスを提供してもらったこと。ここで農山村とのつながりが生まれます。
1995年の阪神・淡路大震災はボランティア元年とも呼ばれ、多くの大学生も支援に駆けつけましたが、その際、学生の間から、普段からボランティア活動をしたくても「場」や「きっかけ」がない。活動するためのネットワークがあれば、という声があがったそうです。
そこで学生たちの活動の場づくり、そして都市と過疎化が進む農山村をつなぐ活動をしたい、そんな思いから、大学生協の呼びかけで、1998年にJUON NETWORKが設立されたそうです。
設立当初からのメンバーである鹿住さんは、大学生のときに知的障害者の子供たちと遊ぶボランティア・サークルに所属。また、東京で学生ボランティアのネットワーク作りにも参加していたこともあって、JUON NETWORKのスタッフになったそうです。
きょうは、以前にもこの番組にご出演いただいた鹿住さんに、いろいろな活動の中から、おもに間伐材を有効活用する「樹恩割り箸」のほか、「森林(もり)の楽校」や「田畑(はたけ)の楽校」のお話などうかがいます。
☆写真協力:JUON NETWORK

樹恩割り箸〜森作りと仕事作り
※オフィシャルサイトを拝見して活動のひとつとして「樹恩割り箸」というのがありました。これはどんな活動なんですか?
「日本の森林を守るためには、ただ放っておけば守れるっていうことではなくて、手入れが必要だと。その手入れのひとつが間伐、“間(あいだ)を伐採する”で、間伐ですね。その “間伐材”とか、あるいは“国産材”が使われることで山側にお金が入るので、森の手入れが進むっていうことになる。日本で森林を守るっていうことは放っておくことじゃなくて、国産材とか間伐材を使うということが、すごく大切なんですね。
日本の森林を守るために、間伐材や国産材を原材料として使うっていうことと、もうひとつ大きな特徴としては、障害者の仕事作り。いま全国4つの障害者施設、障害者と言っても知的障害の人たちが多い施設なんですけれども、その障害者施設で割り箸を作って、大学の食堂で中心的に使ってもらっています。ほかにも一般のスーパーだったり飲食店でも使っていただいたりしています。
なぜ私たちが割り箸作りに取り組んでいるかというと、日本の森林を守るために国産材・間伐材を使うことの中で、JUON NETWORKがもともと大学生協とつながりがあったということ。学生に間伐材とか国産材を使ってもらうには、大学生協が経営している大学の食堂で割り箸として使ってもらえばいいということから、1998年の設立の時にスタートして、26年ぐらいやっています。そういった取り組みですね」

●大学の食堂などで使われているということでしたけれども、一般のかたでも購入はできるんですか?
「はい、そうですね。私どものウエブサイトから購入していただくことができます」
●樹恩割り箸は、年間ではどれぐらい売れていますか?
「大体1000万膳っていう(笑)ちょっとあまりピンとこないと思うんですけれども、1000万膳という量を製造しています。日本で割り箸が1年間にどれぐらい使われているかってわかりますか?」
●え~〜!? どれくらいだろう・・・(笑)
「考えたこともないと思いますけど・・・(笑)」
●でもかなりの量ですよね?
「はい、190億膳と言われています」
●うわっ!
「これでもあまりピンと来ないと思うんですけれども、日本の人口がたとえば1億2000万とか3000万人ですけど、1億人って考えると、ひとり(年間)190膳ぐらい使っているということなんですね。
木材の自給率はずっと20パーセントぐらいだったけれども、最近ちょっと上がってきていて、40パーセントを超えたんですね。それでも木材の自給率は少ないですけどね。こんなに森があるにも関わらず、外国の木を6割使っているっていうことですから。で、割り箸の自給率は、実は2パーセントしかないんですね。
ですから、ほとんど海外から入ってきているんです。その国産の割り箸のうちの大体2パーセントぐらいが、JUON NETWORKの割り箸っていう感じです」

(編集部注:樹恩割り箸は現在、福島の南会津、埼玉の熊谷、東京の日の出町、そして徳島の4つの知的障害者の施設で製造。材料はもちろんその地域から出た間伐材です。こうすることで、障害者のかたの仕事作りのほかに、森作りにも役立っているということなんですね)
森林の楽校〜森の手入れ
※ほかにも「森林(もり)の楽校」そして「田畑(はたけ)の楽校」という活動があります。まずは「森林の楽校」、これはどんな活動になりますか?
「森というのは手入れが必要です。森林ボランティア活動っていうと、木を植えることを多くの人がイメージすると思うんですね。木を植えることも大切なんですけども、むしろその後の手入れのほうが大切なんです。
例えば、木を植えます。日本では春に植えることが多いんですけれども、春に植えると、夏になると周りの雑草がたくさん生えてきます。木は大きくなるけど、成長はゆっくり、草は大きくならないですけれども、成長が早いということで、植樹した木を、夏になると周りの雑草が覆い隠しちゃうので、日の光が当たらなくなってしまい、木の成長が阻害されてしまうわけですね。そこで周りの雑草を刈ってあげる、下草刈りとか下刈り、光が木に当たるようにする作業、これが手入れのひとつですね。

植えてから7年ぐらいは、木が草よりも大きくなるまで下草刈り、下刈りやるんですけども、成長してきて10年ぐらい経ってくると、外から山のほうを見ると緑がたくさんで、日本はいいな~って思うかもしれないんですけども、枝が伸びてきますので森の中が真っ暗、木に光が当たらない状態になってしまうんですね。
そうすると森の役割が発揮できなくなってしまいます。例えば緑のダム機能、水を溜め込んでいつまでも川に水を流してくれるような、そういう機能とか、二酸化炭素を吸収する機能が発揮しにくくなるので、間伐して木を間引く、森の下まで光を当ててあげる作業ですね。そういう手入れをボランティア活動として取り組んでもらうのが“森林の楽校”です。
こういう活動に、JUON NETWORKの特徴でもあるんですけども、単発でもいいから参加してくださいっていう、イベント的なボランティア体験、森林ボランティア活動の入門的な活動が“森林の学校”になります」
●日本全国で開催されているんですか?
「そうですね。北は秋田の白神山地から、南は九州の長崎とか佐賀、全国18か所で開催しています」
田畑の楽校〜援農ボランティア
※続いて「田畑(はたけ)の楽校」について。これはどんな活動ですか?
「これは過疎高齢化で大変な農家さんをお手伝いしようということで行なっている活動、農家を応援する支援する援農ボランティア活動です。この援農ボランティア活動もやはり入門的な活動になります」

●現在、何か所の農家さんを支援されているんですか?
「いま全国4か所でやっています。いちばん古くからやっているのが山梨のブドウ農家のお手伝い、次に始まったのが和歌山県の那智勝浦の棚田、お米棚田のお手伝いで、次に三重県のミカン農家のお手伝い、それと長野県のリンゴ農家のお手伝いという、その4か所で開催しています」
●ブドウ作りのお手伝いとかって、普段できないですよね? 参加者の中から農家さんに転身されたみたいなかたもいらっしゃるんじゃないですか?
「そうなんですよね。農山村地域と都市を結ぶ活動は、私たちは交流人口って言って、 農山村地域に行く人を増やすような活動が基本です。その体験的な入り口を作っているのがJUON NETWORKの特徴なんですね。
山梨のブドウ農家のお手伝いで、交流人口から農山村地域に移り住む定住人口、実際にブドウ農家になったかたが4家族いるっていうことで、JUON NETWORKの活動の中では、いちばん移住した人が多い活動ですね」

●この「森林の楽校」や「田畑の楽校」に参加したいと思ったら、どのようにしたらいいんでしょうか?
「JUON NETWORKのウエブサイトを検索していただいて、そこから申し込みができます。もちろん電話でも申し込めます」
●会員じゃなくても体験だけの参加もできますよね?
「そうですね。基本、私たちは会員ではない人にも参加していただきたいということで、会員にならなくても参加できますし、むしろ会員でないかたの参加のほうが多いです。ただその中から会員になると、会員割引っていうのもあるので、会員になっていただくっていうことも多いですね」
環境教育のリーダーを育てる
※オフィシャルサイトに「森林ボランティア講座」の情報が載っていました。これは具体的にはどんな講座なんですか?
「ちょっと前までは“森林ボランティア青年リーダー養成講座”っていう名前だったんですけども、“里山・森林ボランティア入門講座”っていう名前に変えたんですね。
これは、大学生協が呼び掛けた組織っていうこともありますので、若い森林ボランティアのリーダーを育てようっていうことでスタートしています。大学生や高校生が参加する場合もあるんですけども、基本は大学生から40歳代、50歳未満のかたを対象としています。森林ボランティア活動の技術を身につけていただいて、将来的には活動のリーダーになっていただくことを期待しているっていう、そういう5回連続講座ですね。日にちは離れていますけれども、5回の講座がひとつになっています」
●JUON NETWORKでは「エコサーバー検定」という資格制度も実施されています。これはどんな資格なんですか?
「環境教育のリーダーを育てようということで、森林ボランティア活動も最近は取り入れているんですけども、小学生とか中学生とか、そういう子どもたちに向けたような環境教育を学んでもらう資格制度です。
アメリカに“プロジェクト・ラーニング・ツリー”、木に学べっていう、木から世界を学ぶっていうような感じで、ほかにも環境教育のプログラムがあるんですね。そういうものを(リーダーとして)実施できるように学ぶっていうことと、あと野外での作業の技術を学ぶという、リーダーの養成を目指して実施しているものです。今年度は2月からスタートし、2月に1回3日間の講座やるんですけども、(今回で)20回目ということになります。
JUON NETWORKのエコサーバーっていう資格が取れるだけではなくて、それが取れると、日本共通の指導者資格、『自然体験活動推進協議会CONE(コーン)』が進めている、『ネイチャー・エクスペリメンス・アクティビティ・リーダー NEAL(ニール))』っていう自然体験活動リーダーっていう資格があって、そういうものも取ることができます
(編集部注:鹿住さんいわく、日本ではボーイスカウトやカブスカウト、YMCAやキャンプの協会、ネイチャーゲームの協会など、それぞれの団体が自然体験の指導者を養成する活動を行なっていますが、その共通の資格になるのがNEALだそうです。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください)
◎自然体験活動推進協議会:
https://cone.jp
◎NEAL:
https://neal.gr.jp
ボランティア活動、意識の変化
※いまやSDGsという言葉がメディアで盛んに取り上げられて、その意味や目的などが一般的になってきたと思います。鹿住さんはJUON NETWORKで26〜7年、活動されてきて、いまどんな思いがありますか?
「(設立された1998年)当時は本当に間伐っていう言葉も一般的じゃなくて・・・実は日本でも木を植えてからやっぱり30年、40年、50年ぐらいは間伐が必要な時期なので・・・その頃に比べたら間伐を知っている人も非常に多くなったと思います。
私たちの“樹恩割り箸”が、間伐を知っていただくために果たした役割もあったかなと思うんですけれども、そういうことがあまり知られてないようなところからやってきていると、だいぶ社会的な理解も進んできたなぁというような思いを強く持っていますね」
●20年くらい前と比べて、「森林の楽校」などに参加されるかたの、意識の変化みたいなものって感じますか?
「そうですね。 特に東日本大震災前後で、参加する人の動機って言うんですか、ちょっと変わってきたような感じも受けているんです。昔から自然に触れたいみたいなことだったり、森のためになんかしたいとか、ボランティアしたいっていうのはあったと思うんですね。東日本大震災以降、能登半島地震もありましたけれども・・・。
やっぱり自然を生活の中に取り入れ入れたいって言うんですかね、自然とのつながりを持つ必要性みたいなものをお感じになって参加するっていうような・・・だから暮らしの中で森を切り離して守るっていうよりは、暮らしの中に森とどうつながるかみたいなことを意識しているかたが多くなっているような印象があります。

で、ボランティア活動を災害のボランティアってことで、自分は子供の時、小さかったからボランティアとして被災地に行けなかったけれども、大人になってボランティア活動をしたいと。で、調べていたら自然に対するボランティアもあるんだってことで参加しましたみたいな・・・ボランティアについても、社会的にも関心が広がってきているかなという気もします」
●鹿住さんご自身はいろんなNPO法人の理事などを兼任されています。その辺りはどんな思いがあるんでしょうか?
「私たちもそうですけれども・・・実はJUON NETWORKの設立と同じ1998年にNPO法っていう法律が施行されたんですね。日本はやっぱり基本的に行政が公共のことをやるっていうような意識がとても強いと思うんですけれども、阪神淡路大震災の時に行政だけではとてもその対応ができなかった。で、市民活動とかボランティア活動が被災地で活躍して、大切だっていうことを認識して、そのきっかけでNPO法っていう法律もできたんですね。
そういう意味では、私たちひとりひとりの市民が社会作りっていうんですかね・・・社会を作っていくことに参加していくことがとても大切だと思っているんですね。行政、企業、市民の(それぞれの)立場で、非営利の市民セクターの、この3つのセクターが協力して社会を作っていくことが大切だと思っていますので、その市民の立場で活動を広げたり、みなさんに社会の活動に参加してもらうことを広く呼び掛けて(ひとりでも多くのかたに)参加してもらいたいなと思って活動をしています」
INFORMATION
「樹恩割り箸」はJUON NETWORKのオフィシャルサイトから購入できますよ。価格は紙袋に封入したもので、100膳550円となっています。
「森林(もり)の楽校」や「田畑(はたけ)の楽校」には会員ではなくても体験として一般のかたも参加できるとのことですから、興味のあるかたは、ぜひサイトをチェックしていただければと思います。
JUON NETWORKでは随時会員を募集中。学生会員で年間2000円、個人会員で4000円。また、寄付も受け付けています。ぜひご支援いただければと思います。いずれも詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
◎JUON NETWORK:https://juon.or.jp/
2025/1/19 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンは、シリーズ「SDGs〜私たちの未来」の第23弾!
「SDGs=持続可能な開発目標」の中から「つくる責任 つかう責任」
そして「住み続けられる まちづくりを」ということで、長野県諏訪市に拠点がある「REBUILDING CENTER JAPAN(リビルディング・センター・ジャパン)」通称「リビセン」のリサイクル事業にフォーカスします。
「リビセン」では、解体される空き家や建物から、古材や古道具を引き取って販売する事業を行なっています。
きょうは「リビセン」の取締役「東野華南子(あずの・かなこ)」さんにリサイクル事業を始めた経緯や事業内容のほか、活動の理念「リビルド・ニュー・カルチャー」に込めた思いなどうかがいます。
☆写真協力:REBUILDING CENTER JAPAN

合言葉は「リビルド・ニュー・カルチャー」
※2016年にオープンした「リビセン」は、一般的なリサイクルショップでは扱わない、例えば、床板や柱、古いタンスなどを扱っているのが特徴です。活動の裏には、捨てられて燃やされてしまうのは「もったいない」、ゴミにせずに再び使う、そんな思いがあるんですね。
創業メンバーは、東野さんご夫妻のほか、全部で5人。現在は総勢18人のスタッフで運営されています。
●もともとは、デザイナーのご主人「東野唯史(あずの・ただふみ)」さんとふたりで「medicala(メヂカラ)」というユニット名を掲げ、全国を転々としながら、空間デザインのお仕事をされていたんですよね?
「はい、そうなんです。もともと夫が空間デザインの仕事をしていて、私は文学部卒業で、建築の文脈だったりとかデザインの文脈を学んできたわけではなかったんですけど、依頼があった土地に夫と一緒に行って、そこに住み込みながら、解体しながらデザインしながら施工して、完成したら次の土地に行くっていう暮らしを2年ぐらいやっていました」

●へぇ〜! で、解体される家屋などの古い材料だったり古道具を引き取って、販売する事業をやっていこうと持ちかけたのは、どちらなんですか?
「2014年に夫とふたりで、その仕事を始めたんですけど、1年ぐらい経ったところで、2015年に(アメリカの)ポートランドに『REBUILDING CENTER』っていうリサイクルショップというか、建築建材がたくさんあるようなお店があるんですけど、そこに行ったんですよね。
そこを見た時に夫が、いま日本にもやっぱり空き家の問題だったりとかゴミの問題だったりがある中で、これが日本にあったら、きっと日本の社会をよくできるじゃないですけど、社会がよくなることに貢献できるんじゃないかって思ったのがきっかけで、それでポートランドのREBUILDING CENTERに連絡をして、やることになったっていうことですね。
ポートランドはもともと、アメリカにはDIYの文化もすごくあって、お家は日本だと30年ぐらい経った建物の価値ってなくなっちゃったりするんですけど、アメリカでは手をかけたら、その分ちゃんと建物の価値が上がっていくっていうような仕組みになっているので、みなさん、自分のお家を楽しみながら直しながら暮らしているかたが多いんですよね。
なので、そういう古材だったりとかドアノブだったりとか洗面台だったりとか、何でもリサイクルする文化というか、買えるようなお店がたくさんあって、そのうちのひとつがREBUILDING CENTERという感じですね」

●「リビセン」の合言葉は「リビルド・ニュー・カルチャー」ということですけども、これらにはどんな思いが込められているんでしょうか。
「私たちが本当にずっと気に入って使っている言葉ではあるんですけど、この中に古材とか古道具っていう言葉が入っていないのがすごくポイントなんです。
もともと日本にあった文化というか、物を直して使うっていうこともそうですし、物を簡単に捨てるんじゃなくて、それを次に何かに活かせないかって考える。そういうふうにもともとあったものをもう一回呼び起こすっていうのもあります。
自分の手で何かを作っていくっていう経験だったりとか、もちろん物づくりだけじゃなくって、私たちがこれから暮らす未来にどんな文化があって欲しいか、どんな仕組みがあって欲しいかっていうところを考えようって、そういう意味も込めて『リビルド・ニュー・カルチャー』、私たちのこれからの暮らしを作っていこうっていう気持ちでやっています」
(編集部注:「リビセン」の拠点を長野県諏訪市にしたのは、空間デザインのお仕事で下諏訪に3ヶ月ほど滞在していたら、華南子さんの体調が良くなり、また知り合いもできたことや、長野には古いものがたくさんあるし、東京や名古屋など、都会へのアクセスも良かったので、住まいを東京から下諏訪に移した結果、諏訪市で事業を始めることになったそうです)
<日本の空き家、過去最多に>
2023年の住宅・土地統計調査によると、全国の空き家はおよそ900万戸あり、過去最多の空き家数に。また、総住宅数に占める割合も13.8%と最高を更新。900万戸の空き家のうち、賃貸や別荘などを除き、取り壊し予定や長期間不在の空き家は、およそ386万戸にのぼるそうです。
空き家は放置しておくと、いずれは朽ち果て、また草木が生い茂り、近隣に影響を及ぼすかもしれませんが、所有者がわからない空き家も多くあるようで、自治体が勝手に取り壊すことはできないそうです。
65歳以上のかたの持ち家率が8割を超えるとされる日本、今後も空き家は、増えていく傾向にあるのかも知れませんね。
引き取り依頼、月に70〜80件!
※「リビセン」は、いわゆるリサイクルショップといっても、古材や古道具を売るだけの場所ではないですよね。カフェがあるんですよね?

「古材屋さんができても行かなくないですか?(笑)多分だいたいの人にとっては関係がない場所になっちゃうというか・・・私も以前だったら行かなかっただろうなって思うんですけど、いろんな人にとって関係のある場所だよとか、来ていい場所だよっていうところをちゃんと示すためにカフェを、オープン当時からずっとやっていますね」
●リビセン自体は大きな建物なんですね。
「そうなんです。1,000平米あって1階に古材売り場とカフェがあって、2階に古道具、3階も古道具だったり建具だったりとかを販売しています。あとは1階には雑貨スペースもあって、建具にハマっていた古いガラスを使ったプロダクトだったりとか、それをもう一回ガラス作家さんに吹き直してもらって、グラスとか器にしたものを販売したりしています」

●販売する古材とか古道具は、どうやって集めているんですか?
「基本的には全部、家主さんとの直接のお取り引きが多いです」
●引き取って欲しいっていう依頼が来るっていうことですか?
「そうです。月に70件から80件もあるんですよ」
●すごいですね!
「基本的には車で1時間圏内のご依頼を引き受けていて、それ以上なら、ちょっと出張料金がかかっちゃうよっていうふうにやっているんですけど、それでも月70件から80件あるってことは、全国でどんなスピードで物が捨てられているんだろうって思っていますね」

●確かにそうですね〜。システムとしては事前に下見したりとかされるんですか?
「例えば、物の量が多そうだなっていう時とかは、現地調査に行くこともありますけど、最近は依頼をもらったら、公式LINEでお問い合わせいただいたりもします。公式LINEにこんなものがありますって写真を撮って送っていただいて、この辺を引き取りますねと連絡して現地に行って、そのままお引き取りすることも多いですね」
●なるほど〜。引き取れるものと引き取れないものがありますよね?
「そうですね。私たちに売る力があれば、それこそ何でも引き取れるんですけど、リビセンに来てくれるお客さんが手に取ってくれるようなものだったりとか、自分たちが使い方を提案できるものだったりとか、これ、かわいいですよねってお客さんと一緒に言えるとか、次の人にちゃんと手渡せるぞって、つなげることができるって、自分たちが思えるものを引き取りさせてもらっていますね」

レスキュー率が高いプロダクト!?
※販売している古道具は、具体的にはどんな道具が多いんですか?
「本当にさまざまなんですけど、多分いちばん身近なところだと古いお皿とかはとっても多いですね。1枚300円ぐらいから売っているんですけど、印判皿っていう昔の小っちゃいお皿だったりとか、漆の器だったりもあります。あとは、諏訪だと結構、養蚕が盛んだった地域なので、そういうお家だと籠がたくさん出てきたりとか、そういうものも多いですね」
●販売前にきちんとメンテナンスされるわけですよね?
「そうです。もう本当にそれが大変です(笑)。やっぱりみなさん、おばあちゃんからお家を引き継いだけど、手つかずの場所みたいなところがあって、真っ暗だったりとか、そういう埃がかぶっているようなところに行ってレスキューしてきます。
クモの巣だったり、繭(まゆ)がついたままのお蚕さんのグッズだったり、そういうのを全部水で洗って乾かして値段をつけて、さらにどこからレスキューしてきたのかわかるように、うちは番号で管理しているので、そういう番号をつけて、ようやく店頭に出せるっていう感じなので、レスキューしてきてから店頭に出すまでに長いと1ヶ月ぐらいかかるものもありますね」

●オリジナルの製品も販売されているんですよね?
「はい、そうですね。オリジナルの製品だと古材のフレームとかが今はすごく人気で販売しているんですけど、これは本当にレスキュー率がすっごく高いプロダクトなんですよ」
●その古い材が素材ってことですよね?
「古材とか古道具だけだと、やっぱり古材をお家に欲しいっていう人ってそんなに多くないというか・・・。古材を素敵だなと思っても、お家でどう使っていいかわかんないっていうかたのために、どうにかして、暮らしの中で古材だったりとか、リサイクルのプロダクトを家に置くきっかけを作れたらいいなと思って・・・。
古材を使って枠を作って、レスキューしてきた建具からガラスを外して掃除して、それをはめてフレームを作っているんです。なので、ほとんど新しく買って何かを作っているっていうことがないプロダクトです。後ろのガラスを止める金具だけ、新しく買っているんですけど、それ以外は全部レスキューしたものなので、とてもレスキュー 率が高くて、気に入っているプロダクトです」
「リビセンみたいなおみせ やるぞスクール」
※「リビセン」では、ほかにも古い材を使った空間デザインやDIYのワークショップなどもやっていますが、番組として特に注目したのが、2023年から始めた「リビセンみたいなおみせ やるぞスクール」。ネーミングにも惹かれたんですけど、こんなスクール、やっていたんですね?
「そうなんです! リビセンが2025年で(オープンから)丸9年になるんですけど、やっていく中で本当に大変だなって思うことがたくさんあるんですね。
でも大変な一方で、さっきも申し上げました通り、月に70件から80件、1時間圏内だけでレスキュー(の依頼が)あるから、みんなが各地でレスキューをやってくれることを応援できるといいんじゃないのかなって思って、私たちがしてきた大変な思いを全部学びにして、みなさんにお伝えするっていうスクールをやっています」
●日程はどれぐらいなんですか?
「2泊3日で、がっつりと夜まで懇親会というか、みなさん、本当にずっと質問し続けてくれるみたいな時間なんですけど・・・」

●例えば、どんなプログラムがあるんですか?
「例えば、最初にうちの夫がリビセンが立ち上がった経緯から、今までどういうふうに進んできたかっていう話もあったり、どういうふうにレスキューして、どういう道具を使って掃除してっていう、具体的なレスキューの方法についてのヒントがあったりとか・・・。
あとはリビセンから徒歩5分圏内にお店がたくさんあったりするんですけど、そういうコミュニティがどういうふうに育まれていったかっていう話だったりとかもしていますね」
●でも、これまでに培ってきたノウハウをさらけ出すってことじゃないですか?
「もう! すべて!(笑)」
●いずれ競合するかもしれないとか、何か怖さとかためらいみたいなものはなかったですか?
「ないんですよね・・・(笑)。それにはいくつか理由があるんですけど、ひとつは自分たちに70件から80件のレスキューがあって、例えば富山からレスキュー依頼があっても、東京からレスキュー依頼があっても、やっぱり私たちが行けない。私たちが行けなかったら、どうせ捨てられてしまう。だったら各地でみんながレスキューしてくれたほうがいいよな! っていう・・・。商圏が被らないっていうのがひとつだったりとか。
あとは、夫がデザイナーとしてのキャリアが始まる時に、大学の先生に“デザイナーはデザインで世界をよくするんだ!”って言われたのがきっかけで、デザイナーになって、今もデザイナーとして働いているんですけど、本当にスクールを通じて古材とか古道具をみんなが奪い合う世界になったら、私たちはあっさりリビセンはやめて、自分たちの力を効率よく社会に還元できる方法をまた考えられたらいいなって思っているので、全然怖くないです(笑)」
(編集部注:「リビセンみたいなおみせ やるぞスクール」の参加者の顔ぶれは、工務店などの建築関係、介護職、農家さん、デザイナー、地域起こし協力隊のかたなど、多彩だそうです。今年のスクールは3月からスタート! 「リビセン」のサイトに日程が掲載されていますので、参加してみたいと思ったかたは、ぜひチェックしてください。https://school.rebuildingcenter.jp)
移住者も暮らしやすい街
※華南子さんは埼玉のご出身ということですが、長野県上諏訪での暮らしはいかがですか?
「私にとっては、本当に最高ですね(笑)」
●この時期は寒いですよね?
「本当に地獄みたいに寒くて・・・(笑)。私、初めてこんな寒いところに住んだので、長野に住んでから地獄って暑いと思っていたけど、寒い場所なのかもなって思うようになるぐらい本当に寒いんです。
でも私の生い立ちというか、10年以上同じ場所に住んだことがないんですよね。なので、長野県の上諏訪が初めて(10年)住んでいるんですけど、本当にここでよかったなって思って暮らしていますね。10年同じ町に暮らすと、こんなふうに町の関わり方というか、町と自分の距離感だったりが変わっていくんだって、すごく楽しませてもらっています」
●具体的にどんなところが最高なんですか?
「たくさんあるんですけど、すごくわかりやすいところで言うと、これは諏訪の魅力っていうわけではないですけど、東京に住んでいたことも長かったので、東京との距離も結構ちょうどいいです。2時間ぐらいで行けるので日帰りでも行けるし、仕事もすごくしやすいっていうのも、物理的に地理的に便利なところだし、温泉が気持ちいい! すごく!
すっごく寒いけど、温泉も豊富な地域なので、温泉があることもありがたいし、車で10分で山があるけど、上諏訪は中央線沿線っていうこともあって、私的には結構都会なんですよね。
歩いてスーパーも行けるし、コーヒースタンドもあって、お花屋さんも古道具屋さんもあるっていう・・・車であっちこっち素敵な場所に行くのもいいんですけど、歩くスピードで歩ける距離感の中で、自分の暮らしが楽しいっていうのは、私にとってはすごく心地がいいですね。
諏訪のすごくいいところは、外から来る人に慣れている人が多いというか、中山道が通っていて、東京から名古屋に抜ける、もともと人が行き交う場所だったので、私たちみたいな移住者も暮らしやすいですね。
空き家が出てもまたそこに入居する人も多かったりとかして、ちょっとずつ改善というか、活用されていく兆しのある町だなって思っています」
生きる心強さを持てる場所
※今までレスキューした古材や古道具で、びっくりするようなものはありましたか?
「びっくりするようなものかぁ・・・いろいろあるんですけど(笑)。私たちが諏訪の出身じゃないっていうところが多分大きいんですけど、養蚕のいろいろな道具が出てきたのはすごくいろんな、いい驚きがありました。
この土地を知るきっかけにもすごくなったし、養蚕って言葉では聞いたことがあったけど、実際にここにこういうふうに葉っぱを敷いて、ここでお蚕さんを飼っていたんだみたいな、そこで本当に暮らしていたこととかが垣間見えたのがすごくその土地の解像度が上がったというか・・・。
この土地で暮らす意味だったりだとか、この土地を楽しむきっかけにもなったのは、その養蚕の現場のレスキューだったので、すごく印象深いレスキューではありますね」
●「REBUILDING CENTER JAPAN」の活動は、今後益々注目されると思うんですけれども、そのあたりはいかがですか?
「え~〜、どうでしょう(笑)。注目!? そうですね・・・」
●益々人手が必要になってきますよね?
「そうですね・・・でも自分たちとしては、そんなに大きな会社になりたいっていうことはないので、今ぐらいの人数で楽しく暮らしていけたらいいなって言ったらあれなんですけど・・・。
その一方で、日本は空き家問題とか高齢化の問題だったりとか、最近は居場所作りみたいな話だったりとか、そういう社会問題ってどこも同じようなことを抱えていると思うので、『みたいなスクール』を通じて、ほかの地域で同じような課題感を持っている人たちとつながることで、もちろんリビセンみたいな事業もサポートしつつ、いろんな地域で起きている社会課題を私たちもインプットしながら、また自分たちの地域にフィードバックしていくっていうことは、どんどんやっていきたいなと思っています」

●リビセンの活動を通じて、どんなことを伝えていきたいですか?
「私たちのメインの事業は、もちろん古道具とか古材が外から見てもいちばんわかりやすいところではあるんですけれど、大もとにあるところで『生きる心強さを持てる根拠になる場所』になれたらいいなっていうのを思っています。例えば、物が壊れたら捨てるっていうだけじゃなくて、自分で直せるって思えるってすごく心強いと思うんですよね。
電化製品とかが多かったりすると、自分で直せるって思えるものって、なかなか少ない世の中ではあるなと思うんですけど、自分にもできるかも! っていう気持ちをひとりひとりが少しでも持てて、その一歩を踏み出せたら、どんどん見える世界が因数分解されていったりとか、社会の解像度が上がっていって、自分がよりよく暮らしていくためにとか、よりよい社会を作っていくために、これだったらできるって考えられるような、原体験じゃないですけど、場所を作っていけたらいいなっていうふうに思っています」
INFORMATION

ぜひ「REBUILDING CENTER JAPAN」の活動にご注目ください。今年の「リビセンみたいなおみせ やるぞスクール」は3月21日から23日、4月25日から27日、5月16日から18日、そして10月にも、11日から13日に開催される予定です。「リビセン」で販売している古材や古道具のほか、所在地など、詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
◎「REBUILDING CENTER JAPAN」:https://rebuildingcenter.jp
2025/1/12 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、縄文大工の「雨宮国広(あめみや・くにひろ)」さんです。
雨宮さんは1969年、山梨県生まれ。20歳のときに丸太の皮を剥くアルバイトをきっかけにチェーンソーを使いこなすログビルダーに憧れ、その後、伝統的な木造建築を学ぶために弟子入りし、大工修行。
そして石の斧(おの)「石斧(せきふ)」に出会い、人生が一変。現代の文明社会に疑問を感じ、自然とともに暮らしていた縄文時代の人々の知恵や技術に傾倒していきます。普段は山梨のご自宅にある縄文小屋で暮らしていて、髭や髪を伸ばした、そのルックスも含め、まさに現代の縄文人なんです。
そして2016年からおよそ3年かけて行なわれた、国立科学博物館の人類進化学者「海部陽介」さん率いる一大プロジェクト「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」に全面協力、石の斧だけで丸木舟を作る中心人物として活躍されました。
そんな雨宮さんがいま全力で取り組んでいるのが「JOMONさんがやってきた!」というプロジェクト。これは、日本全国の子供たちと一緒に丸木舟を作り、その舟で日本各地の海を巡るというプロジェクトなんです。
3年前にご出演いただいたときには、すでにこのプロジェクトは始まっていましたが、今年、新たなステージに突入するということで、改めてプロジェクトの全容や今後の展開に迫りたいと思います。
☆写真協力:JOMONさんがやってきた!

樹齢280年の杉の命をいただく
※2021年にプロジェクトの第一章、そのパート1として「杉の命をいただく」という取り組みがありました。これは丸木舟にするための木を伐る活動ですよね?
「そうです。丸木舟を作るためには巨大な杉の木が必要なので、その杉さんの命をいただくというのが、いちばん最初のスタートですね」
●その巨大な木は、どこにあったんですか?
「愛知県 北設楽郡 東栄町、奥三河と言われている地域ですね。愛知県でも名古屋とか街のほうではなくて、山の山の奥で長野県との県境ですね」
●樹齢とか大きさは、どのくらいだったんですか?
「めちゃくちゃ大きかったですよ! 樹齢が280年、樹高、木の高さが46メートル、木全体の重さが多分30トンくらいあったでしょうね」
●ええ〜っ! そんな巨大な杉の木を石斧で伐っていくってことですよね?
「そうなんです。子供たちと一緒に石斧を使って、杉の命をいただくということでした」
●杉と対話しながらっていうことですよね?
「そうですね。もう否応なしに対話が絶対生まれるんですよね。長い期間、向き合いますから」
●樹齢280年の木が倒れたときってどんな思いがありました?
「もう感無量ですし、とにかくありがとうございましたっていう気持ち。それともうひとつは、命をいただいた以上、その杉さんとの約束を果たすことが頭をよぎるというか、絶対にそれはやらなきゃいけないことだなっていうのは、常にありましたね」
●子供たちにも参加してもらって、という作業でしたけれども、どれくらいの日数がかかりましたか?
「19日間です。これは体験教室を3回行なったんですよ。最初の体験教室をやって、次の週、また次の週と3週に渡ってやったので、(木を)寝かせる期間を調整しながらやったんですね。だから伐採だけをやって木を寝かせるには、本当はもっと早くできるんですけども、体験教室をやりながらゆっくりやったので、19日間かかりました」
丸木舟の進水式で奇跡が!?
※2022年には「JOMONさんがやってきた!」の第一章・パート2として「47都道府県・丸木舟作りツアー」がスタートしました。伐った大きな杉の木をトラックに積んで、全国を回ったんですよね。各地で参加した子供たちの様子はどうでしたか?

「もう本当に感動しかないですね。どの県がよかったとか、よく聞かれるんですけれども、本当にどこの県も素晴らしい子供たち、そしてひとりも諦めた子供がいない。これは自分で石斧を作るというところからやるので、そこで諦める子がひとりもいないんですよ。
土曜日に石斧を作って、日曜日にその石斧で削る。それを全国リレーするわけですけれども、それは本当にびっくりすることだったですね」
●石斧を作って、その石斧を使って木をくり抜く作業で、延べ何人くらい参加されたんですか?
「全国ツアーの丸木舟作りは、親御さん含めて1600名くらいですね」
●おお〜そうなんですね! 子供たちもなかなかできる体験じゃないから、目を輝かせていたんじゃないですか?
「そうですね(笑)。子供もそうなんですけど、大人もやったことがある人はひとりもいないんですよ。だから本当に親子で目を輝かせながらやっていましたね。
実際に来てくれた子供たちの年齢層は、ほぼほぼ10歳・・・10歳くらい、もしくは10歳以下の子供です。最年少は4歳くらいで、参加して、自分で石斧を作るっていうね。だから本当に保育園児とか(小学校)1年生から4年生までの子供が主体になって作ったんです。それがまたすごいなと思いますね。高学年とか中学生とかじゃなくてね、はい」

●で、2023年10月には第一章が完了して、丸木舟が完成しました! 舟に名前をつけたんですよね?
「はい、命名ですね。進水式でね」
●なんというお名前になったんですか?
「みんなの舟だから、『ミンナ』という名前です」
●へ〜! カタカナでミンナ、いいですね!
「はい、ありがとうございます」
●丸木舟「ミンナ」の大きさは、どれくらいになるんですか?
「ミンナの大きさは全長が約10メートル、沖縄で完成した時の重さは1.7トンありました」
●実際に水に浮かべて、試乗されたりもしたんですよね?
「ミンナが完成したあとに沖縄で・・・そのミンナを山梨まで一度持ってこなきゃならなかったので、その帰りの道中、トラックに乗せて、山口、静岡、そして山梨の西湖で試乗会を2カ月間やりましたね」
●実際に水に浮いたときは感動だったんじゃないですか?
「そうですね。奇跡が起こったなと思いましたね。なぜかというと、丸木舟は丸太の状態でくり抜いて作るので、左右をバランスよく作るとか、平らにふなべりが真っ直ぐ浮かぶとか、バランスよく作るのはめちゃくちゃ難しいんですよ。一回浮かべただけでは絶対できないっていう、そういう舟作りなんですけども、なんとそれが沖縄の進水式で、一回浮かべただけで完璧に浮かんでしまったと!」
●すご〜い!
「すごいですよ! 本当にすごいです! 手直しは全くなかったですね」

杉さんとの約束を守る
※2023年11月から「JOMONさんがやってきた!」の活動は第二章に入り、「キラキラ星プロジェクト」が始まりました。これはどんな活動なんですか?
「第一章は丸木舟を作るっていう活動でしたよね。第二章は杉の木、丸木舟になった杉の木との約束を果たすためのプロジェクトです」
●具体的にはどんなことをするのですか?
「その約束というのは、杉さんが生きていた時に、私たちが命をいただく時に、杉さんが私たちにこう言ってきたんですよ。“俺の命をお前たちにあげる代わりに、お前たちがそんなに舟を作りたいなら、命をあげよう“と、”その代わりにひとつだけ約束してほしい“と言ってきたんですよ。それが“この地球上のすべての生き物たちを幸せにすることだ! わかったか~!”って言ってきたんです。
それで私たち参加した人たちも“わかりました! 杉さん! 約束を必ず果たします”って言って、石斧の斧を(杉の幹に)入れて木の命をいただいたんですね。そして全国ツアー、1600人の参加者も“杉さんとの約束を守ります!”と言って、みんなが幸せになる舟を作ったんです。これが第一章だったんですよ。
今度はその舟で世界航海をして、すべての生き物を幸せにする航海を、実際にみんなでしていこうというのが第二章なんですね」
●杉さんが言ってきたっていうのは、どういうことなんですか?
「実際に杉の木は人間の言葉は喋らないですからね。私も聴きたかったですけど(笑)・・・私たち人間は、いろんな生き物の声を聴く力はあると思います。いわゆる相手を思いやる、相手の立場になって物を考えるっていうことですね。 もしあなたが、君が杉の木だったらどんな気持ちになるかと・・・」
●なるほど~。
「と言いますと(杉さんは)280年も生きてきて、いろんな生き物たちの家になって、そして私たちにいちばん大切な、生命にいちばん必要な、おいしい水、おいしい空気を毎日作ってきてくれたんですよ。その役目を断ち切られるわけですね。そしたら“俺の命をお前にあげるけども、お前たちは俺以上のことをしてくれ“と、そういうふうに言ってきた。命のやり取りは本来そういうことなんですね。
いろんな生き物の命を私たちはいただいて生きています。その生き物たちの命をいただいたら、より良い地球にしていかなきゃいけないですね。これはもう本当、生命原理で当たり前のことなんですけどね。それを杉さんがこう言ってきたというふうに言っていますけども」

地球をキラキラ星にしよう!
※雨宮さんが取り組んでいるプロジェクト「JOMONさんがやってきた!」の活動は2023年11月から第二章に入り、「キラキラ星プロジェクト」が始まりました。プロジェクト名にある「キラキラ星」には、どんな思いが込められているんですか?
「これは夜、星を見た時に“きれいだな~”って思うでしょ!? みんなこれ、全人類が思うことだと思うんですよ。“あの星、なんか汚ねえ星だな~”なんて思う人はひとりもいないと思う。キラキラする星をね。でも、私たちが住んでいるこの星、地球は今めちゃくちゃ汚いんですよ。その地球を汚しているのは私たちなんですね。その星をキラキラ星にしようよっていうプロジェクトなんです」
●素敵な名前ですね~。全国の海を丸木舟「ミンナ」で巡りながら、海岸のゴミ拾いもされるってことですよね?
「そうですね。この地球を汚しているものは、私たちが毎日出す、暮らしから出るゴミなんですね。想像してみてください。もし全人類がゴミを出さない暮らしをしたら、どうなると思いますか? ゴミが出ないんですよ、暮らしから。それは原始人たちが、縄文人たちがやってきたことなんですね。そういう地球は本当に輝いていたと思います。
ここでひとつ、ゴミというのは一般家庭から出るゴミだけではなくて・・・そもそもゴミという概念は、手に負えない危険なものですよね。そういう意味で考えると戦争の道具とか、核兵器とか、あらゆる毒薬とか、もうすべてがゴミなんですよ。そういうものを作り出さない世の中にしていく、それを目指していますね。
海岸のゴミを拾っても、ただ場所が移動するか、燃やせば気体になるか、形は変わってもなんら地球に害を及ぼさないものには変化しないんですよ。ずっとゴミであり続ける。だからこそ、もうこれ以上ゴミを作らない世界を作っていこう、全人類の暮らしを作っていこうということを、みんなにアピールしながら航海していくということですね。それが大切なところです」
●現在は準備期間っていうことですよね?
「そうですね。2023年の11月から2024年の10月まで、日本一周航海練習ということをしまして、山口県の佐合島(さごうじま)というところで航海の練習をしていました。おかげさまで航海のクルー、ずっと一緒にいつも漕いでくれる常駐クルーが私を含めて3人誕生しました」
●おお~~!
「そして、日替わりクルーという、『ミンナ』を作った子供たちとか、作ってない子供たちもみんなで一緒に漕いでいこうっていうのが、このプロジェクトなんですね。今回、体験教室に参加してくれた子供や大人たちも入れて、60名以上の日替わりクルーも誕生しました」
●この「キラキラ星プロジェクト」が本格的に始まるのは、いつ頃からなんでしょうか?
「今年2025年の4月から航海がスタートします」
(編集部注:今年4月から始まる日本一周の航海は、まず、瀬戸内海を2年かけて巡り、その後、九州編、日本海編、北海道編、さらには太平洋編、南西諸島編と続く予定。毎年、寒い時期は避けて、4月から10月に航海することを繰り返し、7年ほどで日本一周を終える構想になっています)

ドキュメンタリー映画『みんなのふね』
※そんな雨宮さんのプロジェクト「JOMONさんがやってきた!」は、実は第一章の活動が映像として記録され、ドキュメンタリー映画として、ついに完成。タイトルは『みんなのふね〜Jomon-san has come』。監督は、雨宮さんが全面協力した「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」の撮影クルーだった「にしやま・ゆうき」さんというかたなんです。
この映画は、雨宮さんのほうから「にしやま」さんにアプローチし、これからやる活動を映画にしてほしいと頼んだそうですね。映画にしたいと思ったのは、どうしてなんですか?
「『JOMONさんがやってきた!』というプロジェクトを言葉で言っても、なんじゃそれ!? っていう、わけのわかんないプロジェクトなんですけども、それをより知っていただくために、いちばん大切な、杉の木の命をいただいて、全国の子どもたちと舟を作ったというところを、それに参加したわずかな人しか見てないわけですよ。
そこがいちばん大切な部分で、舟ができちゃったら、みんなそのことを見ようともしないし、なかなか見られない。そこを映像を通して全国の人たち、そして全世界の人たちに知ってもらいたい! そういう思いで、これは絶対に映像に残さなきゃと思って、私の知り合いにもテレビ局の人とかいましたけども、みんな断られて、最後の最後に頭に浮かんできたのが、にしやま監督だったんです」
●へぇ~! 完成版はご覧になりました?
「はい! 昨年の12月7、8日と、先行上映会やりまして・・・」
●どんなお気持ちになりましたか?
「いやもう、ありがとうございますって、これしかないですね! 素晴らしい映画です。本当に自分で言うのもなんですけども・・・」
●英語の字幕が入っているんですよね?
「そうです。このプロジェクトは、全世界の人でやっていかないと絶対に達成できないので、英語(の字幕)も入って、全世界の人に発信していきたいですね」
●『JOMONさんがやってきた!』は現状、どんな構想になっていますか?
「今のところ、今年の4月から航海が始まって、7年間かけて日本を一周できたら、その後は世界一周です!」
●おお~!
「これを5年かけてやります。で、日本を出発して5年後に戻ってこられたら、次はアメリカ大陸に向かって、今度は各大陸の沿岸のゴミを拾う航海をずっとしていきますね。これはおそらく300年ぐらいかかるんじゃないですかね」
●うわ~、じゃあ、後継者が必要ですね?
「そうですね。全国にタネを撒いてきましたし、おかげさまで日替わりクルーの練習にも、子どもたちが参加してくれていますし、常に私も“次は頼むぞ!”っていうことを言いながら一緒にやっていますよ」
●改めてになりますが『JOMONさんがやってきた!』の活動を通して、いちばん伝えたいことを教えてください。
「いちばん伝えたいこと・・・これはみなさん、全人類がこの地球船というかけがえのない、ひとつの船に今乗って暮らしているわけですよ。みんなで同じ方向を向いて、キラキラ星に向かって漕いでいかなければ、絶対に達成できないプロジェクトなんですね。
必ずひとりひとりにできることがあって、その小さな行動が絶対に大きな成果を生んで、ゴールすることができるので諦めないで、みんなの心をひとつにして、毎日漕いでいく、毎日楽しく仲よく暮らしていくっていうことを心がけて、漕いでいってほしいなと思います。この『地球船』をね」
●今だからこそ私たちは、縄文時代の暮らしとか考え方に習う必要がありますよね?
「そうですね。科学万能の、この社会が本当にいいんだ! ではなくて、やはり世界の状況が今こういう結果になっているわけですから、一度見直して、本当にこの文明社会がいいのかをしっかり考え直してほしいですね」
INFORMATION
雨宮さんが全身全霊で取り組んでいるプロジェクト「JOMONさんがやってきた!」では、活動資金を寄付という形でも募っています。ぜひサポートをお願いします。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
◎JOMONさんがやってきた!:https://jomonsan.com
ドキュメンタリー映画『みんなのふね〜Jomon-san has come』は順次、全国で公開予定。3月8日には雨宮さんの地元、山梨県甲州市にある勝沼市民会館で上映されることになっています。この映画は自主上映も可能だということで、上映会のスケジュールも含め、詳しくはオフィシャルサイトを見てください。
2025/1/5 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、国立研究開発法人「海洋研究開発機構(JAMSTEC)」の主任研究員「川口慎介(かわぐち・しんすけ)」さんです。
川口さんは1982年、兵庫県宝塚市生まれ。北海道大学・理学部時代は、海ではなく空、それもオゾン層より上の「大気の研究」をしていたそうです。その後、一転「深海の研究」へ。そして東京大学海洋研究所の大学院生時代に、JAMSTECのスタッフと一緒に仕事をしたこともあって、誘われてJAMSTECの職員になり、現在は主任研究員として活躍されています。プライベートではプロレス好きのサッカー部員で、カラオケも得意だとか。SNSでは「海ゴリラ」として知られています。
JAMSTECは、海洋・地球・生命に関する研究や調査を行なう国立の研究機関で、日本が世界に誇る科学調査船「ちきゅう」や有人潜水調査船「しんかい6500」、その母船となる「よこすか」などを保有しています。
川口さんは「しんかい6500」に乗船するなどして、深海や海底に関する研究をされています。そして先頃『深海問答〜海に潜って考えた地球のこと』という本を出されました。
きょうはそんな川口さんに「しんかい6500」による調査のほか、海水に含まれる成分や、海の中で聴こえる音の研究のお話などうかがいます。
☆写真提供:海洋研究開発機構

「しんかい6500」、初めての時の記憶がない!?
※まずは、JASMSTECで、どんな研究をされているのか、教えてください。
「僕は調査船に乗って、陸地から離れた遠洋のほうまで行って、深い海、特に海底の近くで何が起こっているかを実際に潜ったりとか、ロボットを降ろして調べる仕事をしています」
●研究のために川口さんも「しんかい6500」に乗って調査することもあるってことですよね?
「はい、実際に『しんかい6500』に乗り込んで、深い海まで潜ったこともあります」
●これまでに何回ぐらい乗ったんですか?
「僕、実は少なくて、4回だけなんですけども、潜らせてもらっています」
●初めて「しんかい6500」に乗って、深い海に行った時はどんなお気持ちでしたか?
「もう全然覚えてないですね。初めての時のことは全く覚えてないです。きっと興奮していたんだと思います」
●乗る前からワクワクみたいな、そういう感じでしたか?
「う〜ん、もう本当に覚えてないんですけど(苦笑)、どちらかというとやっぱり研究が進む進まないっていう部分のプレッシャーがあったので、そっちでいっぱいいっぱいだったのかもしれないですね」
●(最初の時は)どれぐらいの深さまで潜ったんですか?
「最初の時は2500メートルだったんですけど、その後6000メートルまで潜る機会がありました」
●光が届かない深海って真っ暗ですよね?
「真っ暗ですね」
●外の様子は窓から確認できるんですか?
「はい、窓に顔をへばり付けて、ずっと外を見るんですけど、時々プランクトンとか魚で光るやつなんかがいたりして、ちらっと光が見えたりして幻想的です」
●へえ〜、すごいですね! 1回の潜水時間はどれぐらいなんですか?
「潜水船の蓋が閉じて、潜って帰ってくるまでのトータルで8時間ぐらいですね」
●深海で調査できる時間はどれぐらいなんですか? 到達するだけでも時間はかかりますよね?
「そうなんですよ。だから6000メートルぐらいまで潜ると、行くのに3時間、帰るのに3時間ぐらいで、海底にいるのは2時間もないですね」
●乗船するのは何名ぐらいなんですか?
「潜水船の中には3人乗ります。パイロット側のかたが2名と、研究者1名というのが通常の組み合わせです」
(編集部注:6000メートルくらいまで潜るのに、およそ3時間はかかるというお話でしたが、予定の深さに到達するまでの間、「しんかい6500」の狭い船内で何をされているのか、気になりますよね。お聞きしたら、努めてリラックスするようにしていて、パイロットのかたとおしゃべりをするか、仮眠をとるか、中にはタブレットなどで映画を見る人もいるそうです。
また、船内にはトイレはないので、成人用のおむつを着用して乗船するとのことですが、おむつもどんどん改善されて、不快感はまったくないそうですよ)

母船に戻ってきたからが勝負!?
※研究にはサンプルの採取が欠かせないと思いますが、どんなサンプルをどんな方法で採取するんですか?
「生物だと、掃除機のような形をしているもので吸い取って、網に引っかけるように集めたりだとか、水を取りたい場合だと、ペットボトルのようなものを持っていって、深海で(水を採取したら)蓋を閉じて持って帰ってくるとか、ということをやっています」
●深海になればなるほど、水圧がとんでもなくすごいですよね。そんな深海で採取したサンプルを船の上まで引き上げると、状態が変わっちゃわないのかなって思うんですが、そのあたりはどうですか?
「めちゃくちゃ変わってしまうんですね。圧力が抜けるので変形するっていうのもあるんですけども、深海は基本的に涼しいというか冷たい環境なので、持って帰ってくるまでに、ぬるくなってしまうのが結構深刻な問題になります」
●ぬるくしないために何か方法があるんですか?
「みんな工夫はしているんですけれど、これという方法はなくって・・・僕は最近そこを解決したくって、冷たくするための装置を開発するような仕事もしています。 冷たいまま持って帰ってきて調べた時に、今までと全然違う見え方をしたら、ぬるくなっているってよくなかったんだなっていうのがわかっちゃう、よくも悪くも判明するかなと思って取り組んでいます」
●採取したサンプルは、船の上ですぐ調べるんですか?
「ものによっては本当にそこの時間が勝負になったりしますね。どんどん腐っていくものもありますし・・・だから潜水船で潜ることの調査なんですけど、潜水船が海の上で待っている母船に帰ってきてからのほうが本当の勝負で、徹夜続きになることもあります」
●では母船には、すぐ研究できるような機器とか施設が揃っているってことですよね?
「母船には冷蔵庫、冷凍庫はあるんですけど、基本的なものしかなくて、航海の度に研究者が自分のツールを持ち込んでそれを使います」
●川口さんの研究でこれまでサンプルを通して分かってきたことがあれば、ぜひ教えてください。
「わかってきたことは・・・まだまだわかんないことがあるなっていうのが毎回わかります」
●(笑)謎が多いんですね?
「謎だらけですね!」
(編集部注:川口さんが開発している冷やす装置はスバリ「深海冷凍装置」。パソコンを冷やす機能を応用しているそうですよ)
海水にはあらゆるものが含まれている!?
※川口さんは先頃『深海問答〜海に潜って考えた地球のこと』という本を出されています。この本を出すにあたって、何かコンセプトのようなものはありましたか?

「海の研究者が書いた海の本っていうのは、僕の師匠とか上司もたくさん本を書いているんですけど、これまでだいたい2種類あって、研究者が自分の専門分野のことを詳しく書いて紹介するタイプの本と、もうひとつは(一般のかたに)海に親しんでもらうために、”海って不思議なところだね”っていうポップな感じで書いてあるものと、だいたい2種類に分かれるんですね。
僕は今回その中間ぐらいの本を書きたいなと思って、ポップで読みやすいんだけど、専門的な話も書いてあるっていう、そこを狙いたいなっていうのがいちばん大きなコンセプトで 書きました」
●本の中から、ほんの少し初歩的なことをピックアップして質問させていただきたいと思います。まず海水はしょっぱいですよね?
「はい、しょっぱいですね」
●しょっぱい、そのもとは食塩の成分ですよね?
「そうですね。食塩の成分である主にナトリウムがしょっぱさの原因だというふうに言われています」
●塩分濃度はどこの海でも同じなんですか?
「これ、ほんとに重要なポイントで、海の塩分はどこの海でもだいたい同じなんですけど、専門家からすると全然違います! っていう言い方をします。ちょっとしか塩分は違わないんですけど、そのほんのちょっとの違いが、海水が動いたりとか混ざったりするのにとても大きな影響を及ぼすんですね。
一般に普通に暮らしている人がなめたら、同じしょっぱさだねっていうレベルの塩分なんですけど、科学的にはこれは全然塩分が違うんだというような言い方をしたりします」
●海水には、ほかにどんなものが含まれているんですか?
「海水にはなんでも含まれています。あらゆるものが含まれている・・・ただ多い少ないというのがあって、塩分、しょっぱいって言っている塩素とかナトリウムはとってもいっぱい溶けていますけど、たとえば鉄はほんの少ししか溶けてないです。でもほんの少しは溶けている、金も銀も銅もほんの少しは溶けているっていうのが海水の正体です」
日本近海にもある海底資源
※海底にある資源については、世界でも関心を持っている国が多いと思いますが、日本近海にも海底資源はあるんですよね?
「はい、日本の近海にも海底の資源が見つかっている場所はあります」
●どんな資源が見つかっているんでしょうか?
「日本の近海でよく見つかるのは、ひとつは銅を多く含むような『熱水性鉱床』と呼ばれるもの。日本列島からは離れてしまいますけども、離島の周りにあるのが『マンガン団塊』とか呼ばれるようなマンガンを主体とする海底資源があります」
●実際に海底から引き上げて資源として利用するとなると、それはそれで莫大な費用がかかりそうですね?
「費用はすごくかかると思いますよ。資源として利用するっていうことは大量に採らなきゃいけなくて、大量に採るっていうことは、それに必要な船も大量だし、働く人も大量だし、かかる時間も長いしっていうので費用はたくさんかかると思います」
●そうなると、国家プロジェクトですよね?
「う〜ん・・・微妙・・・(苦笑)表現が難しいですけど、海底資源ってよく相場で1グラム何円っていう部分があって、そこは変動するじゃないですか。でもここの海底に何グラムありますっていうのは変動しないんですよ。
だからもし、すごく貴重になって価格がすごく上がると、国家プロジェクトじゃなくても儲かるからやるっていう企業が出てくるかもしれない。でもそこに何グラムありますか? っていうのがわかっていないと、やっぱり企業は手が出しにくくて、そういう意味で今の段階では国家プロジェクト的に動いているというのが、海底資源に関する現状だと思っています」

勝手になっている海の音!?
※川口さんは数年前から「海の音」の研究をされているそうですね。これはどんな研究なんでしょうか?
「海の音の研究にもいろんな種類があるんですけど、僕は海に人間が鳴らした音というよりは、勝手に鳴っている音をよく聴くと、海の状況がわかるんじゃないかっていう考え方で取り組んでいます」
●勝手に鳴っている音っていうのは、どういう音なんでしょうか?
「一般的にいちばん鳴る音は、たとえば、雨が”ザア〜ザア〜”降ると海面を叩くので音が鳴るとか、波がじゃぶじゃぶすると”ジャブジャブン”という音がするとか、そういうのが勝手になっている音のひとつです。それとは別に生物が動くことで、浅いところから深いところ、深いところから浅いところへと移動すると、体が”ポキポキ”なる音とか、(生物が)餌を食べる時に海面で”ジャブジャブ“する音が聴こえたりもします」
●そういう音は、どうやって録音するんですか?
「深海で音を録る時は、海底に録音機を設置してただひたすら待つ。録音機に音が入ってくるという形で今は録音しています」
●深い海に録音機を設置するってことですよね? どんな録音機なんですか?
「深海の圧力に耐えられる、海水につけても壊れない特殊な装備をした録音機なんですけれども、それはさておき、そういう録音機をたとえば『しんかい6500』に持たせて潜らせて、海底に置いて帰ってくるという方法をとります。
で、結構大事なところで、『しんかい6500』は船自体から出る音があまりにうるさくて、海の自然な音が聴こえないので、録音機を海底に置いたら一度離れて、船の音が入らない状態にして、自然の音を聴いてもらって、改めてまた回収しに行くというようなことをやっています」
●実際に海の音を研究されて、わかってきたことはあるんですか?
「いや〜わかんないですね(苦笑)まだまだわかんないことばっかりです」
●本当に海って謎だらけなんですね?
「はい、謎だらけです」

●海は本当に広くて深いので調べれば調べるほど、謎が増えていくように思いますけれども、今後、調査研究したいテーマはありますか?
「ひとつ大きいのは、深海生物がどうやって時間を感じているのかっていう研究は、いつかしたいなと思っているテーマです。深海生物が季節とか時間を感じているんじゃないかとか、いや感じてないとかっていうことは、昔から言われています。
いずれにせよ、深海には太陽の光が届かないので、昼と夜ってわからないはずなんだけど、時々(深海生物は)わかっているんじゃないか、みたいなデータが取れることもあって、それが音と関係しているんじゃないかな〜っていう話につなげられると、ロマンがあって面白いかなと思って考えています」
●解明してください!
「(笑)頑張ります。応援してください!」
(編集部注:川口さんは、クジラやイルカなどの鳴き声を含め、海の中で鳴っている音は、きっと深海まで響いているので、その音を研究することで、生物の様子がわかるのではないか、そんなこともおっしゃっていました。
川口さんが携わっている海の音をモニタリングするプロジェクトについて詳しくは、JAMSTECのオフィシャルサイトに情報が載っているので、ぜひチェックしてください)
☆海洋研究開発機構(JAMSTEC ):https://www.jamstec.go.jp/smartsensing/j/
INFORMATION
川口さんの新刊をぜひ読んでください。海とは何か、地球とは何かを、生命の起源や深海の謎、気候変動の対策など、地球規模のテーマにそって探求する問答集です。謎だらけ、わからないことだらけの海について、深く潜って考えてみてはいかがでしょうか。エクスナレッジから絶賛発売中。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎エクスナレッジ:https://www.xknowledge.co.jp/book/9784767833187
「海ゴリラ」という名前で展開している川口さんのSNS「X」にもぜひアクセスしてみてください。
◎X:https://x.com/the_kawagucci
◎海洋研究開発機構(JAMSTEC):https://www.jamstec.go.jp/j/
2024/12/29 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、サバイバル登山家の「服部文祥(はっとり・ぶんしょう)」さんです。
服部さんは1969年、横浜生まれ。東京都立大学在学中にワンダーフォーゲル部に所属し、日本国内の山々を縦走。96年に世界第2位の、カラコルム山脈K2・標高8611メートルに登頂。97年から冬の北アルプス 黒部横断などに挑戦。99年からは食料を現地調達するサバイバル登山を始め、その後、狩猟にも取り組んでいらっしゃいます。
山好きのかたは、山岳雑誌『岳人』の連載で、服部さんのことを知っている、というかたもいらっしゃると思いますが、実はもともと『岳人』の編集者で、現在もフリーランスという立場で編集にも携わっていらっしゃいます。
そして作家としても数々の本を出されていて、いちばん新しい本が『今夜も焚き火をみつめながら 〜サバイバル登山家随想録』。これは山岳雑誌『岳人』に連載していた記事を中心に、えりすぐりのエッセイを加えて編纂した本となっています。
今回は14年ぶりのご出演ということで、改めてサバイバル登山とは、どんな山登りスタイルなのか、そんな初歩的なことから、数年前から始めたという自給自足的な古民家暮らしのお話などもうかがっていきます。
☆写真協力:服部文祥

「サバイバル登山」〜フリークライミング思想
※私、小尾は今回初めて「サバイバル登山」という山登りがあることを知りました。改めて、これはどんな登山スタイルなのか、教えていただけますか。
「自分の力で登ることにこだわった登山だと思っているんですけども、メインの思想というか中心の思想はフリークライミングにあります。フリークライミングは、自然のまんまの岩を自然のまんまの自分で登ろうっていう考え方だと、僕は理解しているんですけども、それをやってみると面白いんですね。
その前の段階のことをちょっと説明しておくと、人工登攀(じんこうとはん)っていうのがあって、岩登りがどんどん発展していく中で、岩に穴を開けて、そこにボルトを打って、それから縄梯子をぶら下げて登るっていうふうにどんどん発展していく、それが人工登攀なんですね。その中で、登るってことは一体どういうことなんだろう? って考えた人たちがいて、それがフリークライミングを生んだんです。
登るっていうことは、もともとある自然の岩の、登りたい人にとって、利用できる(ものが少ない)弱点を、自分たちの肉体を利用しながら、使うことでそれ(岩)を登っていく。
簡単に言えば、子供たちが岩とかを見た時に、これ登れる? ずるしないで登れる? みたいな・・・梯子をかけたりとか、上から垂れているロープとかをつかまないで、自分の体だけで登れるっていうようなのと同じだと思うんですね。そういうフェアな思想っていうか、スポーツマンシップみたいな思想を前面に押し出したというか、それに忠実にやろうと思って考えたのがフリークライミングだと思うんですよね。
実際、僕も自分でやってみて面白いし、これが登ることだなっていうのがすごくよくわかる。あと登れなかったら、今まで人間がやってきたように、その対象を加工しちゃうんじゃなくて、梯子をかけちゃうとか、穴を開けちゃうとかっていうんじゃなくて、一回おうちに戻ってというか、一回その岩から降りて自分を鍛えるんです。またそれにチャレンジするっていう、フェアネスの精神みたいなものもある。
岩を加工しないんで、岩は原始のまま、そこにずっとあるわけですよ。だから100回目にチャレンジした人も、最初にチャレンジした人と同じように、その岩と向き合うことができる。簡単に言うと持続可能なんですよね。

人間っていうか、我々は結構、自然環境を都合のいいようにいじってしまって、持続可能ではない世界をたくさん生んでしまったというか、(自然を)壊してしまったんですね。フリークライミングはそうではなくて、できるだけ自分たちの都合のいいようにいじらずにそのまんまの状態にして、だからこそ、ずっとこれから何年も何年も、最初に触った人と同じような喜びを、2回目でも100回目でも1000回目でも感じることができるっていう意味で持続可能なんですよ。
そういう意味でフリークライミングってすごく面白いというか、これから地球を対象に遊ぶ場合の、我々のすごく理想的なやり方だと思うんです。僕は日本の山を登って育ってきたんで、日本の山でフリークライミング的なことができてるのかって考えた時に、できてないな~と思って・・・。
今から日本にできちゃった道とかロープウェイとか、壊してもしょうがないんで、そういうものをできるだけ避けて、フリークライミングと同じように、過剰に便利な道具は使わないってことを課して、そういう条件で山に登ってみたらフリークライミング的にやっぱり面白いんですよ。
で、やったのがサバイバル登山で、名前は営業もあって、目を引くような、耳にちょっとなんなの? って、みんなが思うようなものを敢えてつけたっていう感じですね」
(編集部注 :初めてのサバイバル登山は、南アルプスの北に位置する「仙丈ヶ岳<せんじょうがたけ>」だったそうです。この時、持って行った道具はタープと薄い生地の寝袋など、食料はコメなどの穀類を少しと塩だけ。あとは現地調達にチャレンジしたそうですが、ご本人いわく、食べられる山菜やキノコがわからない、釣りが下手でイワナも釣れない。寒くて腹は減っていたけれど、面白くて清々しい気持ちだった。山を降りたあとに登山として美しいと思ったそうです。
その後、食料の現地調達に向けて、釣りの練習のほか、山菜などの知識を身に付けるために図鑑を見たり、友人に教えてもらったりと、スキルを磨いたとのことです)

肉も現地調達〜山の見方に変化
※食料は基本的には現地調達ということで、釣りに加え、その後、狩猟が加わりました。そのあたりの思いをお話しいただきました。
「食料って我々普通に生活していると、食料品店で買うのが当たり前ですけど、よくよくサバイバル登山をしてみると、本来の食料は自然環境から自分の手で獲ってくるものなんですよね。みんな、そうやってずっと何万年も生きてきて、最近は買うものになりましたけど・・・でもやってみると、そういうもんだなと思っているのに肉に関しては買ってんですよね・・・自分も買っていた。
サバイバル登山を通して、魚を釣って山菜を採ってキノコを採ってみたいなことをやっているけど、肉に関してはまだ買っているな~って・・・。肉もちゃんと自分で調達してみたいなと思って、一回登山はちょっと横に置いといて、狩猟だけをする2シーズンぐらいがあって、獲れるようになった時に、シカやイノシシを食料に、もしかしたら冬もサバイバル登山できるかもしれないって思って、思っちゃうとね、気がついちゃうとやらないといられないってわけじゃないですけど(笑)、気が付いちゃったんでやってみたのが、冬のシカを食料にしたサバイバル登山です」
●猟銃を持ってってことですよね?
「そうです。狩猟を始めた時は冬のサバイバル登山の意識っていうか、そういう発想は全くなくて、とにかく肉をちゃんと自分で調達して、その時、何を自分が感じるのかを知りたいなと思ってやっていたんですけど、獲れるようになっていく過程で、獲れるようになっていったんで、これが食料になるって気がついてしまった。めんどくさいぞ! と思ったんですけど(笑)。やってみると、やっぱりひとりでやると効率があんまりよくない。鉄砲は重いし、シカを獲ると荷物が一気に増えるし、そういう意味ではひとりでは効率がよくないですね」
●仕留めた獲物はその場で解体するんですか?
「そうですね。それしかないんで・・・」
●そうですよね〜。
「その場で解体して持ち運ぶとか、できるだけその場で食うわけです。でも20〜30キロの肉が手に入るわけで、それを全部食うことなんてできないですし、運ぶこともできないんで、悪いけど森に返す、みんなで食べてください。実際みんなで食べてくださいっていう状態になるんですけど、あっという間に鳥とか獣とかに食べられちゃう・・・」
●狩猟を始めて、山の見方は変わりましたか?
「変わりますね。狩猟もサバイバル登山もそうですけど、やっぱり普通の登山って結局、道を歩く。岩登りとかでも、ある程度ルートが決まっていて、そのラインをたどるみたいなところがあるんですけど、食料とか燃料とかを現地で、山の中で調達しようと思ったら、もちろん山をよく見なきゃいけないですね。
登山道を歩いて線上で山と接していたのが、獲物を探すとか獲るとかっていうことで、それが広がっていく。面とまではいかないんですけど、かなり幅を持って広がっていく。実際にそこに生えていたり、そこに棲んでいたりするものを見つけて獲らなきゃいけないんで、よく見るようになりますよね。幅広くよく見るようになる」
(編集部注:服部さんは大学時代の縦走に始まり、エベレストよりも難しい山と言われるK2の登頂のほか、岩登り、沢登り、山スキーなど、いろんなことに挑戦してきました。その理由は、なんでもできたほうがかっこいいし、登山家として、オールラウンダーでありたいという気持ちがあったからだそうです)
自分で考えて超えていく
※先鋭的な登山家のかたは、人がたどったことがないルートを踏破するとか、まだ誰もやってない登り方で頂上に立つとか、「登山史上、初めて」に挑むことがありますよね。なぜ「登山史上、初」にこだわるのでしょうか?
「面白いからですね! っていうのは、やっぱり誰もやってないから、そこは自分で工夫しなきゃいけないわけですよ。何が起こるかわからないですし、どういうふうになっているかも実際に行ってみないとわからないわけなんで・・・。
実際に行って、ぱっと見て、あっここが難しいとか、ここはどうやって登るんだろうみたいな、わかんないところを自分で考えて工夫して、超えていくっていうのは、ものすごくクリエイティヴなことなんですよ。だから未知っていうものはやっぱり、そういうことにチャレンジしたい人にとっては魅力のあることですけどね」
●ワクワクするんですね~。
「でも今はもうそういう未知の部分もなくなってきてしまったんで、そういう志はもう絶滅危惧種というか・・・。さっき言ったフリークライミングはそういう意味では、最初の人と2番目の人も3番目も100番目の人も、最初の人と同じような気持ちを楽しめるようなシステムにはなっているんですけどね。
情報をフリークライマーたちは(自分の中に)入れないんですよ。っていうのは、やっぱり登り方がわかっていたら、あんまり面白くないんで・・・。自分で岩に取りついて、登り方を考えながら登るのが面白いんで、敢えて人が登った登り方を調べたりしないし、登った人たちもそういうことを敢えて言わないんです。
それはその人たちの喜びを奪うことになっちゃうんで、これから登山もそういう方向にいってもいいんじゃないかなと思いますけどね。僕なんかは敢えてもう調べない。今『ヤマレコ』(*)とかでいくらでも調べられるじゃないですか。調べることもあるんですけど、敢えて調べないことによって、すごく面白いっていうか、初めてそこに行った人と同じような気持ちで登ることができる。自分もいろいろ悩んで工夫する余地があるっていう意味で、これから情報を入れないで、敢えて自分も初期衝動を楽しむのは、登山にもあってもいい考えなのかなと思いますけど・・・」 (*山のコミュニティサイト)
●でも登っている最中に怪我しちゃったとかもあると思うんです。山はやっぱり危険と隣り合わせっていう印象もあるんですが、リスク・マネジメントは常に意識されていますか?
「そうですね・・・いや、どうなんですかね? っていうか、マイナスのことを考え始めると、きりがないですよね。それは行かない理由にはならないんで・・・もともと登山者とか我々みたいなタイプの人間はおそらくですけど、僕はそうなんですけど、できないとか、やめる理由を探し出したら、いくらでもあるんで、それはもう考えないですよね。
それよりもどうすれば、自分がやりたいことをできるか、どうすれば、自分の登りたい山に登れるか、どうすれば、自分が憧れているルートを越えられるかっていう方向から、ってわけじゃないですけど、そこで何があるのかっていうことはもちろん予想するわけです。その予想をどうすれば、自分の能力で超えられるかっていう方向でしか考えないんで・・・。
ベクトルが常に上に向いているっていうか、それで突っ込んで怪我とかしたりしたらしょうがないんで、もちろんリスク・マネジメントは考えるんですけどでも、それがやめる理由にはならないっていう意味で、“危ないじゃん”って言われると、“うん、危ないよ”って、危ないから考えて、安全を考えて登ります! っていう感じですかね」
100年前の生活!?
※服部さんは横浜の郊外にあるご自宅のほかに、狩猟でよく行くエリアに古民家を手に入れ、2020年から二拠点生活をされています。横浜のご自宅でも自給自足に近い暮らしをされているとのことなんですが、それでは物足りなくて、古民家暮らしを始めたそうです。そのあたりの思いを語っていただきました。
「サバイバル登山って当たり前だけど、お金を使わないんですよね。食料は現地調達、水は流れているし、空気はもちろんタダだし、寝る場所だって別にキャンプ場じゃないんで勝手に寝るわけです。燃料はもちろんタダで、それをやっていると本来生きるのにお金はかかんないじゃんっていう・・・。で、そっちのほうが面白いし、まっとうというか、もともとはこういうことが生きるってことだよな・・・みたいな感じで思っていたので、それを自分の実生活でもやったら楽しいかなというふうに思って・・・。
横浜の家でもストーブは薪ストーブだけ、ニワトリを飼ってっていうことをやってみたんですけど、実際面白い面もある、っていうか面白いので、のちのち狩猟の基地が別に欲しいなと思っていて・・・。

それまでは電車とバスで猟場に行って、獲ったら電車とバスで帰ってきていたんですよ。荷物がすごく重くて、猟場に解体場みたいな拠点があったら、いろいろ楽だなと思っていたところ、山の廃村の中に古民家みたいなというか、完全な廃屋ですけど、まだギリギリ住めるだろうなって家がふたつ残っていて、たまたま知り合いができて、そのうちのひとつを譲ってもらえることになったんですね」
●ずっと誰も住んでなかった家を住めるような状態にするのは、なかなか大変だったんじゃないですか?
「まあ、掃除だけですね。あと水を引くこと。もともと田舎暮らしにちょっと憧れがあって、登山なんてやっているから、そういうのはあったんですけども、実際に廃屋みたいのを手に入れて、現場に寝泊まりしながら掃除をしていて、単なる田舎暮らしを求めていたんではないってことに気がついて・・・まさにその古民家を100年前のまんま使う生活が、自分の力で生きることに近いってことに古民家を見て気がつかされたっていう、こっちを求めていたんだ! って。
だから土間は土間として使う。囲炉裏は囲炉裏として使う。まあ竈(かまど)ですけど、竈は竈として使う。水は水船(*)から引いてくる。これは塩ビパイプ使ってやっているんで現代的なんですけども、あとは本当に昔のまんまにするほうが・・・。 (*飲み水をためておく大きな桶というか箱のようなもの)
100年前に建った家なんで、100年前の生活に適したようにできているんですよね。それが僕の求める自分の力の割合が多い生活なんで・・・。だから古民家と言っても現代風の別荘みたいな感じにするんではなくて、単に掃除して昔の状況、状態を再生すればいいので、掃除は大変でしたけど、特にリフォームとかそういうのはほとんどしてないんで、そんなに大変ではないと・・・」
●古民家暮らしもサバイバル登山の一環っていう感じですね?
「そうですね。登山の一環というか、僕のあり方というか、世界の向き合い方の延長線上に生まれてきたっていう感じですかね」
(編集部注:1年の半分くらいを古民家で過ごしている服部さん、年に数回、ご家族が泊まりに来るとのことですが、普段、生活に必要なこと、例えば薪割りや火を起こしての食事作りなどは全部ひとりでやるので、清々しいけれど、面倒臭いとおっしゃっていましたよ。畑もやっていて、それは面白いとのことでした)
サバイバル登山家の25年後!?
●サバイバル登山を始めて、今年で25年ぐらいになりますかね?
「そうですね。29歳の時に始めたんで、25年ぐらいですね」
●どうですか、サバイバル登山というスタイルの山登りは円熟してきましたか?
「う~ん、サバイバル登山って言っても、やっぱり行ったことないところに行きたいんですよ。もちろん何度も何度も同じところに行っているんですけど、行ったことないエリアがなくなっちゃったのが寂しいっていうのかな・・・」
●ここ数年は愛犬との山旅もあったりしましたが・・・?
「そうです! 犬は面白いっすね」
●山登りのやり方もちょっと変化してきているんですね。
「うん、変化しています。やっぱり、自分の肉体が歳をとってきて、動かなくはなってないですけど、若い時みたいにできることが増えていかないですよね。できることが増えていかないとリスクをかけられないっていうか、できることが増えていかないから新しいことができないんで、その新鮮さみたいなものはないんですよね。
だから自分の肉体にはもう新鮮さがない。そうなると、あんまりいいことかどうかわかんないですけど、獲物とかその世界に新鮮さを求めてしまって・・・獲物は同じことはほとんどないんで、すごくいつでも新鮮です。犬もやっぱり、ちょっと想像つかないんで面白い、いろんなことを教えてもらいました。新鮮なものを見せてもらいましたね」
●誰でも1年にひとつ歳を重ねますけれども、サバイバル登山家 「服部文祥」の、例えば25年後、80歳の時にはこうなっていたいとかありますか?
「いやぁ~死んでいるかもしれないけど、自然環境の近くで活動したり、特に獲物の相手をしていると遠い未来、遠い未来って言っても、2ヶ月ぐらい、まあ1週間でもそうですね。あんまり考えても意味ないから・・・。
徒歩旅行でもそうですね。20キロ以上先のことを考えても、あんまり意味がないんですよね。雨が降るかもしれないじゃないですか。何か別のことが起こるかもしれないんで、だからその場その場で生きていく。いわゆる、狩猟採集民族みたいに半径10キロとか、時間的には1日2日ぐらいのことしか考えなくなるっていうか、考えてもしょうがない、何が起こるかわからないんで・・・。
遠い未来のことを考えると怖くなるっていうか、気分が悪くなるっていうか・・・それまでに超えなきゃいけないものをイメージしちゃうっていうか・・・でも、元気な爺さんで、畑とか狩猟はもう続けてないかもしれないですけど、自分の力でできるだけ、自分の力で生きていたらいいなとは思いますけどね」
☆この他の服部文祥さんのトークもご覧ください。
INFORMATION
山岳雑誌『岳人』に連載していた人気コラムを中心にまとめた本。第一章の「ケモノを狩る」から第二章の「山に登る」、そして第五章の「現代に生きる」まで5つの章に選りすぐりのエッセイが載っています。導入部の「ちょっと長いはじめに」には、服部さんの生い立ちや登山の半生が綴られていて、これも興味深いですよ。物事の本質や生き方、社会のあり方などを問いかけるようなエッセイ集をぜひ読んでください。
モンベル・ブックスから絶賛発売中。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎モンベル・ブックス:https://webshop.montbell.jp/goods/disp.php?product_id=1991015
2024/12/22 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、「高校地理お助け部」
略して「地理おた部」のメンバーとして活動されている現役の高校の先生「四倉武士(よつくら・たけし)」さんです。
「地理おた部」は「ケッペンちゃん」という、地理を題材にした漫画をオフィシャルブログで展開しているので、ご存知のかたもいらっしゃるかも知れません。
そんな「地理おた部」名義で先頃、新しい本『自然のふしぎを解明! 超入門「地理」ペディア』を出されたということで、 この番組でご紹介することになりました。
きょうは「地理おた部」を代表して四倉さんにどんなメンバーが集まっているのか、そして現役の先生として地理を教える醍醐味のほか、『超入門「地理」ペディア』から、日本の気候的な特徴や地球規模の変動についてうかがいます。
☆イラストレーション:ちまちり、協力:地理おた部/ページ画像・協力:ベレ出版

代表作は「ケッペンちゃん」!
※まずは、気になる「地理おた部」について。どんなことがきっかけで、「地理おた部」が始まったのか、そして具体的にどんな活動をしているのか、お話しいただきました。
「私は本当は専門が歴史関係なんですよ。ただ、高校の地理の先生、社会の先生って日本史、世界史、地理で採用されるので、採用されるまでに地理に触れ合うことが多くて、そのまま地理のほうに自分の進路を変えて、地理を専門にしました。
その際に自分の中で難しいなとか、わかりにくいなっていうところを教材化して、これが本当に合っているのか、ちょっと自信がなかったので、それをインターネットで公開して、いろんな先生に見てもらおうというのがきっかけで始まりました」
●「地理おた部」は、いわゆるサークルみたいな感じなんですか?
「そうですね。私ができないことをできる人たちに・・・私は絵が描けないので、絵を描ける人だとか、私よりも知識がある人にいろいろ協力してもらって作っています」
●メンバーは何名ぐらいいらっしゃるんですか?
「今は私を含めて4人ですね」
●どんなかたがいらっしゃるんでしょうか?
「イラストを担当しているのが、“ちまちり”さんっていうかたで、うちの代表作である『ケッペンちゃん』の漫画を描いています。今回の本の挿絵もすべて彼女が描いています。
あとは、私よりも圧倒的に知識の宝庫である“瀧浪(一誠)先生”っていうかたがいらっしゃいます。1冊目の『ゼロから学びなおす 知らないことだらけの日本地理』っていう本があるんですけど、それは瀧波先生に大変協力していただいて、書いていただきました。
あと、地理をネタにしたお笑い芸人トフィー、たぶん日本にひとりしかいないと思います。元々高校の先生だったんですけど、そこから松竹のお笑い芸人になりまして、今も頑張っているかた・・・多種多様な人が地理おた部のメンバーです」
●ほんと多種多様ですね! 職業もみなさん違いますけど、どうやって知り合ったんですか?
「X、旧Twitterですね。私が教材を発信し、そこから親交があって、いろいろやり取りしていくうちに、この人と一緒だとなんかもっと面白いことができるなっていうことで、私が声をかけて今の形になっています」

●「地理おた部」の活動テーマとか、モットーみたいなものはあるんですか?
「とにかく授業は楽しく、地理を楽しく、わかりにくいことをわかりやすくをモットーにしています。
代表作である『ケッペンちゃん』は、『はたらく細胞』がきっかけになっていて、あれを見て”あ〜なんかこういう漫画を作りたいな”と思って、読んでいるだけで勉強になる、楽しいし面白いし・・・そういう授業で使えるような楽しくてわかりやすい教材を作りたいをモットーに活動しています」
●「地理おた部」のブログでも展開されているケッペンちゃんは、漫画でわかりやすく高校地理を解説していますけれども、ネタとかってどなたが考えるんですか?
「これは全部、私が考えています」
(編集部注:四倉さんによると、地理が「地理総合」という科目になり、選択科目から必須になったため、生徒全員が学ぶことになったそうです。そのため、地理の先生が足りなくなり、専門外の先生も教えることになったとのこと。
このお話をお聞きして、現場の先生は大変だな〜と思ったんですけど、だからこそ、教材になるような地理ネタを発信している「地理おた部」の存在は大きいな〜と思いました)
地理は今を理解できる教科
●今回「地理おた部」として出された新しい本『自然のふしぎを解明! 超入門「地理」ペディア』を拝見しました! 今の地理って世界の国々とか地域の特徴だけじゃなくて、自然環境とか気候の変化、さらには世界の動きまでをも扱う、まさに今の地球を知るための科目なんだなって感じたんですけれども、幅が広すぎますよね?

「そうですね。逆に言えば、きのうやきょうあった事件をそのまま授業の頭で使えたりもするので、台風が来たよねとか・・・だからそれこそ今の世界情勢いろいろ起きているので、起きていることをそのまま授業で使えるところは、やっぱり地理の良さではありますね」
●なるほど、すべて地理につながっているっていうことですね。
「そうですね。なるべく授業の冒頭にニュースや、いろんな出来事を使って、今学んでいることは、まさに今を理解できる教科なんだよっていうことを生徒たちには言っていますね」
●この本では地形、気候、そして環境の3つのカテゴリーに分けて、全部で80のトピックが掲載されています。その中から番組でいくつかトピックをピックアップさせていただきました。
見出しを言いますので、ご説明をお願いしたいんですが・・・まずは「ハワイはいつか日本にやってくる?」という見出しがありました。年末年始をハワイで過ごされるかたもいらっしゃると思いますが、これはどういうことですか?

「要は日本にあるプレートとハワイのプレートが近くて、狭まる関係にあって、プレート同士が近づいているわけですよ。だからだんだんハワイのほうがやってきているっていう形にはなっているんですけど・・・何千万年後とかでもなく、何億年も先なので果てしないんですけども、いずれはなるよっていう話です」
●へ〜〜! いずれは南国のハワイがすぐ近くにあって、気軽に泳いだりとかできちゃうっていうことですか?
「そうですね。でも残念ながら、(日本)海溝があって、そこにハワイは沈むだろうという予測もあったりとか・・・タイムマシンがあったら見られるんですけども、なかなか見ることはできないですね(笑)」
●どれぐらいのペースで近づいてきているんですか?
「1年間に数センチなんですけど、地球の年齢を考えた時に、1年間に数センチだったとしても、何万年とあれば、何キロにもなるわけですよね。だからもう気の長い話ですね。歴史の授業とは桁違いな時間のスパンで動いているので・・・」
日本は世界一の温泉保有国
※続いて、新しい本『自然のふしぎを解明! 超入門「地理」ペディア』に載っているトピックから「温泉大国ニッポン」について。日本は世界一の温泉保有国なんですね。
「そうですね。まず温泉がある国が珍しいのかなっていうところで、火山がないとやっぱり(温泉は)発生しませんし、雨が降らないとどうしても湯の元になりませんし、さらには雨を蓄えるための地盤ですよね。固い岩盤とかがないと水が溜まりにくいので・・・だからやっぱり諸外国を見た時に温泉がある国は少ないですよね」
●ちなみに温泉の数がいちばん多いのは、どの都道府県なんですか?
「数で言うと北海道なんですよね。やっぱり面積が広いからなんですけども・・・。ただ湯の量で考えると、大分が奇跡的な地形になっているらしくて、水が溜まりやすいっていうのもあって・・・実際に大分に行くと学校とかにも、地熱発電の機械があったりするんですよ」

●え~~っ!
「学校に(行った時に)“片隅にある機械はなんですか?”って聞いてみたら“地熱発電です!”っていう・・・不思議ですよね。それぐらいやっぱり大分って恵まれているみたいですね」
●すごいですね~。数が多いのは北海道で、湯の量で言うと大分県なんですね。
「そうですね」
●では続いて、「日本は世界でいちばん雪が積もる国」っていう項目があって驚いたんですけど、ほんとなんですか?
「これは結構、意外に思われると思います」
●はい、思いました!
「雪が降るっていうことは、水蒸気が必要なんですよね。基本的に寒い地域って、そもそも水資源が凍っていたりとか意外と雪が降らなかったりするんですよね。あとは海からものすごく遠かったりとかして、だから(水資源が)凍っているっていう感じなんですよ」
●なるほど~。
「日本って雪が降るすごく奇跡的な地形をしているんですよね。周囲を暖流で囲まれていて、だから海が凍らない。その水蒸気が雲となって、陸地に着いた時に寒さで雪になるっていう形で、だから(本に載せた)データぐらい降っているんですよね。意外ですよね」
●日本より寒そうな国ってたくさんあるイメージがあったんですけど・・・。
「そうですね」
●でも雪が積もる国って考えると、日本が世界でいちばんになるんですね。
「そうですね。だから雪っていうのと、寒さっていうのがどこまでリンクしているかっていうのと、雪ってなんだろうって(考える)きっかけにはなるのかなとは思っています」
●カナダとか雪のイメージがありますけど・・・。
「カナダも海のほうは緯度が高いので、結構、海が凍っていたり、あとは内陸地が水資源から遠くて、そもそも雨が降らない、乾燥しちゃっているっていう地域も多かったりするので・・・」
(編集部注:本に載っている2016年のデータによると、世界の年間降雪量の第1位は青森市で792センチ、2位は札幌市、3位は富山市なんですが、4位のカナダのセントジョンズという街では、年間333センチの降雪なので、青森は倍以上の降雪量なんです。日本は雪がたくさん降る国なんですね)
赤道の「赤」の意味
※続いてのトピック、「赤道の『赤』の意味とは?」、これ、考えたことなかったです。この「赤」の意味って何なんでしょう?

「よく生徒たちも、“赤”って聞くと、なんかあったかいイメージがあったりすると言ってますけど、そもそも古代中国の天文学で使われていたんですよね。太陽が真上を通る地球上の線のことを“赤道”って言っていただけで、だから実は英語にすると“equator line”とか”当分するライン“、だから”red line”って言わないんですよね」
●へぇ~~!
「だから英語にすると意味がわかるっていうか、だからちょうど真ん中だよ! 当分する線だよっていう・・・」
●赤道っていう意味の国家もあるんですよね?
「そうですね。エクアドルがまさにそれで、赤道が通っている・・・だから決して赤っていう意味ではないんですね」
●おしまいは「エルニーニョの意味は”神の子”」というトピックがありました。エルニーニ現象という言葉をよくニュースでも聞きますけれども、改めて用語の由来も含めてどんな現象なのか教えていただけますか?
「エルニーニョっていうのは“神の子イエス・キリスト”っていう意味で、エルニーニョっていうのは、スペイン語で“男の子”を意味するんですよね。
ちょうどクリスマスの時期になると、ペルー沖の海面の温度が上昇して、いつもとは違う魚が大量に獲れて、これは神様の恵みだっていうことで、“エルニーニョ”っていう名前が付いているわけです」

●海面の温度って、なぜ上がるんですか?
「これはちょっと難しいんですけど、南アメリカの近くにはペルー海流っていう南極から来ている寒流、冷た~い水が流れているんですよ。これが貿易風が吹くと、どんどん太平洋のほうに流れていって、(海水を)冷たくしてくれるんですよ。
ところが、この貿易風が弱くなるとどうなるかっていう話なんですよ。弱くなると太平洋に注ぐ量が減っちゃうわけですよね。そのままペルー海流が北上してしまうので、結果として冷たい、ペルー海流の水が太平洋に入らない、温度が上がっちゃう、結果として今までとは違う魚が獲れるっていうことになるわけですね」
●で、海面温度が上がるってことなんですね。
「そうですね。冷たい水が入ってこないので上がっちゃうんですね」
(編集部注:ちなみに、ペルー沖の海面温度が下がることを「ラニーニャ現象」と呼びますが、この「ラニーニャ」は女の子という意味だそうですよ)
今見ている光景に名前が付く!?
※改めて思ったんですけど、地理を学ぶと、普段見ている景色が違って見えそうですね?
「そうですね。授業で習ったことが(学校の)帰りの道で見えるようになってほしいなって思っています。自然堤防とか微高地になっているとかを聞いた時に、家路で、”あれ? 自然堤防じゃない?”とか・・・。
浜堤(ひんてい)っていうのがあるんですけど、海の近くにちょっと高くなっているところがあるんです。海岸沿いにたまに高くなっているところ・・・それを浜堤って言うんですけど・・・。“あっ! これが浜堤か!”みたいな感じで、地理を学ぶことによって、今見ている光景に名前が付いて見えるようになるのは、地理の楽しみでもあるかなとは思っています」
●現役の高校の地理を教える先生として、どんなことを大切にされていますか?
「いちばんは、学ぶってものすごく楽しいことなんだっていうところですね。地理って意外と知らなかったことをものすごく学べる教科ですので、学んだことをそのまま現実世界に活かしたりとか、ニュースが少しでもわかるようになったりだとか・・・。
遠足とか修学旅行に行った時に、“あっ! 先生、これ、あれでしょ?”って生徒が言えた瞬間は、教えていてよかったと思いますね。
ほかにも卒業していった子たちがgoogleアースを使って家を探してみたりだとか、仕事で役立てたりだとか、何か自分たちのスキルアップになる教科だなって思っているので、楽しくそして自分を高める教科だと思って、いつも教えています」

●では最後に「地理おた部」としての今後の目標ですとか、新たに取り組みたいことがあれば教えてください。
「はい、やりたいことはいっぱいあって、今の目先はやっぱりケッペンちゃんをどうにかこうにかしてアニメにできないかな~だとか、V-tuber化してもっとわかりやすく、もしくはAIを使って、ケッペンちゃんが地理を教えるコンテンツを作るだとか・・・。
今、地理が必須化されて、先生たちのほうが困っているんですよ。専門じゃない先生たちが教えなきゃいけない。専門じゃない先生が無理やり教えたことを聞いた生徒たちはもっと可哀そうなんですよね。
なので、そういう人たちみんな、先生も生徒も助けられるようなコンテンツ、この動画を見たら、とにかくわかる!とか、わかんなかったらこの漫画を読む!とか、“地理って楽しいよね!”“面白いよね! わかりやすい!”っていうような教材をこれからもどんどん作っていこうと思っています」
INFORMATION
「地理おた部」の新しい本をぜひチェックしてください。「地形」「気候」「環境」の3つのカテゴリーにわけて、全部で80のトピックをそれぞれ見開き2ページで解説。気になる見出しから読めますし、イラストや写真がたくさん載っているので、とてもわかりやすいですよ。地理や自然の基本が学べる入門書、おすすめです。ベレ出版から絶賛発売中。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎ベレ出版:https://www.beret.co.jp/book/47704
「地理おた部」のオフィシャルブログもぜひ見てください。4コマ漫画「ケッペンちゃん」もチェックしてくださいね。
2024/12/15 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、タレントの「松本明子」さんです。
松本さんは、香川県高松市出身。1982年にテレビ番組「スター誕生!」チャンピオン大会に合格し、それを機に歌手デビュー。その後はバラエティ番組などで人気者となり、バラドルの元祖としても知られていますよね。
そんな松本さんの趣味が山登り。現在アウトドア雑誌に連載を持つ、そんな一面も注目されています。
松本さんが山登りを始めたのは、ある舞台に出演されたときに膝を痛めてしまい、それから運動をしなくなり、どうしたものかと悩んでいたそうです。そんなとき、ママ友や同級生から、運動しないのは健康にもよくないので節約家の松本さんにぴったりの、お金をかけない遊びとして、ハイキングや山登りを勧められたことがきっかけだったそうです。松本さんのYouTubeチャンネルを拝見すると、冬山に行くほど、のめり込んでいらっしゃいます。
きょうはそんな松本さんに趣味の山登り、それがきっかけで始めた軽自動車のキャンピングカー・レンタカー事業のほか、芸能界でも節約家として知られる松本さんに台所の大掃除に大活躍する「あるもの」の活用法についてもうかがいます。
☆写真協力:ワタナベエンターテインメント、オフィスアムズ

心に決めた瞬間!?
※初めての山登りは、どこに行かれたんですか?
「初めて登ったのは2019年の11月ぐらいだったと思います。いちばん最初は神奈川県にある大山(おおやま)っていう山を選びました。電車に乗って登山口までバスに乗り継いで行って登ったんですね。ケーブルカーはあるんですが、早朝から登ったので、まだケーブルカーも動いていない時間、5時半とか6時ぐらいから登ったと思います」
●標高1200メートルを超える山ですよね?
「結構高かったです。お仕事で新幹線に乗るときに、いつも車窓から大山が見えていて、大きくてすごく素晴らしい山だな〜と思って、いつか登れたらいいな〜なんて思っていたんです。いつも新幹線で見ていたので、大山を選んで登ったんですけど、結構石段もハードで・・・で、中腹に神社があるんですね。その神社の脇の道からまた鬼の石段がずーっと続いていて、そこから山道に入っていくんですね」
●膝は大丈夫だったんですか?
「膝をかばいながら、恐る恐る登ったんですけど、結構ハードでしたね。その時に偶然、知っていらっしゃるかたも多いと思うんですけど、百名山を走って登っているランナーのかたがいて・・・田中陽希さんって言ったかな・・・? そのかたがカメラマンのかたとふたりだけなんですけど、颯爽と走って登って動画を撮っていたんです。それをYouTubeとかにあげていらっしゃるかたで、何回も日本中の百名山を制覇しているかたなんですよ。
そのかたがカモシカのように、私の横を颯爽と駆け上がっていくっていう、そのすれ違いのシーンもあったんです。私はもう必死で登ったんですが、やっとの思いで山頂に出た時は、達成感とその絶景を見た感動とで、山登りっていいな、これを本当に趣味にして自分のペースでいいから、少しずつ登れたらいいなっていうのを心に決めた瞬間でしたね」
(編集部注:松本さんは仕事柄、先の予定が立てられないので、山に行くのはいつも急だそうです。翌日が休みだとわかると、天気予報とにらめっこしつつ、山のガイドブックを見ながら、どこの山に行こうか、体力や体調と相談しながら、初心者や女性でも登りやすい、おもに東京近郊、そして、ちょっと足を伸ばして甲府や山梨方面の低山を選ぶことが多いそうです。頂上から富士山が見えたら最高ですよね、とおっしゃっていました)

五感が磨かれた運命の山
※その後、登った山の中で、強く印象に残っている運命的な山があったそうですよ。
「これね、唐松岳(からまつだけ)という山なんですけれども、標高約2700メートル、もう自分の中では本格的な登山。早朝5時台から登ったんですけど、最初、小雨が降っていて、うわ〜これ、先が思いやられるな、せっかく来たのに雨なのかと思って、がっかりきていたんです。
まずはリフトに乗るんですね。ふたり掛けのスキー場にあるようなリフト、それにふたつ乗るんです。一回乗って、もう一回ふたり乗りのリフトに乗り換えていくんです。でもずーっとリフトに乗っている間、小雨なんですよ。寒くて、うわ〜これ、ちょっと天気選び、失敗しちゃったなと思って後悔していたんですけれども、標高2700メートルですから、どんどん登っていくうちに雲を突き抜けちゃうんですよ。
そうすると、右のほうの眼下には八方池っていう、とても素晴らしい池があって、白馬岳が鏡のように映るんですよ。そういうのを見下ろしながら、ずーっと登っていって、もう雲の上まで行きます! そうすると、標高が高くなると樹木が生えてこないんですよね、高すぎて・・・。草木があったのがだんだん見えなくなってきて、笹になっていくんですよ、植物が・・・。その笹を通り越すともう岩なんです。植物は生えない、高すぎて・・・。
で、カンカン照りで、暑くて暑くて、9月くらいに登ったんですけれども、真夏で、サンサンと太陽を浴びているのに雪渓が見えるんです。上のほうの山にはまだまだ雪が残っているんですよね。なんか不思議な光景でしたけれども・・・。
どんどん登って、山頂にやっとの思いで着いた時は、迫り来る周りのアルプスの景色、壮大な景色で濃い緑色の山がこちらに迫ってくるような感じがして、それはそれは感動的、達成感もあるし絶景の感動もあるし・・・。山に登って壮大な景色を見ていると、なんかきのうまで気にしていたこと、”私の悩みごとなんかちっぽけなんだな、ホコリみたいなもんだ、私の悩みなんて”っていうふうな、大らかな気持ちになれるというか・・・。
あと、時間に追われて暮らしている都会の生活の中で、忘れかけていた五感っていうんですかね、土に触れた触感とか、山の匂いとか、山の音とか、小鳥たちのさえずりとか、雲の流れを見ていて、視界がすごく透き通って晴れやかに見えたりとか、五感が磨かれるというか、そういうのも感じましたね。すごくよかったです〜」
「もったいない」から始まったレンタカー事業!?

※お話にあった、北アルプスの唐松岳は東京から直ではなく、前乗りして泊まってから向かったそうです。実は、この時の経験がレンタカー事業につながったそうですよ。
「やはり前の日に松本市に入ってビジネスホテルをとって、宿泊代もかかるし、松本市までの列車代もかかるんですよね。で、結局、登山口まで行くのに、バスもないので、前の日から駅前でレンタカーを借りて、結構お金がかさばっちゃって・・・」
●確かにそうですよね〜。
「お金のかからないレジャーということで選んだのに、長野県の標高が高い山に登ろうとすると、結構お小遣いがかかっちゃうなと思って・・・これはやっぱり私の信条ではもったいない! なんとか交通費と宿泊費を一緒くたにできるような、なんか面白いことはないかな〜と思ってずーっと考えていたんですね。
で、よし、これは車中泊ができる、女性でも運転しやすい、初心者でも私でも運転できる、小回りのきく、大きいキャンピングカーじゃなくって、小ぶりのかわいい軽自動車で車中泊ができるような車があったら、一石二鳥でいいな〜と思ってずーっと探していたんです。
そしたら出会いがありまして、よし、これは自分で乗ろう、いやいや自分で乗るだけではもったいないな、これは山ガールの女の子たちにも乗ってもらえたら、喜ばれるんじゃないかと思って、レンタカーを始めよう! っていう考えがどんどん転換されちゃって、それでひらめいてしまって、すぐ事務所の社長に直談判に行って、こういうことで私の夢なんです、事業を始めさせていただけないでしょうか、ということでお願いをしました。
で、ひとりキャンパーで有名な芸人のヒロシさんにも電話をして、”こういうふうに考えているんだけど、どう思う?”って聞いて、”いいじゃないですか〜!”って言われたんですね。で、やっぱり日本の山となると、山梨の甲府の駅前か、長野の松本の駅前でレンタカー店を出したほうがいいのかな〜って思って、考えを言ったんですね。そしたら、”ぜひとも、経費はかかるかもしれないけれども、絶対に都内でやってください”というふうにヒロシさんから背中を押されて・・・。
(自動車の)免許は持っているんだけれども、山登りに行きたいんだけれども、車を持てない、駐車場代を払うのがもったいないっていう大学生とか、若いカップル、若い夫婦のためにも、そういうレジャーを気軽に楽しんでいただけるように都内でやってください! って背中を押されて、よし、じゃあ近所でやろうっていう考えになっちゃったんですよね〜」
(編集部注:そんな経緯で始めた軽キャンピングカーのレンタカー事業、レンタカー店「オフィスアムズ」のオープンは2021年3月。開業するまでは、運輸局などの許認可を取得したり、レンタカー事業を行なっている会社に、フランチャイズ化のお願いに行ったりと、準備におよそ半年かかったそうです。

「オフィスアムズ」が保有している軽キャンピングカーは、いずれも専門の会社がカスタマイズした、オシャレで可愛い軽キャンばかり。アメリカンスクールバスをイメージした、イエローやミントグリーンにペイントされた軽キャンのほか、荷台に幌(ほろ)タイプのテントがある軽トラなど、どれも魅力的です。ぜひオフィシャルサイトでチェックしてみてください。
☆オフィスアムズ:https://officeams.com
車種によっては女性のために、女優ミラーライト付きのドレッサーやミニテーブルを装備しているそうですよ。また、レンタル・グッズも充実していて、車中泊用のセットのほか、テントや寝袋、ランタン、焚き火セット、さらには照明や充電用のバッテリーなども完備しています。
運営は松本さんと、もうひとり、長年専属ドライヴァーを務めている方と一緒にやっていて、松本さんも芸能界のお仕事がないときはお店にいて、車の掃除・点検、電話の応対などを行なっているそうです)

※開業して3年半が経ち、お客様の傾向も変わってきているそうですよ。
「今年はお陰様で、インバウンド効果で外国人のお客様が結構多く利用されています。英語のホームページもありますので、それを見て海外からネット予約をしてくださるんですよ。松本明子なんて全く知らないかたが、外国人のかたがいらしてくれています。
日本人のかたと外国人のお客さんと全然違うのは、日本人のかたって働き者なんですよ。やっぱり仕事が第一優先で、仕事の合間にレジャーを楽しむっていうことで、1泊とか2泊とかされるかたが主流なんですけれども、外国人のお客様はドカーンと2週間バカンスとか、長く日本でレジャーを楽しむんだっていうことで、1ヶ月間、車を借りま~す! みたいなお客様がいます。“布団を貸してください!”って、車中泊しながら日本全国、京都に行ったり富士山を見たり、九州に行ったりとか北海道に行ったりとかっていうお客様が増えて、ありがたいな~と思っていますね」
もったいない精神〜油汚れにティーパック!?
●ではここからは、松本さんが去年出された本『この道40年 あるもので工夫する 松本流ケチ道生活』から、年末の大掃除に向けてヒントになるお話をうかがっていきたいと思います。
「ありがとうございます」

●松本さんは芸能界で倹約家としても知られていますけれども・・・。
「そうなんです(笑)。私が香川県の出身で、雨が降らない県なんですよ。県民性というか教育というか、とにかく小さい頃から家族とか学校の先生に“節水して! お水を使うのはもったいないから!”っていうことで、水とかペーパーとかは絶対捨てちゃいけない、大切に使うんだっていうのをずーっと親から言われ続けて、学校の先生からも言われ続けて・・・香川県のみなさん、みんな節約家というか倹約家というか、そういうもったいない精神の塊ですね」
●小さい頃から根本にもったいない精神があったんですね~。
「はい! そうなんです」
●この本を読ませていただいて、節約のために仕方なくっていうよりは楽しみながら、いろいろ工夫されているんだなっていうのがすごく伝わってきました。
「ありがとうございます、楽しんでやっています!」
●アイデアを出すのも、すごく楽しまれているんだなと感じたんですけれども、実際にお掃除のヒントになるお話をうかがっていきたいと思います。
まずは出がらしのティーパックが油汚れの救世主、なんですね?
「そうなんですよ!」
●使い終わったティーパックを取っておくんですね?
「そうなんです。使い終わったティーパックを捨てずに取っておくんです。いつも流し台のところにもたくさんストックがあるんですね。私は割とコーヒー派なんですけど、主人とか息子は紅茶党なんですね。なので、毎朝ミルクティーを飲むんですけれども、その出がらしのティーパックを捨てずに取っておく。そうすると炒め物をしたフライパンの油汚れとか食器とか、いきなり洗剤をつけたスポンジで洗うと、スポンジがヌルヌル、ヌメヌメになっちゃって長く使えないんですよね。
もうそれが嫌で嫌で、許せなくて、なんかいいアイデアはないかと思って、新品のティッシュペーパーで油汚れを取るためにぬぐうのも、もったいないと言えばもったいなくて、なんとか捨てるものでできないかなと思って考えていたら、そうだ! 出がらしのティーパック、これでひと拭きしたらどうだろう! と思ってやったのがもう20年前ぐらいなんですけど、消えるんですよ、油が!」
●へ~~っ!
「もうね、9割がた取れます、フライパンの油汚れや食器の油汚れが・・・。なので、スポンジに洗剤をつけて洗う前に(ティーパックで)一拭いしていただけると・・・。これ、紅茶の葉の成分も油汚れを分解するっていう科学的な、理にかなった展開がちゃんと証明されていますので・・・」
●いや~捨てていました(苦笑)
「ぜひとも参考に! もう騙されたと思ってやってみてください」
●すぐに試したいと思います!
セーターをたわしに!? 日焼け止めクリームが大活躍!?
※松本さんの本には、ほかにも「着古したセーターをほどいてアクリルたわしに」というアイデアが載っていました。これは何か、コツのようなものはありますか?
「これはね、高級な毛100パーセントの(お値段が)高いセーターじゃないほうがいいです。できればアクリルが何パーセントか入っている毛糸、もう着なくなった手編みのセーターなんかを全部ほどいて、カギ編みでいいです。もう適当な編み方でいいです。
それで油汚れを拭い取ると、アクリルっていう性質が油を吸収するんですって、この繊維の中に・・・。これでもうほとんど洗剤はいらないです。洗剤もいらないし、地球の環境にも優しいし、これもぜひとも、おすすめですね。アクリルたわしも適当なカギ編みをして(台所に置いて)ありますね」
●なんかカラフルですごく可愛いたわしですよね~。
「そうです、そうです! 見た目にも華やかで」
●あと、余った日焼け止めクリームは掃除アイテムにということで・・・。
「そうなんですよ!」
●日焼け止めクリームって余りますよね。
「ひと夏で使い切らないんですよね。お子さんがテーブルとか床とかにちょっと書いてしまったマジックの汚れ、それを使いきれなかった日焼け止めクリームを塗ってティッシュで拭くと、綺麗に」
●取れるんだ・・・。
「油性のマジックが取れちゃうんですよね~! あとね、ハサミの・・・ネバネバ、粘着がちょっと引っ付いちゃって、ノリのところをハサミでカットしたところに、ネバネバが付いちゃった刃の部分、あれを使い切らなかった日焼け止めクリームを塗ってティッシュで拭くと、あら不思議! 綺麗に取れます!」
●へえ~! すごいです、ほんとに!
「これ、いいですよね~。だから捨てずに、何かに利用してみていただきたいと思います」
(編集部注:ほかにも、歯ブラシだけじゃなく、歯間ブラシを隙間の掃除に再利用しているそうです。ぜひご参考に)
元気の源はレジャーから
●お金を節約する山登りから生まれた軽自動車のキャンピングカー・レンタル事業、実際、松本さんも軽キャンピングカーを使って、山登りに出かけていらっしゃるんですよね?
「はい! そうです」
●やはりキャンピングカー・ライフは楽しいですか?
「そうですね。自由ですし、キャンプの達人ではない私でも、自然に触れるというだけで、自分の心の栄養になりますし、明日また元気になれる、心に栄養をもらえるのがやっぱりアウトドアであり、山登りかなというふうに思いますね」
●どんなところに喜び感じますか?
「ほんとに適当にお弁当を持っていくんですよね、お昼ご飯とかも・・・やっぱり景色を見ながらお弁当を食べると、本当に笑顔になれるというか、体も栄養! 心も栄養! 食べて美味しい! お金もかからない! っていうことで楽しくなりますね(笑)。毎日が元気になります。私の元気の源はそういうレジャーから来ているのかもしれないですね」
●松本さんのレンタカー店「オフィスアムズ」で軽キャンを借りたいなと思ったら、どのようにしたらよろしいでしょう?
「ぜひとも、ホームページでネット予約ができます。すぐ予約もできますので、なんでも相談事があれば、言っていただきたいと思います。それに全面協力しますので・・・あと、記念写真をいつもお客様のスマホで撮っています」
●松本さんと!?
「大学生とか10代、20代は、“店員さんとこんなサービスがあるんですか(笑)”ってよく言われるんですけど、40代、50代のお客様には喜んでいただけます!」
●そうですよ~、松本さんにお会いできるなんて~。
「いえいえ~、元気にお店でスタンバっていますので、ぜひともおしゃべりをしに来てください!」
●ありがとうございます!
INFORMATION
松本さんが運営する軽キャンピングカーのレンタカー店「オフィスアムズ」の軽キャンをぜひご利用ください。オシャレで可愛い軽キャンがそろっていますよ。また、装備やレンタル・グッズも充実しています。お話にもありましたが、松本さんがお店にいるときは、記念写真を撮るサービスも行なっているとのこと。
レンタカーの利用料金など、詳しくは「オフィスアムズ」のオフィシャルサイトをご覧ください。
◎オフィスアムズ:https://officeams.com
松本さんが去年出された本には大掃除のヒントになるアイデアや、日頃の節約につながる特に主婦には役立つヒントが満載です。ぜひ読んでください。アスコムから発売中。詳しくは出版社のサイトを見てくださいね。
◎アスコム:https://www.ascom-inc.jp/books/detail/978-4-7762-1290-4.html