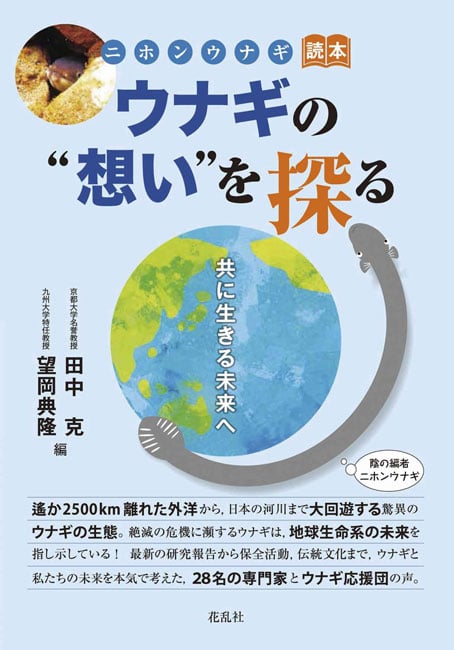2023/11/26 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. DREAMTIME / DARYL HALL
M2. WE BUILT THIS CITY / STARSHIP
M3. ADVENTURES IN THE LAND OF MUSIC / DYNASTY
M4. FIRE / BABYFACE & DES’REE
M5. 勇者 / YOASOBI
M6. CARDBOARD BOX / FLO
M7. WINTER WONDERLAND / TONY BENNETT
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2023/11/19 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、「SDGs QUEST みらい甲子園」の総合プロデューサー「水野雅弘(みずの・まさひろ)」さんです。
です。
水野さんは、持続可能な環境社会を実現するための事業などを行なう株式会社TREEの代表取締役、そしてSDGs.TVのプロデューサーでもいらっしゃいます。
SDGsはご存知の通り「SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS」の頭文字を並べたもので、日本語にすると「持続可能な開発目標」。
これからも地球で暮らしていくために、世界共通の目標を作って資源を大切にしながら経済活動をしていく、そのための約束がSDGs。2015年の国連サミットで採択され、全部で17の目標=ゴールが設定されています。
当番組では17のゴールの中から、おもに自然や環境に関連するゴールを掲げ、定期的にシリーズ企画「SDGs〜私たちの未来」をお送りしていますが、今回は特別編! 高校生が考える社会課題解決のためのSDGsアクション・アイデアコンテスト
「SDGs QUESTみらい甲子園」をクローズアップします。
☆写真協力:みらい甲子園事務局

今回から千葉県大会を開催!
※まずは「SDGs QUESTみらい甲子園」の開催趣旨について教えていただけますか。
「本当に今、時代が大変革の時を迎えています。未来が予測困難な時代なんですけれども、そうした中においても、高校生が自ら未来をちゃんと考え向き合って、特に社会課題をどう解決していくかを起点にしながら探究し、そして、できれば主体的に行動力を高めるような、そんな機会を作ろうと思って始めたのが『SDGs QUESTみらい甲子園』です」
●今年で5回目の開催ということですけれども、開催エリアが年々増えているんですよね?
「そうですね。初年度は北海道と関西から始めまして、今年は19エリア32の都道府県で開催します」
●これまでどれぐらいの高校生たちが参加しているんですか?
「延べでいくと1万人を超えています。年々増えてきまして、昨年は5000人以上、チームでいうと1228チームがエントリーしてくれました」

●今年からは千葉県大会もあるんですよね。
「そうですね。去年までは首都圏大会という形で、千葉県も対象にしていたんですけれども、やはり千葉もたくさんの学校がありますので、千葉県大会をbayfmさんと一緒にやらせていただきます」
●千葉エリアならではのアイデアがどんどん出てくるといいですよね。
「そうですね。千葉は都会でありながらも、房総半島を考えますと本当に多様な社会課題に向き合っていますから、SDGsを起点にした素晴らしいアイデアを期待しています」
●この「SDGs QUESTみらい甲子園」の参加条件を教えてください。
「参加条件は、まずはチーム制です。高校1〜2年生を中心に、今年からリーダーでなければ、3年生も参加可能です。中高一貫校であれば、チームの中に中学生が入っても大丈夫です。2名〜6名で、部活で参加する場合は最大10名までは可能としています」
(編集部注:このコンテストは、競い合うというよりも、ほかの高校の生徒たちと交流してもらうことも目的としていて、応募する生徒たちも、それを楽しみにしているそうですよ。
今回は、各エリアから選ばれた最優秀賞の19チームが全国交流会に進み、最終的にグランプリチームが選ばれることになっています。グランプリチームは、北海道美幌町にある「ユース未来の森」に招待されるそうです)
 <
<高校生の柔軟な発想を期待!
※過去の応募作から、特に印象に残っているアイデアを教えてください。
「この番組に若干合わせて、環境的な視点から申し上げると、例えば静岡は卓球、静岡だけでピンポン玉を年間2.5トン廃棄するそうなんですね。それをリサイクルしてスマホケースを作るアイデアを考案した高校生がいたりとか・・・。
あとは滋賀県から琵琶湖、やっぱり琵琶湖を綺麗な淡水にしていきたいっていうことがあって、自分たちで天ぷら油を集めて、粉せっけんにして、そこに”草津あおばな”という地元で採れる植物を入れて液体化すると、すごく綺麗な色になるんですね。それを彼らは“琵琶湖ブルー”と言っています。天然の液体洗剤を通して琵琶湖を守っていく、普及啓発にしていく、そんなチームもありました。
あともうひとつお伝えすると、たぶん千葉でもたくさんの放置林があるんですね。竹です。日本は里山が竹によって、荒廃していく世界が多いんですけれど、その竹を使ったバイオ竹炭であるとか・・・竹問題っていうのは九州のほうが多かったです」
●大人では発想できない、高校生ならではの柔軟な発想だなという感じがありますよね。
「そうですね。高校生はある意味、グローバル意識はすごく高いんですけれども、社会課題となると、行動範囲が数十キロ圏内なので、地域に対する思いがありますね。地域の課題を環境だけではなくて、差別や相対的貧困やジェンダーの問題、様々なところから高校生らしい発想とアイデアが生まれてきています」

※「SDGs QUESTみらい甲子園」の発案は水野さんなんですよね?
「そうですね。ネーミングも含めて考えました」
●どうして始めようと思われたんですか? その辺りの思いをぜひ聞かせてください。
「僕は2007年から『GREEN TV』というイギリス・メディアの日本代表になって、環境に関わる様々な発信をしてきたんですね。2015年にSDGsが国連で採択された時に、これは共通言語になっていくし、それを起点に普及させることで、無関心のかたたちと語り合える、もう行動しなくちゃいけないなと思い立ち、翌年の2016年に『SDGs.TV』という映像メディアを立ち上げたんですね。その映像メディアを視聴しているのが学校の先生が多かったんです。
その学校の先生から、高校生たちが行動できるような発表の場をぜひ作ってくれないかっていう話をいただいて、大会というか野球の・・・全国それぞれの地域の課題や、世界の課題に向き合っていこうと思って組み立てたのが『SDGs QUESTみらい甲子園』です」
●中学生でもなく大学生でもなく、高校生を対象にしたのはどうしてなんですか?
「高校生になりますと、自分の進路をとても真剣に考え始めます。そういった意味では、キャリアとは言いませんけれども、進学や就職ということを考えた時に、社会課題に向き合っていく、いわゆる最初の芽が出る・・・。
小学生中学生ですと知識的なものが多いですね。高校生になると、もうひとつは経済的な視点も入ってくる。だから大人と子供のちょうど中間になった時に、自分の進路がまだ不透明な大学生も多いんですけれど、やはり高校生の時になるべく早く自分のヒントというか、自分のやりたいことのためには、やっぱり未来を見つめることが比較的重要だと思いまして、高校生に絞りました」
(編集部注:「SDGs QUESTみらい甲子園」は、コンテストではあるんですが、実は、応募してくれた高校生には、大学入試などのポートフォリオとして活用できる参加証明書を発行。また、先生にとっては、学習プログラムとして活用できる、そんな側面もあるんです)

自分の心と大地にタネを植える
※「SDGs QUESTみらい甲子園」のオフィシャルサイトに、グランプリチームが北海道の「ユース未来の森」で木を植えている動画がありました。この「ユース未来の森」について教えていただけますか。
「これは実は今、気候危機と呼ばれている中で、気候変動に対して高校生たちが、何か未来に向けて、活動のひとつとして、森を作っていこうっていうことを昨年度から始めました。全国の高校生がなかなか全員は来られないので、地元の高校生たちと一緒に木を植えていくという形で、気候変動行動のひとつとして、みんなで森作りを始めた次第です」
●水野さんも行かれたことはありますか?
「この10月に僕も参加しまして、汗だくになって植えてきました」
●あの動画を見ていて、生徒さんたちもそうなんですけど、参加されている先生たちが、すごく生き生きとされているなっていう印象があったんですけど・・・。
「そうですよね。道内だけではなくて、今回グランプリをとった鹿児島の種子島から来た先生も、本当に汗をいっぱいかいて、楽しそうに活動していましたね。あの映像も僕が植樹しながらiPhoneで撮影した映像です」
●そうだったんですね~。みなさん、本当に楽しそうなのが印象的でした! やはり植樹体験で気づくこともいろいろあるんでしょうね
「そうですね。彼らにインタビューをすると、やっぱり木を植えることは当然初めてなんですね。林業のかたたちがこうして木を育てていく・・・植えることも大変だし、1年2年ではなくて、20年50年100年と、すごく大変な仕事なんだってことがよくわかったと、生徒たちのコメントからは聞けました」
●やっぱり人ごとではなく、自分ごとになることが大事になってきますよね。
「そうですね。植林が大切とか、間伐が大切とか、いろいろ頭で学んでも、やっぱり自ら大地に立って苗を植えるっていうのは、すごく貴重な体験ではないかなと思います。 ほとんどの生徒が、自分が大人になったら20年後30年後には、ぜひ自分が植えた木を見に行きたい!と・・・ある意味、ちょっと大袈裟かもしれないんですけど、環境を含めた地球への何か・・・自分の心と大地にタネを植えるって感じなんでしょうね」

SDGs.TVの多様なコンテンツ
※水野さんの会社TREEのオフィシャルサイトを拝見すると、当初はマーケティングの事業を展開され、現在は持続可能な環境社会を実現するための事業を柱に据えて活動されています。事業内容を変革する、なにかきっかけがあったのでしょうか?
「大企業のマーケティング・アドバイザーのような形で、いろんなマーケティングに関わってきたんですけれど、今から20年ほど前に、やはり株主中心で、ある意味、行き過ぎた利益追求ということが多くなったことによって、ヒューマンエラーだとか、いろんな法的な事件、事故につながることが多かったんですね。
そうした点において、ガバナンスをしっかりするためには、やはり自分自身ももう少し環境や社会、いわゆる企業活動が与えていることを、しっかりとその企業にも提供すべきでしょうし、社会もそれに向かわなくちゃいけない、そういうことが舵を切ったきっかけですかね。
もうひとつきっかけとして、ちょっと長くなってしまうんですけど、2010年に『生物多様性条約会議COP10』っていうのが名古屋でありまして、それの開会式のプロデュースをしたんです。 その時に全世界で生物多様性の危機的な状況がありました。
これは生物多様性の危機的状況は気候変動もあるんですけど、私たちの消費生活、生産と消費にものすごく影響をもたらしているので、ここはやっぱり企業活動自身を、地球や社会のサステナブルのためにも取り組むべきだと考えました」
●今の主な事業としては「SDGsQUESTみらい甲子園」の学習プログラムにもなっているSDGs.TVというメディアになるんでしょうか?
「そうですね。メディア事業というよりも、これはひとつのプラットホームとしての教育ですね。これは小中高だけではなくて、企業の人材育成研修にも軸足を置いて、多くのかたたちがサステナブルな意識啓発になるようにと、研修事業を中心にしています」
●コンテンツはどんなものがあるんですか?
「SDGs.TVは本当に多様ですね。NGOのアクションから各国の政府の活動ですとか、もちろん国連や気象協会、様々な気候から生物多様性からLGBTQ、フェアトレードから途上国の話もあれば、日本国内のローカルな取り組みのものもあれば、課題から取り組みまで、様々なコンテンツを発信しています。
テキストで学ぶよりは、やっぱりエモーショナルですし、映像にはストーリーがありますよね。そういった意味では全く無関心だった子供たちを見ていると、先生から一方的に教えられるものだと下向いているんですけど、映像を見て心が動いて、これは大人もそうです。映像を見た時にやっぱり腹落ちするというか腑に落ちるというか・・・ですから、映像の力は人々の行動を促すには、とても大切かなと思います」
(編集部注:ちなみにSDGs.TVには500タイトル以上の映像があるそうです。どんな作品があるのか、ぜひオフィシャルサイトをご覧ください)
「気候行動探究ブック」を無料配布!

※学校の授業で地球温暖化や環境問題を学んでいる10代のみなさんは、私たち大人以上に危機意識を持っているように思います。その辺りは、いかがですか?
「この5〜6年、中学生高校生と出会っていると驚くのは、やっぱりエシカル意識がすごく高いです。 少し感度の高い子供たちはフェアトレードとかにも関心がありますね。
最近は本当に美容院を選ぶにしても、物を買うにしても、店を選ぶ中において・・・究極は就職、大学生も就職をしていく中において、SDGsにちゃんと取り組んでいるかとか、そういうことに目線がいく若い10代は、私たちの時代とは違って多いなと思います。
ただ気候変動で考えると、欧米と比べると日本人の10代は、まだそれだけの危機意識はちょっと弱いかなとは思います」
●「気候行動探究ブック」というものを全国の高校生に無料で配られたんですよね?
「そうですね。みらい甲子園はSDGsで申し上げると1番〜17番、それは社会課題は多様なもので構わないんですけど、やはり世界の気候変動教育ってすごく重要なんですね。イタリアやイギリスではもう国をあげて行なっているんですが、日本はまだまだ気候変動教育は進んでいませんので、行動を促すような教材を作りまして、全国およそ4300校に進呈しました」
●これはどんなブックになっているんですか?
「世界中の同じ世代の高校生たちの気候行動の情報ですとか、温暖化が与える影響、そして私たちがどういうことに取り組むべきかということをわかりやすく解説しています。
国立環境研究所のかたや国連のかた、スウェーデン・ストックホルムのレジリエンス・センターのかた、そんな専門家からの映像メッセージも入れて、多様な行動をみんなで考えるような探究ブックにしています」
●「SDGs QUESTみらい甲子園」 に応募してくる高校生たちには、どんなことを期待していらっしゃいますか?
「アンケートをとったんですけれど、みらい甲子園に参加してSDGsの意識が高まったっていうかたは大半ですし、行動意識が変わったっていう結果が最も多いんですね。 ですから、エントリーした高校生には未来を切り開く力、そして自分たちが変えるんだと主体的な考え方、そんなことを持っている、ひとりでも多くの次世代が育っていくことを期待しています」
●一方で番組を聴いてくださっている大人のみなさんに、何か伝えたいことがありましたら、ぜひお願いいたします。
「これは高校生から聞いたことなんですけど、自分たちのアイデアを自治体に持っていったら、”こんなこと、できないよ”とか、結構否定されることが多かったらしいんです。 そうではなくて、やっぱり常識が通用しない未来を考えますと、これだけ生成AIも出てきて、本当に新しい社会が今始まろうとしている。そんな時には大人も、高校生や中学生から学ぶことがたくさんありますし、一緒に共創していく思い、それを持って応援していただきたいなと思います」
INFORMATION

現在「SDGs QUESTみらい甲子園」千葉県大会では、高校生のみなさんのアイデアを募集しています。持続可能な社会を実現するために解決したい、あるいは、変えたいと考える「探究テーマ(課題)」をひとつ選び、その解決策となる具体的な「SDGsアクション」のアイデアをお送りください。
参加条件は、千葉県の高校に通う1年生・2年生、ふたりから6人で構成するチーム。高校3年生だけのエントリーはできませんが、チームに入ることはできます。
千葉県大会の応募の締め切りは、12月20日(水)午後1時。エントリー方法など、詳しくは「SDGs QUESTみらい甲子園」のオフィシャルサイトをご覧ください。
◎SDGs QUESTみらい甲子園 :https://sdgs.ac
水野さんが代表を務める株式会社TREEのサイトもぜひ見てください。
◎株式会社TREE :https://tree.vc
2023/11/19 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. I DON’T CARE / ED SHEERAN & JUSTIN BIEBER
M2. YOUNG HEARTS RUN FREE / CANDI STATON
M3. A MILLION DREAMS / ZIV ZAIFMAN,HUGH JACKMAN,MICHELLE WIL-LIAMS
M4. TRY EVERYTHING / SHAKIRA
M5. We Are / ONE OK ROCK
M6. POWER TO THE PEOPLE / BLACK EYED PEAS
M7. I NEED TO WAKE UP / MELISSA ETHERIDGE
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2023/11/12 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、YouTubeの動画配信で話題! 週末縄文人の「縄(じょう)」さんと、「文(もん)」さんです。
「縄」さんは1991年、秋田生まれ。大学時代はワンダーフォーゲル部で活動、多くの時間を山で過ごし、趣味は釣りと料理。
「文」さんは1992年、東京生まれ。幼少期は、アメリカのニュージャージー州やアラスカ州で暮らしていたそうです。
そんなおふたりは3年ほど前から、平日はサラリーマンとしてお仕事をされ、週末だけに縄文活動を開始。自然の中にあるものだけ、つまり現代の道具を一切使わずに縄文生活にチャレンジされています。
当初は山梨県の森で始めたそうですが、現在は長野県の敷地面積およそ2000坪、標高1000メートルにある山あいの森を借りて、活動されています。サラリーマンですから、活動着はワイシャツとスーツなんですよ。
ちなみに、週末縄文活動のことは、会社や仕事関係には基本内緒。YouTubeの動画にも顔出しはしていないんです。
そんなおふたりが出された本が『週末の縄文人』、これも話題になっています。
きょうは週末縄文人のおふたりに、本気で取り組んでいる活動の中から試行錯誤の末、気力体力を振り絞り、ついにやり遂げた火起こしと、竪穴住居づくり、そして縄文活動から見えてきた先人たちの知恵や暮らしに思いを馳せます。
☆写真提供:横井明彦、協力:(株)産業編集センター 出版部

週末は縄文人!
●まずは、そもそもどうして週末に縄文人としての活動を始めたのか、それをお聞きしたいんですけれども、縄さん、教えていただけますか?
縄さん「もともとは僕が、文明が崩壊したあとに生活に必要なものを、自分たちで自然から生み出すことができるのか、みたいなことをやりたくて・・・変な話なんですけど、鉄を自分たちで作るとか、石鹸を作るとか、生活に必要なものを自然から作りたいっていう、活動と動画を撮りたいなと思っていたんですね。
でも、それをやる場所がなくて、相方に相談したところ、相方のお父様の土地が山にあるって言ってくれて、それで相方から一緒にやろうと言ってくれました。
僕は現代にも通じているテクノロジー、鉄とか薬とか石鹸とか、そういう今のインフラというか生活を支えるテクノロジーに興味があったんですけど、相方はどっちかっていうと、もっとプリミティヴなというか、原始人とか縄文人とかのテクノロジーに興味があって、どうせやるんだったら原始時代から始めたいって言っていたんですね。
それでゼロから文明を始めて、ステップアップしていく活動にしようっていうので、自然にあるものだけを使って、ゼロから文明を築くっていう取り組みで、今は技術的には縄文時代にいる、そんな活動をやっています」
●なるほど〜。文さんは縄さんから、こういうことやってみたいんだって言われた時は、どんなふうに思われました?
文さん「また何か面白いことを言ってるな〜と(笑)、もともと仲のいい会社の同期だったので・・・。僕はそういうことは全然思いつかなかったんですね。
でも、今ちょっと縄が話してくれたみたいに、僕はもともと、もっとプリミティヴな、プリミティヴだけじゃないんですけど、自分と全然違う暮らしをしている文明の人とか文化の人にすごく関心があったんですね。
彼らがどういうふうに世界を見ているかとか、そういうことに関心があったので、やるんだったら自分のルーツでもあるし、全然自分とは違う世界をきっと見ていたであろう、縄文とか石器時代の人から始める、かつ道具そのものを使わずに進めたいっていうのは、僕はすごく思っていたことだったんですね。
ナイフとかそういう道具を使うというのは、たぶん縄のほうの最初のプランにはあったと思うんですけど、そこは道具はなしでやりたいなっていうのは、僕のどっちかというと強い思いでした。そこから見えてくるものがあるんじゃないかなっていう感じですかね」
(編集部注:おふたりは縄文時代にだけ、こだわっているのではなく、ゼロから文明を築き、ゆくゆくは江戸時代、できれば、現代にまで文明を進めたいという夢を持っていらっしゃいます)

火起こし~神々しい美しさ
●週末縄文人がまず取り組んだのが、「火起こし」ということですけれども、現代の道具を使わずに火起こしするのは、縄さん、大変だったんじゃないですか?
縄さん「そうですね。本当に一回の週末で、3日間ぐらいで火をつけられるだろうとか思っていたんですけど、最初は煙すら出なくて、めちゃくちゃ大変でした。
手をこすり合わせる『キリモミ式』っていう火起こしがいちばんオーソドックスだったので、それをやってみたんですけど、(棒が)まっすぐじゃなくて、どんどん回していると、穴から飛んでいくんですよね。まずはまっすぐな棒がないみたいなところからわからなくて、毎週毎週通って一個ずつできないことを潰していって、全然できないまま続いて、3ヶ月後ぐらいにようやく(火が)ついたっていう・・・」
●それはキリモミ式で、最終的に火がついたんですね。
縄さん「そうですね、つけられましたね。でも最初はふたりがかりですね。今はひとりでもできるようになりましたけど、ふたりで疲れたら交代して、みたいなやり方で、できるようになりましたね」
●おふたりでの共同作業ということで、YouTubeの動画でも「いける、いける〜!」って励ましあっていましたよね。
縄さん「あれ、マジで大事なんですよね。たまに人前でやるとすごく笑われるんですけど、本当に違うよね! あれ、やるとやらないでは・・・」
文さん「全然違う、全然違う」
縄さん「マジで最後のひと踏ん張りで、本当に(火が)つくかつかないか決まるので、もうこれで決めるぞ! もうないぞ! いけー!みたいにいうと、本当につくんですよ」
文さん「筋トレのたぶん、限界までいった時に、もうひと踏ん張り、最後いけー! みたいな感じだと思う・・・限界を超えるのには必要なんですよね」
●やっぱりひとりじゃなくて、ふたりでやるっていうのに意味があるんですね。
文さん「そう思います。意味があるし、ひとりだと文明は作っていけないと思います」

※手にマメをつくり、痛い思いをしながらも、ついに火が起きたときはどんなお気持ちでしたか? 文さん、いかがですか?
文さん「最初にたぶん動画でもそういうふうに言っているんですけど、『美しい』という、それがまず来ました。今まで当然、火というものは見たことはあったんですけど、今まで見てきた火とは全然違って、本当に・・・何だろう・・・マッチとかライターとかそういうのがあれば、火がつくって当たり前にわかると思うんですけど・・・。
でも、自然の中で火の気が何もない森の中で、何もないところから、ブワッてあの明るくて熱いエネルギーの塊みたいなのが生まれた時はもうびっくりして、神々しいと言いますか、そういうものも、はらんだ美しさみたいなものを感じました」
●それこそ途中でマッチを使っちゃえとか、ライターを使っちゃえとかは思わなかったですか?
文さん「それをやっちゃうと、僕たちのやりたかったことには近づけないというか、ただ火起こし風動画を作るだけだったら、別にズルしてマッチでやっちゃってとかってできると思うんですけど、僕らの目的はそこにあるんじゃなくて、本当にそれができるようになるとか、本当に自然のものだけで、何かをやるプロセスで見えることとか、感じることを体験したいっていうことにあるので、それは全然一度も考えてないです」
笹地獄!? 竪穴住居づくり
※おふたりは火起こしのほかにも、石斧づくりや、紐(ひも)をよったり、土器を作ったりと、これも試行錯誤しながら挑戦。そして、ついに取り組んだのが「竪穴住居」づくり。
どんな竪穴住居を作ったのかというと・・・穴の直径がおよそ2メートル、深さが40〜50センチ、床面積は、3〜4人がぎりぎり寝られるテントほどの広さ。本物に比べると小ぶりな作りになっているそうです。構造は、石斧で切った木の枝を、柱や梁などにして、およそ30本の木を組み、その上に屋根材として大量のクマザサをふいた住居なんです。

竪穴住居づくりで、いちばん大変だった作業はなんでしょうか? 文さん、お願いします。
文さん「これはたぶんふたりとも同じなんですけど、笹で屋根をふく作業です」
●どう大変だったんですか?
文さん「まずその全工程にかかったのが30日、そのうちの半分がこの屋根作りだったんですよ。骨格作りは本当に2週間くらいでできちゃって、骨格ができるともうなんかできた気持ちになるので・・・」
縄さん「できた気持ちで半分打ち上げしていましたね。もう終わりだみたいな、あと4日で終わりだとか言って・・・」
文さん「骨組みの前でふたりで肩を組んで写真を撮って、終わった感が出ていたよね(笑)。なんだけど、地獄はそこからだったみたいな・・・。
結局そこから、笹の束を15本から20本ぐらいをひとつにまとめて、屋根に下から順番に結びつけていって、それでどんどん上に向かって屋根をふいていくんですけど、その作業がさらに今までかかってきた作業と同じぐらいかかりましたね。本当は3〜4日とかで、もしかしたら終わるかなとか、僕はうっすら思っていたんですけど、全然進まないんですよ」

縄さん「だいたい1日のスケジュールを言うと、朝7時ぐらいから昼過ぎまで5時間から6時間ひたすら中腰でクマザサ、クマザサは背が低いんで、ひたすら中腰で笹を折り続けるっていう作業、それをご飯を食ってから日が暮れるまで。
それを結ぶツルも、地味にそのツルもあるんですけど、笹を結ぶツルを集める作業もそのあとに数時間やって、日が暮れるまでひたすら結ぶ作業。結ぶのもすぐできるかと思いきや、その束を1回束ねて結んで、3本に1本ぐらい(切れて)。
とにかくめっちゃ丈夫な屋根を作るってなったんで、めちゃくちゃ締めていたんですけど、ツルって意外に切れるんですよ。プツって切れて、ああ!ってなって、また別のツルを探してみたいな、そういうのをうだうだやっているっていうのが朝から晩まで、それが15日間っていう感じですね」
文さん「笹を折る作業、笹を収穫する時に手でパキパキ折っていくんですけど、笹って節みたいなのがあるから、そこをパキって折るとまあ簡単に取れるんですよ。でも簡単に取れるとはいえ、それを2万本分やっていると、手がどんどんひび割れて、血が出てきてマメになってカチカチになって・・・。
本当に最後、指先とかもありえないぐらい硬くなって、スマホに反応しなくなったんですよ。スマホをタップしてもカンカンカンってなって、現代生活にだいぶ支障も出ていました」
竪穴住居に、神々しい一筋の光
※苦労の末についに完成した竪穴住居を見て、どんな思いがこみ上げてきましたか。縄さん、どうですか?
縄さん「僕はあんなに綺麗なものを自分の人生で作ったことがなかったんで、子供の頃、図工は3とかだったし、あんなに手間をかけて、あんなに美しいものを自分たちだけで、しかも道具を使わないで自然のものだけで作った、みたいな達成感があって、すごく嬉しかったですね。あとやっぱり昔の人もこんな家を建てていたんだみたいな・・・。

僕は縦穴住居の中から見える外の景色がすごく好きなんですね。笹をふいた四角い入り口から外の原っぱが見えるんですけど、ちょっと角度を変えると僕らが普段焚き火をしている焚き火台が見えて・・・ここから(見える)景色って全部100%自然にあるものだけで作っていて、縦穴住居で、あ〜これ!って、縄文時代の人も見ていた景色だな、これっ! 誰がなんと言おうと、そうだ! みたいな・・・なんかそういう気分になれたんですよね。
また、竪穴住居の中ってめっちゃ暗くて、そこにマジで一筋の光みたいな感じで、入り口から光が差してくるんですよ。それもちょっと言葉にしづらいんですけど、めちゃめちゃ神々しくて、ずっと見続けていて・・・本当にあんなに豊かな感動は人生で今まで味わったことないなっていう経験でしたね」

●文さんはいかがですか?
文さん「僕も衣食住の『住』を自分で作れたっていうのは、すごくありえないこと。普段暮らしていて、衣と食はなんとか作れたとしても、家を自分たちだけで建てたっていうことの感動と、やっぱり僕もその中の雰囲気、半地下にあってすごく暗くて、入り口の部分からわずかな光が入ってきて、最初(中に)入ると真っ暗で何も見えないんですけど、徐々に徐々に目が慣れて中が見えてきて、目の前に座っている相方の顔がぼんやりと見えてくるんですよ。
なんだろう・・・中に入ると、遊びに来た人みんなが言うんですけど、なんか話しちゃうねみたいな、初めて会った人とかでも、なんか深い話ができちゃうねとか、安心感があるよね、みたいなこと言うんですよ。
それってあの家の持つ、ほの明るい暗さとか、みんなで結局、円になって真ん中にある火を見ながら語るあの感じとか、あの家の機能、人を近づけるあの家の機能っていうのも、今の家にはない凄さだなっていうふうに、作って住んでみて初めて思いました」
自然の見方、文明のありがたみ
※週末縄文人の活動を始めてから、それぞれにどんな変化がありましたか? 縄さん、お願いします。
縄さん「僕はもともと自然がすごく好きで、大学時代も山登りや渓流釣りが好きだったんですね。でも僕は町育ちだったので、自然って休みにレジャーで行くもので、レジャーで行く自然ってちょっと物寂しい気もしていて、自然を味わい尽くしてない気がしていたんです。そうすると、田舎で森に住んでいる人とかそういう人にすごく憧れがあって、それで自然のこういう取り組みをしたいなっていうのがあったんですね。
この活動をしていると、昔は自然の、ただの雑木林みたいに思っていたものが全部宝物に見えると言いますか、石ひとつとってみても、これは『打製石斧(だせいせきふ)』に使えるとか、『磨性石斧(ませいせきふ)』に使えるとか、鋭いから火起こしの穴あけに使えるとか・・・。
粘土を見ても、あっ!これは土器に使えるなとか、木を見ているとこれは樹皮が編み物に使えるかもとか、この植物は繊維になるから紐になるかもとか、なんか自然の見方が本当に豊かになったっていう・・・自分の変化がすごく憧れていた自然の見方に近づいている気がして、本当にこういう人間になりたかったなっていうものになれている気がして、すごくこの活動をやっていて良かったなと思っていますね」
●文さんはこの週末縄文人の活動から、平日現代人の生活ってどう見えていますか?
文さん「今まで僕はどっちかというと、文明に対して批判的というか、社会人になるまでスマホも持っていなかったりとか、文明に対して反発していたんですよ。環境にも悪いしみたいな、そんなの使っていたら人間の能力が落ちるとか、そういう感じがあったんですけど、この活動を始めて文明ってすごいな!って、本当に逆に思うようになりました。
文明ってたぶん人がよりよく安心して安全に、より便利に楽しく幸せに暮らせるようにもともとあるものなんですよね。
それは僕らが実際、石斧を使って、それまで石を手に持ってガンガン切んなきゃいけなかったのが、それだと肘とか手がものすごく痛くなるし、あの太い木は切れないし、そこで石斧っていうものが発明されて、自分たちの体も痛めつけることなく、太い木もより早く切れるようになって、そこでもっとがっちりした広い家に住めるようになるとか・・・。
そういう文明がひとつひとつ進んでいくことで、自分たちの暮らしがよくなっていって、そこには少しでも自分たちの暮らしをよくしたいっていう思いがあるからこそ、文明は進んできたんですよね。
今は自分たちはその延長線にいるわけで、ここまで文明が進んできたってことは、それだけそこに、よりよく生きたいっていう人の思いがあったんだなっていうことに気づけたというか・・・。
目の前にあるマグカップひとつとっても、水がこれだけ溜められるってすごいなとか、当たり前すぎて気づけない部分にちょっと気づけるようになったっていうのはあります」

縄文人に聞きたい!?
※最後に、突拍子もない質問なんですけど・・・もし、縄文時代の人たちに会えるとしたら、どんなことを聞いてみたいですか?
縄さん「今は、縄文時代レベルの土器を作ろうとしているので、粘土をどこで寝かしていましたかとか、あとはあの『火焔型土器(かえんがたどき)』っていうめちゃくちゃ意匠を凝らした、うにゃうにゃしている土器があるんですけど、まずあれをどうやって作っているんですか? あれ、上が重すぎて、作っているうちに潰れてきちゃうんです。普通に僕らがやっているやり方でやると・・・。これ、どうやって乾かしてんだろうなっていうのが、近々の悩みでまず聞きたい。そうですね・・・土器を作っているところを見たいっすね」
●文さん、いかがでしょう?
文さん「ちょうど今やっているのが粘土なんで、さっき縄が言っていた、そもそも粘土をどう寝かせていたかっていう・・・今の人はビニールにくるんで寝かせられるんですけど、昔の人はそんなものはないので、どういうふうに寝かせていたのかは、めちゃくちゃ知りたいのと、あと最近挑戦しているけど、失敗続きなのが釣りなんですよ。
縄文時代に鹿角の針って実際使っていて、それが出土していて博物館に行くと見られるんですけど、いわゆるJの形をした針だったり、両端が尖ったまっすぐの棒の形をした釣り針だったり、いろんな釣り針の種類があるんですね。僕らもいろんな種類を作って、実際試しているんですけど、まったく! 釣れなくて、縄文人の釣りに同行したいです。どうやって、あれで釣っているの!? めちゃくちゃ見たい」
縄さん「確かに釣り、見てみたいな〜、めちゃくちゃ見たいわ〜。化け物みたいにデカくて、アホみたいに簡単に釣れるんじゃないかっていう・・・言い訳みたいな話はするんですけど、魚が違うんじゃないかと・・・」
文さん「そもそも魚が違ったんだろう、みたいな負け惜しみはあるんだけどね(笑)」
縄さん「いっつも負け惜しみ、かれこれ4か月釣れないから・・・」
文さん「それ、めちゃくちゃ気になってます!」
縄さん「気になるな〜」

INFORMATION
縄文活動をまとめた本をぜひ読んでください。おふたりの本気度がよくわかります。火起こしに始まり、石斧、紐、土器、そして竪穴住居づくりまで、試行錯誤の末に成し遂げたサバイバル・エッセイ! 面白いです。火の起こし方や石斧の作り方なども掲載。スーツ姿で活動する様子もカラー写真とともに紹介されています。縄文人の活動をやってみたいかたは、相談にのってくれるそうです。連絡先は本に掲載されていますよ。
産業編集センターから絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎産業編集センター:https://www.shc.co.jp/book/19045
週末縄文人のオフィシャルサイトでは動画も見ることができます。
◎週末縄文人:https://wkend-jomonjin.com
2023/11/12 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. (MEET) THE FLINTSTONES / B-52’S
M2. ONCE YOU GET STARTED / CHAKA KHAN
M3. TO FEEL THE FIRE / STEVIE WONDER
M4. Life is Beautiful / 平井 大
M5. 縄文人に相談だ / TATEANAS
M6. CHANGE IN MIND, CHANGE OF HEART / CAROLE KING
M7. 狩りから稲作へ feat.足軽先生・東インド貿易会社マン / レキシ
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2023/11/5 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンは、シリーズ「SDGs〜私たちの未来」の第15弾! お話をうかがうのは、水産資源を守り、環境に配慮した持続可能な漁業の普及活動を行なう、一般社団法人「MSCジャパン」の広報担当シニア・マネージャー「鈴木夕子(すずき・ゆうこ)」さんです。
今回は「SDGs=持続可能な開発目標」の中から「海の豊かさを守ろう」ということでサステナブル ・シーフードにフォーカス! 「MSCジャパン」が取り組んでいる持続可能な漁業のための認証制度やMSC「海のエコラベル」についてうかがいます。
☆写真協力:MSCジャパン

魚の獲りすぎで35,000人もの人たちが失業!?
※まずは「MSC」について教えてください。いつ、どんな目的で設立された団体なんですか?
「MSCは持続可能な漁業を普及する活動を行なっている国際的な非営利団体です。本部はロンドンにあって、1997年に設立されました。MSCが出来たきっかけは、1990年代初頭にカナダのグランドバンクというところで、マダラの漁業が崩壊してしまったということがあるんですね。
どういうことかと言いますと、それまで獲れるだけ獲っていったマダラ漁業なんですけれども、獲りすぎてしまって、全く獲れなくなってしまったということが起きたんですね。それでマダラの漁業が崩壊したことによって、漁業者さんもそうですし、そのマダラを加工して缶詰にしたりとか、そういった加工業者も潰れてしまって、35,000人の漁業者や工場で働く人たちが失業したということが起きました。
そこで魚の獲りすぎが環境や生態系だけではなくて、人の生活にもすごく影響を与えるということが浮き彫りになって、このままではいけないということで、持続可能な漁業に関する認証制度が必要だということになり、MSCの構想が練られ、1997年に設立したということです」
●鈴木さんが所属されている「MSCジャパン」はいつ開設されたんですか?
「それから10年たって2007年に設立されました。当初はまだ持続可能な漁業とかサステナブルといった言葉は、ほとんど聞かれていない時でしたので、日本事務所が設立されて、漁業者さんや企業さんに説明に行ったりしても、なかなか理解していただくことが難しくて、うちは必要ないですっていうような感じだったっていうのは、設立当初からいたメンバーに聞いております。
ただ、最近は魚が獲れなくなったとか、そういった水産資源の危機感が広がっていることですとか、あとは2015年に国連でSDGsが採択されたことですとか、リオデジャネイロ・オリンピックなどで認証の水産物が調達されて、それが東京オリンピックにも続いたりとか、そういったことがあって、設立から10年ぐらい経ってから急速に理解や認証水産物の商品が広がってきたということがあります」
(編集部注:「MSC」は現在、ヨーロッパや南北アメリカ、アジアを含め、世界20カ国に支部があるそうです。毎週のようにオンライン・ミーティングを行ない、世界の水産資源の状況や、漁業に関する最新情報を共有しているそうですよ)

3つの原則と、25の業績評価指標
※ここからは「MSC漁業認証」について、詳しくうかがっていきたいのですが、どんな認証制度なのか、具体的に教えていただけますか。
「MSC漁業認証というのは、持続可能な漁業に与えられる認証なんですね。審査は3つの原則に基づきます。それを漁業者さんが満たす必要があります。
原則のひとつ目が、自然の持続可能性に関するもの。例えば、その漁業者さんが漁獲の対象とする魚種の資源が十分な量があるのかどうか、持続可能なレベルにあるのかどうかというところがチェックされます。その資源が持続可能なレベルにないとなると、もうそこでダメということですね。
ふたつ目が、漁業が生態系に与える影響について。その漁業が対象としている魚以外の魚介類ですとか、あとはウミガメやウミドリとか、ほかの生き物、絶滅危惧種などが間違って網にかかるということがあるんですね。それを最小限に抑えているか。例えば、その網にかかるほかの生き物が多ければ多いほど、生態系に影響があるので、そういった影響を最小限に抑えられているかというところの確認が行なわれます。
3つ目が、漁業の管理システム。ここでチェックされるのが生産資源が豊富にあるか、原則1の生態系への影響ですね。そういった原則を満たすことができるように、きちんと国際ルールや国内法が整備されていて、それが守られているかどうか、この3つの原則のもとで審査されます。
この3つの原則の下に25の業績評価指標というのがあって、その項目に照らし合わせて審査されます。各項目で60点を下回るのがひとつでもあると認証されないということです。
また60点から80点未満の指標についてはOKではあるんですけれども、期限を定めて80点以上になるまで改善するといった条件がついての認証ということになります。なので、かなり厳しい審査が行なわれるということですね」
●たくさんの審査がありますけれども、その審査はどなたがされるんですか?
「審査はMSCがするのではなくて、独立した第三者の審査機関が行ないます。私たちの仕事というのは、その認証制度の規格を設定するんですね。その規格を作った団体が審査まですると、透明性とか公平性が保てないので、第三者がその規格に基づいて、その漁業がきちんと(基準を)満たしているかを審査するということになります」

「近海かつお一本釣り漁業国際認証取得準備協議会」
MSC漁業認証のメリット
※漁業者は、その認証を取得することによって、どんなメリットがありますか?
「まず、サステナブルであるという付加価値をつけることで、ほかの水産物と差別化することもできますし、イメージを向上することができるということですね。あとは新しい市場とか販路の拡大ということもあります。特にMSC認証というのは海外で広がっているので、輸出を考えている漁業者さんにとってはすごく大きいですね。
特に欧米の消費者は、サステナブルな魚でないと買いたくないというかたも多くいらっしゃるので、そういう意味で既存の市場プラス新たな市場を開拓できるということ。
あとは持続可能な漁業を行なうことによって、長期的には漁獲量が増加するということで、自分たちの漁業も持続可能になるというところですね。次世代にも漁業を受け継いでもらえるような、そういったメリットがあります」
●認定されると、認証マークをつけることができるんですよね?
「そうですね。その(認証を受けた)漁業で獲られた水産物がサステナブル(シーフード)として消費者に届くまでに、ラベルを貼るので、消費者が認証を受けた漁業で獲られた水産物ということが分かるようになっています」
●海のエコラベル、ですね。
「はい、MSC『海のエコラベル』という名前です」
●このMSC漁業認証という制度を漁業関係者に広めて理解してもらうためには、大変なパワーがいると思うんですけれども、いかがですか?
「MSC漁業認証の取得は、漁業者さんの自発的な意思によるものなんですね。自分たちがちょっと挑戦してみようかなというふうに興味を持った漁業者さんから問い合わせをいただいて、そこでいろいろ説明をすることになります。
MSC漁業認証の審査がすごく厳しくて、審査項目も多岐に渡るということを、まず知っていただきます。その中でも例えば、漁業者さんが漁獲している以外の生き物とか、その周りの環境までが審査項目に入ったりするので、初めのうちは、なぜそこまで審査の対象になるのかという疑問を持たれることがよくあるんですね。そういった漁業者さんの通常の漁業の中では、あまり馴染みのない部分は丁寧に話すようにしています。
ただ、漁業認証を取得しようと考えている漁業者さんは魚がなくなってしまう、減ってしまうと、漁業そのものが成り立たなくなるという危機感をすでにお持ちです。次世代に水産資源を残したいという使命感も持っていらっしゃるので、こういった話をするとご納得いただいています」
(編集部注:MSC漁業認証を取得した漁業は現在、日本では18件、世界では539件あるそうです。最近では、SDGsの気運の高まりや、水産資源の減少傾向などもあり、MSC漁業認証の取得を目指す漁業関係者からの問い合わせが増えているとのこと。
この認証は、取得すれば、それで終わりではなく、5年ごとに更新の審査が行なわれ、改善の条件が付けられるので、認証を維持すればするほど、持続可能な漁業の質が高まっていく、そんな制度になっているそうです)

MSC漁業認証の質を守る、もうひとつの認証制度
※ここまでお話をうかがってきて、MSC漁業認証については、ある程度、理解できたんですが・・・ふと、素朴な疑問が浮かんできました。認証を取得した漁業の水産物と、そうじゃない水産物が混ざったりすることはないんですか?
「それはないですね。というのは、MSC認証にはふたつの認証があって、そのふたつの認証からなっているんですね。先ほどお話ししたMSC漁業認証と、あとMSC CoC(シー・オー・シー)認証というふたつがあります。この『CoC』っていうのは、英語ですと“Chain of Custody(チェイン・オブ・カストディー)”と言いまして、日本語にすると管理の連鎖、鎖という意味があります。
せっかく漁業者さんが漁業認証を取得しても、その魚が消費者の手元に届くまでに認証ではない水産物が混じってしまったら、全く意味がなくなってしまうので、漁業者さんが水揚げしたあとに卸売業者さんから水産物のパッケージを行なう最終の包装業者までの、サプライチェーン全体に対する認証がCoC認証というものになっています。
そのふたつがセットになって初めてラベルが付けられるということは、その漁業者さんが獲った、認証を取得した水産物が確実に自分たちのところに届いているんだなということの証明になります」
●なるほど。認証水産物が仲介業者とか加工業者にいっても、そこでも認証水産物ではないものと混ざるっていうことはないわけですね?
「そうですね。混ざるということはないです。入荷して加工・保管などすべての段階において認証の商品であるということが、識別できるような管理が求められたりとか、あとは製造ラインを分けるなどしても確実に分別することが求められています」
●漁業者から小売店までの流通ルートの中で、この認証に対する理解と認識がすごく大事になってくると思うんですけれども、その辺りはどうやって広めているんですか?
「MSCとしても、MSC認証制度の重要性を業界のかたがたに発信しているんですけれども、最近では魚が減ってきていることの危機意識ですとか、持続可能な水産資源を管理するという重要性がすごく高まってきているので、水産業界ではこうした取り組みを行なうということが、当たり前という風潮にはなってきているというのを感じています」

MSC「海のエコラベル」、500品目以上!
※私たちが、持続可能な漁業を応援するためにはMSC「海のエコラベル」がついた水産物を積極的に買うことだと思うんですけど、どこで販売していますか?
「よく聞かれる質問で、なかなか見たことがないと言われることがあるんですけれども、実は結構身近なところで手に入ります。
イオングループですとか、生協/コープ、セブン&アイグループ、ライフ、あとはマクドナルドとか、私たちにとって身近なスーパーとかレストランに置いてあったりします。あとはスーパーの店頭だけではなくて、航空会社の機内食とかホテルのレストラン、大学の学食などでもMSC『海のエコラベル』を表示したメニューが提供されています。
どういったものにMSCラベルが貼られているかと言いますと、魚の切り身とかそういった鮮魚だけではなくて、水産加工品、ちくわやカニカマ、からし明太子とか。あとは白身魚のフライなどの冷凍食品ですとか、缶詰めなどもあります。最近新しいところでは猫の餌、猫缶にもMSCラベルが付くようになりました」

●かなり身近にあるわけですね!
「そうなんです。ただ見たことがないという声も大きいのは、やはり日本ですとスーパーの種類がすごくいっぱいあるので、近所のスーパーでは扱ってなかったということもあるかと思います」
●意識してちゃんと見てみます!
「はい、ありがとうございます。意識しないと全然目に入ってこないんですけど、一度意識すると実は結構あるなっていうことに気付くかと思います 」
●では改めて、リスナーのみなさんに伝えたいことを教えてください。
「実はMSC『海のエコラベル』が付いている商品というのは、日本で500品目以上あって、たくさんの種類がいろいろなところで売られています。サステナブルな商品っていうと、ちょっと値段も高いんじゃないの? と思われるかもしれないんですけれども、実はそんなことはなくて、通常の商品とほとんど(値段は)変わらないですね。
なので、商品を選ぶ時にラベルが付いたものを選ぶようにすると、持続可能な漁業を目指す漁業者さんが増えていって、海の環境を守ることにもつながりますので、ぜひ見かけたら選ぶようにしてください。
また、近所のスーパーでもし売ってない場合は(お店のかたに)扱ったりしていますか? というふうに聞いていただくことも、スーパーのかたたちはお客様の声を聞くようにしていますので、それもすごく大きな力になると思いますので、ぜひよろしくお願いします」

INFORMATION

「MSCジャパン」では消費者に、MSC認証制度とMSC「海のエコラベル」をもっと広く知ってもらうために、年3回キャンペーンを行なっているそうです。先月は、この番組のホームページでもご紹介しましたが、「サステナブルシーフード・ウィーク」というキャンペーンが展開されていました。来年1月には「サステナブルなお魚レシピ」を公開するそうです。
ちなみにMSCアンバサダーは、海洋生物好きで知られているココリコの田中直樹さんですよ。MSC認証とMSC「海のエコラベル」、そして活動について詳しくはMSCジャパンのサイトをご覧ください。
◎MSCジャパン:https://www.msc.org/jp
2023/11/5 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. FISH! / JEFFREY FOSKETT
M2. THE SEA / CORINNE BAILEY RAE
M3. BY THE SEA / SUEDE
M4. SPIRIT OF THE SEA / BLACKMORE’S NIGHT
M5. 魚 / スピッツ
M6. TO THE SEA / JACK JOHNSON
M7. BEYOND THE SEA / CELTIC WOMAN
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」
2023/10/29 UP!
◎深澤 遊(東北大学大学院の准教授)
『「枯木こそ山のにぎわい」〜枯木が育む生き物と森林生態系』(2023.10.29)
◎新宅広二(動物行動学者)
『あなたのお悩みに「動物」を処方!?心がちょっと軽くなる“動物行動学的”読むお薬』(2023.10.22)
◎笠原里恵(信州大学の助教)
『この秋、可愛くてワイルドな「カワセミ」を観察しよう~水辺のある公園や小さな河川にきっといる!?』(2023.10.15)
◎奥野克巳(立教大学・異文化コミュニケーション学部の教授/人類学者)
『「人類学」入門~ボルネオ島の狩猟民プナンから「人間」が見えてくる!?』(2023.10.08)
◎森 昭彦(サイエンス・ジャーナリスト/ガーデナー)
『「雑草」を知れば知るほど、「人生」は豊かになる!?』(2023.10.01)
2023/10/29 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、東北大学大学院の准教授「深澤 遊(ふかさわ・ゆう)」さんです。
深澤さんは1979年、山梨県生まれ。信州大学 農学部卒業、京都大学大学院 農学研究科修了。そして、研究職から、森林組合やトトロのふるさと財団の職員を経て、現在は東北大学大学院の準教授として活躍されています。
子供の頃の深澤さんはコケが大好きな少年で、小学校3年生の夏休みの自由研究が「リアルコケ図鑑」。その後、やはり小学生の頃に、国立科学博物館の子供向け講座でアメーバの仲間「変形菌」に出会い、その時もらった飼育セットで変形菌を育てたり、自分で見つけた変形菌をスケッチしたりと、夢中になっていたそうです。
現在、深澤さんは、森林の生態に関する研究をされていて、特に枯木が生き物や環境に対してどんな役割を果たしているのかを調査・研究されています。そして先頃『枯木ワンダーランド』という本を出されました。
きょうはそんな深澤さんに枯木を舞台に繰り広げられる、生き物たちの驚くべき営みや、枯木が人間にもたらす恩恵のお話などうかがいます。
☆写真協力:深澤 遊

枯木のスペシャリスト
※まずは、深澤さんのご専門を教えてください。
「森林の生態学を研究しています。生態学っていうのは生物がどのように暮らしているかとか、環境やほかの生物と、どのような関係性を持って暮らしているのかを調べる学問分野です。
その中で森林生態学は森にどのような生物がいて、それらによって森がどのように成り立っているのかを調べています。僕はその中でも特に木が枯れたあとの枯木ですとか、そこに棲んでいる菌類など、微生物の生態に注目して研究しています」
●具体的には、どんな研究をされているんですか?
「具体的には、森の枯木の中にどんな種類の菌類がいて、それによって枯木がどのように分解されていくかを調べています。最初は同じ枯木でも分解に関わる菌類の種類によって、全く違うように腐朽していくんですよ。それが森林の炭素貯留量に影響する可能性ですとか、森林の生物多様性に影響する可能性のようなものを探っています」
●どんな菌類なんですか?
「枯木に生えているシイタケとか、そういったキノコを想像していただければいいと思うんです。キノコは、要は花みたいなもので、枯木の表面に菌が花を咲かせたような状態なんですよね。
その菌の本体は枯木の中の菌糸。カビと同じような形で枯木の中にいて、それが本体なわけですね。その本体の菌糸が、枯木を分解して栄養にして生活しているんですけども、枯木の中でどういう菌がいて、どういうふうに菌が枯木を分解しているのかっていうようなことを研究しています。
枯木の中を削ってみると、枯木の断面に黒い線が見えるんですよね。その黒い線は枯木の中にいる菌類のコロニーの境界線なんです。それを見ると本当にモザイク模様みたいになっていて、枯木の中でいろんな菌類のコロニーがあって、それが空間の獲得競争をして、陣地争いみたいな状態になっているんですね。そういうのを見ると面白いですね」

(編集部注:深澤さんは大学の2年生まで山岳部で活動、大学院生の時にはアメリカのカリフォルニア州にあるヨセミテ国立公園に行き、クライミングを楽しんだこともあるとか。研究者になって調査のためにひとりで山に出かけることもあるので、やはり、安全を確保する山の経験は活きているそうです)
生き物で賑わう枯木!?

※ここからは深澤さんが先頃出された本『枯木ワンダーランド』から、番組で気になったワードや項目についてお話をうかがっていきます。
前書きに「枯木も山のにぎわい」ではなくて「枯木こそ山のにぎわい」と表現されています。枯れてしまった木が「にぎわう」とは、どういうことなのか、教えてください。
「これは枯木に棲んでいる生き物が、非常に多様だっていうことですね。森に虫を探しに行って何も見つけられなかったら、多分枯木をひっくり返せば、大抵何かいますし、例えば、クワガタが好きな人だったら、枯木の中にクワガタの幼虫が棲んでいることをよく知っていると思います。
それだけではなくて、腐った倒木の上にはよく苔や木の芽生えも生えていますし、目を近づけてみるといろいろなキノコが生えていたり、小さい虫が歩き回っていたり、何かを食べていたりします。

さらに、先ほど言いましたようにノコギリで切って中を覗いてみると、菌類のコロニーの境界線が見えたりしますので、それらを見ているだけでも面白いんですよ。さらに培地の上に培養してどんな菌類なのか調べたりですとか、枯木の成分の分析をして、どんな物質が残っているかを調べると、枯木の中の生き物の営みがわかってきて、さらに面白いです。
そういうことが見えてくると、枯木は多種多様な生き物の営みでにぎわっているということがよくわかると思います」
●枯木ってものすごく情報量があるんですね?
「そうですね」
●2015年からは森の中にあるご自宅の庭で、枯れたコナラをそのままにしておいたり、伐採した同じくコナラなどの丸太を庭に放置してあるということですけれども、お庭が研究のためのフィールドになっているっていうことですか?
「はい、そうです。庭はやっぱりいちばん近いフィールドなので、大事にしています。生態学で新しい発見をするのに、やっぱりどれだけ生き物を観察できるかっていうのが肝になることが多いんですね。遠くのフィールドと違って、庭はいつでも観察できるので、誰も知らない発見ができるかもしれません」

●今、特に注目していることはあります?
「実際、本にも書いたんですけれども、ある冬の朝、リスが庭にやってきて枯木の樹皮を剥いて、その下の菌を食べることを初めて発見したんですよ。さらにその樹皮の下に菌が生えていて、その菌に独特な昆虫がやってくることも庭の調査からわかりました」
●ものすごく近いフィールドでいいですね、研究しがいがあって!
「そうです。自分の(部屋の)椅子の上から全部見えるので・・・」
お菓子の家に棲む!?
※枯木は、分解するまでには長い時間がかかると思いますが、年ごとに、季節ごとに、枯木を利用する生き物も変化していくってことですか?
「そうですね。やっぱり分解していくので時間に伴って、分解していく時の成分だとか、いろいろなものが変化していくので、そこに棲んでいる生き物もだんだん移り変わっていきます」
●どういう生き物が、どうやって変化していくのかを教えていただけますか?
「はい、いちばん重要になるのはやっぱり水分で、木が生きている時は、ある程度水分を含んでいて、これによって菌類の侵入を防いでいるっていう側面があるんですけれども、木が枯れると一旦乾燥していきます。この乾燥によって菌類が成長して、木を分解できるようになるんですね。
最初は、木が生きていた時から内部に潜んでいた菌類がいて、”内生菌”っていうんですけれども、これが成長を開始します。 ただこの菌はあまり木材の分解力はなくて、糖分なんかを食べて生きているんですよ。この糖分がなくなるとすぐにいなくなっちゃうんです。
そのあとに木材を分解できるような種類の菌類が胞子とかで定着してきて、枯木を分解していくと、だんだん木材がボロボロになっていきますよね。そうすると水が染み込みやすくなって、含水率がだんだん上がってきます。
そうなると表面にだんだん苔が生えてきたりだとか、乾燥した木材が好きなカミキリムシやゾウムシの幼虫から、湿った材木が好きなクワガタムシの幼虫に、内部の昆虫種も移り変わってきたりします。この頃になると、倒木の表面に木の芽生えが生えてきたりして、次の世代の森が倒木の上で育っていくわけです」

●生き物たちは枯木から、どんな恩恵を受けているんですか?
「枯木に棲んでいる生き物にとって多くの場合、枯木は住処であると同時に食べ物でもあります。イメージとしてはお菓子の家に棲んでいるようなものなのかもしれません」
●枯木って本当にただの燃料みたいなイメージもありましたけれども、そうではないわけですね。枯木には、いろんな生き物に必要な養分があるっていうことですか?
「そうですね。枯木は重さの半分程度が炭素でできています。炭素はすべての生き物が体を作る上でいちばん重要な物質で、あらゆる生き物はどこかから炭素をもらってくる必要があるわけですね。
植物は光合成によって空気中の二酸化炭素から炭素をもらってきていて、ほかの生き物は植物を食べることで、あるいはほかの動物を食べることで炭素を得ています。枯木を食べる生き物は、枯木から炭素を得ているっていうわけです」
枯木は燃料!? バイオマス発電の是非
※本の第2部に「枯木が世界を救う」という見出しがついていて、その中に「枯木が消える」というチャプターがあります。これは森から、枯木が消えてしまうってことですか?
「はい、そういうことです」
●これは日本の話ですか?
「日本では現在まだ、それほど消えていないと思います。ただ心配なのは、枯木などのバイオマスを燃やして発電するバイオマス発電が、とても推奨され始めていることです。
木材は確かに木が成長すれば(発電は)できるので、再生可能エネルギーなんですけれども、燃焼で失われるスピードに対して、木が成長するスピードはあまりにも遅いので、とてもではないですが、現在の人口が必要としているエネルギー量をバイオマス発電で賄って回していくことができるとは思えません。
なので、バイオマス発電が広く行なわれるようになったら、山から枯木はあっという間になくなってしまうんじゃないかと思います」
●あっという間になくなってしまったら、生物多様性がそれこそ損なわれてしまうと思うんですけれども、ほかにはどんな影響が考えられますか?
「やっぱり枯木が燃料として使われると、枯木の中に保存されていた炭素が二酸化炭素として大気中に放出されますので、温暖化が進行するんじゃないかと思います。バイオマスを発電に使うと、化石燃料を使った場合の2〜3倍の炭素を放出する可能性もあるそうです」

●改めてなんですけど、木は光合成を行なう過程で、地球温暖化の主な原因になっている二酸化炭素を吸収してくれているんですよね。で、木はその二酸化炭素を自分の中に溜めているということですよね?
「はい、そうですね。それで体を作っているので」
●その木が枯れてしまったら、その二酸化炭素は・・・?
「分解されたり燃やされたりすると、二酸化炭素として放出されるってことになります」
(編集部注:枯木をバイオマス発電などに広く利用するようになると、森から枯木がなくなってしまうというお話がありましたが、深澤さんは森の中にある枯木を、単なる燃料として見ることに警鐘を鳴らしています。詳しくはぜひ、深澤さんの本『枯木ワンダーランド』をチェックしてください)
枯木の下もワンダーランド
※枯木を観察していて、どんなときにいちばんワクワクしますか?
「やっぱりまだ見たことのない生き物を見つけた時ですかね。初めて見る変形菌とか、キノコ、苔、虫、ナメクジ、カタツムリ、ヘビ、サンショウウオとか、いろいろな生き物を枯木で観察できますので・・・。あとは、ものすごい巨木の枯木を見た時とかは、目の前に保存されている時間の長さにくらくらしたりします」
●都市公園には枯木がそのままにしてあったりとか、丸太が放置されているっていうことはなかなかないと思うんですけれど、もし見かける機会があったら、どんなところを見ると面白いですか?
「もし許されるのであれば、樹皮を少し剥がしてみたりですとか、樹皮の裏側にいろいろな生き物が隠れていたりしますし・・・・。あと丸太、枯木を転がして、その下に隠れている生き物を探してみると面白いと思います。
実際、僕も枯木を調査しながら、いろいろな国で枯木の下を見てみるってことをやっているんですけれども、国とか場所によって、本当に枯木の下に潜んでいる生き物が全然違っていて面白いですよね。
日本だとミミズがいたり、シロアリとかアリがいたり、時々ヘビがいたりとかすることが多いです。アメリカの東海岸では、枯木の下にサンショウウオがいっぱいいたりだとか、ヨーロッパではナメクジが大量にいたりしましたね」
●国によって全然違うんですね! では最後に、今後の研究で明らかにしたいことを教えてください。
「研究テーマは、マクロなものからミクロなものまで、いろいろあるんですけれども、マクロなテーマとしては、枯木を分解する菌類や、その分解機能が世界的に見て、どのような分布をしているのかを明らかにしたいと考えています。これは地球の環境が変わると、菌類の種や枯木の分解がどのように変わるかといった予測にもつながると思います。
ミクロなテーマとしては、個々の菌類が環境に応答しているとしたら、その生理的なメカニズムですとか、これはちょっと違う話になってしまうんですけれども、菌類の菌糸が持つ機能と知能とか、そういったものについて明らかにしていきたいと思っています」

INFORMATION
『枯木ワンダーランド~枯死木がつなぐ虫・菌・動物と森林生態系』
深澤さんの本をぜひ読んでください。枯木が分解の過程で、いかに生物多様性に貢献しているのか、まさに「枯木こそ、山の賑わい」というのがよくわかりますよ。そして、森から枯木をなくすことで、どんな影響が出てくるのか、さらに枯木が地球環境の保全に役立っている仕組みなど、興味深い内容になっています。深澤さんが描いた精密なスケッチも必見! 築地書館から絶賛発売中です。
詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎築地書館:http://www.tsukiji-shokan.co.jp/mokuroku/ISBN978-4-8067-1653-2.html
深澤さんのサイトもぜひ見てください。
2023/10/29 UP!
オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」
M1. NORWEGIAN WOOD / THE BEATLES
M2. TREES / TWENTY ONE PILOTS
M3. FIELDS OF GOLD / STING
M4. AMAZING GRACE / SARAH BRIGHTMAN
M5. エイリアンズ / キリンジ
M6. A HARD RAIN’S A-GONNA FALL / BOB DYLAN
M7. I STILL HAVEN’T FOUND WHAT I’M LOOKING FOR / U2
エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」