2021/12/17 UP!
千葉には歴史的な遺構がたくさんあります。その中でも特に有名なのが貝塚です。
千葉県がその数日本一を誇る「貝塚」。中でも日本最大級、縄文時代の遺跡についてご紹介します。
国内の貝塚のおよそ3割が千葉県で発見されているんです。縄文時代は今よりも暖かく、海岸線はもっと内陸にあって、栄養豊富な東京湾の海の幸に恵まれた千葉には、すでにたくさんの人が暮らしていといいます。千葉市若葉区には「貝塚」という地名もありますし、高速道路にも「貝塚インター」があります。その近くにある日本最大級の縄文貝塚・加曽利貝塚をご紹介していきます。

加曽利貝塚は、千葉市若葉区にある日本最大級の貝塚で、直径およそ140mでドーナツの形をした北貝塚と直径およそ190mで馬の蹄の形をした南貝塚の2つが上空から見ると8の字形をつくっています。2017年には国の特別史跡に指定されている日本の歴史にとっても、重要な場所なんです。小学校の時に社会科見学でいかれたという方もいらっしゃると思います。

加曽利貝塚の敷地は縄文遺跡公園となっていて、その中に、千葉市立加曽利貝塚博物館があります。ここには発掘された縄文土器や石器、動物、魚、人の骨などが展示され、当時の人々の生活の様子を知ることができます。また、現在も発掘調査が行われているそうなんです。今回は千葉市立加曽利貝塚博物館の長原亘さんにお話を聞いています。

長原さん:加曾利貝塚は日本で最も重要な貝塚。縄文時代の大きな貝をさまざまなことで利用した村人が作った最大の村というふうに思ってもらったらいいと思います。で、実際には貝塚の貝があるところだけが遺跡というわけではないので、だいたい15.1ヘクタールぐらい・・東京ドーム3個分ちょいぐらいの大きさが史跡に指定されているんですが、指定外のとこも含めて、かなりの広範囲で遺跡として認識されています。実際には加曽利貝塚の場合は、すぐ近くまで海があったわけではないということが分っています。地図の上の直線距離だと5キロぐらい離れていた。今千葉市内という意味で言うと、千葉神社だとか千葉県庁があるあたり、あの辺りぐらいまでしか海は入っていなかったのではないかという風に今のところ考えているので、実際に川を伝って行き来するとなると、直線距離で5キロなので、もう少し移動距離はあったんじゃないかなっていうふうに思います。
海岸線から五キロも離れていて、おそらく道は真っ直ぐでなないでしょうから実質十キロぐらいあったかもしれません。片道2時間ぐらいかかっていたかもしれない。だから海に貝を取りにいって、また帰ってくるとなると、半日以上かかってしまうのではないかということでした。
さて、貝塚と何か?という質問に、多くの方は「貝を食べた後の貝殻を捨てていた場所」「ゴミ集積の場所」と習ったと思います。教科書にもそう書いてありました。でも、検証などが進んでくると、どうあらそうでもなさそうだという説が上がってきたようなんです。

長原さん:実際にですね、発掘調査をしてみたりとかしますと「ゴミ捨て場」という側面は否定はできないんですけど、実際には縄文人、わざわざ貝がある所を掘って人骨を埋葬・・お墓として使ったりだとか、縄文時代の犬、縄文犬をわざわざ穴掘って埋葬してあげるですとか、貝層そのものの上をですね、ならして人がいろいろ何かお仕事をしたりだとかしている。そういうところをわざわざ使うということは、村の一部として、普通に活用する空間であったってことは間違いないだろうと。なので、そういう意味で言うと単なるゴミ捨て場ではない、ということが貝塚を研究をしている方の中では常識的な話になってきていると思ってください。今後さらに貝塚の調査をして研究していく中で、もしかしたら決定的にただのゴミ捨て場では無いっていう証拠が出てくる可能性はあるだろうな、とは思っています。

さて、その加曽利貝塚にはどんな貝が埋まっているのでしょうか?
長原さん:イボキサゴという貝(小型の巻貝)は、小さいがゆえに実として食べるのは、とても満足感得るにはかなりの労力が必要なんですね。ただ、それをとったものを食べて美味しいんだけども満足感は得られないわけで。だけどもたくさん持ってきている、わざわざ。ということは何か目的があって持ってきてるという風に考えざるを得ないんですが、その目的もまだ明確なものはわかっていません。ただ、1つの考え方として最近加曽利貝塚で推している考え方という意味では、実際にお湯に入れてですね、煮出していくと“いい感じ”にお出汁が取れるんですよね。そのお出汁でとれたものに、例えば山のもの、山菜でも良いし、山のものでも良いし、味付け無味無臭だったものに、そういう味付けがして食べやすくする。そういう効果を狙った調味料の役割のもあるのではないかという考え方も最近推してはいます。ただ、それはたぶんいろんな用途の中の一部なんじゃないかなっていうふうには思います。

なんと、出汁をとっていたのではないかという話なんですね。それならばたくさんの貝が必要になります。しかもそんな生活が2000年以上続いているとなるとそれはそれは大量になるわけです。
さて、加曽利貝塚の発掘調査はどのくらい行われたんでしょうか?全部を発掘していないのには理由があり、そしてロマンがありました。
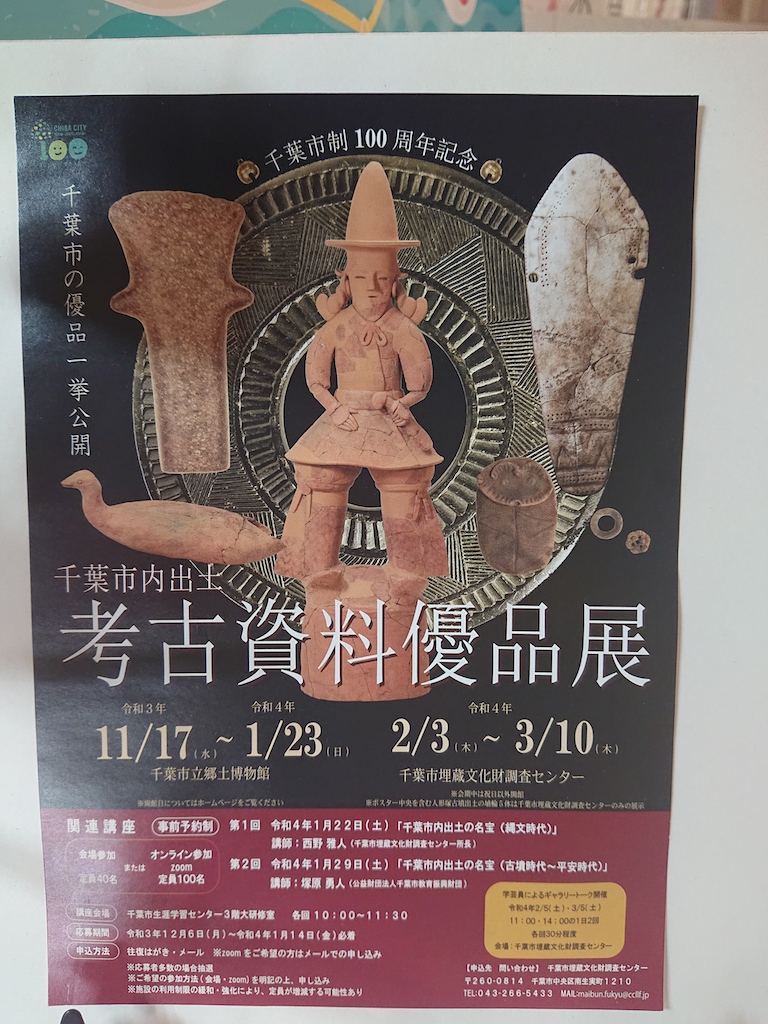
長原さん:そもそも加曽利貝塚だけで考えても、発掘調査の面積は15 haぐらいのうちの8%程度しかまだ調査を行っていません。なので発掘調査をしていない所には、まだまだ未知の情報がたくさん眠っているということは間違いありません。基本的に発掘調査は別の見方をすれば、破壊とイコールなので、今、現代の発掘調査の技術よりも、10年後・20年後のほうがもっとさらに精緻に細かく、さらに技術が発達している可能性も当然あるわけで、そういうときに、その時まで待って発掘調査をした方が、もしかしたら、日本の歴史的な遺産の1つとしてはいいのではないかというふうに考えている研究者は多いので、我々はなるべく壊さないで遺跡を理解を深まるような調査研究法というのもどんどん作らなきゃいけないというふうに考えています。掘ってみなくても、「あ、これ、〇〇」ってわかる時代も多分遠い未来ではなく出てくるでしょう。そういうことになってから、また調査することがたぶんまあいいのではないかと、私なんかは考えています。

確かに!発掘調査は、破壊するということ。元には戻せない。でも技術がさらに進歩すれば全部を掘り出さなくても、何が埋まっているのかがわかる時代がきっとくる。 例えば、地上から地中に向けてレーダーを発射して、その反射などから地面の中の構造物を探すとかは既に始まっているそうです。もちろん、全部を掘り起こすことは可能なんだそうですが、もしかしたら大事な発見を見落としてしまうかもしれない心配もある。8%の発掘実績でも、出土したものから得られる膨大な資料、推察そして検証など、やることがたくさんあって、間に合わないぐらい。ならば、残してある部分については未来の発掘調査に委ねようということなんですね。

貝塚には未知の情報がたくさん眠っている。まさに縄文時代のタイムカプセルですね。
未来にきっと新しい発見があるってロマン広がりますね!

コロナが落ち着いて学校などの社会科見学も徐々に再開されているそうです。縄文時代の人々がどう暮らしていたのか、貴重な資料や、発掘現場も目の当たりにすることができる千葉市立加曽利貝塚博物館。縄文文化の謎とロマンを探しにお出かけしてみてはいかがですか?








