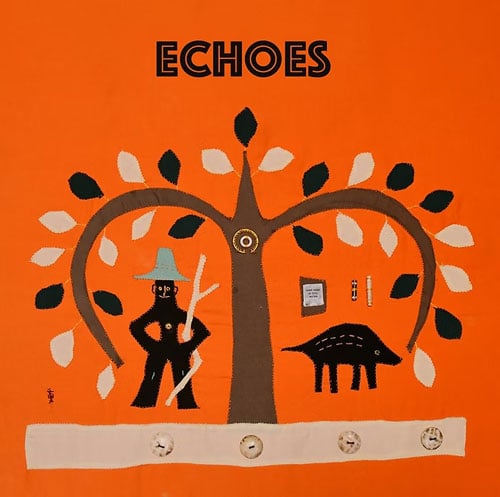2022/11/20 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、「無人島プロジェクト」の代表「梶 海斗(かじ・かいと)」さんです。
梶さんは1988年生まれ。京都出身。同志社大学卒業後、リクルートに入社。その後、無人島ツアーを企画し、2016年に株式会社ジョブライブを設立、代表取締役に。そして現在、無人島プロジェクトの事業を展開されています。
きょうはそんな梶さんに無人島体験ツアーや、島でのキャンプ生活がもたらす効果などお話しいただきます。
☆写真協力:無人島プロジェクト

生きるを学ぶ体験
※いったいどんなプロジェクトなのか、お話をうかがっていきましょう。まずは、無人島プロジェクトについて教えてください。
「はい、日本全国には6400近くの無人島があるんですけれども、そういった無人島にお客様をお連れして、『生きるを学ぶ』体験というのを提供しています」
●無人島プロジェクトのテーマが「生きるを学ぶ」なんですね。
「そうですね。まさに来ていただくお客様には『生きるを学ぶ』を大切にしていただきます。みなさん、日々色んなことをされていると思うんですね。仕事をしたりだとか趣味にいそしんだりだとか・・・・実はその生活の根底に、食べるとか水を飲むとかそういったところがありますよね。
無人島に行くと、さあご飯を食べようと思っても食料調達から始まりますし、調理しようと思うと火を起こさなくてはいけないところがあって、それが当たり前に今の日常では提供されていることに気付けたりもするんですよね。
無人島でしか気付けないことがたくさんあって、そういったことも含めて、生きるとは何なのか、生きることにどういうことが含まれているのかを、少し気付いていただくっていうようなことですね。生きるを学べるような価値があるかなと考えていまして、それがひとつテーマになっています。
一方で、無人島というくくりで言いますと、先ほども言いましたように日本全国に無人島は6400もあって、(有人島を含めると)日本には6800近くの島があるんですけれども、人が住んでいない島のほうが多いんですね。それをどう活用していくのかが、地域を盛り上げるためにも非常に重要になってきますので、そういう活用プロジェクトも、ひとつのテーマだと思います」
『十五少年漂流記』に憧れて

※梶さんが個人的に、初めて無人島に行ったのはいつ頃なんですか?
「初めては、私が19歳の頃ですので、2007年から2008年ぐらいじゃないですかね」
●どこの無人島に行かれたんですか?
「私は京都出身ですので、京都から近い島はどこにあるのかを、インターネットが(今ほど)発展していない中でなんとか調べて、たどり着いたのが瀬戸内海で・・・瀬戸内海の無人島に京都から行ったのが初めてでした」
●どうしてまた無人島に行ってみようと思われたんですか?
「無人島っていう言葉が冒険心をくすぐるというか、そういうのがあると思うんです。自分自身は小学生の時に、『十五少年漂流記』っていう小説を読んだんですね。ロビンソン・クルーソーみたいなやつなんですけど・・・15人の少年が、船が難破して、たどり着いたのが無人島で、そこで共同生活をしていくっていうストーリーなんです。
仲間と一緒に限られた環境で生き抜いて、絆ができていくっていうようなことに対して憧れがあって、いつか(無人島に)行ってみたいなっていうことを、ずっとなんとなく心のどこかに持っていました。それが大学生になった時に何か新しいことをしたい、キャンプで何かできないかなと思った時に無人島に行ってみようって、ふと思い立ったんですね。
行けるかどうかは全然わからないので、手探り状態だったんですけど、まずは人口が30人とか40人ぐらいしかいないような小さい有人離島にフェリーが出ていますので、そこに行って漁師さんに頼み込んでみたんですよ。そうすると無人島に渡してあげるというような話があって、今こうなるとは(その時は)思っていませんけど、そこが本当にいちばん最初の始まりでしたね」
●それを今度はビジネスにしようと思われたのは、いつ頃なんですか?
「思い立ったのは社会人2年目ですので、2013年から2014年ぐらいのタイミングだと思うんです。無人島に初めて行ってから毎年行くようになったんですよ。友達を連れて行くとすごく喜んでくれるんですね。
こんな体験できるところないし、誘ってくれる友達もなかなかいないから、自分が楽しんでいたのと同じように仲間も楽しんでくれていたんです。そういう人たちが増えていく・・・次は誰を連れて行きたいとか、将来子供できたら子供と行きたいよね、みたいな話とかをもらうようになって、なんとなく心の中に、需要はあるんだなって思っていたんだと思います。
で、いざ自分でビジネスを立ち上げようっていう気持ちになった時に、何をテーマにするのかを考えた時に、そのひとつとして無人島をやりたいなって思ったんですね」
(編集部注:梶さんは小学生の頃にYMCAのキャンプ教室に参加。そのとき、キャンプのスキルを身につけていたので、無人島に初めて行ったときでも、不安はなかったそうです。子供の頃からアウトドアや自然が大好きだったそうですよ)
個人から企業向けプランまで

※無人島プロジェクトでは現在、どんなツアーや事業を行なっているんですか?
「まずは、今までお話ししたような私のルーツである個人向けのツアーですね。日本全国、みなさん、無人島にほぼ行ったことない人ですし、キャンプも初めてという人が20%から30%ぐらいはいらっしゃるので、アウトドアにそんなに慣れていないかたでも無人島で2泊3日、初めて出会った仲間たちと冒険するツアーをやっているんです。
これがすごく人気で、今までで1500人近くのかたにお越しいただいています。1回あたり20人から30人で行きますので、それなりの回数になるんですけれども、みなさんすごく満足して、初めて出会ったと思えないぐらい仲良くなって、たくましくなって(無人島から)帰ってきてくれます。これが個人向けのツアーで、我々スタッフとかインストラクターが付いていくパターンです。
もうひとつが仲間たちだけで無人島を借り切って、自分たちでキャンプするプランもやっています。これが『無人島セレクト』っていう名前でやっているんですけど、島を選べるんですよ。島がいくつかあって、その中から(参加者が)この島いいな〜って思ったら、そこに行く船の手配だとかキャンプ道具の手配は我々でさせていただきます。
無人島で過ごす注意事項とかそういうガイダンスをさせていただいたうえで、みなさんで1泊2日楽しんでいただきます。もちろん、なにかあって連絡いただいたらすぐ助けに行くんですけど、助けに行くようなことはあまり起きないですね。そういう個人向けプランもあります。
あとは我々、日本全国の無人島、あちこちと提携していますので、そういったところをオーダーメイドで使わせていただいています。
例えば、無人島を借り切ってイベントをやりたいとか、子供向けの体験教室をやりたいとか、企業研修で新入社員にたくましくなる経験をしてほしいとか・・・やっぱり助け合わないと無人島では生きていけないので、難易度は会社によって様々なんですけど、こんな体験をしたいとか、そういったお話をうかがいながら、ゼロから一緒に作っていくオーダーメイド・プランがあって、これも人気ですね」
(編集部注:無人島プロジェクトでは現在およそ100の島と提携しているそうです)
ルールは敬語禁止!?

※先ほどお話にあった、アウトドア初心者のかたが多く参加する個人向けツアーで、20人から30人の参加者が2泊3日の無人島体験をする企画、これは「ベーシックキャンプ」というツアーなんですが、このツアーには、こんなルールがあるそうですよ。
「ルールは敬語が禁止(笑)。日常では社会的な立場とか年齢とか、いろいろあるけれども、 今からみんなは無人島に行って、無人島に漂着したんだと。だからひとりの人間として助け合わなきゃいけない。助け合って3日間、きちんと生き抜いて帰ってこようね。
もちろんスタッフはいて、そのためにサポートはするけど、みんなで生き抜くことが今までにない経験で楽しいことだから、それをサポートするガイドみたいなもんですよ。だからみんなで、スタッフも含めた30人で、3日間生きていきましょう! っていうガイダンスから始まるんですね」
●へぇ〜、面白いですね。
「もちろん敬語は、慣れなかったら、最初は出ちゃうんですけど、徐々にみんな慣れていきますね。何をするにも、火を起こすにも食料を調達するにもテント建てるにも、助け合わなきゃいけないので、固くなっちゃっているのが自然に取れていって、2日目の夜にはもう明日終わってしまうのが寂しいねとか、生き抜くことがどんなに大変なのかを一緒に理解し合えたねとか、ちょっと苦しいことを一緒に分かち合えた仲間たちになって帰ってきてくれるんですよ。

無人島を活用していろいろやらせていただいていますけど、私がこの無人島の企画をやりたいなって思えたのは、非日常体験を通じて人生の転機になり得るような、すごく濃い3日間を作れるところが、とても魅力的だなと思って始めたってことがあります。
初めましての人たちと、敬語禁止ルールとかがある中で、3日間一緒に助け合って生き抜くツアーにはなるんですけれども、ただ体験をするだけではない深さとか、そういったものも提供できているんじゃないかなって思っています」
(編集部注:無人島プロジェクトでは、ロケ撮影のコーディネイトも行なっています。例えば、ゴールデンボンバーの全国ツアーファイナルの無人島ライヴをサポートしたこともあるそうです。無人島からの配信ライヴで、その映像にはドローン撮影もあり、島の全景が映し出され、ロマンを感じたそうですよ)
「生きる」を全部やってみる
※無人島でのキャンプは、参加者のかたの意外な才能が発揮されたりすることもあるんじゃないですか?
「むちゃくちゃありますよ。本当にひとりひとりできることもそうだし、キャラクターも違うので、みんなの中心になって盛り上げることが上手な子もいますし、みんなが見てないところで、”これから暗くなると思って”と言って、大量の焚き木を持ってきてくれる子がいたり、誰も気づかなかったわ、それ! っていうような・・・。

魚を捕ってくる子もいれば・・・スキルっていう観点でいうと、料理が上手な子とか、歌を唄うのが上手とか踊れるとか泳げるとか、それぞれ人生があって、できることが違うので、それを生かしていただける環境があって、みんなの役に立つ、っていうような状態なので、本当にバラバラな個性があって楽しいですよね」
●サバイバルに近い状態ですから、積極的に自分たちで動かなきゃっていう気持ちにもなりますよね。
「そうですね」
●動かなきゃ始まらないですよね。
「それがいいところだとは思うんですけどね。何もしないってこともできるんですけど、何もしなかったら楽しくないですし・・・」
●そうですよね〜。
「みんな、無人島って環境は、着いちゃったんで諦めるんですよね(笑)。諦めた上で、いかにみんなで楽しい時間を過ごすのか、どうやって過ごせるのかっていうことに、自然とフォーカスしていけるので、初めて出会ったんだけど、ある意味ひとつの方向を向きやすいのが面白いところですね」
●参加されたかたに、価値観が変わったとか人生感が変わったとか、そんなかたもいらっしゃるんじゃないですか?
「ありがたいことに、そういうお話をいただくことも多いですね。100円持っていれば、わずか1〜2分でコンビニで肉まんが買えて、めちゃめちゃおいしいじゃないですか。それがどれだけ恵まれたことなのか、みたいな話とか・・・お布団ってすごいんだなみたいな、そんな話もありますね。
あとは、日常の日々の暮らしが、すごくありがたいことなんだと気づいて、違う場所に移住をすることを考えるかたがいたりとか、人々と助け合って生きていくことに、もっとフォーカスした生き方をしたいっていうので、都会からちょっと違うところに生活(の拠点)を変えたりだとか・・・。
逆に結婚の決意をされるかたとか、離婚を決意するかたとか・・・いろんな感情が溢れるんだと思うんです。ねらっているわけじゃないですけど、島で出会って結婚するかたがいたりもしますね」
●ここまで生きることを全力でするって、都会にいたらなかなかないですよね、そういう経験ってね。
「ないと思うんですよ。便利なものはいっぱいありますし、逆に言うとそれは人の力だと思うんですけど、ただ人生に一度ぐらいは、自分で自分の生きるを全部やってみるっていう体験があってもいいかなとは思いますね」
「やりたい」をかなえる
※無人島プロジェクトの、12月以降、または来年のツアーでおすすめはありますか?
「やっぱり無人島っていうと夏のイメージ強いじゃないですか。みんなヤシの木の生えた常夏の島を思い浮かべると思うんですね。暗い曇り空のゴツゴツした岩肌の、風が吹きすさぶ島には行きたくないっていうのが本音だと思いますので(笑)、我々のツアー自体はだいたい夏なんですよ。ゴールデンウィークとか7日から10日ぐらいの連休でやることが多いんです。
ただ、先ほどお伝えした少数のグループで、無人島を借り切って使っていただける『無人島セレクト』のプランだったりとか、あとはやりたいことに合わせた企画を提供するオーダーメイドのプランは年中やっていますので、そこはお問い合わせいただければと思います。
たまにすごい強者が、真冬の無人島サバイバル体験をやりたい、YouTubeで配信したいとか、そういったお話もいただくことがあるので、無人島でこれをやりたいっていうのをかなえるのが我々かなと思いますので、まずはお問い合わせいただければと思いますね」
●では、最後に梶さんにとって無人島とは?
「無人島だから人の温かみだったり、社会の温かみだったり、生きることに対する大切さを感じさせてくれる場所だなって思っています」
INFORMATION
無人島プロジェクト

無人島プロジェクトで実施しているツアーは以下の通り。
参加型の個人向けツアー、2泊3日の「ベーシックキャンプ」は現在、姫路と博多での開催となっています。
仲間と行く個人向けツアー「無人島セレクト」は、行きたい無人島を選べるプランです。
ほかにも研修や会社の行事を無人島で行ないたい法人向けのオーダーメイド・プランなどもあります。
詳しくは、無人島プロジェクトのオフィシャルサイトをご覧ください。
◎無人島プロジェクトHP:https://mujinto.jp
2022/11/13 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、北極冒険家の「荻田泰永(おぎた・やすなが)」さんです。
荻田さんは1977年、神奈川県生まれ。21歳のときにたまたま見たテレビのトーク番組で、冒険家の大場満郎さんが若者たちを連れて北極に行くことを知ったそうです。
エネルギーを持て余していた荻田さんは、北極に行ってみたいと思い、大場さんに手紙を書き、大場さん主宰の「北磁極を目指す冒険ウォーク」に参加することに。そしてカナダの北極圏から北磁極までの700キロを、食料などを積んだ重いソリを引いて、35日間かけて、徒歩で走破。
実は荻田さん、参加する前は、アウトドアの経験はまったくなく、海外に行くのも、飛行機に乗るのも初めてだったそうですよ。
その後、たったひとり徒歩で、それも食料などの補給を受けずに北極点を目指す冒険にチャレンジするなど、20年間に16回、北極に行き、北極圏をおよそ1万キロ以上、移動。2018年には「植村直己冒険賞」を受賞、国内外で注目されている北極冒険家でいらっしゃいます。
きょうはそんな荻田さんに、20年以上通い続けている北極の魅力や、先頃出された絵本『PIHOTEK(ピヒュッティ)〜北極を風と歩く』のお話などうかがいます。
◎写真:荻田泰永

北極冒険の扉を開く
※2000年に冒険家・大場満郎さんの「北磁極を目指す冒険ウォーク」に参加されて、北極に行ったわけですけど、初めての北極体験は荻田さんに何を残しましたか?
「何を残したんでしょうね。最初は大場さんの旅に参加する前は、なんか広い世界に出てみたいなっていう思いはありながらも、出方が分からないし、出る扉の存在も分からなかった。どの扉を開ければいいのか全く分からないし、(大場さんが)扉の存在を教えてくれたし、開けたらどういう世界が待っているかを、一回体験させてもらったんです。
その翌年から今度はひとりで行くようになるんですけども、やっぱり一回(扉を)開けると、次もう一回、自分で開けてみようっていうところに、えいや〜っと行けるので、そのきっかけを作ってもらったって感じですね」
●その扉を開けて、もう20年以上、北極に通われていますよね。何がそんなに荻田さんを惹きつけるんですか?
「よく(言われるのは)初めの北極で夢中になっちゃったんですね、とかね。翌年からひとりで行くんですけどね。確かに魅力があるんですけど、正直に言うと別にほかに行けるところがなかったから、また北極に行っただけです。
行動力が本当にある人は、たぶん大場さんのテレビを見る前にもう動いているんですよ。でも私はその行動力はなかったんですね。動けなかったんです。だから大場さんの計画、言葉に乗ったんです。連れて行ってもらったんです。”行った”んじゃないんです。”連れて行って”もらったんです。
翌年、北極に行くんですけども、その時も北極以外行ったことがないから、今度はひとりで動かなければって時に、必然的に行ける場所は北極しかないわけですよ。土地勘があるのはそこしかないんで・・・。
だから魅力があったから重ねて行ったっていうよりは、最初のうちはそこしか行けないから、もう1回行ったっていう要素が強くて・・・ただ何度も重ねて行くと、今度は北極に行く理由がちょっとずつ見つかってくるし、面白さとか難しさとか、そういうものが分かってくるんですよね。
例えば現地で、昔から住んでいるイヌイットの人たちと一緒に狩りに行くと、やっぱり日本とは違う常識に出会えるし、違う価値観に出会えるし、全く違う自然の世界がそこにあるし、そういうのも魅力ですね。
極地冒険は、やる人が少ないので情報も少ないですし、装備もないです。ないからこそ自分で考える、自分で工夫しなければいけない。アウトドアショップに行ってお金で解決できないんですよね。
ないものは自分で作るとか、地元の人たちはどんなものを使っているんだろうっていうのを観察して、そこから真似るとかね。なんかエッセンスを盗むとか、そういうのが必要になってくるんですけど、それがまた面白い。そこに主体性があるんですね。道具をお金で解決できるって、そこにはあまり主体性がないんですよ。そういうところの面白さですかね」
(編集部注:荻田さんが北極冒険の拠点にしているのは、おもにカナダ北極圏のレゾリュートという、人口が200人ほどの小さな村だそうです。食料や装備などは、もちろん日本で準備していくそうですが、足りないものはカナダのバンクーバーほか、レゾリュートでも調達するとのこと)
いちばん怖いのは自分自身
※荻田さんは2012年と2014年に北極点に向けて、無補給単独徒歩での到達にチャレンジされました。北極点は南極と違って海の上、なんですよね。
「そうですね」
●ということは、氷の上をずっと歩いて行くっていうことですよね?
「そうですね。みなさんはあまり北極と南極って何が違うんだろうとか、イメージがわきづらいとは思うんですけど、大雑把にいうと南極は”南極大陸”であって、北極の場合は”北極海”って海なんですね。
私は南極は1回行ってますけども、メインは北極であって、北極の場合はだから海の上を歩く、海の表面を歩くんです。
北極海ってまあ広いわけですね。対岸はロシア、シベリア、ユーラシア大陸、その反対側に北米大陸があって、2000キロから3000キロ四方の大きな海になっていますけども、平均の水深でいうと2000メートル近くあるんです。
海の深さが平均して2000メートルあるんですけど、氷の厚み、海の表面の氷の厚みは平均すると2メートルくらいのもんですね。2000メートルの海の水に対して、表面の2メートル凍っているだけなんで、本当に薄い膜が張っている程度です。その上を歩いて行くのが極地の冒険です。薄膜なので、氷は流れるし、動くし、風の作用で流れたりとか、海流で流れたりとか、表面の氷は激しく動き回るんです。
だから、割れたりとか、ぶつかったりとか、流されたりとかっていうのはしょっちゅう起きる。平らなスケートリンクみたいな平原とか氷原を想像するかもしれないですけど、現場に立つと凸凹なんですよ。海辺のテトラポットを積み上げたみたいな氷が、自動車大のブロックが、何個も積み上がった壁のような状態が永遠と続いているのが北極海ですね」

●危険だらけじゃないですか! 何がいちばん怖いですか?
「いちばん怖いのは自分自身ですよね。我々、東京で生活していても危険はいっぱいあるじゃないですか。みなさん、自然の中に行くと、危険でしょ危険でしょって言うんですけど、私は都市のほうが予測不可能な危険がはるかに多いと思うんです。
なぜかっていうと、都市の中では人為的な作用で、どうにもできない要素があまりにも多いんです。他者が多いから・・・。では極地でそういうことが起きるかっていうと、極地っていうか自然の中ってないんです。自然の中で起きることは、全部自然の法則に則っているんです。
よく言われるのが、自然の中では何が起きるか分かんないでしょって・・・。分かるんです。ただいつどこで起きるかが分からない、もちろんね。北極を歩いていても、起きる危険の要素は種類をあげつらえば、数は少ないんですよ。寒さとか、ホッキョクグマとか、風とか、足元が薄い氷であるとか、数えられるぐらいのものしかないんです。
都市だったら、数えきれないぐらい要素がありますよね。その要素はすべて他人が関わっているんです。全く予測不可能です、こっちのほうが・・・。でも極地は起きる要素は数限られているし、そのひとつひとつが、なぜどういう理由で起きるかがちゃんと分かるんですよ」
●想定できるってことですね。
「できるんですよ。ただそれを事故に結びつけちゃうのは、自分自身の経験不足だったりとか、知識不足だったりとか、準備不足とか、装備が不足しているとかっていう自分の中の問題だから、いちばん怖いのは自分自身ですね」
(編集部注:荻田さんは2018年に日本人として初めて、南極点・無補給・単独徒歩での到達に成功されています。荻田さんいわく、南極は大陸でほぼ平坦なので、極端な言い方をすると、北極よりは簡単だったそうですよ。北極の経験があるからこその成功だったんでしょうね)
できることのちょっと上!?
※食料や燃料などを補給せずに、ひとりで歩くスタイルは、冒険のハードルを一気に上げている気がするんですけど、どうして、そこにこだわっているんですか?
「なぜかって言ったら、そうしないとできちゃうから。要は無補給は外部からの物資補給を受けない。外部のサポート、人の力を借りない。単独はひとりで徒歩、機動力は自分の体っていうことですね。つまり条件は”無補給・単独・徒歩”の3つです。
無補給じゃなかったら、外部からの物資補給を受けるっていうこと。単独じゃなかったら複数人ってことですね。徒歩じゃなかったら機動力を使うってことです。スノーモービル使うとか、犬ぞりを使うとか。
要は物資補給を受けたら、北極点(到達)なんて今の自分の力だったらできちゃう。初めからできると分かっていることをやったって、何にもやる必要ないじゃないですか。ただの確認作業なので・・・。
これは自分ができるかな、できないかなっていうのを見極めて、今自分が確実にできることのちょっと上をやらなかったら、そこのちょっとの部分が成長なわけですよ。確実にできることの下をやったところで成長はないんですよね。
かといって、あまりにも飛び越えすぎて、確実にできることと、やろうとしていることに、あまりにも乖離(かいり)があると、それは無謀と言われることになっちゃうので、 そのさじ加減は全部自分で決めるんですけどね。で、なんでそれ(無補給・単独・徒歩)をやるかっていうと、 それが自分ができることのちょっと上のところだから、それを選んだだけですね」

●なるほど、そういうことなんですね。当然、多めに食料とかは持って行くってことですよね?
「ある程度多めに、といっても、そんなにたくさんは持っていかないですけどね」
●テントとかも含めて装備や物資は、どれぐらいの重さになるんですか?
「大体50日とか60日分の食料や装備を引くんですけど、100キロから120キログラムぐらいですね」
●へ〜! それをソリに積んで引っ張るっていうことですか?
「そういうことですね。自分の力で、体にハーネスっていうベルト付けて、腰からロープを取ってソリにつないで・・・。ソリといっても船の形でボート状のものなんですけど、足元はスキーを履いて、自分の力で引っ張っていくっていうスタイルですね」
※北極の場合、冒険に適した時期はいつ頃なんですか?
「北極の場合は海が凍った時を狙っていくんですね。 北極といってもやっぱり季節の巡りがあるので、北半球ですから日本と同じです。8月ぐらいがいちばん暖かくて、そうすると海の氷も大体、全部じゃないですけども、結構溶けるんですね 。また青青とした海に戻るんです。そうなると、もちろん歩けない。
いちばん歩ける時期が3月前後ですね。その時期がいちばん気温も下がって、いちばん氷が分厚く安定した時を狙って行く、っていうのが2月から3月、4月、5月の上旬ぐらいまでですね」
●最低気温だと、どれぐらいになるんですか?
「私が軽減したのはマイナス56度までは、動いていますね」
(編集部注:荻田さんが経験したマイナス56度、想像できない世界ですよね。荻田さんによれば、現地で低温に体を慣らすトレーニングを行なって、冒険の旅に出るので、時にはマイナス30度でも暖かく感じることがあるそうです。寒さとは温度という数字ではなく、寒く感じるかどうかだとおっしゃっていましたよ)
イヌイットからもらった名前!?
●先頃「PIHOTEK (ピヒュッティ) 北極を風と歩く」という絵本を出されました。私も読ませていただきましたけれども、たったひとりで北極を歩く”僕”の1日が描かれていますよね。この僕を通して 生きるということをすごく考えさせられたんですけれども、このタイトルの「ピヒュッティ」にはどんな意味があるんですか?

「これはぜひ本を読んでいただきたいなっていうのもあるんですけど、ネタバレをしちゃうと、私が北極のイヌイットの村で、イヌイットのおじさんからもらった名前なんですね。
イヌイットってよそから来た人たちと親しくなると名前をくれるんです。 で、ピヒュッティっていう名前をつけてくれたんですけど、その意味は”雪の中を歩いて旅をする男”っていう意味があって、お前にぴったりだろう! って、つけてくれたっていうのがエピソードですね」
●初めてピヒュッティという言葉を聞いた時は、どんなことを感じられました?
「語感は可愛いらしいじゃないですか(笑)。 だから、なんかしっくり来るような来ないような、みたいな感じでしたけど・・・嬉しかったですね」
●この絵本は荻田さんがストーリーを考えたんですよね?
「そうですね」
●絵本のイメージは、いつ頃からあったんですか?
「2020年の年末ぐらいから動き出して、実際、完成して発売したのが今年の8月です。だから1年半以上やってましたね。
きょうの話を通して、私かなり理屈でしゃべってるんですよ 。理屈っぽくしゃべってるし、たぶん理屈をだいぶしゃべってると思うんですけど、こうやって言葉で説明できる部分は、実は私のやっていることもそうだし、世界全体を見渡しても、言葉で表現できる部分は本当にごく一部でしかないんですね。
例えば、ホッキョクグマは言葉を持ってないわけですよ。ホッキョクグマは何を考えているかって言葉では表せないですよね。でも彼らだって何かを考えているわけですよ。それは、人間の言葉で書き起こそうと思ったら言えるけども、でも人間の言葉で書き起こした瞬間に、それはホッキョクグマの考えていることじゃないし、とかね。
だからなんていうかな・・・言葉の限界はどうしてもあるし、私がやっていることって冒険とか探検って言われますけども、 日本語を分解したら、”冒険”は危険を冒す、険しきを冒す、危ないことをするっていう意味ですよ。”探検”は、探り調べること、探査・検査・検証とかっていう意味ですから、探検っていうのはね。
私は確かにさっきも言ったように、危険なことはあるかもしれないけど、危険を冒しに行っているわけじゃないし、 危険であるのは(北極に)行っている間の付随事項みたいなものであって、それがメインじゃないんですよね。
何かを調べに調査に行っているかって言ったら、そういうわけでもないし・・・そうなると、私がやっていることは、探検とか冒険っていう言葉で100パーセント言い表しているかっていうと、全く言い表せていないんです。
じゃあなんですかって言っても、 言葉がないから言い表せないんですよ。言葉で表せられないんだったら絵で表現するとか・・・別の表現方法も人間は持っているんですよね。そういうイメージもあって、絵本を作ってみようかなっていうのはありますね」
(編集部注:絵本『PIHOTEK(ピヒュッティ)〜北極を風と歩く』の絵は、絵本作家で画家の井上奈奈さんが担当されています。荻田さんは以前から井上さんとは知り合いで、絵を描いてもらうのは、この人しかいない、と思ってお願いしたそうです。お陰で、深味のある“大人の絵本”に仕上がったとのこと)

テーマは「風と命」
※この絵本を通して、どんなことを伝えたいですか?
「そうですね。感じ方は人それぞれで全然いいんですけども、今回、私が書いた絵本は、”風と命”をテーマにしています。命をテーマにすると、生きる生かされるとか、食べる食べられるとか、主体と客体に分けた話にどうしてもなりがちなんですけど、命に主体も客体も本来ないはずなんですよ。
全部つながっているわけですから・・・全てつながっていますよね。地球っていう宇宙から閉ざされた空間の中で、40億年ほど前に生命が生まれてから、ずーっと繰り返しているわけですよ。
私の体を作っているカルシウムとかアミノ酸とかっていうのは、ある日突然、無から急に発生したものじゃなくて、分子レベル原子レベルでいったら、100年前とか1万年前とか1億年前には何かの植物だっただろうし、土の中に埋まっていたかもしれないし、何かの動物だったり・・・そういう物質が私を作っているわけであって、そういった時に私という主体はどこにあるかって言ったら、そんなものないんですよね。
そういうつながり、その関係性全体こそが主体であって・・・だから命っていう話を書こうかなって思った時に、主体と客体に分けない話にしようと思って、全部が交じり合っていくような話にして、ああいう感じになりました! ぜひみなさんに読んでもらえたら嬉しいですけど・・・」
(編集部注:荻田さんは、北極に行くきっかけを作ってくれた冒険家の大場満郎さんがしてくださったように、2019年に若者たちを連れて、カナダ北極圏をおよそ1ヶ月かけて600キロ歩いたそうです。20年前の自分と旅したような気分になり、とても新鮮だったそうですよ。この活動はできれば、今後も続けていきたいとのこと)
INFORMATION
荻田さんが先頃出された絵本は、北極をたったひとりで歩く“僕”の1日が描かれ、北極の冒険を追体験できます。井上奈奈さんの、柔らかいタッチの絵とのコラボレーションが深みのある世界を醸し出しています。素敵な大人の絵本、ぜひ読んでください。講談社から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎講談社HP:https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000363049

荻田さんは去年、神奈川県大和市に「冒険研究所書店」という本屋さんを開業されました。冒険に関する本は多いものの、普通の本屋さんだそうですよ。詳しくはぜひ荻田さんのオフィシャルサイトを見てください。
◎荻田泰永さんHP:https://www.ogita-exp.com
2022/11/6 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは漫画家、そしてイラストレーターの「まつおるか」さんです。
まつおるかさんは1994年生まれ、大阪出身。小さい頃から絵を描くのが好きで、中学生の頃から漫画家になりたかったそうです。そして現在はプロとして活躍、シャチを始めとする海の生き物のコミック・エッセイやキャラクター・グッズ、LINEのスタンプなどが人気なんです。特に可愛いシャチのキャラクターで知られています。
ペンネームのまつおるかは、シャチの別名「オルカ」を文字っていて、それほど、シャチにぞっこんなんです。
きょうはそんなまつおるかさんに、大好きなシャチへの思いや、「すみだ水族館」の愛くるしいペンギンのお話などうかがいます。
☆イラストレーション:まつおるか
☆誌面提供:まつおるか著『下町ペンギン物語』(発行:株式会社KADOKAWA)

可愛くて強いシャチ
※シャチは英語名で「キラーホエール」とも呼ばれていて、怖いイメージがあると思うんですが、シャチのどんなところに魅力を感じているんですか?
「目の上のところに白い“アイパッチ”って言われる特徴的な模様があるんですけど、あれが人に例えると眉毛っぽくて、ちょっと癒し系な顔をしているんです。あとは口の下に白い部分があるんですけど、あれもにっこり笑っているような、そんな顔をしています。
実は顔だけ見るとすごく可愛らしくて、そういう可愛らしさと、海の王者と言われるほどの強さを持っているところが、私は魅力だと感じています」
●シャチのことを好きになったきっかけは、何かあったんですか?
「和歌山県にアドベンチャーワールドという動物園と水族館が一緒になったような施設があるんですけど、そこで小さい頃、初めてシャチを見たんです。私はそのアイパッチの部分が目だと思って、なんか変な顔をした生き物だなと感じていたんですね。
でも大人になってから、そこが目じゃないっていうのが分かって、意外と可愛い顔をしているっていうのと、その生態をものすごく調べて、サメも食べるし、頭もいいし・・・でも家族思いで、すごく可愛らしい生き物だと知ってから、すごく虜になりました」
●小さい頃からずっとシャチが好きだったっていうよりは、大人になってからいろんな魅力を知ったという感じなんですね。
「そうですね。改めて知ってからですね」
●シャチが飼育されている水族館として、関東で有名なのは千葉県の鴨川シーワールドだと思うんですけれども、行かれたことはありますか?
「もちろん、あります」
●私は千葉出身なので、小さい頃はよく鴨川シーワールドに連れて行ってもらったんですけど、やっぱりシャチを間近で見ると、大きくてカッコ良くて迫力がありますよね。ショーを見て、あるいは展示プールで泳ぐシャチを見て、まつおるかさんはどんなことを感じましたか?
「耳を澄ますと、シャチたちの鳴き声が聞こえるんですね。喉から出しているわけじゃなくて、超音波みたいな音だと思うんですけど、”キューン”みたいな、すごく小っちゃい可愛らしい声なんですよ。
あの大きい体で見た目に反して”キューンキューン”って言ってるのが、すごく可愛くて・・・あとは飼育員さんを見つけたら追いかけて遊んでって、子供のような感じで、すごく可愛らしいと思っています」

シャチの婚活パーティー!?
(編集部注:海の王者ともいわれるシャチ、別名オルカは体の大きさはオスの平均で6メートルから7メートルくらい、メスで5メートルから6メートルほど。体重はオスで4トンから6トンくらいだそうです。
数は多くはありませんが、世界中の海に生息するシャチは地域によって食べるものや習性は少しずつ異なっていて、クジラやアザラシなどを好む肉食派もいれば、おもにサケなどの魚を好む魚食派もいるようです。また、同じ海域にいる定住型、世界の海をめぐる回遊型、そして沖合にいる沖合型の3つのタイプに分かれるとのこと。
そんなシャチは、年長のメスを中心とした、数頭から数十頭の群れで暮らしていて、高い知能と社会性があるとされています。また、エコーロケーションという方法でコミュニケーションをとり、仲間と一緒に巧みに狩りを行なうこともあるそうです)
※まだまだ知られていないシャチの生態があると思うんですが、オスとメスがたくさん集まって婚活するって、ほんとですか?
「らしいですね。絶対そうとは言い切れないと思うんですけど、おそらく100頭ぐらい集まって、パートナーを探しているんじゃないかとは言われていますね」
●なんか婚活パーティーみたいですね(笑)
「ほんと、時代でいうと、そんな感じなんでしょうね」
●何かアピールとかお互いにし合うんですか?
「シャチは目が横に付いているので、真っ正面からお見合い、っていうか、婚活をしているのではなくて、横並びになって、お互い見えるようにするそうです」
●へぇ〜! 面白いですね。まつおるかさんが描かれているシャチは、とっても可愛くて愛嬌があると思うんですけれども、やっぱり生態を知って自分なりにデフォルメして描かれているんですか?
「そうですね。背びれの形がオスとメスでは違うんですね。あとはお腹の模様が違うっていうのがあるんです。(その違いに)めちゃくちゃ沿って描いているわけではないんですけど、オスだったらオス、メスだったらメスみたいな、(シャチを)好きな人が見ても、この人、間違ってるってならないように気をつけてはいます」
●具体的にオスとメス、どう違うんですか?
「オスは、背びれがめちゃくちゃ垂直というか、真っ直ぐ伸びていて、2メートルぐらいまでなるそうなんです。それに対してメス(の背びれ)はイルカみたいな、鎌形って言われているんですけど、ああいう形になっていますね」
●お腹も違うんですか?
「やっぱり哺乳類なので、実はメスには尾びれ側におっぱいがあるんですね。ちょんちょんって、よく見たらなんですけども(おっぱいが)あるのを、気をつけて描いていますね」
●ほかに何か心がけていることはありますか?
「やっぱり絵を描くので、これは色を変えたほうがいいかなとか・・・つやとか気にして描いていますね」
●つや!? なるほど、シャチはつややかですよね。
「そうですね。ツルツルしているので・・・犬とか猫とかモフモフした感じではなくて、ツルツルしたように見えるように描いていますね」

美しい生き物、野生のシャチ
※野生のシャチに会いに行ったことはありますか?
「以前、北海道の羅臼で野生のシャチを見ることができたんです。どうしても行ってみたいなと思っていたら、家族が行ってみたいって言ってくれて、4人で見に行くことになりました。
私は北海道が初めてだったので、ものすごく遠く感じて(笑)、関西から行ったんですけど、こんなにかかるのか、北海道すごい! ってなったんですけど・・・。
ホエール・ウォッチングとして船が出ていて、午前と午後の便で1日2回出てくれているんですけど、午前中はまったく全然見られなくて、いても鳥みたいな、海鳥がちょこちょこいるくらいで、ものすごくガッカリしたんですね。
(見られる)確率が40%で、一緒に(船に)乗っていらっしゃったお客さんのおじさんが、僕は3年通っているんだけど、見たことないんだよねとか言っていて、私も見られなかったら、どうしようって、期待半分、絶望が半分って感じだったんです。
午後の便ですごく探してくれて、遠くのほうにシャチがおったぞ! と言われて、すごく遠くにオスの背びれが見えて、見られた! と思ったら、船を近くに寄せてくれて、結構な群れが海の中に見えたんですよ。
シャチは息継ぎをするために水面に上がってくるんですけど、その時に顔がバッチリ見えたんですね。10メートルくらい先だったんですけど、結構近くて、大きかったんですよね、ものすごく。
その野生のスケールというか、本当に地球上にこんなに美しい生き物がいるんやと思って、私、感動しすぎて、ずっとぼろぼろ泣いていたんですね。携帯のカメラで撮っていたんですけど、それどころじゃないのでブレブレで(笑)、あとから見たら、なんかちょっと写ってるかなぐらいで・・・ちょうど繁殖期のシーズンだったんですかね・・・赤ちゃんもいる、小っちゃい、可愛いって言って、ずっと泣いていました」
●感動の対面だったんですね。
「一生の思い出ですね」
すみだ水族館の、恋多きペンギンたち
●まつおるかさんは先頃、『下町ペンギン物語』という本を出されました。 この本では東京スカイツリータウン内にある、今年開館10周年の「すみだ水族館」に飼育されているペンギンたちの日常や生態が、とっても面白く描かれていますよね。

私も読ませていただいたんですけど、カラーでイラストもすごく可愛いですし、ペンギンが先輩カップルたちを見て、恋愛を学ぶ様子など、すごく微笑ましくって楽しく読ませていただきました。
「ありがとうございます」
●海の生き物好きとしては、ペンギンも以前から気になっていたんですか?
「水族館っていうとやっぱりペンギンが人気で、(地元の)名古屋港水族館にももちろんいるので見るんですけど、私はシャチがいちばん好きやからっていうので、これ以上好きになっちゃいけないというかセーブをかけていたんです。
でもお仕事を通して(ペンギンが)こういうことをしているんですよとか、こういう生態なんですよとか、やっぱり密接に絡んでいったので、どうしてもあらがいきれずに、あっ、ペンギン可愛い! ってなっちゃいました(笑)」
●すみだ水族館には、何種類ぐらいのペンギンがいるんですか?
「すみだ水族館には、マゼランペンギンのみですね。 私が(取材で)聞いた時は49羽とおっしゃっていました」
●ペンギンたちの名前もすごく可愛いですよね。
「可愛いですよね(笑)」
●特に気になったペンギンはいましたか?
「お気に入りというか、推しなんですけど、”わっしょい”っていう子が健気で可愛らしいなと思っています(笑)」
●健気というのは、具体的にどんなところが・・・?
「わっしょいは、今”つむぎ”っていう女の子に片思いをしているオスの子なんですけど、つむぎちゃんは若くて恋っていうのをあまり分かっていないんです。でも、わっしょいはその子に対して、ちょっとずつアピールをしているところなんですね。
ガツガツいって引かれないように、ちょっとずつ距離を詰めようっていう感じがすごく可愛らしくて、頑張れ! って思っています(笑)」

●飼育員の方々にお話を聞いて、いちばんびっくりしたペンギンの行動はありますか?
「ペンギンは一生に一羽というか、パートナーは大体決まっているんですね。ほかのペンギンを調べる上で、私はそういうのは知っていたんですけど、今回(飼育員さんに)お話うかがって、修羅場がありました! って言われたんです。
略脱愛というか浮気をしたりとか、ほかの彼氏を取ったりとか、そんなことがあるらしくて、(ペンギンは)意外と情熱的に生きているんだなっていうのを知ってびっくりしました」
(編集部注:まつおるかさんは「すみだ水族館」の取材で、特別にバックヤードに入れてもらって、ペンギンの赤ちゃんとご対面、その愛くるしさにも魅了されたそうですよ)

シャチのイメージを変えたい
※まつおるかさんは、今後も海の生き物を描いていかれると思いますが、やはりいちばん題材にするのは、シャチなんでしょうね。
「そうですね。やっぱりシャチなんですけど・・・シャチは怖いとか、あまり知られていないんですね。そういうイメージを払拭したいですね。家族愛があって、すごく可愛らしい生き物なんだよっていうのをアピールしたいなと考えています」
●シャチは家族愛があるんですね。
「そうなんです。家族で子育てをするんです。おばあちゃんがリーダーで、その娘や孫とかでグループを形成しているんですね。
例えば、お母さんがちょっとご飯を食べたいってなったら、おばあちゃんが子守を代わったりとか、すごく賢くて本当に人間と同じような感じで、里帰り出産じゃないですけど、順番に子供をみんなで育てるっていう習性があって、家族愛が強いすごく可愛らしい生き物です」
●海の生き物たちのいちばんの魅力は、どんなところだと思いますか?
「海は中身を見ないと分からないというか、ぱっと見だと海に生き物がいる感じがしませんけど、ひとたび海の中に入ったら、いろんな生き物が命を営んでいるというか、小っちゃいプランクトンから大きい、それこそクジラまで、あらゆる命がそこにいるんだなっていうのをすごく感じます」
●では最後に、もし海の生き物になれたとしたら、何になりたいですか? そして何をしたいですか?
「そうですね・・・シャチになって、ダイナミックにジャンプをしてみたいなって思いますね」
●いいですね〜!
「あとは仲間と”キューン”って言ってお話をしたりとかしてみたいですね」
INFORMATION
まつおるかさんの新しい本は「すみだ水族館」で飼育されているペンギンたちの意外で面白い生態、例えば、うぶな恋心、夫婦間のトラブル、ただならぬ男女関係など、人間よりも複雑なペンギンの世界を垣間見られるコミック・エッセイです。ペンギンの可愛いイラストはもちろん、飼育員さんが撮った貴重な写真も掲載されています。おすすめです!
KADOKAWAから絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
2022/10/30 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、東洋大学・助教で、
キリン博士として知られる「郡司芽久(ぐんじ・めぐ)」さんです。
郡司さんは1989年、東京都生まれ。子供の頃から動物、特にキリンが大好きで、
好きな動物の研究をしたいという強い思いで大学に入学。27歳の時に、キリンの研究で念願の博士号を取得、「キリン博士」と呼ばれるようになったそうです。
そして、東京大学大学院から国立科学博物館、筑波大学を経て、現職の東洋大学・生命科学部の助教として活躍。専門は解剖学と形態学。2019年には『キリン解剖記』という本を出版、話題になりました。そして先頃、新しい本『キリンのひづめ、ヒトの指〜比べてわかる生き物の進化』を出されています。
きょうはそんな郡司さんに、知っていそうで知らないキリンの不思議や、生き物のユニークな進化のお話をうかがいます。
☆写真:郡司芽久

大発見! 8番目の首の骨!?
※郡司さんは、2016年に「キリンには8番目の首の骨がある」という論文を発表され、注目されました。改めて、これはどういうことなのか、ご説明いただけますか。
「キリンと私たち人は、同じ哺乳類というグループの仲間なんですけれども、哺乳類に含まれる動物は基本的に首の長さに関わらず、首の中にある頚椎(けいつい)っていう骨の数がみんな7個という体づくりの基本的なルールが存在しています。
キリンであっても私たち人であってもクジラであっても、首の中の頸椎という骨の数はみんな7個と、今までの研究でわかってきたんですが、色んな動物園からキリンの遺体を献体していただいて、内部の筋肉の構造であったり、骨の構造であったりっていうのを調べていくと、確かにキリンは頚椎という骨の数は7個なんだけれども、実はほかの動物ではほとんど動かない胸椎(きょうつい)という胸の骨がよく動いていて、それによって7個の頚椎と、あとひとつ胸の骨がグニグニ動くことによって、頭の位置とか首の位置を動かしているんだということが明らかになりました。
その胸の骨が、あたかも8番目の首の骨みたいにふるまっている、動いているんじゃないかということで、これまでキリンは私たちと同じような首の骨格の構造をしていると考えられてきたけれども、やっぱり首が長くなって柔軟に動くようになるのに関連した、構造の変化が存在するんじゃないかということが明らかになりました」
●大発見ですよね!?
「そうですかね〜(笑)」
●専門は解剖学なんですよね?
「はい、そうです」
●病理解剖とは違うってことでしょうか?
「そうですね。病理解剖は一般的になぜ亡くなってしまったのかっていう、いわゆる死因を調べるために行なうものです。多くの方がたぶん解剖と聞いてイメージされるのは、この病理解剖かなと思うんです。
私が行なっている解剖はなんで死んでしまったのか、というよりも、それぞれの動物の体の構造がどんなふうになっているのかを調べて、いろんな動物の体の構造を比較することで、動物が進化の過程で体の構造をどんなふうに変化させてきたのか、その進化のプロセスみたいなものを明らかにしていくことをやっています」
(編集部注:解剖といっても郡司さんが取り組んでいらっしゃるのは、比較解剖学というものなんですね。
郡司さんは、全国の動物園から、亡くなったキリンを献体という形で託され、解剖するそうです。キリンに限らず、動物の亡骸は大学の研究用として、または博物館に骨格標本を展示するような教育普及用として活用されるとのこと。
郡司さんは年間3頭から5頭のキリンを解剖、これまでに46頭の解剖を行なったそうです。あんなに大きなキリンの解剖は、さぞかし大変な作業だと思ったんですけど、郡司さん曰く、キリンはスレンダーな動物なので、楽ではないけど、体のわりにそれほどではない、とのことでした)
キリンの首が長くなったのはなぜ!?

※郡司さんが先頃、出された本『キリンのひづめ、ヒトの指〜比べてわかる生き物の進化』にはご専門のキリンの研究成果も引用されています。キリンの大きな特徴というと、なんといっても長い首になりますが、これも進化なんですよね。
「そうですね。進化の結果として長い首を持つようになったという感じですね」
●首が長くなったのは、高いところにある木の葉っぱを食べるためなんですよね?
「いくつかの仮説がありまして、その仮説も本書の中でご紹介しています。なんとかのためっていう表現は、すごくわかりやすいのでよく使うんですけど、実際の進化は何か目的があって、これがしたいから、こうなるみたいなことができているわけではないんですね。
私たちも空を飛びたいから羽が欲しいなと思っても、そんなものが生えてくるわけではありませんよね。やっぱり体はそんなに自由に変化できるものではなくて、私たちの祖先に当たるような生き物から、変えられる部分がちょっとずつ変わって、今の多様な生き物が生まれてきてるんです。
キリンの場合は、例えば首が長い個体が長生きできたりだとか、子供をたくさん残せたりだとかっていう、生きていくのに有利なポイントがどうやら長い首には存在しています。それによって首が長い個体が生んだ子供は、やっぱり首が長い子が多くて、それが何世代も何世代も積み重なることで、最終的に首が長い子ばっかりになったと考えられています」
●キリンは首も長いですけど、足も長いですよね? 大人のキリンの背の高さや足の長さは大体どれぐらいなんですか?
「大人のキリンだと、オスとメスで背の高さは違うんですけど、大体4メートルから5メートルぐらいですね。 足の長さが180センチぐらいです」
●足だけで180センチ! すごいですね。体もかなり重いですよね?
「そうですね。メスのほうがやっぱり軽くて、メスで700キロぐらい、オスだと1トン近くなる子もいますね」
●首が長くて足も長いと、水を飲むのも一苦労な感じがしますけれども・・・。
「そうですね(笑)。けっこう不格好に水を飲んでいて、大変そうだなと思いますね」
●そういうのもいずれ進化していくんでしょうか?
「もともとそこまで水をたくさんは飲まない生き物だっていうことも 知られています。葉っぱとかを食べて生きているので、葉っぱの中に含まれる水分をかなり利用して、あまり水を飲まなくても大丈夫なようには、どうやら進化しているらしいんです。それでも動物園では普通に水を飲んでいるところとか、当然、野生でも見られるので、なんか大変そうだなって思いますね(笑)」
キリンは高血圧!?
※新しい本には「キリンは地球上でもっとも高血圧な生き物」とありました。これも首が長くなったことに関係があるんですよね。
「そうですね。キリンはとても首が長くて、しかも頭を高く持ち上げているので、心臓から脳までがすごく離れているんですね。 心臓は血液を送るんですけど、重力が地球上には存在しているので、重力に逆らって高いところの脳まで血液を送らなければなりません。 首が長くて高いところにある体型の進化に伴って、どんどん高血圧になって、高いところにある脳までちゃんと血液を届けられるような体になっていったと考えられています」
●キリンが高血圧は数値でいうと、どれぐらいになるんですか。
「キリンの血圧は上が250ぐらいです。だいたい人の平均的な血圧の倍ぐらいあります」
●かなり高血圧な感じがしますね。
「人間だと病院に行かなくちゃ、っていう感じですね」
●ちなみに心臓は大きいんでしょうか?
「もちろん人間に比べると大きいんですけれど、体のサイズも大きいので、あの体のサイズに対する心臓の大きさっていう意味では、そこまですごく大きいっていうわけでもないと言われています」
(編集部注:国内の動物園で飼育されているキリンは、今は意外に多くて、200頭ほど。一方、生息地のアフリカ大陸には、およそ12万頭いるそうです。
そんなキリンは長い間、1種とされてきたんですが、2016年の遺伝子解析で、4種に分類されたとそうですよ。その4種とは、キタキリン、アミメキリン、マサイキリン、そしてミナミキリン。
とはいえ、キリンが1種なのか、4種なのかは研究者の間でも意見が分かれるところで、今後の研究によって、また変わる可能性があるそうです)
キリンと人の共通点
※キリンと人では見た目も大きさもまったく違う生き物ですが、見方を変えると共通するところはありますよね。
「そうですね。先ほど紹介した首の骨はとてもいい例で、あれだけ首の長さが違うんですけど、中に入っている骨の数はキリンでも人でも一緒だったりとか・・・。あとは体の全体的な構造も大きく見ると、足の骨格であったり手の骨格は、もちろん違う部分もあるんですけど、大枠としてはかなり共通したものが存在しています」
●首の骨以外の共通点というと、どんなところになるんでしょうか。
「例えば、手足の骨格の仕組みでいうと、外から生きているキリンを眺めていると、足の真ん中あたりに関節があって、私たちの膝とは逆方向に曲がってるんですね。動物園で“キリンの膝って人間とは逆向きに曲がってるんだね”って、お母さんとお子さんでお話されてたりするんですけど、実はそこはキリンの膝じゃなくて踵(かかと)なんですね」
●踵!?
「そうなんです。実はキリンの場合は、踵が足の真ん中辺にあります。私たちも膝と踵は逆向きに折れ曲がってるんですけど、キリンの場合は、足の真ん中に踵があって膝みたいに見えるので、逆向きかなと思うんですね。でも実は踵なので、人間と同じような曲がり方をしています。
膝はもっともっと高い位置、お腹の近くに実はありまして、なので膝の曲がる向きとか、踵の曲がる向きは、骨格の構造からすると人間とよく似た、ただプロポーションは随分違うけど、中の構造はかなりよく似ている仕組みになっています」
●本には、生き物を解剖して、比較することが非常に重要だと書かれていましたけれども、やはりそれは進化を知ることにつながるっていうことですか?
「そうですね。もちろんそれもそうなんですけど、やっぱり何かを理解しようと思った時に、例えば人のことを理解しようと思った時に、人のことだけを調べていても何が人特有のことなのかっていうのは、なかなか見えてこないんですね。
これは人にしかない、これは人以外にもあるっていうのを知るためには、いろんな生き物を見比べて比較してあげて、共通するところと違うところをそれぞれはっきりさせてあげるっていう、そういった作業の果てに、人の特徴はこういうことなんだねっていうのが見えてくると思っています。なので、キリンでも人でもなんでもそうですけど、理解する時にはほかの生き物との比較がとても大事になってきます」

進化は変化、退化も進化!?
※生き物たちの進化とは、環境に適応していくのが進化なんでしょうか。退化することもありますか?
「進化って一般的にいうと、”すごくなる”みたいなイメージがたぶん多くの方が持っていらっしゃると思うんですけど、生物学 においての進化っていう言葉は”変化”とけっこう近い言葉です。
世代を超えて親から子供に引き継がれていく、変化みたいなことを進化と呼んでいます。なので一般的な言葉だと、進化と退化っていうのは反対の言葉みたいな扱いだと思うんですけど、実は学問の世界では退化も進化のひとつだと考えられています。
基本的に生物学の進化は、体の構造だったり行動だったり、様々な部分が変化して、しかもそれが親から子へと引き継がれていくような変化のことを進化と呼びます」
●生きる環境にどんどん適応していくっていうことなんですね?
「そうですね。やっぱり生きている環境でより生き長らえるというか、より子供を残すのに有利な特徴を持っている個体がたくさん生き延びる、そうすると子供にもその特徴が引き継がれていって、だんだんその特徴を持っている個体が増えていく、最終的にその特徴を持っている個体ばっかりになることが、これが大まかにいう進化のプロセスです」
●人間はまだ進化の途中なんでしょうか?
「人間もここ何千万年の間にも変化が起きていると考えられているので、やっぱりあらゆる生き物はまだ進化の途上にあると、進化の途中であるというのは言えるかなと思います。
ただ、人間の場合は環境を自分たちに合わせて、作り変えることができてしまっているので、例えば、ちょっと過ごしにくいなっていうような場所でも、建物を作ったり洋服を着たりとか・・・基本的なところで言えば、そんなことから始まって、環境のほうを自分たちに合わせることを、人間は行なっているので、これまでの生物の進化の形とは、やっぱり変わってくるかなと思います」
●何億年先も人類が存在するとして、大きな進化や変化はないかなという感じなんでしょうか?
「そうですね。姿形が全く変わるような進化が起きるかって言ったら、起こらない可能性のほうが高いのかな、というふうに思います」
一家団欒の話題になる研究!?
※郡司さんは解剖学をご専門とされていますが、ご自身にとって、解剖学とは?
「私は普段、生き物の体の中を調べているんですね。さっきの比較の話ともつながってくるんですけど、いろんな動物の体の中を調べて、それぞれの動物がどんなふうに進化してきたのかをたくさん見ていくと、そこと自分の体、人間の体を改めて見比べることにもつながってきます。
人間はこういう生き物なんだなとか、自分はこういう体なんだなっていうことを、動物を通じて改めて見返してきたっていうのが、解剖学をやっていく中で、すごく感じてきたことなんですね。
自分と向き合ったりだとか、体ってやっぱりすごいなとか、生きていて、ご飯を食べる、寝るとか、そういう日々の当たり前の活動の中にも、すごいことがいっぱい詰まってるんだなっていうのを改めて分からせてくれた学問です」
●では、最後にキリン博士として、今後やりたいことを教えてください。
「私は普段、研究をしています。みなさんが日常の一家団欒みたいな時間に、きょうこんな話を聞いたんだけどねって、話題にあげたくなるような面白い研究をしていきたいなというのが、研究者としての目標のひとつなので、今後もみなさんに面白いなとか楽しいなって思ってもらえるような発見を、たくさんできたらなと思っています」
INFORMATION
郡司さんの新しい本をぜひ読んでください。人とキリンは見た目はまったく違いますが、骨格など似ている部分に注目すると、進化の仕組みが理解しやすくなります。この本では手足、首、心臓など8つの器官を通して、いろいろな動物に刻まれた進化の不思議を垣間見ることができます。とても面白い進化の話が満載です。自分の体を知るきっかけになるかもしれません。
NHK出版から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎NHK出版HP:https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000819172022.html
郡司さんの研究についてはオフィシャルサイトを見てください。
2022/10/23 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、青森県南部町に親子3人で暮らす田村余一さんと奥様のゆにさんです。
田村さんご夫妻は、水道・電気・ガスと契約せずに、必要なものは、なるべく自分たちで作る自給自足の生活を実践していて、テレビのニュース番組などでも取り上げられ、注目されているんです。
余一さんは1977年、南部町生まれ。大学卒業後は都会に出て、いろいろな仕事を経験。その後、ふるさと南部町に戻り、実家の土地を開墾し、2009年から廃材を使った家づくりを始め、試行錯誤しながら7年かけて完成させたそうです。
一方、奥様のゆにさんは1987年、北海道・札幌市生まれ。高校卒業後、東京でアルバイトをしながら歌手として活動、そして2016年、29歳の時にSNSで偶然見つけた余一さんの「お嫁さん募集」に応募。自然に寄り添った暮らしをしたいと思っていたこともあり、南部町に移り住み、その後、入籍。2018年にひとり息子の泰地(たいち)くんが生まれています。
田村さんファミリーが暮らす青森県南部町は、八戸市に隣接していて、余一さんいわく、冬は厳しいけれど、自然が豊かでリンゴや梨など、いろいろな果物が採れる「フルーツの町」だそうです。
今週はそんな南部町で、畑で野菜を育てたりしながら、自給自足の暮らしを実践されている田村さんご夫妻に暮らしぶりや、自然の中での子育てのお話などうかがいます。
☆写真協力:田村余一、田村ゆに、村川僚、仁木俊文

遠回りな気がした!?
●先頃出された、自給自足の生活や日常を綴った本『都会を出て田舎で0円生活はじめました』を、私も読ませていただきました。
余一さん&ゆにさん「ありがとうございます!」
●暮らしを変えれば人生が変わるということで、自由気ままに生きることを味わえると本に書かれていて、本当に日々全力で生きていらっしゃるなと感じました。大変そうではありますけれども、それがすごく楽しそうで、羨ましいなと思えるような内容でした。
そもそもなんですけれども、どうして自給自足の生活をしようと思われたんですか?

余一さん「まあ自給自足はひとことでいうと、自分のことは自分でやる、ここでオッケーだよっていうラインも自分で決めるっていうので、自分のものは自分で作って、それを糧にして生きていくというか、そういう意味だとは思うんですけどね。
世の中のシステムとしたら経済というものがあって、お金を稼いでそのお金でお家を買う、食べ物を買う、着る洋服を買う。あとは例えば、お子さんがいればお子さんをどこかに預けるとか、とにかく1回お金を稼いでそれで手に入れるとか、(お子さんを)誰かに預けるっていうことをするんですね。
僕もいわゆる社会人というものに一瞬だけなってみて、まあフリーターがほとんどでしたけど、そういう経験を通して、なんかすごくそれが遠回りな感じがしたんですよ。
なんで食べものを得るのに1回お金を稼がなきゃなんないんだろう・・・食べものを得るのに関係ないことをしなきゃなんないんだろう・・・というふうに思っていたんです。
うちの実家が兼業農家だったのもあって、お米を買ったことがない。お野菜や果物とかはほとんど買うことがなかったので、食べ物は自分で作れるなっていうのはあったんですよね。

うちの親父が大工だったのもあって、大工作業していたのを子供時代から見ていたので、家もまあ造れるんだよな〜っていうのもあり、これはいきなりそっちをやり始めたほうが早いなと思ったんですよね(笑)。なので、こっちのほうが早くてダイレクトでわかりやすいなと思いました。それで始めたようなものがありますかね(笑)」
●ゆにさんは余一さんと結婚して、自給自足の生活に入っていったわけですけど、不安とかはなかったですか?
ゆにさん「割と私は考える前に行動してみたいと思うほうなんですね。たぶんいろいろ考え始めれば、やったことない暮らしだし、不安というのは出てきてたと思うんですけど、とりあえずやってみようと思って、やりながら考えていったって感じです。
知らないことはすごく楽しかったし、実際にやってみて、地に足がついた暮らしとか、家庭菜園も自分の手で豊かにしていけるっていうのを実感できた時に、もう楽しみしかなかったですね。失敗はいろいろあるんですけど、でもそういうのも自分の学びになるし、こっちに来てから不安とか感じたことがあまりないですね」

電気・ガス・水道と契約しない生活
※今も電気やガス、水道と契約しないで暮らしていらっしゃるんですよね。
余一さん「そうですね」
●不自由はないんですか?
余一さん「不自由っていう感じじゃなくて・・・めんどくさいことはありますね。まあ自由なんですよ。
水をどういうふうに引っ張ってくるかとか、電気はどういうふうに使うかとか、どこからどういうふうに引っ張って配線するとか、そういうのは全然自由なので、不自由ではないんですけど、それを自分でやるので面倒ではあるよね、ちょっと(笑)」
ゆにさん「手間はかかるよね」
余一さん「手間はかかるので・・・あれ!? 水が出なくなった! っていうと、水源の近くまで行って確認して、枯葉が詰まっていたので取り除いたりっていうのは、なんか面倒ですよね(笑)」
●生きていくためにまず確保しないといけないのは水ですよね。
余一さん「水は大事ですよね」

●日々、水はどうしているんですか?
余一さん「うちの嫁さんがこっちに来て1〜2年の間、日々、畑の溝を切ってたんですよ。畑の周りをちょっとスコップで掘る作業があるんですね。それをやっていたら、どんどんぬかるみになって、だんだんドロドロ水になって、気がついたら、ちょろちょろって川みたいになって、水が湧いてきちゃったんですよ。
それをいろいろ年々工夫を凝らしながら、きれいなお水にして、ちゃんと溜めて使いたい時に一気に使えるようなタンクも接続して使っているよね」
ゆにさん「生活用水のほうはそうですね」
余一さん「生活用水として使っていますね。ちょっと残念ながら飲めないような水なので、飲むことはしていないんですけど、洗濯する、食器を洗う、お野菜の苗にお水をやるっていうのはその湧いた水でやっております」
●料理をしたりとか、お湯を沸かしたりするのはどうされているのですか?

余一さん「それは木を燃やします。木質燃料だね、ほんとにうちは。一般の家庭だと電気だったりガスだとは思うんですけど、うちは田舎でもありますし、今はお家がどんどん解体されて、出る廃材がただのゴミになるので、“すみません。それください”っていうと大体のところではもらえるんですよね。なので、そういう建築廃材なんかを燃やしていますね」
●ここでも廃材が活躍しているわけですね。
余一さん「そうですね。やっぱり廃材の中でも建築に活かせるものと、活かしにくいものがあるので、活かしにくいものからどんどん薪に変えていくような感じはあります」
●電気はソーラーパネルを利用されているんですよね?

余一さん「そうです。ソーラーパネルで発電してバッテリーに溜めて、それをちびちび使ったり・・・天気が続くと電気がすごくいっぱい溜まって余っちゃうので、そういう時は大判振る舞いで電動工具を動かして、どんどん薪を切ったりとか、あとはホームべーカリーとかそういう家電製品、ちょっと熱量を使うやつ、電気量を使うやつをその時に使ってみたりとか、そのようなことをしています」
(編集部注:実はトイレも別棟の小屋に、自作した便座を設置し、コンポスト方式で土に返すようにしているそうです。夏場はトイレットペーパーの代わりに、季節に応じて植物の葉っぱを使用、春はふきのとう、夏はキウイの葉っぱがいいとおっしゃっていましたよ)
男の子はたくましく
※ひとり息子のたいちくんは現在4歳、ということですが、子育てはどうですか?
ゆにさん「子供っていろいろ興味が変わっていくので、私たちが教えたいなと思っていることにたいちの興味が重なった時に、すかさずいろいろ教えてあげたりしてます。
この暮らしは私たち夫婦がやりたいなと思ってきたことなので、たいちに無理強いはせずに、彼は彼なりにいろんなことに興味とか好奇心があると思うので、彼がやりたい方向性を大事にしつつ、生活の知恵みたいなのを伝えていけたらいいなという考えで教育しています」
●YouTubeも拝見させていただいたんですけど、たいち君はすごくたくましいなと感じました。
余一さん「あ〜、それはよかった! やっぱりたくましく育ってほしいですね、男の子は。そこは意識していますね(笑)、僕は男としては・・・」
ゆにさん「ふふふ(笑)」
●たいち君は幼稚園には行ってないんですよね。
余一さん「はい、そうです。そこも自給自足なんですね。第三者にはお任せしないというか、自分の食べ物を自分で得る、自分の子供は自分で育てるっていう感じですね。ある一定の年齢になってくると親がうざくなってきたりもするので、そうなった時に小学校なり中学校がその先にあるわけなんで、その時はお預けしようかなと思っていますけどね。

とりあえず今は、お父さん、お母さんっていうか、うちらは『とと』『かか』って呼ばれているんですけど、『とと! かか!』って寄ってきてくれるんで、寄ってきてくれるうちは、ほんとに大事に可愛がってあげようっていうのはありますね。そのうち、やだーっていったら、じゃ〜バイバイですよね(笑)。とにかくこうやって僕ら、とと、かかを愛してくれているんなら、こっちもいっぱい愛情を注いでやりたいよね(笑)」
鶏の命をいただく
※先頃出された本に、鶏をさばいて、いただいたという話が載っていました。鶏の命をいただくと決めたのは、どうしてなんですか?
余一さん「うーんちょうどそれをした時が真冬だったんですけど、冬になるとお野菜が採れなくなって、おのずとスーパーに行って買う機会が増えて、お肉も買ったりするんですが、うちに鶏がいるのにスーパーに鶏肉を買いに行くっていうのも、これもまた遠回りだなって思ったんですね。
そもそも卵をいただいたり、お肉として(鶏を)いただこうっていう、結果というか着地点っていうのは決めた上で飼育していたので、このタイミングだよなって夫婦で会議して決めたよね」
ゆにさん「うんうん」

●さばいてみて、どんなことを感じました?
余一さん「なんでしょうね〜あれは・・・単純に言葉にすると命を絶つ行為をするんですけど、う〜ん、悲しいでもないしね。自分でやっているわけなんで、それを悲しいわけじゃないし、う〜ん、うまく言えないですよね。
ただ目があったんですよね。その目がすーっと閉じていったのを見た時に、ぶわっと涙が溢れてきてですね・・・でもそれって悲しいとかでもないし、なんだろうな・・・自分に対しての怒りとか嫌悪感でもないしね。ただなんか涙が出てきて、これはなんだろうなっていう・・・そこは消化しきれてないですね。
自分でもあまり無理に言語化しないようにはしているんですね。言葉にすることで急に陳腐になったりすることってあるので、無理にそういうことはしないようにしているんですけど、よくわからないっていうのが正直なところです」
ゆにさん「不思議なんですけど、野菜は栽培ができて、普通に収穫できた時に
一種の答えみたいなのが出て、すっきりする感じがあったんですよ、これまで。
でも鶏さんを食べるっていうことに関しては、こうやることによってすっきりっていうよりは、なんか疑問がすごく多くて、なんでこういうことをしないと人は生きられないんだろうみたいなところで、答えが出ずに終わるというか、モヤモヤした感じでその時期は終えていましたね」
●たいち君にはどんなお話をされたんですか?
ゆにさん「なんだろう・・・シンプルに今やっていること、感情的なことっていうよりも、今何をやっているっていうのをたんたんと説明していくようにしていました。たいち自身はほんとに、目の前で起きている事実をただありのまま受け止めていて、別に怖がるということもなかったし、その時に食肉用に加工した部位を広げて、ここはこれなんだよとか説明して・・・」
余一さん「どういうお肉の部分ね・・・ここは胸肉だよとか、もも肉だよっていうのを、なんとなく(たいちは)ふぅ〜んとか、へぇ〜っていう感じで聞いていたよね(笑)」
1日の幸せは晩ご飯
※自給自足と聞くと、不便とか、大変とか、そんなイメージを持つかたが多いと思うんですけど、おふたりのお話をうかがっていると、楽しそうだな〜と感じました。無理はしてないんですよね?
余一さん「そうですね。もちろん自然環境に負荷をかけないっていうのも大事なんですけど、それ以上に自分たちに負荷がかかると続かなくなるので、うちら今これは苦痛だよね、なんか大変よね、ってなったら、それは足るを知る自給自足の一部で、自分でオッケーなところで、しっくりくるところにまた別のポイントをずらしていくっていうのかな・・・。
今ここを目指したけど、これはきついから、やっぱりもうちょっと楽なこのラインでいこうとか、っていうふうに全部それを自分で決めているので、そこだね。なんかいちばん、自分のことを全部自分で決めていけるっていうのが、この生活の魅力かなって思います」

●田村さんご夫妻は『「うちみる」プロジェクト』を進めてらっしゃいますけど、これはどんなプロジェクトなんですか?
余一さん「これはですね、僕らもこの生活をすることで、人間にも自然環境にもひょっとしたら社会にも、すごくいい影響があるんじゃないかっていうのを感じていまして、それはやっぱり発信したいなと思って、インターネットやSNSで発信しているんですね。まあ単純にいうと、うちを見てください! って意味で、『うちみる』っていう感じでやらせてもらっていますね」
※ところで、1日の生活の中で、いちばん幸せを感じるのは、どんな時ですか?
余一さん「それはもう晩ご飯の時です(笑)。うちは1日1食にしているんですよ、ご飯を。そういうのでもいろいろ負荷が減るんですよね。内臓にかかる負荷も減りますし、単純に時間の節約もされるし、食材の節約にもなるので、そういうのもあるんですね。
朝起きて働いて、夜のご飯まで頑張る! っていう1日のご褒美が、嫁さんが作るご飯なので、そこに向かっていますね、毎日朝起きてから。さあっ、飯食えるからきょうも頑張ろうっていう(笑)」
●ゆにさんは、どんな時がいちばん幸せですか?
ゆにさん「私も食べることが好きなので、そのご飯の瞬間はとても幸せだなと思っています。本当に朝起きて、食べ物があれば、十分な睡眠をとって、十分な食料があれば、人って生きていけるんだなと思いますね。

最低限の食べるものを確保するために畑を耕してとか、最低限かかるお金を稼ぐために少し労働してみたいな、そういうのもあるけど、やっぱり”食”で満たされるために生きているなと今考えているところがあるので、毎日の晩ご飯の食卓につく時がいちばん幸せだなと思います」
(編集部注:田村家のひと月の生活費は4万円ほど。地域の便利屋さんとしてお困りごとなどを引き受けるお仕事をして稼いでいるそうですよ)
憧れで終わらせないで
※自給自足の生活に憧れているかたにアドバイスがあるとしたら、どんなことでしょう? まずは余一さんからお願いします。
「うーんとね、何事もやってみなきゃわかんなくてですね。よく言われるのが、”すごく憧れるんですけど、自分には無理です。でも応援してます”みたいな、最終的にはポジティブなご意見をよくいただくんですけど、やってもないのになんで自分では無理なんだろうって、自分の可能性をなんで信じないんだろうって、すごく思うんですよね。
だから(自給自足の生活に)憧れている人に対しては、ほんと憧れで終わらせないで! っていうのをとにかく言いたいです。
具体的にはちょっとノコギリで木を伐ってみるとか、伐った木を斧で割って、焚き火にして、お鍋でご飯を炊いてみるとか、そういうちっちゃなことからなんですよね。いきなりすべて、電気・ガス・水道を契約しない生活にぐるっと変えることって、たぶんうちらでも無理だったので、ちょっとずつなんですよね。
ちょっとずつ右肩上がりになりゃいいやっていうぐらいのやり方じゃないと、すごく負荷がかかると思うので・・・それかものすごくお金をかけなきゃだめですよね。急に土木工事を入れるとか、業者さんに頼んで一気に整えて、そこに入って頑張りますとかね。
でもそれはやっぱり違うと思うので、まずは手を動かして、土に触れるとか、木に触れる、そういうものにダイレクトに向かうことを、ちょっとずつでいいのでやってほしいと思います」
●ゆにさんはいかかですか?
ゆにさん「最近こうやって本を出させていただりとか、メディアに出させていただいて、6年経った時の、完成形というか、ある姿が今なんですね。最初はほんとに何もないところから始まっていて、まず暮らしに居心地の悪さ、不快なところを感じたりとか疑問を持ったりして、そこで自分なりにできることをやって、変えていくことで始まりましたね。
食べるものにいろいろこだわったりしたら、スーパーで買いたいものがないなって思ったら、自分で作ってみるとか・・それもプランターにタネをひとつ撒くところから始まっていくので、自分の暮らしに疑問を持ったところを少しずつ改善していけば、いつかその人なりの桃源郷を作っていけるかなと・・・。
今ある私たちは、私たちが住みたい場所を自分たちで作っているし、これをまんま誰かがやれば、その人が幸せな暮らしになるかっていうと、ちょっと違うと思うので、自分たちなりに疑問を持って、きょうからできること、改善していくことで、こういった暮らしににつながっていくのかなと思いますね」

INFORMATION
田村さんご夫妻の初めての本です。特に自給自足の生活に興味のあるかたには、気になること、知りたいことが満載です。無理せず仲良く暮らしていらっしゃる田村ファミリーのリアルな生活が綴られていて、楽しく読めます。サンクチュアリ出版から絶賛発売中です。
新しい展開として「むらコミュニティ」という、プロジェクトを進めるそうです。「うちみる」プロジェクトを含め、詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
◎サンクチュアリ出版:
https://www.sanctuarybooks.jp/book-details/cate00054/book1351.html
◎うちみるプロジェクト:http://uchimill.naturebounds.com/
『都会を出て田舎で0円生活はじめました』を抽選で3名のかたにプレゼントいたします。応募はメールでお願いします。
件名に「本のプレゼント希望」と書いて、番組までお送りください。
メールアドレスはflint@bayfm.co.jp
あなたの住所、氏名、職業、電話番号を忘れずに。番組を聴いての感想なども書いてくださると嬉しいです。応募の締め切りは10月28日(金)。当選発表は発送をもって代えさせていただきます。たくさんのご応募、お待ちしています。
応募は締め切られました。たくさんのご応募、誠にありがとうございました。
2022/10/16 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、一般社団法人「森の演出家協会」の代表「土屋一昭(つちや・かずあき)」さんです。
土屋さんは1977年、東京都青梅市生まれ。2009年からネイチャーガイドとして活動、その後、森林セラピーガイドの資格を取得。そして2015年に森の演出家協会を設立、現在は青梅と奥多摩にある2軒の古民家を拠点に、森・人・食をつなぐ森の演出家として活動されています。
きょうは森林セラピーガイドの活動や、マッチング率抜群のアウトドア婚活イベントのお話などうかがいます。
☆写真協力:一般社団法人 森の演出家協会

東京最後の野生児!?
※土屋さんは「東京最後の野生児」と呼ばれていたそうですね。そう呼ばれるようになったのは、どうしてなんですか?
「僕が高校時代に、フジテレビの『晴れたらイイねッ!』っていう番組で、アナウンサーの益田由美さんが東京最後の野生児と名をつけてくださって、そこからですね、野生児として活動し始めたのは・・・」
●そもそもその番組には、どうして出演することになったんですか?
「その当時、高校の生物部に入っていまして、自分が野鳥と話ができたりとかしていて・・・たまたまテレビ局が来て、自分を出したいということで・・・」
●へぇ〜そうなんですね〜。東京都っていうと高層ビルのイメージすごく強いですけれども、東京の西のほうはそうではないんですね?
「そうですね。自然豊かで自分の住んでいる所は、普通にクマさんがいる場所なので、東京なのに」
●えっ! 青梅で、ですか?
「はい、青梅のちょっと山奥に行くと、今年は栗が豊作で、栗を採りに行っている時もなんか気配を感じて、近くにクマがいたりとかしますね」

●子供の頃の遊び場が地元の森や川だったんですね。
「そうですね。多摩川の、羽田からずっと上っている上流では食べられる、すごく美味しいお魚がいっぱいいます」
●子供の頃はどんな遊びをしていたんですか?
「遊びというか、狩りですね。天然のヤマメを素手で採るっていう、代々受け継がれているんですけど、二代続けてできますね」
●すごいですね。そういうのはお父様から教わるのですか?
「はい、そうです。父親から学んで」
●お父様からの教えで、今でも大切にしていることってありますか?
「やっぱり自然は危ないこともあれば、すごく楽しいこともあるっていうことですね。日々カラダで体験体感しているので、ちょっとでも雨が降ったりとかしたら、いちばん早く逃げるガイドですね。最初に自らカラダが(危険を)感じ取れる、そういうのを目的にずーっと五感で体験して体感していますね」
●確かに自然の中で遊ぶには危ないことも含めて、いろいろ知っておかないといけないことも多いと思うんですけれども、そういうことはすべてお父様から教わってきたんですか?
「はい、そうですね」
ガイドとしての危機察知能力

※先ほど森の中で、危険を感じ取れるとおっしゃっていましたが、具体的にはどうやって察知するんですか?
「例えば、僕は先ほど言ったように五感で体験体感しているので、いつも鼻が効いているんですね。ちょっと風が吹いてきてクマ臭がするとか、例えばこれはサルだなとか、あとイタチ臭、タヌキ臭、全部分かるんですね、ヘビも。
さっき逃げるって言ったのも、いちばん最初に自分が感じて、危ないぞっていうのをまずお客様に知らせたい・・・だけど、クマの場合は逃げちゃいけないんで、クマがいた時には違う対処をするんですけど、なるべくキャーキャー言わせないように、クマがいたと知らせながら、目を離さずに降りていくとか。
ガイドウォークの前にも安全対策として、リスクマネージメントをちゃんとお教えしてから行きますね」
●臭いで分かるものなんですね?
「はい、マーキングをしていて、クマが自分のところに寄ってくるなって臭いを出しているんですね。クマはどんな臭いってよく聞かれるんですけど、自分はよく動物園に行って、クマだったり色んな(動物の)臭いを嗅いできたんですね。わからなかったら動物園に行くのが早くて、クマ臭はそのクマの臭いがすごくわかるんですよ。イノシシも特徴的で、動物はみんな違う臭いがしますね」
●なるほど、それで感知するわけですね。
「はい、ヘビも危ないなって思った瞬間に一瞬で逃げないと、マムシとかってそのまま飛んできたりするので。
ガイドがなんで逃げているんだって言われるかもしれないですけど、いつも体験体感しているからこそ、自分がやられちゃったら、二次被害が起きてしまうかもしれないので、瞬間に自分がぱっと動作をすることによって、お客様に知らせる行動もしているんです」
●天気の急変とかはどうやって感じるんですか?
「それも、急に冷たい風になったりとか・・・あとは土の匂い、雨の匂いがわかってくるんですね。風が読めると、あと10分ぐらいで雨が降ってくるなとか、そういうのもわかってきますね」
●匂いで!?
「匂いと肌感覚で、風が来た時にちょっと冷たく感じたりとかですね。この頃、豪雨も多いので、小っちゃい落ち葉が流れてきた瞬間から、これは上流で(大雨が)降っているから離れましょうとか、そういう形でわかりますね」

鳥の鳴き真似、まるで本物!
※自然遊びの先生はお父さん、ということでしたが、お父さんから鳥の鳴き真似も習ったそうですね?
「そうですね。二代続けて小さい頃から鳥の鳴き声ができるように、歯笛(はぶえ)で・・・父親もちょっと歯に隙間があって、そこに息を吹き込んだりして鳴き真似をするんですね」
●レパートリーってどれぐらいあるんですか?
「だいたい10種類くらいの鳥を呼べますね」
●へぇ〜! 今(鳴き真似を)できたりしますか?
「やってみましょうか」
●やったぁー! お願いします。
「森に来たと思って聴いてみてください。何種類かやってみますね。[土屋さんの歯笛で鳴き真似♪] 聴こえましたか?」
●すごーい! 森ですね!
「森に来ましたか」
●森にいました!(笑)すごーい! 本当に鳥じゃないですか、土屋さん!
「そうですね。きのうもガイドウォークで鳥を呼んだら20羽ぐらいきて、みなさんびっくりしていましたね」
●ちなみに今やっていただいたのは、なんという鳥なんですか?
「シジュウカラっていう鳥と、あとはメジロですね」
●今は歯でやっていたんですよね。
「そうですね。歯の隙間で・・・」
●それで鳥を呼び寄せるわけですね。
「そうです。シジュウカラは何を言っているかがわかるようになってきて、それを研究しているかたもいますね。その鳴き声によって、逃げろーとか、ヘビが来たよーとか、求愛だったりとかですね」
●どうやって聴き分けるんですか?
「鳴き声のトーンがやっぱり違ったりするので・・・。さっきはメジロの高鳴っていうのをやっていて、これは求愛だったんですけど、”チュウチュウチュウチュウ”と上にあがって、ずーっと鳴いていくんですね」
●では、求愛じゃないバージョンもあるっていうことですね。
「はい、鳥をずーっと1年中、見ていると、ウグイスは春から夏にオスしか鳴かなくて、”ホーホケキョ”と。でもそれ以外は地鳴きと言って、”チャッチャ”っていう鳴き声だったりとか、実は1年中、ウグイスはいるんです」
●面白いですね〜。鳴き真似をいろいろ研究するっていうのもいいですね〜。
「そうですね。地方によってウグイスも鳴き方が違ったり、方言があったりとかして面白いですね」
●えーっ! 鳥にも方言があるんですか?
「はい。やっぱりそこにいる鳥の、いちばんかっこいいオスの鳴き真似をするんですね。鳥はそこが面白いんですね」
●鳥の世界にもカリスマがいるんですね!
「そうですね。かっこいい鳴き声がするほど、メスが寄ってくるという・・・」
※もう少し野鳥の鳴き真似を聴きたいと思って、土屋さんにお願いしました。続いては、シジュウカラの求愛です。
[土屋さんの歯笛♪]
●あともうひとつ、なにかあります?
「いちばんみなさんがわかるウグイスですかね。ウグイスの場合は歯笛じゃなくて口笛ですけど、ちょっとやってみましょうか。[土屋さん歯笛♪]」

五感メソッド〜12段の石積み
※森林セラピーガイドとして、一般のかたを森にいざなう活動を続けていく中で「五感メソッド」という手法が確立していったと聞いています。どんなメソッドなのか、教えていただけますか。
「自分の五感メソッドは、やっぱり鳥と会話ができるっていうのが強みですね。見る体験、聴く体験の、五感のうちの二感を自分ができるというのが・・・。
あと調理師(免許)を持っているので、地産地消じゃなくて自産自消ですね。自分が作ったものとか、あとそこにあるものをみなさんで採って食べる・・・食活って言うんですけど、嫌いなものも、お子さんでも自分で採ったものは食べられるっていう食育活動・・・そういうのもやっていますね。
森活と言って、森の活動もしていながら、森の中でゴミ拾いだったりとか、あと森の中に来てもらって、座感って言うんですけど、座って深呼吸してもらったりとか・・・。
普通のガイドウォークではなくて、石積みをするんですね。石も12段積むっていう、これも自分が考えたメソッドに入っているんですけど、5段6段は誰でもできちゃうんです。12段っていう壁がありまして、これは石と意思の疎通ができないと、自分の心と石が体験や体感して、本当に体が一体にならないと12段って結構難しいんですね」
●確かに。石を12段積み上げるんですよね。グラグラしちゃいそうですけれど。
「グラグラしている時は心も揺らいでいたりとか、それこそ本当に石と意思疎通・・・(笑)」
●すごく集中できそうですね。
「最初はみなさん、ちょっと疲れているかたとか、あんまりやりたくなかったりとかする中、それでもよくて、深呼吸をしながら・・・誰かがひとつ達成すると、私も! ってなるんですね。最後には本気で12段を積んで帰って行かれるんですね」
●みなさん、できるようにはなるんですか?
「はい、必ずみなさん、なっていますね。時間はかかりますけど」
(編集部注:土屋さんが森林セラピーガイドの資格を取ることにしたのは、新宿で調理師として働いていた頃、都会の空気や仕事のストレスで体に不調をきたした時に、森の中に座っているだけで体力や気力が蘇ってきたからだそうです。
そんな経験から森には癒しの効果があると確信、その理論や科学的な根拠を身につけるために、試験の3日前に申込み、猛勉強をして見事、合格したそうです)
森の中で婚活イベント
※土屋さんは、意外な活動として、アウトドアでのウェディングや婚活のプロデュースもされていますよね。
「そうですね。自分も装飾デザイナーとかフラワーデザインの資格を取りました。生け花とかもひと通り全部学んで、それもちゃんと勉強したんですけど、やっぱり自然を知っているので、先生たちはなにも教えることがないっていう、最初から基本を知っているというか、自然で僕は生まれているので、ほかの人よりは全然違うというふうに言われましたね」
●さすが野生児ですね!
「もう野生爺になってきましたけど(笑)」
●あははは。アウトドアでのウエディングですとか、婚活のプロデュースっていうのは、具体的にどんなことをされているんですか?
「婚活については、自分が手掛けたのは、森の中で、石のところに女性が座っていて、それで男性がそこに5分なら5分、最初から座ってもらって、リラックスしたアイスブレイクした状態から始まるんですね。だからやっていく回数ごとに結婚された方とかいらっしゃいますね」
●え〜っ! マッチング率が高いんですね。
「マッチング率、すごく高いですね」
●どういうパターンがいちばんマッチング率が高いなって感じましたか?
「やっぱり自然の中で体験や体感することですね。それこそヤマメを手で捕ってもらうとか、男女がキャーキャー言いながら捕って、それを塩焼きにして、みなさん同じ行動をして焼いて食べる、そのヤマメの美味しさと同時に婚活ができるみたいな・・・」
●面白いですね。確かに自然の中でやるっていうのがすごくリフレッシュ、リラックスして、素になれそうな感じもしますよね。
「そうなんです。最初からもう素で、お互いが素で、そこでバーベキューとかすると、所作が綺麗だったりとか、違うところが見えてくるじゃないですか、お互いに。この人、火を起こせてかっこいいって思ったりとか、そういうのが生身の人間なので、最初に飲み会とかではなくて、自分の場合はフィールドが森なので、森の中で演出しながら、森の婚活事業をやっています」

野生児を次世代に
※それでは「森の演出家」としての夢を教えてください。
「夢はやっぱり次世代に残したいなと思って、全国に森の演出家が、森プロがいっぱい増えればいいなと。結構これは難しいと思ってはいるんですけど、野生児を次世代に残さないといけないので、小さいお子さんもどんどんフィールドに行ってもらって、野生児を今増やしているところです」
●では最後に、東京最後の野生児として伝えたいことをお願いします。
「やっぱり野生児は森に生かされている、自然がなければ、森の活動ができないので、自然はやっぱりすごく大切なものですよね。
温暖化になってきましたけど、いろいろなものがやっぱり変わって、東京の奥多摩でも変わってきたり、温度が高くなっているとか・・・そういうことも小さいお子にも学んでもらう、そういう教室も始めていますので、次に繋がる森の演出家になりたいと思っています」

INFORMATION

土屋さんは、東京の青梅と奥多摩の古民家を拠点に森林浴ほか、森の中で鳥の声を聴いたり、多摩川の水に触れたり、森の恵みを食べたりと、五感を使った2時間のガイドウォークを実施。企業研修や免疫力アップなどにも活用されているそうです。
ほかにも森の演出家協会では新潟県長岡で、キャンプのノウハウを、実践を通して学ぶ「キャンプの楽校」なども実施されています。
詳しくは一般社団法人「森の演出家協会」のオフィシャルサイトをご覧ください。
◎「森の演出家協会」HP:https://www.mori-pro.life/
2022/10/9 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、海洋ごみ由来の再生ポリエステルで作ったウエアを展開するアパレルブランド「マリブシャツ」のブランドマネージャー「菅井章弘(すがい・あきひろ)」さんです。
2004年にアメリカ・カリフォルニアのマリブビーチで誕生したマリブシャツ。創業者はグラフィック・デザイナーで広告デザイン事務所を経営していたデニー・ムーアさん。
若い頃から海とサーフィンを愛し、アンティークな広告アートやサーフシーンの写真をコレクションしていたデニーさんが、Tシャツに、集めたアートや写真をプリントして販売したのがきっかけで、マリブシャツというブランドが生まれたそうです。その特徴はビンテージライクでシンプルなデザイン、ラインナップはTシャツやパーカーがメインとなっています。
日本版のマリブシャツは2021年から販売がスタート。オリジナルのマリブシャツがコットン製なのに対して、日本版は海洋ごみ由来の再生ポリエステルを使っているのが大きな特徴です。
これは菅井さんをはじめとする日本側のスタッフが、ビーチやサーフシーンで愛されているマリブシャツであるならば、ブランドとして自然環境になにか貢献できないか、そんな思いから「海への恩返し」というコンセプトが生まれ、海洋ごみを原料とする再生素材のブランド「マリブシャツ・ジャパン」が誕生しました。キャッチコピーは「このウエアは海をきれいにする」となっています。
菅井さんにお話をうかがう前に、海洋ごみの現状について。
プラごみは、年間におよそ800万トンもの量が世界の海に流れ出ているとされていて、これはごみの収集車に換算すると、1分に1台分のプラごみを海に捨てているのと同じだそうです。このまま増え続けると、世界の海に流れ出ているプラごみは2050年には魚の量を超えると言われています。
海洋ごみの問題にどう取り組んでいくのか、いま私たちの覚悟と行動が問われています。
そこで今週は、シリーズ「SDGs〜私たちの未来」第9弾! 「SDGs=持続可能な開発目標」の中から「海の豊かさを守ろう」!
☆写真協力:マリブシャツ

シンプルでお洒落! 水陸両用!?
※それでは、ブランドマネージャーの菅井章弘さんに商品の特徴について具体的にお話をうかがっていきます。

●きょうはマリブシャツの商品をたくさんスタジオにお持ちいただきました。ありがとうございます。それぞれ商品の説明をお願いします。これはショートパンツですか?
「これは我々がラッシュガードと呼ぶ素材、あだ名なんですけど、その素材を使用しております。要は海でも街中でもプールでも着用できる、そういうものです」
●すごくシンプルでワンポイントのロゴがあって、これはいいですね。女性も男性も着やすいというか・・・いま菅井さんが着てらっしゃるのもそうですか?
「同じ素材のTシャツです。そもそもこの素材でTシャツを販売していたんですね。で、お客様のリクエストで、この素材でパンツができないですかという声をいくつか聞くようになったのと、あとは今の流行りですけど、セットアップできるとかっこいいので、それでパンツも作ってみたという次第です」

●シンプルですごくお洒落、モダンでかっこいいですね。ほかにもTシャツ、パーカー、ロング Tシャツ、トレーナーなど、いろんな商品をお持ちいただきましたけれども、ひとつずつご紹介いただけますか。
「まず、今おっしゃっていただいたような商品群というかアイテムを作っている理由なんですけど、これも本国のマリブシャツ、彼らも同じようにTシャツやパーカーばかりを作っているんですね。彼らはそのことでカリフォルニアであるとか、ハワイとかの海辺のライフスタイル、これを提案しているんです。
僕らの場合はビーチサイドというよりは、ベイエリアって感じで都市部も含んだ、でも海を感じられるようなリラックスしたライフスタイルの提案をしたいということで、トレーナーやパーカー、Tシャツなどに商品を絞っております。

僕たちの特徴としては、先ほどからお話している海洋ごみからリサイクルされたポリエステルを原料にして商品を作ろうということを決めてやっております。ただポリエステル100%にしてしまうと、作れる商品の幅が狭くなってしまいますので、ポリエステルと綿のミックスのグループであるとか・・・」
●気持ちいいですね、肌触りも・・・。
「これはすごく手をかけて作っております。あとは先ほどのショートパンツや、僕が着ているT シャツに機能を持たせるために、敢えてポリエステル100%で作っている商品のグループもあります」
●撥水加工というか・・・?
「撥水というより、濡れても全然いいっていう状態ですね。これを販売されているアパレル様にも僕ら卸しているんですが、水陸両用なんて言って販売されたりしています」
ONE OCEAN、未来につなぐ
※マリブシャツの素材になっている再生ポリエステルの原料は、どこで作っているんですか?
「北米にある再生原料を主に作っているプラント、企業がございます。そちらから原料を購入して、僕たちが糸から作って生地にして、洋服にしているという流れです。
ここにその見本があるんですが、その北米の企業は大型の船を出して、例えば太平洋でごみを回収するんですね。その回収したごみを自分たちのプラントに持ち込んで、洗浄して砕いたものがこの状態です。ガラスの破片みたいな、これを溶かして、ティペットっていうんですけど、このつぶ状のものがポリエステルの原料です」

●ガラスの破片みたいなものからビーズのような形状になりましたね。
「この状態にすると移動ができるんですね。この状態から様々な、例えばこういうペットボトルも作られます。この状態のものを、彼らが原料を供給する工場が中国にあるんですが、その工場に持ち込んで、この綿の状態にまで彼らがしてくれます」
●ビーズのような状態から綿に・・・?
「溶かして小さなノズルから吹き出すことで、この繊維状のものができるんです。ただこの綿だと洋服にはならないんですね。ここから綿とミックスしたり、いろいろな手法で、僕たちが糸を作るんです。この糸を編んで生地にして洋服になっています」
●なるほど〜、そういう経緯なんですね。海洋ごみ由来のエコ素材の名前が「ONE OCEAN」って言うんですよね?
「マリブシャツを始めるにあたって、立ち上げたというより、そもそも我々が開発を進めていた素材になります。マリブシャツ・ジャパンとしてマリブシャツ・チームとして、今はマリブシャツのためにこのONE OCEANという素材グループを使っております。
ONE OCEANというのは、海洋ごみからリサイクルしたポリエステルを原料にした素材のグループです。その中にこのような、ボクらがTCと呼ぶ、綿と混紡した素材であるとか、ポリエステル100%の素材であるとか様々あります。
我々がONE OCEANっていう名前をこのグループに付けたのは、やはり海はひとつしかない、これに尽きます。しかも未来につなぐのにもひとつしかないから、そのひとつを守ろうという意味でONE OCEANという名前をつけました」
使ったプラごみの量を表示!?
※商品に「ONE OCEAN」のカードが付けられていて、その裏にペットボトルの絵が表示されていますが、これは何ですか?

「これはそのものずばりこの商品に含まれている、海で回収されたごみの量を1.5リットルのペットボトルに換算して表しております」
●このパーカーは8本分くらいですね。
「8.3本ですかね。大きなペットボトル8.3本分の、海のプラごみがなくなって、ここに入っているという、その証です」
●そうなんですね〜。地球にいいことしているなっていうことを、着ながら感じられますね。
「そう思っていただきたく・・・」
●ブランド「マリブシャツ」のデザイン的な特徴っていうのは、どんなところなんですか?
「やっぱり僕たち、せっかく海洋ごみを再生して洋服にしたのに、すぐ飽きられて捨てられてしまうようなものを作りたくなかったので、そのことがあって、定番っていうものにこだわりました。
それと本国のマリブシャツも同じ考え方で、カジュアルな定番のお洋服、でもリラックスした生活を提供するっていうのが僕たちの狙いなんで、デザインのこだわりはもうとにかく定番の商品を作ること。
ここには私たちマリブシャツ・チームのメンバーの葛藤もあるんですけど、定番というのはなかなか難しくて、どこまでシンプルにするか、でもこれはデザインのポイントとして入れたい、みたいなことを話し合って、その中からシンプルで長く着られて、様々なコーディネートに取り入れやすいものを狙って作っております」

●シンプルなのに地味すぎないっていうのが、すごいなって思います。お洒落です。 アーティストとのコラボ商品もあるんですよね?
「これが、無地にこだわっている理由なんですが、本国のマリブシャツは、デニーさんが集めたアートをあしらって販売しております。我々もそれを考えたんですが、僕たちだけで洋服を完成させきらず、着てくださるかたとか、外の人たちと何かをすることによって完成する余白を残したいっていうのもあって、僕らは無地がメインになっているんですね。なので、時折アーティストのかたとコラボレーションをして、そのかたのアートをプリントして販売しております。
その中で国内だと、中西伶さんや小泉遼さんの絵をプリントしてっていうことをしております。アーティストさんとのコラボは、いま名前を挙げた画家のかた、あとはカメラマンさんとか・・・アーティストという意味では、フラワーアレンジメントのとても著名というか若いかたなんですけど、元気に活動されているかたがいます。そのかたとも共感した時に、アレンジした花をカメラマンさんに撮っていただいて、コラージュしてっていう形でのコラボもあります。
コラボレーションする時の考え方は、そのかたとシンパシーがあった時とか、アーティストのかたも、マリブシャツが海洋ごみから再生して上質なものを作っている、そういうことに共鳴して(一緒に)やろうって言ってくださったり・・・そういう時にコラボレーションしております」
(編集部注:マリブシャツはアーティストとのコラボのほか、BEAMSのB:MINGやSNIDELといったアパレルブランドともコラボレーションしたことがあるそうです)
マニラ麻やバナナでエコ素材を開発!?
※マリブシャツは、アパレル関連の事業を行なっている「MNインターファッション」という会社のブランドですが、このMNインターファッションでは、マリブシャツで使っている海洋ごみ由来の素材のほかにも、エコ素材を開発しているそうです。どんな素材があるんですか?
「素材では”ブリコ”という素材のブランドを持っております。特徴としては、インドの工場にいらなくなった廃棄衣料を持ち込んで、反毛(はんもう)っていうんですけど、砕くんです。そして綿状にして、ここからまた糸を再生して生地を作る、そういうリサイクルの生地のブランドがあります。
あとは、エコ素材で”ワクロス”あるいは”バナナクロス”という、これも商標をとっている我々の生地ブランドなんですが、綿=コットンは栽培するために水を大量に使う、あるいは土地を痩せさせてしまうことがあるんですね。
なので、綿よりももっと効率的に成長してくれて繊維が取れるもの、ということで、ワクロスには成長の早いマニラ麻を使っています。これはひとつの畑で1年間に何度でも採れるんですね。水を使わずに土地も傷めずにどんどん成長してくれます。このマニラ麻を紙にして、この紙を繊維状にしたものがワクロスです。紙にすると抗菌性とかいろいろな機能がつくので、役に立つ素晴らしい素材になるんです。
あとはちょっと面白いんですけど、バナナクロスはバナナの幹の部分を使っているんですよ。栽培されているバナナは、実を採る時に幹ごと切っちゃうんですよね。実を採ったあとの廃棄される幹はすごい量になるから、これを再利用しようと・・・植物なので幹から繊維が採れますから、その繊維を生地にしたり・・・このような素材があります」
海のごみをなくしたい!
※国連が主導する「持続可能な開発目標=SDGs」もそうですけど、環境に配慮しない企業は今後、生き残れないと思うんですが、菅井さんはどう思いますか?
「これは本当にそう思います。企業にだけその責任を負わせるのではなく、我々も生活の中で、そのことを考えるべきだなってものすごく思います。
そこがそもそもマリブシャツをやろうなんて言い出したところでもあるんですけど、我々マリブシャツ・ジャパンのメンバーはアウトドアとかサーフィンをやるメンバーが多くて、常に自分が触れている自然が汚れているとか、海が汚れているとかって気になるんです。
ほんとに目に見えて分かることだから、まずはそういうこともあるし、あとはカーボンニュートラルのこともそうですけど、とにかく、僕たちが安全に生きるためには、どうしても化学的に作ったケミカルなものも必要だと思うんです。
ただ、やりすぎ、使いすぎで、地球がおかしくなるようなところには行ってはいけないし、行きつつあるから、今おっしゃられたようなサステナブルな目標はいろいろ項目がありますけれども、ちゃんと考えて、それを抑えてやっていく活動がなかったら、もう地球が持たないと思うので必要なことだと思います」
●そうですね。先ほどマリブシャツ・ジャパンのメンバーにはアウトドア好きが多いとおっしゃっていましたけど、菅井さんもサーフィンをされるんですよね。
「恥ずかしながら。もう引退してしまったんですけど・・・」
●引退・・・?
「もう僕は50を越しているので、ちょっと今は行っていないんですけど、40ちょっとまで・・・20代前半ぐらいから20年間ぐらいはサーフィンをやっておりました」
●わ〜〜、どの辺りで?
「僕、生まれが茨城県なのですが、阿字ヶ浦とか大洗とかでガンガンにやっていました」
●かっこいいですねー!
「全然(笑)カッコよくないです。ちょっとここでサーフィンの話を挟みたいんですけど、僕ら茨城勢から見ると湘南のサーファーとかすごくカッコよくて、ウエットスーツとかも綺麗だし、持っているボードのブランドとかも! 千葉もそうですよね、お洒落! だけど茨城のサーファーは今は違うんでしょうけど、僕がやっていた頃はウエットスーツはみんな黒一色だし、あまりカッコよくなかったです」
●え〜〜、そうなんですか(笑)。マリブシャツの創業者デニー・ムーアさんもサーファーなんですよね?
「デニーさんもサーファーです。彼はマリブビーチってところで生まれたから、小さい頃から海に触れ合っていて・・・あとはご両親の趣味なんでしょうね。デニーさんから聞いたんですが、小さい頃からハワイによく連れて行かれていて、日本でいう沖縄旅行みたいなものですよね」
●菅井さんもデニーさんもサーファーということですから、お互いにシンパシーみたいなものを感じたんじゃないですか?
「お互いにルックス的には元サーファーですね。現サーファーって感じじゃないですね(笑)」
※では最後に、ブランド・マネージャーとして、マリブシャツというブランドを、どんな風に育てていきたいですか?
「やっぱり最初に立てた志というか、本当に海洋ごみはすごいことになっていて、これを取り除くためには、ただ取り除いてくださいって言っても、誰も手を出せない。でも取ってくれば、このように原料になって再利用して洋服が作れる。だからこれをどんどんとにかく続けていきたいですよね。そして海のゴミをなくしたい。これが僕たちの今強い思いになっているので、それを続けていくというのが願いですね」

INFORMATION
アパレルブランド「マリブシャツ」

マリブシャツの Tシャツやパーカーは、本当にシンプルなデザインで、カラーの基本は黒と白。素材の質感が素晴らしく、生地もしっかりしているので、長く着られる、まさに定番ウエア、おすすめです。ぜひお試しください。
お買い求めは「マリブシャツ」のECサイトから、どうぞ。
◎「マリブシャツ」HP: https://malibushirtsjapan.com/concept
2022/10/2 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、イラストエッセイストの「松鳥むう」さんです。
漫画風なイラストと親しみやすいエッセイで人気の松鳥さんは、離島とゲストハウス、そして地元滋賀県内の民俗行事をめぐる旅をライフワークとされています。
20歳のときの卒業旅行で、屋久島に行ったことをきっかけに島旅にハマってしまった松鳥さんは、これまでに118の有人島を訪れていて、泊まったゲストハウスは100軒以上。その土地の日常の暮らしに、ちょっとだけお邪魔させてもらう旅が好きで、地元の民俗行事や郷土料理との出会いも大事にされています。
きょうは主に、あまり知られていない珍しい郷土料理のお話などうかがいます。
☆写真&イラストレーション:松鳥むう

元気の素、鹿児島の茶節
※松鳥さんは先頃『むう風土記(ふどき)〜ごはんで紐解く日本の民俗・ならわし 再発見録』という本を出されました。この本の狙いは、どんなところにありますか?

「幅広い年齢のかたに読んでもらいたいのと、自分の地域を改めて見る、みたいなことをしてもらいたいなと思ってるんですね。イラストをいっぱい入れたのは、文字が読めない小っちゃい子でも、イラストを見て面白いなと思ってくれたらいいなと思って・・・。
あと、私がボキャブラリーが少ないっていうのもあるんですけど、わかりやすい言葉で書いているので難しくないです。私が民俗行事にハマった時に、いろいろ面白いなと思って、本をあさったんですけど、先生がたが書いていらっしゃるのが多くて、興味はあるけど難しくて、読んでいる途中からカァーって寝てしまって(笑)・・・もうちょっととっつきやすいのがあったらいいなと思って、そんな感じで書いています」
●とっても読みやすかったです〜。この本に載っている記事の中からいくつかお聞きしたいと思うんですけれども、いろんなご飯が載っていましたね。興味深い食がたくさんあったんですけれども、まずは鹿児島県の”茶節(ちゃぶし)”。これはどんなものなんでしょうか?
「味噌汁を飲むような汁物の茶碗にお味噌を大さじ一杯、鹿児島なんで麦味噌なんですけど、そこに鰹節をひと握り入れて、そこにお茶をかけて飲むんです。簡単に言えば、グツグツしない超簡単な味噌汁ですね」

●本には「元気の素(もと)」、そして「のんべえの安らぎ」とも書かれていましたね。
「後半のは私の感想なんですよ、のんべえなんで(笑)。元気の素は鹿児島の郷土料理で、茶節はそうだって言われているんですけど、おばあちゃん世代でも、今はあまり飲む人がおられないらしくって、だいぶ上のおばあちゃん世代の人たちが毎朝飲んだりとか・・・。
あと、風邪をひいた時に親が作ってくれたという人がいたりしますけど、私はこれ(お酒を)飲んだあとの一杯に絶対いいと思っていて、全国の居酒屋の締めのメニューに入れるべきだと私は思っているんですよ(笑)」
●私ものんべえなので、すごく興味深いです!
「ちょっと飲んだあと、茶節を飲んだら二日酔いないですから、ぜひ飲んでください、簡単なんで」
●味はお味噌汁みたいな感じってことですよね?
「そうですね。お味噌の味と鰹節の出汁が勝っちゃうので、そんなにお茶の味はしないです。自分で作るときは、地元の人がお茶でもお湯でもいいって言ってたんで、自分の家でやるときはお湯をかけてやります」
(編集部注:沖縄にも「カチューユー」という、同じような汁物のお料理があるそうです。茶碗などに味噌と鰹節を入れてお湯を注ぐだけ。食欲がないときや風邪をひいた時などにおすすめだそうです)
記憶を失う!? 白川村の「どぶろく祭り」
※新しい本『むう風土記』で、岐阜県・白川村で開催される「どぶろく祭り」が紹介されていました。これはどんなお祭りなんですか?
「 毎年9月から10月に行なわれるんですけど、私が書いたのはその白川村の中でも平瀬温泉っていう、みなさんが知っているあの観光地の白川郷からちょっと離れているところなんですよ。10数キロ離れているところで、同じ村なんですけど、そこの集落の『どぶろく祭り』にお邪魔したんです。
どぶろくは、みなさんご存知の通り、あの白いどろっとしたやつなんですけど、それを神社で作っていらっしゃいます。全国各地にどぶろく祭りはあって、そういうところはたいがい地元の神社にどぶろくを作る場所があって、地元の人が作らはるんですけど、特別な許可をもらって作っていらっしゃって・・・。
この祭りがすごいのが、コロナ禍ではほかの場所の人とか入れなくてダメなんですけど、コロナ前の時はお客さんとか観光の人も来てよかったんです。観光地の白川郷のほうでも、別の神社でどぶろく祭りがあるんですけど、そっちだと観光客が多いから、どぶろくをひとり一杯ぐらいしかもらえないらしいんです。平瀬温泉のほうはそこまで観光客が来ないらしくて、何杯も飲めるって言われたんで喜んで行ったんですよ。

最初からどぶろくを飲むだけの祭りじゃなくって、ちゃんと獅子舞とかまわったりするんですよ。それで最後、神社でみんなござを敷いて、そこにみんな座って、どぶろくを注いでくれるお姉さまがたが、席をまわってくれはるんです。
まぁ“わんこそば”のように、なくなったと思ったら、いきなり現れてまた注いでいって(笑)、最初は観光客やからあんまり飲んだら申し訳ないと思って、遠慮していたんですけど、あまりにも来てくれるんで、喜んで飲んでいたら、記憶が一瞬のうちに消えて! すごいです、どぶろく。
でも地元の人たちはみんなそれを飲んで、さらにそのどぶろくを飲んだあとに、集落の別のスペースにステージを組んでいて、その平瀬温泉地区に住んでいる人たちはみんな芸達者で、みんなそこのステージで(芸を)発表されるんですよ、どぶろくをたんまり飲んだあとに!
私は記憶がなくなっているから、それを見てないんですけど、見た友達はめっちゃ素晴らしくレベルが高いって言ってはりました。しかもその平瀬温泉集落の人は芸達者の人が多くて、芸能プロダクションみたいなものを自分らで作っていて、若い人からおじいちゃんおばあちゃんまで入ってらっしゃるそうです」
●活気がありますね!
「ありすぎて、普段すごく小っちゃい集落なんで、そんな人がたくさんいるように見えないんですけど、すごいんです」
地元の人でも知らない納豆餅
※松鳥さんの地元滋賀に「納豆餅」という食べ物があるんですね?
「そうなんですよ。滋賀でも、私もその地域の人ではないので、全然知らなかったんですよ。滋賀県の大津市の山のほうに仰木(おうぎ)っていう地区があるんですけど、そこだけで食べられていて、ほかの人は多分、滋賀県の人も全然知らないんですよ」

行事食「納豆餅」
●どんな食べ物なんですか?
「たぶん関東の人は納豆餅っていうと、東北の丸めたお餅に納豆をまぶして食べるっていうのを知っている人が結構多いと思うんですけど、滋賀県のほうのは丸めたお餅を一回開いて、丸い平らな形にして、そこに納豆を置いて、納豆を餅で包んで食べるんですよ。三角チックな形で手も汚れず食べやすいという・・・。
しかもその餅のまわりにきなこをまぶすんですけど、きなこは砂糖じゃなくて塩味にしてまぶすんです。納豆と塩は合うじゃないですか。めっちゃいいですよね。
東北の納豆餅をお箸で食べると、納豆と餅がいつもバラバラになってうまく食べられないんですよね。餅を食べたあとに納豆を食べるみたいになってたから、包んでしまうとめっちゃ食べやすいみたいな・・・」
●なるほど〜。
「その滋賀県の納豆餅が、山を越えた隣の京都の山側にも、同じような納豆餅があって、そちらはバリエーションがもっと豊かなんですよ。
滋賀県と同じ包むバーションもあったり、ロールケーキみたいにして、ロールケーキのスポンジが餅で、中のクリームの部分が納豆みたいなロール状のとか、あと普通に切り餅、餅に埋め込んで四角い、よく売っている形にしたバーションとがあるんですよ」
●へぇ〜すごい。納豆文化があるっていうことなんですかね?
「そうです、そうです。昔から、平安時代の貴族の人は食べていたっていう文献があるらしいので(納豆文化は)あるんですね。その納豆餅のエリアは、田んぼのまわりに昔は大豆を植えていたので、どこの地域でも植えていると思うんですけど、大豆の栄養が稲にいくからいいっていうので、それで大豆があるから納豆を作っていたっていう感じらしいです」
(編集部注:ほかにも松鳥さんの地元滋賀には、ドジョウとナマズとご飯を漬け込み、発酵させた「ドショウとナマズのなれずし」という珍味があるそうです。松鳥さんがおっしゃるには、ブルーチーズの味にやや近い感じだそうですよ)

千葉の郷土料理「しもつかれ」
※千葉県のおすすめの伝統料理はありますか?
「千葉の人には多分メジャーではないと思うんですけど、今回の本にもちょっと書いている”しもつかれ”っていう料理があって、主には栃木県あたりがメインの郷土料理として取り上げられることが多いんですね。
このしもつかれっていうのが千葉と茨城と栃木と埼玉・・・きゅっと集まった県境があるじゃないですか。あの辺の郷土料理で、毎年初午(はつうま)の日に食べられる郷土料理なんです。だいたい2月の節分のあとぐらいなんですけど、その時に農家さんが地元の稲荷神社に、赤飯としもつかれを供えるっていうことなんです。
なぜ名前が“しもつかれか”っていうのは、話が長くなるので、それは本を読んでいただきたいなって思うんですけどね(笑)。
(具材として)入れるのは、大根と人参と油揚げ、あと酒粕と鮭の頭を入れて煮て、大根と人参は“鬼おろし”っていう台所用具でガリガリガリガリ擦って、鮭の頭も細かくなるまで煮る料理なんですね。
昔は年末に“年取り魚”っていって、塩鮭か塩鰤(しおぶり)を食べる文化が昔は各地域にあったんですけど、塩鮭が1月になってもちょこちょこ食べて、最後に余った頭まで残さず全部食べてしまおう、みたいのも合わさってできた郷土料理ですね。酒粕も入れるんで、蔵で酒粕が余っているのを入れるみたいな、農家さんだから大根いっぱい余っているから入れるみたいになったらしいんです。
そこに節分の時に出る大豆も入れちゃう、みたいな・・・それでグツグツ煮るんですね。好き嫌いがぱーんと分かれる郷土料理で、酒粕と鮭の匂いが相まって、嫌いな人は嫌いらしいなんですけど、私は好きなんですけどね。酒粕は好きなんで・・・」
●私、千葉出身ですけど、ぜんぜん知らなかったですね〜。
「千葉も上から下まで広いですもんね! そりゃ知らんですよ」
●興味深いですね〜。
「しもつかれ、ぜひ食べてみてください」
地元のスーパーのお惣菜コーナー!?
●伝統的なお祭りとか行事って、意外と近くにあるのかもっていうのをこの本を読んで思ったんですけど。
「あります、あります! 私もきっかけは、実家の隣の町にたまたま行った日に、神社でお祭りをやっていて、そこで行事食を出されて分けてもらったのがきっかけだったんですよ。
郷土食とか民族行事に興味を持ったのは、30後半か40歳の時なんです。その民族行事に出会ったのが・・・ぜんぜん知らなかったので、探したら多分めっちゃいろいろ出てくると思います。ただ、その料理を作れる人は年配のかたがたが圧倒的に多いので、今のうちに巡っておかないとなくなるなっていうのはありますね」
●旅先で美味しい郷土料理とか、代々伝わる家庭の味に出会うための、なにかコツのようなものってありますか?
「地元の図書館で調べるのと、もうひとつは地元のスーパーのお惣菜コーナーに行くと、知らん食べ物がちょろっと現れるんですよ。だいたいどこに行ってもメジャーなお惣菜は一緒なんですけど、あれ? これなんやろ? みたいなのがあるので、その時はそれを買って食べてみて、みたいな・・・」
●旅先で出会う食から、松鳥さんはどんなことを感じますか?
「材料が当時は豊富にあったであろうから、その郷土料理ができあがったけれど、環境や物流の変化でどんどん変わっていって、逆に揃えるのが大変になって、それでどんどん食べる人がいなくなって、現代の環境と合わないから、廃れていくんだろうなと思いつつ・・・。
でも、その料理がこの食材で作られたのはどうしてかって調べていくと、昔の人の生活とか物とか、人がどういうふうに動いていたのか・・・今とは違うルートで動いているんですよね。離れた地域に同じ食があったりしていて、その辺を巡っていくのも楽しいなって思います」

有人島・沖島から比良山系を望む

☆この他の松鳥むうさんのトークもご覧下さい。
INFORMATION
『むう風土記〜ごはんで紐解く日本の民俗・ならわし 再発見録』
松鳥さんの新しい本をぜひ読んでください。松鳥さんが旅で出会った食文化や伝統行事などがイラストともに紹介されています。こんな郷土料理があったのか、と驚きの連続で、楽しく読めますよ。おすすめです。
「A&F」から絶賛発売中です。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。
◎「A&F」HP:https://aandf.co.jp/books/detail/mufudoki
本の発売を記念して、松鳥さんのトークイベントが10月22日(土)の午後2時から、東京駅前の新丸ビル7階の「MUSMUS」で開催されることになっています。山形県酒田市の郷土ごはんと飲み物がついて、入場料は2,000円。
詳しくは松鳥さんのオフィシャルサイトを見てくださいね。
◎松鳥むうさんのサイト http://muu-m.com
2022/9/25 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、中部大学・准教授で、
サボテン博士の「堀部貴紀(ほりべ・たかのり)」さんです。
堀部さんは岐阜県出身。名古屋大学大学院を修了後、1年ほど岐阜放送・報道部に勤務。その後、研究の道に戻り、現在は中部大学でサボテンを研究中。日本では数少ないサボテン博士でいらっしゃいます。
堀部さんがサボテンを研究するようになったきっかけは、日本でいちばんサボテンの生産量が多いとされている愛知県春日井市のお祭りで、食用のサボテンに遭遇したこと。名古屋大学で園芸学や植物生態学を専攻していた堀部さんは俄然、サボテンに興味がわき、また、国内でほとんど研究されていないことを知って、春日井市にある中部大学にいれば、サボテンのサンプルがたくさん手に入る、そう思い、2015年からサボテンを専門に研究されています。
そして先頃『サボテンはすごい! 過酷な環境を生き抜く驚きのしくみ』という本を出されました。
きょうは、ほとんど知られていないサボテンのトゲの秘密のほか、いま世界が注目している、地球を救うかも知れない、サボテンの計り知れない可能性についてうかがいます。
☆写真協力:堀部貴紀

トゲの、驚きの役割
※園芸用として人気の多肉植物がありますが、サボテンも多肉植物、ですよね?
「はい。サボテンも基本的には多肉植物です。ただし、多肉植物って結構いい加減な言葉でして、学術上の定義がないんですね。こうだったら多肉植物という定義がなくて、だいたい水っぽくて膨らんでいたら、多肉植物っていう言葉の使われ方をしているんです。
でもサボテンの中には見た目が樹木みたいな、木みたいなサボテンもいるので、多肉植物じゃないサボテンもいます」
●へぇ~、そうなんですね。アロエはサボテンじゃないんですか?
「よく言われるんですけど、アロエはサボテンじゃないんですね。で、サボテンは何か? ってことなんですけど、サボテンは、バラ科とかイネ科とかあると思うんですけど、サボテン科っていうのがあって、サボテン科に含まれるやつをサボテンと言います」

●サボテンは世界に何種類ぐらいいるんですか?
「だいたい最近の研究だと、2000種類ぐらいですかね。ただし、品種がいろいろあって、イチゴでも『とちおとめ』とか『あまおう』とかあると思うんですけど、そういう品種を入れると、大体8000品種と言われています」
●そんなにあるんですね~。サボテンの原産国はどちらになるんですか?
「サボテンの原産国は、だいたい南北アメリカですね。結構広くて、北はカナダ南部から南はアルゼンチン・パタゴニア地方の先端までですね。南北アメリカ全体にサボテンはいます」

●そうなんですね~。サボテンの大きな特徴といえば、トゲですけれども、あれは何ですか?(笑)
「あれは葉っぱが変化したものだと言われています」
●葉っぱ!?
「昔、サボテンのトゲは葉っぱだったんですけど、葉っぱがだんだんと変化していって、葉っぱになったと考えられています」
●トゲの役割って何ですか?
「実はいろんな役割があって、まずは動物から食べられないように体を守っているよ、っていうのもあるんですけど、ほかにも例えば、強い光から身を守るカーテンみたいな役割をしたりですとか、あと高温とか低温から身を守る毛布みたいな役割をしてたりとか・・・まだまだあって、トゲから蜜をだしてアリを呼んだりとか、あと空気中の水を吸着するような機能も報告されています」
●ほぉ~、そうなんですね。サボテンは独特な形をしていますけど、どうしてあんな形になったんですか?
「まずサボテンは、丸っこいイメージがあるかと思うんですけど、あれはまず体の中に水を貯めているんですね。より具体的にいうと、茎の中に貯水組織といって、水をいっぱい貯める細胞があるんです。それがいっぱいあるから、ああいう丸くて水のタンクみたいになっているんですね。なので、長い期間、雨が降らなくても平気なんです。これまで長いものだと6年間、雨が降らなくても枯れなかったという報告がありますね」

体の一部からも繁殖!?
※植物のほとんどは花を咲かせ、タネを作って自分たちの生存範囲を広げていますが、サボテンはどうやって増えていくんですか?
「ほかの植物と同じようにまずタネで増えます。花が咲いて果実がなって、その中にタネが入っていて、そこから増えるんですけど、もうひとつ特徴的な増え方があって、植物体の一部からも繁殖するんですね。
具体的にはサボテンの枝とか茎の一部がぽろっと落ちて、そこからまた大きくなるんです。そういうのを『栄養繁殖』って言うんですけど、イモとか球根みたいなイメージですね。ぽろっと落ちた茎とかには水分がたくさん含まれているので、タネよりも生存する確率が高くなるんですね。タネはやっぱり小さいし、水もぜんぜん含んでいないけど、植物体の一部ですといっぱい水があるから、生存する確率が高いってことになります」
●サボテンの花は毎年咲くわけじゃないですよね!? 毎年咲くんですか?
「一応、毎年咲くんです。あまりサボテンの花が咲くイメージはないと思うんですけど、花が咲くまでに時間がかかるんです。種類にもよるんですけど、例えば”桃栗三年柿八年”という言葉がありますけれども、サボテンだと長いものだと最初の花が咲くまでに30年ぐらいかかります」
●だから花のイメージがあまりないんですね。
「そうなんですよね。でも1回咲くようになったら、毎年だいたい咲くんですよ」
●受粉は昆虫ですか?
「自生地ですとハチとか、夜咲く花だとコウモリとか蛾とか、まあやっぱり昆虫が多いですね」
●過酷な環境の自然界で、どうやって増えているのか、ちょっと想像がつかない世界なんですけど・・・。
「そうですよね。まあ普通にタネで増えるのもありますし、それこそトゲを使って、ほかの動物にくっついて移動していくサボテンもいるんですよ。
アリゾナ砂漠にいるやつなんですけど、“ジャンピング・カクタス”って呼ばれていて、ちょっとでも触るとトゲで体にくっ付いてくるんですよ。体の一部がぽろっと取れて、それを取ろうとすると、またその手にくっ付くので、ジャンプしているみたいだから、ジャンピング・カクタスっていうんですね。
そういうやつなんかは、本当にすれ違った動物にペタッとくっ付いて運ばれていって、別の場所で落ちて、根を張って成長するみたいな育ち方をするやつもいます。たくましいですね」
巨大なサボテンの林!?

※新しい本に、6〜7年前にアリゾナ州の国立公園に調査に行った話が載っていました。なぜアリゾナに行くことにしたんですか?
「それは、サワロサボテンっていうほんとに西部劇に出てくるような、ザ・サボテンがアリゾナ砂漠にいるんですね。それを見たかったからです」
●本の表紙になっている、大きなサボテンが林のようになっているのがその場所ですよね?
「そうです、そうです! アリゾナのサワロ国立公園っていう所ですね」
●実際にこの大きなサボテンをご覧になっていかがでしたか?
「いや〜もうびっくりというか感動ですよね! 普段そんなに生き物を見て感動するほうではないんですけれども、本当に初めて圧倒されて感動しましたね。おっ! すごいみたいな」

●大木ですよね、このサボテン!
「そうなんです。乾燥地なので木があまり生えていないんですね。さっきの大きなサワロサボテンは10メートル以上になるものも多いんですけど、それが何千本と見渡す限り生えていてなかなか感動ですよ。日本の人にも行ってほしい、本当に!」
●世界最大のサボテンが、このサワロサボテンになるんですか?
「昔はそのサワロサボテンが世界で最大だって言われていたんですけど、実は今は世界最大じゃないんです。
当時1996年には、17.5メートルあったので、ギネス記録を持っていたんですけど、2007年にほかのサボテンが19.2メートルの記録を出して、それは和名でいうと武倫柱(ぶりんちゅう)っていうサボテンがいて、(サワロサボテンと)同じような見た目のサボテンなんですけど、そっちが今は世界最大だと言われています」
●それはどこにいるんですか?
「それもアリゾナに生えているんですね。サワロと同じような場所に生えていて、見た目はそっくりですね」
●そんな大きなサボテンがいるんですね~。
「いやもう~びっくりしますよ! 近くで見たら」
●サワロサボテンに巣を作る鳥がいるんですよね?
「はい、キツツキですね。あとフクロウなんかも棲んでいますね。というのも乾燥地に行きますと木がないもんですから、サボテンがいちばん大きな植物になるんですね。なので、キツツキなんかがサボテンの幹に穴を開けて巣を作って、そこに棲んでいるんです」
●サボテンにキツツキ!?
「実際にソノラ砂漠に行きますと、サワロサボテンは穴だらけなんですよ。いたるところに穴が開いていて、その中に鳥が棲んでいるんですね。(現地に)行った時に幹をパーンと叩いたら、中から鳥がバサバサって出てきたんです。ガイドに怒られましたけれども、叩くなって(苦笑)」
●動物たちとの関係性があるんですね。
「生態系において大事な役割をしている植物を『キーストーン種』というんです」
●キーストーン種!?
「そうです。サワロサボテンはアリゾナ砂漠において、キーストーン種であるっていうふうに言われています。大事な役割をしているよ、っていうことですね」
*編集部注:堀部さんの本には、国内でサボテンを見られるスポットも掲載されています。伊豆シャボテン動物公園や筑波実験植物園などのほかに、なんと千葉県銚子市にあるウチワサボテンの群生地が紹介されています。
銚子市長崎町の海岸沿いにあって、海を背景にサボテンが見られる場所は珍しいそうで、堀部さんいわく、青い海にサボテンが映えて、おすすめだそうですよ。

メキシコは国旗にもスーパーにもサボテン!?
※サボテンといえば、メキシコをイメージするかたも多いと思います。堀部さんは、サボテンの聖地ともいえるメキシコにも調査に行かれていますが、メキシコの国旗には、サボテンが描かれているんですよね?
「そうなんです! あまり知られていないんですけど、メキシコの国旗を見ると、ど真ん中にサボテンが描かれているんですよ」
●知らなかったです! その由来は?
「ちょっと難しい話になっちゃうんですけど、昔アステカ人があちこちさまよっていた時に、神様のお告げとして、サボテンの上でヘビを食らっているワシがいる土地を探しなさい! そういうお告げがあったんですね。
そして見つかったのが、今メキシコシティがある場所なんですよ。そういう建国神話に由来していて、それで未だに国旗にはサボテンとワシが描かれているんです。国旗をよく見ると真ん中にサボテンがあって、その上にワシが乗っていて、さらに(ワシの)口にはヘビをくわえているんですよ」
●なるほど! 神話の通りなんですね。
「そうなんです!」
●メキシコでは食用サボテンをたくさん作っているんですよね。
「メキシコだとサボテンは、どちらかというと野菜なんですね」

●へぇ〜、どんなサボテンが食用に向いているんですか?
「だいたい食べるのはウチワサボテンですね。ウチワ型の平たいサボテンがあるんですけど、それを食べますね」
●どんな味がするんですか? サボテンって。
「日本にいると(サボテンは)食べられるの? みたいな、絶対まずいだろって言われるんですけど、結構美味しいんですよ。ちゃんと調理するとサボテンは美味しいんです! 言い切れますね」
●メキシコのスーパーマーケットに行くと、野菜と同じように食用のサボテンが並んでいるっていうことですか?
「普通に並んでいますし、特設コーナーを設けられることが多いですね、食用サボテン専門のコーナーが・・・。
サボテンはメキシコに行くと普通にその辺に生えているんですね。なので、昔は貧しい人が食べるものだと思われていたらしいんですけど、最近は機能性の報告なんかも多くて、富裕層が敢えてサボテンを食べるようになっているみたいです」

●ちょっとサボテンの味、想像がつかないんですけど〜。
「味はひとことでいうとネバネバして酸っぱいのが、サボテンの味なんですね。ちゃんと理由があって、サボテンはCAM(キャム)型光合成っていうちょっと変わった光合成をしていて、その光合成をするとリンゴ酸っていう酸が溜まるんです。だから酸っぱいっていうのと、ネバネバの物質は多糖なんですけど、水を逃さないためにそういうネバネバ物質を溜めているんですよ。だから酸っぱくてネバネバした味になるんです」
●酸っぱくてネバネバ・・・!?
「日本でいうとオクラとかメカブが近いですね。結構美味しいですよ」
●どうやってサボテンを調理するんですか? どんな料理に使われるんですか?
「日本だとちょっと誤った認識が広がってるんですけど(笑)、まず食べるサボテンは若くて柔らかい時のサボテンを使うんですよ。日本だと大きくなったサボテンをサボテンステーキだって言って食べちゃったりする、あれは違うんですよ。ああいうふうには食べないんですよ。大きいと固くなっちゃって、あまり食べられないんですね、タケノコみたいな感じで・・・。
メキシコや海外だと、柔らかいウチワサボテンを肉料理の添え物にすることが多いですね。というのもヌルネバ系なので、チキンとか赤みの肉とかと一緒に食べると飲み込みやすくなるんですよ。嚥下促進作用(えんげそくしんさよう)があって食べ合わせがいいと・・・。あとはそのままちょっと焼いたりとか、生でサラダに入れたりとかして食べることも多いですよね」

●へぇ〜、食べて見たいです〜。
「美味しいですよ、結構!」
*編集部注:サボテンの生産量と消費量は、やはりメキシコが世界一とされています。
サボテンが地球を救う!?
※サボテンが地球を救うと本に書かれていますが、いま世界でサボテンが注目されているそうですね。
「はい。まずサボテンに注目が集まっている理由はひとことで言いますと、どこでも育てられて用途が広いからなんですね。
具体的に言いますと、例えば野菜が育てられないような乾燥地でもサボテンなら育てられる。なので、地球温暖化や砂漠化に対して強いんですね。用途も例えば野菜にもできるし、家畜の飼料にもできるし、加工食品にもできるし、最近だとサプリメントや化粧品にも使える。つまりなんでも使えると。
さらに少ない水や肥料でも育てられるし、無駄がないと! つまり持続性がある植物として注目が集まっています。すごいんですよね。
2017年には国連食糧農業機関FAOが、これからはサボテンを積極的に使っていこうという声明も出しています。世界が注目!」

●サボテンには知られていないポテンシャルが、もっともっとありそうですね!
「そうなんです! これまでは、今もそうなんですけど、サボテンを食べるっていうことに注目が集まっていたんですね。でも、私が個人的に注目しているのは二酸化炭素の固定です。地球温暖化対策にサボテンが使えるかも知れない、というのに注目しています」
●え〜っ、サボテンが、ですか?
「そうなんです。具体的に言いますと、例えば地球温暖化を防ごうと思ったら、空気中の二酸化炭素を吸収しないといけないんですね。それで植林というのがひとつの選択肢としてあります。木を植えると。ただし、乾燥地だと木が植えられないんですね。でもサボテンだと乾燥地でも植林できる。なので、乾燥地で二酸化炭素を固定できるっていうのがひとつあるんですね。
しかも最近、実際に昨年の11月にイギリスで、COP26気候変動枠組み条約締約国会議というのがあったんですけど、そこでメキシコの企業がサボテンを使った植林事業、カーボンオフセット事業を実際に紹介しているんです。なので、すでに世界の企業は、サボテンを使ったカーボンオフセットを始めているんですね」
●サボテンって本当にすごいですね!
「すごいです! ついでに私の研究も紹介していいですか?」
●もちろんです!
「ちょうどそこをやっていまして、実はサボテンを二酸化炭素の固定に使うメリットがもうひとつあって、サボテンは空気中の二酸化炭素を結晶化することができるんです」
●結晶化!?
「具体的に言いますと、透明な金平糖(こんぺいとう)みたいな結晶に二酸化炭素を変換しちゃうんですよ。バイオミネラルって言うんですけど、石みたいにしちゃうんですね。そうするとなにがいいかって言いますと、普通の木だと枯れた時に木の中にあった二酸化炭素は全部また逃げていっちゃうんです。
なので、保持できるのは一時的なんですけど、サボテンだと体に閉じ込めた二酸化炭素の一部が結晶化しているので、サボテンが枯れても出ていかないんです」
●残るわけですね!
「残るんですね、地面に。なので、二酸化炭素の長期固定にサボテンは使えるかもしれないということです。そうすると1000年以上、安定して二酸化炭素を固定できる、そのメカニズム、どうやってサボテンが二酸化炭素を結晶化しているのかとか、その結晶がサボテンの中で何をやっているのかを私は今調べています」
*編集部注:実は堀部さんはつい最近、カンボジアに行っていたそうです。これは日本の企業や政府機関とともに行なう人道支援事業のためで、カンボジアにたくさん残されている地雷原の跡地に、食用になるウチワサボテンを植え、雇用を産み出し、産業を作るというものだそうです。サボテンの可能性がさらに広がりそうですね。
●では最後に、サボテン博士として研究対象であるサボテンから、改めてどんなことを感じていらっしゃいますか?
「そうですね。正直、サボテンに限ったことではないんですけれども、生き物ってすごいなぁっていうことですね。と言いますのは、サボテンについて調べていると、乾燥とか高温に耐えるための仕組みが何重にも存在するんです。
さっきご紹介した茎の形だったりとかトゲだったりとか、あと根っこの構造なんかも乾燥に強くなるための仕組みが何重にも備わっているんですね。それはサボテンだけではなくて、すべての生き物はそれぞれに特徴的な生きる力っていうのを持っているんです。
そういうのを見るとすごく感心しますし、なんか元気づけられるんです。生き物は、生きるための仕組みをすごく備えて、よくできているから、多分自分も大丈夫なんじゃないかなみたいに思っているんですよね。勝手に励まされるみたいな感じです」
INFORMATION
サボテンに興味を持ったかたは、堀部さんの本をぜひ読んでください。サボテンに関する学術的なことも載っていますが、サボテンの初心者のかたが読んでも「へ〜〜っ! そうなんだ〜!」の連続で、面白いですよ。アリゾナやメキシコに調査に行った時の珍道中も楽しく読めます。サボテン・多肉植物のミニ図鑑も掲載されています。ぜひご覧ください。
ベレ出版から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎ベレ出版HP:https://www.beret.co.jp/books/detail/841
堀部さんの研究室のサイトもぜひ見てくださいね。
◎堀部さんの研究室HP:https://www3.chubu.ac.jp/faculty/horibe_takanori/
2022/9/18 UP!
今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、フリーライターで写真家の「山本高樹」さんです。
山本さんは1969年、岡山生まれ。出版社勤務と海外を巡る旅のあと、2001年からフリーランスとして活動、2007年からはインド北部の山岳地帯、標高3500メートルの地に広がるチベット文化圏「ラダック」地方を長期取材。
その後もラダックの取材をライフワークとし、現地の人たちやその土地の気候風土と向き合い、丁寧な取材をもとに文章を書き、本として出版されています。そして2020年に出版した『冬の旅 ザンスカール、最果ての谷へ』が第6回「斎藤茂太賞」を受賞。
そんな「山本」さんが3年ぶりにインド北部を訪れ、先頃帰国されたということで、改めて番組にお迎えすることになりました。
きょうは最新版のラダックの旅、そして先頃出された本『旅は旨くて、時々苦い』から世界の旅で出会った「食」のお話をうかがいます。
☆写真:山本高樹

インド北部、へき地をまわるひとり旅
※山本さんはこの夏に、次に出版する本の取材のためにインド北部を訪れています。3年ぶりの海外ということで、最初は英語のフレーズがすぐに出てこなかったり、荷造りに手間取ったりと、勘が戻らなかったそうですよ。
今回訪れたのは、山本さんのメイン・フィールド、インド北部のラダック地方ということなんですが、日本から目的地まで、どうやって行ったんですか?
「僕が取材した範囲に関しては、インドの首都デリーまで日本から直行便が飛んでいますので、それに乗って行きました。
デリーからラダック地方の中心地になるレイという町までは、飛行機で1時間ちょっとで飛ぶので、往路は飛行機でそこまで行って、そのあとはひたすら1ヶ月半ぐらいずーっと車だったりバスだったり、陸路でだいたい1800キロぐらい移動しました。平坦な道は最後の300キロぐらいしかなくて(苦笑)、あとはずっと悪路でしたね」

●えぇ〜、そうなんですか。タフな旅でしたね。
「そうでしたね。トレッキングはしなかったので、そういう意味では体力は使わなかったんですけど、ずーっと悪路で揺られている状態だったので、別の意味で体力を使う旅だったのかなと思います」
●行かれたのは8月ですか?
「7月の中旬から8月の下旬ぐらいまで、1ヶ月半ぐらいという感じです」
●その頃のインド北部はどんな気候なんですか?
「僕が行った地域は、ほとんど標高が3500メートル以上の富士山ぐらいの標高のところが多くて、日差しは強くて暑いんですけれども、夜は涼しくてクーラーとか全然なくても眠れるような、乾燥してすっきりした気候ですね」
●今回もやっぱり、へき地を巡る旅っていう感じだったんでしょうか?
「そうですね(笑)。本当にへき地ばっかり。ただ、行き慣れている場所ではあるので、新鮮な驚きを持つ旅というよりは、どっちかというと帰省したみたいな感じの(笑)、久しぶりに戻ったなみたいな感じの旅でしたね」
●どのあたりを重点的にまわられたんですか?
「本のための取材という目的があったので、陸路で少しずつ移動しながら、行く先々を少しずつ、町や村の調査をしながらまわってましたね」
●今回もおひとりで行かれたんですか?
「そうですね。僕は職業がライターで、写真も撮る人間なんですね。人件費を余分にかけられないので、写真が撮れなかったらカメラマンさんをお願いするんですけど、僕は自分で撮れるので、より予算を節約するためにひとりで行くというパターンです。どんな仕事でもひとりで取材に行っていますね」

忘れられない衝撃の味
※へき地の旅は体力を維持するためにも、特に食事が大事になってくると思いますが、今回の旅で美味しいものとの出会いはありましたか?
「まわっている中で、スピティというチベット文化圏の、標高4000メートルぐらいのところにあるデムルという村に行ったんですけれども、そこに10年以上前から友達の実家があって、彼の家に泊めてもらったんです。
昔も食べさせてもらったんですけども・・・その村はたくさん牛を飼っていて、新鮮なミルクでヨーグルトやバター、チーズとか作るんですね。そこで朝ごはんにパンに付けて食べたバターやヨーグルトがすっごいフレッシュで、忘れられない衝撃の味で、本当に美味しいんですよ!
標高4000メートルの青い草しか食べていない、牛から採った牛乳で作ったバターとかヨーグルトなので、混じりっけなしのスッキリとした味なんですよ。10年ぶりぐらいに食べさせてもらって、やっぱり感動しましたね」

●いいですね〜。今回そのお友達のおうちにずっと泊まっていたんですか?
「その家に泊まっていたのは、3日間ぐらいでした。たまたま彼と連絡がとれて、行っていい? って言ったら、ちょうど今町まで車で来ているから乗っけてってあげるよって言われて、(彼の家まで連れて行ってもらって)泊まったんです」
●本当にそういうフランクな感じで旅をされているんですね。
「行く先々で知り合いの馴染みの宿のおうちに泊めてもらったりとか、友達が車を出してあげるよって言って、乗っけていってもらったりとか、その友達のやっている宿に泊めてもらったりとか、そのパターンがすごく多いですね」
●今回の旅で印象的な出来事ってありましたか?
「その友達の家に泊めてもらった時に、スピティのデムルという村に滞在している最中に、その村で夏の終わりに収穫祭をやるんですけれども、その儀式に立ち合わせてもらったのがすごく印象的でした。
あまり詳しくは話せないんですけれども、まだマル秘の部分があるので・・・(笑)、すごくいい体験をさせてもらって、いい写真を撮らせてもらって・・・それもたまたま呼んでもらって、たまたまその場に居合わせて、たまたま天気がよくってっていうパターンだったので、本当に運がよかったなと思います」
●次回の本を楽しみにしていますね! 今回の旅を通してインドやラダックの方々に対する思いとか、何か変化はありましたか?
「いや〜どうなんですかね〜。3年ぶりぐらいに行ったので、みんな感動の再会をしてくれると思ったんですけど、全然普通でなんにもなかったです(笑)。あ〜また来たの、みたいな感じで、当たり前のように扱われて、全然なにもなかったですね(笑)」
●ある意味いいですね。家族のような感じでね!
「まったくなんにも・・・親戚に久しぶりに会ったぐらいの感じです(笑)」

旅の記憶は、味の記憶に結びつく

●山本さんは先頃『旅は旨くて、時々苦い』という本を出されました。私も読ませていただいたんですけれども、「人は旅に出るとそのうちのかなりの時間を食べるという行為のために費やす」と書かれていましたね。それぞれの国で出会った「食」と共に、様々な思い出が綴られていて、情景をすごくイメージしながら、一緒に旅をしている気分になれました。
「ありがとうございます!」
●今回、「食」を切り口にした本を出そうと思ったのは、どうしてなんですか?
「もともと僕30年ぐらい前から、あっちこっち旅を繰り返してきていて、その度にまめに日記とか書いていたので、ノートは全部手元にあるんですね。そういう旅の話を、いつか振り返って書く機会があればいいなと思っていたんです。
すごく雑多な記憶の集積だったので、何をどうまとめていいのかみたいなところで考えていたんですけれども、ある時、あ! 食べたことの味の記憶っていうのは、意外とその時、経験した旅の記憶と結びついてよく覚えているなと。
やっぱり味覚って結構、五感全部を使って感じるものなので、そうやって自分の記憶に深く結ぶついた状態で保存されているんじゃないかなと思って、味の記憶を手がかりに記憶を振り返っていくと、たくさん思い出されることがありました。そういうのをまとめていくと、どうなるんだろうと思いついて書き始めたのが、今回の本のきっかけですね」

●確かに旅先での食事は、ただ空腹を満たすだけじゃない何かがありますよね?
「そうですよね。成功する時もあれば、あまりうまくいかないこともあったりとか(笑)、こんなはずじゃなかったものが出てきたりとかしますよね」
●それも思い出になりますよね。
「そうですよね。よく覚えていたりとか・・・あとトラブルにあってすごく困っている時に食べた物ってよく覚えているじゃないですか」
●確かににそうですね。
「逆に誰かに助けてもらった時に食べさせてもらった物もすごくよく覚えているし、そういう物ってずーっと思い続けていくと思うんですよね。そういうのを手がかりに本を、文章を書いてみたらどうだろうって思ったのが、この本のスタートラインだったというところです」
ドイツの安いパンと、ラダックのコーヒー
※この本に載っているエピソードから、いくつかお聞きしますね。「スーパーでいちばん安いパンとベルリンの壁」という記事がありましたが、これはどんなお話なんですか?
「これはひとつふたつ前の話から始まるんですけど、中国を旅したあとに、同じ最初の海外旅行の時に、北京からモスクワまでシベリア鉄道に乗ったんですね。
その時にたまたま同じコンパートメントになったドイツ人の若者がいて、僕とほぼ同じ歳ぐらいの人で、僕がベルリンに行くと言うと、彼がベルリンに来たらうちの大学の学生寮に泊めてあげるよって、夏休みだから空いている部屋あるから来い来い、って言ってくれて、僕はバカ正直に本当に行ったんです。
住所を頼りに出かけて行って、彼のところに1週間ぐらい泊めてもらって、居候させてもらった時の話を書いたんですけれども、今考えると、すごいなと(笑)、無茶やっているなと思うんですけどね。
その時に彼の住んでいた学生寮のすぐ近くにスーパーマーケットがあって、彼に案内してもらって、毎朝、朝ご飯に食べるパンとか、間に挟むハムとかをそこで買っていたんです。彼がいちばん安いパンがいちばん美味いぞ! って言ってくれて、確かにいちばん美味しかったんですね(笑)。
ドイツなのでパンがとても美味しくて、しかもいろんな種類のパンがスーパーに山積みになっていて、店の中にパンの焼きたての香りがふわ〜っと漂っているんです。その中でいちばん安いパンを3つ4つ買って、持って帰って半分に切って、サワークリームを塗ったりハムを挟んだり、みたいな形で食べていたっていうのを思い出して・・・」
●いいですよね〜。
「そういう話はやっぱりよく覚えているんですよね。あの時に食べたパン、美味かったなぁ〜みたいな感じで、なんか似たような匂いとか嗅ぐと、あ! あの時のあれ! みたいな感じで思い出したりとか、そういうことありますよね」
●そうですよね。記憶が蘇ってきますよね〜。あと「スノーキャップ・カプチーノと勉強の日々」、こちらはインドのお話でしたけれども・・・。
「そうですね。今年の夏も行ったラダックという場所での話なんです。僕は2007年から1年半くらい足掛け、時間をかけて、ラダックで長期取材をしていた時期があって、それはラダックについて本を書こうと思い立ったからなんですけれども、そのためには現地の言葉を学ばなければということで・・・」
●ラダック語、ですよね?
「チベット語の方言で、チベット語とも少し発音が違うんですけれども、とにかく学ぶしかないと。ちょっとでも現地の人に近づきたいなと思って・・・やっぱり現地語を喋れると現地の人の心のハードルも下がるので、なんとかしてそういう技術を身につけたいと思っていました。
時間だけはあったので、取材に行かない時に、町にいる時にはずっと勉強していたんです。その時によく通っていたお店の、当時はまともなコーヒーを出してくれる店が、そのレイという町にはあまりなくて、貴重なカフェインを摂取しながら、勉強していた時期を思い出しながら書いた文章ですね」
●「砂漠に降る恵みの雨のような存在」っていうふうに本に書かれていましたね。
「お店の名前が「Dessert Rain Café(デザートレインカフェ)」という名前だったんですね。もう今は閉店してしまったんですけど、あの頃あのお店の中で涼しい風に吹かれながら勉強していた日々を今でもよく覚えています」
(編集部注:山本さん流の美味しいご飯の探し方として、行った先でぶらぶらしながら、地元の人たちが集まっているお店に入って、おじさんたちが食べているものを注文するそうです。ほかにも宿のおかみさんが作ってくれる「おうちごはん」的なものがいいとのことでした。つまり土地の人が食べているものが、いちばん美味しいということなんですね)
※今まで旅先で食べたもので、強烈に印象に残っているお料理はありますか?
「またラダックで食べた物なんですけれども、トレッキングに行っている時に食べさせてもらった”トゥクパ”って言って、すいとんとか、ほうとうみたいな感じで、小麦粉を練ったものを汁で煮込んだ料理があるんですね。
ガイドしてくれた男の人がきょうはヤクの干し肉があるぞ! って言ってくれて・・・ヤクは毛長牛という、ヒマラヤの高地に住んでいる毛が長い牛なんですけど、その肉が美味しいんです。さらにそれを干し肉にしているものがあって、それをトゥクパにして煮込むと素晴らしい旨味が出て、お肉自体もホロホロに美味しくて、それはすごく美味しかったですね。
干し肉は、ラダック人でも高地に行って遊牧民と交渉して、もしあったら買ってきてくれって言われるぐらいすごくレアなものらしくて、とても美味しくいただいた記憶です」

時々いただけるご褒美
※都会で暮らしていると、食材は買ってくるもので、お腹が空けば、食べるものはすぐ手に入ります。でも山本さんが取材に行くへき地では、そうはいきませんよね。
「そうですね。まず大地を耕しタネを蒔くところから始めますからね」
●そうですよね〜。やっぱり現地では食材は育てる物、収穫する物っていう感じなんですか?
「全部が全部、もちろんそうではなくて、やっぱり近代化に伴って外部から輸入している物だったりとかもたくさんあるんですね。でもやっぱり伝統的な料理であったり、そもそも生活を支えている基盤は、農業だったり牧畜だったりしている部分が未だにたくさんあるので、その辺はすごく大事にしているというか、生活に根ざしている、生きるために働いているっていう感じがすごくあると思います」
●食べることと生きることが直結しているんだろうなっていう印象があるんですけれども、実際にいかがですか? 感じられることはありますか?
「やっぱり旅に出ると、食べることと生きることの結びつきみたいなものが、すごく解像度が上がったように感じられる部分があると思うんですよ。
路頭に迷ったら困るじゃないですか。泊まる宿が見つかんなかったり、どこかでご飯を食べようと思ったら、お店が全部閉まっていたりとか、ストライキかなんかでとか、実際にそういうことが時々あるんですね。
そういう時に、どうしようって思った時に、たまたまご飯を見つけられたりとかすると、あ〜食べる物があって良かったなってしみじみ思いますし、お腹を壊して辛い時に、だれか優しい人がお粥とか作ってくれたりすると、なんかそれもしみじみ美味しかったりしますよね。
そういう時にありがたみを感じることがあるので、やっぱり旅は僕たちが生きている、当たり前のことをわかりやすく示してくれる効能があるのかなって思いますね」
●山本さんは旅をされていて、どんな瞬間に幸せを感じますか?
「どうですかね〜。人によっていっぱいあると思うんですけど、今回に関しても自分が想像もしていなかった時にとてつもないギフトを貰える時があって、あまり詳しくは話せないんですけど・・・(笑)。
今までの旅でも、本当に奇跡なんかじゃないかと思うような瞬間に立ち会えることがあったりしたんです。それは狙って体験できるものでは、絶対ないんですけれども、ずっと現地のことを見守り続けていると、時々そういうご褒美をもらえることがあるのかなと思える時があります。
そういう自分がいただいたものを、僕は物書きであったり写真家であったりするので、ひとりでも多くの人に本という形で伝えていけたらなと思っています」
☆この他の山本高樹さんのトークもご覧下さい。
INFORMATION
30年以上、世界を旅してきた山本さんが訪問先で出会った「食」をテーマに書き上げた本です。味の記憶とともに綴られた旅の紀行文を、じっくり味わうことができますよ。ぜひ読んでください。「産業編集センター」から絶賛発売中です。
詳しくは出版社のサイトをご覧ください。
◎「産業編集センター」HP:https://www.shc.co.jp/book/17377
本の出版を記念して、鎌倉市大船の書店「ポルべニール ブックストア」で現在、ラオス写真展と、世界の食文化フェアが開催されています。会期は10月3日まで。ぜひお出かけください。
詳しくは「ポルべニール ブックストア」のサイトをご覧ください。
◎「ポルべニール ブックストア」HP:https://www.porvenir-bookstore.com/
山本さんのオフィシャルサイト「ラダック滞在記」そして個人サイトもぜひ見てください。
◎「ラダック滞在記」HP:https://ymtk.jp/ladakh/
◎山本高樹さんの個人サイト:https://ymtk.jp/wind/